26 / 27
終章 立花左近の思い
江戸の鳥越で将軍と語る
しおりを挟む
それから、五十年ほどの歳月が流れた。
文禄・慶長の役も、石田三成と徳川家康の直接対決となった関ヶ原の合戦も、豊臣家が滅びた大坂夏の陣も過ぎていった。そして近年島原の乱も鎮圧された。それは江戸時代前期最大の反乱であり、幕府軍が大軍を派遣したが鎮圧までには時間がかかった。反乱方は皆殺しに等しい凄絶な戦であった。
江戸幕府が開かれてから、四十年の月日が流れている。
寛永十八年(一六四一年)、江戸幕府三代将軍・徳川家光は自身の咄衆(はなししゅう)を長く勤めた老人を見舞うため、お忍びで城から出かけた。明らかにすると大げさになるからである。その屋敷は浅草鳥越にある。
咄衆は古くから相伴衆、伽衆などと呼ばれており、ときの支配者の側について話し相手をしたり外出の供をしたりする役職である。足利の歴代将軍の頃には赤松氏、山名氏など守護職にある者があたり、話し相手というよりは合議の役割を果たしていた。それが豊臣秀吉の頃になると、解釈の幅が広くなったようで何でもありという状況になる。外国の文化も柔軟に受け入れて旧来のものを刷新しようとした主君・織田信長を見ていたこともあるだろう。何より自身に教養がないことを自覚していた秀吉はありとあらゆるものを吸収しようとした。彼の伽衆には大名だけではなく文化人・公家・商人まで加わった。それが茶の湯の文化を浸透させる結果にもなった。
江戸幕府にもこの役職がある。初代の徳川家康は天海僧正など宗教者の側近を持ったが、秀吉の頃のような伽衆ではなかった。もっと現実的なこと、江戸の町をどう作っていくか、寺社の役割をどうしていくかなど、施政上必要なことがらを相談していたのである。二代目将軍秀忠の頃からは正式に咄衆という役職となり、かつて勇名を轟かせた歴戦の将が選ばれた。伊達政宗、加藤嘉明、藤堂高虎など誰もが知っているような面々である。秀忠の頃には政事の相談相手、あるいは地方との調整役となることもあったが、三代の家光の時代になると、その趣もだいぶ変わってきた。かれらが歳を取ったこともあるが、父や祖父のように実戦経験のない家光には、かれらの誇らしい武勇譚の数々が憧憬の対象であり、吸収すべき最優先事項になった。政事についてはすでに大老が中心となって担っていたので、自身が一から考える必要もなかったのである。
今は、伊達も加藤も藤堂ももういない。
かれは七十を過ぎ、しばらく前から脚が不自由になっていたこともあって、咄衆を退いていた。それでも求めに応じてたびたび登城したし、寺社への参詣など外出のお供もこれまでと同様に勤めていた。将軍は能がたいそうお気に入りだったので頻繁に役者に演じさせていたが、それを見ている側にはたいていかれが付いていた。家光はこの老人に敬意を表して頭巾や杖を贈り、それを自身、すなわち最高権力者の御前で使うことを許可した。それを許される例は珍しく、どれほどかれが大切にされていたかが推し量れる。しかし、そんな厚遇を甘受する間もなかった。かれはときたま吐き戻すようになり、衰弱していた。家光もお抱えの医師を差し向けたりしたのだが、年齢のこともあり、本復は難しいだろうということだった。
家光は鳥越に向かう道すがらつぶやいた。
「左近、いや、立斎も伏せるようになったか……」
家光は過去の記憶をたどった。父秀忠がまだ存命だった頃のことである。
伊達政宗、加藤嘉明らとともに立花左近宗茂が座していた。
左近、すなわち統虎である。その諱は復唱するのも一苦労なほど変わっていた。
統虎から数えて、鎮虎、正成、親成、尚政、俊正、信正、常正と続き宗茂となった。かれにとって、諱は大した意味を持たないようにも思われる。その物事にこだわらないさまは、例えるならば柳河の水の流れのようにさらさらとしているのだった。結局、かれの通り名は変わり続ける諱ではもちろんなく、飛騨守でもなく、隠退するまでずっと左近将監の「左近」であった。
養子にとった息子忠茂が家督を継いで左近将監になってからは、出家後の「立斎」と呼ばれるようになった。結局、関ヶ原の翌年に三十代前半で亡くなったぎんとの間に子を授かることはなく、その後の継室との間にも子はできなかった。忠茂は実弟の四男である。
家光が思い出したのは、老人がまだもう少し若い頃の話である。
伊達政宗が武張った物言いをして座がしんとしてしまったことがあった。
父秀忠も黙ってしまった。なにしろ、伊達政宗は咄衆の筆頭であるし、陸奥の太守、大藩の主でもあった。大坂の陣で活躍したという自負もある。家康の外戚でもある。あるある尽くしなので、傲岸不遜な部分が出てきてしまうのは仕方ないかもしれない。
誰もがものを言いがたい。そんな沈黙を破ったのは左近宗茂であった。
「早く御膳を賜ると嬉しいのですが。なにぶん腹が減っておりまして」とさらりと言ってのけたのである。一同がほっとしたことは言うまでもない。
まだ子供だった家光にもかれの態度は印象深く残った。
その後も万事がその調子であった。話をするにしても、水を向けられたときに淡々と話すのみである。自身のことよりも、敵味方を問わずどこに誰がいたか、状況はどうであったかなどあらましを述べるのが上手だったので、座の一同も話に乗りやすく場が盛り上がるのだった。そのうち家光はかれをたいへん気に入り、「左近を呼べ」と言っては参詣や能に随伴させるようになった。
江戸の藩邸で養生している立斎は思ったより元気そうだった。相変わらず脚をひきずって少々やつれてはいたが、変わらずにこやかに家光を出迎えた。
「立斎、加減はどうじゃ」
「いやいや、上様がお越しになられると伺った途端に治りましてございます。まったく、調子のよいことにございますな」
近況を二、三話した後、「さて、せっかくお越しいただいたのですから、何かお話いたしましょうか」と立斎は尋ねた。
家光は思案しているふりをしていたが、「いや、今日はわしの話を聞いてもらおうか、もちろん横になって聞いてもらってかまわん」と言う。
「はい」と立斎は素直にうなづき、布団のある方へ向かう。横になることはさすがにできないので、布団にもぐって座る形になった。家光は待ちかねたように言う。
「最近、水野日向守が覚書をしたためてな、わしに送ってきた」
「ほう、日向殿が」
水野日向守勝成は備後福山藩主である。もちろん、立斎は昔からよく知っている。
しかしいまだに日向守勝成という名には今ひとつ違和感がある。立斎にとっては、「放浪者の水野六左衛門」の印象があまりにも強く、他の名を凌駕していたのである。水野六左衛門、あの肥後国衆一揆のときに佐々成政の家臣として現れた放浪者である。ほんのしばらく世話していたこともあった。それが実は徳川家康の従兄弟であると知ったときは仰天するあまりしばらく口が利けなかったほどである。それどころか関白秀吉から碌までもらっていたという。生来恵まれた境遇であり、武勇も華々しいのに不品行も盛大で実父から奉公構、すなわち勘当されていたのだからおかしい。本名では仕官ができないから仮の名乗りをしていたのだ。
関ヶ原の後、六左衛門は刈屋藩主・水野日向守勝成になった。昔日の傍若無人な姿はどこへやら、父の許しを得て以降は家康によく従い、刈屋から大和郡山そして備後福山藩主となり譜代大名としての格を上げてきた。一方、立斎は西軍側に付いた結果、柳河を失っていたので旧交を温めるどころではなかった。家康の治世では延々と浪人暮らしが続き、秀忠の代でようやく赦され陸奥棚倉藩主として大名に復帰することとなった。後で老中の土井利勝に聞いた話によれば、水野日向が立花はよくできた人間なので、赦免すべきだと言っていたらしい。
わしはずいぶん回り道をしたったい。
最後に戦場を共にしたのは意外に最近だ。五年前に起こった島原の乱の際、ともに参戦したのである。ともに七十歳前後の老いた身に鞭を打っての出陣であった。おそらく、歳の順に並べたら一、二ではないか。しかし七十にしてはお互いまともだった、と立斎は一人うなずく。
五十年前、肥後でともに戦ったときには、こんなことになるとは想像もできなかった。
それもまた一興か。
少しぼうっとしている立斎の顔を家光が覗き込む。はっと気づいた立斎は慌てて向き直り、「失礼を。しばし昔日を思い出しまして」と詫びた。家光はさもありなんという顔で、話を続ける。
「その覚書に、日向守が九州を渡り歩いていた頃のことも少々書かれておってな。熊本城の受け取りの際に十時摂津連貞の消息を聞いたことまで書いておったわ」
加藤清正の息子が改易になった際、熊本城の受け取りをし、細川家に引き継いだのは水野日向だった。加藤清正の正室清浄院は水野の実妹である。熊本城の件はごく最近の話である。あのとき、十時はまだ生きておったか、と立斎はしばし思案した。
「はい、摂津はずっと日向殿に怒っておりました。世話になっておいて喧嘩沙汰を起こして逃げたと言って。まぁ、当時もそりは合わないようでした。似た者同士は往々にしてそのような感じです」と立斎は面白そうに言う。
「肥後の一揆のこともな。わしも島原の乱の収拾に苦労したことを忘れてはおらん。西国の反乱というのは一筋縄では行かぬと知った。そこで、左近、いや立斎にもその話を聞こうと思うた。今それができるのは、日向と立斎ぐらいじゃ」
立斎はうなずく。ときを継いで、いつの間にか長老になったということか。
かれは将軍が聞きやすいように、六左衛門改め日向守と出会った兵糧入れの話や柳河城黒門の戦いのことなどを、ぽつりぽつりと話した。その語り口は、若き日に隈部親永に語りかけたときよりはるかにさらさらと、淡々としていた。
「あらかた、以上のようなことでございます」
数年前の島原の乱は激しいものであったが、あの場に赴いた限られた人間しか分からない。いわば局地的なものである。そうでない大多数の人間にとって戦というものは非日常的な、いわばお伽ばなしになっているのだと立斎は感慨に耽る。
「しかし、放し討ちとは凄まじいのう。隈部の一党も捕えられて以降、身体も弱っておったのだろうが、正々堂々と果し合いで決着をつけようとしたのは天晴れなり。それを受けて立った立花の十二人も誠に見事である。武士の鑑といえる話じゃ。それに較べて、今の大名連中はその魂をなくしておる。平時にあってもそれを失ってはいかんと思う」
立斎は苦笑した。いや、それはただの殺し合いに過ぎない。そのようなことがない世になったことを喜ぶべきで、美談に仕立て上げられ、魂などとと解釈されるのはいかがなものか。しかし、それは当代将軍の矜持であるので、何がしかの弁明をはさむことはしなかった。
隈部親永はいまんわしの話ば聞いたらどげん思うと?
肥後の一揆はもう五十年も前の、長い長い戦乱の世の、すぐに忘れられてしまうほどの出来事に過ぎない。それを御前で自身が聞かせることになろうとは。冥途の親永が知ったらどんな顔をするだろうか。
「しかし、日向様が若き日の道行きをしたためるなど、感心いたしました。わたくしも上様にこの話をすることがあるとは思っておりませんでした。あの方は控えめに申しても、大層な荒くれ者で一番槍を入れなければ気が済まない。大将の器量はございましたが、それを上回る短気さ。ゆえに佐々の後、小西、加藤、黒田、わが家中と渡り歩き、どこも喧嘩して飛び出しました。かぶき者の典型でしょうな。それがどこで開眼されたのか、今は立派になられて」
家光はクスリと笑った。
「あぁ、まだ開眼したりないようじゃ。今度は大徳寺で修行すると言っておるぞ」
「そうでした。大徳寺に塔頭を建てられましたな」
家光はしんみりした様子になる。
「……しかし、このような話を聞く機会も、どんどん減っていく。それがときの流れというものだろうが。立斎は厭というほど長生きしてくれい」
家光が帰途についた後、立斉は少し疲れたので横になっていた。
しかし、半刻ほどで目を覚ますとまだ夕暮れには間があった。そこで彼は庭に出て、流れる水の音に耳を済ませた。
あれから、肥後は加藤家から細川家が治めることになった。両家とも城氏や阿蘇氏など地元の有力豪族、肥後国衆の係累を家臣に取り立てた。また、そうならなかった者の多くも庄屋格を得て、昔日のように自らの土地で堂々と暮らしている。親永の直系は三歳の子石見丸が生き延び、後に中富という姓で庄屋格を得ている。
また、一族の隈部尾張守鎮連が立花家に出仕し、その血脈は承継された。
ぼちぼちやったが、肥後もんは皆それぞれに生きて、継いどるとよ。
立斎は庭の石に腰掛けて、夏の夕暮れを静かに感じている。蛍もそろそろ終わる時期であるが、蝉はまだまだ健在である。
あれから五十年、わしもよう生きた。生々流転、すべては流れる水のごとし。ようよう回りまわって親永と同じ歳になったとね。
「城春にして草木深し……か。柳河やったら、水清しっちゅうとこたい。あぁ、また堀だらけの柳河の春ば見たか。ぎん、わしは柳河にはもう帰れんとよ……ばってん、ここにも水は流れちょる。それも一興たい」
毛がわずかに生えた白い頭を撫でながら、立斎はいつまでも庭を眺めていた。
(終わり)
文禄・慶長の役も、石田三成と徳川家康の直接対決となった関ヶ原の合戦も、豊臣家が滅びた大坂夏の陣も過ぎていった。そして近年島原の乱も鎮圧された。それは江戸時代前期最大の反乱であり、幕府軍が大軍を派遣したが鎮圧までには時間がかかった。反乱方は皆殺しに等しい凄絶な戦であった。
江戸幕府が開かれてから、四十年の月日が流れている。
寛永十八年(一六四一年)、江戸幕府三代将軍・徳川家光は自身の咄衆(はなししゅう)を長く勤めた老人を見舞うため、お忍びで城から出かけた。明らかにすると大げさになるからである。その屋敷は浅草鳥越にある。
咄衆は古くから相伴衆、伽衆などと呼ばれており、ときの支配者の側について話し相手をしたり外出の供をしたりする役職である。足利の歴代将軍の頃には赤松氏、山名氏など守護職にある者があたり、話し相手というよりは合議の役割を果たしていた。それが豊臣秀吉の頃になると、解釈の幅が広くなったようで何でもありという状況になる。外国の文化も柔軟に受け入れて旧来のものを刷新しようとした主君・織田信長を見ていたこともあるだろう。何より自身に教養がないことを自覚していた秀吉はありとあらゆるものを吸収しようとした。彼の伽衆には大名だけではなく文化人・公家・商人まで加わった。それが茶の湯の文化を浸透させる結果にもなった。
江戸幕府にもこの役職がある。初代の徳川家康は天海僧正など宗教者の側近を持ったが、秀吉の頃のような伽衆ではなかった。もっと現実的なこと、江戸の町をどう作っていくか、寺社の役割をどうしていくかなど、施政上必要なことがらを相談していたのである。二代目将軍秀忠の頃からは正式に咄衆という役職となり、かつて勇名を轟かせた歴戦の将が選ばれた。伊達政宗、加藤嘉明、藤堂高虎など誰もが知っているような面々である。秀忠の頃には政事の相談相手、あるいは地方との調整役となることもあったが、三代の家光の時代になると、その趣もだいぶ変わってきた。かれらが歳を取ったこともあるが、父や祖父のように実戦経験のない家光には、かれらの誇らしい武勇譚の数々が憧憬の対象であり、吸収すべき最優先事項になった。政事についてはすでに大老が中心となって担っていたので、自身が一から考える必要もなかったのである。
今は、伊達も加藤も藤堂ももういない。
かれは七十を過ぎ、しばらく前から脚が不自由になっていたこともあって、咄衆を退いていた。それでも求めに応じてたびたび登城したし、寺社への参詣など外出のお供もこれまでと同様に勤めていた。将軍は能がたいそうお気に入りだったので頻繁に役者に演じさせていたが、それを見ている側にはたいていかれが付いていた。家光はこの老人に敬意を表して頭巾や杖を贈り、それを自身、すなわち最高権力者の御前で使うことを許可した。それを許される例は珍しく、どれほどかれが大切にされていたかが推し量れる。しかし、そんな厚遇を甘受する間もなかった。かれはときたま吐き戻すようになり、衰弱していた。家光もお抱えの医師を差し向けたりしたのだが、年齢のこともあり、本復は難しいだろうということだった。
家光は鳥越に向かう道すがらつぶやいた。
「左近、いや、立斎も伏せるようになったか……」
家光は過去の記憶をたどった。父秀忠がまだ存命だった頃のことである。
伊達政宗、加藤嘉明らとともに立花左近宗茂が座していた。
左近、すなわち統虎である。その諱は復唱するのも一苦労なほど変わっていた。
統虎から数えて、鎮虎、正成、親成、尚政、俊正、信正、常正と続き宗茂となった。かれにとって、諱は大した意味を持たないようにも思われる。その物事にこだわらないさまは、例えるならば柳河の水の流れのようにさらさらとしているのだった。結局、かれの通り名は変わり続ける諱ではもちろんなく、飛騨守でもなく、隠退するまでずっと左近将監の「左近」であった。
養子にとった息子忠茂が家督を継いで左近将監になってからは、出家後の「立斎」と呼ばれるようになった。結局、関ヶ原の翌年に三十代前半で亡くなったぎんとの間に子を授かることはなく、その後の継室との間にも子はできなかった。忠茂は実弟の四男である。
家光が思い出したのは、老人がまだもう少し若い頃の話である。
伊達政宗が武張った物言いをして座がしんとしてしまったことがあった。
父秀忠も黙ってしまった。なにしろ、伊達政宗は咄衆の筆頭であるし、陸奥の太守、大藩の主でもあった。大坂の陣で活躍したという自負もある。家康の外戚でもある。あるある尽くしなので、傲岸不遜な部分が出てきてしまうのは仕方ないかもしれない。
誰もがものを言いがたい。そんな沈黙を破ったのは左近宗茂であった。
「早く御膳を賜ると嬉しいのですが。なにぶん腹が減っておりまして」とさらりと言ってのけたのである。一同がほっとしたことは言うまでもない。
まだ子供だった家光にもかれの態度は印象深く残った。
その後も万事がその調子であった。話をするにしても、水を向けられたときに淡々と話すのみである。自身のことよりも、敵味方を問わずどこに誰がいたか、状況はどうであったかなどあらましを述べるのが上手だったので、座の一同も話に乗りやすく場が盛り上がるのだった。そのうち家光はかれをたいへん気に入り、「左近を呼べ」と言っては参詣や能に随伴させるようになった。
江戸の藩邸で養生している立斎は思ったより元気そうだった。相変わらず脚をひきずって少々やつれてはいたが、変わらずにこやかに家光を出迎えた。
「立斎、加減はどうじゃ」
「いやいや、上様がお越しになられると伺った途端に治りましてございます。まったく、調子のよいことにございますな」
近況を二、三話した後、「さて、せっかくお越しいただいたのですから、何かお話いたしましょうか」と立斎は尋ねた。
家光は思案しているふりをしていたが、「いや、今日はわしの話を聞いてもらおうか、もちろん横になって聞いてもらってかまわん」と言う。
「はい」と立斎は素直にうなづき、布団のある方へ向かう。横になることはさすがにできないので、布団にもぐって座る形になった。家光は待ちかねたように言う。
「最近、水野日向守が覚書をしたためてな、わしに送ってきた」
「ほう、日向殿が」
水野日向守勝成は備後福山藩主である。もちろん、立斎は昔からよく知っている。
しかしいまだに日向守勝成という名には今ひとつ違和感がある。立斎にとっては、「放浪者の水野六左衛門」の印象があまりにも強く、他の名を凌駕していたのである。水野六左衛門、あの肥後国衆一揆のときに佐々成政の家臣として現れた放浪者である。ほんのしばらく世話していたこともあった。それが実は徳川家康の従兄弟であると知ったときは仰天するあまりしばらく口が利けなかったほどである。それどころか関白秀吉から碌までもらっていたという。生来恵まれた境遇であり、武勇も華々しいのに不品行も盛大で実父から奉公構、すなわち勘当されていたのだからおかしい。本名では仕官ができないから仮の名乗りをしていたのだ。
関ヶ原の後、六左衛門は刈屋藩主・水野日向守勝成になった。昔日の傍若無人な姿はどこへやら、父の許しを得て以降は家康によく従い、刈屋から大和郡山そして備後福山藩主となり譜代大名としての格を上げてきた。一方、立斎は西軍側に付いた結果、柳河を失っていたので旧交を温めるどころではなかった。家康の治世では延々と浪人暮らしが続き、秀忠の代でようやく赦され陸奥棚倉藩主として大名に復帰することとなった。後で老中の土井利勝に聞いた話によれば、水野日向が立花はよくできた人間なので、赦免すべきだと言っていたらしい。
わしはずいぶん回り道をしたったい。
最後に戦場を共にしたのは意外に最近だ。五年前に起こった島原の乱の際、ともに参戦したのである。ともに七十歳前後の老いた身に鞭を打っての出陣であった。おそらく、歳の順に並べたら一、二ではないか。しかし七十にしてはお互いまともだった、と立斎は一人うなずく。
五十年前、肥後でともに戦ったときには、こんなことになるとは想像もできなかった。
それもまた一興か。
少しぼうっとしている立斎の顔を家光が覗き込む。はっと気づいた立斎は慌てて向き直り、「失礼を。しばし昔日を思い出しまして」と詫びた。家光はさもありなんという顔で、話を続ける。
「その覚書に、日向守が九州を渡り歩いていた頃のことも少々書かれておってな。熊本城の受け取りの際に十時摂津連貞の消息を聞いたことまで書いておったわ」
加藤清正の息子が改易になった際、熊本城の受け取りをし、細川家に引き継いだのは水野日向だった。加藤清正の正室清浄院は水野の実妹である。熊本城の件はごく最近の話である。あのとき、十時はまだ生きておったか、と立斎はしばし思案した。
「はい、摂津はずっと日向殿に怒っておりました。世話になっておいて喧嘩沙汰を起こして逃げたと言って。まぁ、当時もそりは合わないようでした。似た者同士は往々にしてそのような感じです」と立斎は面白そうに言う。
「肥後の一揆のこともな。わしも島原の乱の収拾に苦労したことを忘れてはおらん。西国の反乱というのは一筋縄では行かぬと知った。そこで、左近、いや立斎にもその話を聞こうと思うた。今それができるのは、日向と立斎ぐらいじゃ」
立斎はうなずく。ときを継いで、いつの間にか長老になったということか。
かれは将軍が聞きやすいように、六左衛門改め日向守と出会った兵糧入れの話や柳河城黒門の戦いのことなどを、ぽつりぽつりと話した。その語り口は、若き日に隈部親永に語りかけたときよりはるかにさらさらと、淡々としていた。
「あらかた、以上のようなことでございます」
数年前の島原の乱は激しいものであったが、あの場に赴いた限られた人間しか分からない。いわば局地的なものである。そうでない大多数の人間にとって戦というものは非日常的な、いわばお伽ばなしになっているのだと立斎は感慨に耽る。
「しかし、放し討ちとは凄まじいのう。隈部の一党も捕えられて以降、身体も弱っておったのだろうが、正々堂々と果し合いで決着をつけようとしたのは天晴れなり。それを受けて立った立花の十二人も誠に見事である。武士の鑑といえる話じゃ。それに較べて、今の大名連中はその魂をなくしておる。平時にあってもそれを失ってはいかんと思う」
立斎は苦笑した。いや、それはただの殺し合いに過ぎない。そのようなことがない世になったことを喜ぶべきで、美談に仕立て上げられ、魂などとと解釈されるのはいかがなものか。しかし、それは当代将軍の矜持であるので、何がしかの弁明をはさむことはしなかった。
隈部親永はいまんわしの話ば聞いたらどげん思うと?
肥後の一揆はもう五十年も前の、長い長い戦乱の世の、すぐに忘れられてしまうほどの出来事に過ぎない。それを御前で自身が聞かせることになろうとは。冥途の親永が知ったらどんな顔をするだろうか。
「しかし、日向様が若き日の道行きをしたためるなど、感心いたしました。わたくしも上様にこの話をすることがあるとは思っておりませんでした。あの方は控えめに申しても、大層な荒くれ者で一番槍を入れなければ気が済まない。大将の器量はございましたが、それを上回る短気さ。ゆえに佐々の後、小西、加藤、黒田、わが家中と渡り歩き、どこも喧嘩して飛び出しました。かぶき者の典型でしょうな。それがどこで開眼されたのか、今は立派になられて」
家光はクスリと笑った。
「あぁ、まだ開眼したりないようじゃ。今度は大徳寺で修行すると言っておるぞ」
「そうでした。大徳寺に塔頭を建てられましたな」
家光はしんみりした様子になる。
「……しかし、このような話を聞く機会も、どんどん減っていく。それがときの流れというものだろうが。立斎は厭というほど長生きしてくれい」
家光が帰途についた後、立斉は少し疲れたので横になっていた。
しかし、半刻ほどで目を覚ますとまだ夕暮れには間があった。そこで彼は庭に出て、流れる水の音に耳を済ませた。
あれから、肥後は加藤家から細川家が治めることになった。両家とも城氏や阿蘇氏など地元の有力豪族、肥後国衆の係累を家臣に取り立てた。また、そうならなかった者の多くも庄屋格を得て、昔日のように自らの土地で堂々と暮らしている。親永の直系は三歳の子石見丸が生き延び、後に中富という姓で庄屋格を得ている。
また、一族の隈部尾張守鎮連が立花家に出仕し、その血脈は承継された。
ぼちぼちやったが、肥後もんは皆それぞれに生きて、継いどるとよ。
立斎は庭の石に腰掛けて、夏の夕暮れを静かに感じている。蛍もそろそろ終わる時期であるが、蝉はまだまだ健在である。
あれから五十年、わしもよう生きた。生々流転、すべては流れる水のごとし。ようよう回りまわって親永と同じ歳になったとね。
「城春にして草木深し……か。柳河やったら、水清しっちゅうとこたい。あぁ、また堀だらけの柳河の春ば見たか。ぎん、わしは柳河にはもう帰れんとよ……ばってん、ここにも水は流れちょる。それも一興たい」
毛がわずかに生えた白い頭を撫でながら、立斎はいつまでも庭を眺めていた。
(終わり)
0
あなたにおすすめの小説
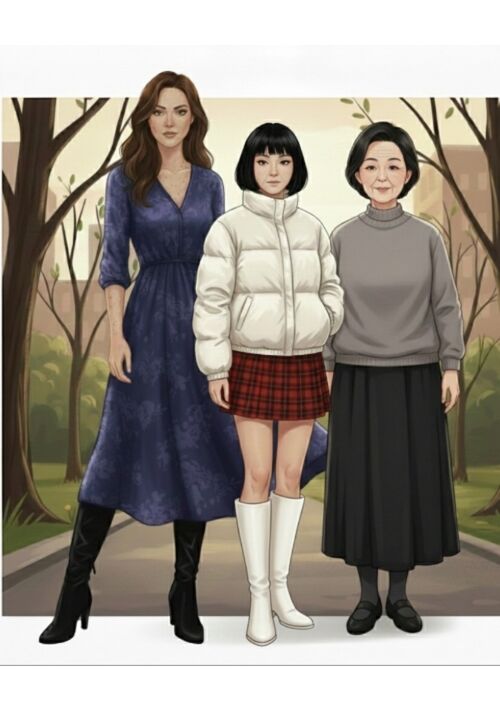
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

本能寺からの決死の脱出 ~尾張の大うつけ 織田信長 天下を統一す~
bekichi
歴史・時代
戦国時代の日本を背景に、織田信長の若き日の物語を語る。荒れ狂う風が尾張の大地を駆け巡る中、夜空の星々はこれから繰り広げられる壮絶な戦いの予兆のように輝いている。この混沌とした時代において、信長はまだ無名であったが、彼の野望はやがて天下を揺るがすことになる。信長は、父・信秀の治世に疑問を持ちながらも、独自の力を蓄え、異なる理想を追求し、反逆者とみなされることもあれば期待の星と讃えられることもあった。彼の目標は、乱世を統一し平和な時代を創ることにあった。物語は信長の足跡を追い、若き日の友情、父との確執、大名との駆け引きを描く。信長の人生は、斎藤道三、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、伊達政宗といった時代の英傑たちとの交流とともに、一つの大きな物語を形成する。この物語は、信長の未知なる野望の軌跡を描くものである。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。


滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















