14 / 35
ここから始めよう
しおりを挟む勝重が気にかけていた自身の役目については、じきに父藩主から内々の命があった。
その内容は鞆(とも)に在住し地域の監督と窓口を担うというものだ。専任の奉行は必要に応じて任命するが、まず下地を整えてほしいと勝成は付け足した。
そう告げられたとき、勝重は少し意外に感じた。
「城の普請や土地の開削ではなく、鞆の監督役ということでしょうか」と勝重はいう。
「そうじゃ、物足りんか」と勝成はあご髯を撫でながら息子に問う。
勝重は一端、斜め上に目線を泳がせてから、「そうですな。どのようなお役目をいただくのかと思案しとりましたが、正直、意外な方へ話が行ったと思うております」と答えた。
勝成はフッと笑みを浮かべる。
「かようなこと、わしが父から命ぜられたら、よう理由も聞かぬうちから不服じゃとまくし立てて喧嘩になっとったはず」
勝重は父の喩え話に思わず吹き出して、笑顔になる。
「父上はいつでも早駆けの一番鑓でしたからのう。いや……わしは特別この役がしたいというのはございませぬ。鞆を監督する仕事があると気づいとらんかったということですのんじゃ」
勝成は、息子による備中ことばにつられて笑いだす。
「ああ、おぬしは聞く耳を持っとる。さすが江戸で小姓組を勤めただけのことはある。わしならばすぐにお払い箱じゃったのう」
「いや、さような」と勝重は慌てる。
勝成は微笑んで息子を見つめる。
日だまりのような温もりを思わせる、心からの笑顔だった。
「うむ、まことによう勤めあげた。おぬしはわしの自慢のせがれじゃ」
勝重は驚いた。
父がこれほど満面の笑みで、自身を正面切って褒めてくれたことはなかったからである。驚くと同時に何かもぞもぞとした恥ずかしさと、胸の奥から沸き立つような喜びを感じていた。
父は話し続ける。
「鞆を預かる者は実に多岐に渡る仕事をせねばならん。じきに水路は城前の海や入川と繋げることになろうが、備後の入口になる地。多くの船、人、ときには賓客も入る。旧くから漁師町あり、船宿あり、船大工あり、鍛冶町あり、古刹に名刹あり、商人あり……と小さい中に様ざまひしめき合っておる町じゃ。
主城は新しくするが古くからある町や村、何より人のつながりは大事にしたい。その上で、鞆の町にもまた新たな役割を担ってもらおうと考えとる。したがって初めから奉行だけではよう回しきれん。若く、新たなことに柔軟に取りかかる者が要る。まあ、ありていに言えば、わしはおぬしじゃからできる役目と思うておるんじゃ」
勝成の説明は丁寧だった。
父の言わんとしていることは十分飲み込めた。
息子はまっすぐな目で藩主を見る。
「はい、謹んでお役を頂戴いたしまする。そうとなりましたら、さっそく明日にでも鞆に出向いてまいります。どなたかに案内をいただけますでしょうか」
勝成は変わらず笑顔でうなずく。
「ああ、鞆に祇園社という社がある。そちらの宮司を訪ねてくれみゃあ」
「祇園社でございますか。承知」と少し意外そうな表情で勝重は答える。
これで話は終了したーーといいたいところだが、勝成はまだ何か言いたそうだ。
「殿、何か」と勝重は父を促すように尋ねる。
「うむ、まあ、その……かつて、わしゃ九州で幾人かの武将に付いて、鑓を振るっとったんじゃ」
「はい」と話の方向が見えない勝重はうなずく。
「それで、巡りめぐって黒田筑前守(長政)の下に付いたんじゃが、これがまた反りの合わぬこと合わぬこと。犬と猿っちゅうやつじゃ」
「はい」
「それで、一行は大坂の羽柴秀吉にお目見えせんと中津で船に乗ったんじゃ。筑前守はもうピリピリしとってのう、わしのおるんが不愉快きわまりなかったようじゃ」
「ふむ、しかし命令したのでございましょう」
「ああ、父親の黒田官兵衛がな。父親の方はわしを重く見て下さったんじゃが、それでなおさら倅は不愉快に」
「ああ……」
「そうしたら、筑前守はいきなりわしに船の帆をかけろと命じた」
「は? 父上は船も操れるので」
「ようせん。じゃけえ頭に来てのう。やっちゃろうとやけのやんぱちで帆柱を登っていったんじゃ」
「またそれは無茶な……」
「ああ、さすがに他の者が慌ててのう。家臣の後藤又兵衛基次がわしに降りろと言い、筑前守にさんざん謝って取りなしてくれた」
「え、あの後藤又兵衛ですか? 大坂の陣で戦った、大坂方の将じゃった……」と勝重は聞き返す。
「然り」
勝重はため息をつく。
「世話になっとる御仁だったんじゃ……」
「そうじゃ……実に惜しいことじゃった」と勝成もため息をつく。
「それで、大坂へ向かったと」
勝成はこうべをぶんぶん振る。
「もうとっくに堪忍袋の緒が切れとった。次に入った鞆の津で下船した折り、こっそり逃げ出した。以後は虚無僧になって放浪じゃ。この話は家中の者に話したことはないけえ、おぬしも知らんかったろうが」
勝重は目をぱちくりさせる。
「知っております」
「は? 誰から聞いたんじゃ?」と勝成も目をぱちくりさせる。
「親良が言うとりました。黒田筑前守といさかいを起こして鞆で船から逃げ出したと。細かい話ではございませんでしたが、顛末だけ」
「ああ、さようか。三村の親父にはあらかた話しとった。じゃけえ親良が知っとるんじゃ。合点がいった」と勝成は納得したようにうなずいている。
「ああ、母上も先だって申しておりました」
「お登久が!」と勝成は驚く。
「わしをしみじみと眺めて、『ほんまによかった』と喜んでおられました」
勝成もそれを聞いてしんみりした様子になる。
「そうじゃ、鞆の津はわしの寄る辺ない放浪の始まりで、それを終わらせる一歩にもなった。じゃけえ、おぬしにとっても鞆が始まりの地になってくれればええと思うたんじゃ。親の勝手な思いじゃがのう。がっかりしたか」
勝重は首を横に振って改めて平伏した。
「まだまだ若輩でございますが、しかと務めさせていただきます」
翌日、勝重と藤井靱負、そして供を許された三村親良も加わり神辺を出発する。
鞆には村上水軍の築造とされ、つい先頃までは福島正則が支城としていた鞆城(ともじょう)がある。
かつて、織田信長と対立した将軍足利義昭が鞆に亡命政府を置いていたことから、この城も規模は小さいながら要害として重要な役割を果たした。歴史的に重要な城である。
福島はここに三重の天守を築いたが、幕府の一国一城令発布ののち天守は三原城に移築されたので、今は館が手つかずで残っているばかりである。
勝重らは馬で鞆にたどり着く。
(鞆城跡より瀬戸内海を望む)
まず鞆城を見ることにし、いったん馬を繋いだ。城館への道はそう険しくないので一行はすぐに上りきることができた。館の方に向かうと、意外なことに人が何人も入っていて、扉も窓も障子戸もそこらかしこが開け放してある。埃煙りがもうもうと立っているのも見える。靱負と親良は鼻と口を覆って、いちばん近くにいる頬かむりした老人に声をかけた。
「掃除されとるんでしょうか」
老人は大きな声で返す。
「ええ、福島さまのご家来衆が出ていかれてもうしばらく経ちますけえ、埃だらけでもう。何でもじきに水野さまのご家人が入られるちゅうことで、鞆の衆が交替で掃除しよるんじゃ」
その声は少し離れている勝重にもよく聞こえた。靱負が老人に何か伝えようとするのを勝重は制する。それを見た親良が替わって尋ねる。
「まことに大儀なことにござります。さて、忙中恐縮じゃがお伺いしたい。わしらはこれから祇園社に詣でるんじゃが、どちらに行ったらええじゃろうか。まだよう土地に慣れとらんのじゃ」
老人は城の裏手を指して言う。
「あの道を下りようて左に、城沿いにもういちど左に曲がってつかあさい。まっすぐ行くと祇園さんのお山にぶつかりますで、すぐに分かるじゃろう思います」
勝重と靱負と親良は老人に礼をして去る。
「わしが住むんじゃと申されたらよろしいのに」と靱負が言う。
「いや、最初(はな)から失礼ではないか。あんなに丁寧に掃除をしてくれとるのに」と勝重は返す。
「いやいや、偉そうでええんじゃ。次期藩主なのじゃから」と親良が苦笑する。
勝重はふうとひとつ息をつく。
「まことに、まことに有難いもんじゃのう」
(当時の祇園社、現在の沼名前神社の燈籠)
そうこうする間に老人が「祇園さん」と口にしていたのに相違ない社が左手に見えてくる。現代は沼名前神社(ぬなくまじんじゃ)となっている。ゆっくりと石段を踏みしめて上がる。
ここに来るまでは、土地の社の宮司にいきなり面会するというのでわずかに緊張していた勝重だが、気持ちはだいぶ落ち着いていた。
「若、後ろをご覧になられませ」と不意に靱負が声をかける。勝重と親良は後ろを振り返る。
「おおっ」と二人は感嘆する。
来た方を見下ろすと、そこには蒼い瀬戸内海が広がっている。仙酔島や走島が望めるし、漁師の小舟がいくつも行き交うのが見える。まるで絵のような風景だった。
「素晴らしい眺めじゃ」と勝重はつぶやいて、穏やかな海をしばらく眺めていた。
0
あなたにおすすめの小説
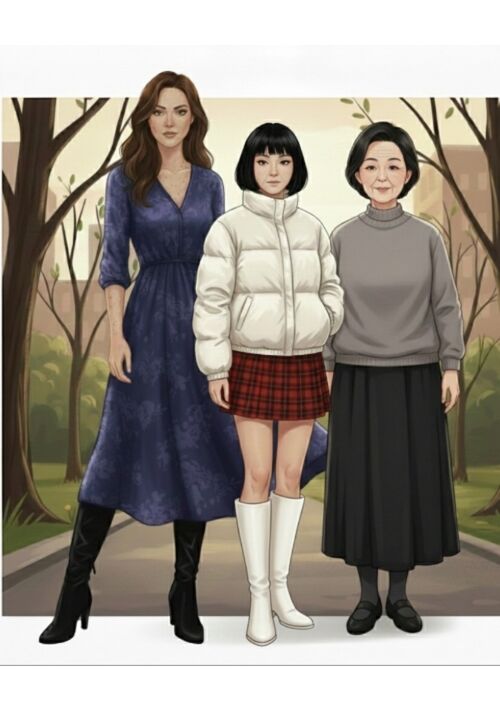
熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)
MisakiNonagase
恋愛
高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
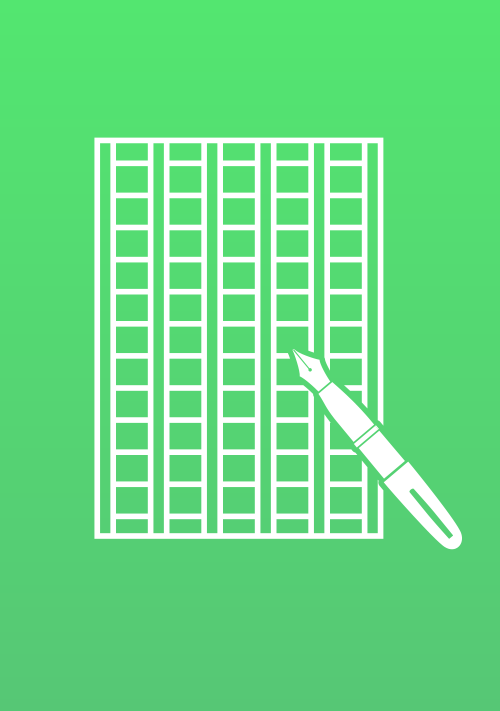


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。
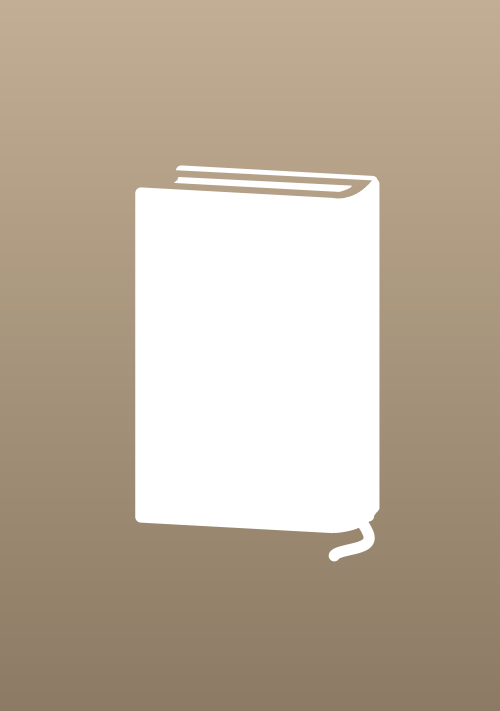

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

久々に幼なじみの家に遊びに行ったら、寝ている間に…
しゅうじつ
BL
俺の隣の家に住んでいる有沢は幼なじみだ。
高校に入ってからは、学校で話したり遊んだりするくらいの仲だったが、今日数人の友達と彼の家に遊びに行くことになった。
数年ぶりの幼なじみの家を懐かしんでいる中、いつの間にか友人たちは帰っており、幼なじみと2人きりに。
そこで俺は彼の部屋であるものを見つけてしまい、部屋に来た有沢に咄嗟に寝たフリをするが…
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる






















