25 / 89
激闘 大坂夏の陣
夏の陣 大和方面軍の先鋒大将 古都を守る
しおりを挟む
慶長二十年(一六一五)の四月二十六日、勝成の姿は京都二条城にあった。家康並びに秀忠に呼ばれたのである。
前年の暮れ、豊臣秀頼とその母、淀を戴く豊臣勢は徳川勢とついに直接対峙することとなった。
十五年前の関ヶ原合戦の後、豊臣家は摂津・河内・和泉三国のみに領地を与えられていた。家康は豊臣秀頼の後見役であったから、淀は秀頼が成人した折に政権を返上してくれると信じていた。あくまでも家康はそれまでの代理なのだと。
しかしやはり、それは甘かった。
慶長八年(一六〇三)に家康は征夷大将軍となり、慶長十年(一六〇五)にはその位を息子の秀忠が継ぐ。この段に至って秀頼が、豊臣家が政権に返り咲く途は完全に断たれた。豊臣方は憤慨するが、忸怩たる思いで事態を静観しているしかない。その上、徳川は豊臣家の莫大な金銀を蕩尽させるべく、寺社の修造や再建事業を次々と豊臣家に預けた。その一端だった方広寺の梵鐘に関して豊臣方はとことん追い詰められることになる。
慶長十四年(一六一四年)のことである。
梵鐘には銘文が刻まれ、その一節に「国家安康 君臣豊楽」云々という部分があった。家康はそこに難癖をつけた。家康の名を割って、豊臣が楽しむと読めるというのである。
「内容はあらかじめ徳川に示していた。今更それを言われるとは理不尽な言いがかりであろう」と豊臣家臣の片桐且元が訴えたが、突っぱねられた。そして恭順の意を示すよう、豊臣秀頼の江戸参勤、豊臣家の他国への転封、淀を江戸に人質に出す――のいずれかを選ぶように迫った。
屈辱的な条件を突きつけられ、淀、すなわち豊臣方の堪忍袋の緒が切れた。
豊臣方は戦仕度にかかった。
潤沢な財を使って諸国の牢人衆に集結を呼びかけた。もちろん金で集まる衆もいるが、「徳川憎し」の念でやってくる者らもいる。関ヶ原で敗北した旧西軍方の将、または家臣たちである。主家を潰され、牢人にならざるを得ない者が多数いたのである。また、豊臣家に深い恩義を感じて大坂城にやって来る者もいた。
その中で主力の将になったのは、真田信繁、明石全登(てるずみ)、毛利勝永、長宗我部盛親、薄田(すすきだ)隼人、そして後藤又兵衛基次だった。
この中で明石全登の目的は他とは異なっていた。
彼は宇喜多秀家の家臣だったが敬虔なキリシタンであった。
この頃、キリシタンへの迫害は一段と激しさを増していた。かつては有力なキリシタン大名だった高山右近がルソン(フィリピン)に国外追放になったのもこの年である。豊臣が政権を取り返すことで、禁教を解いてもらうことに一縷の望みをつないだのである。実際、大坂城に籠城した中には、同様の志を持つ者や宣教師も入っていた。
そして、後藤又兵衛基次である。
彼は七年前、主家の黒田家から一族郎党を引き連れて出ていった。かねてから彼を疎んじていた黒田長政に奉公構をくらい、細川家や池田家にしばらく留まったものの、どこでも長居はできなかった。
どこかで聞いたような話である。
水野勝成と同じような道を、その後の後藤又兵衛も辿っていたのである。しかも、奉公構をくらわせたのは黒田長政である。長政は勝成の父のようにそれを解くことはなかったし、又兵衛も解かれようとはかけらも思っていなかった。
慶長十九年(一六一四)十一月、家康の東軍方と大坂方が大阪城の西方で衝突する。
大軍が控える中、戦闘は散発的に発生した。講和に向かう手段を模索する双方が使者をやりとりする日々が続いた。冬の間の戦は兵の疲弊も激しい。長引かせたくないというのは双方とも思っていたことである。外に詰めるばかりの東軍はなおさらである。
十二月半ば、東軍は大坂城に向けて大砲をぶっ放した。この直接の攻撃で動揺した大坂方は、十二月二十日に和議を結ぶに至った。
この戦の大将は徳川秀忠であるが、実際は大御所家康が差配している。
冬の陣は和議で終わったが、家康は段階を踏んでさらに豊臣方を弱体化させるつもりだった。戦の講和条件として大坂城を本城だけ残し、二の丸と三の丸を破却すること、人質を出すこと、誓詞を出すことが求められ、大坂方は渋々条件を飲んだ。東軍勢は二の丸、三の丸の破却を拡大解釈し、ここぞとばかりに大坂城の堤と堀ほぼ埋め立てて、城は裸同然の体になった。これに激昂した大坂方は浪人をさらに集め、武器を調達し、城中では火薬の製造まで始めた。
最後の決戦に向けて準備をはじめたのである。
勝成は二条城で今後の豊臣方の動静と、相対する徳川方の軍勢の配置について、大まかな説明を受けている。大坂方がすでに周辺に攻撃の手を伸ばしていることを家康が述べる。
「堺が焼き討ちを受けた。被害は甚大じゃ」
「豊臣方は我らの進攻を阻むために畿内を焼き付くすつもりか」と勝成が問う。
家康がうなずく。
「大坂方はすでに大和にも手を伸ばし、大野治房が郡山を焼き討ちしとる。それが奈良、じきに京にも及ぶで。日向守には大和方面に駆けつけ、奈良侵入を阻止する役目を任せたい。そこから、河内にて一番隊の藤堂高虎、二番隊の井伊直政に合流し大坂まで一気に攻め上るんじゃ」
「して、同道されるはどなたじゃ。わしら二千ほどの兵しかおらん」と勝成が問う。
家康はじろりと勝成を見ると、些事であるかのように静かに切り出した。
「まずは大和の同胞衆じゃ。松倉重政、奥田忠次、神保相茂、山岡景以らをおぬしの直属にする。それから……」
勝成は目を見開いた。
「待ってくだされ。大和衆といえば、さきの陣で指揮を執った藤堂和泉守高虎に従わない者もいたと聞く。藤堂殿に従わぬ者がわしに従うはずなかろう」
家康がきつい一発を浴びせる。
「どたわけっ、話は終いまで聞きゃあ。大和衆ぐらいで及び腰になりおって」
脇に控える本多正信が取りなしを入れる。
「日向殿は大御所の御意のもと働くのだから、逆意は即ちわれらへのものと同じ。成敗すればよいでござろう」
いとも簡単に言ってくれるわ、と勝成は座りなおす。
まぁ、山岡は恩人道阿弥のせがれじゃけぇそこからなら何とかなるで。考えながら勝成は再び平伏するが、家康はまだ不機嫌である。
「話を戻す。直属の大和衆ほか本多忠政、松平忠明、そして伊達正宗、松平忠輝らの軍を付ける。総勢三万、先鋒大将はおぬしじゃ」
先鋒大将? 三万の?
勝成は仰天した。
しかも奥州の雄、伊達政宗もか、しかも家康の子にして伊達の娘婿の忠輝まで付けるか。
勝成は心中で唸った。先鋒も殿(しんがり)も経験しているが、総勢三万の大隊の先鋒大将を任されるのは初めてである。しかも厄介そうな面々もいる。昔日であれば深く考えず、あなうれしやと小躍りするところだが、この場においてはそう単純に喜べない。しかし、家康はこれ以上の苦情は受け付けぬとばかり難しい表情を変えない。
ここは肚をくくるしかないと勝成は思う。
「身に余るありがたきお役目、しかと務めまする。つきましては、一つだけお願いがございます」
「何じゃ」と家康がじろりと勝成を見た。
「冬の陣にても同道いただいた、堀直寄殿をわが勢にぜひお願いしたい」
信濃飯山藩主である堀直寄はずけずけものを言うが、とにかく頭の回転が早く聡い男だと勝成は見ていた。今回の戦にはうってつけである。家康はしばらく思案してから答えた。
「よかろう。堀の隊は大和口に付ける」
それだけ言うと家康はいくらか機嫌を直した。
家康はこの時、拠点を五つほどに分けていた。すなわち河内・大和街道・紀州街道・城北・京である。このうち、河内は藤堂と井伊に、紀州は浅野長晟に、城北には京極高知、京都警護には上杉景勝を置き、九鬼水軍も背後に構える。あとは大和街道である。どことなく生き生きと策を練る大御所は七十をとうに越えた老人とは思えないが、歳月は確かに過ぎている。この戦に出るのはあらかた、名だたる将の子の世代である。勝成も息子の長吉、いや元服なった勝重と共に出陣するのだ。
「六左衛門、いや日向守、この戦はわしにとっても、また皆にとっても最後の大戦になろう。ここ京都が惨禍に見舞われた応仁の乱から百五十年経つ。以来、この国は戦が絶えなかった。その間他国に侵入されなかったのだけは幸いだで。しかし、これからはそうはいかん。今はどんな遠くからでも大隊が寄せてくる。皆力を合わせ、国を守れるだけの備えをせんといかん」
勝成は家康がこの大戦のはじまりに、もうその先まで見ていることに改めて感心したが、勝成のみならず脇に座す秀忠にも説いているとみた。直に言うと説教になるから、父子というのは難しい。勝成は微笑んだ。
「素晴らしきご慧眼にござる。そう言えば伊達殿もいすぱにやに使節を派遣されとりましたな」
「あれは、わしとは考えが全く違うで」
家康は静かに、しかしきっぱりと言い切った。伊達の考えについて談義するつもりはないので勝成もそこで話を戻した。
「伊達殿にしたらわしはとんだ端物じゃろ。大人しく従うわけはないがのう」
家康はかかかと笑った。
「おぬしのお手並み拝見じゃ。くれぐれも昔のように一番鑓、先駆けなどと功名にはやるのは曲事につき、心しておけ」
関ヶ原のときと変わらない決まり文句である。
相変わらず、その変わらないところが勝成には小気味いい。まぁ、わしがきちんと働くよう難物をあてたか。勝成は納得していた。わしにとっても最後の戦になるかもしれんしのう。
しかし、悠長に構えている暇はない。勝成は京の南に待機している自軍に召集をかけて、山城国長池まで進み一夜を過ごすこととした。
事態は風雲急を告げていた。
勝成が長池に入ったとの知らせを受けた大和の代官や在地領主の使者らが訪れ、大野勢らの進攻について状況を述べ立てた。
城主筒井正次が逃げだしてもぬけの殻になった大和郡山城に始まり、城下も焼き討ちされ、その無法は奈良に迫る勢いだと言う。
「しかるに、日向守様いま直ちにご出陣を、平にお願いしたく」
勝成は懇願する者の顔を見た。
この者らは必死に助けを求めている。少ない人数で今の今まで持ち堪えようとしていたのだ。
先ほどまで、会ってもいない大和衆を厄介だと思っていたことを勝成は悔い、目を見開いた。
「あい承知した。いざ奈良じゃ! 古の都を焼かせることまかりならんっ」
その晩のうちに勝成隊三千は出立した。途中の木津川でも大和山辺の領主、奥田忠次の使者から要請を受け、翌朝には奈良で大和衆諸将と合流した。みな一様に勝成の水野隊三千人の到着に歓声を上げた。早馬からは本多忠政、松平忠明、堀直寄、伊達政宗も続々と大和路に集結しつつあるとの報が届いた。勝成は大和衆と奈良で後続を待ちながら、戦いに備えた。
間もなく勝成に大野治房の軍勢が退却しているとの報せが入った。
大野勢は二千と言っても、その内情は実浪人や荒くれ者を道中で調達したのもかなり含まれている。焼き討ちや略奪、町を破壊するにはよいが、組織的戦闘には不向きに違いない。ましてや先鋒には鬼日向こと水野勝成、後には伊達政宗の大軍が控えているとなれば、大坂方きっての武闘派である治房といえども、退却を決めざるを得なかった。
奈良は戦闘なく守られた。
大和衆一同はそれを聞いておーっと歓声を上げた。
「水野の旗印を見て、大野は退いたのや。さすが鬼日向様や」
「あの大鑓を見てみい、あれに敵うもんはおらへん」
勝成は呆気にとられた。
大和衆が水野隊を賛美するさまがあまりにも熱狂的だったからである。まだ何もしとらんでいかん。勝成はいくらか居心地の悪さを感じていた。
しかし、これが大和衆と信頼関係を結ぶきっかけになる。その意味でこの奈良進軍は大きな意味があったのだ。家康がわしを真っ先にここに出したのは理由があったのだ。ただ大和衆と合流するだけではない、大きな意味があった。
勝成は目の前が開けるような心地がする。
その日のうちに本多忠政、松平忠明、堀直寄らの隊も続々と到着した。大和方面軍の結集である。
奈良から法隆寺に至る途上、破壊され、きな臭い匂いが残る瓦礫の村々が現れはじめた。それは累々と続き、先には昔は城だったのだろうとかろうじて分かる黒焦げの巨大な建物が現れた。勝成は息を飲んだ。
「ひでえ、ひでえ有様じゃ。ここが……」
「大和郡山城にございます。城主は逃げており無事ですが、城下焼き討ちの際逃げ遅れた民が多数……」
奥田忠次がそう言って、手を合わせた。
勝成も同じようにした。
兵も民もない。これが、これが戦の非道なんじゃ。
もうこれで、終わりにせんといかん。
法隆寺から大坂の藤井寺に向かおうとする途中、大和方面隊一行は休憩を取った。
その時に家臣の中山将監が連れてきたのは新免改め、宮本武蔵だった。
武蔵はその頃すでにいくつもの決闘を経て高名の兵法家となっていたので、勝成も喜んで客将として迎えることにした。
「まず、殿にお尋ねしたい儀がござる」
会見を求められ勝成は彼の話を聞いた。そこで初めて、おとくが美作を出るときに花とどんぐりを渡して求婚した少年が彼であると知ったのである。
「それでは、おとくが言っていた美作の小僧はおぬしか」と勝成は目を丸くする。
「さようにございます。おとく様とはその後一度三村様のお屋敷で少しお話しただけで、殿が訝るようなことは全くございませぬ。さて、お尋ねしたいのは、殿がなぜ奥方様を離縁したのかということにございます。刈屋にもお訪ねしたことがございましたが、話を聞き驚いた次第。御嫡子を与えられた奥方を離縁するとは、よほどの事情があったのかと」と武蔵はまっすぐな目で問う。
勝成は正直、「家中のことをずけずけと聞きおって」とカチンと来てはいたが、真剣な様子の武蔵には、とても重要なことのようだった。そこで勝成は手短に事情を説明した。
すると、みるみるうちに武蔵の目に涙があふれた。
「おとく様は変わっておらぬ。やはり間違いはなかった。殿、それがしはおとく様に勝手ながらお約束したことがございます」
「何じゃ」
「強くなって、おとく様のお子をお守りするとお約束申し上げたのでござる。聞けば、ご嫡男美作守様はこたび出陣されるとか。ぜひそれがしを美作守の隊に付けていただきたいのです。されば先陣を切り、必ずや御嫡男を勝利にお導きいたしまする」
勝成は武蔵の真剣な、愚直なまでの思いに圧倒された。
こいつはどアホウじゃ。
初恋が叶うことがないと知りながら、惚れた女にとことん尽くすと決めておる。おそらく他のおなごには目もくれずに、ずっとそれだけを支えに剣の腕を磨いてきたんじゃ。そのために自分の命も捧げるという。まことのどアホウじゃ、
しかしそういう奴は嫌いではない。
翻って、自分はおとくに何かしてやれただろうか。勝成はふっと考えた。おとくはわしに添うて幸せだったろうか。おとくがかつて、芳井村をずっと見つめていたことが思い出された。添い遂げてやることもできず、それどころか備中に帰してやることもでけんかった。
勝成はがばっと武蔵に頭を下げた。
「貴殿に美作守に付いていただきたい。こちらからも頼む」
「畏れ多いことでございます。それがしもこれで約束の半分ほどは果たすことができまする」と武蔵は心底から嬉しそうに言う。
「いや、それほどまでにおとくに、せがれに忠心を持っていただき、心より礼を申す」
武蔵の表情はすぐにいつもの仏頂面に戻った。
「礼は殿や美作守様が無事に凱旋されてからでお願いいたします。また、このいきさつについては美作守はじめ御家中の皆様にはくれぐれも内密にお願いしたい」
「そうじゃな。承知した」と勝成も同意した。
前年の暮れ、豊臣秀頼とその母、淀を戴く豊臣勢は徳川勢とついに直接対峙することとなった。
十五年前の関ヶ原合戦の後、豊臣家は摂津・河内・和泉三国のみに領地を与えられていた。家康は豊臣秀頼の後見役であったから、淀は秀頼が成人した折に政権を返上してくれると信じていた。あくまでも家康はそれまでの代理なのだと。
しかしやはり、それは甘かった。
慶長八年(一六〇三)に家康は征夷大将軍となり、慶長十年(一六〇五)にはその位を息子の秀忠が継ぐ。この段に至って秀頼が、豊臣家が政権に返り咲く途は完全に断たれた。豊臣方は憤慨するが、忸怩たる思いで事態を静観しているしかない。その上、徳川は豊臣家の莫大な金銀を蕩尽させるべく、寺社の修造や再建事業を次々と豊臣家に預けた。その一端だった方広寺の梵鐘に関して豊臣方はとことん追い詰められることになる。
慶長十四年(一六一四年)のことである。
梵鐘には銘文が刻まれ、その一節に「国家安康 君臣豊楽」云々という部分があった。家康はそこに難癖をつけた。家康の名を割って、豊臣が楽しむと読めるというのである。
「内容はあらかじめ徳川に示していた。今更それを言われるとは理不尽な言いがかりであろう」と豊臣家臣の片桐且元が訴えたが、突っぱねられた。そして恭順の意を示すよう、豊臣秀頼の江戸参勤、豊臣家の他国への転封、淀を江戸に人質に出す――のいずれかを選ぶように迫った。
屈辱的な条件を突きつけられ、淀、すなわち豊臣方の堪忍袋の緒が切れた。
豊臣方は戦仕度にかかった。
潤沢な財を使って諸国の牢人衆に集結を呼びかけた。もちろん金で集まる衆もいるが、「徳川憎し」の念でやってくる者らもいる。関ヶ原で敗北した旧西軍方の将、または家臣たちである。主家を潰され、牢人にならざるを得ない者が多数いたのである。また、豊臣家に深い恩義を感じて大坂城にやって来る者もいた。
その中で主力の将になったのは、真田信繁、明石全登(てるずみ)、毛利勝永、長宗我部盛親、薄田(すすきだ)隼人、そして後藤又兵衛基次だった。
この中で明石全登の目的は他とは異なっていた。
彼は宇喜多秀家の家臣だったが敬虔なキリシタンであった。
この頃、キリシタンへの迫害は一段と激しさを増していた。かつては有力なキリシタン大名だった高山右近がルソン(フィリピン)に国外追放になったのもこの年である。豊臣が政権を取り返すことで、禁教を解いてもらうことに一縷の望みをつないだのである。実際、大坂城に籠城した中には、同様の志を持つ者や宣教師も入っていた。
そして、後藤又兵衛基次である。
彼は七年前、主家の黒田家から一族郎党を引き連れて出ていった。かねてから彼を疎んじていた黒田長政に奉公構をくらい、細川家や池田家にしばらく留まったものの、どこでも長居はできなかった。
どこかで聞いたような話である。
水野勝成と同じような道を、その後の後藤又兵衛も辿っていたのである。しかも、奉公構をくらわせたのは黒田長政である。長政は勝成の父のようにそれを解くことはなかったし、又兵衛も解かれようとはかけらも思っていなかった。
慶長十九年(一六一四)十一月、家康の東軍方と大坂方が大阪城の西方で衝突する。
大軍が控える中、戦闘は散発的に発生した。講和に向かう手段を模索する双方が使者をやりとりする日々が続いた。冬の間の戦は兵の疲弊も激しい。長引かせたくないというのは双方とも思っていたことである。外に詰めるばかりの東軍はなおさらである。
十二月半ば、東軍は大坂城に向けて大砲をぶっ放した。この直接の攻撃で動揺した大坂方は、十二月二十日に和議を結ぶに至った。
この戦の大将は徳川秀忠であるが、実際は大御所家康が差配している。
冬の陣は和議で終わったが、家康は段階を踏んでさらに豊臣方を弱体化させるつもりだった。戦の講和条件として大坂城を本城だけ残し、二の丸と三の丸を破却すること、人質を出すこと、誓詞を出すことが求められ、大坂方は渋々条件を飲んだ。東軍勢は二の丸、三の丸の破却を拡大解釈し、ここぞとばかりに大坂城の堤と堀ほぼ埋め立てて、城は裸同然の体になった。これに激昂した大坂方は浪人をさらに集め、武器を調達し、城中では火薬の製造まで始めた。
最後の決戦に向けて準備をはじめたのである。
勝成は二条城で今後の豊臣方の動静と、相対する徳川方の軍勢の配置について、大まかな説明を受けている。大坂方がすでに周辺に攻撃の手を伸ばしていることを家康が述べる。
「堺が焼き討ちを受けた。被害は甚大じゃ」
「豊臣方は我らの進攻を阻むために畿内を焼き付くすつもりか」と勝成が問う。
家康がうなずく。
「大坂方はすでに大和にも手を伸ばし、大野治房が郡山を焼き討ちしとる。それが奈良、じきに京にも及ぶで。日向守には大和方面に駆けつけ、奈良侵入を阻止する役目を任せたい。そこから、河内にて一番隊の藤堂高虎、二番隊の井伊直政に合流し大坂まで一気に攻め上るんじゃ」
「して、同道されるはどなたじゃ。わしら二千ほどの兵しかおらん」と勝成が問う。
家康はじろりと勝成を見ると、些事であるかのように静かに切り出した。
「まずは大和の同胞衆じゃ。松倉重政、奥田忠次、神保相茂、山岡景以らをおぬしの直属にする。それから……」
勝成は目を見開いた。
「待ってくだされ。大和衆といえば、さきの陣で指揮を執った藤堂和泉守高虎に従わない者もいたと聞く。藤堂殿に従わぬ者がわしに従うはずなかろう」
家康がきつい一発を浴びせる。
「どたわけっ、話は終いまで聞きゃあ。大和衆ぐらいで及び腰になりおって」
脇に控える本多正信が取りなしを入れる。
「日向殿は大御所の御意のもと働くのだから、逆意は即ちわれらへのものと同じ。成敗すればよいでござろう」
いとも簡単に言ってくれるわ、と勝成は座りなおす。
まぁ、山岡は恩人道阿弥のせがれじゃけぇそこからなら何とかなるで。考えながら勝成は再び平伏するが、家康はまだ不機嫌である。
「話を戻す。直属の大和衆ほか本多忠政、松平忠明、そして伊達正宗、松平忠輝らの軍を付ける。総勢三万、先鋒大将はおぬしじゃ」
先鋒大将? 三万の?
勝成は仰天した。
しかも奥州の雄、伊達政宗もか、しかも家康の子にして伊達の娘婿の忠輝まで付けるか。
勝成は心中で唸った。先鋒も殿(しんがり)も経験しているが、総勢三万の大隊の先鋒大将を任されるのは初めてである。しかも厄介そうな面々もいる。昔日であれば深く考えず、あなうれしやと小躍りするところだが、この場においてはそう単純に喜べない。しかし、家康はこれ以上の苦情は受け付けぬとばかり難しい表情を変えない。
ここは肚をくくるしかないと勝成は思う。
「身に余るありがたきお役目、しかと務めまする。つきましては、一つだけお願いがございます」
「何じゃ」と家康がじろりと勝成を見た。
「冬の陣にても同道いただいた、堀直寄殿をわが勢にぜひお願いしたい」
信濃飯山藩主である堀直寄はずけずけものを言うが、とにかく頭の回転が早く聡い男だと勝成は見ていた。今回の戦にはうってつけである。家康はしばらく思案してから答えた。
「よかろう。堀の隊は大和口に付ける」
それだけ言うと家康はいくらか機嫌を直した。
家康はこの時、拠点を五つほどに分けていた。すなわち河内・大和街道・紀州街道・城北・京である。このうち、河内は藤堂と井伊に、紀州は浅野長晟に、城北には京極高知、京都警護には上杉景勝を置き、九鬼水軍も背後に構える。あとは大和街道である。どことなく生き生きと策を練る大御所は七十をとうに越えた老人とは思えないが、歳月は確かに過ぎている。この戦に出るのはあらかた、名だたる将の子の世代である。勝成も息子の長吉、いや元服なった勝重と共に出陣するのだ。
「六左衛門、いや日向守、この戦はわしにとっても、また皆にとっても最後の大戦になろう。ここ京都が惨禍に見舞われた応仁の乱から百五十年経つ。以来、この国は戦が絶えなかった。その間他国に侵入されなかったのだけは幸いだで。しかし、これからはそうはいかん。今はどんな遠くからでも大隊が寄せてくる。皆力を合わせ、国を守れるだけの備えをせんといかん」
勝成は家康がこの大戦のはじまりに、もうその先まで見ていることに改めて感心したが、勝成のみならず脇に座す秀忠にも説いているとみた。直に言うと説教になるから、父子というのは難しい。勝成は微笑んだ。
「素晴らしきご慧眼にござる。そう言えば伊達殿もいすぱにやに使節を派遣されとりましたな」
「あれは、わしとは考えが全く違うで」
家康は静かに、しかしきっぱりと言い切った。伊達の考えについて談義するつもりはないので勝成もそこで話を戻した。
「伊達殿にしたらわしはとんだ端物じゃろ。大人しく従うわけはないがのう」
家康はかかかと笑った。
「おぬしのお手並み拝見じゃ。くれぐれも昔のように一番鑓、先駆けなどと功名にはやるのは曲事につき、心しておけ」
関ヶ原のときと変わらない決まり文句である。
相変わらず、その変わらないところが勝成には小気味いい。まぁ、わしがきちんと働くよう難物をあてたか。勝成は納得していた。わしにとっても最後の戦になるかもしれんしのう。
しかし、悠長に構えている暇はない。勝成は京の南に待機している自軍に召集をかけて、山城国長池まで進み一夜を過ごすこととした。
事態は風雲急を告げていた。
勝成が長池に入ったとの知らせを受けた大和の代官や在地領主の使者らが訪れ、大野勢らの進攻について状況を述べ立てた。
城主筒井正次が逃げだしてもぬけの殻になった大和郡山城に始まり、城下も焼き討ちされ、その無法は奈良に迫る勢いだと言う。
「しかるに、日向守様いま直ちにご出陣を、平にお願いしたく」
勝成は懇願する者の顔を見た。
この者らは必死に助けを求めている。少ない人数で今の今まで持ち堪えようとしていたのだ。
先ほどまで、会ってもいない大和衆を厄介だと思っていたことを勝成は悔い、目を見開いた。
「あい承知した。いざ奈良じゃ! 古の都を焼かせることまかりならんっ」
その晩のうちに勝成隊三千は出立した。途中の木津川でも大和山辺の領主、奥田忠次の使者から要請を受け、翌朝には奈良で大和衆諸将と合流した。みな一様に勝成の水野隊三千人の到着に歓声を上げた。早馬からは本多忠政、松平忠明、堀直寄、伊達政宗も続々と大和路に集結しつつあるとの報が届いた。勝成は大和衆と奈良で後続を待ちながら、戦いに備えた。
間もなく勝成に大野治房の軍勢が退却しているとの報せが入った。
大野勢は二千と言っても、その内情は実浪人や荒くれ者を道中で調達したのもかなり含まれている。焼き討ちや略奪、町を破壊するにはよいが、組織的戦闘には不向きに違いない。ましてや先鋒には鬼日向こと水野勝成、後には伊達政宗の大軍が控えているとなれば、大坂方きっての武闘派である治房といえども、退却を決めざるを得なかった。
奈良は戦闘なく守られた。
大和衆一同はそれを聞いておーっと歓声を上げた。
「水野の旗印を見て、大野は退いたのや。さすが鬼日向様や」
「あの大鑓を見てみい、あれに敵うもんはおらへん」
勝成は呆気にとられた。
大和衆が水野隊を賛美するさまがあまりにも熱狂的だったからである。まだ何もしとらんでいかん。勝成はいくらか居心地の悪さを感じていた。
しかし、これが大和衆と信頼関係を結ぶきっかけになる。その意味でこの奈良進軍は大きな意味があったのだ。家康がわしを真っ先にここに出したのは理由があったのだ。ただ大和衆と合流するだけではない、大きな意味があった。
勝成は目の前が開けるような心地がする。
その日のうちに本多忠政、松平忠明、堀直寄らの隊も続々と到着した。大和方面軍の結集である。
奈良から法隆寺に至る途上、破壊され、きな臭い匂いが残る瓦礫の村々が現れはじめた。それは累々と続き、先には昔は城だったのだろうとかろうじて分かる黒焦げの巨大な建物が現れた。勝成は息を飲んだ。
「ひでえ、ひでえ有様じゃ。ここが……」
「大和郡山城にございます。城主は逃げており無事ですが、城下焼き討ちの際逃げ遅れた民が多数……」
奥田忠次がそう言って、手を合わせた。
勝成も同じようにした。
兵も民もない。これが、これが戦の非道なんじゃ。
もうこれで、終わりにせんといかん。
法隆寺から大坂の藤井寺に向かおうとする途中、大和方面隊一行は休憩を取った。
その時に家臣の中山将監が連れてきたのは新免改め、宮本武蔵だった。
武蔵はその頃すでにいくつもの決闘を経て高名の兵法家となっていたので、勝成も喜んで客将として迎えることにした。
「まず、殿にお尋ねしたい儀がござる」
会見を求められ勝成は彼の話を聞いた。そこで初めて、おとくが美作を出るときに花とどんぐりを渡して求婚した少年が彼であると知ったのである。
「それでは、おとくが言っていた美作の小僧はおぬしか」と勝成は目を丸くする。
「さようにございます。おとく様とはその後一度三村様のお屋敷で少しお話しただけで、殿が訝るようなことは全くございませぬ。さて、お尋ねしたいのは、殿がなぜ奥方様を離縁したのかということにございます。刈屋にもお訪ねしたことがございましたが、話を聞き驚いた次第。御嫡子を与えられた奥方を離縁するとは、よほどの事情があったのかと」と武蔵はまっすぐな目で問う。
勝成は正直、「家中のことをずけずけと聞きおって」とカチンと来てはいたが、真剣な様子の武蔵には、とても重要なことのようだった。そこで勝成は手短に事情を説明した。
すると、みるみるうちに武蔵の目に涙があふれた。
「おとく様は変わっておらぬ。やはり間違いはなかった。殿、それがしはおとく様に勝手ながらお約束したことがございます」
「何じゃ」
「強くなって、おとく様のお子をお守りするとお約束申し上げたのでござる。聞けば、ご嫡男美作守様はこたび出陣されるとか。ぜひそれがしを美作守の隊に付けていただきたいのです。されば先陣を切り、必ずや御嫡男を勝利にお導きいたしまする」
勝成は武蔵の真剣な、愚直なまでの思いに圧倒された。
こいつはどアホウじゃ。
初恋が叶うことがないと知りながら、惚れた女にとことん尽くすと決めておる。おそらく他のおなごには目もくれずに、ずっとそれだけを支えに剣の腕を磨いてきたんじゃ。そのために自分の命も捧げるという。まことのどアホウじゃ、
しかしそういう奴は嫌いではない。
翻って、自分はおとくに何かしてやれただろうか。勝成はふっと考えた。おとくはわしに添うて幸せだったろうか。おとくがかつて、芳井村をずっと見つめていたことが思い出された。添い遂げてやることもできず、それどころか備中に帰してやることもでけんかった。
勝成はがばっと武蔵に頭を下げた。
「貴殿に美作守に付いていただきたい。こちらからも頼む」
「畏れ多いことでございます。それがしもこれで約束の半分ほどは果たすことができまする」と武蔵は心底から嬉しそうに言う。
「いや、それほどまでにおとくに、せがれに忠心を持っていただき、心より礼を申す」
武蔵の表情はすぐにいつもの仏頂面に戻った。
「礼は殿や美作守様が無事に凱旋されてからでお願いいたします。また、このいきさつについては美作守はじめ御家中の皆様にはくれぐれも内密にお願いしたい」
「そうじゃな。承知した」と勝成も同意した。
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし
かずえ
歴史・時代
旧題:ふたり暮らし
長屋シリーズ一作目。
第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。
十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。
頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。
一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ
朽縄咲良
歴史・時代
【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】
戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。
永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。
信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。
この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。
*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

【読者賞】江戸の飯屋『やわらぎ亭』〜元武家娘が一膳でほぐす人と心〜
旅する書斎(☆ほしい)
歴史・時代
【第11回歴史・時代小説大賞 読者賞(読者投票1位)受賞】
文化文政の江戸・深川。
人知れず佇む一軒の飯屋――『やわらぎ亭』。
暖簾を掲げるのは、元武家の娘・おし乃。
家も家族も失い、父の形見の包丁一つで町に飛び込んだ彼女は、
「旨い飯で人の心をほどく」を信条に、今日も竈に火を入れる。
常連は、職人、火消し、子どもたち、そして──町奉行・遠山金四郎!?
変装してまで通い詰めるその理由は、一膳に込められた想いと味。
鯛茶漬け、芋がらの煮物、あんこう鍋……
その料理の奥に、江戸の暮らしと誇りが宿る。
涙も笑いも、湯気とともに立ち上る。
これは、舌と心を温める、江戸人情グルメ劇。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
勝利のために走るのではない。
生きるために走る者は、
傷を負いながらも、歩みを止めない。
戦国という時代の只中で、
彼らは何を失い、
走り続けたのか。
滝川一益と、その郎党。
これは、勝者の物語ではない。
生き延びた者たちの記録である。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
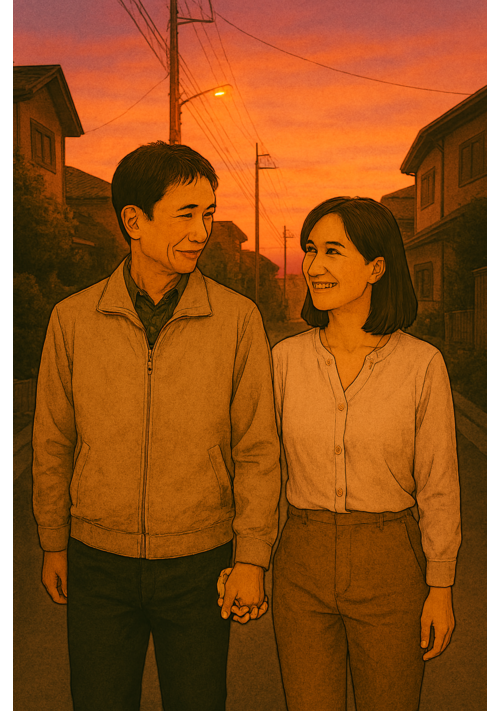
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















