63 / 89
◼️番外編 これが武蔵の生きる道
島原の乱を越えて
しおりを挟む島原の乱。
この反乱のいきさつについて、少しだけ説明しておこう。
島原・天草はキリシタン(キリスト教徒)の多い土地だ。ポルトガルの宣教師が長く定住し、教会やセミナリオ(学校)が建てられ、信徒の共同体組織(ミゼリコルディア)が固く守られていた。肥前全域にそれは広がっていたが、特に五島や天草の信徒組織は結束が固かったといわれる。この地域の領主であった小西行長や有馬晴信は自身もキリシタンだったので、信徒は保護されていた。しかし、豊臣秀吉の「判天連追放令」を契機に事態は暗転した。
それでもまだ秀吉の頃には迫害の度合いはゆるやかで、ルイス・フロイスやグネッキ・オルガンティーノら初期の宣教師たちも長崎に滞在していた。しかし、徳川幕府になって以降、段階的に禁教・迫害の動きは激化する。
慶長17年(1612)には幕府直轄の地域で教会の破壊と布教の禁止が命じられる。この流れの中で、「岡本大八事件」という贈収賄事件が起こり、最後のキリシタン大名、有馬晴信は切腹の沙汰となった。
慶長19年(1614)にはさらに「判天連追放令」が発布され、すべての宣教師、信徒の追放が命じられた。すでに大名を隠退していたキリシタン、高山ジュスト右近はこの時に海外に追放される。
この後、元和にかけて信徒の探索、逮捕、棄教を迫り拷問するといった「大迫害」へと進んでいくのである。踏み絵の実施、俵責め、穴吊るしなどの拷問は有名である。
寛永になって起こったこの「島原の乱」の原因は農民一揆だともいわれる。この地域の年貢の取り立てがたいへん厳しく、その苛政に耐えかねたということ。加えて、この直前に肥後熊本藩で加藤家から細川家への改易があり、浪人となった者が溢れていたということも理由として挙げられている。
それでも、その素地にキリシタンに対する激しい弾圧があったことは疑うべくもない。彼ら反乱の徒の旗印は聖杯にパン、頂点に十字架、下方に天使が描かれていたのだから。
武蔵は小倉藩に戻り、直ちに戦備えに加わった。養子の伊織は藩の侍大将として指揮を取ることになった。そして武蔵は、小笠原忠真の甥である長次が藩主を勤める豊前中津に赴くことになる。長次がまだ若く戦に不馴れだったので後見役を任されたのである。加えて、武蔵が齢56だったことも考慮されただろう。
多少の浪人(牢人)が加わっていたとしても、領民一揆に過ぎないーーというのが当初の見方だった。しかし事態は幕府側にとって望ましくない方向に進んでいく。
一揆勢は島原藩の松倉勝家勢と互角以上に戦い、逆に松倉勢を籠城に追い込んだ。一揆勢は島原城下を焼き払う。また、一揆に加わった天草勢は本渡城を攻め、唐津城も落城寸前まで攻め込まれた。一揆勢はここでひとつに結集することに決めた。天草から見て有明海の向こう側、島原藩の支城・原城がその場所だった。途中で藩の食糧、武器庫を根こそぎさらい籠城に備える。籠城の総勢は3万7000人といわれている。
原城は小高い丘に築かれており広く海に面している。要害として申し分ない、実に攻めにくい城だった。
初めに上使として派遣された板倉重昌は何度も一揆勢に攻撃をかけようと試みたが、城から投石が繰り返され、打撃が加わるばかり。幕府も業を煮やしていた。そこで上使を松平信綱に替えて九州諸藩で総掛かりの攻撃を行なうことにした。そこに武蔵の小倉藩や福山藩、九州全域の諸藩が加わることになったのである。総勢は12万余りといわれる。
一方で、一揆軍に楔(くさび)を打てない板倉は焦っていた。このままでは幕府の面子を潰すことになってしまうし、自身としてもふがいない。そこで板倉は援軍が到着する前に独断で総攻撃をかけた。
しかし、それは最悪の結果をもたらした。攻め手の上に投石や銃弾が雨あられと降り注ぎ、次々と兵が倒れていく。幕府側の犠牲者は4000人といわれる。
その中には板倉重昌も含まれていた。
寛永15年(1638)1月、水野日向守勝成は福山藩の6000人とともに島原の地にたどり着いた。
原城攻めは著しい進展を見せていない。「一揆勢はキリスト教を伝播したポルトガルの支援を期待して、海に面した城に籠城した」という情報が入ったため、幕府側は11日、長崎に入港していたオランダ船のデ・ライブ号に要請して海側から砲撃を加えた。攻撃としては決定的なものではない。ポルトガルが支援することはないと一揆勢に知らしめるための心理戦である。
そして実際に、一揆をポルトガルが支援することはなかった。
1月28日には副将に付いた戸田氏鉄が城からの投石によって負傷した。この後で、総指揮官である松平伊豆守は意を決して戦略を練り直すこととした。歴戦の将に意見を聞くために集まってもらったのである。すなわち、立花宗茂、水野勝成、黒田一成らの老将達である。黒田一成は黒田勘兵衛、長政、忠之三代に仕えた家臣で、黒田十二将と呼ばれた一人である。
「城内には3万の人がおるけん、いくら兵糧を積んでいようが、それほど長くは持たぬ。もう籠城もひと月以上になる。そろそろ底が見えて来とるやろう。肝要なのは補給路を完全に絶つこっちゃ」と黒田一成が言う。
「降伏の呼びかけは、都度した方がよか。兵糧がなければ皆心が揺れる。城内には女子や子どももおるち聞きようたけん。そいでん折れんやったら……」
「われら12万の総攻撃じゃ。おらんだ船ではないが、わしら急造で軍船をこしらえとる。海の退路も絶つ」と水野日向守が締めくくる。
松平伊豆守は力強くうなずいた。
一方、武蔵も島原に到着している。福山藩の旗印を見つけてあいさつがてら顔を出した。そこには、もうとっくに少年ではなくなった水野美作守勝重が藩の大将として在陣している。江戸でもたびたび顔を合わせていたので、久しぶりという感はない。それでも大きな兜を付け甲冑具足を身に付けているのを見ると、22年前の大坂の陣を思い出すのだ。
「こたびは大将を務められるのですな」と武蔵は目をしばたく。
「武蔵殿に付いてもらえませんから、心もとないかもしれませぬな」と勝重は笑う。そして、側にいた自身の嫡男を呼び寄せた。少年は甲冑具足にまだ慣れていないようだ。少しぎこちなくやってきて挨拶する。
「水野伊織と申します。こたび初陣として参りました」
きりりと濃い眉につぶらな瞳をした少年の名を聞いて武蔵は嬉しそうに、うん、うんとうなずいた。
「ご武運をお祈りしておりますぞ」
原城は籠城状態のまま、2月に入り日を重ねた。兵糧を入れる途は完全に絶たれている。幕府勢はすでに内通者を得ていて、城内の様子は逐一伝わっている。
もう一粒の米もない。
皆痩せ細って、目ばかりギョロギョロし、力衰えて寝込んでいる者もいる。キリシタンの者は時がくるとふらふらと集まり、祈りの言葉をひたすら繰り返している。
一揆勢はこのとき城の崖を下りて海に行き、海草を採って食糧にしていたという。飢餓状態に陥っていることは明白だった。
それでも一揆勢の大将である天草四郎時貞が矢文や使者による降伏の呼び掛けに応じることはなかった。幕府勢は総攻撃をかける時だと判断した。
原城を取り囲んだ12万人あまりの幕府勢が号令の時を待っていたその時である。
突然動いた一団があった。
鍋島勝茂の軍勢が城の一画に火を放って、一斉に三の丸に突入したのだ。まだ攻撃の指令は出ていない。攻撃は2月28日に予定していたのだが、まだ27日だったのだ。他藩の隊は鍋島が一番乗りに早駆けしたとみて、われ先にと突入していった。突然の攻撃に籠城側も決死の覚悟で立ち向かう。もっと具体的に言えば、相討ちを覚悟して捨て身でかかってくるのである。籠城勢には武士(浪人)もいるがそうでない者が大半である。しかも皆飢えのため体力もない。
そのような人々が、これを命の限りと鑓を持ってまっしぐらに向かってくる。手負いの獣と同じである。突入してくる者は格好の獲物といってよい。勢い任せで飛び込んだ幕府軍の兵がここで多く犠牲になった。
このとき備後福山藩の総大将、水野美作守勝重は鍋島勢が早駆けするのを見て、自隊に本丸への総攻撃を命じる。皆がなだれ込むように本丸に乗り込んでいく。勝重は隣り合った日向延岡藩の有馬直純と競うように本丸に飛び込んだ。
一番だ。
そう思ったのは一瞬のことだった。
冑も甲冑具足も付けていない生身の、痩せ細った人間の群れが竹槍を持って襲いかかってきた。
殺られる。
勝重は生命の危険を感じて、向かってくる人間たちを鑓でなぎ払い、突き刺していく。鑓はすぐに使い物にならなくなる。勝重は抜刀し、竹槍を避けながら敵を斬り捨てていく。甲冑を何度も竹槍がかすめていく。藩士が何人も助太刀に入るが、きりがない。そのうち味方の悲鳴が聞こえてくる。
「ぎゃああああっ」
振り返っている余裕はない。勝重は脂汗を流しながらひたすらにかかってくる者を斬り伏せていった。
この時、武蔵は中津藩主とともに城に突入しようとしていた。丘を上がろうとしている一勢に、いきなり石が雨あられのように降ってきた。籠城勢が投石しているのだ。味方が一人、二人と、「うわあああっ」と転げ落ちていく。武蔵が倒れた味方に手を貸そうとしたその時だった。
ゴンッ。
武蔵の頭に大きな石が命中した。
武蔵はよろめいて、その場に倒れた。
このように籠城した一揆勢は捨て身の反撃に出ていたのだが、多勢に無勢、続々と突入してくる幕府軍の前に一人、二人……十人……百人と倒れていく。辺りは血の匂いが充満し、血だまりに足を滑らせて転ぶ者も少なくなかった。しまいには倒れた者がそこらじゅうに溢れ、足の踏み場もないようなありさまだった。
原城は落城した。
一揆勢は皆殺された。首を取られた。
大将の天草四郎時貞も討たれ、首を取られた。
以後、籠城勢以外の領民にも厳しい宗門改め(キリシタン根絶のための)と粛清が行われることになる。
武蔵は水野美作守勝重が原城の本丸一番乗りを果たしたので、ねぎらいの言葉をかけようと福山藩の旗印を求めて人波をかき分けていた。
人々の顔は疲れきっていた。どこを歩いても勝利を得たと喜び勇んでいる人はいない。刃こぼれして錆だらけの刀のように、ただ疲れきって無言でいるだけだ。武蔵もさらしを頭に巻いて、まったく同じ様子だったが、美作守が一番乗りをしたことを聞いて祝ってやりたかった。
本当に立派だったと伝えてやりたかった。
福山藩の見慣れた沢瀉紋(おもだかもん)の旗差物の武士の群れの中に、武蔵は勝成ともう一人の老将を見いだす。勝成の方が武蔵に気がついて、声をかけてくれた。武蔵が陣を訪れたわけを告げると、勝成が連れていこうと歩き出す。勝成とともにいた老将も、「ああ、わしもねぎらいたか」と言い一緒についてきた。
大将の椅子に腰かけている美作守は兜を外した姿で虚ろな目をしていた。武蔵はその前に膝まずいて、挨拶をする。美作守の目が武蔵の姿を捉え、その背後に立つ父親と老将を認めた。それを見て彼の感情が堰を切ったように溢れだした。
「武蔵殿、父上、立花左近殿、わしゃちぃともわからんのじゃ」
3人は美作守の鬼気迫る様子に思わず息を飲んだ。
「これは、まことに戦なんじゃろうか。本丸に攻めかけたところまではわしもそうじゃと思うとりました。しかし、死にもの狂いでかかってくる敵を次から次へと斬り伏せて、前後左右無我夢中で斬り伏せて、ふと我に返って辺りを見回したら、敵は皆、骨と皮のように痩せ細って……もう手向かう力なぞどこにも残っとらんような……そんな亡骸がごろごろと転がっておった。なんもかんも皆殺しじゃ。その首を取っておる者の姿を見ておったら……女子どもの首まで取っておる。大坂の陣も難儀な戦でございましたが……わしは武蔵殿に守られておったけえ、何も見とりゃあせんかったんか。どうか教えてくだされ」
3人は顔を見合わせている。
すると、立花左近が勝成に向かってぽつりと言う。
「そげん問いかけば、わしもずっとしちょった。答えの出ん方が多かった。やけんが、己に問い続けるんがわしらの務めやないやろうか」
「そうじゃな……」と勝成が同意する。
武蔵はしばらく考えていた。そして、ゆっくりと美作守に告げる。
「こたびはケガしてしもうて、ろくに働けんかった。それで申すのも何じゃが、わしは大名ではなくいつでも客将じゃけえ、ここは遠慮なく言上つかまつる。美作様、わしゃ、この戦を自身の戦果に加えて誇りにしようとは決して思わんよ。表向きのことはいろいろあるじゃろうが、それでええんじゃなかろうか。いずれにしても貴殿はようお役目を勤めんさった。それでええんじゃ、ええんじゃ」
美作守は武蔵の顔をじっと見つめて、うなずいた。2人の老将は苦笑いしつつ、そのやりとりを見守っていた。
水野日向守勝成はこの少し後、三代将軍徳川家光に自身の人生を回顧する『覚書』を献上している。そこには波瀾万丈の戦歴が記されているが、島原の乱についての記述は控えめである。書いた当時はまだ記憶に新しいものだったからかもしれない。
ただ、のちに漢文で自身の人生を綴った碑文にも島原の乱の記述はまったく出てこない。
このことは彼の最後の戦に対して彼自身がどう感じていたのか、想像する役に立つのではないだろうか。
◼️
寛永16年(1639)、新免武蔵は前年に養子の伊織が小倉藩の家老に任ぜられたことなどを理由に藩の兵法指南役を辞することにした。自身の兵法を一子相伝として伊織に伝え継ぐことは十分に成したと武蔵は思う。それならば、親がいつまでも子の側にいるのも煩わしいはずだ。
そのように思うきっかけがあった。
立花左近宗茂はこの前年、つまり島原の乱に参陣した年に家督を養子の忠茂に譲って隠退した。そしてこの年、水野日向守勝成は家督を嫡子の勝重に譲った。二人とも譲る時期をかねてから見計らっていたのだろうが、島原の乱がひとつの区切りだったといえるかもしれない。
島原の乱に参じた武蔵には、二人の気持ちがよく分かるような気がした。そして、自身もまた新たな環境を得たいという気になったのである。
名残惜しそうに引き留める藩主の小笠原忠真に、武蔵はにこやかに暇乞いをする。
「殿、本来ならば伊織のみがお世話になれば済む話でございました。それにも関わらず、仕官は面倒だなどと考えていた私まで取り立てていただき、長く重用下さったこと、幸甚の極みにございました。おかげさまで自身の兵法も形となり、多くの弟子を得ることまでできました。これからは自身の終の住みかをどこぞに見つけて、兵法の書を書き上げることに余生を費やしたく存じます」
忠真は寂しそうに聞いている。すでに養父の決心を聞いて承知している伊織はただただ、そのやりとりを生涯心に刻み込もうとするかのように、真剣に聞いている。
「どこか行くあてはあるのか。いくらでも紹介状を用意するぞ」と忠真は最後に聞く。
「どうでしょう、しばらく放浪しながら考えますかな。風に任せようかと思うております」
そして武蔵はまた、新たな旅に出ていった。
自分だけの道を行くために。
〈此道を学人の智力をうかがひ、直なる道ををしへ、兵法の五道六道のあしきところを捨させ、をのつから武士の方の實の道に入、うたかひなき心になす事、我兵法のおしへの道なり。〉
(『五輪書』風の巻から引用 ※1)
完
※1 『決定版 五輪書 現代語訳』宮本武蔵
大倉隆二訳・校注(草思社)
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。


四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

もし石田三成が島津義弘の意見に耳を傾けていたら
俣彦
歴史・時代
慶長5年9月14日。
赤坂に到着した徳川家康を狙うべく夜襲を提案する宇喜多秀家と島津義弘。
史実では、これを退けた石田三成でありましたが……。
もしここで彼らの意見に耳を傾けていたら……。
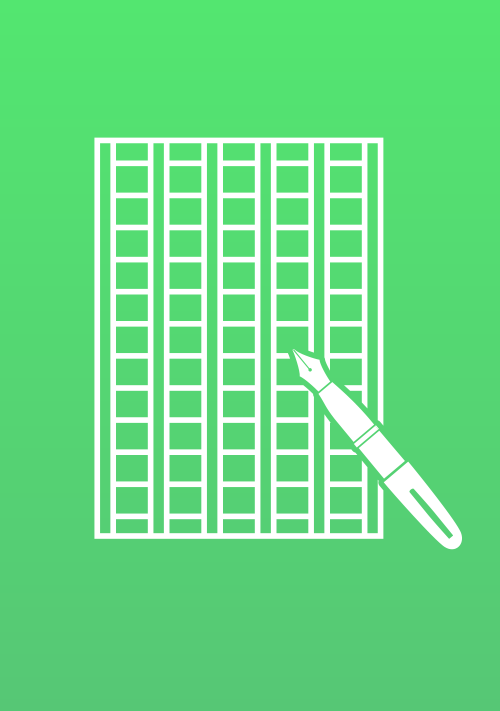
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















