14 / 154
六 ラプンツェル殺人事件
6
しおりを挟む
というわけで、朝である。容赦なく朝。意識がそのまま落ちてしまった。不可抗力すぎる。
これでも、結構俺頑張った方、偉い。
青年の腕の中に抱き込まれて目が覚めたダリオはひとしきり現実逃避した後で、す、と冷静になった。こいつの体液恐ろしすぎだろ……と改めて思う。これで、当初より結構手加減してくれるようになっているらしい。初めて頬を舐められた時の原液100%で昨日の内容をされていたら、たぶん発狂待ったなしだっただろう。
頭が馬鹿になり過ぎる。そのような状態で決定的な選択をしなくてよかった。
昨日のふるまいを思い出して喚きたいような気もしたが、記憶を反復してもご利益はない。生産性がないことは止めるに限る。
「はぁ」
つめていた息をゆっくりと吐く。シーツの上で、力が抜けて行くのを感じた。ごろりと転がったまま、テオドールの顔を観察した。しようとしたのだが、少し直視しかねるような気持ちになって、視線を落とす。頬を押し当てたシーツの感触が気持ちよかった。よい匂いがする。体を綺麗に清められ、寝台もおろし立てのようにさらさらとして気持ちいい。テオドールが取りかえたのか。彼しかいないのだから、そうなのだろうが、シーツをかえるテオドールなど、想像しづらいものがある。もし彼がやったのなら、絵面が結構面白いなと思った。ふ、と笑いが零れて、ダリオはようやくテオドールに視線を戻す。
テオドールは死体のように目をつぶって動かず、その彫像のような美しい顔をダリオはじっと見つめた。一緒に寝たことはなく、こんなにじっくり彼の顔を見たのもやはり初めてである。目を閉じていても、ため息が出るように美しい青年だ。
角度によっては藍色から紫へと揺らぐまつげが、目元に艶のある陰影を落としている。まなじりは、すっと切れ上がっており、涼やかさと同時に妖美な色気を添えていた。白皙の額から、高い鼻梁は、どんな芸術家ならその完璧な形を作れただろう。やわらかな黒髪は夜の闇を思わせる漆黒で、首筋から肩の稜線まで無駄のない筋肉の美しい造形を描いている。
綺麗だな、と思うが、ダリオにとって重要なのはそこではなかった。
(どう考えてるんだ、こいつ)
整いすぎた顔を見つめながら、昨日のやり取りについて思い出した。
テオドールはどうしてダリオのことを好き勝手しないのか。結局聞けていない。伝えたのは、もっと彼のことを知りたいと思うダリオの要請だけだ。
あの時はなんかこう、なんもかんもつながった気がして、ちゅ、と軽くキスしたら、追いかけてきてキスされて……まあ気のせいだったな、とダリオは結論付けた。
(何も分からん)
口にしなければ分かるわけがない。わかった気がしただけだ。
つまり振り出しに戻る。
(なんで追っかけてきたんだ)
ダリオがキスしたからといって、別にテオドールが追いかけてくる必要はなかった。メンテナンス要請と思われたのか? ありうる。
普段からダリオの身体の調子を整えるといって、メンテナンスされている一環だ。テオドールはちょこちょこと頻繁に、メンテナンスしてもいいかタイミングを見計らって聞いて来る。昨日のように深くまではしないけれども、軽くされただけでもダリオは毎度バスルームに直行だ。
身体の変化についてダリオの内側に触れてきたのはどうか。悲しいお知らせだが、本人の言う通りただの『診察』の可能性が高い。テオドールは、ダリオのメンテナンスについてはかなり熱心だ。
(治療やメンテナンスこまめにしてきて、執着されてるなとは思うが、欲望とかほとんど感じねぇし……昨日は少しあったような気がしたけど、俺の願望だったな……気のせいだな……)
以前も因果関係のおかしいセクハラ発言をしてきたが、性愛関係に関しては、そもそも種族的に理解しづらいのかもしれない。
(まあ、人外だしな……象と蟻……そこ軽視してもろくなことにならないやつ……)
その割に、歩み寄ってくれている方だろう。他人に自分と同じ前提を求めるのは、人間同士でも酷というものだ。生態系も異なるようなテオドールが、ダリオに対してなるべく社会的コンセンサスの形成をしようとしてくれているだけ、稀有なことなのだろう。ダリオが逆の立場なら、これまでの価値観を引っくり返すような相手の言動に、自ら歩み寄れるか疑問だ。言うほど簡単なことではない。こいつ、なにげに凄い努力家だよな、とダリオはテオドールに対して、敬意を覚えるところがあった。恐らく、ダリオがしている歩み寄りよりも、テオドールの方がかなり寄って来てくれている。
(あー駄目だ。やばい、好きになる……無理……)
ダリオは内心煩悶した。ダリオより何倍も何十倍も、下手したら何百何千何万倍か知らない、大きな生き物が、こちらを壊さないようにおそるおそる触れて来る。物凄く注意深く、慎重に、ダリオの意思を尊重しようとして、時たま仰天するようなこともするが、それだってかなり寄って来てくれてるわけで。やたらメンテナンスしてくるのも、壊さないようにするための調整じみた行いなのだろう。
最初に不法侵入されて、コミュニケーションも脅しかと思ったので、こういう態度になってしまっているが、改めるべきのような気もしてきた。だが、今改めるとなると、俺、好意隠せないんだが……とダリオは眉根を寄せた。
それを差し出していいのかわからない。
性欲ひとつとってもそうだ。
ダリオは欲情してしまい、しっかり気持ちよくなってしまったのだが、テオドールはどうだったのだろう。彼に性欲などあるのだろうか。そもそも勃起自体するのか謎である。今まで、寝るのも知らなかったくらいだ。もしかしたら眠っているのとは違うのかもしれない。見たままとは限らないのだ。結局、異次元異種族のことは分からない。人間同士でも、他者のことなんて分からない。それが当たり前だ。だから、分からないことは、ひとつひとつ距離を見て確認していくしかない。性急につめ寄っても、それはダリオの欲望だ。テオドールの要望ではない。
考えに没頭していたダリオは、ふと強い視線を感じて、ぎょっとする。
「ダリオさん」
いつの間にか、青年が切れ長の目で、こちらを見つめ返していた。一本一本のまつげが、恐ろしく長い。妖艶な目じりは、ぞくっとするような色香をたたえ、アビスの冷たいロイヤルブルーを、かすかに宝石のシラーめいた紫が揺れている。それは深海で燃える炎のような、この世にありえない幻想美の凝縮だった。その炎をいつまでも見ていたいような不思議な浮遊感を覚え、ダリオはぼんやりと魅入ってしまう。
「お前も寝るんだな」
するっと考えなしに出た言葉は、間の抜けた感想になった。気のせいでなければ、テオドールは少し表情をやわらげ、一瞬笑ったように思えた。
「睡眠は必要としませんが、真似事にも風情があります」
吐息のかかる距離で、抱き込まれたまま言われると、ダリオは声がつまって、言葉少なくなった。
「そうか」
なんか余計に間抜けになったなと思うが、頭が回らない。
「ダリオさんは、体の調子はいかがですか」
「調子は驚くほどよいな」
自分で言って気づいたが、爽快感にみなぎっている。なんでだ。今なら二十四時間寝ないで働けそうで、やばい薬でもキメたみたいな気分になった。テオドールがわずかに目を見開くと、ずい、と顔を寄せて来た。
「僕の影響かもしれません」
近づかれた分、ダリオは手でテオドールの胸を押し返すようにして微妙に距離を取る。
「そういや、お前……勝手に中が濡れるとか、俺の体どうなってるんだ」
「ああ……」
テオドールは珍しく言い淀んだ。
「ダリオさん、少し触れますが、よろしいですか?」
「ああ……? どうぞ?」
「それでは失礼します」
乗り上げるようにして、テオドールが右手を寝台につくと、ダリオの顔に影が落ちた。無抵抗にしていると、青年はシャツの下へと優しく五指を差し込ませる。そのまま潜り込んだ二本の指が背部へと向かい、臀部の尾てい骨を、ざりり、と下から上へなぞりあげるようにした。
いやらしさはなく、ただ触診されているような、何か確かめる手つきだ。尾てい骨から下へと臀部の皮膚を指圧しながら、次第に浮き上がるダリオの腰骨の輪郭を再度辿り、今度はまた前にゆっくりと戻ってくる。最後に、腹部からへその下を親指の腹でなぞると、真正面から口を開いた。
「この次元に、僕の影響が出ることは……多々ありますが、昨日の事象は、レアケースです。あれは、僕の影響だけでは起きないことかと」
「……あ、わかった。もういい」
ダリオは中途半端に察して、テオドールの口を手でふさいだ。その手を、テオドールが引きはがして、かえってつかえがとれたように囁く。
「ダリオさんが僕を受け入れて悦んでくださったので、あのように」
「止めろ止めろ、もういい、ストップ」
「ダリオさんがお尋ねになったことでは?」
「あーそうだね」
テオドールは首をかしげている。
「昨日は、ダリオさんの体を見て驚き、不躾に凝視してしまいましたので、申し訳ありませんでした」
ダリオが不快に思ったのかと考えたのか、謝罪してきて、逆に胃が痛い。もしかして、セクハラをしたのかと思って謝ってきているなら、違うし、以前言われたことを自分で考えて、謝罪選択するなんて、素直すぎる。
「いや違うし、それはいい。あと、全然わからんが、昨日は驚いてたのか」
「はい。端的に申し上げると、僕を受け入れたいと、あなたの体が劇的に変化していた。つまり、繁殖可能なように、本格的な変態へと入りつつあったので、」
淡々と真顔ながら、妙な迫力で繰り出されるそれに、ダリオはもう一度テオドールの口を両手のひらでふさいだ。
「あーやっぱりちょっとだけ待ってくれ」
テオドールは、口を塞がれたまま、大人しく目だけでダリオをじっと見返している。青年の言うとおり、聞いたのはダリオで、知りたいのもダリオである。
「悪い。落ち着いた」
そっと手のひらを外すと、ダリオは引きつった顔で尋ねた。
「繁殖可能なように、変態しつつあったって、い、今も? いや、まあ、いいが……え、これ今後もやっぱり引き続き濡れるのか?」
「いえ、一時的なものですから、今は元に戻っています」
「そ、そうか」
ほっとしたような、残念なような、ダリオは力が抜けた。
「ですが、ダリオさんが僕を受け入れたいと思ってくださったら、同じようになるかもしれません」
ダリオは少し口を開き、閉じた。自分が受け入れたいと思ったら、濡れる、ということは……と次第に顔面に血がのぼるのを感じた。片手で顔面を覆う。告白もしていないのに、開陳されまくっている。それともテオドールには何も伝わっていないのか。どうなんだ。
「あ、あのな、繁殖って、子ども作るってことだよな?」
「そうですね」
「よく分からないが、お前、性欲あるのか?」
「性欲……ですか」
勃起するのか、と聞いた方がよかったのだろうか。テオドールは少し思案する風である。
「僕たちは元々、お互いの精神を交えることで繁殖をします。この次元の人々に当てはめて僕らの性欲に該当する状態を説明することは、正確性を欠くかもしれません」
「精神を交える」
おうむ返しになってしまう。
「より近い表現、観念は――法悦、でしょうか。仏や神の教えを聞き、信じ、心にわく悦び。恍惚感、エクスタシーの意もあるのでしたか。その意味では、僕にも性欲があると申せましょう」
「その、具体的に、お前勃起したり、するのか? というか、俺が昨日繁殖可能な状態になりつつあったって、それだと、どういう」
「ダリオさん」
覆い被さるようにして、テオドールが顔を寄せて来る。 間近に覗き込む人外の引き絞られた瞳孔は、深い亀裂のようで、ダリオはかたまった。
「精神を交える方法は、法悦に当たるような恍惚感、エクスタシーを与えて、あなたの中に入れていただく。あなたの肉体だけではなく、あなたの心の中に」
とん、と胸元を美しい指先が触れることなく指し示す。
「僕とあなたの精神が、絡み合い、互いに溶け合い、身悶え、魂の尾をよじらせながら、ぐちゃぐちゃに溶け合って一つになるということですよ。通常の生物では難しいでしょう。でも、昨日のあなたは、その余地があった。僕をあなたの中に、受け入れようとしてくださっていた」
それが、形として体機能変化で現れていたのでしょう、と。
テオドールの説明に、ダリオはもう顔から火が出る思いだった。色々テオドール側へ発覚している上に、言われたことを想像して、腹の奥がずくりと疼痛を覚える。
「安心してください。繁殖は、僕には時期尚早でもあります。何より、あなたの同意を得ずに、繁殖に持ち込むつもりはありません」
「そ、そうか……」
避妊は最低限のマナーだ。今回の事件にかかわった人間の男性よりも、人外のテオドールがわきまえているのはなんか皮肉な話だなと思うが、頭のわいたダリオは、ますます好きになる……クソヤバ怪異なのに……と煩悶する羽目になった。もはやテオドールが何をしても好感度が上がるステータスぶっ壊れ状態に脳が判断レベルを下げまくっている。
「僕の言うことは、不安ですか?」
「いや……え、いや、お前、いつも嘘はつかないだろ。そこは信用してるよ。あと、なんだ。テオ、お前さ……あー、時期的によくて、俺が同意したら、その、繁殖? 相手、俺も選択に入って来るの、か?」
え、入って来るの? とダリオはよく分からない恥ずかしさで、早口になった。種族が違う。それなのに、繁殖相手として、候補の射程に自分が入って来るのか?
そうしたら。テオドールは、嫣然と微笑んだのだ。
「ダリオさん――僕の『花』」
まるで隠した宝箱の中を見るように覗き込みながら、繊細な手つきでテオドールの長い指がダリオの頬に触れる。
「あなたに、僕を受け入れる変化が起きて……僕がどれほど驚いたことか、あなたには分からないでしょう」
ゆっくりと、まるで慈しむように頬を繰り返し指先がなぞった。それは、どこか遠慮がちに、触れがたいものを確かめるような動きだった。
「僕らは、『花』に拒絶されることの方が多いのです」
そういえば、当初そんなことを言っていた。あれは脅しではなく、普通に事実を言っていたのかもしれん、とこの段になってダリオは思った。あの時のテオドールに心理的駆け引きをされたかと思っていたが、これまでの付き合いから、こいつはマジレス生物だと察している。
「僕らがどれほど『花』に執着し、執心しようとも、『花』からは忌み嫌われ、逃げられ、憎まれ、恐怖され、最期、支配者側は『花』を蹂躙して殺す――得られないのであれば、手折るしかありません」
熱のない淡々とした物言いは、他人事のようだった。テオドールの考えというより、彼の普段の言動を見るに、種族全体の傾向の話なのかもしれない。これまで実際に起きた種族的経験を、どこか突き放して言うような印象を受けた。物騒なことを無表情に言いながら、その美しい指先は、ただただゆっくりとダリオの顔の輪郭を確認するように辿っている。やがて、テオドールはひとりごとのように呟いた。
「この姿も、擬態に過ぎませんしね……」
ダリオは一瞬面食らった。
「そうか」
返答に困って、またもや間の抜けた返しになる。擬態と言うことは、本体は人の形をしていないということだろうか。ダリオとしては、よほど生理的嫌悪を覚えるようなものでなければ、本物だろうが擬態だろうが、どちらでもいい。だが、もしかしたらその生理的嫌悪を催させるようなものなのかもしれない。
「あ~、擬態ってのは、本体が別の姿ってことか?」
「はい。おそらくダリオさんには、耐えられないでしょう。僕ら支配者を垣間見て、正気でいられる生物は少ないのです。ですから、見せるつもりはないのですが、絶対に可能性がないとも言い切れませんので」
「その時になってみなければ分からない、としか言えないな。性格も変わったりするわけじゃないんだろ」
「存在の連続性は保たれています」
「じゃあ、いいかな、分からんがたぶん、お前がお前なら俺は別に」
テオドールがテオドールであるなら、姿かたちが変わっても、ダリオに酷いことはしないだろう。彼が彼のままに、ダリオにしてくることは、実のところ、嫌なことなどひとつもない。テオドールは倫理観がぶち抜いているが、ダリオに対しては呆れるほど愚直だった。驚くほど積極的合意を確認してくるし、ダリオが嫌だと言えば止める。当たり前のことだが、この当たり前ができない人間は多い。
ダリオは体格が良く、表情もそうくるくる変わるタイプでもないから、寒くないか気遣われて服を着せてもらったり、気分や体調を気にかけてフォローしてもらったりということはあまり経験したことがない。
そういうことを過剰にされれば嫌気がさすかもしれないが、テオドールはいちいちダリオの意思確認をするし、何よりダリオの自己決定を優先してくる。
ただ、大切にされていることを日々感じさせられるだけだ。
それなら、何されたって、ダリオは構わなかった。ダリオがテオドールを好きになったのは、彼がダリオを大事にしてくれたからだ。元々ダリオは、テオドールのことは化け物だなと思っているし、その点を改めて強調されたとしても、あまり引っかからなかった。
好きだと、ダリオは言ってしまいたかった。だが、テオドール風に言うなら、時期尚早、タイミングではないなという気がずっとしている。テオドールにはまだ、そうした感情を理解する受容体が出来ていないように思われた。これまでもそうだ。『花』に対する挙動に、好意にも似て決してそのものではない感情のベクトルを感じていた。本人の申告のとおり、それは種族的本能のような執着や執心なのだろう。ダリオの好意とは、やはり違うものだという感じがする。だから、彼の種族は、『花』が得られなければ、蹂躙してしまうのではないか。まるで、子どもの癇癪だ。テオドール自身はそこから一つ頭を飛びぬけているようではあるが、過信する気にもなれない。なにしろ、ダリオはテオドールのことなどわからないのだ。
しくじりたくない、とダリオは思う。相手を尊重しなければ、ひとりよがりになる。気持ちを押し付けたって、理解できないものをプレゼントしても相手も迷惑なだけだ。少しずつ、階を作っていくしかない。
「ダリオさん――」
少しだけためらうような手つきで、テオドールがダリオの頬を撫でた。彼の目が細まる。
「今朝もメンテナンスしてもよろしいですか?」
ダリオは別に体調はよかったが、肘をついた片手で体を支え、上半身を起こすと、手を伸ばしテオドールの頭を引き寄せた。
ちゅ、と唇がダリオのそれを吸い、角度を変え、何度もついばんでいく。テオドールの体液効果は相変わらずで、主導権を握るのは難しい。ダリオも何かしてやりたいなと思う気持ちはあるが、当分無理そうだった。
「……ふっ……」
鼻を擦り合わせ、テオドールは、ちゅっ、ちゅ、と小鳥が餌をぱくつくように、繰り返しダリオの唇を食んだ。
「僕の『花』——」
ダリオの名と、僕の『花』を交互に、テオドールはそれ以外の言葉を忘れたかのようだった。ダリオは、自分がテオドールの繁殖相手に選択で入って来るのか尋ねたが、もうこれが答えも同然だ。
ひらいていく――花開かされる。ダリオは、テオドールに開かされていくのを感じた。体が、開いてしまう。もう、体の奥から、こぷり、と塊のように蜜が零れ落ちるのを聞いた。
これでも、結構俺頑張った方、偉い。
青年の腕の中に抱き込まれて目が覚めたダリオはひとしきり現実逃避した後で、す、と冷静になった。こいつの体液恐ろしすぎだろ……と改めて思う。これで、当初より結構手加減してくれるようになっているらしい。初めて頬を舐められた時の原液100%で昨日の内容をされていたら、たぶん発狂待ったなしだっただろう。
頭が馬鹿になり過ぎる。そのような状態で決定的な選択をしなくてよかった。
昨日のふるまいを思い出して喚きたいような気もしたが、記憶を反復してもご利益はない。生産性がないことは止めるに限る。
「はぁ」
つめていた息をゆっくりと吐く。シーツの上で、力が抜けて行くのを感じた。ごろりと転がったまま、テオドールの顔を観察した。しようとしたのだが、少し直視しかねるような気持ちになって、視線を落とす。頬を押し当てたシーツの感触が気持ちよかった。よい匂いがする。体を綺麗に清められ、寝台もおろし立てのようにさらさらとして気持ちいい。テオドールが取りかえたのか。彼しかいないのだから、そうなのだろうが、シーツをかえるテオドールなど、想像しづらいものがある。もし彼がやったのなら、絵面が結構面白いなと思った。ふ、と笑いが零れて、ダリオはようやくテオドールに視線を戻す。
テオドールは死体のように目をつぶって動かず、その彫像のような美しい顔をダリオはじっと見つめた。一緒に寝たことはなく、こんなにじっくり彼の顔を見たのもやはり初めてである。目を閉じていても、ため息が出るように美しい青年だ。
角度によっては藍色から紫へと揺らぐまつげが、目元に艶のある陰影を落としている。まなじりは、すっと切れ上がっており、涼やかさと同時に妖美な色気を添えていた。白皙の額から、高い鼻梁は、どんな芸術家ならその完璧な形を作れただろう。やわらかな黒髪は夜の闇を思わせる漆黒で、首筋から肩の稜線まで無駄のない筋肉の美しい造形を描いている。
綺麗だな、と思うが、ダリオにとって重要なのはそこではなかった。
(どう考えてるんだ、こいつ)
整いすぎた顔を見つめながら、昨日のやり取りについて思い出した。
テオドールはどうしてダリオのことを好き勝手しないのか。結局聞けていない。伝えたのは、もっと彼のことを知りたいと思うダリオの要請だけだ。
あの時はなんかこう、なんもかんもつながった気がして、ちゅ、と軽くキスしたら、追いかけてきてキスされて……まあ気のせいだったな、とダリオは結論付けた。
(何も分からん)
口にしなければ分かるわけがない。わかった気がしただけだ。
つまり振り出しに戻る。
(なんで追っかけてきたんだ)
ダリオがキスしたからといって、別にテオドールが追いかけてくる必要はなかった。メンテナンス要請と思われたのか? ありうる。
普段からダリオの身体の調子を整えるといって、メンテナンスされている一環だ。テオドールはちょこちょこと頻繁に、メンテナンスしてもいいかタイミングを見計らって聞いて来る。昨日のように深くまではしないけれども、軽くされただけでもダリオは毎度バスルームに直行だ。
身体の変化についてダリオの内側に触れてきたのはどうか。悲しいお知らせだが、本人の言う通りただの『診察』の可能性が高い。テオドールは、ダリオのメンテナンスについてはかなり熱心だ。
(治療やメンテナンスこまめにしてきて、執着されてるなとは思うが、欲望とかほとんど感じねぇし……昨日は少しあったような気がしたけど、俺の願望だったな……気のせいだな……)
以前も因果関係のおかしいセクハラ発言をしてきたが、性愛関係に関しては、そもそも種族的に理解しづらいのかもしれない。
(まあ、人外だしな……象と蟻……そこ軽視してもろくなことにならないやつ……)
その割に、歩み寄ってくれている方だろう。他人に自分と同じ前提を求めるのは、人間同士でも酷というものだ。生態系も異なるようなテオドールが、ダリオに対してなるべく社会的コンセンサスの形成をしようとしてくれているだけ、稀有なことなのだろう。ダリオが逆の立場なら、これまでの価値観を引っくり返すような相手の言動に、自ら歩み寄れるか疑問だ。言うほど簡単なことではない。こいつ、なにげに凄い努力家だよな、とダリオはテオドールに対して、敬意を覚えるところがあった。恐らく、ダリオがしている歩み寄りよりも、テオドールの方がかなり寄って来てくれている。
(あー駄目だ。やばい、好きになる……無理……)
ダリオは内心煩悶した。ダリオより何倍も何十倍も、下手したら何百何千何万倍か知らない、大きな生き物が、こちらを壊さないようにおそるおそる触れて来る。物凄く注意深く、慎重に、ダリオの意思を尊重しようとして、時たま仰天するようなこともするが、それだってかなり寄って来てくれてるわけで。やたらメンテナンスしてくるのも、壊さないようにするための調整じみた行いなのだろう。
最初に不法侵入されて、コミュニケーションも脅しかと思ったので、こういう態度になってしまっているが、改めるべきのような気もしてきた。だが、今改めるとなると、俺、好意隠せないんだが……とダリオは眉根を寄せた。
それを差し出していいのかわからない。
性欲ひとつとってもそうだ。
ダリオは欲情してしまい、しっかり気持ちよくなってしまったのだが、テオドールはどうだったのだろう。彼に性欲などあるのだろうか。そもそも勃起自体するのか謎である。今まで、寝るのも知らなかったくらいだ。もしかしたら眠っているのとは違うのかもしれない。見たままとは限らないのだ。結局、異次元異種族のことは分からない。人間同士でも、他者のことなんて分からない。それが当たり前だ。だから、分からないことは、ひとつひとつ距離を見て確認していくしかない。性急につめ寄っても、それはダリオの欲望だ。テオドールの要望ではない。
考えに没頭していたダリオは、ふと強い視線を感じて、ぎょっとする。
「ダリオさん」
いつの間にか、青年が切れ長の目で、こちらを見つめ返していた。一本一本のまつげが、恐ろしく長い。妖艶な目じりは、ぞくっとするような色香をたたえ、アビスの冷たいロイヤルブルーを、かすかに宝石のシラーめいた紫が揺れている。それは深海で燃える炎のような、この世にありえない幻想美の凝縮だった。その炎をいつまでも見ていたいような不思議な浮遊感を覚え、ダリオはぼんやりと魅入ってしまう。
「お前も寝るんだな」
するっと考えなしに出た言葉は、間の抜けた感想になった。気のせいでなければ、テオドールは少し表情をやわらげ、一瞬笑ったように思えた。
「睡眠は必要としませんが、真似事にも風情があります」
吐息のかかる距離で、抱き込まれたまま言われると、ダリオは声がつまって、言葉少なくなった。
「そうか」
なんか余計に間抜けになったなと思うが、頭が回らない。
「ダリオさんは、体の調子はいかがですか」
「調子は驚くほどよいな」
自分で言って気づいたが、爽快感にみなぎっている。なんでだ。今なら二十四時間寝ないで働けそうで、やばい薬でもキメたみたいな気分になった。テオドールがわずかに目を見開くと、ずい、と顔を寄せて来た。
「僕の影響かもしれません」
近づかれた分、ダリオは手でテオドールの胸を押し返すようにして微妙に距離を取る。
「そういや、お前……勝手に中が濡れるとか、俺の体どうなってるんだ」
「ああ……」
テオドールは珍しく言い淀んだ。
「ダリオさん、少し触れますが、よろしいですか?」
「ああ……? どうぞ?」
「それでは失礼します」
乗り上げるようにして、テオドールが右手を寝台につくと、ダリオの顔に影が落ちた。無抵抗にしていると、青年はシャツの下へと優しく五指を差し込ませる。そのまま潜り込んだ二本の指が背部へと向かい、臀部の尾てい骨を、ざりり、と下から上へなぞりあげるようにした。
いやらしさはなく、ただ触診されているような、何か確かめる手つきだ。尾てい骨から下へと臀部の皮膚を指圧しながら、次第に浮き上がるダリオの腰骨の輪郭を再度辿り、今度はまた前にゆっくりと戻ってくる。最後に、腹部からへその下を親指の腹でなぞると、真正面から口を開いた。
「この次元に、僕の影響が出ることは……多々ありますが、昨日の事象は、レアケースです。あれは、僕の影響だけでは起きないことかと」
「……あ、わかった。もういい」
ダリオは中途半端に察して、テオドールの口を手でふさいだ。その手を、テオドールが引きはがして、かえってつかえがとれたように囁く。
「ダリオさんが僕を受け入れて悦んでくださったので、あのように」
「止めろ止めろ、もういい、ストップ」
「ダリオさんがお尋ねになったことでは?」
「あーそうだね」
テオドールは首をかしげている。
「昨日は、ダリオさんの体を見て驚き、不躾に凝視してしまいましたので、申し訳ありませんでした」
ダリオが不快に思ったのかと考えたのか、謝罪してきて、逆に胃が痛い。もしかして、セクハラをしたのかと思って謝ってきているなら、違うし、以前言われたことを自分で考えて、謝罪選択するなんて、素直すぎる。
「いや違うし、それはいい。あと、全然わからんが、昨日は驚いてたのか」
「はい。端的に申し上げると、僕を受け入れたいと、あなたの体が劇的に変化していた。つまり、繁殖可能なように、本格的な変態へと入りつつあったので、」
淡々と真顔ながら、妙な迫力で繰り出されるそれに、ダリオはもう一度テオドールの口を両手のひらでふさいだ。
「あーやっぱりちょっとだけ待ってくれ」
テオドールは、口を塞がれたまま、大人しく目だけでダリオをじっと見返している。青年の言うとおり、聞いたのはダリオで、知りたいのもダリオである。
「悪い。落ち着いた」
そっと手のひらを外すと、ダリオは引きつった顔で尋ねた。
「繁殖可能なように、変態しつつあったって、い、今も? いや、まあ、いいが……え、これ今後もやっぱり引き続き濡れるのか?」
「いえ、一時的なものですから、今は元に戻っています」
「そ、そうか」
ほっとしたような、残念なような、ダリオは力が抜けた。
「ですが、ダリオさんが僕を受け入れたいと思ってくださったら、同じようになるかもしれません」
ダリオは少し口を開き、閉じた。自分が受け入れたいと思ったら、濡れる、ということは……と次第に顔面に血がのぼるのを感じた。片手で顔面を覆う。告白もしていないのに、開陳されまくっている。それともテオドールには何も伝わっていないのか。どうなんだ。
「あ、あのな、繁殖って、子ども作るってことだよな?」
「そうですね」
「よく分からないが、お前、性欲あるのか?」
「性欲……ですか」
勃起するのか、と聞いた方がよかったのだろうか。テオドールは少し思案する風である。
「僕たちは元々、お互いの精神を交えることで繁殖をします。この次元の人々に当てはめて僕らの性欲に該当する状態を説明することは、正確性を欠くかもしれません」
「精神を交える」
おうむ返しになってしまう。
「より近い表現、観念は――法悦、でしょうか。仏や神の教えを聞き、信じ、心にわく悦び。恍惚感、エクスタシーの意もあるのでしたか。その意味では、僕にも性欲があると申せましょう」
「その、具体的に、お前勃起したり、するのか? というか、俺が昨日繁殖可能な状態になりつつあったって、それだと、どういう」
「ダリオさん」
覆い被さるようにして、テオドールが顔を寄せて来る。 間近に覗き込む人外の引き絞られた瞳孔は、深い亀裂のようで、ダリオはかたまった。
「精神を交える方法は、法悦に当たるような恍惚感、エクスタシーを与えて、あなたの中に入れていただく。あなたの肉体だけではなく、あなたの心の中に」
とん、と胸元を美しい指先が触れることなく指し示す。
「僕とあなたの精神が、絡み合い、互いに溶け合い、身悶え、魂の尾をよじらせながら、ぐちゃぐちゃに溶け合って一つになるということですよ。通常の生物では難しいでしょう。でも、昨日のあなたは、その余地があった。僕をあなたの中に、受け入れようとしてくださっていた」
それが、形として体機能変化で現れていたのでしょう、と。
テオドールの説明に、ダリオはもう顔から火が出る思いだった。色々テオドール側へ発覚している上に、言われたことを想像して、腹の奥がずくりと疼痛を覚える。
「安心してください。繁殖は、僕には時期尚早でもあります。何より、あなたの同意を得ずに、繁殖に持ち込むつもりはありません」
「そ、そうか……」
避妊は最低限のマナーだ。今回の事件にかかわった人間の男性よりも、人外のテオドールがわきまえているのはなんか皮肉な話だなと思うが、頭のわいたダリオは、ますます好きになる……クソヤバ怪異なのに……と煩悶する羽目になった。もはやテオドールが何をしても好感度が上がるステータスぶっ壊れ状態に脳が判断レベルを下げまくっている。
「僕の言うことは、不安ですか?」
「いや……え、いや、お前、いつも嘘はつかないだろ。そこは信用してるよ。あと、なんだ。テオ、お前さ……あー、時期的によくて、俺が同意したら、その、繁殖? 相手、俺も選択に入って来るの、か?」
え、入って来るの? とダリオはよく分からない恥ずかしさで、早口になった。種族が違う。それなのに、繁殖相手として、候補の射程に自分が入って来るのか?
そうしたら。テオドールは、嫣然と微笑んだのだ。
「ダリオさん――僕の『花』」
まるで隠した宝箱の中を見るように覗き込みながら、繊細な手つきでテオドールの長い指がダリオの頬に触れる。
「あなたに、僕を受け入れる変化が起きて……僕がどれほど驚いたことか、あなたには分からないでしょう」
ゆっくりと、まるで慈しむように頬を繰り返し指先がなぞった。それは、どこか遠慮がちに、触れがたいものを確かめるような動きだった。
「僕らは、『花』に拒絶されることの方が多いのです」
そういえば、当初そんなことを言っていた。あれは脅しではなく、普通に事実を言っていたのかもしれん、とこの段になってダリオは思った。あの時のテオドールに心理的駆け引きをされたかと思っていたが、これまでの付き合いから、こいつはマジレス生物だと察している。
「僕らがどれほど『花』に執着し、執心しようとも、『花』からは忌み嫌われ、逃げられ、憎まれ、恐怖され、最期、支配者側は『花』を蹂躙して殺す――得られないのであれば、手折るしかありません」
熱のない淡々とした物言いは、他人事のようだった。テオドールの考えというより、彼の普段の言動を見るに、種族全体の傾向の話なのかもしれない。これまで実際に起きた種族的経験を、どこか突き放して言うような印象を受けた。物騒なことを無表情に言いながら、その美しい指先は、ただただゆっくりとダリオの顔の輪郭を確認するように辿っている。やがて、テオドールはひとりごとのように呟いた。
「この姿も、擬態に過ぎませんしね……」
ダリオは一瞬面食らった。
「そうか」
返答に困って、またもや間の抜けた返しになる。擬態と言うことは、本体は人の形をしていないということだろうか。ダリオとしては、よほど生理的嫌悪を覚えるようなものでなければ、本物だろうが擬態だろうが、どちらでもいい。だが、もしかしたらその生理的嫌悪を催させるようなものなのかもしれない。
「あ~、擬態ってのは、本体が別の姿ってことか?」
「はい。おそらくダリオさんには、耐えられないでしょう。僕ら支配者を垣間見て、正気でいられる生物は少ないのです。ですから、見せるつもりはないのですが、絶対に可能性がないとも言い切れませんので」
「その時になってみなければ分からない、としか言えないな。性格も変わったりするわけじゃないんだろ」
「存在の連続性は保たれています」
「じゃあ、いいかな、分からんがたぶん、お前がお前なら俺は別に」
テオドールがテオドールであるなら、姿かたちが変わっても、ダリオに酷いことはしないだろう。彼が彼のままに、ダリオにしてくることは、実のところ、嫌なことなどひとつもない。テオドールは倫理観がぶち抜いているが、ダリオに対しては呆れるほど愚直だった。驚くほど積極的合意を確認してくるし、ダリオが嫌だと言えば止める。当たり前のことだが、この当たり前ができない人間は多い。
ダリオは体格が良く、表情もそうくるくる変わるタイプでもないから、寒くないか気遣われて服を着せてもらったり、気分や体調を気にかけてフォローしてもらったりということはあまり経験したことがない。
そういうことを過剰にされれば嫌気がさすかもしれないが、テオドールはいちいちダリオの意思確認をするし、何よりダリオの自己決定を優先してくる。
ただ、大切にされていることを日々感じさせられるだけだ。
それなら、何されたって、ダリオは構わなかった。ダリオがテオドールを好きになったのは、彼がダリオを大事にしてくれたからだ。元々ダリオは、テオドールのことは化け物だなと思っているし、その点を改めて強調されたとしても、あまり引っかからなかった。
好きだと、ダリオは言ってしまいたかった。だが、テオドール風に言うなら、時期尚早、タイミングではないなという気がずっとしている。テオドールにはまだ、そうした感情を理解する受容体が出来ていないように思われた。これまでもそうだ。『花』に対する挙動に、好意にも似て決してそのものではない感情のベクトルを感じていた。本人の申告のとおり、それは種族的本能のような執着や執心なのだろう。ダリオの好意とは、やはり違うものだという感じがする。だから、彼の種族は、『花』が得られなければ、蹂躙してしまうのではないか。まるで、子どもの癇癪だ。テオドール自身はそこから一つ頭を飛びぬけているようではあるが、過信する気にもなれない。なにしろ、ダリオはテオドールのことなどわからないのだ。
しくじりたくない、とダリオは思う。相手を尊重しなければ、ひとりよがりになる。気持ちを押し付けたって、理解できないものをプレゼントしても相手も迷惑なだけだ。少しずつ、階を作っていくしかない。
「ダリオさん――」
少しだけためらうような手つきで、テオドールがダリオの頬を撫でた。彼の目が細まる。
「今朝もメンテナンスしてもよろしいですか?」
ダリオは別に体調はよかったが、肘をついた片手で体を支え、上半身を起こすと、手を伸ばしテオドールの頭を引き寄せた。
ちゅ、と唇がダリオのそれを吸い、角度を変え、何度もついばんでいく。テオドールの体液効果は相変わらずで、主導権を握るのは難しい。ダリオも何かしてやりたいなと思う気持ちはあるが、当分無理そうだった。
「……ふっ……」
鼻を擦り合わせ、テオドールは、ちゅっ、ちゅ、と小鳥が餌をぱくつくように、繰り返しダリオの唇を食んだ。
「僕の『花』——」
ダリオの名と、僕の『花』を交互に、テオドールはそれ以外の言葉を忘れたかのようだった。ダリオは、自分がテオドールの繁殖相手に選択で入って来るのか尋ねたが、もうこれが答えも同然だ。
ひらいていく――花開かされる。ダリオは、テオドールに開かされていくのを感じた。体が、開いてしまう。もう、体の奥から、こぷり、と塊のように蜜が零れ落ちるのを聞いた。
85
お気に入りに追加
1,008
あなたにおすすめの小説

そばかす糸目はのんびりしたい
楢山幕府
BL
由緒ある名家の末っ子として生まれたユージン。
母親が後妻で、眉目秀麗な直系の遺伝を受け継がなかったことから、一族からは空気として扱われていた。
ただ一人、溺愛してくる老いた父親を除いて。
ユージンは、のんびりするのが好きだった。
いつでも、のんびりしたいと思っている。
でも何故か忙しい。
ひとたび出張へ出れば、冒険者に囲まれる始末。
いつになったら、のんびりできるのか。もう開き直って、のんびりしていいのか。
果たして、そばかす糸目はのんびりできるのか。
懐かれ体質が好きな方向けです。今のところ主人公は、のんびり重視の恋愛未満です。
全17話、約6万文字。

【完結】最強公爵様に拾われた孤児、俺
福の島
BL
ゴリゴリに前世の記憶がある少年シオンは戸惑う。
目の前にいる男が、この世界最強の公爵様であり、ましてやシオンを養子にしたいとまで言ったのだから。
でも…まぁ…いっか…ご飯美味しいし、風呂は暖かい…
……あれ…?
…やばい…俺めちゃくちゃ公爵様が好きだ…
前置きが長いですがすぐくっつくのでシリアスのシの字もありません。
1万2000字前後です。
攻めのキャラがブレるし若干変態です。
無表情系クール最強公爵様×のんき転生主人公(無自覚美形)
おまけ完結済み
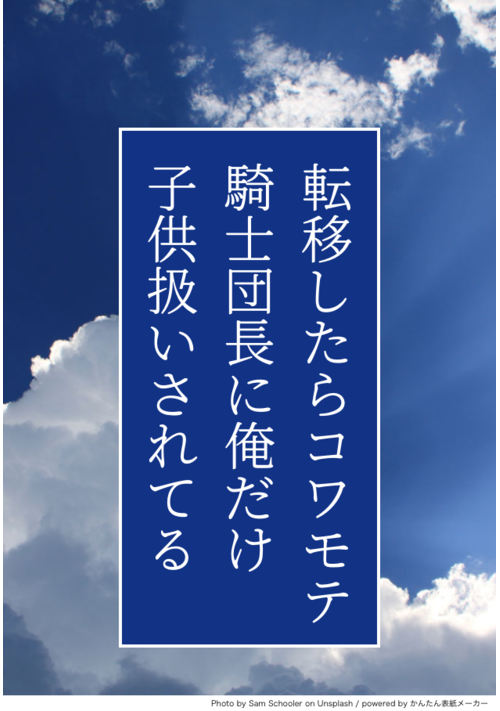
転移したらなぜかコワモテ騎士団長に俺だけ子供扱いされてる
塩チーズ
BL
平々凡々が似合うちょっと中性的で童顔なだけの成人男性。転移して拾ってもらった家の息子がコワモテ騎士団長だった!
特に何も無く平凡な日常を過ごすが、騎士団長の妙な噂を耳にしてある悩みが出来てしまう。


幽閉王子は最強皇子に包まれる
皇洵璃音
BL
魔法使いであるせいで幼少期に幽閉された第三王子のアレクセイ。それから年数が経過し、ある日祖国は滅ぼされてしまう。毛布に包まっていたら、敵の帝国第二皇子のレイナードにより連行されてしまう。処刑場にて皇帝から二つの選択肢を提示されたのだが、二つ目の内容は「レイナードの花嫁になること」だった。初めて人から求められたこともあり、花嫁になることを承諾する。素直で元気いっぱいなド直球第二皇子×愛されることに慣れていない治癒魔法使いの第三王子の恋愛物語。
表紙担当者:白す(しらす)様に描いて頂きました。

弱すぎると勇者パーティーを追放されたハズなんですが……なんで追いかけてきてんだよ勇者ァ!
灯璃
BL
「あなたは弱すぎる! お荷物なのよ! よって、一刻も早くこのパーティーを抜けてちょうだい!」
そう言われ、勇者パーティーから追放された冒険者のメルク。
リーダーの勇者アレスが戻る前に、元仲間たちに追い立てられるようにパーティーを抜けた。
だが数日後、何故か勇者がメルクを探しているという噂を酒場で聞く。が、既に故郷に帰ってスローライフを送ろうとしていたメルクは、絶対に見つからないと決意した。
みたいな追放ものの皮を被った、頭おかしい執着攻めもの。
追いかけてくるまで説明ハイリマァス
※完結致しました!お読みいただきありがとうございました!
※11/20 短編(いちまんじ)新しく書きました!
※12/14 どうしてもIF話書きたくなったので、書きました!これにて本当にお終いにします。ありがとうございました!


ボクが追放されたら飢餓に陥るけど良いですか?
音爽(ネソウ)
ファンタジー
美味しい果実より食えない石ころが欲しいなんて、人間て変わってますね。
役に立たないから出ていけ?
わかりました、緑の加護はゴッソリ持っていきます!
さようなら!
5月4日、ファンタジー1位!HOTランキング1位獲得!!ありがとうございました!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















