1 / 96
1巻
1-1
しおりを挟む
座禅豆の柔らかさ
油堀沿いの道を男がひとり走っている。
小銀杏の髷に濃茶の縞小紋、草履が脱げんばかりの勢いで、船宿の前に浮かぶ猪牙船も、寒風に舞うしだれ柳の枝も男の目には入っていない。
時は文政六年(一八二三年)師走、日もすっかり落ちた七つ半(午後五時)のことだ。
男はそのまま深川佐賀町にある孫兵衛長屋へと続く路地に入り、奥から二軒目に飛び込んだ。
「やっと帰り着いた……」
「どうしたの、そんなに息を切らして」
家に入るなり土間にへたり込んだ男を呆れたように見たのはきよ、男は清五郎という。ふたりは三つ違いの姉弟で、きよは年が明けたら数え二十三を迎える。部屋は少々狭いが建て付けは良く、大家や近隣が善人揃いだったこともあり、姉弟はそれなりに心地よく暮らしていた。
「乾物屋さんはまだ開いていた?」
続いて訊ねるも、清五郎は息も絶え絶えの様子で言葉が出ない。どうやらずっと走ってきたらしい。
清五郎は少し前に、ぶどう豆を買いに行った。
夕食を終えてのんびりしていたところ、清五郎が不意に座禅豆を食べたいと言い出したためだ。すぐにでも食べたい様子だったので、それなら明日にでも煮売り屋で買ってこよう、と言ったのだが、きよの手作りがいいと言う。
正直に言えば、座禅豆を煮るのは面倒だ。座禅豆は黒い大豆であるぶどう豆を醤油や味醂で煮て作るお菜だが、あらかじめ乾いた豆を水に浸けて戻しておかなければならないし、とにかく煮上がるのに時間がかかる。けれど、『手作りがいい』と言われれば悪い気はしない。それでは、と探したところ、ぶどう豆の買い置きがほとんど残っていなかった。
座禅豆にするぶどう豆は、長屋に回ってくる振売から買っている。振売が運んでくる品は青物、魚貝、豆腐、醤油、酒、団子といった食い物から、古布、竹笊といった暮らしに必要な品々、子どもが喜ぶシャボン玉に飴、と人それぞれだが、ひとりで担げる量は知れているため、扱う品目は限られる。今日は豆売りが回ってくる日ではないし、そもそもこんな遅くに商う振売はいない。
仕方がない、今度にしようと言ったのだが、清五郎は諦めきれなかったようだ。油堀を抜けた先の富岡八幡宮あたりの乾物屋ならまだ開いているかもしれない。木戸が閉まるまでにはまだ間がある。空振りを覚悟で行ってみる、と言うので、送り出したのである。
それがこれほど息を切らして戻ってくるとはどうしたことか。
乾物屋までは大した道のりではないが、清五郎は迂闊なところがある。気が急くあまり、渡したお金を落としたのかもしれない。そこらの草むらに転がり込めば見つけるのは難しいし、そもそも地べたに落としたところで大した音はしないから気付きもしない。
店に辿り着いてみたら懐にお金はなく、乾物屋に『冷やかしか!』と怒鳴られた。悔しさ半分、恐ろしさ半分で駆け戻った。せいぜいそんなところだろう、ときよは思ったのである。
ところが、話はそんなに簡単ではなかった。
「やっかいなことになった」
「どういうこと?」
とりあえずこれを飲んで落ち着きなさい、と湯飲みに入れた水を差し出すと、清五郎は一息に飲み干し、経緯を話し始めた。
「富岡さんの参道に入ったところで、小僧が雨戸を立てかけてるのが見えたんだ。いけない、閉まっちまう! って大急ぎで駆け込んだら、あいにくそこにお侍がいて……」
「ぶつかっちゃったの……?」
「そう。思いっきり左側から、どーんって……」
「左ってことは刀……?」
清五郎が黙って頷く。きよは、冷たい水をぶっかけられた心地だった。
東照大権現様から始まった徳川の世も、家斉様の代ともなると平穏そのもの、飢饉や大火などの禍はあるにしても、大きな戦は起こらなくなった。武士が刀や鎗を振り回すことも減り、どうかすると質入れして竹光でごまかす者までいる始末である。
それでも刀が武士の命とされることに変わりはなく、うっかりぶつかった日には、武士同士であっても諍いが起こる。町民や農民に至っては、その場で斬り捨てられかねない。
弟の起こしたとんでもない事態に、血の気が引く。
清五郎は末っ子ということもあって、家族みんなにかわいがられてきた。とりわけきよは、自分より年下なのは清五郎だけだったため、ありとあらゆる面倒を見てきた。もしかしたら弟のためにはよくないかもしれないと思うこともあったが、清五郎をかわいく思う気持ちは止められない。一緒に江戸に出てきたのも、面倒を見られてばかりだった弟をいきなりひとりで放り出すのはしのびない、なにかあっては大変だと思ったからだ。
甲斐あって、なんとか一年は無事に過ごせた。清五郎も少しずつ成長してきたようだし、どうにかこのまま……と思った矢先の出来事に、きよは動悸が止まらなくなる。
大急ぎで弟の様子を確かめたが、どこにも怪我はないようだ。怪我をしていたら、あんな勢いで走ってこられるわけがない。とりあえずほっとしたものの、なにもなしに済んだとは思えなかった。
「それで、お咎めは……? お金を払えって言われたとか……」
詫び料でも求められたのかもしれない。昨今、お金に困っている侍も多いと聞く。手討ちにするよりも、お金を払わせるほうがいいと考えることもあるだろう。余分なお金などないが、背に腹は代えられない。なんとしてでも掻き集めて……と考えかけたとき、清五郎がもぞもぞと身体を捻った。
生まれたときから知っているきよにはわかる。弟がこんなふうに身体を動かすのは、後ろめたいことがある証だ。お侍の刀にぶつかったのは不注意だったが、ある意味事故のようなもの。それとは別に、なにかまずいことをしでかしたに違いない。
「――正直におっしゃい。なにをやらかしたの?」
「それが……。そのお侍、俺がぶどう豆を買いに来たのを知って、おまえが煮るのかって訊いてきたんだ。だから俺、つい、そうだ、俺は料理人だからな、って言っちまった。そしたら、その豆を食わせろって。どうやらそのお侍も、座禅豆が食いたかったみたいで……」
近所の煮売り屋のものが気に入らず、他に売っているところはないかと探していた。
煮売り屋は乾物屋からいろいろなものを仕入れる。乾物屋なら、このあたりの煮売り屋に詳しいはずだ。他に座禅豆を商っている店はないか、と訊きに来たところに、清五郎が飛び込んできた。こんな時間に若い男が豆を買いに来たというのが不思議でならない。聞けば料理人、これから座禅豆を煮るつもりだと言われて俄然興味が湧いたとお侍は言ったらしい。
「いくらお侍でも、手討ちは後味が悪い、豆を分捕るぐらいで許してやろうって思ったんじゃないかな」
「どこの誰ともわからない男が煮た豆を欲しがるなんてことがある?」
「それは俺が『千川』の料理人だって言ったから……」
『千川』というのは、姉弟が奉公している料理屋である。富岡八幡宮の参道にあり、最初は清五郎だけが世話になっていたのだが、しばらくしてきよも一緒に働くようになった。
かなり大きな店で、評判もすこぶるよく、そこらの煮売り屋とは比べものにならない。座禅豆も出しているし、人気の品だから、その侍が欲しがるのも無理はない。
問題は、清五郎が料理人ではないことだ。
「なんでそんな出任せを言うのよ! あんたは『千川』で働いてはいても、料理人じゃない。できた料理を運んでるだけだし、家でだって、自分で豆を煮たことなんてないでしょう!」
「わかってるけど、つい……」
唇を尖らせる弟に、きよは目眩がしそうになっていた。
きよと清五郎が江戸に来てから、まもなく一年になる。
ふたりは逢坂で油問屋を営む菱屋五郎次郎とたねの間に生まれた。
姉の自分が言うのもなんだが、清五郎は子どものころから見栄えが良く、やんちゃながらも憎めない質だったため、友だちも多かった。娘たちからも人気が高く、天狗になっていたせいか、仲間とつるんで悪さをすることもあった。家族の心配の種ではあったけれど、十八の年までは大きな事件を起こすことなくきていた。
ところが昨年の秋、茶店で居合わせた若者が、清五郎に喧嘩をふっかけてきた。どうやら、清五郎が娘たちにちやほやされているのが気に入らなかったらしい。
相手の腰には刀がある。喧嘩をしてはいけない相手だとはわかっていたらしいが、執拗に絡まれるうちに気が高ぶり、とうとう殴り合いになってしまった。
幸い清五郎は大した怪我もせずに終わったが、相手はそうはいかなかった。顔や身体のあちこちに青痣ができ、熱まで出してしまったのだ。
悪いことに、相手は蔵屋敷勤めの武士の息子だった。父親の怒りはすさまじく、清五郎の首を刎ねかねない勢いで乗り込んできた。その場は留守だとごまかしたけれど、父親は必ず仕返しすると息巻く。とてもじゃないがここには置いておけない、ということで、清五郎は江戸で料理屋を営む知人で、古くからの取引先でもある川口屋源太郎に預けられることになったのだ。
だが、清五郎は家のことなどやったこともなく、そもそも我が儘で、気が高ぶるとなにをしでかすかわからない。両親も、ひとりで暮らしていけるのか、と心配した。かといって、奉公に上がるのに女中をつけるのもおかしな話だ。それなら、ということでお目付役と世話役をかねて、きよが一緒に行くことになった。父にしてみれば、きよを厄介払いしたい気持ちが強かったのだろう。
――きよは生まれながらの厄介者だった。
きよが生まれたのは享和二年卯月、ただでさえ畜生腹で縁起が悪いと言われる双子の上に、心中者の生まれ変わりとされる男女の組み合わせだった。
父は生まれたばかりの娘を処分しようとしたが、母が抱え込んで離さなかったため、根負けした末に家に置くことにした。ただし、表向きは生まれたのは男子、清三郎だけとし、娘は屋敷の奥深くに隠した。
それから二十余年が過ぎ、奉公にも出せず嫁にもやれず、いよいよ娘を持て余した父が、逢坂にいられなくなった弟とともに江戸に出した、というのがこれまでの経緯である。
源太郎の営む『千川』で料理を運ぶのだって未熟なのに、あろうことか料理人を騙るとは。
唖然とする姉に、清五郎は不満たっぷりに言う。
「年が明けたら二十歳になるってのに、小僧みたいな仕事をしてるなんて思われたくなかった。馬鹿にされちまうじゃないか」
清五郎は、江戸に出るまでは実家の店の手伝いをしていた。物覚えは悪くなかったため、父に習い、留守のときには父に代わって帳簿を付けることもあった。
親兄弟は、店を手伝っている最中でも仲間から声がかかれば飛び出していく清五郎を見て、あんな不真面目な態度ではとても任せられない、と思っていた。それでも本人は、いずれ番頭ぐらいには取り立ててもらえると期待していたのかもしれない。
にもかかわらず、慣れ親しんだ逢坂から追い出され、江戸で奉公。しかも、できた料理を運ぶだけという簡単な仕事とあって、誇りを傷つけられた気になったのだろう。
入ったばかりなのだから簡単な仕事しか任せられないのは当たり前、年季が入っていれば小僧のほうが上、なんて思いも及ばない。だからこそ、ちょっとでも聞こえがいいように、料理人を騙ってしまった……
考えれば考えるほど、愚かな弟の振る舞いに、頭がくらくらしてくる。普段かわいがっているからこそ、よけいに不甲斐ない気持ちが募った。だが、話がそこで終わるはずもない。首根っこを掴まえてぐらぐら揺すぶりたくなる気持ちを抑え、きよは先を促した。
「それで?」
「そのお侍は、俺に座禅豆を屋敷に届けろって。座禅豆が気に入ったら許してやる。『千川』も贔屓にしてやるぞ、って……」
わけがわからない。だが、ともかくその侍は、斬り捨てる代わりに持ってこいと言うほど座禅豆に執着しているようだ。
「気に入らなかったら、ただではすまないと思う。きっと手討ちにされる……」
息子が青痣を作らされただけでも、大層な勢いで怒鳴り込んできたのだ。侍と町民の間では、喧嘩両成敗なんてありえない。ましてや、こちらの一方的な不注意で武士の命を穢したのだ。
「その侍、腕っ節は強そうだったし、鬼みたいに恐い顔だった。もたもたしてるうちに気が変わって、やっぱり斬る、って言い出したらことだと思って、大急ぎで帰ってきたんだ。思い出しても震えがくる……。ああもう、どうしよう!」
「どうしようって、『千川』の座禅豆を買って届けるしかないでしょ! その上で、事情を話して謝りなさい。料理人は騙りですが、この豆は紛れもなく『千川』のものですって」
「騙りなんて働いたことがばれたら、ただじゃすまねえよ!」
「座禅豆さえ気に入ってもらえたら、許してもらえるかもしれない。なにより、最初に馬鹿な嘘をついたあんたが悪いの! 明日にでも座禅豆を買いましょう」
「でも姉ちゃん、『千川』の料理は値が張るし、そもそも持ち帰りなんてやってないよ」
「そんなこと言ってる場合じゃないでしょ!」
『千川』は料理屋だから、煮売り屋のように持ち帰ることはできない。だが、事情を話せばきっとわかってくれる。なんとか売ってもらって、届けに行くしかない。
だが、清五郎は気が進まないらしく、うだうだと理屈を捏ねる。
「それはうまくないよ。『千川』の旦那さんに料理人を騙ったなんて話をしたら、なおさら呆れられちまう。ただでさえ、面倒を起こして流れてきた厄介者なのに。あーもう、いっそこのまま逃げちまうってのは?」
「あんたが『千川』に奉公してるのはわかってるのよ? もし行かなかったら『千川』に乗り込んできかねない。あんたまさか、『千川』を巻き添えにするつもりなの⁉」
「それは……」
姉に詰め寄られて清五郎は意気消沈。だが、しばらく考えていたあと、ぱっと目を輝かせて言った。
「そうだ! なにも『千川』の座禅豆を持っていく必要ないよ。姉ちゃんのを持っていけばいいんだ!」
「私の?」
「それが『千川』のものかどうかなんてわかりっこない。姉ちゃんの座禅豆はそこらの煮売り屋のよりずっと旨いから、絶対気に入るよ」
清五郎は、さも嬉しそうに続ける。
「明日のうちに豆を煮れば、明後日には届けられる」
頭がくらくらするのを通り越して、頭痛がしてきた。きよは、あまりにも考えなしの弟を叱りつけた。
「清五郎の馬鹿! そんなの通るわけないじゃない! 座禅豆は、注文があってから作るような料理じゃないのよ!」
座禅豆は、たいていの料理屋なら置いている。相手がお侍だとしても、作り置きがあることぐらいわかりそうなものだ。
けれど、清五郎はさらにきよの気持ちを逆なですることを言う。
「今日はよく売れた。おかげで売り切れて、一から煮直したせいで時間がかかった、ってことにすればいい」
「あんたってば、嘘に嘘を重ねるって言うの⁉」
「大丈夫、大丈夫、ばれっこない。絶対うまくいくって!」
「いくわけないわよ! そもそも、ぶどう豆はどうする気? あんた、買ってこなかったでしょ!」
弟は手ぶらで帰ってきた。這う這うの体で逃げ出し、それどころではなかったのだろう。だが、清五郎は平然と言う。
「少しは残ってるんだろ? たくさん食いたかったから買いに出たけど、今回は諦める。俺の分はぽっちりでいいよ。じゃ、よろしく!」
そう言うが早いか清五郎は草履を脱ぎ捨てて家に上がり、寝支度を始めた。
とはいっても風呂敷に包んであった布団を広げるだけ。あとは着物を脱いでひっ被れば終わりだ。明日も仕事があるし、行灯の油も惜しい。こんな日はさっさと寝るに限る、というところだろう。
ほどなく、清五郎は寝息を立て始めた。こんな騒動を起こしておいて、よくもすんなり寝付けるものだ、と呆れてしまう。
自分は眠れそうにない。やむなく、きよはぶどう豆が入った枡を手に取る。
揉め事の原因となったぶどう豆など見たくもないし、人を騙すのはとても嫌だけれど、弟が手討ちにされては大変だ。とにかく座禅豆を煮るしかない。
きよは深いため息とともに、ぶどう豆を洗い始めた。
何度も水を替え、小さな豆殻や葉を丁寧に取り除く。多少傷のある豆でも、普段ならもったいないと一緒に煮てしまうけれど、今日はちゃんと選り分けた。傷のある豆は飯と一緒にでも炊けばいい。『千川』が客に傷のある豆を出すわけがない。まったく同じになんてできっこないけれど、せめてそれぐらいは……と思いながら、きよは冷たい水でぶどう豆を洗い続けた。
二日後、清五郎は煮上がった豆を届けに行った。件の侍は留守だったそうで、家人に預けたと言って帰ってきた。その後、お侍がなにか言ってくるかと生きた心地がしなかったが、その日も翌日も、その次の日になっても音沙汰がなかった。
座禅豆を気に入ってくれたのか、面倒くさくなったのか、とにかく清五郎を咎めるのはやめにしたらしい。
胸を撫で下ろしつつ、きよは、料理人を騙るのはもちろん、どんな嘘も二度とついてはいけない、と清五郎に強く言い聞かせた。
それからしばらくしたある日、『千川』の勝手口にいたきよは、主の源太郎に声をかけられた。源太郎は、きよの父、五郎次郎よりひとつ年上らしいが、浅黒い顔に皺がたくさんあり、髷に交じる白髪も父よりもずっと多いため、五つ六つ上に見える。大店の主というのは厳しい人だと思われがちだが、源太郎は姉弟が江戸に来てからなにくれとなく面倒を見てくれたし、他の奉公人にとっても情けの深い雇い主だった。
「おきよ、もう豆は煮えたかい?」
「そろそろ出来上がります」
日頃のきよの仕事は、屋内で野菜を洗ったり切ったりといった下拵えばかりだが、今日は珍しく勝手口の脇に七輪を持ち出し、火の番をしていた。
「それはよかった。どうしても座禅豆を食わせろって、客がうるさくてな」
「え……これをですか?」
鍋の中にあるのは、きよが源太郎に頼まれて煮ていた座禅豆だ。
清五郎が乾物屋で揉め事を起こした翌々日、源太郎の妻さとが、客からもらったという菓子をくれた。さとは背丈はきよと大差ないが太り肉で貫禄たっぷり、ふっくらとした頬は冬の寒いときでも桃色で、鈴を転がすような声でよく笑う。少々心配性が過ぎるが、それも優しい人柄ゆえだろう。親元を離れているきよと清五郎を我が子のようにかわいがってくれていて、菓子やお菜を裾分けしてくれることが多かった。
小鉢に入れて持たせてくれたため、空で返すのも憚られ、清五郎が届けた残りの座禅豆を入れて返したところ、さとばかりか源太郎も大いに気に入ってくれた。もっと食べたいから自分たち用に作ってくれ、豆はもちろん醤油や味醂、炭も用意するから、と頼まれた。おまけに、豆を煮るのは時間がかかるから、店で煮ていいとまで言われて断れなかったのだ。
仕事の傍ら、こまめに火を加減したおかげで煮上がりは上々、皺ひとつない艶やかな座禅豆が出来上がった。
とはいえ、店の客に出すなんてありえない。これは主夫婦のために作ったものだし、なにより、下働きのきよが作ったものを客に出したら、板長の弥一郎が怒り出すだろう。弥一郎は源太郎の息子だが、言葉数が少なく、いつも険しい顔をしている。しかも仕事に厳しい。もしきよが作ったものを出したと聞いたら烈火の如く怒るに違いない。
そもそも座禅豆ならば、弥一郎が作ったものがある。それを差し置いて、きよの料理を出そうとする意味がわからなかった。
「板長さんに叱られます。それに、座禅豆を切らしてるわけでもないのにどうして……」
当然の疑問を口にしたきよに、源太郎は小声で言う。
「弥一郎の座禅豆が旨いのはわかってるが、今日の客はちょっと面倒なんだ」
「というと?」
「黒羽織で腰には刀」
「同心様ですか?」
「いや、前に馬に乗ってるのを見たことがある」
「じゃあ、与力様……」
町中で見かける羽織姿は、おおむね侍か大店の番頭より上の町人だろう。中でも黒羽織で帯刀となると、市中を見回る同心か与力ということになる。同心は馬に乗ることは許されていないため、源太郎が馬に乗っている姿を見たというのであれば、それは与力に違いない。
目を見張るきよに、源太郎は頷いた。
「たぶんな。その客は、座敷に上がるなり座禅豆を注文した。で、いつものを出したら、全部食った上で、他の座禅豆を食わせろ、ときたもんだ」
「他の? でもそんなものありませんよね?」
そう言ったとたん、きよは嫌な予感に襲われた。
その与力というのは、もしかしたら先日清五郎が乾物屋でぶつかった侍ではないのか。
いつも出しているのとはまったく違う座禅豆を、『千川』のものだと偽って届けたのだから、『千川』には二通りの座禅豆があると思い込んでも不思議はない。
届いた座禅豆に満足できなかったけれど、お勤めかなにかの都合でこれまで来られなかった。今になってやっと時間ができたため、文句を言いに来たのではないか。
もしも清五郎にお咎めがあったらどうしよう、ましてや『千川』まで巻き込んでしまったら、と血の気が引いた。
そんなきよの思いを余所に、源太郎は話を続けた。
「だろう? 俺も、うちの座禅豆はこれだけだって言ったんだ。だが、客のほうが『あるはずだ。それに、外から豆を煮る匂いがしてくる。これとは違う匂いだ。あれを持ってこい』って聞かない。それで、おまえが煮ている最中だって思い出してね。そろそろできるころじゃないか、って来てみた」
「ずいぶん鼻が利くお方ですね……」
『千川』の造りはしっかりしている。季節は冬、すっかり冷え込んでいるから戸口だって閉まっている。それなのに外、しかも勝手口で煮ている豆の匂いがわかるなんてすごい、ときよは感心しそうになった。だが、感心している場合ではない。おそらく、源太郎もそれどころではないのだろう。さっと周りを見回して、袖から小鉢を取り出した。
「なにを考えているかはわからないが、うまいこと気に入られれば、今後も贔屓にしてくれるかもしれない。与力様なら手下だってたくさんいる。客を増やす絶好の機会じゃないか」
「気に入られるとは限りませんよ」
むしろその逆の可能性のほうが高い。だが、事情も知らぬ源太郎にそれを告げたところでわかってくれるはずもない。さらに源太郎はせっつく。
「とにかく、お役人相手に問題は起こしたくない。さっさと豆を盛ってくれ。いつも座禅豆を盛っている器だし、これなら弥一郎に見られてもばれないはずだ」
「湯気が上がってても?」
「なんとかこっそり持っていく」
やめましょう、嘘はよくありません、と何度も言ってみたが、源太郎は聞き入れようとしない。やむなくきよは、小鉢に座禅豆を盛り上げた。
源太郎は、ほっとしたように店の中に戻っていったが、きよはあらゆる意味で心配でならなかった。
弟にお咎めがあるのではないか、ということはもちろん、その与力が清五郎がぶつかった相手ではなかったとしたら、自分の料理への評価が気になる。いや、それより切実なのは、誰が作ったものであっても、客に出された時点でそれは『千川』の料理となり、すべての責任は板長のものとなる。客の口に合わなかった場合、弥一郎の顔に泥を塗ることになるし、逆なら逆で料理人の誇りを傷つけかねない。
――どうか清五郎とは無縁の人でありますように。不味くて食べられないほどではありませんように。物足りなくても、出来立てで味が馴染んでいないせいだって言い訳できるぐらいでありますように! それから、まかり間違っても、褒められたりもしませんように……とはいえ、褒められたらやっぱり嬉しいかも……
きよの気持ちは千々に乱れる。
この座禅豆を煮上げたら、きよは家に帰っていいことになっていた。それでも成り行きが気になって、あえてゆっくり七輪の火の始末をしていると、勝手口からまた源太郎が出てきた。手にはさっきの小鉢を持っている。
「ど、どうなりました?」
「ものすごく気に入ってくれて、あっという間に食っちまった」
「そうですか……。他になにかおっしゃってましたか? お訊ねのこととか……」
「お訊ね? これといっては……」
幸い清五郎は今、使いに出ている。清五郎絡みの来店であれば、きっと所在を訊ねるはずだ。なにも訊かれなかったのであれば、清五郎がぶつかった人ではなかったのだろう。とりあえず一安心だが、心配はそれだけではない。
「それで、板長さんには?」
「客は板場に背を向けるように座ってたから、たぶん気付かれてない。相当旨かったらしい。もう一杯くれってさ」
そこまで話して、源太郎は慌てて小鉢を差し出した。
「客が待ってる。さっさと盛ってくれ」
こうなったら一鉢も二鉢も同じだ。きよは、毒を食らわば皿までも、という気持ちでまた豆を小鉢に盛った。主夫婦に渡す分が少なくなるが、それは仕方がないというものだ。
弥一郎のことを抜きにすれば、自分の料理を喜んで食べてくれる人がいるというのは嬉しい。ましてや、誰が作ったかなんて知るよしもない客まで気に入ってくれたとなると、勝手に目尻が下がってしまう。込み上げる笑みを抑えきれないまま、きよは豆を炊いた鍋を手に勝手口から中に入った。
その瞬間、一気に血の気が引いた。
弥一郎がいたからだ。
白と紺の格子縞の着物に襷を掛け、頭を手ぬぐいで覆っている。源太郎よりも頭半分背が高く痩身、まるで似ていないようだが、耳の形がそっくりなところを見ると紛れもなく親子なのだろう。
弥一郎が、店を開けている間に板場を離れることは滅多にない。ましてや、勝手口までやってくるなんて考えられない。おそらく、あの客に出した座禅豆が己の手によるものではないと気付き、きよを咎めにきたに違いない。
「すみません!」
たとえ店主に強いられたにしても、結果としてきよが作ったものを客に出したという事実は揺らがない。言い訳は見苦しいだけだ。そう考えたきよは、詫びの言葉だけを口にして深く頭を下げた。
ところが、返ってきたのは弥一郎のぶっきらぼうな言葉だった。
「座禅豆をくれ」
「え?」
「客が褒めまくってた」
「板長さんの座禅豆は、すごく美味しいですから……」
「――あの客は『温かい上に、柔らかくて旨かった。なにより甘みがなんともいえない』と言った。俺のとは違う」
「本当にすみませんでした!」
「いいから早く食わせろ。冷めないうちに試したい」
そう言うと弥一郎は、きよから鉄鍋を奪って勝手口の脇にある卓の上に置いた。続いて蓋を取り、一瞬動きを止める。
煮汁は、豆の色を吸って漆黒に染まっている。弥一郎は大きめの匙で、三つか四つの豆と、あわせて煮汁もたっぷり掬い取り、口の中に入れた。
「本当に甘い……。舌の先で潰せるほど柔らかいし、味もよく染み込んでる。煮豆は火から下ろしたあと一晩寝かせて味を含ませるのが常だが、こいつは煮上がったばかりなのに、どうしてこんなにしっかり味が入っているんだ……」
普段は最小限の言葉しか口にしないのに、料理を語るときだけは多弁になる。不思議な人だ、と思っていると、弥一郎が訊ねてきた。
「なにか秘訣でもあるのか?」
「え……? 普通に煮ただけですけど……」
「戻した豆を水で煮て、柔らかくなったら味をつけて煮詰める。おまえは違うのか?」
「私は最初に水に醤油や味醂を入れておいて、その中で豆を戻します」
「そんな荒っぽいやり方は聞いたことがない」
弥一郎はわずかに目を見張っている。その表情にきよはなんだか居心地が悪くなった。
「でも、私の母はいつもそうしてたんです」
「豆を戻すついでに味を付けちまえば、手っ取り早いってことか」
「よくわかりませんけど……とにかく私はこのやり方しか知らないんです」
油堀沿いの道を男がひとり走っている。
小銀杏の髷に濃茶の縞小紋、草履が脱げんばかりの勢いで、船宿の前に浮かぶ猪牙船も、寒風に舞うしだれ柳の枝も男の目には入っていない。
時は文政六年(一八二三年)師走、日もすっかり落ちた七つ半(午後五時)のことだ。
男はそのまま深川佐賀町にある孫兵衛長屋へと続く路地に入り、奥から二軒目に飛び込んだ。
「やっと帰り着いた……」
「どうしたの、そんなに息を切らして」
家に入るなり土間にへたり込んだ男を呆れたように見たのはきよ、男は清五郎という。ふたりは三つ違いの姉弟で、きよは年が明けたら数え二十三を迎える。部屋は少々狭いが建て付けは良く、大家や近隣が善人揃いだったこともあり、姉弟はそれなりに心地よく暮らしていた。
「乾物屋さんはまだ開いていた?」
続いて訊ねるも、清五郎は息も絶え絶えの様子で言葉が出ない。どうやらずっと走ってきたらしい。
清五郎は少し前に、ぶどう豆を買いに行った。
夕食を終えてのんびりしていたところ、清五郎が不意に座禅豆を食べたいと言い出したためだ。すぐにでも食べたい様子だったので、それなら明日にでも煮売り屋で買ってこよう、と言ったのだが、きよの手作りがいいと言う。
正直に言えば、座禅豆を煮るのは面倒だ。座禅豆は黒い大豆であるぶどう豆を醤油や味醂で煮て作るお菜だが、あらかじめ乾いた豆を水に浸けて戻しておかなければならないし、とにかく煮上がるのに時間がかかる。けれど、『手作りがいい』と言われれば悪い気はしない。それでは、と探したところ、ぶどう豆の買い置きがほとんど残っていなかった。
座禅豆にするぶどう豆は、長屋に回ってくる振売から買っている。振売が運んでくる品は青物、魚貝、豆腐、醤油、酒、団子といった食い物から、古布、竹笊といった暮らしに必要な品々、子どもが喜ぶシャボン玉に飴、と人それぞれだが、ひとりで担げる量は知れているため、扱う品目は限られる。今日は豆売りが回ってくる日ではないし、そもそもこんな遅くに商う振売はいない。
仕方がない、今度にしようと言ったのだが、清五郎は諦めきれなかったようだ。油堀を抜けた先の富岡八幡宮あたりの乾物屋ならまだ開いているかもしれない。木戸が閉まるまでにはまだ間がある。空振りを覚悟で行ってみる、と言うので、送り出したのである。
それがこれほど息を切らして戻ってくるとはどうしたことか。
乾物屋までは大した道のりではないが、清五郎は迂闊なところがある。気が急くあまり、渡したお金を落としたのかもしれない。そこらの草むらに転がり込めば見つけるのは難しいし、そもそも地べたに落としたところで大した音はしないから気付きもしない。
店に辿り着いてみたら懐にお金はなく、乾物屋に『冷やかしか!』と怒鳴られた。悔しさ半分、恐ろしさ半分で駆け戻った。せいぜいそんなところだろう、ときよは思ったのである。
ところが、話はそんなに簡単ではなかった。
「やっかいなことになった」
「どういうこと?」
とりあえずこれを飲んで落ち着きなさい、と湯飲みに入れた水を差し出すと、清五郎は一息に飲み干し、経緯を話し始めた。
「富岡さんの参道に入ったところで、小僧が雨戸を立てかけてるのが見えたんだ。いけない、閉まっちまう! って大急ぎで駆け込んだら、あいにくそこにお侍がいて……」
「ぶつかっちゃったの……?」
「そう。思いっきり左側から、どーんって……」
「左ってことは刀……?」
清五郎が黙って頷く。きよは、冷たい水をぶっかけられた心地だった。
東照大権現様から始まった徳川の世も、家斉様の代ともなると平穏そのもの、飢饉や大火などの禍はあるにしても、大きな戦は起こらなくなった。武士が刀や鎗を振り回すことも減り、どうかすると質入れして竹光でごまかす者までいる始末である。
それでも刀が武士の命とされることに変わりはなく、うっかりぶつかった日には、武士同士であっても諍いが起こる。町民や農民に至っては、その場で斬り捨てられかねない。
弟の起こしたとんでもない事態に、血の気が引く。
清五郎は末っ子ということもあって、家族みんなにかわいがられてきた。とりわけきよは、自分より年下なのは清五郎だけだったため、ありとあらゆる面倒を見てきた。もしかしたら弟のためにはよくないかもしれないと思うこともあったが、清五郎をかわいく思う気持ちは止められない。一緒に江戸に出てきたのも、面倒を見られてばかりだった弟をいきなりひとりで放り出すのはしのびない、なにかあっては大変だと思ったからだ。
甲斐あって、なんとか一年は無事に過ごせた。清五郎も少しずつ成長してきたようだし、どうにかこのまま……と思った矢先の出来事に、きよは動悸が止まらなくなる。
大急ぎで弟の様子を確かめたが、どこにも怪我はないようだ。怪我をしていたら、あんな勢いで走ってこられるわけがない。とりあえずほっとしたものの、なにもなしに済んだとは思えなかった。
「それで、お咎めは……? お金を払えって言われたとか……」
詫び料でも求められたのかもしれない。昨今、お金に困っている侍も多いと聞く。手討ちにするよりも、お金を払わせるほうがいいと考えることもあるだろう。余分なお金などないが、背に腹は代えられない。なんとしてでも掻き集めて……と考えかけたとき、清五郎がもぞもぞと身体を捻った。
生まれたときから知っているきよにはわかる。弟がこんなふうに身体を動かすのは、後ろめたいことがある証だ。お侍の刀にぶつかったのは不注意だったが、ある意味事故のようなもの。それとは別に、なにかまずいことをしでかしたに違いない。
「――正直におっしゃい。なにをやらかしたの?」
「それが……。そのお侍、俺がぶどう豆を買いに来たのを知って、おまえが煮るのかって訊いてきたんだ。だから俺、つい、そうだ、俺は料理人だからな、って言っちまった。そしたら、その豆を食わせろって。どうやらそのお侍も、座禅豆が食いたかったみたいで……」
近所の煮売り屋のものが気に入らず、他に売っているところはないかと探していた。
煮売り屋は乾物屋からいろいろなものを仕入れる。乾物屋なら、このあたりの煮売り屋に詳しいはずだ。他に座禅豆を商っている店はないか、と訊きに来たところに、清五郎が飛び込んできた。こんな時間に若い男が豆を買いに来たというのが不思議でならない。聞けば料理人、これから座禅豆を煮るつもりだと言われて俄然興味が湧いたとお侍は言ったらしい。
「いくらお侍でも、手討ちは後味が悪い、豆を分捕るぐらいで許してやろうって思ったんじゃないかな」
「どこの誰ともわからない男が煮た豆を欲しがるなんてことがある?」
「それは俺が『千川』の料理人だって言ったから……」
『千川』というのは、姉弟が奉公している料理屋である。富岡八幡宮の参道にあり、最初は清五郎だけが世話になっていたのだが、しばらくしてきよも一緒に働くようになった。
かなり大きな店で、評判もすこぶるよく、そこらの煮売り屋とは比べものにならない。座禅豆も出しているし、人気の品だから、その侍が欲しがるのも無理はない。
問題は、清五郎が料理人ではないことだ。
「なんでそんな出任せを言うのよ! あんたは『千川』で働いてはいても、料理人じゃない。できた料理を運んでるだけだし、家でだって、自分で豆を煮たことなんてないでしょう!」
「わかってるけど、つい……」
唇を尖らせる弟に、きよは目眩がしそうになっていた。
きよと清五郎が江戸に来てから、まもなく一年になる。
ふたりは逢坂で油問屋を営む菱屋五郎次郎とたねの間に生まれた。
姉の自分が言うのもなんだが、清五郎は子どものころから見栄えが良く、やんちゃながらも憎めない質だったため、友だちも多かった。娘たちからも人気が高く、天狗になっていたせいか、仲間とつるんで悪さをすることもあった。家族の心配の種ではあったけれど、十八の年までは大きな事件を起こすことなくきていた。
ところが昨年の秋、茶店で居合わせた若者が、清五郎に喧嘩をふっかけてきた。どうやら、清五郎が娘たちにちやほやされているのが気に入らなかったらしい。
相手の腰には刀がある。喧嘩をしてはいけない相手だとはわかっていたらしいが、執拗に絡まれるうちに気が高ぶり、とうとう殴り合いになってしまった。
幸い清五郎は大した怪我もせずに終わったが、相手はそうはいかなかった。顔や身体のあちこちに青痣ができ、熱まで出してしまったのだ。
悪いことに、相手は蔵屋敷勤めの武士の息子だった。父親の怒りはすさまじく、清五郎の首を刎ねかねない勢いで乗り込んできた。その場は留守だとごまかしたけれど、父親は必ず仕返しすると息巻く。とてもじゃないがここには置いておけない、ということで、清五郎は江戸で料理屋を営む知人で、古くからの取引先でもある川口屋源太郎に預けられることになったのだ。
だが、清五郎は家のことなどやったこともなく、そもそも我が儘で、気が高ぶるとなにをしでかすかわからない。両親も、ひとりで暮らしていけるのか、と心配した。かといって、奉公に上がるのに女中をつけるのもおかしな話だ。それなら、ということでお目付役と世話役をかねて、きよが一緒に行くことになった。父にしてみれば、きよを厄介払いしたい気持ちが強かったのだろう。
――きよは生まれながらの厄介者だった。
きよが生まれたのは享和二年卯月、ただでさえ畜生腹で縁起が悪いと言われる双子の上に、心中者の生まれ変わりとされる男女の組み合わせだった。
父は生まれたばかりの娘を処分しようとしたが、母が抱え込んで離さなかったため、根負けした末に家に置くことにした。ただし、表向きは生まれたのは男子、清三郎だけとし、娘は屋敷の奥深くに隠した。
それから二十余年が過ぎ、奉公にも出せず嫁にもやれず、いよいよ娘を持て余した父が、逢坂にいられなくなった弟とともに江戸に出した、というのがこれまでの経緯である。
源太郎の営む『千川』で料理を運ぶのだって未熟なのに、あろうことか料理人を騙るとは。
唖然とする姉に、清五郎は不満たっぷりに言う。
「年が明けたら二十歳になるってのに、小僧みたいな仕事をしてるなんて思われたくなかった。馬鹿にされちまうじゃないか」
清五郎は、江戸に出るまでは実家の店の手伝いをしていた。物覚えは悪くなかったため、父に習い、留守のときには父に代わって帳簿を付けることもあった。
親兄弟は、店を手伝っている最中でも仲間から声がかかれば飛び出していく清五郎を見て、あんな不真面目な態度ではとても任せられない、と思っていた。それでも本人は、いずれ番頭ぐらいには取り立ててもらえると期待していたのかもしれない。
にもかかわらず、慣れ親しんだ逢坂から追い出され、江戸で奉公。しかも、できた料理を運ぶだけという簡単な仕事とあって、誇りを傷つけられた気になったのだろう。
入ったばかりなのだから簡単な仕事しか任せられないのは当たり前、年季が入っていれば小僧のほうが上、なんて思いも及ばない。だからこそ、ちょっとでも聞こえがいいように、料理人を騙ってしまった……
考えれば考えるほど、愚かな弟の振る舞いに、頭がくらくらしてくる。普段かわいがっているからこそ、よけいに不甲斐ない気持ちが募った。だが、話がそこで終わるはずもない。首根っこを掴まえてぐらぐら揺すぶりたくなる気持ちを抑え、きよは先を促した。
「それで?」
「そのお侍は、俺に座禅豆を屋敷に届けろって。座禅豆が気に入ったら許してやる。『千川』も贔屓にしてやるぞ、って……」
わけがわからない。だが、ともかくその侍は、斬り捨てる代わりに持ってこいと言うほど座禅豆に執着しているようだ。
「気に入らなかったら、ただではすまないと思う。きっと手討ちにされる……」
息子が青痣を作らされただけでも、大層な勢いで怒鳴り込んできたのだ。侍と町民の間では、喧嘩両成敗なんてありえない。ましてや、こちらの一方的な不注意で武士の命を穢したのだ。
「その侍、腕っ節は強そうだったし、鬼みたいに恐い顔だった。もたもたしてるうちに気が変わって、やっぱり斬る、って言い出したらことだと思って、大急ぎで帰ってきたんだ。思い出しても震えがくる……。ああもう、どうしよう!」
「どうしようって、『千川』の座禅豆を買って届けるしかないでしょ! その上で、事情を話して謝りなさい。料理人は騙りですが、この豆は紛れもなく『千川』のものですって」
「騙りなんて働いたことがばれたら、ただじゃすまねえよ!」
「座禅豆さえ気に入ってもらえたら、許してもらえるかもしれない。なにより、最初に馬鹿な嘘をついたあんたが悪いの! 明日にでも座禅豆を買いましょう」
「でも姉ちゃん、『千川』の料理は値が張るし、そもそも持ち帰りなんてやってないよ」
「そんなこと言ってる場合じゃないでしょ!」
『千川』は料理屋だから、煮売り屋のように持ち帰ることはできない。だが、事情を話せばきっとわかってくれる。なんとか売ってもらって、届けに行くしかない。
だが、清五郎は気が進まないらしく、うだうだと理屈を捏ねる。
「それはうまくないよ。『千川』の旦那さんに料理人を騙ったなんて話をしたら、なおさら呆れられちまう。ただでさえ、面倒を起こして流れてきた厄介者なのに。あーもう、いっそこのまま逃げちまうってのは?」
「あんたが『千川』に奉公してるのはわかってるのよ? もし行かなかったら『千川』に乗り込んできかねない。あんたまさか、『千川』を巻き添えにするつもりなの⁉」
「それは……」
姉に詰め寄られて清五郎は意気消沈。だが、しばらく考えていたあと、ぱっと目を輝かせて言った。
「そうだ! なにも『千川』の座禅豆を持っていく必要ないよ。姉ちゃんのを持っていけばいいんだ!」
「私の?」
「それが『千川』のものかどうかなんてわかりっこない。姉ちゃんの座禅豆はそこらの煮売り屋のよりずっと旨いから、絶対気に入るよ」
清五郎は、さも嬉しそうに続ける。
「明日のうちに豆を煮れば、明後日には届けられる」
頭がくらくらするのを通り越して、頭痛がしてきた。きよは、あまりにも考えなしの弟を叱りつけた。
「清五郎の馬鹿! そんなの通るわけないじゃない! 座禅豆は、注文があってから作るような料理じゃないのよ!」
座禅豆は、たいていの料理屋なら置いている。相手がお侍だとしても、作り置きがあることぐらいわかりそうなものだ。
けれど、清五郎はさらにきよの気持ちを逆なですることを言う。
「今日はよく売れた。おかげで売り切れて、一から煮直したせいで時間がかかった、ってことにすればいい」
「あんたってば、嘘に嘘を重ねるって言うの⁉」
「大丈夫、大丈夫、ばれっこない。絶対うまくいくって!」
「いくわけないわよ! そもそも、ぶどう豆はどうする気? あんた、買ってこなかったでしょ!」
弟は手ぶらで帰ってきた。這う這うの体で逃げ出し、それどころではなかったのだろう。だが、清五郎は平然と言う。
「少しは残ってるんだろ? たくさん食いたかったから買いに出たけど、今回は諦める。俺の分はぽっちりでいいよ。じゃ、よろしく!」
そう言うが早いか清五郎は草履を脱ぎ捨てて家に上がり、寝支度を始めた。
とはいっても風呂敷に包んであった布団を広げるだけ。あとは着物を脱いでひっ被れば終わりだ。明日も仕事があるし、行灯の油も惜しい。こんな日はさっさと寝るに限る、というところだろう。
ほどなく、清五郎は寝息を立て始めた。こんな騒動を起こしておいて、よくもすんなり寝付けるものだ、と呆れてしまう。
自分は眠れそうにない。やむなく、きよはぶどう豆が入った枡を手に取る。
揉め事の原因となったぶどう豆など見たくもないし、人を騙すのはとても嫌だけれど、弟が手討ちにされては大変だ。とにかく座禅豆を煮るしかない。
きよは深いため息とともに、ぶどう豆を洗い始めた。
何度も水を替え、小さな豆殻や葉を丁寧に取り除く。多少傷のある豆でも、普段ならもったいないと一緒に煮てしまうけれど、今日はちゃんと選り分けた。傷のある豆は飯と一緒にでも炊けばいい。『千川』が客に傷のある豆を出すわけがない。まったく同じになんてできっこないけれど、せめてそれぐらいは……と思いながら、きよは冷たい水でぶどう豆を洗い続けた。
二日後、清五郎は煮上がった豆を届けに行った。件の侍は留守だったそうで、家人に預けたと言って帰ってきた。その後、お侍がなにか言ってくるかと生きた心地がしなかったが、その日も翌日も、その次の日になっても音沙汰がなかった。
座禅豆を気に入ってくれたのか、面倒くさくなったのか、とにかく清五郎を咎めるのはやめにしたらしい。
胸を撫で下ろしつつ、きよは、料理人を騙るのはもちろん、どんな嘘も二度とついてはいけない、と清五郎に強く言い聞かせた。
それからしばらくしたある日、『千川』の勝手口にいたきよは、主の源太郎に声をかけられた。源太郎は、きよの父、五郎次郎よりひとつ年上らしいが、浅黒い顔に皺がたくさんあり、髷に交じる白髪も父よりもずっと多いため、五つ六つ上に見える。大店の主というのは厳しい人だと思われがちだが、源太郎は姉弟が江戸に来てからなにくれとなく面倒を見てくれたし、他の奉公人にとっても情けの深い雇い主だった。
「おきよ、もう豆は煮えたかい?」
「そろそろ出来上がります」
日頃のきよの仕事は、屋内で野菜を洗ったり切ったりといった下拵えばかりだが、今日は珍しく勝手口の脇に七輪を持ち出し、火の番をしていた。
「それはよかった。どうしても座禅豆を食わせろって、客がうるさくてな」
「え……これをですか?」
鍋の中にあるのは、きよが源太郎に頼まれて煮ていた座禅豆だ。
清五郎が乾物屋で揉め事を起こした翌々日、源太郎の妻さとが、客からもらったという菓子をくれた。さとは背丈はきよと大差ないが太り肉で貫禄たっぷり、ふっくらとした頬は冬の寒いときでも桃色で、鈴を転がすような声でよく笑う。少々心配性が過ぎるが、それも優しい人柄ゆえだろう。親元を離れているきよと清五郎を我が子のようにかわいがってくれていて、菓子やお菜を裾分けしてくれることが多かった。
小鉢に入れて持たせてくれたため、空で返すのも憚られ、清五郎が届けた残りの座禅豆を入れて返したところ、さとばかりか源太郎も大いに気に入ってくれた。もっと食べたいから自分たち用に作ってくれ、豆はもちろん醤油や味醂、炭も用意するから、と頼まれた。おまけに、豆を煮るのは時間がかかるから、店で煮ていいとまで言われて断れなかったのだ。
仕事の傍ら、こまめに火を加減したおかげで煮上がりは上々、皺ひとつない艶やかな座禅豆が出来上がった。
とはいえ、店の客に出すなんてありえない。これは主夫婦のために作ったものだし、なにより、下働きのきよが作ったものを客に出したら、板長の弥一郎が怒り出すだろう。弥一郎は源太郎の息子だが、言葉数が少なく、いつも険しい顔をしている。しかも仕事に厳しい。もしきよが作ったものを出したと聞いたら烈火の如く怒るに違いない。
そもそも座禅豆ならば、弥一郎が作ったものがある。それを差し置いて、きよの料理を出そうとする意味がわからなかった。
「板長さんに叱られます。それに、座禅豆を切らしてるわけでもないのにどうして……」
当然の疑問を口にしたきよに、源太郎は小声で言う。
「弥一郎の座禅豆が旨いのはわかってるが、今日の客はちょっと面倒なんだ」
「というと?」
「黒羽織で腰には刀」
「同心様ですか?」
「いや、前に馬に乗ってるのを見たことがある」
「じゃあ、与力様……」
町中で見かける羽織姿は、おおむね侍か大店の番頭より上の町人だろう。中でも黒羽織で帯刀となると、市中を見回る同心か与力ということになる。同心は馬に乗ることは許されていないため、源太郎が馬に乗っている姿を見たというのであれば、それは与力に違いない。
目を見張るきよに、源太郎は頷いた。
「たぶんな。その客は、座敷に上がるなり座禅豆を注文した。で、いつものを出したら、全部食った上で、他の座禅豆を食わせろ、ときたもんだ」
「他の? でもそんなものありませんよね?」
そう言ったとたん、きよは嫌な予感に襲われた。
その与力というのは、もしかしたら先日清五郎が乾物屋でぶつかった侍ではないのか。
いつも出しているのとはまったく違う座禅豆を、『千川』のものだと偽って届けたのだから、『千川』には二通りの座禅豆があると思い込んでも不思議はない。
届いた座禅豆に満足できなかったけれど、お勤めかなにかの都合でこれまで来られなかった。今になってやっと時間ができたため、文句を言いに来たのではないか。
もしも清五郎にお咎めがあったらどうしよう、ましてや『千川』まで巻き込んでしまったら、と血の気が引いた。
そんなきよの思いを余所に、源太郎は話を続けた。
「だろう? 俺も、うちの座禅豆はこれだけだって言ったんだ。だが、客のほうが『あるはずだ。それに、外から豆を煮る匂いがしてくる。これとは違う匂いだ。あれを持ってこい』って聞かない。それで、おまえが煮ている最中だって思い出してね。そろそろできるころじゃないか、って来てみた」
「ずいぶん鼻が利くお方ですね……」
『千川』の造りはしっかりしている。季節は冬、すっかり冷え込んでいるから戸口だって閉まっている。それなのに外、しかも勝手口で煮ている豆の匂いがわかるなんてすごい、ときよは感心しそうになった。だが、感心している場合ではない。おそらく、源太郎もそれどころではないのだろう。さっと周りを見回して、袖から小鉢を取り出した。
「なにを考えているかはわからないが、うまいこと気に入られれば、今後も贔屓にしてくれるかもしれない。与力様なら手下だってたくさんいる。客を増やす絶好の機会じゃないか」
「気に入られるとは限りませんよ」
むしろその逆の可能性のほうが高い。だが、事情も知らぬ源太郎にそれを告げたところでわかってくれるはずもない。さらに源太郎はせっつく。
「とにかく、お役人相手に問題は起こしたくない。さっさと豆を盛ってくれ。いつも座禅豆を盛っている器だし、これなら弥一郎に見られてもばれないはずだ」
「湯気が上がってても?」
「なんとかこっそり持っていく」
やめましょう、嘘はよくありません、と何度も言ってみたが、源太郎は聞き入れようとしない。やむなくきよは、小鉢に座禅豆を盛り上げた。
源太郎は、ほっとしたように店の中に戻っていったが、きよはあらゆる意味で心配でならなかった。
弟にお咎めがあるのではないか、ということはもちろん、その与力が清五郎がぶつかった相手ではなかったとしたら、自分の料理への評価が気になる。いや、それより切実なのは、誰が作ったものであっても、客に出された時点でそれは『千川』の料理となり、すべての責任は板長のものとなる。客の口に合わなかった場合、弥一郎の顔に泥を塗ることになるし、逆なら逆で料理人の誇りを傷つけかねない。
――どうか清五郎とは無縁の人でありますように。不味くて食べられないほどではありませんように。物足りなくても、出来立てで味が馴染んでいないせいだって言い訳できるぐらいでありますように! それから、まかり間違っても、褒められたりもしませんように……とはいえ、褒められたらやっぱり嬉しいかも……
きよの気持ちは千々に乱れる。
この座禅豆を煮上げたら、きよは家に帰っていいことになっていた。それでも成り行きが気になって、あえてゆっくり七輪の火の始末をしていると、勝手口からまた源太郎が出てきた。手にはさっきの小鉢を持っている。
「ど、どうなりました?」
「ものすごく気に入ってくれて、あっという間に食っちまった」
「そうですか……。他になにかおっしゃってましたか? お訊ねのこととか……」
「お訊ね? これといっては……」
幸い清五郎は今、使いに出ている。清五郎絡みの来店であれば、きっと所在を訊ねるはずだ。なにも訊かれなかったのであれば、清五郎がぶつかった人ではなかったのだろう。とりあえず一安心だが、心配はそれだけではない。
「それで、板長さんには?」
「客は板場に背を向けるように座ってたから、たぶん気付かれてない。相当旨かったらしい。もう一杯くれってさ」
そこまで話して、源太郎は慌てて小鉢を差し出した。
「客が待ってる。さっさと盛ってくれ」
こうなったら一鉢も二鉢も同じだ。きよは、毒を食らわば皿までも、という気持ちでまた豆を小鉢に盛った。主夫婦に渡す分が少なくなるが、それは仕方がないというものだ。
弥一郎のことを抜きにすれば、自分の料理を喜んで食べてくれる人がいるというのは嬉しい。ましてや、誰が作ったかなんて知るよしもない客まで気に入ってくれたとなると、勝手に目尻が下がってしまう。込み上げる笑みを抑えきれないまま、きよは豆を炊いた鍋を手に勝手口から中に入った。
その瞬間、一気に血の気が引いた。
弥一郎がいたからだ。
白と紺の格子縞の着物に襷を掛け、頭を手ぬぐいで覆っている。源太郎よりも頭半分背が高く痩身、まるで似ていないようだが、耳の形がそっくりなところを見ると紛れもなく親子なのだろう。
弥一郎が、店を開けている間に板場を離れることは滅多にない。ましてや、勝手口までやってくるなんて考えられない。おそらく、あの客に出した座禅豆が己の手によるものではないと気付き、きよを咎めにきたに違いない。
「すみません!」
たとえ店主に強いられたにしても、結果としてきよが作ったものを客に出したという事実は揺らがない。言い訳は見苦しいだけだ。そう考えたきよは、詫びの言葉だけを口にして深く頭を下げた。
ところが、返ってきたのは弥一郎のぶっきらぼうな言葉だった。
「座禅豆をくれ」
「え?」
「客が褒めまくってた」
「板長さんの座禅豆は、すごく美味しいですから……」
「――あの客は『温かい上に、柔らかくて旨かった。なにより甘みがなんともいえない』と言った。俺のとは違う」
「本当にすみませんでした!」
「いいから早く食わせろ。冷めないうちに試したい」
そう言うと弥一郎は、きよから鉄鍋を奪って勝手口の脇にある卓の上に置いた。続いて蓋を取り、一瞬動きを止める。
煮汁は、豆の色を吸って漆黒に染まっている。弥一郎は大きめの匙で、三つか四つの豆と、あわせて煮汁もたっぷり掬い取り、口の中に入れた。
「本当に甘い……。舌の先で潰せるほど柔らかいし、味もよく染み込んでる。煮豆は火から下ろしたあと一晩寝かせて味を含ませるのが常だが、こいつは煮上がったばかりなのに、どうしてこんなにしっかり味が入っているんだ……」
普段は最小限の言葉しか口にしないのに、料理を語るときだけは多弁になる。不思議な人だ、と思っていると、弥一郎が訊ねてきた。
「なにか秘訣でもあるのか?」
「え……? 普通に煮ただけですけど……」
「戻した豆を水で煮て、柔らかくなったら味をつけて煮詰める。おまえは違うのか?」
「私は最初に水に醤油や味醂を入れておいて、その中で豆を戻します」
「そんな荒っぽいやり方は聞いたことがない」
弥一郎はわずかに目を見張っている。その表情にきよはなんだか居心地が悪くなった。
「でも、私の母はいつもそうしてたんです」
「豆を戻すついでに味を付けちまえば、手っ取り早いってことか」
「よくわかりませんけど……とにかく私はこのやり方しか知らないんです」
12
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

私が王子との結婚式の日に、妹に毒を盛られ、公衆の面前で辱められた。でも今、私は時を戻し、運命を変えに来た。
MayonakaTsuki
恋愛
王子との結婚式の日、私は最も信頼していた人物――自分の妹――に裏切られた。毒を盛られ、公開の場で辱められ、未来の王に拒絶され、私の人生は血と侮辱の中でそこで終わったかのように思えた。しかし、死が私を迎えたとき、不可能なことが起きた――私は同じ回廊で、祭壇の前で目を覚まし、あらゆる涙、嘘、そして一撃の記憶をそのまま覚えていた。今、二度目のチャンスを得た私は、ただ一つの使命を持つ――真実を突き止め、奪われたものを取り戻し、私を破滅させた者たちにその代償を払わせる。もはや、何も以前のままではない。何も許されない。

【完結】20年後の真実
ゴールデンフィッシュメダル
恋愛
公爵令息のマリウスがが婚約者タチアナに婚約破棄を言い渡した。
マリウスは子爵令嬢のゾフィーとの恋に溺れ、婚約者を蔑ろにしていた。
それから20年。
マリウスはゾフィーと結婚し、タチアナは伯爵夫人となっていた。
そして、娘の恋愛を機にマリウスは婚約破棄騒動の真実を知る。
おじさんが昔を思い出しながらもだもだするだけのお話です。
全4話書き上げ済み。

愛された側妃と、愛されなかった正妃
編端みどり
恋愛
隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。
夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。
連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。
正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。
※カクヨムさんにも掲載中
※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります
※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。
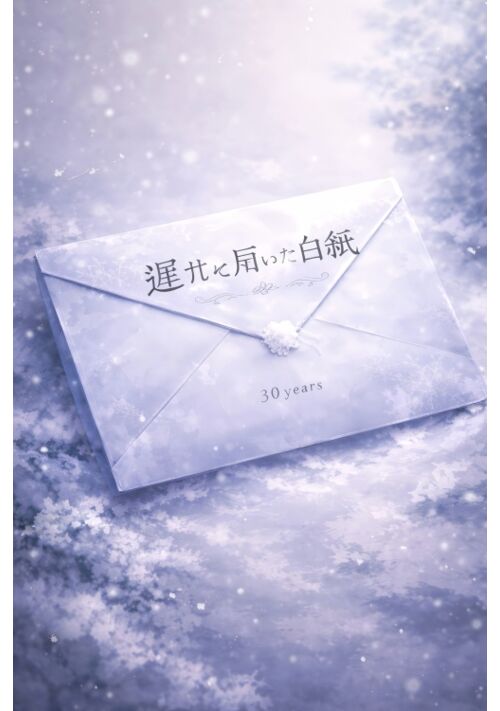
三十年後に届いた白い手紙
RyuChoukan
ファンタジー
三十年前、帝国は一人の少年を裏切り者として処刑した。
彼は最後まで、何も語らなかった。
その罪の真相を知る者は、ただ一人の女性だけだった。
戴冠舞踏会の夜。
公爵令嬢は、一通の白い手紙を手に、皇帝の前に立つ。
それは復讐でも、告発でもない。
三十年間、辺境の郵便局で待ち続けられていた、
「渡されなかった約束」のための手紙だった。
沈黙のまま命を捨てた男と、
三十年、ただ待ち続けた女。
そして、すべてを知った上で扉を開く、次の世代。
これは、
遅れて届いた手紙が、
人生と運命を静かに書き換えていく物語。

冷遇王妃はときめかない
あんど もあ
ファンタジー
幼いころから婚約していた彼と結婚して王妃になった私。
だが、陛下は側妃だけを溺愛し、私は白い結婚のまま離宮へ追いやられる…って何てラッキー! 国の事は陛下と側妃様に任せて、私はこのまま離宮で何の責任も無い楽な生活を!…と思っていたのに…。

王子を身籠りました
青の雀
恋愛
婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。
王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。
再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

「がっかりです」——その一言で終わる夫婦が、王宮にはある
柴田はつみ
恋愛
妃の席を踏みにじったのは令嬢——けれど妃の心を折ったのは、夫のたった一言だった
王太子妃リディアの唯一の安らぎは、王太子アーヴィンと交わす午後の茶会。だが新しく王宮に出入りする伯爵令嬢ミレーユは、妃の席に先に座り、殿下を私的に呼び、距離感のない振る舞いを重ねる。
リディアは王宮の礼節としてその場で正す——正しいはずだった。けれど夫は「リディア、そこまで言わなくても……」と、妃を止めた。
「わかりました。あなたには、がっかりです」
微笑んで去ったその日から、夫婦の茶会は終わる。沈黙の王宮で、言葉を失った王太子は、初めて“追う”ことを選ぶが——遅すぎた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。




















