3 / 8
金魚も悪くないだろ?
しおりを挟む
*
翌週の土曜日。私は約束通り、再びユキさんのアパートを訪れていた。
間取りは6畳1Kと小ぢんまりしているが、いつも作業場にしているというバルコニーは広々と開放的だ。
「今日は何を作るの?」
作業台にブロックアイスを置き、削るための道具を揃え……と忙しく準備を進めている横顔に尋ねると、彼は台の片隅で風に煽られている紙を指さす。
見ると、大雑把な四角形の中に、何やらひょろひょろとした線が数本と、魚らしき影が弧を描くようにふたつ描かれていた。おおよその設計図らしい。
「ねぇ、これって金魚?」
「正解。その適当な絵でよく分かったね」
ということは、このひょろひょろしたのは水草だろうか。
「さあ。イメージが湧いたところでさっそく始めるよ。氷彫刻は時間との勝負だから」
そう言うや否や、彼は作業台の前に立ち、ノミやチェーンソーを使って、氷を削っていく。
時間との勝負、という言葉を裏づける、スマートで迷いのない手つき。
作ってみたい! なんて意気込んでいたわりに、いざとなったら、彼から「ちょっと押さえてて」「ここを少しノミで」と指示が飛ばない限り、何もできなかった。
彼の魔法に、すっかり見惚れてしまって。
そんなふうに上の空でサポートを続けること、一時間弱。設計図より何十倍も素敵な氷彫刻が全貌を現し始めたとき、ふと、あることが気にかかった。初対面のときに、印象的だったこと。
「ユキさんって、もしかしてハーフだったりする……?」
ためらいがちに尋ねると、彼は手を止めずに「――なんで分かったの?」と虚をつかれたように訊き返す。
「目の色、日本人っぽくないなって。カラコンにしては地味だし」
答えると、「あぁ……」と曖昧な返事をした後、
「ところでさ、本当に俺とこんなことしてて平気?」
ノミを操りながら、まるで話をそらすように、今度は彼が問いかけてきた。
「えっ? なんで? 迷惑?」
「いや、そうじゃなくてさ。高三だったよね? 進学するなら今追い込みの時期だろうし、それにほら、たまには息抜きに友だちとどっか遊びに行ったりしないのかなー……って」
耳が痛くて何も返せず、私は「ハハッ……」と力なく笑う。
「ご心配なく。自慢じゃないけど成績はかなりいいほうだし、中学時代から安定のぼっちなんで」
「あ、やっぱり?」
間髪入れず軽々しい口調で言った彼に、思わず鋭い視線を投げた。
「やっぱりとはなんだ、やっぱりとは。察しついてたならわざわざ訊くなぁ~」
拗ねて頬を膨らませると、彼はさして悪びれもせず「ごめんごめん」と苦笑する。
「……ほんとはね、分かってるんです」
ぽつり、と呟く。
彼は手を止めなかったけれど、ちゃんと私の声に耳を傾けてくれているのを感じた。だからそのまま話し続けた。
小学生の頃から、苗字、名前ともに「あ」から始まるせいで、出席番号はたいてい1~3番。好成績も相まって周囲の印象に残りやすく、優等生のイメージが定着するのも早い。で、みんなから一目置かれるようになって、その敬意がいつの間にか距離に変わって、敬遠されるようになる。
母の意向も無視できなかったし、自分に見合った、それも、いわゆる一般的な青春とは縁遠そうな女子校に入れば何かが好転するかな、なんて期待したけれど、そうそう思うようにはいかなくて。
それなりにレベルの高い学校なので、ドラマやアニメでよく見るような過激で陰湿ないじめはないのだが、代わりに、求めていた刺激もなかった。
女の子らしいふわふわした話題にはついていけないし、いくら男子がいなくても、やはり年相応の青春感というものは存在する。
住む世界が違う、と遠ざけているうちに、また独りになった。
そしてようやく気づいた。
テスト期間中だけ、「相原さんってほんと頭いいよね。ノート見せてよ」なんて近づいてくるくせに、陰では「とっつきにくくない?」と囁いているあの子が悪いんじゃなくて。
入り込めない上品さを纏いながら、お喋りに花を咲かせているお嬢様たちが悪いんじゃなくて。
そうやって壁を作って、心のどこかで周囲を見くだして、何も行動しない私自身に問題があるのだと。
「だけど、人ってそんな簡単には変われないでしょ?」
自覚して反省したところで、急に勇気が湧いてくるわけでもないし、どうすれば改められるのか分からない。だから結局、白黒はっきりしていて、頑張った分だけ認められる勉強に逃げてしまう。でもそれすらも、すぐに疲れて投げ出したくなる。
悪循環の繰り返し。
私は、わがままで小心者で、とんだ贅沢娘なのだ。
「あははっ、君って面倒くさいね」
話を聞き終えた直後、語尾に星マークがついていそうなほどあっけらかんとした口調で返した彼に、またカチンとくる。
「知ってます。ユキさんにだけは言われたくないです」
彼は私の憎まれ口には応戦せず、「言いたいことは分からなくもないけど」と続けた。
「そんなにあれこれ考えて自分を追い込まなくても、自覚できたなら、同じように、無理せず納得できる道をゆっくり探していけばいいんじゃない? 先は長いんだから」
「明日死んだらどうするんですか?」
「もちろんその可能性もゼロじゃないけど、明日が来る確率よりはよっぽど低いだろ? 未来のことなんて神様しか知らないんだし、不安を数え始めたらキリがない。焦ったってしょうがないよ」
「まぁ、そうかもしれないけど……」
「それに俺、思うんだよね。傍から見てどれだけ素晴らしい生き方をした人でも、死に際に何かしらの後悔は絶対してるって。ただ、その後悔よりも、もっと大事な誇りや幸せを見つけられたってだけで。そういう人が、君の言う、二割の人間なんじゃないの?」
たしかに一理あるかも、とは思うが、なんというか、楽観的だ。男と女の違い、ってやつだろうか。
今ひとつ腑に落ちず仏頂面の私に、彼は切り替えを促すようにパンパンと手を叩いた。
「ほらほら、ぼーっとしてないで。仕上げだよ」
彼に急かされて、金魚の部分に赤色を、水草の部分に緑色を入れれば、夏を思わせる涼しげな氷彫刻が完成した。
きらめく氷の中を優雅に泳ぐ、二匹の金魚。
「きれい……」
感動とともに漏れるのは、相変わらずありふれた言葉だけれど。
ただの氷の塊をこんなふうに変身させてしまうなんて、やっぱり魔法使いだ。
*
「こんなところに置いといたら、すぐ溶けちゃうじゃん……」
バルコニーの片隅で新聞紙の上に置かれ、直射日光を浴びている氷彫刻を見て、アカネは残念そうに肩を落とした。
昨日また雪が降ったので、早朝にはまだ少し溶け残っていたのだけれど、幸か不幸か、今日は雲ひとつない真っ青な晴天。気温こそ低めだが、太陽は元気に顔を出し、積雪はみるみるうちに路上から姿を消している。
このぶんだと間違いなく、氷彫刻も短命だろう。
「しばらく冷凍庫に入れておけばいいのに」
彫刻のそばにしゃがんでスマホのカメラを向けながら、往生際悪く言う彼女に、
「溶けるまでが作品なの。見るべき人に見てもらったんだから、この彫刻の役目はもう終わりだよ」
そう言い聞かせると、ようやく諦めたのか、「やだなぁ。芸術家ぶっちゃって」と呆れ気味に言いながら立ち上がる。
そして、隣にいる俺を振り返り、
「でも、氷ひとつでこんなの作っちゃうなんて、本当にすごいね。名前ともつながりがあるし、ぴったりじゃんっ」
なんて無邪気に笑った。
その笑顔が眩しくて、
「あー……」
なんだか嘘をついているような気分になって、
「正確に言えば、逆かな」
訂正する。
――それに、この彫刻に秘めた想いにも、気づいてほしくて。
「この名前を好きになるために、氷をいじり始めた」
続けると、彼女が小さく息を呑んだのが分かった。
なんとなく好きなもの、嫌いなものは、ささいなきっかけでひっくり返る場合がある。
逆に、本当に心からそう感じているものは、後からどんな理由が加わったとしても覆らない。
だから、どんな物事も第一印象で決め込まないで、いろんな角度から見て、触れてみるといい。
そうすれば、後悔しないし、傷つくことも減るから。
昔、誰よりも俺の可能性を信じてくれた人が言っていた言葉。
当時は、なんか説教くさいな、と鼻で嗤っていたけれど、今ならほんの少しだけ分かる。
アカネの考えとも、相反するようで通じている部分がある気がする。
――君が自分の名前を、好きになってくれますように。
「どう? 金魚も悪くないだろ?」
勝算を持って問いかければ、彼女は淡く頬を染めて、花がほころぶようにふわりと微笑み、俯き加減でうなずいた。
「――うん」
あぁ、ずるい。やっぱたまんない。
翌週の土曜日。私は約束通り、再びユキさんのアパートを訪れていた。
間取りは6畳1Kと小ぢんまりしているが、いつも作業場にしているというバルコニーは広々と開放的だ。
「今日は何を作るの?」
作業台にブロックアイスを置き、削るための道具を揃え……と忙しく準備を進めている横顔に尋ねると、彼は台の片隅で風に煽られている紙を指さす。
見ると、大雑把な四角形の中に、何やらひょろひょろとした線が数本と、魚らしき影が弧を描くようにふたつ描かれていた。おおよその設計図らしい。
「ねぇ、これって金魚?」
「正解。その適当な絵でよく分かったね」
ということは、このひょろひょろしたのは水草だろうか。
「さあ。イメージが湧いたところでさっそく始めるよ。氷彫刻は時間との勝負だから」
そう言うや否や、彼は作業台の前に立ち、ノミやチェーンソーを使って、氷を削っていく。
時間との勝負、という言葉を裏づける、スマートで迷いのない手つき。
作ってみたい! なんて意気込んでいたわりに、いざとなったら、彼から「ちょっと押さえてて」「ここを少しノミで」と指示が飛ばない限り、何もできなかった。
彼の魔法に、すっかり見惚れてしまって。
そんなふうに上の空でサポートを続けること、一時間弱。設計図より何十倍も素敵な氷彫刻が全貌を現し始めたとき、ふと、あることが気にかかった。初対面のときに、印象的だったこと。
「ユキさんって、もしかしてハーフだったりする……?」
ためらいがちに尋ねると、彼は手を止めずに「――なんで分かったの?」と虚をつかれたように訊き返す。
「目の色、日本人っぽくないなって。カラコンにしては地味だし」
答えると、「あぁ……」と曖昧な返事をした後、
「ところでさ、本当に俺とこんなことしてて平気?」
ノミを操りながら、まるで話をそらすように、今度は彼が問いかけてきた。
「えっ? なんで? 迷惑?」
「いや、そうじゃなくてさ。高三だったよね? 進学するなら今追い込みの時期だろうし、それにほら、たまには息抜きに友だちとどっか遊びに行ったりしないのかなー……って」
耳が痛くて何も返せず、私は「ハハッ……」と力なく笑う。
「ご心配なく。自慢じゃないけど成績はかなりいいほうだし、中学時代から安定のぼっちなんで」
「あ、やっぱり?」
間髪入れず軽々しい口調で言った彼に、思わず鋭い視線を投げた。
「やっぱりとはなんだ、やっぱりとは。察しついてたならわざわざ訊くなぁ~」
拗ねて頬を膨らませると、彼はさして悪びれもせず「ごめんごめん」と苦笑する。
「……ほんとはね、分かってるんです」
ぽつり、と呟く。
彼は手を止めなかったけれど、ちゃんと私の声に耳を傾けてくれているのを感じた。だからそのまま話し続けた。
小学生の頃から、苗字、名前ともに「あ」から始まるせいで、出席番号はたいてい1~3番。好成績も相まって周囲の印象に残りやすく、優等生のイメージが定着するのも早い。で、みんなから一目置かれるようになって、その敬意がいつの間にか距離に変わって、敬遠されるようになる。
母の意向も無視できなかったし、自分に見合った、それも、いわゆる一般的な青春とは縁遠そうな女子校に入れば何かが好転するかな、なんて期待したけれど、そうそう思うようにはいかなくて。
それなりにレベルの高い学校なので、ドラマやアニメでよく見るような過激で陰湿ないじめはないのだが、代わりに、求めていた刺激もなかった。
女の子らしいふわふわした話題にはついていけないし、いくら男子がいなくても、やはり年相応の青春感というものは存在する。
住む世界が違う、と遠ざけているうちに、また独りになった。
そしてようやく気づいた。
テスト期間中だけ、「相原さんってほんと頭いいよね。ノート見せてよ」なんて近づいてくるくせに、陰では「とっつきにくくない?」と囁いているあの子が悪いんじゃなくて。
入り込めない上品さを纏いながら、お喋りに花を咲かせているお嬢様たちが悪いんじゃなくて。
そうやって壁を作って、心のどこかで周囲を見くだして、何も行動しない私自身に問題があるのだと。
「だけど、人ってそんな簡単には変われないでしょ?」
自覚して反省したところで、急に勇気が湧いてくるわけでもないし、どうすれば改められるのか分からない。だから結局、白黒はっきりしていて、頑張った分だけ認められる勉強に逃げてしまう。でもそれすらも、すぐに疲れて投げ出したくなる。
悪循環の繰り返し。
私は、わがままで小心者で、とんだ贅沢娘なのだ。
「あははっ、君って面倒くさいね」
話を聞き終えた直後、語尾に星マークがついていそうなほどあっけらかんとした口調で返した彼に、またカチンとくる。
「知ってます。ユキさんにだけは言われたくないです」
彼は私の憎まれ口には応戦せず、「言いたいことは分からなくもないけど」と続けた。
「そんなにあれこれ考えて自分を追い込まなくても、自覚できたなら、同じように、無理せず納得できる道をゆっくり探していけばいいんじゃない? 先は長いんだから」
「明日死んだらどうするんですか?」
「もちろんその可能性もゼロじゃないけど、明日が来る確率よりはよっぽど低いだろ? 未来のことなんて神様しか知らないんだし、不安を数え始めたらキリがない。焦ったってしょうがないよ」
「まぁ、そうかもしれないけど……」
「それに俺、思うんだよね。傍から見てどれだけ素晴らしい生き方をした人でも、死に際に何かしらの後悔は絶対してるって。ただ、その後悔よりも、もっと大事な誇りや幸せを見つけられたってだけで。そういう人が、君の言う、二割の人間なんじゃないの?」
たしかに一理あるかも、とは思うが、なんというか、楽観的だ。男と女の違い、ってやつだろうか。
今ひとつ腑に落ちず仏頂面の私に、彼は切り替えを促すようにパンパンと手を叩いた。
「ほらほら、ぼーっとしてないで。仕上げだよ」
彼に急かされて、金魚の部分に赤色を、水草の部分に緑色を入れれば、夏を思わせる涼しげな氷彫刻が完成した。
きらめく氷の中を優雅に泳ぐ、二匹の金魚。
「きれい……」
感動とともに漏れるのは、相変わらずありふれた言葉だけれど。
ただの氷の塊をこんなふうに変身させてしまうなんて、やっぱり魔法使いだ。
*
「こんなところに置いといたら、すぐ溶けちゃうじゃん……」
バルコニーの片隅で新聞紙の上に置かれ、直射日光を浴びている氷彫刻を見て、アカネは残念そうに肩を落とした。
昨日また雪が降ったので、早朝にはまだ少し溶け残っていたのだけれど、幸か不幸か、今日は雲ひとつない真っ青な晴天。気温こそ低めだが、太陽は元気に顔を出し、積雪はみるみるうちに路上から姿を消している。
このぶんだと間違いなく、氷彫刻も短命だろう。
「しばらく冷凍庫に入れておけばいいのに」
彫刻のそばにしゃがんでスマホのカメラを向けながら、往生際悪く言う彼女に、
「溶けるまでが作品なの。見るべき人に見てもらったんだから、この彫刻の役目はもう終わりだよ」
そう言い聞かせると、ようやく諦めたのか、「やだなぁ。芸術家ぶっちゃって」と呆れ気味に言いながら立ち上がる。
そして、隣にいる俺を振り返り、
「でも、氷ひとつでこんなの作っちゃうなんて、本当にすごいね。名前ともつながりがあるし、ぴったりじゃんっ」
なんて無邪気に笑った。
その笑顔が眩しくて、
「あー……」
なんだか嘘をついているような気分になって、
「正確に言えば、逆かな」
訂正する。
――それに、この彫刻に秘めた想いにも、気づいてほしくて。
「この名前を好きになるために、氷をいじり始めた」
続けると、彼女が小さく息を呑んだのが分かった。
なんとなく好きなもの、嫌いなものは、ささいなきっかけでひっくり返る場合がある。
逆に、本当に心からそう感じているものは、後からどんな理由が加わったとしても覆らない。
だから、どんな物事も第一印象で決め込まないで、いろんな角度から見て、触れてみるといい。
そうすれば、後悔しないし、傷つくことも減るから。
昔、誰よりも俺の可能性を信じてくれた人が言っていた言葉。
当時は、なんか説教くさいな、と鼻で嗤っていたけれど、今ならほんの少しだけ分かる。
アカネの考えとも、相反するようで通じている部分がある気がする。
――君が自分の名前を、好きになってくれますように。
「どう? 金魚も悪くないだろ?」
勝算を持って問いかければ、彼女は淡く頬を染めて、花がほころぶようにふわりと微笑み、俯き加減でうなずいた。
「――うん」
あぁ、ずるい。やっぱたまんない。
1
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説


【完結】カワイイ子猫のつくり方
龍野ゆうき
青春
子猫を助けようとして樹から落下。それだけでも災難なのに、あれ?気が付いたら私…猫になってる!?そんな自分(猫)に手を差し伸べてくれたのは天敵のアイツだった。
無愛想毒舌眼鏡男と獣化主人公の間に生まれる恋?ちょっぴりファンタジーなラブコメ。

シン・おてんばプロレスの女神たち ~衝撃のO1クライマックス開幕~
ちひろ
青春
おてんばプロレスにゆかりのOGらが大集結。謎の覆面レスラーも加わって、宇宙で一番強い女を決めるべく、天下分け目の一戦が始まった。青春派プロレスノベル『おてんばプロレスの女神たち』の決定版。
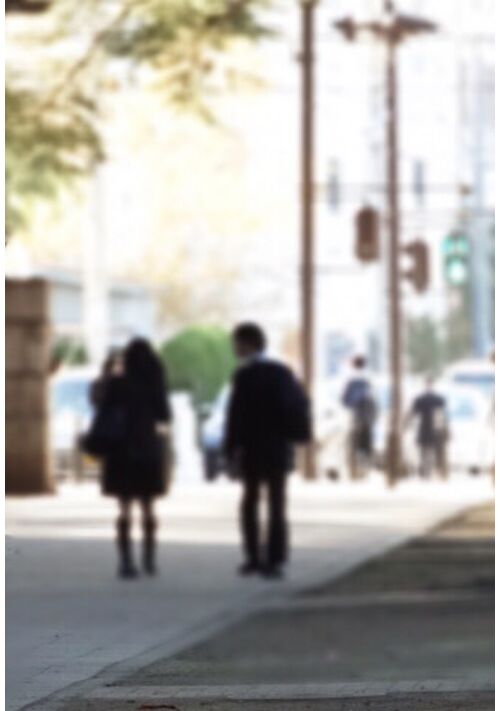
【完結】君への祈りが届くとき
remo
青春
私は秘密を抱えている。
深夜1時43分。震えるスマートフォンの相手は、ふいに姿を消した学校の有名人。
彼の声は私の心臓を鷲掴みにする。
ただ愛しい。あなたがそこにいてくれるだけで。
あなたの思う電話の相手が、私ではないとしても。
彼を想うと、胸の奥がヒリヒリする。

私の隣は、心が見えない男の子
舟渡あさひ
青春
人の心を五感で感じ取れる少女、人見一透。
隣の席の男子は九十九くん。一透は彼の心が上手く読み取れない。
二人はこの春から、同じクラスの高校生。
一透は九十九くんの心の様子が気になって、彼の観察を始めることにしました。
きっと彼が、私の求める答えを持っている。そう信じて。

おれは農家の跡取りだ! 〜一度は捨てた夢だけど、新しい仲間とつかんでみせる〜
藍条森也
青春
藤岡耕一はしがない稲作農家の息子。代々伝えられてきた田んぼを継ぐつもりの耕一だったが、日本農業全体の衰退を理由に親に反対される。農業を継ぐことを諦めた耕一は『勝ち組人生』を送るべく、県下きっての進学校、若竹学園に入学。しかし、そこで校内ナンバー1珍獣の異名をもつSEED部部長・森崎陽芽と出会ったことで人生は一変する。
森崎陽芽は『世界中の貧しい人々に冨と希望を与える』ため、SEEDシステム――食料・エネルギー・イベント同時作を考案していた。農地に太陽電池を設置することで食料とエネルギーを同時に生産し、収入を増加させる。太陽電池のコストの高さを解消するために定期的にイベントを開催、入場料で設置代を賄うことで安価に提供できるようにするというシステムだった。その実証試験のために稲作農家である耕一の協力を求めたのだ。
必要な設備を購入するだけの資金がないことを理由に最初は断った耕一だが、SEEDシステムの発案者である雪森弥生の説得を受け、親に相談。親の答えはまさかの『やってみろ』。
その言葉に実家の危機――このまま何もせずにいれば破産するしかない――を知った耕一は起死回生のゴールを決めるべく、SEEDシステムの実証に邁進することになる。目指すはSEEDシステムを活用した夏祭り。実際に稼いでみせることでSEEDシステムの有用性を実証するのだ!
真性オタク男の金子雄二をイベント担当として新部員に迎えたところ、『男は邪魔だ!』との理由で耕一はメイドさんとして接客係を担当する羽目に。実家の危機を救うべく決死の覚悟で挑む耕一だが、そうたやすく男の娘になれるはずもなく悪戦苦闘。劇団の娘鈴沢鈴果を講師役として迎えることでどうにか様になっていく。
人手不足から夏祭りの準備は難航し、開催も危ぶまれる。そのとき、耕一たちの必死の姿に心を動かされた地元の仲間や同級生たちが駆けつける。みんなの協力の下、夏祭りは無事、開催される。祭りは大盛況のうちに終り、耕一は晴れて田んぼの跡継ぎとして認められる。
――SEEDシステムがおれの人生を救ってくれた。
そのことを実感する耕一。だったら、
――おれと同じように希望を失っている世界中の人たちだって救えるはずだ!
その思いを胸に耕一は『世界を救う』夢を見るのだった。
※『ノベリズム』から移転(旧題·SEED部が世界を救う!(by 森崎陽芽) 馬鹿なことをと思っていたけどやれる気になってきた(by 藤岡耕一))。
毎日更新。7月中に完結。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















