101 / 124
見られたくない触れさせたくない
しおりを挟む「えっと……?」
「肩の傷、見せろだって」
「あ、はい」
襟ぐりのボタンをひとつずつ、ぷつんぷつんと下まで外していく。チャイナブラウスを脱いで肌着一枚になる為、上着の前を開こうとした手がピタリと停止する。真後ろに立っている岡崎さんを黙って見上げる。きょとんとした顔をしている岡崎さんは「なんだよ」と言って疑問符を頭上に浮かべているが、色々と察してほしい。
私の正面に座っている、ちいちゃな丸眼鏡をかけ、少々お腹が出ている白衣の男性は、ほくほくと笑いながら、何かを岡崎さんに伝えると彼は、あ、という顔をし、頬を染めて、灰色の髪をわしゃわしゃとかきながらカーテンの向こう側へと引っ込んでいった。その姿を見届けて、やっとブラウスを脱ぎ、患部をお医者様に見せることが出来た。
肩の傷の具合を診てもらおうと、岡崎さんに街中にある病院に連れられてきた。街外れにひっそりと建てられた、人気のない、こじんまりとした病院。まだお昼間で、あんなにも晴れていたのに、この建物の近辺のみ、どんよりと暗く、雨も降りそうな位に空は曇っている。カァカァと烏の鳴き声まで聞こえてきた。なんだろう、富●急の戦●迷宮を縮小させたかの様な。本当に患者さんは訪れているのだろうかと不安になる。
「だ、大丈夫だって。ちょっと雰囲気アレだけど、ちゃんとイワンにも調べさせといたから。まともではねぇけど腕は確かのとこだから。人体改造とかはされねぇから。コ●ラみたいな腕に生まれ変わったりしねぇから」
寂れた雰囲気がとてつもない建物を前にして、岡崎さんは口をひきつらせ、慌ててフォローしてきたが、もはやまともではないって時点でやばくないだろうか。
まぁ、いっかぁ。寂れているだけで、お化け屋敷みたいに骨が落ちていたり、壁に血がこびりついてるとかはなさそうだし。思わずウッとなる状況でも、すんなりと享受出来るようになったのは、人生の経験値が上がっている証拠と考えて良い筈だとプラスに捉えることにした。
中では、電気の切れかかった白い蛍光灯がチカチカと点滅を繰り返していた。小さい頃はよく病院にお世話になっていた私には、いつも患者さんや看護師さん、医療事務の方で込み合っているイメージのある受付や待合室に、ひとりとして誰も居ないことに対し、不気味さよりも先に、伽藍とした光景への新鮮さが勝った。廃墟と大差ない、むしろ、そのものである病院には、確かにたった一人だけお医者様が居た。
「你好」
診察室に入ると、挨拶をされ、急いでぺこりと頭を下げる。患者さん用の椅子に腰掛ける様にジェスチャーをされ、もう一度一礼してから腰掛ける。
よかった。普通のひとに見える。てっきりこの病院の雰囲気に似合った、顔色は悪くマスクをして常に点滴を引っ張って歩いている、患者さんよりも患者さんらしいひとがいらっしゃるのかと思えば、目の前に座るのは人当たりの良さそうな笑みを浮かべる、穏やかな空気を纏ったお医者様だった。館長さんと少し雰囲気が似ているかもしれない。
中国語がわからない私に代わって、岡崎さんがペラペラと流暢に、たぶん私の身体の事情をお話しているのを見ると、勉強は苦手とは言っていたものの、やっぱりこのひと、かなり地頭が良いと思わずにいられない。イワンさんとも、ロシア語を駆使して難しそうな会話をしていたし、今だって、恐らく何らかの医療用語も多少は入り交じる、ビジネス会話の域をも出る話を詰まることなくスムーズに続けている。
そもそも、日本よりも中国で過ごした歴の方が恐らく長い岡崎さんにとっては、日本語の方が外国語なのか? バイリンガルというやつなのか。いや、ロシア語も話していたし、トリリンガル? でも岡崎さんなら、実は他の国の言語も話せそう。
自分のことを冗談交じりにハイスペックとおちゃらけて言っているけど、間違いじゃない気がする。(黙ってキリッとしていれば)
顔はいい方だとは思うし、人当たりも良いから、誰からも親しみを持たれやすい。事実、病院に来るまでの道のりで、何度も色んな人から親しげに話し掛けられていた。その中には、明らかに岡崎さんに特別な好意を持っているだろう女性達の存在もあった。
ご飯も掃除も洗濯も、全部そつなくこなせちゃうし、基本的になんでも出来るし、たまに意地悪だけど、なんだかんだ優しいし、頼り甲斐はあるし、そりゃあモテるよなぁと、急にそんなひとのそばに居る自分が、とてつもなく恥ずかしくなる。本当に私なんかが、このひとの隣に居ていいものなのかと。
なんてことを悶々と頭のなかで考えていると、私の代わりにお医者様の話を聞いてくれている岡崎さんの慌てふためく声にハッとする。私の右隣に立っているひとを見上げると、何かお医者様にからかわれでもしたのか、にこにことしているお医者様に、必死に中国語で何事かを伝えている。いいよいいよ、と手を振りながら立ち上がり、薬品棚に向かい、こちらに背を向けてゴソゴソと漁り始めた白衣の男性に、岡崎さんは猛抗議? 言い訳? をしていたが、適当にあしらわれている内に気も抜けていったらしい。しかし、まだ頬を赤く染めたまま眉を寄せて口をパクパクとさせている。魚みたい。ちらりと赤い目が一瞬私を見下ろしたので首を傾げると、灰色の髪をわしわしと乱しながらプイと顔を背けられた。な、なんだってんだ。
何か入った茶色の紙袋を手に、戻ってきたお医者様が、私に何かを伝えながら、それを渡してきた。はてなマークをあちこちに飛ばしながら、とりあえず「しぇ、谢谢?」とお礼を言う。にっこりと糸目を見せて笑ったお医者様は、岡崎さんにあれこれと説明口調で話をして、それから私の左足を指差した。一言、診せてくれないかと言われた気がした。
立ち上がり、スカートを少し捲って、するするとタイツを下に引っ張って脱ぐとき、素っ頓狂な声を上げた岡崎さんは勢いよく後ろを向いていた。ゼェハァと肩で息をしている岡崎さんに対し、何故か私の方が冷静だった。別に、脚ぐらいなら気にしないのに。下にスパッツ履いてるから、パンツも見えないし。香澄ちゃんの件のときもそうだったけど、女性遊びに長けている割には、時折変に初心っぽいのはどうしてなんだ。
晒した左足には傷痕や痣は残っておらず、一見どこも悪くなさそうに見えるが、問題は内部の損傷だった。太刀川さんから、まともに歩ける様になると思うなと言われた通りの結果だった。応急処置は施されたものの、その後に適切な治療は行われることはなかった為に、ずっと歩行に支障を来している。
左足に痛みが走らない様、お医者様はあちこちの角度から触れてみたり、観察したり、少し動かしてみたりと、ふぅむと顎に手を当てて考えている。
もう履いてもいいよとジェスチャーで示され、ごそごそと身を整えると、お医者様は岡崎さんのことを聞き慣れない名前で呼ぶ。ちら、と顔だけ少し振り返った岡崎さんは、私がちゃんとしているのを見て、ほっとした表情で向かい合わせになった。
ペラペラと流暢な中国語が部屋に流れていく。その滑らかさとは裏腹に、岡崎さんの表情は複雑に、どんどんと陰っていく。どうする? といった風に、こてんと首を傾げて、何か尋ねているお医者様を相手に、岡崎さんはすぐの返事をしない。躊躇している風にも見えた。
暫し続いた沈黙の末、岡崎さんは荒々しく灰色の頭をぐしゃぐしゃにし、首を振って、簡潔に一言だけ答える。その返答に、お医者様は緩く笑んで小さく頷くのみだった。
「行くぞ、志紀」
荷物を持ち、私の両手を取って、ゆっくりと立ち上がらせた岡崎さんは、私のことを診てくれた先生に声を掛けてから、先に診察室に背を向ける。私も、その後をついていくために頭を下げる。
顔を上げた拍子に、室内の右奥にあるカーテンで囲われたベッドが目についた。ベッド横にある少し開いた窓から入り込んだ風で、ずれたカーテンの隙間から、ベッドに横たわる誰かの足が見えた。私達以外に患者さんが居たのかと、何となくそこから目が離せないでいた。
しかし、私の視界に人の良さそうな笑みを浮かべた恰幅の良いお医者様が入り込む。奥にあるベッドに、これ以上目を向けさせない様にしようという意思が伝わってくる。お医者様はちょいちょいと私の後ろを指差し、岡崎さんが待っているよということを示した。
「喘息の方は呼吸音も綺麗で調子良いってよ。順調に回復に繋がってるって」
「そうですか」
「肩の方は、まだちょっとな。ぶんぶん前みたいに動かせる様になっても、あんまり重いもんだとかは持たねぇように、だってよ」
診察を終えて、人気のない病院内の手すりを持ちながら、私のゆっくりな歩行ペースに岡崎さんが合わせてくれている。ここに来たときと同じようにおんぶをすると言ってはくれたのだが、近頃の体力低下がどうも気になり、自分で歩きたいと伝えると、岡崎さんは無理はするなよと言って私の意思を尊重してくれた。のだが、予想以上に足が重く、且つペースがあんまりにも遅い。すたすたと先を歩くイメージが強い岡崎さんにとっては、この鈍重さは煩わしいだろうし、顔に出さないにしろ、苛々もしてるかもしれない。岡崎さんのことを考えて、お言葉に甘えておけば良かったかもしれない。
「ただ、痕は残るかもしんねぇって」
撃たれた場所の。と続ける岡崎さんの声は萎んでいた。隣を見上げると、岡崎さんは眉を寄せ苦しそうに、申し訳なさそうな顔で前を見ている。何故か私よりも哀愁を漂わせる横顔をしていた。その姿がなんだかとても可哀想に思えて、つんつんと岡崎さんのジャケットを軽くつまんだ。
「岡崎さん」
「ん、んー?」
「何を言われたんですか?」
「え。なにを……って。なにが?」
「さっき、お医者様に何言われたんだろうって。私、お二人が何を話してるのか全然わかんなくて。顔赤くしてたから」
「あっ、あぁ、べっ、べつに。たいしたことじゃねーよ」
「……」
「……」
「なんでちょっとニヤニヤしてんですか」
「しっ、してねーもん! ちょっと、その、お、思い出し笑いしてただけ」
「へぇ。どんなこと思い出してたんですか。思い出して笑っちゃう位のエピソードなんでしょ。教えて下さい」
「だめですー。そういうフリ食らって、いざ話してみると全然笑えないってやつなんですー。口に出しちゃうと意外とたいしたことねぇ話で、ひとに喋るんじゃなかったって後悔することねぇ? 自分ではそんときすげぇ面白かったけど、いざ人に話すとなるとクソつまんねぇって自覚しちゃうやつ」
「わ、わからないでもない」
「だろ? 時とタイミングは大事ってな」
よかった。いつもの調子に戻ってくれた。ののほんとした声色と表情が再び生き返ってくれたことに心の底からほっとする。岡崎さんの悲しんでる顔や辛そうな表情は見たくない。
「そういえば、その、診察料とお薬代とかって」
「あーあー、もう払っといたから、大丈夫大丈夫」
「そうじゃなくて、私、お金とか、工面できなくて……」
「んだよ。気にすることねぇって言ってんのに。たいしたことねぇよ。某凄腕の闇医者みたいに、とんでもねぇ価格ぼってきたりしてくる訳じゃねぇし」
「生活費まで全部、岡崎さんには甘えっぱなしなのに」
「甘えりゃいいじゃん」
「……」
「いーんだよ。俺がやりたくてやってんだから。寧ろ、俺がお前に付き合わせてんだ。これ位して然りだろ」
この話はもうこれで終わり、と私が気にしない様に、岡崎さんが自身の大きな手でぽんぽんと私の頭を撫でた。付き合わせてる、だなんて。そんなことないですよ、と口に出しそうになった唇を噛む。それを言ってしまったら、私の記憶のなかに眠るあの男性が怒り狂うに違いないと思い留まらせた。
「志紀。まだ歩けるか。もうしんどい? 家戻りたい?」
「えっ。あ、だ、大丈夫です。まだ全然」
「そか。なら散歩がてら、買い物して帰ろうや。久しぶりに外出てきたんだし、家籠ってばっかじゃな。お前、中国初めてなんだろ。ちょっとはそれらしい景色も見て周りたいだろ」
言われてみれば、そうだった。ここが上海なんだなとはっきりと明確にわかる景色を見たのは、この国に連れられてきた初日の船からの夜景位だったかもしれない。
そのときのことを思い出して、ぼんやりとしていると、ごく自然な動作で右手全部が暖かいものに包まれ、軽く前に引かれる。自然と歩き出した足は、私の手を繋いだひとの少し後ろをついていく。
「冷蔵庫」
「は、はい」
「もう何が無かったっけ。何がもう切れそうだっけ」
「ええっと、卵がもうあと二個しかなかった気が。あと、牛乳がそろそろ一人分くらいしか残ってなかったです」
「あー、そうだったそうだった。お前、今日の夜、何食いたい気分?」
「お魚食べたいです」
「ありだな。刺身も食いてぇわ。焼いて食う用と合わせて買っとくか」
返事をしながら、横目で隣を歩く岡崎さんを見上げる。灰色の髪にかかり、ちらちらと見える耳がちょっとだけピンク色になっていた。私の手を握る手は、いつもより体温が高く、強い。握り返す勇気までは持てなかったけれど、頬が熱くなるのは誤魔化しきれなかった。
観光地なのだろう、古い中国の歴史の趣がある、赤を貴重とした古風の建物が立ち並ぶ歓楽街は、多くの人で賑わい活気がある。岡崎さんに手を引かれ、慣れた様子でスムーズに人の波を潜り抜ける岡崎さんに大人しくついていく。あちこちに目を向け、珍しい風景に内心興奮する。急に自分が異国に居るのだという強い実感が沸いてくる。
日本ではない国の土地を踏むことは不安もあるけれど、初めてだらけの景色を見るこの新鮮な感覚は非常に好ましい。何よりも、これ以上の頼りになるひとは居ないだろう灰色の髪の案内役の方が、あそこはああで此処はこういう場所で、と逐一細かい説明を入れてくれるから、私の好奇心も昂り、質問も多くなる。ツアーガイドとか向いてるんじゃないですか? なんて冗談を言って、いつもより比較的、積極的にお喋りをする私に、岡崎さんは嬉しそうにしていた。
それにしてもだ。買い物途中、レジに立っていたお店のおじさんおばさんに話し掛けられた岡崎さんが、ベラベラと気軽に話をする光景には圧倒される。最初はあまりにも大きな声で呼び掛けられたものだから、何かこちらが不手際を起こしてお店のひとを怒らせてしまったのだろうかと焦ったのだが、そうではないらしい。このお店のひととは顔見知りなのか、おじさんとおばさんは、私たちの後ろでレジ待ちをしている人達がそこそこに並んでいるのにも構わず、ばしばしと岡崎さんの身体を叩きながら豪快に笑って会話を楽しんでいる。岡崎さんも相手に合わせ、お医者様と話していたときとの穏やかさとは違い、少し荒々しい中国語で対話していた。私はというと、後ろに並ぶお客さんが苛々とし始めた雰囲気を感じ取ってヒヤヒヤしていたのだけれど、その派手な髪色で誰なのか分かった途端に、そのお客さん達までもが「なんだ、お前だったのか!」という風に、岡崎さんに親しげに近寄り、次々と話し掛けてくる。
あっという間に数名に囲まれてしまった岡崎さんの姿に、ほんとすごいな、このひと、と心中で感想を漏らす。
この国の言葉は圧倒的だ。アクセントが強い為に、私みたいに、彼らの言語を聞き慣れていない人間には、普通に話し掛けられているのか、それとも怒られているのかの違いが分からずに、ただ圧倒されてしまう。それに負けず劣らず、強いアクセントで言い返す岡崎さんの姿には、やはりポカンとさせられる。あの会話に放り込まれても、絶対に勝てる気がしない。
特にトラブルも起こることなく、お会計を無事に済ませた。全部の買い物袋を持ってくれる岡崎さんに、私も持ちますと申し出るも、「重いもんはあんま持つなって言ったトコでしょうがよ」と断られてしまう。右手ひとつで荷物を軽々と持ってしまう岡崎さんの怪力ぶりにはおお……と拍手を送りたくなるし、左手は必ず私の手を捕まえにくるところで、赤くなっているだろう顔を隠したくなる。
「なんか、岡崎さんがどんな相手にも負けることも怯むことなく、どこまでも我を見せたお喋りが出来るその起源を発見した気がします」
「なにそれ。厚かましいって言われてる? 俺」
「まさか! 誉めてるんですよ。私には、あんな風に強くものを言うことって中々難しいから」
「この国じゃあ、主張激しめにいかねーと相手には伝わらねぇよ。どの国でも言えることだけど、あんまり遠慮ばっかしてたら、お前みたいなのはナメられるし、食い物にされちまうぞ」
「うーん……」
「まぁ、日本は空気を読むってことに長けてるから、確かに感覚的には難しいのかもな。お前なんか特に。けど、まぁ、それが日本独特の美徳ではあるんだよ。謙虚、慎ましさとかさ。それもそれで嫌いじゃねぇよ」
皆違って皆良いってやつ? と色んな国からやってきた多国籍の観光客で賑わう街の一角の名所である古庭園を見つめながら言う岡崎さんに、人々が惹き付けられるのは、こういうところなんだろうなと思う。差別を一番に受けてきたひとだろうに、それはそういうものだときちんと受け止められる。
良いところも悪いところも踏まえた上で、相手に真正面から接する。ひとと関わり合いを持つ上で大事なもの。わかってはいるけれど、身に付けるのは凄まじく難しい。それらを兼ね備えているからこそ、私を含めて皆、岡崎さんとの会話が心地いいと思うのだろう。
あ、と声を上げた岡崎さんが、右手に持った荷物の中身を軽く確認する。
「どうしました?」
「あのオッサンに渡すもんがあるの忘れてた。やらかしたな」
「あれ。じゃあ戻ります?」
「いや、俺ひとりで十分。ひとっ走りで速攻戻ってくっから。ええっと」
近くにあった喫茶店に、こっちだと手を引かれ、中に入る。ムードのある中華風の曲が流れ、落ちついた雰囲気の店内は、そこそこ人が入っている。お茶の葉の良い香りが漂っていた。ここの店主さんとも知り合いらしく、丁度お茶を淹れている最中だった男性が、入店してきた岡崎さんに気軽に声をかけている。よぉと岡崎さんは手を上げ、カウンターに近づき、口髭を生やしたその男性と軽い話をする。ここの店主な、と紹介を受け、軽く礼をされたので、こちらも頭を下げる。
「ここの茶、美味いから。飲みながら待ってろ」
「わかりました」
「ん。じゃあ、ささっと行ってくるわ」
店主さんに持っていた荷物を全部預け、走り去っていく岡崎さんの背中を見送る。別に、そんなに慌てなくても大丈夫なのに。
お店のウィンドウから遠くなっていく岡崎さんの後ろ姿をぼうっと見ていた私に、中国語が振りかかる。話しかけてきた人物の方を見ると、お茶のお道具とお菓子を乗せたお盆を手に、私に何かを伝えている。え、ど、どうしよう。な、なんて言ってるんだろう。
あの、その、と日本語で受け答えして、あたふたしている私に、店主さんはこっちだと、店内からのみ出られるお庭の方を指した。
大人しく、ひょこひょこついていくと、外の風景が開けて綺麗に見えるテラス席に通してくれた。誰も居らず、おそらく一番の席なのだろうことが、此処から見える景色でよくわかる。落ち着いた緑と御池のある庭の真ん中に佇む椅子に座るように促され、言う通りに腰掛ける。
茶壺にお湯を注いで、茶葉も投入してと、日本の茶道とはまた違う、あまり見慣れない作法が目の前で行われる。数ある手順を踏まえて、薄く透き通った色をしたお茶が茶杯に注がれ、差し出される。あとは一人で楽しんでと、ひらひらと小さく手を振って、店主さんは中へ戻っていった。
ほわほわと湯気の上がる茶杯を、両手で掬う様にして手に取る。熱すぎず、手に持ってもアチチとならない。ふう、とひとつ息を吹いて、湯気を逃がす。そっと唇を付けて、暖かい液体を喉奥へと流し込む。ほんのりといい香りがして、味もあっさりとして飲みやすい。岡崎さんの言っていた通り、美味しい茉莉花茶だった。
こくこくとお茶を飲みながら、観光客で賑わい喧騒に溢れた景色をぼんやりと眺める。穏やかで静かで、時間の経過をゆっくりに感じながら、古風な景観をお茶を飲んで楽しむ。
歴史の趣がある建物や空気のその向こうには、天高く聳えるオフィスタワーの数々。ひとつの世界に、ふたつの異なる街と都市がある様なちぐはぐさ。
過去と現在が融合しているみたいだ。そう考えると、色々と自分にも思うところが出て来て、ぐるぐると考えて込んでしまう。慌てて頭を振り、お茶を一口飲んで気を落ち着かせ、店主さんが出してくれた、まんまるな月餅を口にした。平和な時間だなぁ。
15分くらい経っただろうか。もぐもぐと最後のひとくちの月餅も飲み込み、餡子でいっぱいになった口のなかを潤したいと、三杯目のお茶を注ぎ、手にとって口をつけようとした。そのときだった。
どこからか強い視線を感じ、顔を上げる。そして、双眼とはっきりと目が合った。
人混みが溢れる歩行者天国。道行く人が縦横無尽に散り散りになる有象無象の人の海の中だというのに、その色はとても印象的だった。青と赤を混ぜ混むことで完成する、その色は確かに私のことを捕らえている。何故だか目が離せないし、反らせもしない。手にした茶杯が口許に運ばれることもなかった。
交差点の向こう側に居るその男性は、お世辞にも整っているとは言い難い、使い古したぼろぼろのくたびれた鼠色のロングコートを羽織っている。ピンのついた緑色のネクタイも曲がってしまっている。ブラウンの革靴も、どこか砂場を歩いてきたのか埃っぽく、白くなっている。男性の傍らには、今にも千切れそうなベルトを巻き、あちこち擦り傷のついた大きく真っ黒な旅行用のスーツケースがあった。
あちこちにぴょこぴょこ跳ねて、輝きの無いくすんだブロンドの髪の毛もとかされておらず、寝癖をそのままに家を出てきた様だ。身なりに頓着が無い人なのかなとは思うのだが、それでも着こなしがお洒落に見えるのは、その顔立ちと背丈のお陰だろうか。決して目を見張るほど整った顔ではないけれど、白人男性で鼻筋は高く、掘りもあり、はっきりした顔立ちをしている。
こちらを見て、ぽかんと、どこか気の抜けた様な顔をしているけれど、うっすらと開いた口を閉じてあげれば、岡崎さんと同じタイプで、中々にシュッとして見えるタイプなのではないだろうか。背も、灰色頭の彼より僅かの差で小さいけれど、十分にある。
中国に旅行に来られたのかな、と、何故だか惚けた顔をして、こちらを人混みの中から一心に見つめてくる男性に、こてりと首をかしげ、とりあえず軽く会釈をしておいた。
すると男性は、突然ハッとした顔をして、持っていたスーツケースから手を離してしまい、ビターーンと綺麗に、長方形の箱が大きな音をたてて倒れてしまった。う、うわ。大丈夫かな。
男性は大慌てで自身の周りの歩行者に何度も何度も頭を下げて、大荷物を再び自身の手の中に戻した。彼は、再び上気した頬の顔を勢いよく上げた。かと思えば、ずるずるスーツケースを不安定に引きずり運びながら、足を前へ踏み出した。道行くひとの肩やあちこちぶつかり、時に怒鳴られても、すぐに頭を下げ、それでも足早く、前へ前へと一歩ずつ進む。その行く先は、気のせいでなければ、私へと向かっていた。
少しは足元も見て、人にぶつからないよう周りのひとにも気をつけて、と思わず声をかけたくなるほど、紫の瞳だけは一心に私を見つめている。いや、本当に私を見ているのか? と左右後方を確認するが、彼の視線の先に留まる人間は私しかいない。ということは、一度としてこれまでにお会いしたことの無い筈の彼は、私への接触を図ろうとしているのか。それとも、もしかしたら、このお店に急ぎの用があるのか。どっちだ。
徐々に距離を詰めてくる男性の姿に、焦りが増していく。お店の仕切り柵には高さがあるから入ってはこれないとは思うけれど。しかし、もし話し掛けられたらどうしよう。まさかね。知り合いではないし、と言い聞かせるが、必死な男性の姿にあたふたが止まらない。すっかり冷めてしまった茶杯も、いったんテーブルに置く。
知らないひとと話したらダメ、とお母さんの如く、岡崎さんに口を酸っぱくして言われている。けれど、ど、どうしよう。とにかくお店の中に入ってしまおうと立ち上がり、店内へそそくさと背を向けると「Wait! Please!!」と後ろから丁度いい低さの声で叫んではいるも、きつさは全く感じられない、穏やかな声色の、若干訛りが入った英語が、確実に私に向けて飛んできた気がしてならないが、けれど、とにかく岡崎さんの機嫌も悪くしたくないし、こどもの様な約束でも違えたくないという思いから、勢いをつけて謝意の意味での礼をして、店内へと急いで引っ込んだ。
特等席から戻ってきた私が困った顔をしていたのに店長さんが気づき、中国語で声をかけてくれたのだが、どう答えてよいのかわからず、ひきつった笑みを浮かべるしか出来ない。
店内へと引っ込んだから安全、という訳が無い。バタバタと慌ただしい革靴の音をたて、スーツケースを引き摺りながら入り込んできたのは、先程の男性だった。キョロキョロと息を荒くして辺りを見渡しているその男性の様子に、私を探しているのだと確信が持てた。吃驚して息を殺しながら、まだ少し距離があるので、ゆっくりと後退し、身体を屈ませ、テーブルと椅子の陰に隠れた私に、何かを察したカウンター側に居た店主さんが、ちょいちょいとこっちに来るように手招きしてくれたので、そちらに渡ろうとした。
男性が向こう側を見ている間にハイハイ歩きで店主さんの元へ行こうとしたが、タイミング悪く、それとも彼の方が何かを察知したのか、バッとくしゃくしゃのブロンドを揺らしてこちらを振り向いた。四つん這いでハイハイ歩きをしていたチャイナ服を着た女のどれ程怪しいことか。だというのに、彼はほっとした様に口角を緩ませ、ずんずんと荷物をほっぽり転がして、迫り迫ってくる。なんで? 私何かした? 動揺も相まって、すぐには立ち上がれない足が疎ましい。
あと2mか少しのところで、私の前を何かが塞いだ。見上げると、親切にお茶を淹れてくれた店主さんが、私の姿を隠すように立ってくれていて、中国語できつめに何かを男性に言いいながら、あっちあっちと手を振っている。庇ってくれている。男性も、突然立ち塞がった店主さんに動揺を見せ、しかし、すぐに早口言葉か? という程流暢すぎる英語で、店主さんに何かを訴えている。が、店主さんは英語はわからないらしく、だめだめと片手を顔の前に翳して何度も振った。彼は体を移動させた店主さんの横を通ろうとしたが、窘められ、身体をずらし屈んで、店主さんの後ろでへたりこんでいる私の姿を何とか見ようとするも、それも許さないと店主さんも身体をずらし、私の姿を隠した。
男性が英語で話し、店主さんが中国語で応戦するという、永遠に噛み合うことはない不毛なやりとりが延々と繰り返される。場が煮詰まってきた頃合いに、あのひとはいつも戻ってくる。
「わりーわりー。思ってたより遅くなったわ」
ぽりぽりと灰色の髪をかき混ぜながら戻ってきた男性に、志紀、と名前を呼ばれる。顔を上げると同時に身体が持ち上げられ、視点が高くなる。うわっと色気の欠片も無い声を上げて、思わず目の前の太い首にしがみつく。よしよしと背中を撫でられ、赤い目に至近距離で顔を覗きこまれる。
「良い子で待ってたか?」
「は、はい」
「ん。じゃあ、とっとと帰るか。晩飯の準備も、そろそろ始めねーと。じゃあな、おやっさん。ありがとよ」
私を抱き、置いていた荷物も腕にひっかけながら、ぴっと器用にお金を店主さんに投げ渡した岡崎さんは、お店をあとにしようと入り口へ足を進めるが、その行動を引き留める声があった。
あの紫色の眼をしたお兄さんだ。岡崎さんの腕の中から、少しおどおどした挙動とは裏腹に、強い意思を持った、岡崎さんの力強さとはまた種類の違った真っ直ぐな紫とかちりと目が合う。
「わぷっ」
反らせずにいると、その視界を後ろ頭をひん掴まれ、岡崎さんの鍛え抜かれた胸板に押し付けられる。筋肉におしくらまんじゅうされている為に、なにするんですかと抗議するも、「もが、もがが」とくぐもった声しか出ない。なんとか、ずりずりと面を上げて、もうちょい力を緩めてくれと伝えようと口を開けたが、声が出なくなる。
岡崎さんは私を見てはいない。私達の後ろに居るだろう男性の方を振り返っているので、こちらからは岡崎さんの首から横顔しか見えない。
それでも、すぐ上にある左目の赤は強烈だった。私の方を見ていないのに、激烈に燃え上がるその色は、熱さは感じず、むしろ冷えきっている。締まりはなく、にこりともしない岡崎さんの表情はいつも通りだけれど、興醒めた様な、初めて見る顔だった。目の前に居る獲物を狩りとらんとすることを悟られぬようにと牙を潜めた獣。そして、その獲物こそ、先程の優しく穏やかな紫の瞳を持つ男性なのだと察する。可哀想に、私からは何も見えないけれど、男性の戸惑いの声と雰囲気がこちらまで伝わってくる。
ちがう、なにもされてない。なにもされてないから。なんとか手を伸ばし、岡崎さんの右頬に手を添えて、こちらを見下ろさせる。意外にもすんなりと私の方を見てくれた岡崎さんは、私の好きな優しい赤色の目を向けてくれた。すり、と気持ち良さそうに私の手に頬を押し付けて、ん? と問うてくるその姿は、まさに大きな犬。先程の獣はどこへやら。大きな耳と、ぱたぱたと揺れる尻尾が見えた気がした。
かえりましょう、と口パクで伝えると、きちんと読み取ってくれた。すたすたとお店の入り口まで進めたところで、岡崎さんが一度立ち止まる。後ろを振り返らないままに、中国語で力強く、先程の男性に向けて何かを伝えた。それに対し、男性は、か細く、けれど必死に英語で訴えてきたけれど、岡崎さんは振り返ることも、返事もせず、お店を出る。岡崎さんの腕のなかから一瞬だけ、深いような浅いような独特な色味をした紫色と目があったけれど、その瞬間、彼は息を呑んだ様な表情をして、固く口を結んでいた。
「お前ってホンッット変なやつ……特に野郎にばっか引っかかるな。30分ちょーっと目ェ離してただけでアレだもんなぁ。マジで油断も糞もねーよ。やっぱり、どこでも俺がついてなきゃ駄目だな。今度はちゃんと連れてくわ。もう一寸も俺から離れるでないぞ」
「はぁ」
「はぁ、じゃねぇよ。ちゃんとわかってんの、お前」
「わかってます、わかってます。ちゃんとお側についてますから、ポ……岡崎さん」
「ポ? なに? なんて言いかけた? まさかポチとか言おうとした? ト●ロスタイルにすんぞ。四六時中俺の身体に張り付いててもらうぞ、お前」
「えぇ~」
「えぇ~じゃないの」
「私の物真似ですか、それ。全然似てませんよ」
「うっせ。これからクオリティ上げてくんだよ。お前も、もうちっと女っぽくクネクネしてみろよ。一応主人公なんだから、個性上げてこい」
「上げなくていいんです。私、無個性が特徴みたいなもんですから」
「それ、自分で言ってて虚しくならない?」
「もう慣れました」
「でも、ちゃんと逃げようとはしてたな。えらいえらい。そこは成長だな。いつぞやのおっさんのときみたいに、ホイホイふれ合うなんざ真似しでかしてたら、ものすげぇお仕置きしてやろうと思ってたけど」
「お、お仕置きて。そこまで変なひとには見えませんでしたけどね。不思議な雰囲気な方ではありましたけど」
「それが隙っていうんですー! 見たことも口も効いたことのねぇ人間、第一印象で判断すんな。初めて会ったやつ、接触しにきたやつ、全員敵だ位の警戒心持っとけ、お前は。ただでさえつけこまれやすいんだから。そんなんじゃあキャッチとか押し売りにもホイホイつかまっちまうぞ」
「……なんか、イライラしてます?」
「してませんけど」
「えぇ~ほんとにござるか~?」
「ほんとにござる~」
「……とにかくも、岡崎さん」
「なに」
「いつまで玉葱のみじん切りしててるんですか?」
「……あっ!」
「どうするんですか、その量。というか、そんだけ切ってて、よく涙のひとつも出ませんね。すごいですね」
「どっかの誰かさんのダム涙腺と違って、俺の涙腺は枯渇してるからな」
「自信満々に言えることですか」
あーあーと言いながら、山盛りになった玉葱を籠に移す岡崎さんを横目で見ながら、人参の皮をするすると剥いていく。
やっぱり、イライラしてる。顔には出さなくても、岡崎さんの行動はとてもわかりやすい。苛立つ気を落ち着かせようと、無心になって作業を続ける岡崎さんは大抵イライラしてることが殆どだ。
器用というのは大変だ。何ともないよという風に振る舞うのが得意になってしまうと、昂った感情は行きどころを喪ってしまい、自身の中に押し込まれてしまう。
岡崎さんは基本的にちゃらんぽらんではあるし、喜怒哀楽もはっきりしている方だとは思うけれど、本心をさらけ出すのは、たぶん苦手な人だ。さて、今回のイライラは何が原因だろうと考えてみるも、思い当たるのが先程の男性イベント位しかなかった。
「なに? ひとの顔じっと見て。て、照れるんだけど」
「いえ、別に」
「俺の顔面が良すぎて見惚れてた? 惚れ直した?」
「惚れ直し……って」
「どうなの」
至近距離にずいと顔を近づけ、意地悪な笑顔で覗きこんでくる岡崎さんの顔をちらりと横目で見て、すぐに手元の人参に顔を反らす。
顔は、いいんだよなぁ。本当に。黙ってれば、なんてよく言ったけれど、そうでもない。そりゃあ、絶世の美しさなんて、ベタな言葉が似合う太刀川さんや、可憐でとにかく可愛いの代名詞である香澄ちゃん、その他顔がいい勢を比較対象に持ってきてはダメだけれど(彼らが別格過ぎる)、岡崎さんには岡崎さんらしい良さがある。
とにかく、自惚れたことを言うなという反撃の言葉は全くの無意味なので、近くにあったミカンの皮をつまんで、岡崎さんにその刺激をお見舞いしたあげた。クリティカルヒットを食らった岡崎さんは「うをぁああなにすんのぉおおぐぁああ」と両目を抑え、ごろごろごろごろと床を左右に転がり始めた。面白い。
こうしてキッチンに並んで立つのも、やっと当たり前になってきたなぁ。ちょっと前は、私がしんどいところを見せると、すぐに、俺に任せて座ってろなんてきつく言われたものだけど、徐々にずっと立っていられる様になってからは、こうして一緒にごはんの支度をするのが通例になっていった。
「前々から思ってたんだけどさぁ。お前、なんか料理の腕上がってね?」
「え?」
「いや、前は拙い手つきで、見るからに慣れてなかったというか。今まで親とかに作ってもらってたんだろうな~って感じだったじゃん。なんなら、俺が料理教えてやってたじゃん?」
「あぁ、そういえば」
「それが、何よ。悔しいから言ってやらなかったけど、滅茶苦茶手際も良くなったし、味も整ってるし。ブランクがあるにしても、徐々に思い出してるって感じというか。今回も味付けとか、殆ど俺手つけなかったのに、味見したら滅茶苦茶舌に合ったんだけど。なに、毎朝ひと仕事終えて帰ってくる旦那の為に、留守番中に寝る間を惜しんでクッ●パッド見ながら猛練習してた?」
「誰が旦那ですか」
「俺だけど」
「……私も最近、よく思うことがあるんですけどね」
「ん?」
「岡崎さんて、聞いてるこっちの方がこっ恥ずかしくなる冗談、さらっとよく言いますよね」
「馬鹿言え。滅茶苦茶照れてるよ。こう見えても心臓バックンバックンだよ。はち切れそうだよ。めちゃんこ勇気出して発言してるよ、こっちは」
「はぁ」
「……っていうか、冗談じゃねぇし」
「……」
「……」
「それは、まぁ、置いといて」
「え、置いちゃうの。放置しちゃうの」
「教えてもらったんです」
「スルースキル高過ぎだろ。教えてもらったって、なに。唐突なんだけど」
「料理。太刀川さんのところに居たときに」
「……へぇ~~。ふ~~ん」
「うわ、すごいジト目」
「刺青野郎に、花嫁修行に励めとか言われたの? しごかれたの?」
「いえ、自主的にお手伝いで。太刀川さんは寧ろ、私にああしろこうしろとかは全然言ってこなくて、基本的には私の好きにさせてました」
「あっそ」
「今の岡崎さんみたいに」
そう言うと、岡崎さんはかなり眉間に皺を寄せて顔を歪め、複雑そうな表情でお味噌汁を啜った。生まれてしまった沈黙に、不味いことを言ってしまったかと失言を後悔しながら、お漬物をお箸でつまみ、口に運んでもぐもぐと咀嚼する。飲みこんでから、今言ったことは忘れてください、気にしないで、と言おうと顔を上げたら、味噌汁を啜りながらジッとこっちを見ている岡崎さんに、思わず喉をならす。
「な、なんですか。ご飯粒ついてます?」
「いんや」
一気にお味噌汁をぐいと飲み干した岡崎さんは、空になったお皿を綺麗に積み重ね、洗い場に置いた。腕捲りをし、お皿を洗うのかと思いきや、台に両手をつき、はぁ~~と項垂れた。腕の筋肉に筋が浮かび上がっている。そして、ぽつりと岡崎さんが呟いた独り言を、ライトノベルの主人公の様に聞き逃すことはなかった。
「ちょっと前は、乳臭いガキんちょにしか見えなかったってのに、女の成長ってのは恐ろしいわ」
「誉められてます? 私」
「良い意味でも、悪い意味でもな」
「?」
「お前、これから、今日会った男みてぇに、知らねぇ奴に話しかけられても無視決め込めよ。マジで。ナンパとか」
「そんな、居ないでしょ。私なんかに。今日のも別に」
「今日の野郎はガチだったろうが」
「……」
「お前はもう、十分、れっきとした女なんだよ。志紀。もう餓鬼とは言えねぇ」
行きずりの野郎を落とす程のな、と頭をわしわしとかき混ぜられる。私のことを子供扱いしていたときの岡崎さんなら、ここで終わっていたが、今は違う。頭を撫でていた手を滑らせ、サイドの髪をかき分け、その甲で私の頬を擽った。それは、太刀川さんが私にしていた愛撫の手つきと似ていて、顔が熱くなる。まさか、岡崎さんにそんな触れ方をされるなんて思いもしなかったから。
顔を熱く、真っ赤にさせ、俯いた私のほっぺをむにむにと優しく摘まんだり撫でたり、時に蒸発寸前の耳を擽ったり、ふにふにと耳朶に触れてみたりを繰り返してくる。
岡崎さんがどんな表情で私に触れているのか、想像も、見ることも出来ない。ただただ恥ずかしくて、仕方なくて。
「ふぎゅっ」
「ほら。洗ってやるから残り食っちまえ」
「ふぇ、でも、夜は私が」
鼻をぎゅっと摘ままれ、鼻声で自分の当番だということを伝えるも、岡崎さんは「いいから俺に任せなさいよ。お残しは許しまへんで」と給食のおばちゃんの口調で再び腕捲りをしていた。スポンジに洗剤をつけ、カチャカチャと食器を洗い始めた岡崎さんの言う通り、すぐさま残りのおかずに手をつける。
ご飯も食べ終えて、岡崎さんにお皿洗いを交替すると申し出ても譲ってくれず、仕方なくソファに腰かけてテレビをつけるも、特に面白そうな番組はやっていなかったので、岡崎さんが見たいというものがなければ映画でも見たいなぁと思考を巡らせていると、ぴとりと後ろから冷えたものに両頬に触れられる。
「ひゃあ!」
あまりの冷たさに声を上げると、小さな笑い声と共に、意地悪な笑みを浮かべていたのは岡崎さんだ。冷えてしまった両頬を包みながら、隣にどかりと腰掛けた岡崎さんに抗議の眼差しを向けた。さっきはお湯でお皿洗いしてたくせに、わざわざ冷水使ってイタズラを仕掛けてくる辺り、性根からのいたずらっ子だ。
頻繁にあることだが、少なからずこのやりとりを楽しんでいる自分もいて、その度に太刀川さんにやはり、ごめんなさいごめんなさいと頭のなかで呟くこととなる。罪悪感でいっぱいになった胸中、ガサゴソとなにかを漁る音に隣を見ると、ドラッグストアの袋の中から、小さなケースを岡崎さんが取り出していた。
「なんですか? それ」
「んー。手ェ出して」
「……」
「大丈夫大丈夫。ビリビリとかじゃねぇから。イタズラはもうしねぇから」
ほれ、と右の手の平を差し出されたので、ぽすとこちらの右手を添える。おての様になってしまった図に、岡崎さんは少し顔を赤くして「い、いや。手の平で。これでもいいことはいいんだけど」と言ってきたので、手相を見てもらうみたいに掌を上にする。ケースのふたを器用に片手で開けて、自身の手につけたそれを私のカサカサのものにゆっくりと擦り付けていく。先程冷たかった手は、もう温かくなっていた。
「ハンドクリーム?」
「そ。こういうのって、香りだとか、滅茶苦茶種類あんのな。似たようなのもいっぱいあって、どれがどう違うのかわかんなくて、選ぶの時間かかったわ」
「もしかして、お医者様に忘れ物届ける帰りに」
「最近、お前も水作業始めたから、ひびもあかぎれも、乾燥もしてるだろ。いてぇ癖になんも言わねぇで我慢してるし」
「……」
「肌弱いよな。昔っから。カッサカサに荒れてるイメージしかないわ」
昔っからかぁ。岡崎さんにまでその台詞を言わせるほどの時間が経過したのだと、ぼんやりと考える。この時代に来てから、もう何年経ったんだ。あれほど毎日カレンダーとにらめっこしてたのに。数えるのを止めたのは、いつからだったのか。
岡崎さんの長く太い指が、私の指の間に絡むように入りこんできて、滑らかなクリームがきゅむきゅむと刷り込んでいく。それが、何だか少しだけ。
もう片方の手も、岡崎さん直々にきっちりと隅々まで塗られる。十分に潤いは浸透したのに、握られた手はすぐに離されることはなく、戯れで手を握ったり、軽く撫でてみたり、形を確かめてみたりと岡崎さんに遊ばれる。
何を思ったのか、私も自身の手に触れる岡崎さんの手を撫でてみると、岡崎さんは、私の手と指を絡めて握りこんだ。にぎにぎと強弱をいれると、岡崎さんも同じ力加減で同じことをしてきたので、思わず笑ってしまった。岡崎さんも緩い笑みを浮かべている。もう片方の手も取られ、互いの両手を結ぶ形になる。私がやんわりと手をほどき、岡崎さんの掌と自分のものを合わせる様に動くと、目の前の人も同じようにしてくれた。
合わさった掌が、私たちの性別の違いを顕著に表す。以前よりは大分マシになったものの、皮と骨だけの、ちっぽけな私の手とは違い、ずっしりとした、指の太さも全然違う大きな手。お父さんのものとも全然違う、男のひとの手だった。
「手、ちっさいな」
俺と比べて、まじまじと合わせた手を見つめる岡崎さんの言葉に、かぁと顔が赤くなるのが、上昇した体温でわかった。
私、今、岡崎さんと、男のひとと、好意を寄せている男性と二人で暮らしているのか。その事実が、今さら私を羞恥に追いやる。男女ふたりがひとつ屋根の下で過ごして何も起こらない訳ない、そう香澄ちゃんは言っていたし、私も過去にそれはよく体感している。それは絶対に、岡崎さんだって。
「タコみたいになってんな」
「あんま、見ないでください」
「可愛いからやだ」
「は」
「もっと見せろよ」
「ちょ、ま」
可愛いなんて、今まで生きてきて、面と向かって一度も言われたことのないことを、それも岡崎さんに言われて大きく動揺している内に、岡崎さんの顔が近付いてくる。後ろに引こうとしたけれど、両手首を掴まれ逃げられない。息がかかり、もう少しでくっついてしまう位の距離まで近付いてきた岡崎さんと目が合わせられなくて、言葉にならない。目がぐるぐるになって、あうあうと言葉にならない。
もうなに、なんで、そうか、このひと、こうやって、ちょっと強引に、女のひと口説いてきたのか。あれよあれよという間に、そういう雰囲気にもつれ込んじゃうのか。じゃないと、岡崎さんが可愛いだなんて歯の浮く様なこと言う訳ない。ありえない。幻聴だ。絶対幻聴だ。
こつん、とおでこ同士が当たる。じっと熱い視線が私を貫いているのがわかって、顔をあげられない。
「しき」
「こうやって」
「ん?」
「女のひとからかって、たぶらかして、イチャイチャしてたんですか。キャッキャウフフしてたんですね」
「いーや。これはお前だけ」
「うそつき。そんな、ホストみたいなこと言って」
「嘘じゃねぇよ。俺、実はそんなベタベタくっつくの好きじゃねぇし」
「うそ、ぜったいうそ」
「そりゃあ、女の身体は柔っこくて触り心地いいから、サワサワしたい男心はめちゃあるけど、ぶっちゃけ、こういうスキンシップはそんなに。一夜を共にフィーバーしたいって奴には、それなりにベタベタはするけどさ。雰囲気作りは大事だし」
「……」
「でも、そういう下世話な欲無しで、ただくっついてるだけで、なんてーの、幸福感? が半端ねぇんだよ、お前に触ってると。だからこうやって、ベタベタしたくなる」
そりゃあ、ぶっちゃけ悶々とする瞬間は多々あるけども、となんかちょっと聞き逃してはならない言葉がボソッと呟かれた気がするけれど、気付かなかったことにする。
すり、といつの間にか、すっぽりと岡崎さんの腕のなかに抱きすくめられる。
「あ~~マジで癒し。このままもう寝たい」
気だるい声を出しながら、私の首もとに頭を埋めてグリグリしてくる。灰色の髪の毛がくすぐったい。ほんとに、大きなわんちゃん。でも、やっぱりがっちりとした身体も、匂いも、男のひとのものだった。
首もとにかかる岡崎さんの吐息がくすぐったくて、恥ずかしくて、身を捩りながら岡崎さんと顔を合わせる。なんだか少し熱っぽさのある岡崎さんの赤には再び気づかないふりをして、口を開いた。
「明日から」
「ん?」
「私がお洗濯します」
「なんで? 別に、これまで通り、俺がやるけど」
「もんのすごく今更なんですけど……岡崎さんに、私のぱんつとかも全部洗ってもらってるんだなって事実が今じわじわキました。ヤバイです。ほんとマジで恥ずかしい。穴があったら入りたい。埋まりたい」
「いや、全然気にしてないけど」
「私の目を見て言ってください」
「実は滅茶苦茶意識してました」
「あぁああもう、ほんとごめんなさい。お見苦しいものを、ほんとすみません」
「いや見苦しいとかじゃなくて、その。い、いいって、いいって。もうこんだけ経ってたら、ぶっちゃけ見られてもだろ」
「……ぶっちゃけ。恥ずかしいことは恥ずかしいですけど」
「慣れって、そんなもんだろ。一緒に暮らしてりゃ、トイレのときの音だってどうでもよくなるのと同じ」
「音●つけたくなってきました」
「いやだから気にしてねぇって。生理現象だし、仕方ねぇだろ」
「生理言わないで!」
「あっ、そこまで掘り起こしちゃったの」
「もはやトラウマなので」
「ん~、でも感心したこともあったわ」
「何をです?」
「うさぎ柄パンツ履いてたやつが、今やちゃんと上下揃ったブラとパンツ着てるってのはな~。あ、カップも少しだけでかくなってぶべぇっ!」
絨毯の上で鼻を押さえてのたうち回る岡崎さんから距離をとって、ぺたりと座り込む。両手を、熱く火照った頬に当てて、気を落ち着かせる。暫く岡崎さんから離れたい。身を隠したいと思うのに、つんつんとおろした髪を引っ張られる感覚に下を見ると、寝転がった状態でこちらまで近づいてきた岡崎さんが、私の髪をくるくると指に巻き付けて遊んでいた。深みのある赤はとても優しくて、岡崎さんのそばを離れることは出来なかった。
0
お気に入りに追加
134
あなたにおすすめの小説

お見合い相手は極道の天使様!?
愛月花音
恋愛
恋愛小説大賞にエントリー中。
勝ち気で手の早い性格が災いしてなかなか彼氏がいない歴数年。
そんな私にお見合い相手の話がきた。
見た目は、ドストライクな
クールビューティーなイケメン。
だが相手は、ヤクザの若頭だった。
騙された……そう思った。
しかし彼は、若頭なのに
極道の天使という異名を持っており……?
彼を知れば知るほど甘く胸キュンなギャップにハマっていく。
勝ち気なお嬢様&英語教師。
椎名上紗(24)
《しいな かずさ》
&
極道の天使&若頭
鬼龍院葵(26歳)
《きりゅういん あおい》
勝ち気女性教師&極道の天使の
甘キュンラブストーリー。
表紙は、素敵な絵師様。
紺野遥様です!
2022年12月18日エタニティ
投稿恋愛小説人気ランキング過去最高3位。
誤字、脱字あったら申し訳ないありません。
見つけ次第、修正します。
公開日・2022年11月29日。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。
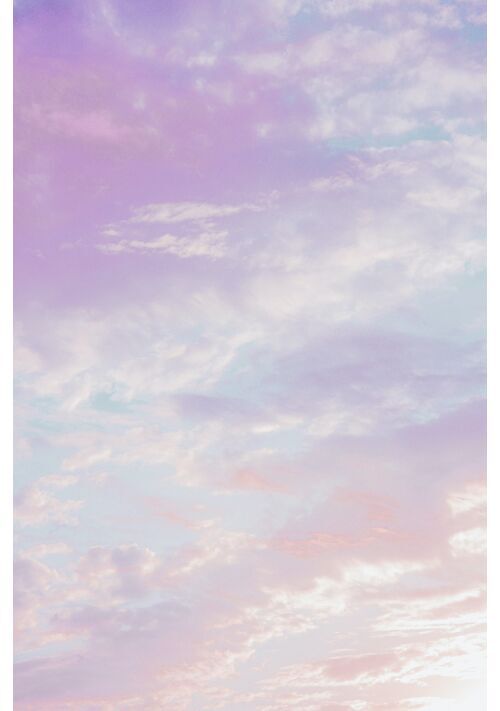
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

【R18完結】エリートビジネスマンの裏の顔
白波瀬 綾音
恋愛
御社のエース、危険人物すぎます───。
私、高瀬緋莉(27)は、思いを寄せていた業界最大手の同業他社勤務のエリート営業マン檜垣瑤太(30)に執着され、軟禁されてしまう。
同じチームの後輩、石橋蓮(25)が異変に気付くが……
この生活に果たして救いはあるのか。
※サムネにAI生成画像を使用しています

イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。

ダブル シークレットベビー ~御曹司の献身~
菱沼あゆ
恋愛
念願のランプのショップを開いた鞠宮あかり。
だが、開店早々、植え込みに猫とおばあさんを避けた車が突っ込んでくる。
車に乗っていたイケメン、木南青葉はインテリアや雑貨などを輸入している会社の社長で、あかりの店に出入りするようになるが。
あかりには実は、年の離れた弟ということになっている息子がいて――。


【R18】豹変年下オオカミ君の恋愛包囲網〜策士な後輩から逃げられません!〜
湊未来
恋愛
「ねぇ、本当に陰キャの童貞だって信じてたの?経験豊富なお姉さん………」
30歳の誕生日当日、彼氏に呼び出された先は高級ホテルのレストラン。胸を高鳴らせ向かった先で見たものは、可愛らしいワンピースを着た女と腕を組み、こちらを見据える彼の姿だった。
一方的に別れを告げられ、ヤケ酒目的で向かったBAR。
「ねぇ。酔っちゃったの………
………ふふふ…貴方に酔っちゃったみたい」
一夜のアバンチュールの筈だった。
運命とは時に残酷で甘い………
羊の皮を被った年下オオカミ君×三十路崖っぷち女の恋愛攻防戦。
覗いて行きませんか?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
・R18の話には※をつけます。
・女性が男性を襲うシーンが初回にあります。苦手な方はご注意を。
・裏テーマは『クズ男愛に目覚める』です。年上の女性に振り回されながら、愛を自覚し、更生するクズ男をゆるっく書けたらいいなぁ〜と。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















