96 / 124
天秤にかける必要もない
しおりを挟む地下室に良い思い出はない。真っ暗で寒いこの空間に、良い思い出があるという人の方が、そもそも珍しいとは思うけれど。
鎖で繋がれた手枷が、地下の冷気で冷たくなり、手首と足首を刺激する。凍傷とまではいかないまでも、麻痺し、感覚は鈍くなっていた。ギプスが取れたばかりの右腕を擦ってみると、まだ少し痛む。
窓が無いから、太陽の暖かい光が射し込むことはない。この空間は、いつまでたっても暗い。明かりは、四隅にある松明と、枕元にひとつだけ置くことが許されたランプだけ。だから、時間感覚もわからなくなる。明けることのない夜が続いている。
身体を流したり、トイレなどの人間として最低限の用事以外で、このベッドから出ることは一歩も許されていない。鉄格子の向こうには、いつも誰かが居る。恨みと憎しみの籠った目で、柵の隙間から四六時中監視されていると、人間としての尊厳を失った気分になる。いや、そんな大層なものは、もう私からは取り上げられていた。檻の中に居る動物の気持ちを理解出来る様になった。
時折やって来る、美帆という女の子が、嫌々という態度を隠しもせず、1日二回、食事を運びに来てくれる。献立はいつも同じで、黴の生えかけたパンが二つと冷えたスープだった。まともに手をつけたのは、いつが最後だっただろう。口の前に運ぶまでは出来ても、無臭にも近い筈なのに、匂いを嗅いだだけで吐き気が襲い、その先へと中々いってくれなくなった。気付けば、すっかり骨と皮だけの身体だ。腕の肉を摘まんでみるというより、皮を引っ張ってみたと言った方が正しい。
三日に一度の頻度で、私の右肩の診察に来るお医者様らしき人物には、栄養状態が悪いなんてどころじゃないと言われ、最近になって、私の食事は固形物ではなく点滴になった。毎日二回注射を打たれ続けた左腕は真っ青で、針の痕がグロテスクで、見ていて気持ちが悪い。
中途半端に生かされている、としか思えない。放っておけば勝手に野垂れ死ぬだろう私のことを、仕方なしに生かしているとしか。
「(マリーも昔、こんな感じだったのかな)」
いや、マリーから聞いた話は、私なんかとは比べ物にならない程もっと悲惨だった。天秤に計るような話ではないけれど。
真っ赤で豪華なドレスを着た、何をしていても優雅という二文字が似合うマリー。幼い私に、穏やかな口調で昔語りをしてくれる彼女は、大勢の人々から数々の責め苦を受け、最後は、真っ白な首に大きな刃を受けて、その生涯を終えたという。
私も、近いうちに同じ道を辿ることになる。
人の顔にも見える壁のシミを淡々と数えるのも飽きた。口を少しだけ開いた、だらしない状態で、ぼーーと何にもない宙を眺めていた。
気づいたら、口の前に持ってきていた左手の爪をカリカリと、ひまわりの種を餌とする齧歯類みたいに齧っている。今や悪癖となっていて、自分でも無意識のうちに黙々と繰り返している。
それだけじゃない。無性に首を掻きむしりたくなる時もある。加減なくボロボロの爪で引っ掻き続けるせいで、首回りは傷だらけで真っ赤になってしまった。大切な血管まで傷つけかねないと、傷口部分にはガーゼが張られ、悪化しない様にと対策されてしまった。
ついこの間は、数日ぶりにやっと眠れ……というより気絶したと思ったら、ひとり倒れた太刀川さんを、あのホテルタワーに置いていくときの映像が夢として蘇り、金切り声に近い悲鳴をあげて、両目を掌底で潰そうとしたところを、見張りの男性たちに取り押さえられた……らしい。そのときのことは詳しく覚えてない。ただ、そのことがあってからの数日間は、暴れる精神異常の患者を拘束するのと同じく、両手両足をがっちりとベットの足に固定され、少しの身動きも許されなかった。きつかった。
じわじわと心の中に広がる黒い靄を紛らわせたくて、親指の爪を割るくらいの力を歯に込めていると、私の行動を打ち止める声が掛かった。
「噛むな、志紀」
びく、と手が震える。暫く硬直してから、ぽて、と布団の上に置いた自身の手を眺める。齧りすぎて歪な形をしたボロボロの爪。痩せ細った手は、骨が不気味に浮き出ている。たった今まで噛んでいた指先は真っ赤だ。爪どころか肉まで一緒に噛んでいたらしい。噛み痕が指の腹についていた。
っていうか、このひと、また来たのか。
長いこととかされることなく、貞●みたいにボサボサに垂れた長い髪の隙間から、格子の向こうに、いつの間にか居座っていた人物を覗き見る。
灰色の髪のひとは、ミイラからの脱皮に近頃成功したらしい。目しか見えなかった顔が明るみになっていた。ところどころ身体のあちこちに包帯や痣などが残っているし、まだ松葉杖の支え無しでは快適に歩けないのか、杖が壁に立て掛けてある。それでも、あの大怪我から数日、数週間は経ったのかな、それだけの期間でここまで回復するなんて流石だと思う。
決まった時間になると、見張りの男性達を下がらせ、私の檻の前に椅子を置き、長い時間を居座るそのひとは、包帯をした両手を使い、自分と同じ目の色をした真っ赤な林檎の皮を器用に剥いていた。するすると一度も途切れることなく、ナイフが赤い皮を剥がしていく。螺旋状に真っ赤な皮が落ちていく様はどこか目を惹かれる。
青黒い痣を顔に蓄えた男性、岡崎さんが此方からの視線を感じ取り、林檎から顔を上げたのを見て、目が合わないように前方に顔を向ける。
膝を抱えていると、室温が上がっていることに気付いた。地下のあまりの冷え込みに寒い寒いと文句を絶やさなかった岡崎さんが、以前自ら持ってきたストーブの電源を入れたのだろう。寒すぎるからと柵の間から差し込まれた、岡崎さんが持ってきた毛布を軽く握り締める。
林檎の皮を剥く音が止むのと同時に、抱えた膝に顔を埋める。
何の反応も示せない木偶の坊を長時間相手にして何が楽しいんだろう。毎晩毎晩やってきても、私は話さないし、答えないし、眠らない。岡崎さんは落語家みたいに、ひとりでベラベラと話し続けているだけ。
「志紀」
「……」
「オイコラ。無視すんな。ほら、こっち向けって」
「……」
「いや、三点リーダーじゃなくて。ちょっと顔上げなさい。狸寝入りなんざ小賢しい真似やめろ。座ったまま寝るとか、お前そんな器用じゃねぇだろ。さっき、こっちチラ見してたのわかってんだからな」
俯きがちの、カーテンになった長い髪の隙間から、岡崎さんが柵の間からこちらに差し出しているものを見る。真っ白な器のなかには、瑞々しい黄色の身をした林檎が、まるでお花みたいな形に詰められている。職人か。お花の上にはひとつだけ、ウサギりんごが、こちらを可愛らしく見上げていた。
ん、と器が揺れる。取れということなのだろう。ふるふると首を振って、お断りし、もう一度抱えた膝の間に顔を埋める。
「いつも言ってんだろ。ひとつでも食わねーと、俺、この腕下ろさねぇからな」
「……」
「あーあー。まーた耐久勝負か。せーっかく腕の傷塞がったのになぁ。また開いちまうなぁ。リゼに怒られるなぁ」
「……」
「っつってんのに、お前、マジで受け取らねーんだもんなぁ」
「……」
「昨日の五時間お粥耐久レースは流石に堪えたわ。熱かったし。普通に火傷したし」
「……」
「あ、あの、マジで。一言でいいから喋ってくんない? 流石にヒロインが…だけじゃマズイって。黙点娘って呼ばれちゃうぞ。嫌だろ、流石に嫌だろ」
それでも、私の手が伸ばされることはない。行き場の無くなった岡崎さんの腕が引いた気配がする。
しゃりしゃりと食す音が聞こえてきたことから、再び覗いてみると、岡崎さんの膝に戻ったウサギのみが居なくなっており、岡崎さんが自らの口に運んでいるのだとわかった。彼はもごもごとウサギを補食しながら、どこから持ってきたのか、おろし皿を華麗に取り出して、お花形になっていた林檎たちを、ひとつずつ擦りおろし始めた。
火傷をした、と言っていた。すりおろし途中の岡崎さんの両手を見て、心がツキリと軋んだ。
「これなら流し込めるだろ」
再びこちらに差し出されたのは、決して大根おろしなどではない。甘酸っぱい匂いが漂ってくる、すりおろし林檎の入った器だった。しかし、なんの反応も示さない私に、岡崎さんは今度は凄みはしなかった。
「人間ってのは、口からメシ食わねーと気力なんざ出ねぇんだよ。液体体内に注入するだけのそれは食事とは言わねぇ。半分じゃなくてもいい。一口啜るってだけでもいいから」
言うことを聞かず、拗ねている子供を言い聞かせようとする口調だった。私、もうそんな年じゃないんだけどな。あぁ、もしかして、それを狙ってるのかな。子どもじゃないってムキになるんじゃないかって。
俯いてばかりの私と視線を合わせる為だろう。足が痛いだろうに、屈みこんで、俯きがちの私と無理やり目を合わせてくる。少しだけ顔を傾けて、眉を情けなく下げ、様子を伺ってくる岡崎さんの姿は、あまりにも人を気遣いすぎているというか、彼らしくなくて。そもそも、私に対しても基本的には、強引で横暴と言える態度が多かったのに。
あんまりにも一心に見つめてくるその視線に、甘いドキドキからではない心拍数が上がる。耐えられなくなり、そんな目で見てほしくなくて、気付けば震える手で器を受け取っていた。その赤い瞳が僅かに喜びに染まったのが、何とも言えない。
器を手にしたものの、中身は口につけることなく、どれくらいの時間が経っただろう。岡崎さんは持参した、溢れそうなたわわなお胸を強調した水着を着たお姉さんが表紙の雑誌をペラペラとめくり、興味無さ気に時々一人で他愛ない感想を述べている。しかし、逆だ。本の上下が。
「あのさ、あの爽やかな軟派野郎。帽子被った兄ちゃん居たじゃん」
「……?」
「あーなんていうの、ありゃあスーツとは言わねぇわな。英国紳士って程じゃねぇ服着た、派手な帽子被った、目力やたら強いパリコレ兄ちゃん」
「……」
「あいつ、志紀の兄貴だったりすんの? 保護者だって言ってたけど。あれ、でも前に一人っ子とか聞いた気がするんだけど」
帽子屋のことを尋ねられていると気付き、兄妹ではないと否定する為に首を振る。ちんちくりんな私と血が繋がっていると勘違いされたら、ジャックは間違いなく怒る。私の反応を確認し、そうかと頷いた岡崎さんが、それ以上、摩訶不思議な私の友人について突っ込んでくることはなかった。
帽子屋のことを思い出すと、自然と彼の顔を最後に見た記憶が甦る。そして、暖まりつつあった足先から体がピキピキと凍っていくのがわかった。震えが止まらない。それは手先にまで到達し、林檎の入った器を持つ手から力が抜けて、ごとりとベットの上に落ちて、黄色の液状を溢してしまう。
「志紀?」
がしゃりと、柵を掴んで誰かが立ち上がる音がする。私の膝上に広がっていく黄色のそれが真っ赤に染まっていく。誰の血だと考えて、私の膝の上に体重を預け、長い睫毛を伏せ、目を閉じていた男性が何処にも居ないことに気付く。そのひとの名前を呼び、呼吸が荒くなる。かたかたと震えて歯が鳴る。両手で顔を覆い隠し、自分でも理解できない言葉を延々と呟きながら、身体を縮みこませる。やがて呟きは、悲鳴混じりの叫びに変わる。半狂乱になる私の名前を、誰かが必死に呼んでいる。
「志紀、落ち着け。こっち見ろ。な? しき」
「けほっ、っおえ」
「志紀!」
もう誰の言葉も耳にしたくない。ぼとぼとと涙が溢れる両目をぎゅっと瞑り、頭が潰れるのではないかという程、両手で耳をきつく塞いだ。鼻を啜り、荒い呼吸と嗚咽を繰り返していると、昔しつこく患っていた感覚が、気管から甦る気配がした。
ヒューヒューと呼吸の最中に入り交じる雑音にゾッとした。お母さんを一番に苦しめたものが息を吹き返したのだと気付いたのと同時に、それが牙を向く。何かが引っ掛かっている様な、妙な咳が止まらなくなり、呼吸困難に陥った。身に纏う胸元の布をきつく握り締め、咳と共に身体を大きく跳ねさせて苦しみ出した私に、誰かが「待ってろ」と叫んだ。目の前が真っ暗になった。
「終わったから入っていいわよ。てっちゃん」
「……志紀は?」
「薬飲ませて、副作用で今は寝てる。寝不足系女子だったし、丁度良かったわね。すぐの処置で大事には至らずよ。顔真っ赤だけど、それは熱からのものだから、心配しないで。突然仕事部屋駆け込んで来たから、何事かと思っちゃったわよう」
「また、でけぇ借りが出来たな」
「ほんとに。このことはシラユキにはナイショにしててあげるわ。でも、これで最後よ。最低限の治療は施すなって言われててね。バレたら怒られる、じゃ済まないと思うし」
「わかってるよ」
「外じゃ寒いでしょ。暖房も効いてるし、中に入ったら? 顔も見たいんでしょ」
「べっ、べつに」
「じゃあ何、その、床を破壊しかねない貧乏揺すり。うぃーうぃるろっきゅー? ボヘミアン●プソティ観に行きたくなってきた」
「ばっ、こ、これはアレだよ。武者震いだよ!」
「あの女の子討ち取るつもりなの? 別に、必死の形相で、たすけてくださぁい! ってセカオワしにきたこと、笑いはしないわよ。説明も無しに、いきなり首ひんづかまれて連れ出されたときは、股関蹴り上げてやろうかコイツとは思ったけど」
「……」
「落ち込んじゃって。すっかり子犬ね」
「前からか」
「ん?」
「これ」
「あぁ。なにを珍しく真剣に読んでるのかと思ったら、あの娘のカルテ読んでたの。そうそう、気管が弱いみたいよ。ていうか、さっき部屋に来たとき、さりげなくパチッたわね、このコソ泥。手癖悪いったら」
「猫アレルギーだってことは知ってた。昔、身体が弱かったってのも。でもアイツ、何ともなさげで、基本的には大食らいで、ピンピンしてたから」
「治まってたものも、ストレスだとか環境で誘発されるのがあるのよ。てっちゃん」
「……」
「地下は環境悪いしね。埃とか。あと、この季節じゃあ、いくら暖房効かせようとも芯から暖まる訳じゃないもの。風邪引いたら一発で喘息引き起こすだろうな~って思ってたら、一緒に来ちゃったみたいね。そりゃ辛いわ」
「……」
「怪我もだけれど、PTSDの方が重症」
「ぴー? なんだそれ。新しいゲーム機?」
「PTSD。Post Traumatic Stress Disorder。心的外傷後ストレス障害ってのよ。今の遠坂さんは、まさにソレ。魂の抜けた脱け殻そのもの。症状は、貴方が一番そばで見てるから分かるでしょう」
「……」
「無理もないわ。普通の女の子が銃で撃たれるなんて経験、そりゃあトラウマものよ。どこまでも一般人みたいだし。なんで、あの太刀川が、あんな子に御執心だったのかわからない位に。それは、てっちゃんにも言えることだけれども。元々、気に病みやすい子だったんじゃない? 今回の太刀川の一件も引き金になったんでしょう。今まで心のなかで溜め込んでたものも、一気に爆発したって感じかしら」
「シラユキもそれ知ってて、志紀をこんなとこに囲ってんのか」
「そりゃあそうよ」
「……」
「限界まで弱らせて、本人がもう耐えきれないってなったところで、口を割らせる目的もあるんだから。このまま話さないつもりなら、そろそろ拷問にかけることも考えてるみたいよ~」
「志紀は何も知らねぇって言ってんだろ。喋るも何も、吐くネタがそもそも無ぇんだ」
「知らなくてもいいんでしょう」
「……」
「天龍、いえ、ヤクザに関わったからこそ、シラユキは痛め付けるのよ。情報を握ってるか否か、そんなこと、本当はどうでもいいのよ。事情はどうあれ、彼女が太刀川尊嶺の女として在ったという事実は本当なんだし」
「……」
「今のシラユキはあの子をただ生かしては置かない。事実、シラユキは本気で殺すつもりで撃ったんだろうし。白鷹にいる限り、あの子は、いつ終わるかもわからない苦しみを、死ぬまで受け続けることになるでしょうね」
「……」
「あら、今度はてっちゃんか三点リーダーばっかり使ってる」
「待て待て待て待て。リゼ、お前ほんとは、最初から俺達の会話聞いてたんじゃ。待機してたんじゃ」
「あ~~あ~~二股なんてヒッドイ男ね~~~! シラユキとあんだけイチャコラ私達に見せつけといて、これだものね~~」
「二股じゃねーし。俺はこう見えて一途なんです。わかりにくいだけで」
「どっちに?」
「……」
「二兎を追う者は一兎をも得ずって言うでしょ。てっちゃん」
「……いつか私を切り捨てなきゃいけない日が来る、ね」
「ん?」
「いーや。俺ァとっくに腹決めてるよ。優柔不断なタイプじゃねーし」
「そう」
「だからさぁ、さっきからチクチクチクチク、けしかけてくんのやめてくんない」
「あら? 何を?」
「ほんと怖い女だよ、お前も。マジで俺の周りって、見た目ばっかりで、中身まともな女が居ねぇのな。化粧塗りたくる前に内面磨け、内面を」
「あらやだ、てっちゃん。疚しい考えがあるって自覚のある人間は、みんなそういう誤魔化し方をするのよ」
「だろうな。えーっと、イワンイワンイワン。あった。あいつ電話出っかな」
「今3時になったとこよ。飲んだくれて寝てる頃合いでしょう」
「まぁいいや。出るまで鬼電してやる」
「あーあ。遠坂さんが何にも有益なネタ持ってないってのが本当なら、どうしたもんかしらねぇ~。霧絵ちゃんとも連絡取れなくなったし」
「やめとけって。あの性悪サディストに関わんのは。何回も言ってんだろ。ロクな目に遭わねーぞ」
「ってもねぇ、かなりの実力者であることは確かな訳だし」
「ちなみにさぁ、突然話変わるけど。リゼ、お前さ、人間が目の前から消えるっての体験したことあるか?」
「は?」
「瞬きしてたら消えてたんだよ。ビックリじゃね。しかも二度も、連続で」
「いや、誰が? そんなことある訳無いでしょ」
「だよな。無ぇよな。流石に」
「夢でも見て、寝惚けてたんじゃないの?」
「夢でもそうじゃなくても怖いんだよ。だから居てもたっても居られねぇ。目の前に居るって確認してねぇと落ち着かねぇんだよ。俺、わりとリアリスト寄りだったんだけどなぁ」
「ちょっと、なんの話?」
「俺が勝手に焦ってるって話。……あ、繋がった。よぉ、イワン。ちょっと頼まれてくんね? 報酬は弾むからよ」
ゆっくりと目を開く。茹だるような熱に冒されている頭が現状を認識するのに、随分と時間が掛かった。すっかり見慣れた薄暗い天井を暫くぼんやりと見つめると、私が寝ているベッドの隣に誰か居ることに気がつく。柵の外ではない、ベッドの横、すぐ近くで。この檻の中に入ることが出来るのは、片手で数える程しか居ない。その内の一人は、お医者様、食事を運びに来るあの女の子に、たまに様子を見に来るリゼさん、そしてごく稀に現れる、この女性だけだ。
「話す気になった?」
天井を見つめたままで居る私に、腕と足を組んで椅子に腰かけ、軍服を纏った女性が、尋問紛いに、次々と質問を事務的に投げ掛けてくる。けれど、どれもこれも私には答えられないものばかりで。ひとつ、ふたつしか返ってこなかった回答に落胆しているのか、予想通りというところなのか、シラユキさんが沈黙し、立ち上がり退出しようとする。檻の鍵を解いて出ていこうとした、身長の高く姿勢の良い背中に声を掛けたのは、私だった。
「箱は」
久し振りに発した声は、か細くて頼りない。息を引き取る少し前のおじいちゃんも、こんな感じだった。シラユキさんは、こちらを振り向きはしないものの、問いかけには淡々と答えてくれた。
「中身は確認した。何も入ってなかったわ」
「壊したんですか」
「でなければ調べられない」
シラユキさんの背中から視線を外し、再び黒に染まる天井を見上げる。
そっか、壊されちゃったのかぁ。太刀川さん、怒るだろうな。あれだけ長い時間をかけて造ってくれたのに。苦労したって本人も言ってたし。作業机に向かう太刀川さんの背中が霞み、色彩が失われ、モノクロになっていく。
左腕をなんとか持ち上げて、両目の上に置く。込み上げてきたのは笑いだった。視界を隠し、壊れたように笑い声を漏らし続ける私に、シラユキさんは何も言わない。人間どうしようも無くなると、笑うことしか出来なくなるって、ほんとなんだな。笑いながらでも涙は出るんだな。変なの。
「シラユキさん」
「……」
「貴女がそうなってしまったのも、貴女の気持ちも、ほんの少しだけ、わかった気がします」
「わかってたまるものか」
「全部じゃないです。ほんの少しだけ」
「……」
「私、ちっさい頃に、同い年位の子供たちからいじわるされたことがあったんです。大切にしていたものを壊されちゃって。ただ泣いてばっかりで。古い友人に、怒ったり仕返ししてやろうだとか思わないのかって聞かれたんです。全然、そんなこと考えてなくて。そもそも、何を聞かれてるのかも、よくわからなかったんですけど」
「……」
「誰かを憎むって、こんなに辛くて痛いんですね」
息を呑んだような音が聞こえてきた気がする。
「わかって、たまるか」
言葉は鋭いけれど、シラユキさんの呟きは私に対してのものではない。まるで母親に対して、強がって言い訳でもする、小さい子を連想させる。自分に言い聞かせたものだった。それでも、と私の口は勝手に言葉を紡ぐ。
「今の私は、貴女とそう変わらないと思います。シラユキさん」
シラユキさんからの返事はなく、代わりに返ってきたのは、檻に鍵をかける音だった。
「あの服、どこから調達したんですか」
こほ、と咳をしながら声を発した私に驚き、赤い目を真ん丸にして、読んでいたグラビア雑誌から顔を上げたのは、今日も今日とて日課の如く、こんな地下に足繁く通う岡崎さんだ。このあと何処かへ出掛ける予定なのか、コートを羽織っている。
此所に連れて来られて、私から岡崎さんに声を掛けたのは、これが初めてで、それに対して岡崎さんが驚愕しているのがわかる。
動揺からガタガタと椅子からずり落ちそうになった岡崎さんを柵越しに見つめていると、彼は、今更ながら動揺を悟られないようにする為(手遅れが過ぎる)に、私がよく知っている何ともなしな表情に戻り、余裕のアピールか、長い足を組んで、再び逆さまの雑誌を見つめ、三秒に一度はこちらに視線を寄越しながら「あの服って?」と平静を装いつつも、裏返った声を返してきた。
「トイレで会ったとき、女のひとの格好してましたよね」
「はっ!? し、してないし。する訳無いだろ。ヘンタイじゃあるまいし」
「そうですか」
「……」
「……」
「えっ、ほ、他に聞きたいことは……」
「……」
「あっ、あーー! そう! そうなの! 潜入するには必要だったから、やむを得ずな! 趣味じゃねぇよ!? 目覚めてもねぇよ!? 身分もちょろまかさねーとだったし? 俺達のナリじゃ目立つし? だからあの、ほら、鈴蘭。覚えてるだろ? あいつの店から一式借りた」
「十分目立ってましたよ」
「そりゃあ、そうだろ。あんな完璧な女、そうそうお目にかかれねーだろ。朝倉のオッサンは、完全に化け物小屋から出てきたとしか思われなかっただろうけど。俺は、千年に一度の美女もハリウッド女優もひれ伏すレベルで」
「そうですね」
「オイコラ。なに面倒くせぇなコイツみてぇな面してんだ」
「鈴蘭さん、お元気ですか」
「おーおー、元気元気。相変わらず物好きな客、上手いこともてなしてるよ。お前にも会いたがってたぞ。遊びに来るって約束したのに中々来てくれねぇっつって」
返事の代わりに出てきたのは渇いた咳だった。二、三度繰り返していると、岡崎さんが立ち上がり、「大丈夫か」と柵の間から此方を覗き込んでくる。手で口を塞いで、ひとつ頷く。
潜入と言っても、あれだけ警戒体制が強いホテルだったのだ。身分確認も綿密に行われていたのにと更に疑問をぶつける。
岡崎さんは手にしていた雑誌をぺいと放り投げ、「しんどかったら、すぐに言えよ」と前屈みに腰掛けた。
「下に蔓延ってた連中は、フォックスがこれでもかって位、えーと、その……アレ、誘惑してな。その内に、俺達はそそくさと……」
「意外とザル警備だったんですね」
「あいつの本気の色香に勝てる奴なんざ、中々居ねぇよ」
「確かに、そうですね。でも、忍び込むにも証明関係は?」
「そこはイワンが頑張ったよ。色々と。滅茶苦茶ぼられたけどな」
落ち着いていた熱が上がってきたのだろうか。視界がぼんやりとしてきた。ベッドの背もたれに背を預けると、私が調子を崩し始めたことに気付いた岡崎さんに、もう寝てろと言われるが、構わず話を続けた。もう、ここに出向くことは無いと告げるために。
「もう、此所には来ないでください」
「……なんで?」
「岡崎さんまで白い目で見られちゃいますから。知らないでしょ。たぶん、お昼間位かな、見張りのひとに悪口言われてましたよ。あいつは何考えてんだって」
「別に気になんかしねーよ。白い目でも黒い目でも、そういうので見られるのは慣れてら」
「私が嫌なんです」
「だから気にすんなって」
「気にしますよ。岡崎さんが大切にしてる居場所なのに。私のせいで、貴方に居心地の悪い思いをしてほしくない」
「……周りがどうこう言ってるのなんざ、いちいち重く受け止めてんじゃねぇよ。お前の悪いところだろ」
「しょうがないですよ。全部事実ですもん。私、天龍の女ですもん」
「……」
「岡崎さん。私、今からヤなこと言います。軽蔑されたって仕方ない。でも、ちゃんと聞いてほしいんです」
膝を抱えて、呼吸を整える。これ以上、私に寄り添おうなんて岡崎さんが思わないように、ちゃんと話さなきゃ。白鷹に属する岡崎さんが、自分の立場を蔑ろにしてまで、私なんかを気遣ったり庇ったりしちゃいけない。そんな価値は私には無いんだとわかってもらう為に。誤魔化しや嘘なんて無い。取り繕う必要もない。ただただ、私は、ひた隠しにしていた汚い自分を晒け出せばいい。躊躇なんて、もう必要ない。
「西園寺さんじゃなくて、朝倉さんの方が死んでくれたらよかったのにって、ずっと思ってるんです」
岡崎さんからの視線を強く感じる。私を見つめる赤に、どんな感情が込められているのかわからない。知りたくもない。知ってしまったら、きっと、この口は言葉を出せなくなってしまう。
「あのとき、ジェイさんの邪魔をしなければ良かったって、ずっと後悔し続けてるんです。見捨てれば良かったって。あのまま撃たれてくれれば、西園寺さんは今でも生きて、太刀川さんの少し後ろで、いつもみたいに無茶しがちなあの男性を支えてくれてたかもしれないなって」
「……無理だろ」
「何がですか」
「お前は、誰だろうがお構い無しに、手ェ差し伸べちまう奴だ。親交が浅かろうが、目の前で切り捨てるなんざ、土台無理な話だろ」
「でも、後悔してるんですよ?」
「ああしときゃ良かったって悔やむ連中は、世界中にごまんと居る」
「でも、ひとの生死に関わることです」
「……」
「一度間違えたら、もう戻ってこないんです。取り戻せないんです。直接的でなくても西園寺さんを死なせてしまったのは、その一端を担ったのは、他でもない私なんです」
「……」
「ひとの命は平等だって、ずっと信じてた。でも実際は、優先順位があるなんて、知りたくなかった」
誰かを助けることで、あの日、母を掬い上げることが出来なかった自分を帳消しにしたかった。慰めたかった。一種の罪滅ぼしだった。だけど、こうした形で打ち砕かれてしまうと、これから私は、どう生きていけばいいのかわからなくなってしまう。
何よりも、太刀川さんと岡崎さんが戦って、生き残ってくれたのが太刀川さんだったら良かったのにと一抹でも考えてしまった私が、のうのうと岡崎さんと話すなんてことは、自分自身でも赦せなかった。今だって、こうして、岡崎さんの前に姿を晒す自分が恥ずかしくて仕方なくて、自らの首を掻き毟りたくなる。
それも、全部全部、吐露した。どうだ、嫌だろう。命懸けで助けた女から恩義を与えられることなく、貴方が死ねばよかったのになんて言ってくる女をこれ以上相手にするなんて。時間の無駄とすら思うだろう。自分があれだけ傷だらけになって、死にかけたのは何だったんだとも、憎悪を抱きもするだろう。
罵倒してくれたらいいのに、私の懺悔を聞き終えた岡崎さんは黙ったままで何も言わない。呆れてものも言えないのか。それとも、こんな女だとは思わなかったと失望したのか。きっと、岡崎さんの中に居る志紀は、世間知らずで臆病な、ちょっとしたことを過剰に気にする女の子で止まったままだったろうから、そのイメージが崩れ落ちている最中なのかも。
沈黙が続き、はぁ~~と大きなため息が聞こえてくる。そして、がしがしと灰色の頭を掻く音も。
椅子から立ち上がる音がして、このまま出ていくのかと思ったら、ヤンキーよろしく、ガンと鉄の柵を軽く蹴られる。微妙に振動した柵の向こうで、檻の中に居る大人しい動物を見る客の如く、こちらを岡崎さんがジッと凝視している。
岡崎さんの方を見ることが出来ず、俯いたままでいると、「こっち見ろ。オイコラ」とヤクザらしいドスの効いた低い声での脅しがかけられる。あれか、謝意を述べるときは人の目見て誠心誠意謝罪しろってアレか。ベッドの上だと土下座しにくいな、出来るかな。
咳き込みながら、熱で浮かされた頭を緩慢に上げる。目を合わせることをあれだけ恐れていた赤を、なんとか視界に収める。さぞ、怒りに満ちた赤が居らっしゃると思いきや、予想外にも、眉を下げた自信なさ気な、しょぼくれた様子の男性がそこに居た。その様子に、今度は私が目を丸くする。
「なに当たり前のこと話してんだよ、お前は。優先順位なんざ誰にだってあるに決まってんだろ」
「……」
「どうせ、お前、あのとき連れ出すのは自分じゃなくて、太刀川にしてくれりゃ良かったのに、とか考えてんだろ」
「そうしてくれたら良かったじゃないですか。私なんかよりも、白鷹の皆さんが欲しいって言ってるものは、太刀川さんならたくさん持ってた筈です。白鷹の皆さんにも、どうして私の方を連れて来たんだって責められたでしょう」
「太刀川かお前なら、俺はお前を選ぶ」
「……」
「……当たり前だろ」
立場だとか今後のことだとか、何にも考えちゃいない。自分の心がこうしたいと思ったことを、そのまま行動に移しただけだ、と迷いなく岡崎さんは告げる。太刀川さんを置いていくことで、私がどれだけの苦しみを背負うかもわかった上で、この選択をしたのだと。
「ただ、お前と違って、俺ぁ微塵も後悔なんざしちゃいねぇよ」
「……」
「俺は、こうして手が届くとこに、いや今は物理的にゃ届かねぇけど……遠坂志紀が居るってだけで満足してんだよ。周りがどうこう言おうが知ったこっちゃねぇ。自分の気分が満たされりゃいいって利己主義な方なんだよ、俺は」
自分だって変わりはしないと岡崎さんは続ける。暫しの沈黙のあと、岡崎さんは灰色の睫毛を伏せて、重くなった口を開いた。
「俺さぁ。お前にだけにゃ、あんな、理性も何もかも馬鹿になった本性、知られたくなかったんだよね。見られたくなかった。墓場まで隠し通そうと思ってたんだ。何でだと思う」
「……」
「ただの人殺しの癖して、お前の言う、変にカッコつけた理想のいい人間で居たかったんだ」
「……ごめんなさい」
「何謝ってんの。何に対しての謝罪、それ」
「貴方に勝手な理想押し付けて、苦しい思いさせて、ごめんなさい」
「誰が苦しいっつった? 勝手にひとがどう思ってたか決めつけんじゃねぇよ」
「でも」
「俺は存外いい気分だったよ。だから、柄でもねぇのにヒーローらしく振る舞い続けてたんだ」
「……」
「言ったろ。こちとら白いどころじゃねぇ、虫けら見る目で見られ続けるだけの人生歩いてきてんだ。クソみてぇな扱いしか受けられない、誰も情けなんざくれねぇ、人としても扱われねぇ、この先どっかの小屋か何かにぶちこまれて見せ物になるか、肉をバラ売りにされるかの未来しか想像出来なかった。今のお前みたいに、もうどうにでもなっちまえ、こんなとこにこれ以上留まり続けるのはクソ食らえだって思いながら、地べた這いつくばって生きてきたんだよ」
岡崎さんは黙り込み、ほんの少しだけ私みたいに俯いたあと、顔を上げて、強く輝く赤い瞳で私を捉えた。
「お前に会うまではな」
芯の籠った声で言い放つ。目を見開かない訳が、なかった。
「カタギの人間に、それも初めて面合わせたガキと、あんなになんてことねぇ普通の話したのは、アレが初めてだった。地味に緊張してたの、気付かなかったろ。怖がって逃げられんじゃねぇかって思ったら、どんな物好きか、付き合ってくれるし」
「岡崎さ……」
「酒か女以外のものも貰ったことなかった。それも報酬としてだったし。見返り無しに、こんなクソ野郎に傘差してくれる奴も居るのかってビックリした」
「……」
「あまつさえ、考え無しに、会って数分の人間助けようと『いくらですか』ときた。世間知らずにも程があんだろってなったのが一発目だったけど……この世も捨てたもんじゃねぇなって思えたんだよ。もう少し踏ん張ってみるのも悪くねぇかもな、とも」
「そんな風には、見えなかった」
「ったりめーだろ。んな恥ずかしいこと考えて感激してたなんざ、会って数分の奴に悟られてたまるかよ」
「……」
「そのあとも縁というか……まぁ、結びつけるのに必死になったのは俺だけだったけど。色々画策だとかはそりゃあったし、ひた隠しにはしてたけど、そんなもん関係無しに、お前にいいひとだって言われるのは嬉しかったよ。そりゃあ、お前のこと騙してた訳だから、自分のことが嫌んなって否定したくなる自分も居たけど、言われたことねー言葉ばっかで、新鮮で、正直嬉しかったし。もっと言われてーなとか、頼られたいとか、初めて思うようになって。でも、お前も意固地じゃん? 中々頼りにしてくんねーで、ムキにもなったけど」
ぎゅう、と岡崎さんが柵を握りしめる。鉄で出来ている筈のそれが、めきょりと音を立てて、ほんの少し曲がった。
「俺と話したことも、そもそも出会ったことも、後悔してるかもしんねぇけど……そんなもん知るかよ。俺にしてみりゃ関係ねぇ。俺があの日、お前に会ってどう思ったか、そこまでああだこうだって勝手に決めつけることは、例え志紀……お前でも、絶対に赦さねぇ」
燃えたぎる赤は、先程までは無かった怒りに満ちている。けれど、怖くなかった。誰かを攻撃するようなものではなくて、炎のような色をしたそれは、一度見たら、もう二度と忘れることはない。
「もうこんな時間か」
岡崎さんは鉄格子から手を離し、ポケットの中からスマホを取り出して呟いた。再びポケットの中に端末を仕舞い込んで、岡崎さんから聞かされた言葉たちをどう受け止めればよいのかと惑ったままでいた私の名前を、優しく呼んだ。
「志紀。お前どうせ、このままおっ死んでもいいやとか考えてんだろ。そりゃあそうだよなぁ。地下室じゃあ夢も希望も未来もあったもんじゃねぇ。今が朝か昼か夜かもわかんなくなるし。知らねぇだろ。人間暗いところに居ると、マイナス思考しか働かなくなるらしいぞ。それ以上、その考えすぎ悪化させるのは不味いだろ。だからさ、何もかも諦めて死んじゃいたい~だとか思ってんなら」
「……」
「その命、俺にくれよ」
「……え」
「や、だって。要らないんだろ。だったら俺に預からせてくれよ。ていうか、どうせ捨てるってんなら、俺に頂戴。リサイクルリサイクル」
「は、え、いや。何言って」
「よしよし。そうと決まりゃ、後は全部俺に任せろ。お前は、このまま流れに乗ってくれたらいいから。津波に乗るサーファーの如く。大海原を駆けるタイ●ニックの如く」
「いや、それ危ないし、最後のは沈没……ち、ちがっ、そうじゃなくて、今のどういうことですか。待ってください、ねぇ」
「待たねぇよ。善は急げって言うだろ」
鉄格子を先程からガンガン蹴り続ける岡崎さんの行動の意図がわからない。ただただ、またとんでもないことをやらかそうとしているという予感だけは当たっている気がする。それはふらつく頭でもわかった。というか、足、まだ完治してないんじゃ。どういうこと。
強度を確かめている風に見える岡崎さんは、壁に立て掛けてあった松葉杖で、牢屋の上部をつっつき始める。が、その前にと、牢屋に入る為に必要なパスワードを入力する端末に、岡崎さんは容赦なく拳を振り下ろし、なんとその馬鹿力で一発で破壊した。プスプスと浮かぶ煙と、時折見える電流から分かるとおり、完全に端末は砕け、お陀仏となった。けたたましく鳴り始めた警報音を気に留めず、岡崎さんはガタガタともう一度鉄格子を揺らす。
「やっぱ端末壊しても駄目か」
先程の松葉杖を手にして、再びぐいぐいと強弱を入れて、牢屋の上部を揺らし始めた。
「お、岡崎さ……自分が何してるのかわかって」
「知らねーの? テコの原理だよ、テコの原理。ウィ●・ターナーが海賊に憧れる全国の男児達に教えてくれたろ。ちゃんと覚えとけよ、ジャック・●パロウ」
「い、いや私、●ャックじゃない。キャプテンはつけてください。そうじゃなくて」
「この建物はそんなに新しくねぇんだ。金も無ぇわで、使われてねぇ廃墟をとりあえず住める様に、やっつけで自分達で改装しただけだから。ほら、ところどころ脆い」
なんて言っていたら、天井が僅かに崩れ、砂埃と共にギギギと重い音を立てて、大きな鉄格子がまるごと岡崎さんの方に倒れていく。しかし、難なく受け止めた岡崎さんは、すぐさま端に移動し、ひとりで持てるとは思えない鉄格子を雑に捨て置いた。
柵という隔たりを取り去った岡崎さんは、あの松葉杖で足を引きずっていたのは何だったんだ、演技か、と言いたくなる程、しっかりとした足取りで、ずかずかとベッドの上に居る私に遠慮なく近付いてくる。
境界の無くなったことに心が脅え、やだ来ないで、と両手を翳すが、岡崎さんは気にも留めない。気持ちを焦らせる警報音が聞こえていないのか、岡崎さんは私と違い、焦る様子は見せず、あくまで冷静に、私の手足を縛る鎖を、まるで糸か何かを切るみたいに引き千切った。錠は外れていないものの、解放された両手を信じられない気持ちで見下ろしていると、おでこに暖かいものが押し当てられる。目と鼻の先に、岡崎さんの真剣な表情があって、息が止まる。
「熱ィな」
そりゃあ熱があるから、と言いたいけど、それだけではないことはわかる。赤い目に写る自分が顔を赤くしているのに気づき、直ぐ様顔を伏せようとしたが、あれだけ恋しいと思っていた暖かくて大きな手が、頬に触れ、ほんの少し強引に顔を上げさせられる。無理矢理な形で、目が合った。カーテンの役割を果たすことが多かったサイドの長い髪を耳にかけられ、なぞる様に、あるいは形を確かめる様に、ほっぺたを大きな手が包み込む。
頭がパンクしかけて、ぐらりと身体が揺れる。横に倒れそうになった私を支えたのは岡崎さんで、抱き上げようとしてくれる前に何かに気付いたのか、岡崎さんも突然顔を真っ赤にした。
「あーー……うん、そうね。そうだった」
ブツブツ言いながら、急いでファー付きのコートを脱ぎ、ちょっとだけ顔を背けながら私に羽織らせ、限界まできっちりとジップをされる。ぶかぶかでサイズが合わないのは当たり前だけれど、今の今まで体温の高いひとの着ていたコートは暖かかった。
「いやほら、外は寒いから」
「……そと?」
「うん。風邪もだけど、喘息の発作起きると、しんどいだろ」
「……だっ、だめ。だめです。早まらないで。岡崎さん、落ち着いて」
「落ち着いてるけど」
「私は此所にいます。此所で、大人しくしてますから」
「俺が嫌なんだよ」
「なんで」
「バーカ。自分で考えろ。ガキ」
「なっ……う、うわっ」
片手で抱え上げられ、吃驚して、思わず岡崎さんの首回りに腕を回す。落ちない様にしがみつくと、すぐ近くにある岡崎さんの顔がなんだか少し嬉しそうで、なんなら鼻歌まで奏で出したから、どうかしてると本気で思った。
耳元で非難する私の言葉をハイハイで受け流し、すたすたと松葉杖片手に進んでいく岡崎さんが地下の廊下に出ると、警報音を聞いた白鷹の組員の皆さんが続々と駆けつけてくる。皆、敵襲だと思ったのだろう。各々が武器を携えていたが、目の前に立ちはだかるのが岡崎さんだと気付いて「なんだ、お前か」とほっとしたが、その腕の中に居るのが、捕らえていた筈の天龍の女だとわかると、再び岡崎さんに武器を向けた。
「岡崎! てめぇ何考えてやがる! その女は」
「御託並べてんのは、自分でもわかってる。でもな」
岡崎さんは、松葉杖を、彼にとっては味方であり仲間である筈の人達に向ける。前を見据えたまま、声だけは私に届けて。
「生きてる限り、何度だってやり直しはきくんだ。間違えても、後悔しても、今度はやらかさねぇようにって経験積んでけばいい。後のことは後で考えりゃいい。その時々にやりてぇって思ったことを、やっときゃいいんだよ。いちいち気にして踏み止まってたら、人生つまんねぇだろ」
力強く身体を抱かれ、岡崎さんが目の前に立ち塞がるひとたちを、軽快に次々と蹴散らしていく。向こうも惑いながらも、岡崎さんという強者に立ち向かうが、岡崎さんさんはまるでじゃれついてくる子供でも相手にするかの様な加減で対処していく。病み上がりって、なんだっけ。
地下にやってきた人達を全員相手し終え、伸びた人達を踏み越えて地上に出る。星空が綺麗な夜だった。暴れ倒した岡崎さんの腕の中で、明らかに体調を悪化させ、顔色を悪くした私は、もうものを言う気力も抵抗も出来ずに、くたりと岡崎さんのぎっしりと筋肉がつまった身体に体重を預けざるをえなかった。
館を飛び出て、広い庭を噴水を通り過ぎ、私を抱えた岡崎さんが爽快に走り抜ける。ぼんやりと見えた岡崎さんの横顔は笑顔で、まるで、これまで長年自身を縛りつけていた檻から解き放たれた獣に見えた。おかしなの。牢獄から出されたのは私だっていうのに。
巨大な門を潜り抜けたすぐ側に置いてあったものは、見覚えのある巨大な黒いバイクだった。岡崎さんはいつかと同じように、熱のある頭を揺らす私を後ろに乗せ、今回はすっぽりとヘルメットを私に被せた。自分もいやにゴツゴツしいゴーグルを装着し、バイクに跨る。大きな背中が目前に広がる。もうまともに思考も働かなくて、とにかく楽になりたくて、咳き込みながら、前方の広い背中に頭と身体を預けた。
発進音と共に車体が振動し、風を切る音が聞こえてくる。どこへ向かってるのかわからない。肌を刺す冷たさを持った風が寒くて仕方なくて、ぽかぽかと暖かい湯たんぽにしがみついて暖を取るのに、いつの間にか必死になっていた。
うっすらと目を開けると、そこは高速道路だった。色んな車がたくさん猛スピードで走っているというイメージが強いが、真夜中だからか、私達しか居ない。どこまでも続く長い高速の上から見る夜景は、オフィスビルの光できらきらとしていた。
前方の岡崎さんが後ろに居る私の、その向こうを気にする素振りを見せて、更にアクセルを踏んだ。加速したことで、より岡崎さんの背中にしがみつく形となるのが何とも言えない。
「徹也!!」
強く眩いライトが、走行する私達をピンポイントに照らす。巨大な音ともに、危ないという概念はないのか、ヘリコプターで私達を追いかけてくるのは紛れもない白鷹の人達だった。止まれ、とスピード違反者を取り締まる警察の様な警告が発せられる。ヘリの窓を開け放ち、こちらにスナイパーライフルを構えているのは美帆ちゃんだ。彼女が岡崎さんに恋慕の情を抱いていることは、鈍い鈍いと言われ続けた私でも気づいている。だからこそ、その銃口をこちらに向けつつも、一発として放ってこないのは、岡崎さんを撃ちたくないと躊躇している証なのだろう。
そんな彼女の後ろから、岡崎さんの名前を呼び制止しているのは、軍服を強風でたなびかせ、軍帽が飛ばないように押さえ、険しい顔をしているシラユキさんだった。彼女もまた銀色の銃を構え、こちらに向けている。
「徹也! 聞こえてんでしょ! 止まれって言ってんのよ!」
「止まりませーーん止まれませーーん!」
「徹也ァ!!」
「悪ィなシラユキ! 衣笠のとっつあんとの約束を反古にするつもりはねぇ! なんかあったら、すぐ駆けつけてやらァ!」
「いい加減手を煩わせないで! その女を何処に連れていくつもりなの! 何処まで行っても、貴方達に自由は無いのよ!」
「だろうな! けど、んなこたァ今はどうでもいい! 志紀は俺がもぎ取ったんだ。だったら、コイツの処遇を決めるのは、お前らじゃねぇ! 俺だろうよ!!」
「この……!」
どうしてと惑った表情で引き金を引くことが出来ない美帆ちゃんの代わりに、シラユキさんが己の銃で鉛弾を繰り出す。岡崎さんは後ろをちらりと見るだけで、上手くハンドルを切り、弾丸を避けていく。そしてシラユキさんが弾を詰め直しているその機を利用して、今度は岡崎さんが動いた。急加速したと思えば、次に急ブレーキを踏み、スリップを利用した急停止で、逆にヘリコプターに真正面に向き合った。そこからは、まさにスローモーション。バイクの足元らへんを岡崎さんが足で行儀悪く叩くと、車体から飛び出してきた筒の様なものを掴み、留め具を抜いた。煙が吹き出し始めた棒状のそれを、勢いよくヘリコプターの中へと投げこむと、巨大な煙幕がヘリコプターの中も外も包み込んだ。操作不能になったヘリコプターは大きなその機体を揺らす。数秒間の内に、あんまりにも鮮やかに行われた所業を、上手く飲み込めていない私は置いてきぼりだ。追跡不能となったヘリの様子を見届け、再び岡崎さんは、煙幕に包まれるヘリに背を向けバイクを発進させる。
「シキティ!!」
自然と、顔を後ろに向ける。雲みたいに真っ白な煙に巻かれ、ヘリの姿すら見えなくなった光景は、段々と遠くなっていく。けれど、私の耳には届いていた。一人にしか呼ばれることのない筈のあだ名を叫んだひとの声が。
随分と遠くまで走ってきた高速を走り抜ける中、おかざきさん、と咳き込みながら目の前の人の名を呼ぶ。まだ、今なら戻れる。戻った方がいいという意を込めて。けれど、彼は、腰に添えられた私の左手に自身の手を重ねるだけだ。
高速を降りたバイクが暫く港町を走り、潮風の匂いが近くなる。バイクが止まったのは海岸近くで、少し離れたところに船着き場が見える。停船する船の側まで来て、先に降りた岡崎さんが、後ろで火照った頭をかくかくと不安定に揺らす私の頬とおでこに手を当てる。手袋もせず、潮風に晒されながら長時間運転していた為に、いつも暖かい岡崎さんの手は冷えきっている。けれど、熱い身体にはひんやりとして気持ちがよかった。思わず両目を閉じ、その手を享受してしまう。
「熱、上がってんな」
岡崎さんは私の頭を軽く撫でたあと、私をよいしょと背負い、子供をあやすみたいに軽く揺らした。
「しばらく寝てろ。着いたら起こしてやるから」
「どこ、いくんですか」
シラユキさんの言ってた通り、私に逃げる場所なんてないのに。岡崎さんは、ふわふわした声で尋ねる私に軽く笑いながら、「ナイショ」とだけ答えて、船着き場の待合室の様な所に足を進めた。暗闇を、明るいライトが、淡く、優しく照らしていた。中は暖房が効いているしく、先客の野良猫達が寒さを凌ぐ為に、中でゴロゴロと寛いでいるのが岡崎さんの肩越しに見えた。室内に入っていっても猫ちゃんたちは逃げることはなく、むしろ足元に近寄ってきて、よく来たな、まぁ入ってお前らも暖まれよ、と言わんばかりに、岡崎さんと私を見上げて鳴いている。
暖かい空間に、柔らかいオレンジと白の照明。にゃあにゃあと可愛らしい猫ちゃん達の鳴き声。そして、ぽかぽかとし始めた岡崎さんの背中の温度と匂いに包まれて、疲れ果てた私の意識はあっさりと落ちた。
0
お気に入りに追加
134
あなたにおすすめの小説

お見合い相手は極道の天使様!?
愛月花音
恋愛
恋愛小説大賞にエントリー中。
勝ち気で手の早い性格が災いしてなかなか彼氏がいない歴数年。
そんな私にお見合い相手の話がきた。
見た目は、ドストライクな
クールビューティーなイケメン。
だが相手は、ヤクザの若頭だった。
騙された……そう思った。
しかし彼は、若頭なのに
極道の天使という異名を持っており……?
彼を知れば知るほど甘く胸キュンなギャップにハマっていく。
勝ち気なお嬢様&英語教師。
椎名上紗(24)
《しいな かずさ》
&
極道の天使&若頭
鬼龍院葵(26歳)
《きりゅういん あおい》
勝ち気女性教師&極道の天使の
甘キュンラブストーリー。
表紙は、素敵な絵師様。
紺野遥様です!
2022年12月18日エタニティ
投稿恋愛小説人気ランキング過去最高3位。
誤字、脱字あったら申し訳ないありません。
見つけ次第、修正します。
公開日・2022年11月29日。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。
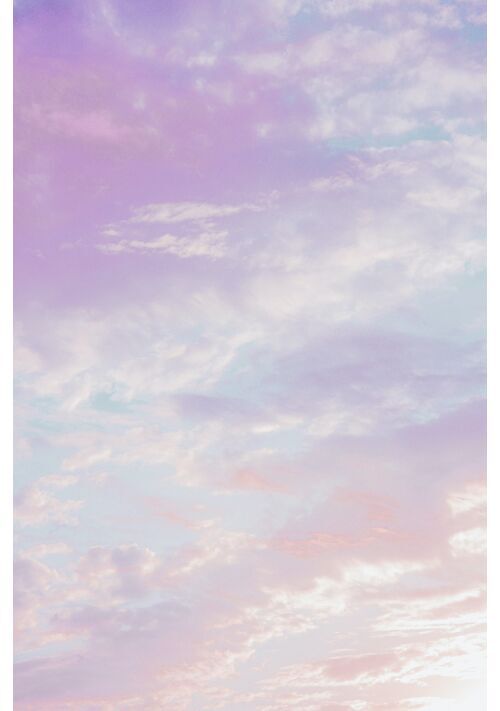
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

【R18完結】エリートビジネスマンの裏の顔
白波瀬 綾音
恋愛
御社のエース、危険人物すぎます───。
私、高瀬緋莉(27)は、思いを寄せていた業界最大手の同業他社勤務のエリート営業マン檜垣瑤太(30)に執着され、軟禁されてしまう。
同じチームの後輩、石橋蓮(25)が異変に気付くが……
この生活に果たして救いはあるのか。
※サムネにAI生成画像を使用しています

イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。

ダブル シークレットベビー ~御曹司の献身~
菱沼あゆ
恋愛
念願のランプのショップを開いた鞠宮あかり。
だが、開店早々、植え込みに猫とおばあさんを避けた車が突っ込んでくる。
車に乗っていたイケメン、木南青葉はインテリアや雑貨などを輸入している会社の社長で、あかりの店に出入りするようになるが。
あかりには実は、年の離れた弟ということになっている息子がいて――。


【R18】豹変年下オオカミ君の恋愛包囲網〜策士な後輩から逃げられません!〜
湊未来
恋愛
「ねぇ、本当に陰キャの童貞だって信じてたの?経験豊富なお姉さん………」
30歳の誕生日当日、彼氏に呼び出された先は高級ホテルのレストラン。胸を高鳴らせ向かった先で見たものは、可愛らしいワンピースを着た女と腕を組み、こちらを見据える彼の姿だった。
一方的に別れを告げられ、ヤケ酒目的で向かったBAR。
「ねぇ。酔っちゃったの………
………ふふふ…貴方に酔っちゃったみたい」
一夜のアバンチュールの筈だった。
運命とは時に残酷で甘い………
羊の皮を被った年下オオカミ君×三十路崖っぷち女の恋愛攻防戦。
覗いて行きませんか?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
・R18の話には※をつけます。
・女性が男性を襲うシーンが初回にあります。苦手な方はご注意を。
・裏テーマは『クズ男愛に目覚める』です。年上の女性に振り回されながら、愛を自覚し、更生するクズ男をゆるっく書けたらいいなぁ〜と。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















