6 / 124
男と女
しおりを挟むまるで、味のないガムを噛んでるみたいだ。高級なお魚の煮付けの筈なのに。もぐもぐもぐもぐと口を動かすも、なんの味もしない。料理人の方から事前に説明を受けた、お出汁をよく効かせたというお味噌汁も今の私にはお湯を飲んでる感覚しかない。時間もかかっただろう、丹精こめられたお料理たちがかわいそうだった。この子たちももっと味のわかる人間に食べてもらいたかっただろうに。私に、もう少し余裕があれば、おいしいおいしいと舌鼓を打つことも出来たかもしれない。しかし如何せん、タイミングが悪かった。
西園寺さんが運転する車に連れられ到着したのは、旅館の従業員の女の子も香澄ちゃんも一生に一度は行ってみたいと話していた有名な高級料亭だった。どうやら旅籠屋も兼営しているらしく、大きな荷物を所持する観光客もちらほら居た。
こういった高級感溢れる場所は私には敷居が高い。緊張からガチガチになっていた。
太刀川さんと西園寺さんは常連さんらしい。案内役の仲居さんの後ろを慣れた様子で歩いている。太刀川さんの後ろをへろへろとついていく私の姿を見て、仲居さんがあれ? なんでこんな子供が? みたいな表情をしたのは気のせいじゃないだろう。
案内された広い和室には二人分のお膳しかない。私はお酌係りでいいのかな。
「私は外に控えておりますので」
そう言って、西園寺さんは退出してしまった。え、ちょ待てよ、なんて声をかける隙もなかった。……かける勇気も無いのだが。
仲居さんが和室と繋がっているお隣の障子に用事があったのか「少し失礼しますね」と言って小さく開けた障子の向こう、ちらりと見えた光景に絶句する。お布団がひとつ、綺麗に敷かれていた。それがどういう意味なのか、仮にもそういった類の旅館で働いているのだ。わからないわけがない。しかし、認めたくない。
見ていない。私は何も見ていない。断じて、何も、見ていない!
頼みの綱の仲居さんもすぐに「お料理お運びします。ごゆっくり」と出て行ってしまわれた。やたらとねっとりとした「ごゆっくり」だった。や、やめて、二人きりにしないで! カタカタと震える手を止めることが出来ない。
一通りのお料理が運ばれてきても、特に話題は無いままだった。正面にいらっしゃる太刀川さんの顔を一度も見ることが出来ない。私にとっては何とも気まずい食事を終えた。
今は太刀川さんの隣について、いつも通りお酌している。いつも通りの行動だからこそ、前回の出来事を嫌でも思い出してしまう。うわぁああもう、なんなんだ、どうしたらいいんだ、どんな顔してたらいいんだ。顔が熱い。でもこのままではいけない。ごきゅり、とつばを飲み込んだ。
「……あ、あの……さっきは、すみませんでした」
「……何の謝罪だそりゃあ」
あなたの行動を止めるために、飼育員が如くガッチリ捕獲してしまったことです。とは言えず、邪魔をしてしまってと答える。太刀川さんはそれでなんのことか察しがついたのか低く笑った。
「邪魔したなんて、微塵も思ってねェんだろ」
「……」
「ありゃあオメェが自分の意思で取った行動だろうが。その結果、見たくもねぇもん見なくて済んだんだ」
「……」
「機嫌取りで謝るんじゃねェよ」
「……すみません」
恥ずかしい。結局は、自分のことばっかりで。この人には全部お見通しで。保身のことばかり考えているずるくて弱い人間なんだと見透かされていて。自分が、恥ずかしくてたまらなかった。軽蔑されても仕方ないと、顔が上げられない。しかし、太刀川さんはまぁでも、と続ける。
「気弱なオメェにしちゃ上出来だったじゃねぇか」
ぽんと頭の上に置かれた手が、よく出来たねとわんちゃんを褒める様に私の頭を撫でた。じんわりと瞼が熱くなる。ここにやって来てから、誰かに誉められたことなど一度もなかった。嬉しいような、なんだかむず痒い気持ちになる。
お酒が無くなったことに気づく。丁度いいや、少し頭も冷やしてこようと「おっおさけもらってきますね!」と勢いよく立ち上がった瞬間だった。
「っう、うわっ!?」
後ろから手首を思い切り引っ張られ、身体が暖かいものに包まれた。お香だろうか、煙草と入り混じった、でもいい匂いがした。え、なにこれ、なんなのこれ、どういう状況? 後ろから力強く抱きしめられて、いる。顔の少し後ろ、右横から私じゃない人の微かな呼吸音が聞こえる。暖かいなんてもんじゃない。……あつい。
「たっ………たちかわさ、ひっ」
濡れたものが、首筋をなぞった。時折、ちゅ、ちゅと恥ずかしい音が首から、至近距離で聞こえてくる。恥ずかしくて、くすぐったくて身をよじる。それは許さないと言わんばかりに、後ろから肩とお腹を逞しい腕でより動かない様固定されてしまった。
どうしようもできない。目をぎゅっとつぶり、私を抱く太刀川さんの刺青の入った腕を離してほしいという意図でも掴む。が、びくりともしない。顔を背けても、余計に露わになった首筋に唇を当てられてしまう。
「っ、や、や、まっ、まって」
「……」
「ひぅっ!?」
くちゅ、と水音が鼓膜に響いた。な、な、と全身の熱が更に上昇する。太刀川さんは私の右耳を形にそって舐めてみたり、食んでみたり、耳朶をやんわりと噛んだりしている。そのたびに、太刀川さんの熱い吐息と息遣いといやらしい水音が否が応でも耳に入ってくる。頭がどうにかなりそうだ。太刀川さんの唇と舌の動きがリアルに伝わってくる。いやいやと抵抗しようとも相手は男の人で、私は好き勝手されるしかなくて。頭は沸騰し、私の思考回路はキャパシティの限界を超えようとしていた。
いつの間にやら向かい合わせにさせられる。正面から首やらなんやらに口付けてくるこの人の意図はなんなんだ。会合にしろ、この行為にしろ、なんだってこの人は私なんかにこんなことするんだ。以前のときと同じく、なけなしの力で肩を押し返そうとする。今度は手首を掴まれ何も出来ない。ひぃひぃと涙目になっている私を太刀川さんはその青い瞳でずっと見ていた。正面から見る眼差しが、とても熱い。
んちゅ、と唇がくっついた。あっもうだめだ。もう限界。わけがわからん。以前された、ただくっつけるだけのものとは明らかに違う。色んな角度から押し付けられる。食べられる、と思った。息がうまくできない。
「んっん、んぅ、」
「……志紀、口開け」
は、と太刀川さんが熱い吐息を漏らして至近距離で私に言うが、むりだよ、頭が働かないよ。太刀川さんから顔を逸らして小さい抵抗をするもまた唇を押し付けられる。ずっとそのまま息も出来ないでじっとしていると、とうとう限界を迎えてぷは、と口が開いた。その隙を見逃さず、太刀川さんはぬるりとしたものを私の口に入れてきた。は、なにこれ、なにこのぬるぬるとしたの。
「んっんむっ!? ふぁ、っう」
私の口内を掻き回すこれはなんだ。した? した!? なんで!? なんで舌入れるの!? 理解出来ない事象にまたも激しく抵抗するも、逆に太刀川さんは私の舌を絡め取ってしまう。
やっと離してもらえたときは、ぜえぜえと息が荒くなっていた。まるでマラソンした後の心臓のバクバク感が私を襲う。まって。ちょっと、タンマ。ほんとにだめ。ポケ●ンセンターに、ポケ●ンセンターに連れて行って。お願いだから。たすけて。
ぐったりとした私をよそに、再びちゅ、ちゅとわざとらしく音をたてて顔に、ちゅ、ちゅーをしてくる太刀川さんが次に手をかけたのは、私の着物の前合わせだった。
ちょっとまって。
一気に冷静になる。頭の中に居る色んな私が緊急会議を始めた。ここまで来たら流石の私でも太刀川さんが何をしようとしているのかわかる。い、いや、抵抗してはいけないのか? そりゃそうでしょう。生活全て何から何までお世話になってるんだ。私が出来ることなら、こんな貧相な体でも求められるというならば、このひとの望む形で恩を返した方がいいに決まっている。
でも本当にそれでいいのかと、赤い目の兎のぬいぐるみを抱えた幼い私が言った。家族の顔が頭に浮かぶ。私を大切に育ててくれた大事な人たち。今まで散々な迷惑をかけて、苦労をさせた家族。ここから帰ることが出来たとき、私は真正面から顔向け出来るのだろうか。
小さいころ、ひとりっこで友だちも上手く作ることができなかった、情けない弱虫の私の遊び相手になってくれた、亡くなったおじいちゃんの顔が浮かぶ。色んなことを教えてくれた。昔の遊びも、勉強も、生き方も。
『志紀。優しく、気高く、聡明に、他人に馬鹿にされても、自分自身に恥じないひとになりなさい』
なんで、こんなときに思い出すんだろう。こんなことでしか恩を返せないと思う孫を、流されるまま男の人に抱かれてしまう孫を、おじいちゃんはどう思うだろう。天国で責めるだろうか。情けなく思うだろうか。呆れるだろうか。幻滅するだろうか。悲しむ、だろうか。
「……い、……いや!」
着物の合わせ目に大きな手を入れられたところで、私はここに来てから一番大きな声を出した。太刀川さんは動きを止め、私を解放してくれた。ぐすぐすと鼻を啜り、ぼろぼろと次々流れる大粒の涙を留めることが出来なくて、手で顔を覆った。
「ご、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい」
今から私が吐き出すことを聞いて、太刀川さんは私をいろんな意味で役立たずと判断し、捨てるかもしれない。 路頭に迷うことになるかもしれない。 はたまた、あの日の男のように斬り捨てられるかもしれない。でもこれだけはわかる。私が、私のなかに大事にしている何かを太刀川さんに譲ってしまえば、私はどうしようもないことになってしまう。後戻り出来なくなってしまう。もう、本当に、遠坂志紀という人間は駄目になってしまう。
「ごめんなさい。許してください。私、出来ることはなんでもします。でもこれだけは、これだけは許してください。勘弁してください。お世話になってる分際でこんなこと言っちゃいけないのも、理解してます。でも、お願いします。ごめんなさい」
何度も何度も頭を下げた。ぼとぼとと落ちた涙が畳を濡らす。やばい。鼻水も落ちたかもしんない。いいよ。もうどう思われたって。どうしてもこれだけは譲りたくないのだ。勿論殺されたくはない。だけど、だけど。
「オメェは相変わらず、謝ってばっかりだな」
太刀川さんは怒ることも呆れることも責めることもなく、乱れた私の着物と髪を直してくれた。未だにぼろぼろぐずぐずと典型的な子供の泣き方をしている私の頭に手を乗せ、先ほどのように撫でた。
「ここで手籠めにしちまえば、後が楽だってこたァわかってんだがな」
ままならねぇもんだ、と太刀川さんはくつくつと笑う。青い瞳が、ぐずぐずになっている私を見た。
「たまには様子見にこい」
「よ、ようす?」
「オメェが寄越したあの植物」
「サボテンです……」
「成長はしてるみてェだが、まだまだ花は咲きそうにねぇな。蕾すら見せやしねぇ」
「まだ早すぎます。休眠期です」
「らしいな」
その後のことはよく覚えてない。太刀川さんに「今日は急に呼び出して悪かったな。ゆっくり休め」と、西園寺さんの車に乗せてもらった。太刀川さんはまだ料亭に残っていた気がする。
車の窓から夏祭りが催されているのが見えた。浴衣を着たたくさんの人が屋台の焼きそば、綿あめを食べていたり、射的や金魚すくいなどの遊びを楽しんでいる。その中にお父さんとお母さんに手を繋いでもらい、手首に水風船をひっかけたちっさな女の子が見えた。その幼気で無邪気な楽しそうな姿を見てただ、羨ましいと思った。
「かえりたいなぁ…」
ぽつりと零れた言葉は、運転席にいる西園寺さんに聞こえたかもしれない。じわりと、視界が滲む。かえりたい、ここじゃない、私が生まれ育った家に、かえりたい。
「で?」
「で、って……。終わり、だけど……」
「ウソ、マジで何も無かったの? セックスしてないの? アンタ太刀川に一発もヤらせなかったの? マジで泣き落としで中断させたの!? あの太刀川がまだあんたに手出してないの!? うそでしょ!?」
「あっあったよ! 十分色々あったよ! というかここ外だから。人いっぱい居るから。香澄ちゃん声おっきいから……!」
「はー!? キスのひとつやふたつなによ! ちょーっと舌入れられただけでぇ! そんなもんはね、挨拶よ! グリーティングよ!」
「わー! わー! 声! お願いだから声抑えてぇええ!」
「ったく。いつも以上に死人みたいな顔で帰ってきて首にえらいキスマークつけられてたから、遂に無理矢理ヤられたのかと思ってたのに。なのに蓋開けたらこれ! はーっ。やってらんないわマジで。慰めてやろうと思ってアイス奢った私がばっかみたい」
そう言って荒々しく、まるでフライドチキンを食べるかのごとくソフトクリームにかぶりつく香澄ちゃんは非常に男前だ。そんなに一気に食べて頭キーンってならないんだろうか。
あれから数日が経った。あまりのショックにお仕事以外では部屋に引きこもりがちになり、覇気のない、 明らかに魂をどこかに落っことしてきてしまった私を見かね、お休みの日に香澄ちゃんが外へ連れ出してくれた。暑い夏といったらアイスでしょ! と香澄ちゃんはアイスクリームが人気のお店に連れて行ってくれた。その上私にチョコレートのソフトクリームまでご馳走してくれた。
もぐもぐとアイスの上に乗っていたクッキーを食していると、何があったのかと追求され、もごもごと洗いざらい話した。そして返ってきたのは罵倒の嵐である。明らかに弱り切っている相手にも、その容赦の無さはまさに香澄ちゃん。いっそ清々しい。あれれ目から汗が出てきた。
「まぁ今まで生娘のままだったってのも不思議な話だけどさ。へぇふーん。まさかねとは思ってたけどそうなんだ」
「なっなにが?」
「アンタ、もしかしたら太刀川にただの囲いのひとりとは思われてないかもよ」
「へ、……え!?」
「お。もう囲われてるってのは否定しないんだ?」
「……それはもう、流石に」
あんなことされて、違うと主張するのはもう難しいだろう。なんで私なんか、と考えるばかりだがそれを口にするとますます香澄ちゃんからの罵倒を受けそうなのでお口にチャックした。
「そりゃそうよね。実際手出されてまだ違う違う否定してるんなら、鈍いとかのレベル超えてただの阿呆よ。殴り飛ばすとこだわ」
「(過激派だ……)」
「遊びだったらいいのよ。単純に囲いのうちの一人だってんなら、飽きられたとしても後腐れなく捨てられて終わることが殆どだから。でも、ああいう色んなモン背負ってる男に本気になられるのは厄介よ。特に、アンタみたいなのには太刀川は重すぎる。潰されるのがオチね」
「まさか! 私なんかに太刀川さんが本気になるわけないよ! 周りにあんなに綺麗なひといっぱいいるのに、わざわざ私みたいなの選ぶわけない」
「でたよ『私なんか』。うっざいわね。なんでそんな自分に自信ないの。そりゃあ、あたしらに比べりゃ美人じゃないしスタイルも微妙だけどさ、別に見れないほどのブスって訳でもないじゃん」
「私喜んでいいのかなソレ……。ほら、私、暗いし、つまんないし……すぐひとのことイライラさせちゃうし……」
「じゃあどうしてそのなんかなんか言ってる根暗女を会合に付き合わせたってのよ。アンタが呼ばれたんでしょ。 みんな大騒ぎだったんだから」
「あの、それなんだけど。前回までは女将さんが努めてたんだよね。会合に同席するって、どういう意味があるの?」
「は? 知らなかったの?」
「う、うん。女将さんに呼ばれておめかしして貰って、すぐに現場に投入されたから。時間もなかったみたいで詳しいことは何も聞けてなくて……」
「慣わしたいなもんよ」
「ならわし?」
香澄ちゃんはソフトクリームのコーンの部分をバリバリ食べ、飲み込んでから話してくれた。
「その組のシマで行う会合の場合、頭はひとり女を連れてくることになってんの。いくら同盟結んでようとも、別の組のシマに腰を下ろす訳だから、招かれた組の連中は警戒しなくちゃならない。特にトップクラスの頭が揃う訳だから、一気にまとめて潰されるってことも有り得ない話じゃないのよ」
「……」
「そこで、昔どっかの組のおえらいさんが取り決めたのよ。会合を開くシマの組長は己と一蓮托生を誓わせる女をひとり同席させろってね」
「い、いちれんたくしょう?」
「運命共同体ってことよ」
「いや。言葉の意味ではなく」
「つまり、 会合に呼ばれる女は頭のステータスを表してるみたいなもんなのよ。 どんなにいい女を侍らせてるかってね。悪く言えば人質ともいうかしら。大事な女が場にいちゃ満足に暴れることだって出来ないでしょ」
「……でも、だって慣わしって……。そんな律儀に守るものなのかな」
確かに、極道はよく義理と人情がどうとよく言われはするけれど、現実はどうだろうか。昔ながらの慣習を守り続ける様な、そんな律儀さが彼らにあるのだろうか。
「アンタがここにくるまでその役割を担当してた女将の前でそれ言ってみ。刺されるわよ」
「……え、まって。じゃあ女将さんって、え?」
「太刀川の愛人のひとりだけど」
「……」
「女将は昔天龍が睨み合ってた組長の愛人だったのよ。で、天龍との抗争でその組長が太刀川に首跳ねられて、それから~……なんやかんやあって太刀川の囲いになった」
「なんやかんやってなに!? 肝心なとこ飛ばし過ぎじゃない!? なんで? 何がどうしてそうなった!?」
「なに。復讐劇にでもなると思った?」
「そっそりゃあ、だって恋人が殺されたって聞けば……」
「ばか。愛人だっつの。そんなお綺麗なモンじゃないわ」
「……」
「あたしはタイプじゃないけどさ。やっぱ太刀川って綺麗なツラしてるもん。むさ苦しいオヤジの相手するばっかりの日常に突然、若くて将来性のある、それもとびっきりの男前が自分のこと攫ってくれたってんならそりゃあどんな女でも落ちるでしょ」
「そういうもんかな……」
「そういうもんよ。あんたが考えてるより単純なのよ。男と女なんて」
難しい、と思った。ほんとうに単純なのかな。女将さんが太刀川さんに心惹かれるのにもっと複雑な何かがあったんじゃないかと思えてならない。でも香澄ちゃんの言うとおり、人間そんなものなのかなとも思う。その答えを確定させるにはまだまだ私には経験値が足りなすぎた。
「まっ、あたしも太刀川はどうせ気まぐれであんたに構ってるだけなんだろうなって思ってたクチだし、太刀川の考えてることなんかよくわかんないんだけどさ。一応あんた、色々と考えて覚悟しといた方がいいかもよ」
「……色々って?」
「本気じゃなくてもそうじゃなくても、太刀川の女でいるってことがどういうことかよ。あんたは否定したいんだろうけど、太刀川の方はあんたのこと、自分の女だって考えてることは明白なんだから」
あっ、アイス無くなったし新しいの買ってくる~。水も取ってくるわと軽やかに席を立った香澄ちゃん。あんなに細いのによく食べるなぁ、あの子。
香澄ちゃんが戻ってくるまでの間、また私はちいちゃな脳みそでどうにもならないことを考え始めてしまうのだ。考えても考えてもやっぱり正解は出て来なくて、ぷすぷすとショートしたままの頭の回線から煙が出るばかりだ。
「いけませんよー。女の子がこんな黒い卑猥物を連想させるもの食べてちゃぁ」
手に持っていたソフトクリームが突然宙に浮いた。へ? と思っているうちに、後ろでバリバリとコーンを食べる音がする。振り返るとそこには頬を膨らませ、リスかハムスターの様にもぐもぐと口を動かしている岡崎さんが立っていた。
「おっ岡崎さん! て、それ私のアイス……」
「はー、ごっそさん。やっぱ夏にはアイスだよなぁ、暑くて死にそうになってたんだよ。丁度良かったわ」
「あなたは会う度に何かしらの理由で死にそうになってますね」
「お前も団子だのアイスだの、会う度甘いもん食ってる確率高いですね。うら若き乙女がいけませんよ~。油断してたらすぐにブクブク太るぞ。シキ・デラックスになっちまうぞ」
「余計なお世話です! いいじゃないですかシキ・デラックス! 上等ですよ! 今私はあれぐらい余裕のある女性(?)になりたいんですよ! ほっといてくださぃいい。うわぁあん」
「面積に余裕のある人間になりたいの? なんで今日そんな情緒不安定なの?」
岡崎さんは香澄ちゃんが座っていた真正面の席にどかりと座り、頬杖をついてテーブルに突っ伏している私を見た。なんだか今はこのひとの顔を見たくなくて顔をそらしてしまう。しかし、そらした方向に岡崎さんが椅子を動かし、私の視界に入ろうとする。反対方向に顔を向ければやはり岡崎さんもガタガタ椅子をうるさく移動させ、私の視界真正面を陣取った。ちょ、ほんとにうるさい。諦めて岡崎さんをちゃんと視界に入れると、彼は満足そうに笑った。
「ってゆうかお前ひとり? ひとりでこんな洒落た店でソフトクリーム食ってんの? おまえそれは……ちょっと……」
「なんですかその可哀想なものを見る目は。違います。ちゃんとお友達ときてます」
「あ、そうなの? お前ちゃんと友達いたんだ。あ、京都一緒に行きてぇって言ってたやつ?」
「い、いますよ。京都云々は別のお友達です。なんですか、私、そんなに友達居なさそうに見えますか」
「居なさそうに見えまーす。友達100人作るが絶対出来ないタイプに見えまーす」
「それ出来る人の方が少なくないですか?」
「馬鹿言えお前。今や顔見たことねぇ声も聞いたことねぇネット上の相手を友達って言っちゃう暗黒の時代だぞ。果てはオフパコだのなんだのと男女の関係にまで発展する淫欲の時代だぞ。そんな輩からしたら100人友達作ろうなんざ余裕のよっちゃんだ」
「ただれた時代ですね。全く」
「いやいや、なにババアみてぇなこと言ってんの? まさにお前ぐらいがドンピシャな年頃じゃん。イン●タ映えばっかり考える世代だろうが」
「イン●タやってません」
「志紀、あんたも水いる……ってなにそいつ、知り合い?」
右手に抹茶アイス、左手に水の入った紙コップを持った香澄ちゃんが怪訝な顔で私と岡崎さんを見比べた。岡崎さんも香澄ちゃんと同じく私と香澄ちゃんを見比べ「お前の友達?」と私に尋ねた。こくりと頷く。へーと岡崎さんは眉間に皺を寄せている香澄ちゃんを見上げる。
「おめぇの友達にしては意外なタイプだな。 性格キッツそうだけど、なかなか別嬪のねーちゃんじゃん。なんだよ志紀。こういうときは俺に紹介し……」
「岡崎さん?」
「なっなによあんた。人のことじろじろじろ見て。金取るわよ!」
岡崎さんは立ち上がり、香澄ちゃんの目の前で顎に手を当て上から下までじっくりと観察し始めた。見ず知らずの男に突如凝視される香澄ちゃんも、珍しく動揺を隠せないでいる。岡崎さん、と窘める様に声をかける。彼は降参ですと手を挙げ香澄ちゃんから距離をとり、振り返った。
「やっぱいいわ」
「え」
「俺の内なるセンサーがこのねーちゃんは関わるとヤベエって感じ取った。志紀、お前も気をつけろよ。俺の勘はよく当た」
「んだとゴルゥアアア!」
「ふぐおぉおっ!」
「うわぁあ岡崎さんんん!」
香澄ちゃんは抹茶アイスを私に渡して岡崎さんの灰色の髪を思い切りひっつかみ、持っていた水を岡崎さんの鼻に流し込んだ。岡崎さんは真っ白な顔で苦しそうにふごふごもがいている。強制鼻うがい……拷問だ……これはまさしく拷問だ……。見てるこっちまで鼻の奥が痛くなってきた。
「あーー鼻水止まんなくなっちまったじゃねぇか。もうネバネバのは出てこねぇよ。サラサラな鼻水しか出てこねぇよ。垂れ流しの蛇口状態だよ。くそ、なんでこうも俺の周りにはろくな女がいねぇんだ。あ、また垂れてきた。志紀、ティッシュくれティッシュ」
「どっどうぞ……」
「あたしの内なるセンサーがこの男はやばいって感じ取ったわ。志紀、どういう繋がりだか知んないけど、こんな男とっとと縁切りな。人生メチャクチャにされるわよ。あたしの勘はよく当たるんだから」
「ちょっとちょっとー。勝手にひとのイメージ下げること言わないでくんない。俺ほどまでに善良な人間もそうそう居ねぇぞ。あー傷ついた。俺の硝子の心は粉々に打ち砕かれ修復不可能です。慰謝料を要求します!」
「どこが善良だ。いい大人がこんな真っ昼間からうろうろして。なに、あんたニート? 社会のクズ?」
「誰がニートだ。こちとら仕事帰りでへとへとだっての」
「どうでもいいけど、まず見た目からして危なすぎるのよ。怪我だらけだし。特になにその髪、ブリーチ失敗したの? 今時赤のカラコンなんて流行らないのよ。かっこいいとでも思ってんの? プッ、ダッサーイ」
「なんなのこの女。言いたい放題言い過ぎじゃね。初対面だよね、俺ら初対面なんだよね。自前ですー。これはまごうとなき自前なんですー。カッコつけてる訳じゃありませんー」
「あ。すげぇ、ほんとに地髪じゃん」
「いだだだだだだ引っ張んな引っ張んな! 抜ける! 禿げる!」
す、すごい。流石香澄ちゃんだ……。会って数分も経ってないのにここまで打ち解けてる。岡崎さんもコミュニケーション能力高いから既知の仲の様なやりとりが目の前で繰り広げられている。
ティッシュを鼻につっこんだ岡崎さんは 隣の空席のテーブルからわざわざ椅子を引っ張ってきて、私達のテーブルで香澄ちゃんの買ってきた抹茶アイスを許可無しに食し始めた。ほ、ほんと遠慮無いなこのひと! 香澄ちゃんも呆れかえって、もはやアイスのことについてはコメントしなかった。
「っていうかあんたら何なの? ほんとどういう繋がり?」
「どうもこうも……。色々あって、岡崎さんとはただの知り合いで」
「おいおい野暮なこと聞いてんじゃねぇよー。見てわかんだろ? 俺とこいつはもう切っても切っても中々切れないネバネバの納豆みたいな関係なんだよ。俺達はソウルで繋がっちゃってんだよ。なっ志紀ちゃん」
「誰が志紀ちゃんですか。肩組まないで下さい。違うからね香澄ちゃん。この人とはそんなんじゃないからね。ネバネバしてないからね」
「今更なに照れてんだよ。全くしょうがねぇ奴だなぁ。安心しろよ。俺にはお前だけだ」
「何ですかそのキメ顔。言っときますけど全然かっこよくないですからね。全くときめきませんからね」
「はん!? おめぇ随分生意気な口聞く様になったじゃねぇか。俺ァそんな子に育てた覚えはありませんよ!」
「育てられた覚えもありませんし」
「おーおー口答えする小生意気なお口はこれかぁ?」
「いっいひゃいいひゃいいひゃい! ひゃなひてぇ!」
「おおよく伸びる伸びる。モチみてぇだな。醤油かけて食ったらうまそう。つかやっぱ甘いもん食いすぎじゃね。ぷにぷにしてんぞお前」
じゃれあう(というよりも一方的にいじられている)私達の真向かいで香澄ちゃんは訝しげな、というよりも少し困惑した様な複雑な表情をしている。
頬を掴まれたままながらもどうしたの、と声をかけようとしたらパッと手を離される。岡崎さんは「アイスも食ったことだし帰るわ。 じゃーな小娘ども 」と帰ってしまった。突然現れて突然去っていく。嵐みたいなひとだ。いや、アイドルの方ではなく。
「……ねぇ志紀」
ぎゅむぎゅむ引っ張られたせいでまだじんじんする頬をさすっていると、香澄ちゃんが先程と同じく何ともいえない複雑な表情で私に尋ねた。
「あんたって、あんな風に男とすらすら話せる子だった?」
「え」
「特にああいう、はっきりもの言ってくるタイプの男が一番苦手なんじゃなかったっけ」
随分と楽しそうに見えたけど、と香澄ちゃんに指摘される。
頬をさすっていた手を止める。確かに、岡崎さんはどちらかというと私の中では苦手とするタイプのひとだ。陽気で、誰とでも仲良く出来て、たぶんひとの輪の中心になれるひと。岡崎さんのような人とあんなじゃれあいをすることだって、本来の私ならばあり得ないことだ。
「なんか、岡崎さんって話しやすい雰囲気作りが上手くて、それに乗せられちゃってるのかも」
「ふーん。……ほんとにそれだけかしらね」
「ん?」
「志紀。まさか、あいつのこと気になってたりとかしないわよね」
「気になるけど……」
「は!?」
「けが大丈夫かな、とか」
「そうじゃないわよこのおばか! 異性として気になってるのかって聞いてんの!」
「え、ええ~? 私が岡崎さんを? それはないよ。岡崎さんとは年も離れてるし、向こうは大人のひとだよ?」
「今時そんな年の差に拘る奴なんて居ないけどね。太刀川だってこどものアンタに構ってる訳じゃん」
「うっ……。そういえば、太刀川さんていくつなの? 岡崎さんとそう変わらない様な……もう少し上のような感じもするけど」
「知らないわよ。あたし太刀川興味ないし。今度会ったとき自分で聞きなさいよ」
「今度……そうか、今度があるのか。そっか……」
何があったかを再び思い出してずーんと気分が落ち込む。次こそどんな顔で会えばいいんだ。まともに顔を合わせられる自信がない。テーブルに突っ伏してうーうーと唸り始めた私に対し香澄ちゃんから何の罵倒も降ってこない。いつもなら、うじうじするな! とかうざいとか、鬱陶しいとか言われるのに。ろくな言葉かけられてないな私。香澄ちゃんは眉間に皺を寄せて考え事をしているようだった。
「……香澄ちゃんどうしたの。何か心配事? 私でいいなら話聞くよ? いつも聞いて貰ってばっかりだし」
「いーや別に。あんたは気にしなくていいわ。あたしの考えすぎだし」
「?」
「……あたしの勘は当たるけど、今回ばかりは外れてほしいって、思っただけよ」
0
お気に入りに追加
134
あなたにおすすめの小説

お見合い相手は極道の天使様!?
愛月花音
恋愛
恋愛小説大賞にエントリー中。
勝ち気で手の早い性格が災いしてなかなか彼氏がいない歴数年。
そんな私にお見合い相手の話がきた。
見た目は、ドストライクな
クールビューティーなイケメン。
だが相手は、ヤクザの若頭だった。
騙された……そう思った。
しかし彼は、若頭なのに
極道の天使という異名を持っており……?
彼を知れば知るほど甘く胸キュンなギャップにハマっていく。
勝ち気なお嬢様&英語教師。
椎名上紗(24)
《しいな かずさ》
&
極道の天使&若頭
鬼龍院葵(26歳)
《きりゅういん あおい》
勝ち気女性教師&極道の天使の
甘キュンラブストーリー。
表紙は、素敵な絵師様。
紺野遥様です!
2022年12月18日エタニティ
投稿恋愛小説人気ランキング過去最高3位。
誤字、脱字あったら申し訳ないありません。
見つけ次第、修正します。
公開日・2022年11月29日。

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?
すずなり。
恋愛
私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。
翔馬「俺、チャーハン。」
宏斗「俺もー。」
航平「俺、から揚げつけてー。」
優弥「俺はスープ付き。」
みんなガタイがよく、男前。
ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」
慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。
終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。
ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」
保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。
私は子供と一緒に・・・暮らしてる。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
翔馬「おいおい嘘だろ?」
宏斗「子供・・・いたんだ・・。」
航平「いくつん時の子だよ・・・・。」
優弥「マジか・・・。」
消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。
太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。
「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」
「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」
※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。
※感想やコメントは受け付けることができません。
メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。
楽しんでいただけたら嬉しく思います。
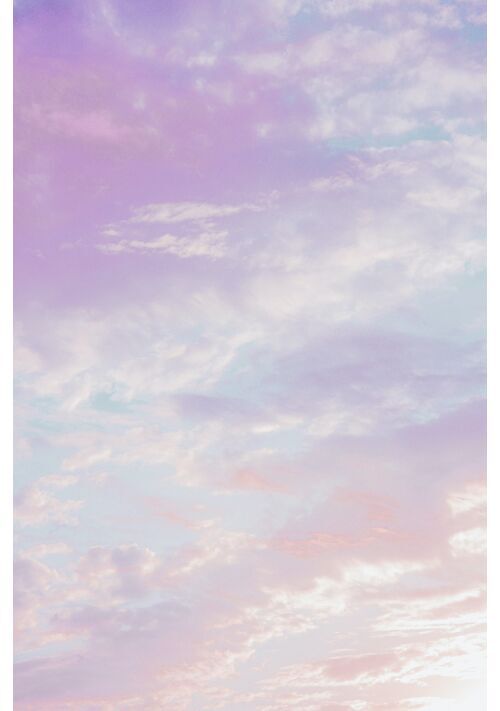
極道に大切に飼われた、お姫様
真木
恋愛
珈涼は父の組のため、生粋の極道、月岡に大切に飼われるようにして暮らすことになる。憧れていた月岡に甲斐甲斐しく世話を焼かれるのも、教え込まれるように夜ごと結ばれるのも、珈涼はただ恐ろしくて殻にこもっていく。繊細で怖がりな少女と、愛情の伝え方が下手な極道の、すれ違いラブストーリー。

【R18完結】エリートビジネスマンの裏の顔
白波瀬 綾音
恋愛
御社のエース、危険人物すぎます───。
私、高瀬緋莉(27)は、思いを寄せていた業界最大手の同業他社勤務のエリート営業マン檜垣瑤太(30)に執着され、軟禁されてしまう。
同じチームの後輩、石橋蓮(25)が異変に気付くが……
この生活に果たして救いはあるのか。
※サムネにAI生成画像を使用しています

イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。

ダブル シークレットベビー ~御曹司の献身~
菱沼あゆ
恋愛
念願のランプのショップを開いた鞠宮あかり。
だが、開店早々、植え込みに猫とおばあさんを避けた車が突っ込んでくる。
車に乗っていたイケメン、木南青葉はインテリアや雑貨などを輸入している会社の社長で、あかりの店に出入りするようになるが。
あかりには実は、年の離れた弟ということになっている息子がいて――。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















