お気に入りに追加
11
あなたにおすすめの小説

愛する貴方の心から消えた私は…
矢野りと
恋愛
愛する夫が事故に巻き込まれ隣国で行方不明となったのは一年以上前のこと。
周りが諦めの言葉を口にしても、私は決して諦めなかった。
…彼は絶対に生きている。
そう信じて待ち続けていると、願いが天に通じたのか奇跡的に彼は戻って来た。
だが彼は妻である私のことを忘れてしまっていた。
「すまない、君を愛せない」
そう言った彼の目からは私に対する愛情はなくなっていて…。
*設定はゆるいです。

【完結】仰る通り、貴方の子ではありません
ユユ
恋愛
辛い悪阻と難産を経て産まれたのは
私に似た待望の男児だった。
なのに認められず、
不貞の濡れ衣を着せられ、
追い出されてしまった。
実家からも勘当され
息子と2人で生きていくことにした。
* 作り話です
* 暇つぶしにどうぞ
* 4万文字未満
* 完結保証付き
* 少し大人表現あり

お飾り王妃の死後~王の後悔~
ましゅぺちーの
恋愛
ウィルベルト王国の王レオンと王妃フランチェスカは白い結婚である。
王が愛するのは愛妾であるフレイアただ一人。
ウィルベルト王国では周知の事実だった。
しかしある日王妃フランチェスカが自ら命を絶ってしまう。
最後に王宛てに残された手紙を読み王は後悔に苛まれる。
小説家になろう様にも投稿しています。
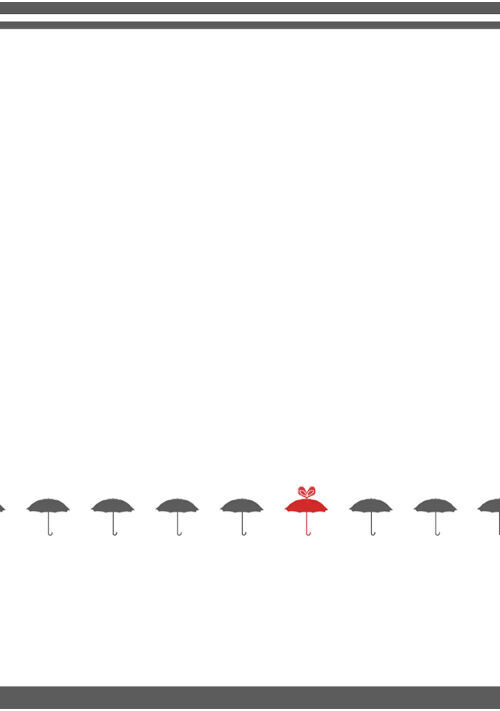
こちら夢守市役所あやかしよろず相談課
木原あざみ
キャラ文芸
異動先はまさかのあやかしよろず相談課!? 変人ばかりの職場で始まるほっこりお役所コメディ
✳︎✳︎
三崎はな。夢守市役所に入庁して三年目。はじめての異動先は「旧館のもじゃおさん」と呼ばれる変人が在籍しているよろず相談課。一度配属されたら最後、二度と異動はないと噂されている夢守市役所の墓場でした。 けれど、このよろず相談課、本当の名称は●●よろず相談課で――。それっていったいどういうこと? みたいな話です。
第7回キャラ文芸大賞奨励賞ありがとうございました。

百合系サキュバス達に一目惚れされた
釧路太郎
キャラ文芸
名門零楼館高校はもともと女子高であったのだが、様々な要因で共学になって数年が経つ。
文武両道を掲げる零楼館高校はスポーツ分野だけではなく進学実績も全国レベルで見ても上位に食い込んでいるのであった。
そんな零楼館高校の歴史において今まで誰一人として選ばれたことのない“特別指名推薦”に選ばれたのが工藤珠希なのである。
工藤珠希は身長こそ平均を超えていたが、運動や学力はいたって平均クラスであり性格の良さはあるものの特筆すべき才能も無いように見られていた。
むしろ、彼女の幼馴染である工藤太郎は様々な部活の助っ人として活躍し、中学生でありながら様々な競技のプロ団体からスカウトが来るほどであった。更に、学力面においても優秀であり国内のみならず海外への進学も不可能ではないと言われるほどであった。
“特別指名推薦”の話が学校に来た時は誰もが相手を間違えているのではないかと疑ったほどであったが、零楼館高校関係者は工藤珠希で間違いないという。
工藤珠希と工藤太郎は血縁関係はなく、複雑な家庭環境であった工藤太郎が幼いころに両親を亡くしたこともあって彼は工藤家の養子として迎えられていた。
兄妹同然に育った二人ではあったが、お互いが相手の事を守ろうとする良き関係であり、恋人ではないがそれ以上に信頼しあっている。二人の関係性は苗字が同じという事もあって夫婦と揶揄されることも多々あったのだ。
工藤太郎は県外にあるスポーツ名門校からの推薦も来ていてほぼ内定していたのだが、工藤珠希が零楼館高校に入学することを決めたことを受けて彼も零楼館高校を受験することとなった。
スポーツ分野でも名をはせている零楼館高校に工藤太郎が入学すること自体は何の違和感もないのだが、本来入学する予定であった高校関係者は落胆の声をあげていたのだ。だが、彼の出自も相まって彼の意志を否定する者は誰もいなかったのである。
二人が入学する零楼館高校には外に出ていない秘密があるのだ。
零楼館高校に通う生徒のみならず、教員職員運営者の多くがサキュバスでありそのサキュバスも一般的に知られているサキュバスと違い女性を対象とした変異種なのである。
かつては“秘密の花園”と呼ばれた零楼館女子高等学校もそういった意味を持っていたのだった。
ちなみに、工藤珠希は工藤太郎の事を好きなのだが、それは誰にも言えない秘密なのである。
この作品は「小説家になろう」「カクヨム」「ノベルアッププラス」「ノベルバ」「ノベルピア」にも掲載しております。

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~
菱沼あゆ
キャラ文芸
突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。
洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。
天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。
洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。
中華後宮ラブコメディ。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

断る――――前にもそう言ったはずだ
鈴宮(すずみや)
恋愛
「寝室を分けませんか?」
結婚して三年。王太子エルネストと妃モニカの間にはまだ子供が居ない。
周囲からは『そろそろ側妃を』という声が上がっているものの、彼はモニカと寝室を分けることを拒んでいる。
けれど、エルネストはいつだって、モニカにだけ冷たかった。
他の人々に向けられる優しい言葉、笑顔が彼女に向けられることない。
(わたくし以外の女性が妃ならば、エルネスト様はもっと幸せだろうに……)
そんな時、侍女のコゼットが『エルネストから想いを寄せられている』ことをモニカに打ち明ける。
ようやく側妃を娶る気になったのか――――エルネストがコゼットと過ごせるよう、私室で休むことにしたモニカ。
そんな彼女の元に、護衛騎士であるヴィクトルがやってきて――――?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















