2 / 9
第二章
十頭、暗躍す ーとがしら、あんやくすー
しおりを挟む
『太政官』とは、明治元年年六月十一日に公布された政体書に基づいて幕末から明治にかけて設けられた官寮名であり、明治政府初期においては行政を司る官庁名でもあった。最高行政機関であることから、明治十八年に内閣制度が発足し廃止されるまでは明治政府と同義でもあった。
天皇を主権者とし、その直下には総責任者である『太政大臣』を置く。実質的な行政の最高責任者である『左大臣』と『右大臣』が置かれ、天皇に対して行政上の責任を負うのは、この太政大臣、右大臣、左大臣の三名のみである。他に、治維新に功績があった人物によって構成される『参議』が在籍し、これらの職責を総合して「太政官」と称し、後年の内閣の様な役割を担う事になっていたのだ。
この制度は、明治維新の混乱により何回も整備統合が行われ、二、三年ごとに機構が全く変貌してしまう事もあったが、西南戦争を経験して組織を強固な物に作り上げ、明治十一年頃に安定した機構となった。
太政官の庁舎は、明治五年三月に皇城内西の丸下に造営したものの、翌六年五月五日、皇城の火災により多くの公文書類もろとも焼失してしまう。即日、赤坂離宮が仮皇居と定められたが、馬場先門内の旧教部省庁舎を活用することとなり、同庁舎に太政官代が設置されたのだった。
その会議室に太政大臣・三条実美と右大臣・岩倉具視、内務卿・大久保利通、司法卿・大木蕎任ら、国政の中心人物が集っていた。
「で、与一は、横浜を離れたのだな」
と、三条に問われた大木が答える。
「はい。手筈通り長崎へ向かいました。しかし、旧征韓党の残党狩り、特に坂上剣山の成敗が叶ったのは収穫でした。戮の運用は順調ですな。佐賀の騒動を御身自ら平定にあたった大久保さんも、これで肩の荷が完全に下りたと云うところですかな?」
無口な大久保は微かに頷いただけだった。が、その代わりとばかりに岩倉が横から口を挟むのだが、「戮す、則ち『罪ある者を殺すの意』とか。毒を以て毒を制す、というわけですな」と、その内容は話しの流れとは直接関係ない上に、皆が分かり切った事の確認にすぎなかった。
概ね、そんな言動の本意は不満の意思表示であり、自分の納得していない事例へと皆を誘導するのが目的である。だが、岩倉が戮の創設に当初から反対していたのは、此処にいる全員が承知していたので、当然、今更の混ぜっ返しには誰も応じなかった。
気を利かせた大木が話題を変える。
「それにしても、妖刀騒ぎの方は、なかなか収まりませんな」
無視された腹いせではないだろうが、またしても岩倉が横槍を入れる。
「そんな怪談じみた風説なんぞは、万人が納得のいく顛末を示さぬかぎり、面白可笑しく広がるに決まっておろう。その為に妖刀とおぼしき刀を片っ端から集めさせ、原因を探ろうとしているのだ。めぼしい学者も今のうちにかき集めておけよ。政府の威信に懸けて、早急に収束させるのだ。こんな世迷い言の類に何時までもかまけておる暇なぞ我らには無い」言い方はともかく、的を射た意見に、皆、今度は意を同じくせざるをえなかった。
「…そうだな」と三条。
「承知しております。その件に関しても、あの御方にお力をお借りすべく、移送に先立って警護の為に与一を長崎に向かわせたのです」大木は、この話題に自ら触れた事に内心では藪蛇だったと後悔しながらも、治安に責任を持つ地位役職として適切に対応している旨を毅然とした態度で示した。
妖刀事件とは俗称であり、要は、日本刀による刃傷沙汰である。実際に殺人まで発展した事例は未だ少なかったのだが、凶器には必ず日本刀が使われている上に、犯人は何かに操られるかのように意識白濁、または前後不覚になった状態で犯行に及んでいるという共通点が、古くから俗信されている妖刀の伝奇と相まって巷に風説された。
まだ、世間が紛擾するところまではいっていないが、事件の構造上、看過できない問題を含んでおり、政府としても看過する訳にもいかなかったのだ。
事件の原因調査の一環として、与一には、旧征韓党残党及び坂上剣山粛清の任と共に、坂上が持つ妖刀・闇の孫六の接収が命じられていたのだった。
「ところで、与一は、戮士の留任を承知したのか?」と、突然、三条は大木に問うた。失念していた懸案事項を一つ思い出したのだ。
「はい」と大木。
「そうか。『毒を以て』も良いが、戮士に事情ありの人間を登用するのも難儀だな」
「しかし、ひとたび任を解けば、奴には野刃所持の罪を問わねばならず、処遇に窮します…留任は我らにも都合が良いかと」
岩倉が、大木の言葉にさり気なく嫌みを挿む。
「ほら見ろ、結局、そうやって厄介事が増すだけだ」
時たま的を射ようとも、所詮、嫌みは何処まで行っても嫌みである。岩倉に打ち止めを宣告するように、此処まで黙って聞いていた大久保が口を開く。治安に関して云えば、内務卿である大久保は、むしろ大木よりも責を担っている立場だった。
「与一の野刃は政府の支給品でなく本人の持ち物であったな。『神斬り』とか何とか大層な名前が付いていたか。そうそう、名前といえば、奴自身の通り名、何故に『与一』なのだ? 那須与一を気取っている訳でもあるまいが…確か、与一の由来は『十余り一』で余一だったものが転じて与一、即ち十一番目の男子に付けられる名前だったはず。奴は兄弟が多いのか?」
一転して饒舌な大久保だった。実は頭の回転が人一倍速い事もあって、ひとたび口を開くと考えた事を咀嚼することなく喋ってしまう癖がある。寡黙で威厳のある男との評判も、饒舌で失敗した反省から過剰に無口を演じている事の誤解に過ぎなかった。
大木が、手元の記録台帳を見ながら答える。
「本人の申し出です。たしか本名かと。元甲賀の忍び、今は紙切り芸人<喜楽亭おもちゃ>を名乗っている養父の言によれば、奴を引き取った際には、自ら与一と名乗り、既に神斬りも所持していた、と記録にあります。流石にこの養父には、神斬りが野刃だとは気付かなかったようですが」
「養子か…いかなる経緯で?」
「さあ、そこまでは。しかし、与一には十一番目の男子の名というだけでなく、余り物の隠喩もあったはず…何やら意味深長ですな」
「余り物の十一男…か」
三条は明かり取りの小窓から見える帝都東京の空を見上げた。
雲一つ無い青空に鳶が一羽舞っている。
鳶は、人の世の雑事に患わされる事もなく、自由に大空を舞う。
三条は、一瞬鳶になりたいと本気で考えていた自分に自嘲しつつ、意識を現実へと―日本の国家最高機関、太政官の最高責任者の責務へと連れ帰った。
「で、あの方の護衛には、他にどのような手立てを講じておるのだ? まさか与一を送っただけではあるまい」
「はい。与一の他に、戮士を数名と―」大木の答弁は続いた。その声を聞きながら三条は無意識に再び空を見上げていた。
元号が明治へと替わって、早八年。
この日本という国が何処へ向かっていくのか。日本行政の最高機関に籍を置く彼等さえも五里霧中の、そのまた最中であった。
東海道といっても、山間部に入ってしまえば獣道に毛が生えた程度、丑三つ時のこの時刻では、当然のことながら擦れ違う旅人もいない。
山道を囲み生い茂る木々の僅かな合間から漏れ届く満月の明かりだけが足下を照らしている。それでも、常人には到底歩けぬ暗さであったが、与一の訓練された夜目には何でもなかった。
旅装束の与一は、暗がりで端からは見えはしないにも拘わらず、それだけに無駄ともいえる相変わらずの地笑顔を湛えていた。
夜道を急ぐ与一。
与一がうっすらと明るい山道の稜線へと消え去った後、自らの気配を悟られないように、山道脇に建立されている道祖神の陰から、二つの人影がその後ろ姿を見据えていた。
一人は、山伏の格好をした大男であった。一珠が握り拳大の大きな数珠を首から下げている。
もう一人は、背格好が与一によく似ていたが、編み笠を深くかぶって顔は見えない。
山伏が「十騎男」と呼びかけると、その男は編み笠を取った。驚いたことに、現れた顔も与一にそっくりだった。ただし、その表情は与一のように笑顔を湛えることはなく、嫌悪感に歪んでいた。
「あいつ、まさかと思ったが、本当に生きてやがった」
「坂上程度では、役不足どころか、傷も負わせられなかったな。まあ、『妖刀憑き』状態、では、真の実力を出し切れなかったか…」
「この俺様が、直々に引導渡してやる」その言葉に触発される十騎男。
山伏が、ガシッと十騎男の肩を掴んで止めた。
振り返る十騎男。「止めるなよ、兄者」
十騎男を睨み付ける山伏。
「奴は、我ら十頭社中の公儀に仇なす障害。確かに排除の対象とはいえ、お前の嫌悪は、お前自身の私事に過ぎん」
山伏は、十騎男から無理矢理に網み笠を奪い取ると被せた。まるで荒馬に目隠しをしてなだめるように。
「まして奴は、曲がりなりにも戮士。謀は密なるを以て良しとすじゃ」
チッと、そっぽを向く十騎男。
与一の消えた山道のその先を凝視して、山伏は言った。
「まさしく、この十頭五番頭、ぼろん坊の役目じゃろう」
天皇を主権者とし、その直下には総責任者である『太政大臣』を置く。実質的な行政の最高責任者である『左大臣』と『右大臣』が置かれ、天皇に対して行政上の責任を負うのは、この太政大臣、右大臣、左大臣の三名のみである。他に、治維新に功績があった人物によって構成される『参議』が在籍し、これらの職責を総合して「太政官」と称し、後年の内閣の様な役割を担う事になっていたのだ。
この制度は、明治維新の混乱により何回も整備統合が行われ、二、三年ごとに機構が全く変貌してしまう事もあったが、西南戦争を経験して組織を強固な物に作り上げ、明治十一年頃に安定した機構となった。
太政官の庁舎は、明治五年三月に皇城内西の丸下に造営したものの、翌六年五月五日、皇城の火災により多くの公文書類もろとも焼失してしまう。即日、赤坂離宮が仮皇居と定められたが、馬場先門内の旧教部省庁舎を活用することとなり、同庁舎に太政官代が設置されたのだった。
その会議室に太政大臣・三条実美と右大臣・岩倉具視、内務卿・大久保利通、司法卿・大木蕎任ら、国政の中心人物が集っていた。
「で、与一は、横浜を離れたのだな」
と、三条に問われた大木が答える。
「はい。手筈通り長崎へ向かいました。しかし、旧征韓党の残党狩り、特に坂上剣山の成敗が叶ったのは収穫でした。戮の運用は順調ですな。佐賀の騒動を御身自ら平定にあたった大久保さんも、これで肩の荷が完全に下りたと云うところですかな?」
無口な大久保は微かに頷いただけだった。が、その代わりとばかりに岩倉が横から口を挟むのだが、「戮す、則ち『罪ある者を殺すの意』とか。毒を以て毒を制す、というわけですな」と、その内容は話しの流れとは直接関係ない上に、皆が分かり切った事の確認にすぎなかった。
概ね、そんな言動の本意は不満の意思表示であり、自分の納得していない事例へと皆を誘導するのが目的である。だが、岩倉が戮の創設に当初から反対していたのは、此処にいる全員が承知していたので、当然、今更の混ぜっ返しには誰も応じなかった。
気を利かせた大木が話題を変える。
「それにしても、妖刀騒ぎの方は、なかなか収まりませんな」
無視された腹いせではないだろうが、またしても岩倉が横槍を入れる。
「そんな怪談じみた風説なんぞは、万人が納得のいく顛末を示さぬかぎり、面白可笑しく広がるに決まっておろう。その為に妖刀とおぼしき刀を片っ端から集めさせ、原因を探ろうとしているのだ。めぼしい学者も今のうちにかき集めておけよ。政府の威信に懸けて、早急に収束させるのだ。こんな世迷い言の類に何時までもかまけておる暇なぞ我らには無い」言い方はともかく、的を射た意見に、皆、今度は意を同じくせざるをえなかった。
「…そうだな」と三条。
「承知しております。その件に関しても、あの御方にお力をお借りすべく、移送に先立って警護の為に与一を長崎に向かわせたのです」大木は、この話題に自ら触れた事に内心では藪蛇だったと後悔しながらも、治安に責任を持つ地位役職として適切に対応している旨を毅然とした態度で示した。
妖刀事件とは俗称であり、要は、日本刀による刃傷沙汰である。実際に殺人まで発展した事例は未だ少なかったのだが、凶器には必ず日本刀が使われている上に、犯人は何かに操られるかのように意識白濁、または前後不覚になった状態で犯行に及んでいるという共通点が、古くから俗信されている妖刀の伝奇と相まって巷に風説された。
まだ、世間が紛擾するところまではいっていないが、事件の構造上、看過できない問題を含んでおり、政府としても看過する訳にもいかなかったのだ。
事件の原因調査の一環として、与一には、旧征韓党残党及び坂上剣山粛清の任と共に、坂上が持つ妖刀・闇の孫六の接収が命じられていたのだった。
「ところで、与一は、戮士の留任を承知したのか?」と、突然、三条は大木に問うた。失念していた懸案事項を一つ思い出したのだ。
「はい」と大木。
「そうか。『毒を以て』も良いが、戮士に事情ありの人間を登用するのも難儀だな」
「しかし、ひとたび任を解けば、奴には野刃所持の罪を問わねばならず、処遇に窮します…留任は我らにも都合が良いかと」
岩倉が、大木の言葉にさり気なく嫌みを挿む。
「ほら見ろ、結局、そうやって厄介事が増すだけだ」
時たま的を射ようとも、所詮、嫌みは何処まで行っても嫌みである。岩倉に打ち止めを宣告するように、此処まで黙って聞いていた大久保が口を開く。治安に関して云えば、内務卿である大久保は、むしろ大木よりも責を担っている立場だった。
「与一の野刃は政府の支給品でなく本人の持ち物であったな。『神斬り』とか何とか大層な名前が付いていたか。そうそう、名前といえば、奴自身の通り名、何故に『与一』なのだ? 那須与一を気取っている訳でもあるまいが…確か、与一の由来は『十余り一』で余一だったものが転じて与一、即ち十一番目の男子に付けられる名前だったはず。奴は兄弟が多いのか?」
一転して饒舌な大久保だった。実は頭の回転が人一倍速い事もあって、ひとたび口を開くと考えた事を咀嚼することなく喋ってしまう癖がある。寡黙で威厳のある男との評判も、饒舌で失敗した反省から過剰に無口を演じている事の誤解に過ぎなかった。
大木が、手元の記録台帳を見ながら答える。
「本人の申し出です。たしか本名かと。元甲賀の忍び、今は紙切り芸人<喜楽亭おもちゃ>を名乗っている養父の言によれば、奴を引き取った際には、自ら与一と名乗り、既に神斬りも所持していた、と記録にあります。流石にこの養父には、神斬りが野刃だとは気付かなかったようですが」
「養子か…いかなる経緯で?」
「さあ、そこまでは。しかし、与一には十一番目の男子の名というだけでなく、余り物の隠喩もあったはず…何やら意味深長ですな」
「余り物の十一男…か」
三条は明かり取りの小窓から見える帝都東京の空を見上げた。
雲一つ無い青空に鳶が一羽舞っている。
鳶は、人の世の雑事に患わされる事もなく、自由に大空を舞う。
三条は、一瞬鳶になりたいと本気で考えていた自分に自嘲しつつ、意識を現実へと―日本の国家最高機関、太政官の最高責任者の責務へと連れ帰った。
「で、あの方の護衛には、他にどのような手立てを講じておるのだ? まさか与一を送っただけではあるまい」
「はい。与一の他に、戮士を数名と―」大木の答弁は続いた。その声を聞きながら三条は無意識に再び空を見上げていた。
元号が明治へと替わって、早八年。
この日本という国が何処へ向かっていくのか。日本行政の最高機関に籍を置く彼等さえも五里霧中の、そのまた最中であった。
東海道といっても、山間部に入ってしまえば獣道に毛が生えた程度、丑三つ時のこの時刻では、当然のことながら擦れ違う旅人もいない。
山道を囲み生い茂る木々の僅かな合間から漏れ届く満月の明かりだけが足下を照らしている。それでも、常人には到底歩けぬ暗さであったが、与一の訓練された夜目には何でもなかった。
旅装束の与一は、暗がりで端からは見えはしないにも拘わらず、それだけに無駄ともいえる相変わらずの地笑顔を湛えていた。
夜道を急ぐ与一。
与一がうっすらと明るい山道の稜線へと消え去った後、自らの気配を悟られないように、山道脇に建立されている道祖神の陰から、二つの人影がその後ろ姿を見据えていた。
一人は、山伏の格好をした大男であった。一珠が握り拳大の大きな数珠を首から下げている。
もう一人は、背格好が与一によく似ていたが、編み笠を深くかぶって顔は見えない。
山伏が「十騎男」と呼びかけると、その男は編み笠を取った。驚いたことに、現れた顔も与一にそっくりだった。ただし、その表情は与一のように笑顔を湛えることはなく、嫌悪感に歪んでいた。
「あいつ、まさかと思ったが、本当に生きてやがった」
「坂上程度では、役不足どころか、傷も負わせられなかったな。まあ、『妖刀憑き』状態、では、真の実力を出し切れなかったか…」
「この俺様が、直々に引導渡してやる」その言葉に触発される十騎男。
山伏が、ガシッと十騎男の肩を掴んで止めた。
振り返る十騎男。「止めるなよ、兄者」
十騎男を睨み付ける山伏。
「奴は、我ら十頭社中の公儀に仇なす障害。確かに排除の対象とはいえ、お前の嫌悪は、お前自身の私事に過ぎん」
山伏は、十騎男から無理矢理に網み笠を奪い取ると被せた。まるで荒馬に目隠しをしてなだめるように。
「まして奴は、曲がりなりにも戮士。謀は密なるを以て良しとすじゃ」
チッと、そっぽを向く十騎男。
与一の消えた山道のその先を凝視して、山伏は言った。
「まさしく、この十頭五番頭、ぼろん坊の役目じゃろう」
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

Battle of Black Gate 〜上野戦争、その激戦〜
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
慶応四年。上野の山に立てこもる彰義隊に対し、新政府の司令官・大村益次郎は、ついに宣戦布告した。降りしきる雨の中、新政府軍は午前七時より攻撃開始。そして――その最も激しい戦闘が予想される上野の山――寛永寺の正門、黒門口の攻撃を任されたのは、薩摩藩兵であり、率いるは西郷吉之助(西郷隆盛)、中村半次郎(桐野利秋)である。
後世、己の像が立つことになる山王台からの砲撃をかいくぐり、西郷は、そして半次郎は――薩摩はどう攻めるのか。
そして――戦いの中、黒門へ斬り込む半次郎は、幕末の狼の生き残りと対峙する。
【登場人物】
中村半次郎:薩摩藩兵の将校、のちの桐野利秋
西郷吉之助:薩摩藩兵の指揮官、のちの西郷隆盛
篠原国幹:薩摩藩兵の将校、半次郎の副将
川路利良:薩摩藩兵の将校、半次郎の副官、のちの大警視(警視総監)
海江田信義:東海道先鋒総督参謀
大村益次郎:軍務官監判事、江戸府判事
江藤新平:軍監、佐賀藩兵を率いる
原田左之助:壬生浪(新撰組)の十番組隊長、槍の名手
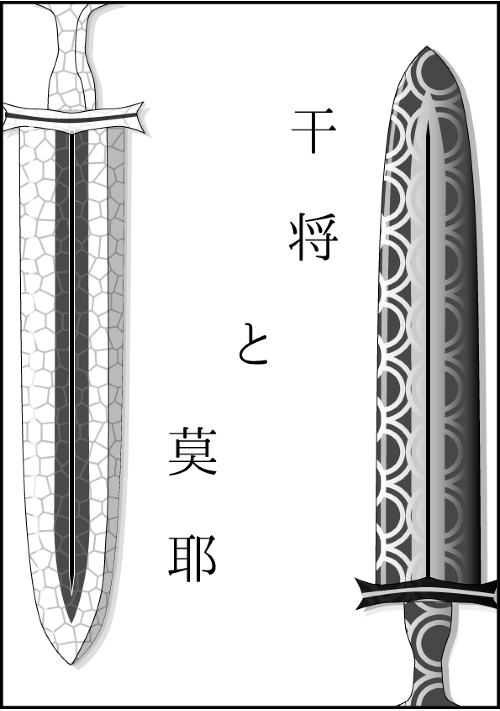

忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

夜の終わりまで何マイル? ~ラウンド・ヘッズとキャヴァリアーズ、その戦い~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
オリヴァーは議員として王の暴政に反抗し、抵抗運動に身を投じたものの、国王軍に敗北してしまう。その敗北の直後、オリヴァーは、必ずや国王軍に負けないだけの軍を作り上げる、と決意する。オリヴァーには、同じ質の兵があれば、国王軍に負けないだけの自負があった。
……のちに剛勇の人(Old Ironsides)として、そして国の守り人(Lord Protector)として名を上げる、とある男の物語。
【表紙画像・挿絵画像】
John Barker (1811-1886), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

散華-二本松少年隊・岡山篤次郎-
紫乃森統子
歴史・時代
幕末、戊辰戦争。会津の東に藩境を接する奥州二本松藩は、西軍の圧倒的な戦力により多くの藩兵を失い、進退極まっていた。寡兵ながらも徹底抗戦の構えを取る二本松藩は、少年たちの予てからの出陣嘆願を受け、13歳以上の出陣を認めたのだった。後に「二本松少年隊」と呼ばれる少年隊士たちの一人、岡山篤次郎を描いた作品です。

晴朗、きわまる ~キオッジャ戦記~
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
一三七九年、アドリア海はヴェネツィアとジェノヴァの角逐の場と化していた。ヴェネツィアの提督ヴェットール・ピサーニは不利な戦いを強(し)いられて投獄された。その結果、ジェノヴァは、ヴェネツィアの目と鼻の先のキオッジャを占領。ヴェネツィア元首(ドゥージェ)コンタリーニはピサーニを釈放して全権を委ねる。絶体絶命の危機にあるヴェネツィアの命運を賭け、ピサーニと、そしてもう一人の提督カルロ・ゼンの逆転劇――「キオッジャの戦い」が始まる。
【表紙画像】
「きまぐれアフター」様より

紅花の煙
戸沢一平
歴史・時代
江戸期、紅花の商いで大儲けした、実在の紅花商人の豪快な逸話を元にした物語である。
出羽尾花沢で「島田屋」の看板を掲げて紅花商をしている鈴木七右衛門は、地元で紅花を仕入れて江戸や京で売り利益を得ていた。七右衛門には心を寄せる女がいた。吉原の遊女で、高尾太夫を襲名したたかである。
花を仕入れて江戸に来た七右衛門は、競を行ったが問屋は一人も来なかった。
七右衛門が吉原で遊ぶことを快く思わない問屋達が嫌がらせをして、示し合わせて行かなかったのだ。
事情を知った七右衛門は怒り、持って来た紅花を品川の海岸で燃やすと宣言する。

空蝉
横山美香
歴史・時代
薩摩藩島津家の分家の娘として生まれながら、将軍家御台所となった天璋院篤姫。孝明天皇の妹という高貴な生まれから、第十四代将軍・徳川家定の妻となった和宮親子内親王。
二人の女性と二組の夫婦の恋と人生の物語です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















