10 / 28
第一話 グリムズロックの護符事件
第六章 怠惰な恋の花 1
しおりを挟む
エレンに割り当てられた二階の東の端の部屋の窓は、邸の裏手に広がる小湖水に面していた。
真ん中に小島があって石造りの礼拝堂のような建物が見える。その小島に三本の柳が生えているようだった。
湖水の向こうには木々が茂り、さらに向こうにさほど高くない丘陵地帯の尾根がうねっている。
「ミス・ディグビー、お手入れの必要な衣類はございますか?」と、グラハム執事が丁重に訊ねてくる。
「ええ。何着かアイロンを頼みます」
「承りました」
執事が服を抱えて出ていく。
エレンは改めて室内を見回した。
一五フィート四方ほどのこざっぱりした寝室だ。
北側にあたる向かい壁に黒い格子に円硝子を嵌めた縦長の窓が並んでいる。
窓の前にオーク材の書き物机がひとつと、深緑の馬毛織を張った肘掛椅子が一脚。
ベッドは右手で衣装棚は左だ。
衣装棚の手前には小ぶりな暖炉があって薪がパチパチと気持ちの良い音を立てて燃えている。
ベッドの手前には鍵のないドアがある。
開けると洗面所だった。
白壁にパイプが走っているところを見ると、有難いことに最新式の水洗トイレらしい。丸い鏡の前には白い小さな化粧台があって、三脚のスツールも据えられていた。豚毛のブラシと石鹸と歯ブラシまで揃っている。エレンは嬉しくなった。
少なくとも快適で衛生的な滞在はできそうな邸だ。
コートとマフと手袋を衣装棚に仕舞ってから、トランクからワインレッドの革表紙の鍵付きの日記帳を取り出して書き物机に向かう。
日記帳を開けば、なかにやや小ぶりの「分離」羊皮紙が挟み込まれている。
その一番上に、そろそろ目になじんできた几帳面な筆跡で一行だけ文が書いてあった。
――クルーニー邸へはご無事につきましたか?
心配そうなニーダムの口調が思い浮かぶような筆致だ。
エレンはほのぼのとした喜びを感じながら下に答えを書いた。
――はい。
それだけ書いてしまうと、どう続けていいのか分からなくなった。
続きを書こうか書くまいか頭を悩ませていたとき、廊下へ続くドアの脇にかかったベルの紐が外から引かれて鳴った。
「ミス・ディグビー、お衣装の手入れがすみました」
外から女の声がする。
慌てて羊皮紙を日記帳に挟んで鍵をかけてから出ると、さっき外でエリザベスお嬢様に手を焼いていたメイドが大きな籠を抱えて立っていた。エレンはまず笑顔を拵えながら名前を思い出した。
「ありがとうヘスター。しばらくよろしくね」
告げると笑顔が返ってきた。有難いことに名前はあっていたようだ。
エレンはちょっと迷ってから訊ねた。「ところで、あなたはミス・エリザベス付きでもあるの?」
「はいミス・ディグビー。子供部屋つきの乳母のようなものです」と、ヘスターは暗く哀しげな声で応えた。
荷物の整理をするヘスターに邸の間取りを訊ねてみる。
「ご一家のお部屋はみな前庭側です。子供部屋はこのお部屋の向かいで、奥様と旦那さまのお部屋は二階の西側です。玄関広間に近いお部屋をミスター・ジョンがお使いです」
メイドはてきぱきと説明してくれた。
「ではミス・ディグビー、お夕食の時間になりましたら銅鑼が鳴りますから、地階の食堂へいらしてください。今日はあなたを歓迎するためにきちんとした晩餐にするから、お隣の紳士方もお呼びとのことですよ?」と、エレンの母親ほどの年配に見えるメイドは意味ありげに目配せをした。
「お隣の紳士方とは?」
「それは勿論、エヴァンス牧師さまとお医者のドクター・マイクロフトですよ!」と、ヘスターは心外そうに答えた。「お二人とも独身なんですよ。牧師様は寡夫でね、ドクターは三年前の火事でお顔に大きな火傷がありますけれど、どっちも良い方ですよ?」
ヘスターがコートの毛皮にブラシをかけながら熱弁する。
「そうなの」
儀礼的に答えてしまってから、エレンは違和感を覚えた。
「ねえヘスター……」
「なんでしょう?」
「駅で噂を聞いたのだけれど、そのエヴァンス牧師のお嬢さんが、このお屋敷のミスター・ジョン・クルーニーとの婚約を破棄されたばかりなのでしょう? そのお嬢さんのお父様をもう晩餐に招くの?」
「あらいやだ、村でそんな噂を?」と、ヘスターは鼻の脇に皴をよせた。「お言葉ながらミス・ディグビー、その噂はそんなに正確とはいえませんよ」
「そうなの? どのあたりが?」
「一番初めのところからそもそも間違っているのですよ。シシーお嬢さんとジョン坊ちゃんは確かに昔から仲良しでしたけれど、婚約と言ったって子供同士の口約束みたいなもので、そんなに正式なものでもなかったのです」
「あらそうだったの? ――じゃ、もしかしてご両親のクルーニーご夫妻は、ご子息とミス・シシーとの婚約をそれほど望んでいたわけではなかったの?」
「そりゃそうですよお嬢さん」と、ヘスターが呆れ声で応じる。「グリムズロックのクルーニー家といったらこの地方で一番の財産家ですよ? シシーお嬢さんはそりゃ確かによくできた娘さんですが、とりたてて有力な親戚もない貧乏牧師の娘ですからねえ。たとえ破産寸前だとしたって、お家柄はとびっきりのミス・キャサリンのほうが、ご両親としちゃよほど望ましいですとも」
「ミス・キャサリンとは面識があるの? どんなお嬢様なの?」
訊ねるとヘスターは破顔した。
「素敵なお嬢様ですよ! 風変わりではありますけど、私は大好きです!」
エレンは困惑した。
どうもいろいろ思っていたのとは違うようだ。
ヘスターが出ていくとすぐ、エレンは部屋の鍵をかけてから、掌を広げて小声で囁いた。
「サラ、出てきて頂戴」
途端に淡い金色の光が陽炎のように立ち上り、おなじみの火蜥蜴が現れた。
「おおエレン。久しのう。ところでここはどこじゃ?」
「グリムズロックのクルーニー邸よ。潜入に成功したの」
「それは重畳。ときにあの若造は?」
「ミスター・ニーダムのことだったら当然一緒じゃありません。それよりサラ、大急ぎで一仕事頼みたいの」
「なんじゃ?」
「いますぐ暖炉から煙突を抜けて屋根に出て、二階の前庭側の、いちばん玄関広間に近い西側の部屋の暖炉へ入って欲しいの。そこがジョン・クルーニーの部屋だから」
「例の魅了魔術に侵されているかもしれぬ若造じゃな? 儂はそこで何をすりゃいいんだ?」
「とりあえずずっと焔の中にいてジョンの生活を見張っていて。毎日何か同じものを飲んでいる様子があったら報せて欲しいの」
「承知した。しかし、それだけの用事をなぜそう急ぐのじゃ?」
「あなたが目立たず屋根の上をウロウロできるのは今このタイミングだけだからよ」
「どういうことじゃ?」
「色よ、色。サラ、あなた自分がどんなに輝かしいか知らないでしょう?」
今はちょうど日暮れ時で、窓の外に見える小湖水の水面が、左手から射す入日に照らされて赤々と輝いている。この邸の赤みの強いスレート屋根も、同じ陽を浴びて燃えるように輝いているはずだ。
「あなたの輝きは焔を宿した最上のルビーみたいだもの。もしだれか魔術師がこの邸の様子を気にしていたら、火蜥蜴だって一目で分かっちゃう」
エレンが真剣に言い募ると、火蜥蜴は皮翼をパタパタさせた。
「そうか。ルビーか。それでは仕方がないのう」
まんざらでもなさそうに言って、火蜥蜴は暖炉の焔のなかにひょいと飛び込んでいった。
「おお、なかなか良い火加減じゃのう」
「サラ、お願いだから急いで!」
エレンは小声で急かした。
真ん中に小島があって石造りの礼拝堂のような建物が見える。その小島に三本の柳が生えているようだった。
湖水の向こうには木々が茂り、さらに向こうにさほど高くない丘陵地帯の尾根がうねっている。
「ミス・ディグビー、お手入れの必要な衣類はございますか?」と、グラハム執事が丁重に訊ねてくる。
「ええ。何着かアイロンを頼みます」
「承りました」
執事が服を抱えて出ていく。
エレンは改めて室内を見回した。
一五フィート四方ほどのこざっぱりした寝室だ。
北側にあたる向かい壁に黒い格子に円硝子を嵌めた縦長の窓が並んでいる。
窓の前にオーク材の書き物机がひとつと、深緑の馬毛織を張った肘掛椅子が一脚。
ベッドは右手で衣装棚は左だ。
衣装棚の手前には小ぶりな暖炉があって薪がパチパチと気持ちの良い音を立てて燃えている。
ベッドの手前には鍵のないドアがある。
開けると洗面所だった。
白壁にパイプが走っているところを見ると、有難いことに最新式の水洗トイレらしい。丸い鏡の前には白い小さな化粧台があって、三脚のスツールも据えられていた。豚毛のブラシと石鹸と歯ブラシまで揃っている。エレンは嬉しくなった。
少なくとも快適で衛生的な滞在はできそうな邸だ。
コートとマフと手袋を衣装棚に仕舞ってから、トランクからワインレッドの革表紙の鍵付きの日記帳を取り出して書き物机に向かう。
日記帳を開けば、なかにやや小ぶりの「分離」羊皮紙が挟み込まれている。
その一番上に、そろそろ目になじんできた几帳面な筆跡で一行だけ文が書いてあった。
――クルーニー邸へはご無事につきましたか?
心配そうなニーダムの口調が思い浮かぶような筆致だ。
エレンはほのぼのとした喜びを感じながら下に答えを書いた。
――はい。
それだけ書いてしまうと、どう続けていいのか分からなくなった。
続きを書こうか書くまいか頭を悩ませていたとき、廊下へ続くドアの脇にかかったベルの紐が外から引かれて鳴った。
「ミス・ディグビー、お衣装の手入れがすみました」
外から女の声がする。
慌てて羊皮紙を日記帳に挟んで鍵をかけてから出ると、さっき外でエリザベスお嬢様に手を焼いていたメイドが大きな籠を抱えて立っていた。エレンはまず笑顔を拵えながら名前を思い出した。
「ありがとうヘスター。しばらくよろしくね」
告げると笑顔が返ってきた。有難いことに名前はあっていたようだ。
エレンはちょっと迷ってから訊ねた。「ところで、あなたはミス・エリザベス付きでもあるの?」
「はいミス・ディグビー。子供部屋つきの乳母のようなものです」と、ヘスターは暗く哀しげな声で応えた。
荷物の整理をするヘスターに邸の間取りを訊ねてみる。
「ご一家のお部屋はみな前庭側です。子供部屋はこのお部屋の向かいで、奥様と旦那さまのお部屋は二階の西側です。玄関広間に近いお部屋をミスター・ジョンがお使いです」
メイドはてきぱきと説明してくれた。
「ではミス・ディグビー、お夕食の時間になりましたら銅鑼が鳴りますから、地階の食堂へいらしてください。今日はあなたを歓迎するためにきちんとした晩餐にするから、お隣の紳士方もお呼びとのことですよ?」と、エレンの母親ほどの年配に見えるメイドは意味ありげに目配せをした。
「お隣の紳士方とは?」
「それは勿論、エヴァンス牧師さまとお医者のドクター・マイクロフトですよ!」と、ヘスターは心外そうに答えた。「お二人とも独身なんですよ。牧師様は寡夫でね、ドクターは三年前の火事でお顔に大きな火傷がありますけれど、どっちも良い方ですよ?」
ヘスターがコートの毛皮にブラシをかけながら熱弁する。
「そうなの」
儀礼的に答えてしまってから、エレンは違和感を覚えた。
「ねえヘスター……」
「なんでしょう?」
「駅で噂を聞いたのだけれど、そのエヴァンス牧師のお嬢さんが、このお屋敷のミスター・ジョン・クルーニーとの婚約を破棄されたばかりなのでしょう? そのお嬢さんのお父様をもう晩餐に招くの?」
「あらいやだ、村でそんな噂を?」と、ヘスターは鼻の脇に皴をよせた。「お言葉ながらミス・ディグビー、その噂はそんなに正確とはいえませんよ」
「そうなの? どのあたりが?」
「一番初めのところからそもそも間違っているのですよ。シシーお嬢さんとジョン坊ちゃんは確かに昔から仲良しでしたけれど、婚約と言ったって子供同士の口約束みたいなもので、そんなに正式なものでもなかったのです」
「あらそうだったの? ――じゃ、もしかしてご両親のクルーニーご夫妻は、ご子息とミス・シシーとの婚約をそれほど望んでいたわけではなかったの?」
「そりゃそうですよお嬢さん」と、ヘスターが呆れ声で応じる。「グリムズロックのクルーニー家といったらこの地方で一番の財産家ですよ? シシーお嬢さんはそりゃ確かによくできた娘さんですが、とりたてて有力な親戚もない貧乏牧師の娘ですからねえ。たとえ破産寸前だとしたって、お家柄はとびっきりのミス・キャサリンのほうが、ご両親としちゃよほど望ましいですとも」
「ミス・キャサリンとは面識があるの? どんなお嬢様なの?」
訊ねるとヘスターは破顔した。
「素敵なお嬢様ですよ! 風変わりではありますけど、私は大好きです!」
エレンは困惑した。
どうもいろいろ思っていたのとは違うようだ。
ヘスターが出ていくとすぐ、エレンは部屋の鍵をかけてから、掌を広げて小声で囁いた。
「サラ、出てきて頂戴」
途端に淡い金色の光が陽炎のように立ち上り、おなじみの火蜥蜴が現れた。
「おおエレン。久しのう。ところでここはどこじゃ?」
「グリムズロックのクルーニー邸よ。潜入に成功したの」
「それは重畳。ときにあの若造は?」
「ミスター・ニーダムのことだったら当然一緒じゃありません。それよりサラ、大急ぎで一仕事頼みたいの」
「なんじゃ?」
「いますぐ暖炉から煙突を抜けて屋根に出て、二階の前庭側の、いちばん玄関広間に近い西側の部屋の暖炉へ入って欲しいの。そこがジョン・クルーニーの部屋だから」
「例の魅了魔術に侵されているかもしれぬ若造じゃな? 儂はそこで何をすりゃいいんだ?」
「とりあえずずっと焔の中にいてジョンの生活を見張っていて。毎日何か同じものを飲んでいる様子があったら報せて欲しいの」
「承知した。しかし、それだけの用事をなぜそう急ぐのじゃ?」
「あなたが目立たず屋根の上をウロウロできるのは今このタイミングだけだからよ」
「どういうことじゃ?」
「色よ、色。サラ、あなた自分がどんなに輝かしいか知らないでしょう?」
今はちょうど日暮れ時で、窓の外に見える小湖水の水面が、左手から射す入日に照らされて赤々と輝いている。この邸の赤みの強いスレート屋根も、同じ陽を浴びて燃えるように輝いているはずだ。
「あなたの輝きは焔を宿した最上のルビーみたいだもの。もしだれか魔術師がこの邸の様子を気にしていたら、火蜥蜴だって一目で分かっちゃう」
エレンが真剣に言い募ると、火蜥蜴は皮翼をパタパタさせた。
「そうか。ルビーか。それでは仕方がないのう」
まんざらでもなさそうに言って、火蜥蜴は暖炉の焔のなかにひょいと飛び込んでいった。
「おお、なかなか良い火加減じゃのう」
「サラ、お願いだから急いで!」
エレンは小声で急かした。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説

マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子
ちひろ
恋愛
マッサージ師にそれっぽい理由をつけられて、乳首とクリトリスをいっぱい弄られた後、ちゃっかり手マンされていっぱい潮吹きしながらイッちゃう女の子の話。
Fantiaでは他にもえっちなお話を書いてます。よかったら遊びに来てね。
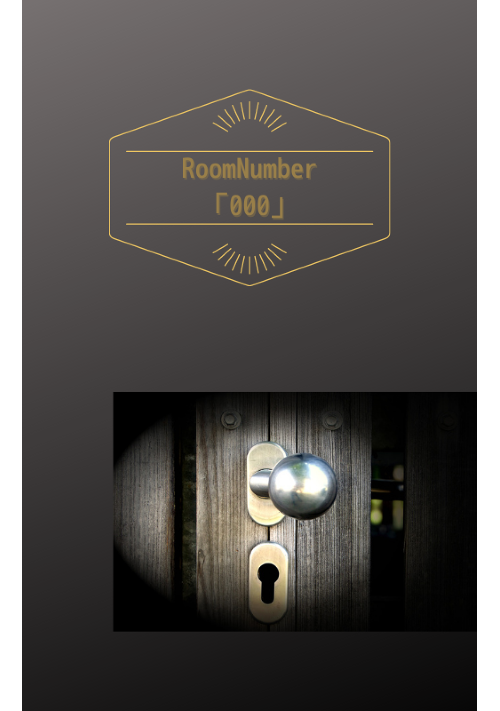
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

校長室のソファの染みを知っていますか?
フルーツパフェ
大衆娯楽
校長室ならば必ず置かれている黒いソファ。
しかしそれが何のために置かれているのか、考えたことはあるだろうか。
座面にこびりついた幾つもの染みが、その真実を物語る

【R-18】クリしつけ
蛙鳴蝉噪
恋愛
男尊女卑な社会で女の子がクリトリスを使って淫らに教育されていく日常の一コマ。クリ責め。クリリード。なんでもありでアブノーマルな内容なので、精神ともに18歳以上でなんでも許せる方のみどうぞ。

寝室から喘ぎ声が聞こえてきて震える私・・・ベッドの上で激しく絡む浮気女に復讐したい
白崎アイド
大衆娯楽
カチャッ。
私は静かに玄関のドアを開けて、足音を立てずに夫が寝ている寝室に向かって入っていく。
「あの人、私が

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















