92 / 96
X 無窮の開演、永遠の閉演
092 諦念
しおりを挟む
九二 諦念
「朝野先輩!」久しぶりに練習へ顔を出すと、瀬戸が走り寄ってきた。
「ああ、瀬戸さん。どうしたの? そんな血相変えて――」
「『ああ、瀬戸さん』じゃないよ、ショウちゃん。あした、いつどこに集合か把握してんの?」
「え? ヨッシー、あしたって――」
「ああ、もう(吉川は頭を掻きむしる)。あのね、あしたはゲネ、ゲネプロなんだってば。グループのLINE読んでないの? 今日とかあした来なかったらオーボエ、瀬戸ちゃんと高志で拾って吹くところだったよ」
「ああ――その、ごめん。大丈夫、もう大丈夫だから。あしたも大丈夫」
「はあ、大丈夫、か。その言葉、信用していいんだね?」吉川がいつになくとげとげしくいう。
「う、うん。もちろん」
「ならいいんだけど。あと、ドレスの採寸はいいんだよね? 人数分しかないんだから、余ったぶんで何とか回すっての、できないんだよ。とりあえず七号は確保してるけど」
「ドレス――ああ、大学入るときに作った礼服、七号だったからサイズはそれでいいと思う。体重も変わってないし。パンプスも黒ストもあるから問題ないよ」
「そうか、まあ、うん。さしあたりオッケーか。あしたは実際のホールで本番通りに演るからね。といっても何回もやったリハ通りだから、平常心、平常心」と吉川はいった。
その後の練習でたしかに衰えは感じた。一週間以上サボったのだ、仕方もない。が、十三歳から(ブランクはあれど)続けてきたのだ、その日の練習で休眠から目覚めるべき点は目覚め、及ばぬ点についてもどうしたら元通りになるか、練習メニューも明瞭に分かった。
朝だ。重い、重い朝。
いつものごとくアラームがうるさい。そうか。ゲネプロの日か。布団の外、現実世界では高志はすでに着替えており、朝の情報番組をテレビで観ている(音は消してあった)。
「おはよう、聖子」
肩越しに振り向き、頬笑む。
カンガルーの子どものようにとても嫌な気分で布団から体を出してゆく。「高志――アラーム、何時にセットしたの?」苦労して上体を起こす。エアコンの温度がかなり高く設定してあるようだ、と少し安心要素を見つけた。普段からこんなあたたかな設定温度なら布団からも抜け出せただろうか。
「おれのは六時。聖子のはたった今。どう、眠れた? 起きれそう?」
目を動かし、周囲を観察する。とはいえ代わり映えのない自分のワンルームである。変わったところがあればむしろその方が困るのだが。「高志、泊まってたっけ」
「アラーム代わりにするから泊ってくれっていったの、覚えてないの?」と、かれは歯を見せて笑った。
支度をし、大学に向かう。駅に近い会場なので直行組は多い。大学の門でチャーターしたバスに乗り、会場へと向かう。
「おはよう、諸君。いや、未来のヴィルトゥオーゾというべきか。ともあれこのバスに乗る者は偉大な演奏を約束されている――途中で降りる場合を除いて、だが。さて、このたび第六十四回冬季定期演奏会のバスガイドは我が団きっての事務屋で部長である、田中が拝命いたしました。さて皆様方、右手をご覧ください――いやそっちやないって。右手、まさに諸君の右手が握るのは栄光であり、勝利であります」
「はーい、さえぎって悪いな、田中。学指揮からひとつ。その演説、今日の分と本番の分で内容が同じならスルーしたいんだけど」と吉川が中腰になって手を挙げる。
「よくぞ見抜いた、学指揮。実はバス車内と控室、休憩、打ち上げ、今日も本番も何もかもすべて違うパターンを用意している――っていうか即興なんやけどな。そう、すべてにおいて一発勝負のみなと同じく、部長のご挨拶とて例外なく、一点ものだ!(おお、と小規模などよめきがバスに広がる)。やって、それくらいしか目立てやん。せっかく部長になったのに」
「分かった分かった、かっこいいから」と、吉川は座席にどん、と座り込む。
「はあ、少しは遊んでくれてもいいのに。というわけでもうすぐ会場入りです。各自、持ち物とかゴミとか、絶対にバスに残さんようにな」
更衣室でそれぞれブラックドレスやタキシード、コンサートマスターは燕尾服をそれぞれ着込む。放送、照明、団員の入りからチューニング、指揮者の入りから演奏、そしてアンコールまでひと通り通す。ほぼ予想している時間通りに終わった。
「あ! ショウちゃん、ショウちゃん!」控室へ向かう廊下で呼びとめられる
「ああ、里美さん。お疲れさま、あとは本番だね」というと、かの女は大げさにうなだれて、
「めっちゃ疲れたわあ、何回もミスったし。うちステージ上がんの初めてでさ、一年のときはお声がかからなくて。夏はよかったんだけどさ、冬は雰囲気違うじゃん? こんな調子じゃ、本番まであと一か月以上は練習したいわ」と額に手を当てた。
「はは、でも大丈夫そうに聴こえたよ。あなたに関しては大丈夫だと思う」歩きながら横山の肩をはたく。完全に移ったな、横山の性格が。
「え? ま、、待って、ショウちゃん。あの中でうちの音、聴き分けてたん?」横山の目つきがにわかに変化した。
「ああ――うちの高校、オケじゃなく吹部なんだけど、まあまあ規模があったから」といって両手で大事に抱えるオーボエに視線を落とす。「吹奏の全日本って五十五名定員でしょ? ここも二管編成でだいたい五〇名だから。意図的に聴き取ろうとすれば、第一バイオリンの特定のプルトもなんとか聴こえるものよ」
「ショウちゃん――それって普通にすごくない? 教育学部とかなら、もっと音楽漬けの学生生活送れるのに」と、横山は驚いてみせる(事実、大いに感嘆しているようだった)。
「ふふ、でもね、わたしには無理だよ。わたしは――」
わたしは、なにをやっても駄目だから。
「朝野先輩!」久しぶりに練習へ顔を出すと、瀬戸が走り寄ってきた。
「ああ、瀬戸さん。どうしたの? そんな血相変えて――」
「『ああ、瀬戸さん』じゃないよ、ショウちゃん。あした、いつどこに集合か把握してんの?」
「え? ヨッシー、あしたって――」
「ああ、もう(吉川は頭を掻きむしる)。あのね、あしたはゲネ、ゲネプロなんだってば。グループのLINE読んでないの? 今日とかあした来なかったらオーボエ、瀬戸ちゃんと高志で拾って吹くところだったよ」
「ああ――その、ごめん。大丈夫、もう大丈夫だから。あしたも大丈夫」
「はあ、大丈夫、か。その言葉、信用していいんだね?」吉川がいつになくとげとげしくいう。
「う、うん。もちろん」
「ならいいんだけど。あと、ドレスの採寸はいいんだよね? 人数分しかないんだから、余ったぶんで何とか回すっての、できないんだよ。とりあえず七号は確保してるけど」
「ドレス――ああ、大学入るときに作った礼服、七号だったからサイズはそれでいいと思う。体重も変わってないし。パンプスも黒ストもあるから問題ないよ」
「そうか、まあ、うん。さしあたりオッケーか。あしたは実際のホールで本番通りに演るからね。といっても何回もやったリハ通りだから、平常心、平常心」と吉川はいった。
その後の練習でたしかに衰えは感じた。一週間以上サボったのだ、仕方もない。が、十三歳から(ブランクはあれど)続けてきたのだ、その日の練習で休眠から目覚めるべき点は目覚め、及ばぬ点についてもどうしたら元通りになるか、練習メニューも明瞭に分かった。
朝だ。重い、重い朝。
いつものごとくアラームがうるさい。そうか。ゲネプロの日か。布団の外、現実世界では高志はすでに着替えており、朝の情報番組をテレビで観ている(音は消してあった)。
「おはよう、聖子」
肩越しに振り向き、頬笑む。
カンガルーの子どものようにとても嫌な気分で布団から体を出してゆく。「高志――アラーム、何時にセットしたの?」苦労して上体を起こす。エアコンの温度がかなり高く設定してあるようだ、と少し安心要素を見つけた。普段からこんなあたたかな設定温度なら布団からも抜け出せただろうか。
「おれのは六時。聖子のはたった今。どう、眠れた? 起きれそう?」
目を動かし、周囲を観察する。とはいえ代わり映えのない自分のワンルームである。変わったところがあればむしろその方が困るのだが。「高志、泊まってたっけ」
「アラーム代わりにするから泊ってくれっていったの、覚えてないの?」と、かれは歯を見せて笑った。
支度をし、大学に向かう。駅に近い会場なので直行組は多い。大学の門でチャーターしたバスに乗り、会場へと向かう。
「おはよう、諸君。いや、未来のヴィルトゥオーゾというべきか。ともあれこのバスに乗る者は偉大な演奏を約束されている――途中で降りる場合を除いて、だが。さて、このたび第六十四回冬季定期演奏会のバスガイドは我が団きっての事務屋で部長である、田中が拝命いたしました。さて皆様方、右手をご覧ください――いやそっちやないって。右手、まさに諸君の右手が握るのは栄光であり、勝利であります」
「はーい、さえぎって悪いな、田中。学指揮からひとつ。その演説、今日の分と本番の分で内容が同じならスルーしたいんだけど」と吉川が中腰になって手を挙げる。
「よくぞ見抜いた、学指揮。実はバス車内と控室、休憩、打ち上げ、今日も本番も何もかもすべて違うパターンを用意している――っていうか即興なんやけどな。そう、すべてにおいて一発勝負のみなと同じく、部長のご挨拶とて例外なく、一点ものだ!(おお、と小規模などよめきがバスに広がる)。やって、それくらいしか目立てやん。せっかく部長になったのに」
「分かった分かった、かっこいいから」と、吉川は座席にどん、と座り込む。
「はあ、少しは遊んでくれてもいいのに。というわけでもうすぐ会場入りです。各自、持ち物とかゴミとか、絶対にバスに残さんようにな」
更衣室でそれぞれブラックドレスやタキシード、コンサートマスターは燕尾服をそれぞれ着込む。放送、照明、団員の入りからチューニング、指揮者の入りから演奏、そしてアンコールまでひと通り通す。ほぼ予想している時間通りに終わった。
「あ! ショウちゃん、ショウちゃん!」控室へ向かう廊下で呼びとめられる
「ああ、里美さん。お疲れさま、あとは本番だね」というと、かの女は大げさにうなだれて、
「めっちゃ疲れたわあ、何回もミスったし。うちステージ上がんの初めてでさ、一年のときはお声がかからなくて。夏はよかったんだけどさ、冬は雰囲気違うじゃん? こんな調子じゃ、本番まであと一か月以上は練習したいわ」と額に手を当てた。
「はは、でも大丈夫そうに聴こえたよ。あなたに関しては大丈夫だと思う」歩きながら横山の肩をはたく。完全に移ったな、横山の性格が。
「え? ま、、待って、ショウちゃん。あの中でうちの音、聴き分けてたん?」横山の目つきがにわかに変化した。
「ああ――うちの高校、オケじゃなく吹部なんだけど、まあまあ規模があったから」といって両手で大事に抱えるオーボエに視線を落とす。「吹奏の全日本って五十五名定員でしょ? ここも二管編成でだいたい五〇名だから。意図的に聴き取ろうとすれば、第一バイオリンの特定のプルトもなんとか聴こえるものよ」
「ショウちゃん――それって普通にすごくない? 教育学部とかなら、もっと音楽漬けの学生生活送れるのに」と、横山は驚いてみせる(事実、大いに感嘆しているようだった)。
「ふふ、でもね、わたしには無理だよ。わたしは――」
わたしは、なにをやっても駄目だから。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説


サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。



遅れてきた先生
kitamitio
現代文学
中学校の卒業が義務教育を終えるということにはどんな意味があるのだろう。
大学を卒業したが教員採用試験に合格できないまま、何年もの間臨時採用教師として中学校に勤務する北田道生。「正規」の先生たち以上にいろんな学校のいろんな先生達や、いろんな生徒達に接することで見えてきた「中学校のあるべき姿」に思いを深めていく主人公の生き方を描いています。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

泥に咲く花
臣桜
現代文学
裕福な環境に生まれ何不自由なく育った時坂忠臣(ときさかただおみ)。が、彼は致命的な味覚障碍を患っていた。そんな彼の前に現れたのは、小さな少女二人を連れた春の化身のような女性、佐咲桜(ささきさくら)。
何にも執着できずモノクロの世界に暮らしていた忠臣に、桜の存在は色と光、そして恋を教えてくれた。何者にも汚されていない綺麗な存在に思える桜に忠臣は恋をし、そして彼女の中に眠っているかもしれないドロドロとした人としての泥を求め始めた。
美しく完璧であるように見える二人の美男美女の心の底にある、人の泥とは。
※ 表紙はニジジャーニーで生成しました
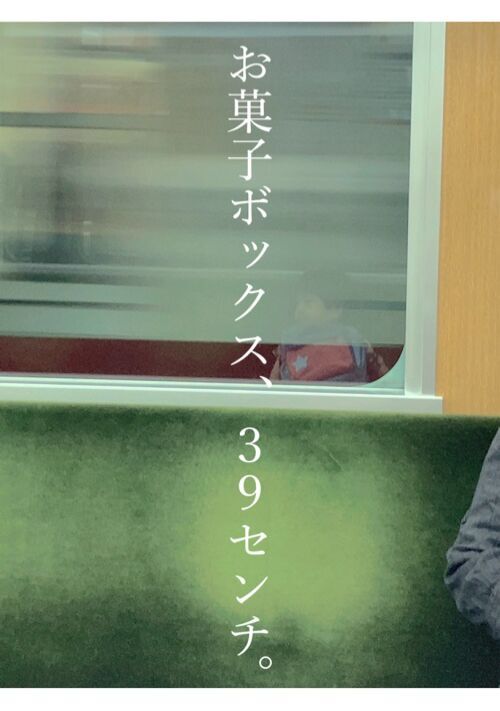
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















