32 / 80
第三章 真実を知る家族
032 不安を抱えて
しおりを挟む 王子様と王女様は、ミュージカルをひと段落させて、王様たちの近くに戻ってきて、握手する。
王妃さま、王子さまたちも笑顔で握手をすると、王女さまたちにも握手。
さっきほどじゃないけど、鼻にかかった声で、んっぬって入るからちょっと笑えちゃう。
『ナギのお方達のおかげで久方ぶりにレイドラアースの地を訪ねることが出来て、嬉しく存じます』
外交のお偉いさんは歌劇調じゃなかった。
改めて、王子様たちを、カイサル・ラクサンヌ・グリーンリバー第一王子とシャリアンヌ・アーリィン・グリーンリバー第三王女と言う名前だとお偉いさんなジョエル・ダンタル侯爵、外務卿が教えてくれた。
一番面倒と聞いていたドラム公爵じゃなくってホッとした。
同じ方向の面倒なのかは謎だけど、わざわざ面倒な場面に遭遇したくないしね。
『こちらこそ、我が国にお出まし頂き、光栄至極です』
ガルフ侯爵が愛想良くダンタル侯爵と握手。
カイサル殿下とシャリアンヌ殿下が、ファリン殿下とルアラン殿下に直で話しかけてきた。うぉう。通訳必要なさそうだし離れたい。
『んっぬ。すまないっんね!公用語だっとぅ、わたぁーしの良さんっがっ伝わらないっんなっ』
ゲ。母国語だともっとすごい可能性を秘めているの!!??
『おっほうほぅ!おっにいしゃっまぁはぁ、ゴッガックゥからぁおっ逃げぇにィなっるぅからぁぁん』
(お兄さまは語学からお逃げになるから)
シャリアンヌ殿下も大差ない気がするんだけど。
独特なアクセント?訛りとは違うみたいだけど、私に移っちゃったらどうしよう。
ちなみにお二人ともわりと美形なのに言動とカボチャパンツで台無しなの。
王子様が二十五才くらいで、王女様が十九才くらいらしい。マジっすか。
王妃さまにこっそり聞いたら、グリーンリバーの女性も通常はドレスだそうなので、王女様は趣味か旅装か。
以前、お見えになった時は膝丈パンツだったそうなので、ドレスがお嫌いなのかも。
『そっなぁーたぁはぁ、陛ぃ下ぁのぉ、ほっごぉーうぉおぅ、うっけったぁむっすーめかぁ?』
(そなたは、陛下の保護を受けた娘か?)
めっっっんどくせぇな!!あ、お口が悪くなっちゃいました。
『グリーンリバーの尊きお方にご挨拶をする事をお許しください。私はジュリアス・グレーデン辺境伯が妻、リーシャ・グレーデンと申します。我が王より、ナギ国のファリン殿下、ルアラン殿下の通訳としてお側につかせて頂いております』
カーテシーの状態で停止して返事を待つ。
「ほぉほー、言葉にこっまればぁ、まっかせることぐぁ、でっきるなぁ?」
(ほほぅ、言葉に困れば、任せることができるかな?)
え。グリーンリバー語はレイドラアース語とちょっと違うけど、これは公用語の時よりちょっとマシなだけでは。
「おんにさまぁ!出っ来ぃるどぅあけ、こうよっぉうぐぉがぁよっろうしゅいぃわぁ」
(お兄さま、出来るだけ公用語がよろしいわ)
ぬー!これは、ちょっと難しいぞ。二カ国通訳になちゃう感じに頭使うぞ。
『っんむ!そっぉうかぁあっんぬっ』
(ぬ?そうか?)
始終こんな感じなの?
『グッゥレェデェンッのにはぁ、会った事ぐぁあっるまっす!!ヨッメをぉもらわぁんぬっとぅおっもってぇいっましタァがっおっ好みぬぉンっ、すぇいでぇしーったのんっねぇっ』
(グレーデンのには、会った事があります!嫁を貰わぬと思っていましたが、お好みのせいでしたのね)
おおぅ、ロリコン扱いぃ!王女様が酷い事言うって文句言いたいけど、この口調で話しを聞くの面倒だから泣き寝入りで良いかな?
横にいたセリウスさまが「流せー」って顔してるし、ルルゥは笑顔で顔を固めてるし、ガルフ侯爵は「スルーせよ」って顔。
うちの王子さまたちはすでに飽きてる。
ナギの人たちが笑顔のまま、凍りついてるよ。
『『彼女はこう見えて成人していて、嫁ぎ先のグレーデンで商業を発展させている敏腕な夫人だ』』
なぜか、ファリン殿下とルアラン殿下が庇ってくれた。話が長くなるし、もう良いんですよー。
王子様とダンタス侯爵が『ほう?』ってなっちゃった。
『見た目はレイドラアースの王子方とナギの王女方と大差なく見えるのに・・・』
グリーンリバーの皆さんの方からそんな言葉が聞こえてきた。
なんだとぉ!!!!
いくらなんでも私は十才には見えんだろうがぁい!!!
ふんぬー!
「ちゃんとリーシャちゃんの方が大人っぽいからねぇ」
後ろからルルゥにそっと肩を抑えられて慰められた。
グレーデンやホーンで小さく見えるのは仕方ないけど、王子さまたちよりは背丈もあるし、顔つきも子供じゃないもん。
『まぁあん!我っが国ぃにぃはぁ、こっこっまでぇペッタンこぉおーっぬあぁフッジィンはぁいらっしゃるっぅくぁしらぁ?』
(まあ!我が国には、ここまでペッタンコの夫人はいらっしゃらるかしら?)
私のお胸を見て、盛大に首を傾げるシャリアンヌ!!!絶許!!
敬称なんか排除だ。
全世界貧乳教会員を敵に回したな!?
そんな会はないけど、ツルペタ仲間を敵に回したよ!
シャリアンヌのお胸は大きくも小さくもない程よい丘に見える。が、王子様と同じベストの上にジャケットなのでハッキリはわからない。ちくせう!!でもお義母さまくらいあったら隠せないボリュームだから、多分人のこと言えるほど、大した事ないよ!!
『シャリゥアァンッンッヌッ!じょっせいぃうぁ、ムッネッっじゃぬぁいんっどぅあっんぬ!くぉっしぃだっよんっぬ!わったぁしぃぬぉツッマぬぉ、ん、ふぉっぉすぉくぅくっびぃれったぁ!くぉっし!よっぉいよっぅんぬ!』
(シャリアンヌ!女性は胸じゃないんだ!腰だよ!私の妻の、ん、細く括れた!腰!良いんだよ!)
細く括れた腰!それも私にはナッシング!
兄妹がしょうもない喧嘩してる。
その内容に私は連続して攻撃を受けてるんだけど。
『『リーシャはリーシャのままで良い。うるさいよりよほど良い事だしな』』
十二歳の王女さまたちに小声で励まされた。
国中の重鎮が集まり、ナギとグリーンリバーのお客様のいる前で子供体型だと周知されたんだけど、もうお家帰りたい。
___________________
グリーンリバーの面倒な二人は大した事を言ってないので、深く考えなくて良いかと訳を付けてなかったんですが、訳した方がいいとのことで訳を追加しました。
改めて打ち直すとくだらなさに精神が病みそうですw
自分にダメージが大きいので、面倒なキャラを考えたことに後悔中です。
イラっとさせてしまっていたら申し訳ない。
とっとと国へ追い出したいです⭐︎
王妃さま、王子さまたちも笑顔で握手をすると、王女さまたちにも握手。
さっきほどじゃないけど、鼻にかかった声で、んっぬって入るからちょっと笑えちゃう。
『ナギのお方達のおかげで久方ぶりにレイドラアースの地を訪ねることが出来て、嬉しく存じます』
外交のお偉いさんは歌劇調じゃなかった。
改めて、王子様たちを、カイサル・ラクサンヌ・グリーンリバー第一王子とシャリアンヌ・アーリィン・グリーンリバー第三王女と言う名前だとお偉いさんなジョエル・ダンタル侯爵、外務卿が教えてくれた。
一番面倒と聞いていたドラム公爵じゃなくってホッとした。
同じ方向の面倒なのかは謎だけど、わざわざ面倒な場面に遭遇したくないしね。
『こちらこそ、我が国にお出まし頂き、光栄至極です』
ガルフ侯爵が愛想良くダンタル侯爵と握手。
カイサル殿下とシャリアンヌ殿下が、ファリン殿下とルアラン殿下に直で話しかけてきた。うぉう。通訳必要なさそうだし離れたい。
『んっぬ。すまないっんね!公用語だっとぅ、わたぁーしの良さんっがっ伝わらないっんなっ』
ゲ。母国語だともっとすごい可能性を秘めているの!!??
『おっほうほぅ!おっにいしゃっまぁはぁ、ゴッガックゥからぁおっ逃げぇにィなっるぅからぁぁん』
(お兄さまは語学からお逃げになるから)
シャリアンヌ殿下も大差ない気がするんだけど。
独特なアクセント?訛りとは違うみたいだけど、私に移っちゃったらどうしよう。
ちなみにお二人ともわりと美形なのに言動とカボチャパンツで台無しなの。
王子様が二十五才くらいで、王女様が十九才くらいらしい。マジっすか。
王妃さまにこっそり聞いたら、グリーンリバーの女性も通常はドレスだそうなので、王女様は趣味か旅装か。
以前、お見えになった時は膝丈パンツだったそうなので、ドレスがお嫌いなのかも。
『そっなぁーたぁはぁ、陛ぃ下ぁのぉ、ほっごぉーうぉおぅ、うっけったぁむっすーめかぁ?』
(そなたは、陛下の保護を受けた娘か?)
めっっっんどくせぇな!!あ、お口が悪くなっちゃいました。
『グリーンリバーの尊きお方にご挨拶をする事をお許しください。私はジュリアス・グレーデン辺境伯が妻、リーシャ・グレーデンと申します。我が王より、ナギ国のファリン殿下、ルアラン殿下の通訳としてお側につかせて頂いております』
カーテシーの状態で停止して返事を待つ。
「ほぉほー、言葉にこっまればぁ、まっかせることぐぁ、でっきるなぁ?」
(ほほぅ、言葉に困れば、任せることができるかな?)
え。グリーンリバー語はレイドラアース語とちょっと違うけど、これは公用語の時よりちょっとマシなだけでは。
「おんにさまぁ!出っ来ぃるどぅあけ、こうよっぉうぐぉがぁよっろうしゅいぃわぁ」
(お兄さま、出来るだけ公用語がよろしいわ)
ぬー!これは、ちょっと難しいぞ。二カ国通訳になちゃう感じに頭使うぞ。
『っんむ!そっぉうかぁあっんぬっ』
(ぬ?そうか?)
始終こんな感じなの?
『グッゥレェデェンッのにはぁ、会った事ぐぁあっるまっす!!ヨッメをぉもらわぁんぬっとぅおっもってぇいっましタァがっおっ好みぬぉンっ、すぇいでぇしーったのんっねぇっ』
(グレーデンのには、会った事があります!嫁を貰わぬと思っていましたが、お好みのせいでしたのね)
おおぅ、ロリコン扱いぃ!王女様が酷い事言うって文句言いたいけど、この口調で話しを聞くの面倒だから泣き寝入りで良いかな?
横にいたセリウスさまが「流せー」って顔してるし、ルルゥは笑顔で顔を固めてるし、ガルフ侯爵は「スルーせよ」って顔。
うちの王子さまたちはすでに飽きてる。
ナギの人たちが笑顔のまま、凍りついてるよ。
『『彼女はこう見えて成人していて、嫁ぎ先のグレーデンで商業を発展させている敏腕な夫人だ』』
なぜか、ファリン殿下とルアラン殿下が庇ってくれた。話が長くなるし、もう良いんですよー。
王子様とダンタス侯爵が『ほう?』ってなっちゃった。
『見た目はレイドラアースの王子方とナギの王女方と大差なく見えるのに・・・』
グリーンリバーの皆さんの方からそんな言葉が聞こえてきた。
なんだとぉ!!!!
いくらなんでも私は十才には見えんだろうがぁい!!!
ふんぬー!
「ちゃんとリーシャちゃんの方が大人っぽいからねぇ」
後ろからルルゥにそっと肩を抑えられて慰められた。
グレーデンやホーンで小さく見えるのは仕方ないけど、王子さまたちよりは背丈もあるし、顔つきも子供じゃないもん。
『まぁあん!我っが国ぃにぃはぁ、こっこっまでぇペッタンこぉおーっぬあぁフッジィンはぁいらっしゃるっぅくぁしらぁ?』
(まあ!我が国には、ここまでペッタンコの夫人はいらっしゃらるかしら?)
私のお胸を見て、盛大に首を傾げるシャリアンヌ!!!絶許!!
敬称なんか排除だ。
全世界貧乳教会員を敵に回したな!?
そんな会はないけど、ツルペタ仲間を敵に回したよ!
シャリアンヌのお胸は大きくも小さくもない程よい丘に見える。が、王子様と同じベストの上にジャケットなのでハッキリはわからない。ちくせう!!でもお義母さまくらいあったら隠せないボリュームだから、多分人のこと言えるほど、大した事ないよ!!
『シャリゥアァンッンッヌッ!じょっせいぃうぁ、ムッネッっじゃぬぁいんっどぅあっんぬ!くぉっしぃだっよんっぬ!わったぁしぃぬぉツッマぬぉ、ん、ふぉっぉすぉくぅくっびぃれったぁ!くぉっし!よっぉいよっぅんぬ!』
(シャリアンヌ!女性は胸じゃないんだ!腰だよ!私の妻の、ん、細く括れた!腰!良いんだよ!)
細く括れた腰!それも私にはナッシング!
兄妹がしょうもない喧嘩してる。
その内容に私は連続して攻撃を受けてるんだけど。
『『リーシャはリーシャのままで良い。うるさいよりよほど良い事だしな』』
十二歳の王女さまたちに小声で励まされた。
国中の重鎮が集まり、ナギとグリーンリバーのお客様のいる前で子供体型だと周知されたんだけど、もうお家帰りたい。
___________________
グリーンリバーの面倒な二人は大した事を言ってないので、深く考えなくて良いかと訳を付けてなかったんですが、訳した方がいいとのことで訳を追加しました。
改めて打ち直すとくだらなさに精神が病みそうですw
自分にダメージが大きいので、面倒なキャラを考えたことに後悔中です。
イラっとさせてしまっていたら申し訳ない。
とっとと国へ追い出したいです⭐︎
24
お気に入りに追加
678
あなたにおすすめの小説

スローライフとは何なのか? のんびり建国記
久遠 れんり
ファンタジー
突然の異世界転移。
ちょっとした事故により、もう世界の命運は、一緒に来た勇者くんに任せることにして、いきなり告白された彼女と、日本へ帰る事を少し思いながら、どこでもキャンプのできる異世界で、のんびり暮らそうと密かに心に決める。
だけどまあ、そんな事は夢の夢。
現実は、そんな考えを許してくれなかった。
三日と置かず、騒動は降ってくる。
基本は、いちゃこらファンタジーの予定。
そんな感じで、進みます。
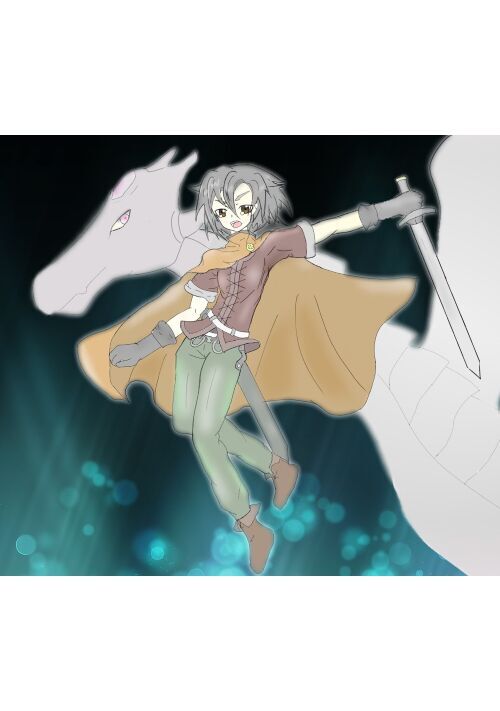
常世の守り主 ―異説冥界神話談―
双子烏丸
ファンタジー
かつて大切な人を失った青年――。
全てはそれを取り戻すために、全てを捨てて放浪の旅へ。
長い、長い旅で心も体も擦り減らし、もはやかつてとは別人のように成り果ててもなお、自らの願いのためにその身を捧げた。
そして、もはやその旅路が終わりに差し掛かった、その時。……青年が決断する事とは。
——
本編最終話には創音さんから頂いた、イラストを掲載しました!

婚約破棄されて辺境へ追放されました。でもステータスがほぼMAXだったので平気です!スローライフを楽しむぞっ♪
naturalsoft
恋愛
シオン・スカーレット公爵令嬢は転生者であった。夢だった剣と魔法の世界に転生し、剣の鍛錬と魔法の鍛錬と勉強をずっとしており、攻略者の好感度を上げなかったため、婚約破棄されました。
「あれ?ここって乙女ゲーの世界だったの?」
まっ、いいかっ!
持ち前の能天気さとポジティブ思考で、辺境へ追放されても元気に頑張って生きてます!

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~
おとら@ 書籍発売中
ファンタジー
アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。
どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。
そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。
その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。
その結果、様々な女性に迫られることになる。
元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。
「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」
今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

迷い人と当たり人〜伝説の国の魔道具で気ままに快適冒険者ライフを目指します〜
青空ばらみ
ファンタジー
一歳で両親を亡くし母方の伯父マークがいる辺境伯領に連れて来られたパール。 伯父と一緒に暮らすお許しを辺境伯様に乞うため訪れていた辺境伯邸で、たまたま出くわした侯爵令嬢の無知な善意により 六歳で見習い冒険者になることが決定してしまった! 運良く? 『前世の記憶』を思い出し『スマッホ』のチェリーちゃんにも協力してもらいながら 立派な冒険者になるために 前世使えなかった魔法も喜んで覚え、なんだか百年に一人現れるかどうかの伝説の国に迷いこんだ『迷い人』にもなってしまって、その恩恵を受けようとする『当たり人』と呼ばれる人たちに貢がれたり…… ぜんぜん理想の田舎でまったりスローライフは送れないけど、しょうがないから伝説の国の魔道具を駆使して 気ままに快適冒険者を目指しながら 周りのみんなを無自覚でハッピーライフに巻き込んで? 楽しく生きていこうかな! ゆる〜いスローペースのご都合ファンタジーです。
小説家になろう様でも投稿をしております。

死亡フラグだらけの悪役令嬢〜魔王の胃袋を掴めば回避できるって本当ですか?
きゃる
ファンタジー
侯爵令嬢ヴィオネッタは、幼い日に自分が乙女ゲームの悪役令嬢であることに気がついた。死亡フラグを避けようと悪役令嬢に似つかわしくなくぽっちゃりしたものの、17歳のある日ゲームの通り断罪されてしまう。
「僕は醜い盗人を妃にするつもりはない。この婚約を破棄し、お前を魔の森に追放とする!」
盗人ってなんですか?
全く覚えがないのに、なぜ?
無実だと訴える彼女を、心優しいヒロインが救う……と、思ったら⁉︎
「ふふ、せっかく醜く太ったのに、無駄になったわね。豚は豚らしく這いつくばっていればいいのよ。ゲームの世界に転生したのは、貴女だけではないわ」
かくしてぽっちゃり令嬢はヒロインの罠にはまり、家族からも見捨てられた。さらには魔界に迷い込み、魔王の前へ。「最期に言い残すことは?」「私、お役に立てます!」
魔界の食事は最悪で、控えめに言ってかなりマズい。お城の中もほこりっぽくて、気づけば激ヤセ。あとは料理と掃除を頑張って、生き残るだけ。
多くの魔族を味方につけたヴィオネッタは、魔王の心(胃袋?)もつかめるか? バッドエンドを回避して、満腹エンドにたどり着ける?
くせのある魔族や魔界の食材に大奮闘。
腹黒ヒロインと冷酷王子に大慌て。
元悪役令嬢の逆転なるか⁉︎
※レシピ付き

【完結】聖獣もふもふ建国記 ~国外追放されましたが、我が領地は国を興して繁栄しておりますので御礼申し上げますね~
綾雅(ヤンデレ攻略対象、電子書籍化)
ファンタジー
婚約破棄、爵位剥奪、国外追放? 最高の褒美ですね。幸せになります!
――いま、何ておっしゃったの? よく聞こえませんでしたわ。
「ずいぶんと巫山戯たお言葉ですこと! ご自分の立場を弁えて発言なさった方がよろしくてよ」
すみません、本音と建て前を間違えましたわ。国王夫妻と我が家族が不在の夜会で、婚約者の第一王子は高らかに私を糾弾しました。両手に花ならぬ虫を這わせてご機嫌のようですが、下の緩い殿方は嫌われますわよ。
婚約破棄、爵位剥奪、国外追放。すべて揃いました。実家の公爵家の領地に戻った私を出迎えたのは、溺愛する家族が興す新しい国でした。領地改め国土を繁栄させながら、スローライフを楽しみますね。
最高のご褒美でしたわ、ありがとうございます。私、もふもふした聖獣達と幸せになります! ……余計な心配ですけれど、そちらの国は傾いていますね。しっかりなさいませ。
【同時掲載】小説家になろう、アルファポリス、カクヨム、エブリスタ
※2022/05/10 「HJ小説大賞2021後期『ノベルアップ+部門』」一次選考通過
※2022/02/14 エブリスタ、ファンタジー 1位
※2022/02/13 小説家になろう ハイファンタジー日間59位
※2022/02/12 完結
※2021/10/18 エブリスタ、ファンタジー 1位
※2021/10/19 アルファポリス、HOT 4位
※2021/10/21 小説家になろう ハイファンタジー日間 17位

無一文で追放される悪女に転生したので特技を活かしてお金儲けを始めたら、聖女様と呼ばれるようになりました
結城芙由奈@コミカライズ発売中
恋愛
スーパームーンの美しい夜。仕事帰り、トラックに撥ねらてしまった私。気づけば草の生えた地面の上に倒れていた。目の前に見える城に入れば、盛大なパーティーの真っ最中。目の前にある豪華な食事を口にしていると見知らぬ男性にいきなり名前を呼ばれて、次期王妃候補の資格を失ったことを聞かされた。理由も分からないまま、家に帰宅すると「お前のような恥さらしは今日限り、出ていけ」と追い出されてしまう。途方に暮れる私についてきてくれたのは、私の専属メイドと御者の青年。そこで私は2人を連れて新天地目指して旅立つことにした。無一文だけど大丈夫。私は前世の特技を活かしてお金を稼ぐことが出来るのだから――
※ 他サイトでも投稿中
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















