269 / 1,035
第三章 第一節 魔法少女
第268話 なにを見たのだ——
しおりを挟む
他殺体が見つかった——。
生体管理局の管理AIからの一報は、イギリス警察を混乱させた。
この時代においては殺人事件や事故はほとんど発生しなくなったため、死体がどこかしらで見つかる、という事例はさほど多くない。それが他殺体となると、さらにその希少性は高まる。殺人を扱う刑事であっても、一生に一~二回出くわすかどうかだ。
ジョナサンは刑事になってからもう数年経つが、自分が現場に出向かされるとは思っていなかった。自分はすでにベテランの域に達していると思っていたし、なにより死体検分の立ち会いなどは、ぺーぺーの新人の仕事と相場が決まっている。
しかもAI管理局が指摘してきた場所は、運のわるいことにランカシャー警察の管轄の一番端にある港街「フリートウッド」だった。ここに港があったのは、もう二百年以上も前の話で、海洋資源が枯渇してからはすっかり寂れ果て、今ではただの倉庫街となっていた。そこはロボット作業員以外には遠隔操作で監視をする『素体』が十体あるかないか、という『閑疎』な場所で、直接、人間が足を踏み入れることはない。
だが、ひとっこひとりいないはずの場所で死体が見つかったのが不可解だった。
生体管理局のAI監視システムの目を盗んで、人を殺した事実だけでも驚愕なことであったが、だれもいないはずの場所で、となると、最新鋭のAI分析システムでもお手上げ状態のようだった。
納得のいく理由づけはおろか、もっともらしい仮説すらなく、結局『分析不能』のひと言で、人間側に丸投げしてきている始末だ。
「なんで先輩が選ばれたんでしょうね?」
電磁誘導パルスレーンに誘導された自動運転で、空を飛んでいるスカイモービルの運転席で新米刑事のディオが軽口を叩いた。
ジョナサンはその無神経質さにイラッとした。ジョナサン自身、その答えをもらわないまま、なし崩し的に現場に出向かされたことに腹がたっているのだ。それをただの疑問形ごときで、気軽に口の端にのぼらされてはたまらない。
ディオはスパニッシュ系の陽気な性格で、正直物で信心深い男だったが、お世辞に仕事ができるとは言えなかった。なにかあると、『これ、ぼくの仕事っすか』というのが口癖で、犯罪の種類や現場、一緒に組むバディをえり好みするきらいがあった。
残念なことに、デュオはジョナサンをえり好みの対象にしてくれなかった。犯罪管理局からの指示でジョナサンと組まされると聞くと、いちもにもなく馳せ参じた。
「他殺体が発見されたんだ。だれかが立ち会うしかないだろ。それに上からのご指名だ」
「でも、これぼくらの仕事っすかねぇ」
「あぁ。オレたちの仕事だ。死人がでたときは、ロボット検死官やAI鑑識システム以外に、生身の人間がかならず二名以上現場に立ち会うことが、国際法で義務づけられているからな」
「でもなんで『フリートウッド』なんかに?。あんなとこ、なにもないでしょう」
「オレも知っちゃあいない。この倉庫街はシステムによって管理されている『食料保管庫』だから、基本的に人間は立ち入り禁止なはずだ。どうやって監視をくぐり抜けて入ったかがまったくわからんよ」
「えぇ。かなり警備は厳しいはずですし、許可なく人間が近づいただけで、ロボット警備兵が大挙してすっ飛んできて排除されますからね。このエリアに近づくだけでも至難の技ですよ。現にわれわれも現場へ急行させられたのに、近接許可がでるのに24時間待ちぼうけを喰らわされましたからね」
「あぁ。捜査しろと出動命令をよこしやがったのに、まるいちにち足止め喰らわすったぁ、どういう了見なんだろうな」
「それよか、AI監視システムはどうなってんでしょう。他殺体となれば、殺した犯人がいるっていうわけでしょう。なんで殺意を感知した時点で通報なり、生体操作で随意筋のロックとかしなかったんでしょう」
「いや、だいたい被害者がだれかがまだわかってないんだ。それがおかしい。ふつうなら命が脅かされた時点で、生体管理局のAIが危機を捕捉するだろうし、心肺停止したら、その瞬間にアラートや通報がリアルタイムでAI監視網にひっかかるはずだ」
「そうですよね。死後数日経った『死体』、なんて形で発見されるわけがないッスよね」
眼下に『フリートウッド』の倉庫街が見えてきた。倉庫は余った土地を埋め尽くすように広がっていた。ひとつの街がまるまる倉庫になっているような景観で、しかもどれもが平屋建てか、せいぜい二階建てという造りになっている。人が住まわない場所には、最先端の技術も、予算のかかる高層建築も必要ないという、割り切った発想の街だった。
上から街並みをみると、この場所にはスカイモービルでしかアクセスできないという事実をあらためて思い知らされる。
指定場所に近づくと、誘導ビーコンによって自動牽引されて、スカイモービルがゆっくりと下降をはじめた。
「死体の主は、陸路で来たのかな?」
「いや、ここまでの道はもう完全になくなってますよ。街がなくなってもう二世紀経ってますから、整備も怠っているし、途中までこれたとしてもここまではさすがに……」
「なら、船を使って海から近づいたのか?」
「それも無理だと思いますよ。ここの海は環境の変化で相当に荒れるそうですし、そもそも船をどこから調達するんです。スカイ・シップならまだしも、海の上をいく船なんてタンカーやクルーズ船くらいしか今はないですよ」
「だったら、被害者はどうやって……、いや犯人もそうだ。ふたりはどうやってここに来たんだ?」
スカイモービルから降りると、案内係とおぼしきロボットが待ちかまえていた。
「ランカシャー警察のジョナサンとディオだ。検死の立ち会いにきた。もうロボット検死官と鑑識AI班は到着してるんだろ?」
「お待ちしていました」
ロボットは、挨拶らしい挨拶もここまでの苦労を労うこともなく、くるりと背をむけて前に進みはじめた。あとからついてこい、ということらしい。ジョナサンは自動で目的地まで人々を運ぶ『コンベア・ロード』がないか捜してみたが、元々ここに人が来ることは想定されていないのだからあるわけがない。しぶしぶ自分の足で歩き出した。歩きはじめるとディオが訊いてきた。
「ところで、なんでこの場所に他殺体があるとわかったんですか?」
「あぁ。この間、『給電ステーション』の定期検査中に事故があっただろう」
ディオが『給電ステーション』に反応して、見るとはなしに空を見あげた。
「宇宙に浮かんでいる太陽光エネルギーを直接取り込むっていう、あれですね」
「いや、それは『太陽光オービタル』だ。『給電ステーション』はその光エネルギーを『エーテル電気』に変換して地表に送る中継基地で『外気圏』にあるやつだ」
「まー、ようするに、そのワイヤレス給電の施設のメンテナンス中に事故があったってことすよね」
「あぁ、ほんの0・数秒——。一瞬だけ給電が切断される事故が起きた。で、そのわずかな瞬間に、死体の生体チップの信号を生体管理局がキャッチアップしたらしい」
「偶然見つかった……、ってことですか」
案内係に連れて来られたその建屋は、街で言えば中心部になるであろう場所に位置する倉庫だった。ほかの建物に比べてもひときわ大きく見えた。
建屋の正面にあるおおきな扉に目をむけると、扉を背にして、ロボット検死官が仁王立ちのまま待っていた。このロボットは正式には、『KIT』のなんたらかんたらという型番号がついていたが、刑事たちはみな『キッチュ』と呼んでいた。検死官のロボットのくせになぜかトレンチコートを着ていて、まるっきり古くさいドラマの刑事の姿を模していた。ただ、問題はそれが目が痛くなるようなド派手な原色使いで、しかも冬も夏もかまわず着てくるため、現場の人間たちにはすこぶる評判がわるかった。どぎついやら暑苦しいやらで、いつからか『けばけばしい・悪趣味』という意味のあだ名で呼ばれたが、誰もそれに異を唱えるものはなかった。
その隣には鑑識システムロボが鎮座していた。ちょっとしたデスクほどの大きさで、六本脚で歩行する。現場をスキャンし、その場で検査や分析を行う機能を搭載しているので自走するラボという謳い文句だったが、刑事たちはみな『キッチン』と呼んでいた。テーブル面に設えられた検査エリアが、むかし各家庭に備わっていた『台所』という場所に似ているという話だった。
今では職業人やそういう趣味を持つ人でもない限り、家庭で『料理』を作るということがないので、ジョナサンもたぶん『台所』に似ているのだろう、という認識しかない。
キッチュ・キッチン——。毎度おなじみのコンビだ。
ジョナサンたちが近づくと、正面に立っていたロボット検死官『キッチュ』の目が光って起動した。まる一日待たされることになったので、省電力設定になっていたらしい。それを合図のようにして隣の六本脚の鑑識システムロボ『キッチン』が、折り曲げた脚を持ちあげて身体を起こした。
「待ってましたよ。ジョナサンさん、デュオさん」
見てくれからはすこし想像しにくい高い声が、ふたりを歓迎した。
「おぉ、悪いな。許可がおりなくて、丸一日足止めくったよ」
ジョナサンは相手がロボットであるとはわかっていたが、すこし皮肉をこめて、キッチュに詫びをいれた。
「検死官どの、死体どこですかね。まさかぼくたちが遅れたから、死体が腐乱しちゃってるなんてこと、ないですよね?」
ディオが端にも棒にもかからない冗談をキッチュにかました。
「ご安心ください。死体は『エレメント・フリージング(元素凍結)』倉庫内にあります」
「おいおい、おれたちが遅れたからといって、勝手にフリージング処理するのはだめだろう」
「いえ。死体は元素凍結倉庫内で見つかったのです。ですからわたしたちが運び込んだわけではありません」
「ちょっと待ってくれ。死体が凍結室で見つかったって……。そこは外部の人間の手で勝手に開けたり閉めたりできないだろう。まさか開閉システムがハッキングでもされたのか?」
「いいえ。まったく異常は感知されていません。この倉庫は330日と13時間一度も入出庫された記録はありません」
ディオがそのおかしな報告に、すぐさま食いついた。
「え?。どういうことです?。約一年も開け閉めがないって……、その被害者は一年前に殺されたってことですか?」
「それがわからないので、人間の方へ立ち会いを依頼しているのです。あまりにもイレギュラーすぎて、われわれAIでは合理的な説明ができません。ぜひ人間の直感やひらめきの力を貸してください」
「つまり、我々の『想覚』や『霊覚』を働かせてくれってことですね」
「ずいぶん気を使いそうッすね。これってぼくらの仕事ッスかねぇ」
少々『頭』を使う事案とわかって、ディオがまたいつものように軽口を叩いてきた。
「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」
キッチュはディオの抗議をまるっきり無視して、背後にある大きな扉のほうに近づいて言った。すぐにズズズとくぐもった響きとともに扉が開きはじめる。キッチュは足裏から超流動斥力波を発生させて、身体をすこしホバリングさせると、そのまますこし浮遊した状態で滑るように中へと入っていった。すぐに鑑識ロボのキッチンがそのうしろに続く。
建物のなかはいくつもの通路が縦横に通っていて、区画ごとにきれいに切り分けられていた。そこに、おなじような見た目の『元素凍結室』が整然と並び、それが奥までずっと続いている。
ジョナサンは思ってた以上に広いと感じた。捜し出すまでに、相当時間がかかることを覚悟したが、キッチュは迷いもなく進んでいった。そして300メートルほど進んだところでキッチュが停止し、ふたりのほうへ上半身だけ回転させて言った。
「ここの『元素凍結室』です」
そう示された部屋はほかの場所に比べて、かなり小さかった。外から見ただけではわからなかったが、容積は『スカッシュ』のコートくらいしかないように思える。
「ほかと比べて、ずいぶん小さい部屋っすね」
ディオが見たままの印象を口にした。
「えぇ。この部屋は『レンタル貯蔵庫』で、『資源』をお持ちの方用として用意されたものですから……」
「はぁ、『資源持ち』様専用っすか?。で、ここはだれが借りてるんです?」
「いえ、この10年間借り手はおりません。ずっと空きとなっております」
ジョナサンの頭に疑問が浮かんだ。
「ずっと空きなら中はどうなってる?。元素凍結装置は動いてないのだろう?」
「いえ、空でも常に稼働しております。ですので、なかのものはすべて凍結しております」
「カッチ、カッチなのかい?」
ディオがすこしからかうような口調で訊いた。
「えぇ。常温での元素単位の『凝結』ですが、見た目は冷温で凍ったような……、そう『カッチ、カッチ』になっております」
「やっかいだな。凝結された死体では、検死に時間がかかりそうだ……」
ジョナサンはさらに時間をとられるのを予感したが、どっちにしろ最後まで立ち会うのが仕事なのだから、諦めるしかないと腹を括った。
「まぁ、いい。この扉を開けてくれ」
ディオが扉の前に進み出た。現場を前にしてテンションがあがってきたようで、ジョナサンに先んじて現場に踏み込もうとばかりに、うずうずしている様子が見て取れた。
扉がひらくとなかから、すこしひんやりとした白い靄がふわっと吹き出してきた。かすかにフリージング臭が鼻をつく。ディオは開くか、開かないかというタイミングで、なかに滑り込もうとしたが、すぐに足をとめてその場に立ち尽くした。
吹き出してきた靄でなかは見えなかったが、見えているディオの横顔だけでただ事ではないとわかった。
「どうした、ディオ?」
ディオの目はおおきく見開かれて、顔が強ばっていた。
「ひとり……じゃない……」
貯蔵庫のなかで、ゴトリ、と音がした。
その瞬間、貯蔵庫の入り口から、死体が滑り出てきた。
一体……ではなかった——。
ゴトン、ゴトンという派手な音と共に、凍った死体があとからあとから滑り出してきた。ディオがその死体に足元をすくわれて、その場に転倒するのが見えた。ジョナサンも避けきれない。凍った死体に足を叩かれ、背中からひっくり返りそうになり、隣に立っていたキッチュのコートの裾をつかんだ。だが、その悪あがきをあざ笑うように、あとからあとから死体の雪崩が押し寄せてきて、ジョナサンを引き剥がそうとする。
ジョナサンにあらゆる人種の死体が襲いかかった——。
黒人の男の死体にひざ頭をぶつけられて、よろめいたところに東洋系の女性の死体が胸を強打した。あわてて立ちあがった股のあいだを、ヒスパニック系の髭面の男の死体がすりぬけていく。
死体は完全体だけではなかった。途中から頭だけがまとまって何個も転がってきたかと思うと、腕、脚が滑ってきて、その隙間に胴体がそれを追い抜いていったりした。
怒濤の勢いで押し寄せる死体に、さすがの『キッチュ』も足元がふらついていた。ふと背後を見るとすでに『キッチン』は横倒しになっている。死体の洪水はなおも続き、貯蔵庫の入り口からはなおも死体が吐き出され続ける。
『数十体やそこらなんかじゃきかないぞ』
パニックになりかかった頭でどこか冷静な部分が、ざっくりとでも死体の数を把握しようと務めていた。あまりにも信じがたい状況で、かえってどこかが醒めてしまったのかもしれない。
ジョナサンはふと、昔映像学習で見た、魚が陸揚げされたときの映像を思い出した。種類はわからなかったが、冷凍されたおおきな魚が、床を滑るようにしてどんどん集められている映像。まだ海洋資源が豊富に獲れていた500年ほど前の話だ。もしかしたら元漁港だったこの「フリートウッド」でも、むかしは見られたかもしれない光景だ。
今、自分にふりかかったこの事態は、それに似ている。ただ違いは、滑ってくるのが魚ではなく人間だということだ。
死体の転がってくる勢いがやっとおさまったと思った時には、ジョナサンは散乱したおびただしい数の死体に囲まれていた。一番遠くまで滑っていった死体は、ほかの死体に押されたせいで、100メートルほど奥にまでに達している。
「くそぅ、マジかよ」
ジョナサンは腹立ちまぎれに言ったが、すぐにディオがどうなったか気になって、すぐに右目の網膜の下部に表示されている自分とディオのヴァイタル・データを注視した。
その数字はディオがまだ生きていることを示していた。あわててあたりを見回す。
どこにもいない——?。
一瞬そう思ったが、床を埋め尽くす死体の隙間から、ディオが半身をおこすのが見えた。よくみると彼は壁面近くにある、ポールのようなものにつかまって、死体の雪崩を耐え忍んでいたようだった。地面に這いつくばっていたため、顔や頭に傷を負っており、痛々しかった。
「ディオ、大丈夫か?」
ジョナサンは声をかけたが、ディオはそれには答えようとしなかった。彼は貯蔵庫の開いたままの入り口のなかを覗き込んでいた。いや、なにかに見入られていたというべきかもしれない。
これ以上、なにがあるというのか……。
ジョナサンも気になって、入り口のほうへ目を向けた。
と、わずかになかの光が見えた。そしてその光のなかで、誰かが、いやすくなくとも何かが、動いているのが見えた。ジョナサンからはよく見えない角度だったので、それがなにかはまったく見当もつかない。
だが、正面でそれをまともに見たディオは、目をおおきく見開いていた。よく見ると手や足が震えている。あわててディオの元へ駆け寄る。
「おい、ディオ、どうした?」
ジョナサンはすこしでも落ち着くように、とびっきり優しい口調でそう言った。だが、ディオの返事は長くたなびく悲鳴だった。ディオは自分の顔を自分で掻きむしりながら、悲鳴をあげはじめた。ジョナサンはディオの横で片膝をたてると、ディオの背中にゆっくりと手をまわした。落ち着かせようと背中をさすりかけた手がとまる。
ジョナサンの網膜に表示されたディオのヴァイタル・データに異常な数字が示されていた。いや異常というレベルではない。ディオの脳波は尋常ならざる波形を刻んでいる。
ジョナサンはディオの顔を見た。
ディオは狂っていた——。
あきらかに目の焦点があっていない。顔は恐怖のあまり病的なまでに歪み、まともではない表情となっていた。そして、口元にはぞっとする薄ら笑いを浮かべていた。
ジョナサンは反射的にディオがなにかを見た貯蔵庫のなかに目をむけた。
ほんの一瞬だけだったが、奥のほうでなにものかが動いているのが見えたような気がした。そこに空間の切れ目のような光が漏れでていて、その何者かがそのなかへ戻ろうとしている——。そう見えた。が、すぐにそれは消え去り、ただの貯蔵庫の壁だけになった。
ジョナサンはディオの顔に目を向けた。
すでに悲鳴はやんでいたが、代わりにディオは笑い出していた。顔にはすぐ軽口を叩きたがる陽気なディオの面影はすでになかった。笑い声がしだいに大きくなる。それは得体のしれない邪教で使われる楽器を、けたたましく打ち鳴らしているような禍々しい笑い声だった。およそ人間の声帯から発せられるとは思えない。
ジョナサンは恐怖のあまり、その場に崩れ落ちた。
なにを見たのだ——。
なにを見たら、一瞬にして気が狂ってしまうのだ?——。
なにを……。
生体管理局の管理AIからの一報は、イギリス警察を混乱させた。
この時代においては殺人事件や事故はほとんど発生しなくなったため、死体がどこかしらで見つかる、という事例はさほど多くない。それが他殺体となると、さらにその希少性は高まる。殺人を扱う刑事であっても、一生に一~二回出くわすかどうかだ。
ジョナサンは刑事になってからもう数年経つが、自分が現場に出向かされるとは思っていなかった。自分はすでにベテランの域に達していると思っていたし、なにより死体検分の立ち会いなどは、ぺーぺーの新人の仕事と相場が決まっている。
しかもAI管理局が指摘してきた場所は、運のわるいことにランカシャー警察の管轄の一番端にある港街「フリートウッド」だった。ここに港があったのは、もう二百年以上も前の話で、海洋資源が枯渇してからはすっかり寂れ果て、今ではただの倉庫街となっていた。そこはロボット作業員以外には遠隔操作で監視をする『素体』が十体あるかないか、という『閑疎』な場所で、直接、人間が足を踏み入れることはない。
だが、ひとっこひとりいないはずの場所で死体が見つかったのが不可解だった。
生体管理局のAI監視システムの目を盗んで、人を殺した事実だけでも驚愕なことであったが、だれもいないはずの場所で、となると、最新鋭のAI分析システムでもお手上げ状態のようだった。
納得のいく理由づけはおろか、もっともらしい仮説すらなく、結局『分析不能』のひと言で、人間側に丸投げしてきている始末だ。
「なんで先輩が選ばれたんでしょうね?」
電磁誘導パルスレーンに誘導された自動運転で、空を飛んでいるスカイモービルの運転席で新米刑事のディオが軽口を叩いた。
ジョナサンはその無神経質さにイラッとした。ジョナサン自身、その答えをもらわないまま、なし崩し的に現場に出向かされたことに腹がたっているのだ。それをただの疑問形ごときで、気軽に口の端にのぼらされてはたまらない。
ディオはスパニッシュ系の陽気な性格で、正直物で信心深い男だったが、お世辞に仕事ができるとは言えなかった。なにかあると、『これ、ぼくの仕事っすか』というのが口癖で、犯罪の種類や現場、一緒に組むバディをえり好みするきらいがあった。
残念なことに、デュオはジョナサンをえり好みの対象にしてくれなかった。犯罪管理局からの指示でジョナサンと組まされると聞くと、いちもにもなく馳せ参じた。
「他殺体が発見されたんだ。だれかが立ち会うしかないだろ。それに上からのご指名だ」
「でも、これぼくらの仕事っすかねぇ」
「あぁ。オレたちの仕事だ。死人がでたときは、ロボット検死官やAI鑑識システム以外に、生身の人間がかならず二名以上現場に立ち会うことが、国際法で義務づけられているからな」
「でもなんで『フリートウッド』なんかに?。あんなとこ、なにもないでしょう」
「オレも知っちゃあいない。この倉庫街はシステムによって管理されている『食料保管庫』だから、基本的に人間は立ち入り禁止なはずだ。どうやって監視をくぐり抜けて入ったかがまったくわからんよ」
「えぇ。かなり警備は厳しいはずですし、許可なく人間が近づいただけで、ロボット警備兵が大挙してすっ飛んできて排除されますからね。このエリアに近づくだけでも至難の技ですよ。現にわれわれも現場へ急行させられたのに、近接許可がでるのに24時間待ちぼうけを喰らわされましたからね」
「あぁ。捜査しろと出動命令をよこしやがったのに、まるいちにち足止め喰らわすったぁ、どういう了見なんだろうな」
「それよか、AI監視システムはどうなってんでしょう。他殺体となれば、殺した犯人がいるっていうわけでしょう。なんで殺意を感知した時点で通報なり、生体操作で随意筋のロックとかしなかったんでしょう」
「いや、だいたい被害者がだれかがまだわかってないんだ。それがおかしい。ふつうなら命が脅かされた時点で、生体管理局のAIが危機を捕捉するだろうし、心肺停止したら、その瞬間にアラートや通報がリアルタイムでAI監視網にひっかかるはずだ」
「そうですよね。死後数日経った『死体』、なんて形で発見されるわけがないッスよね」
眼下に『フリートウッド』の倉庫街が見えてきた。倉庫は余った土地を埋め尽くすように広がっていた。ひとつの街がまるまる倉庫になっているような景観で、しかもどれもが平屋建てか、せいぜい二階建てという造りになっている。人が住まわない場所には、最先端の技術も、予算のかかる高層建築も必要ないという、割り切った発想の街だった。
上から街並みをみると、この場所にはスカイモービルでしかアクセスできないという事実をあらためて思い知らされる。
指定場所に近づくと、誘導ビーコンによって自動牽引されて、スカイモービルがゆっくりと下降をはじめた。
「死体の主は、陸路で来たのかな?」
「いや、ここまでの道はもう完全になくなってますよ。街がなくなってもう二世紀経ってますから、整備も怠っているし、途中までこれたとしてもここまではさすがに……」
「なら、船を使って海から近づいたのか?」
「それも無理だと思いますよ。ここの海は環境の変化で相当に荒れるそうですし、そもそも船をどこから調達するんです。スカイ・シップならまだしも、海の上をいく船なんてタンカーやクルーズ船くらいしか今はないですよ」
「だったら、被害者はどうやって……、いや犯人もそうだ。ふたりはどうやってここに来たんだ?」
スカイモービルから降りると、案内係とおぼしきロボットが待ちかまえていた。
「ランカシャー警察のジョナサンとディオだ。検死の立ち会いにきた。もうロボット検死官と鑑識AI班は到着してるんだろ?」
「お待ちしていました」
ロボットは、挨拶らしい挨拶もここまでの苦労を労うこともなく、くるりと背をむけて前に進みはじめた。あとからついてこい、ということらしい。ジョナサンは自動で目的地まで人々を運ぶ『コンベア・ロード』がないか捜してみたが、元々ここに人が来ることは想定されていないのだからあるわけがない。しぶしぶ自分の足で歩き出した。歩きはじめるとディオが訊いてきた。
「ところで、なんでこの場所に他殺体があるとわかったんですか?」
「あぁ。この間、『給電ステーション』の定期検査中に事故があっただろう」
ディオが『給電ステーション』に反応して、見るとはなしに空を見あげた。
「宇宙に浮かんでいる太陽光エネルギーを直接取り込むっていう、あれですね」
「いや、それは『太陽光オービタル』だ。『給電ステーション』はその光エネルギーを『エーテル電気』に変換して地表に送る中継基地で『外気圏』にあるやつだ」
「まー、ようするに、そのワイヤレス給電の施設のメンテナンス中に事故があったってことすよね」
「あぁ、ほんの0・数秒——。一瞬だけ給電が切断される事故が起きた。で、そのわずかな瞬間に、死体の生体チップの信号を生体管理局がキャッチアップしたらしい」
「偶然見つかった……、ってことですか」
案内係に連れて来られたその建屋は、街で言えば中心部になるであろう場所に位置する倉庫だった。ほかの建物に比べてもひときわ大きく見えた。
建屋の正面にあるおおきな扉に目をむけると、扉を背にして、ロボット検死官が仁王立ちのまま待っていた。このロボットは正式には、『KIT』のなんたらかんたらという型番号がついていたが、刑事たちはみな『キッチュ』と呼んでいた。検死官のロボットのくせになぜかトレンチコートを着ていて、まるっきり古くさいドラマの刑事の姿を模していた。ただ、問題はそれが目が痛くなるようなド派手な原色使いで、しかも冬も夏もかまわず着てくるため、現場の人間たちにはすこぶる評判がわるかった。どぎついやら暑苦しいやらで、いつからか『けばけばしい・悪趣味』という意味のあだ名で呼ばれたが、誰もそれに異を唱えるものはなかった。
その隣には鑑識システムロボが鎮座していた。ちょっとしたデスクほどの大きさで、六本脚で歩行する。現場をスキャンし、その場で検査や分析を行う機能を搭載しているので自走するラボという謳い文句だったが、刑事たちはみな『キッチン』と呼んでいた。テーブル面に設えられた検査エリアが、むかし各家庭に備わっていた『台所』という場所に似ているという話だった。
今では職業人やそういう趣味を持つ人でもない限り、家庭で『料理』を作るということがないので、ジョナサンもたぶん『台所』に似ているのだろう、という認識しかない。
キッチュ・キッチン——。毎度おなじみのコンビだ。
ジョナサンたちが近づくと、正面に立っていたロボット検死官『キッチュ』の目が光って起動した。まる一日待たされることになったので、省電力設定になっていたらしい。それを合図のようにして隣の六本脚の鑑識システムロボ『キッチン』が、折り曲げた脚を持ちあげて身体を起こした。
「待ってましたよ。ジョナサンさん、デュオさん」
見てくれからはすこし想像しにくい高い声が、ふたりを歓迎した。
「おぉ、悪いな。許可がおりなくて、丸一日足止めくったよ」
ジョナサンは相手がロボットであるとはわかっていたが、すこし皮肉をこめて、キッチュに詫びをいれた。
「検死官どの、死体どこですかね。まさかぼくたちが遅れたから、死体が腐乱しちゃってるなんてこと、ないですよね?」
ディオが端にも棒にもかからない冗談をキッチュにかました。
「ご安心ください。死体は『エレメント・フリージング(元素凍結)』倉庫内にあります」
「おいおい、おれたちが遅れたからといって、勝手にフリージング処理するのはだめだろう」
「いえ。死体は元素凍結倉庫内で見つかったのです。ですからわたしたちが運び込んだわけではありません」
「ちょっと待ってくれ。死体が凍結室で見つかったって……。そこは外部の人間の手で勝手に開けたり閉めたりできないだろう。まさか開閉システムがハッキングでもされたのか?」
「いいえ。まったく異常は感知されていません。この倉庫は330日と13時間一度も入出庫された記録はありません」
ディオがそのおかしな報告に、すぐさま食いついた。
「え?。どういうことです?。約一年も開け閉めがないって……、その被害者は一年前に殺されたってことですか?」
「それがわからないので、人間の方へ立ち会いを依頼しているのです。あまりにもイレギュラーすぎて、われわれAIでは合理的な説明ができません。ぜひ人間の直感やひらめきの力を貸してください」
「つまり、我々の『想覚』や『霊覚』を働かせてくれってことですね」
「ずいぶん気を使いそうッすね。これってぼくらの仕事ッスかねぇ」
少々『頭』を使う事案とわかって、ディオがまたいつものように軽口を叩いてきた。
「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」
キッチュはディオの抗議をまるっきり無視して、背後にある大きな扉のほうに近づいて言った。すぐにズズズとくぐもった響きとともに扉が開きはじめる。キッチュは足裏から超流動斥力波を発生させて、身体をすこしホバリングさせると、そのまますこし浮遊した状態で滑るように中へと入っていった。すぐに鑑識ロボのキッチンがそのうしろに続く。
建物のなかはいくつもの通路が縦横に通っていて、区画ごとにきれいに切り分けられていた。そこに、おなじような見た目の『元素凍結室』が整然と並び、それが奥までずっと続いている。
ジョナサンは思ってた以上に広いと感じた。捜し出すまでに、相当時間がかかることを覚悟したが、キッチュは迷いもなく進んでいった。そして300メートルほど進んだところでキッチュが停止し、ふたりのほうへ上半身だけ回転させて言った。
「ここの『元素凍結室』です」
そう示された部屋はほかの場所に比べて、かなり小さかった。外から見ただけではわからなかったが、容積は『スカッシュ』のコートくらいしかないように思える。
「ほかと比べて、ずいぶん小さい部屋っすね」
ディオが見たままの印象を口にした。
「えぇ。この部屋は『レンタル貯蔵庫』で、『資源』をお持ちの方用として用意されたものですから……」
「はぁ、『資源持ち』様専用っすか?。で、ここはだれが借りてるんです?」
「いえ、この10年間借り手はおりません。ずっと空きとなっております」
ジョナサンの頭に疑問が浮かんだ。
「ずっと空きなら中はどうなってる?。元素凍結装置は動いてないのだろう?」
「いえ、空でも常に稼働しております。ですので、なかのものはすべて凍結しております」
「カッチ、カッチなのかい?」
ディオがすこしからかうような口調で訊いた。
「えぇ。常温での元素単位の『凝結』ですが、見た目は冷温で凍ったような……、そう『カッチ、カッチ』になっております」
「やっかいだな。凝結された死体では、検死に時間がかかりそうだ……」
ジョナサンはさらに時間をとられるのを予感したが、どっちにしろ最後まで立ち会うのが仕事なのだから、諦めるしかないと腹を括った。
「まぁ、いい。この扉を開けてくれ」
ディオが扉の前に進み出た。現場を前にしてテンションがあがってきたようで、ジョナサンに先んじて現場に踏み込もうとばかりに、うずうずしている様子が見て取れた。
扉がひらくとなかから、すこしひんやりとした白い靄がふわっと吹き出してきた。かすかにフリージング臭が鼻をつく。ディオは開くか、開かないかというタイミングで、なかに滑り込もうとしたが、すぐに足をとめてその場に立ち尽くした。
吹き出してきた靄でなかは見えなかったが、見えているディオの横顔だけでただ事ではないとわかった。
「どうした、ディオ?」
ディオの目はおおきく見開かれて、顔が強ばっていた。
「ひとり……じゃない……」
貯蔵庫のなかで、ゴトリ、と音がした。
その瞬間、貯蔵庫の入り口から、死体が滑り出てきた。
一体……ではなかった——。
ゴトン、ゴトンという派手な音と共に、凍った死体があとからあとから滑り出してきた。ディオがその死体に足元をすくわれて、その場に転倒するのが見えた。ジョナサンも避けきれない。凍った死体に足を叩かれ、背中からひっくり返りそうになり、隣に立っていたキッチュのコートの裾をつかんだ。だが、その悪あがきをあざ笑うように、あとからあとから死体の雪崩が押し寄せてきて、ジョナサンを引き剥がそうとする。
ジョナサンにあらゆる人種の死体が襲いかかった——。
黒人の男の死体にひざ頭をぶつけられて、よろめいたところに東洋系の女性の死体が胸を強打した。あわてて立ちあがった股のあいだを、ヒスパニック系の髭面の男の死体がすりぬけていく。
死体は完全体だけではなかった。途中から頭だけがまとまって何個も転がってきたかと思うと、腕、脚が滑ってきて、その隙間に胴体がそれを追い抜いていったりした。
怒濤の勢いで押し寄せる死体に、さすがの『キッチュ』も足元がふらついていた。ふと背後を見るとすでに『キッチン』は横倒しになっている。死体の洪水はなおも続き、貯蔵庫の入り口からはなおも死体が吐き出され続ける。
『数十体やそこらなんかじゃきかないぞ』
パニックになりかかった頭でどこか冷静な部分が、ざっくりとでも死体の数を把握しようと務めていた。あまりにも信じがたい状況で、かえってどこかが醒めてしまったのかもしれない。
ジョナサンはふと、昔映像学習で見た、魚が陸揚げされたときの映像を思い出した。種類はわからなかったが、冷凍されたおおきな魚が、床を滑るようにしてどんどん集められている映像。まだ海洋資源が豊富に獲れていた500年ほど前の話だ。もしかしたら元漁港だったこの「フリートウッド」でも、むかしは見られたかもしれない光景だ。
今、自分にふりかかったこの事態は、それに似ている。ただ違いは、滑ってくるのが魚ではなく人間だということだ。
死体の転がってくる勢いがやっとおさまったと思った時には、ジョナサンは散乱したおびただしい数の死体に囲まれていた。一番遠くまで滑っていった死体は、ほかの死体に押されたせいで、100メートルほど奥にまでに達している。
「くそぅ、マジかよ」
ジョナサンは腹立ちまぎれに言ったが、すぐにディオがどうなったか気になって、すぐに右目の網膜の下部に表示されている自分とディオのヴァイタル・データを注視した。
その数字はディオがまだ生きていることを示していた。あわててあたりを見回す。
どこにもいない——?。
一瞬そう思ったが、床を埋め尽くす死体の隙間から、ディオが半身をおこすのが見えた。よくみると彼は壁面近くにある、ポールのようなものにつかまって、死体の雪崩を耐え忍んでいたようだった。地面に這いつくばっていたため、顔や頭に傷を負っており、痛々しかった。
「ディオ、大丈夫か?」
ジョナサンは声をかけたが、ディオはそれには答えようとしなかった。彼は貯蔵庫の開いたままの入り口のなかを覗き込んでいた。いや、なにかに見入られていたというべきかもしれない。
これ以上、なにがあるというのか……。
ジョナサンも気になって、入り口のほうへ目を向けた。
と、わずかになかの光が見えた。そしてその光のなかで、誰かが、いやすくなくとも何かが、動いているのが見えた。ジョナサンからはよく見えない角度だったので、それがなにかはまったく見当もつかない。
だが、正面でそれをまともに見たディオは、目をおおきく見開いていた。よく見ると手や足が震えている。あわててディオの元へ駆け寄る。
「おい、ディオ、どうした?」
ジョナサンはすこしでも落ち着くように、とびっきり優しい口調でそう言った。だが、ディオの返事は長くたなびく悲鳴だった。ディオは自分の顔を自分で掻きむしりながら、悲鳴をあげはじめた。ジョナサンはディオの横で片膝をたてると、ディオの背中にゆっくりと手をまわした。落ち着かせようと背中をさすりかけた手がとまる。
ジョナサンの網膜に表示されたディオのヴァイタル・データに異常な数字が示されていた。いや異常というレベルではない。ディオの脳波は尋常ならざる波形を刻んでいる。
ジョナサンはディオの顔を見た。
ディオは狂っていた——。
あきらかに目の焦点があっていない。顔は恐怖のあまり病的なまでに歪み、まともではない表情となっていた。そして、口元にはぞっとする薄ら笑いを浮かべていた。
ジョナサンは反射的にディオがなにかを見た貯蔵庫のなかに目をむけた。
ほんの一瞬だけだったが、奥のほうでなにものかが動いているのが見えたような気がした。そこに空間の切れ目のような光が漏れでていて、その何者かがそのなかへ戻ろうとしている——。そう見えた。が、すぐにそれは消え去り、ただの貯蔵庫の壁だけになった。
ジョナサンはディオの顔に目を向けた。
すでに悲鳴はやんでいたが、代わりにディオは笑い出していた。顔にはすぐ軽口を叩きたがる陽気なディオの面影はすでになかった。笑い声がしだいに大きくなる。それは得体のしれない邪教で使われる楽器を、けたたましく打ち鳴らしているような禍々しい笑い声だった。およそ人間の声帯から発せられるとは思えない。
ジョナサンは恐怖のあまり、その場に崩れ落ちた。
なにを見たのだ——。
なにを見たら、一瞬にして気が狂ってしまうのだ?——。
なにを……。
0
お気に入りに追加
26
あなたにおすすめの小説

❤️レムールアーナ人の遺産❤️
apusuking
SF
アランは、神代記の伝説〈宇宙が誕生してから40億年後に始めての知性体が誕生し、更に20億年の時を経てから知性体は宇宙に進出を始める。
神々の申し子で有るレムルアーナ人は、数億年を掛けて宇宙の至る所にレムルアーナ人の文明を築き上げて宇宙は人々で溢れ平和で共存共栄で発展を続ける。
時を経てレムルアーナ文明は予知せぬ謎の種族の襲来を受け、宇宙を二分する戦いとなる。戦争終焉頃にはレムルアーナ人は誕生星系を除いて衰退し滅亡するが、レムルアーナ人は後世の為に科学的資産と数々の奇跡的な遺産を残した。
レムールアーナ人に代わり3大種族が台頭して、やがてレムルアーナ人は伝説となり宇宙に蔓延する。
宇宙の彼方の隠蔽された星系に、レムルアーナ文明の輝かしい遺産が眠る。其の遺産を手にした者は宇宙を征するで有ろ。但し、辿り付くには3つの鍵と7つの試練を乗り越えねばならない。
3つの鍵は心の中に眠り、開けるには心の目を開いて真実を見よ。心の鍵は3つ有り、3つの鍵を開けて真実の鍵が開く〉を知り、其の神代記時代のレムールアーナ人が残した遺産を残した場所が暗示されていると悟るが、闇の勢力の陰謀に巻き込まれゴーストリアンが破壊さ
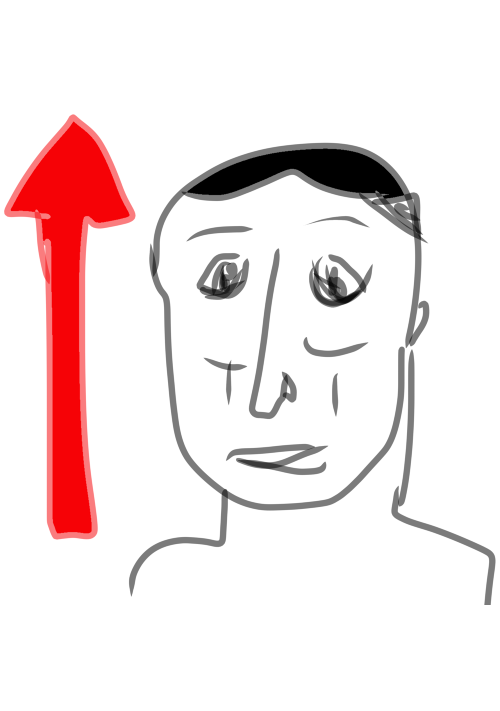
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。

決戦の夜が明ける ~第3堡塁の側壁~
独立国家の作り方
SF
ドグミス国連軍陣地に立て籠もり、全滅の危機にある島民と共に戦おうと、再上陸を果たした陸上自衛隊警備中隊は、条約軍との激戦を戦い抜き、遂には玉砕してしまいます。
今より少し先の未来、第3次世界大戦が終戦しても、世界は統一政府を樹立出来ていません。
南太平洋の小国をめぐり、新世界秩序は、新国連軍とS条約同盟軍との拮抗状態により、4度目の世界大戦を待逃れています。
そんな最中、ドグミス島で警備中隊を率いて戦った、旧陸上自衛隊1等陸尉 三枝啓一の弟、三枝龍二は、兄の志を継ぐべく「国防大学校」と名称が変更されたばかりの旧防衛大学校へと進みます。
しかし、その弟で三枝家三男、陸軍工科学校1学年の三枝昭三は、駆け落ち騒動の中で、共に協力してくれた同期生たちと、駐屯地の一部を占拠し、反乱を起こして徹底抗戦を宣言してしまいます。
龍二達防大学生たちは、そんな状況を打破すべく、駆け落ちの相手の父親、東京第1師団長 上条中将との交渉に挑みますが、関係者全員の軍籍剥奪を賭けた、訓練による決戦を申し出られるのです。
力を持たない学生や生徒達が、大人に対し、一歩に引くことなく戦いを挑んで行きますが、彼らの選択は、正しかったと世論が認めるでしょうか?
是非、ご一読ください。

シーフードミックス
黒はんぺん
SF
ある日あたしはロブスターそっくりの宇宙人と出会いました。出会ったその日にハンバーガーショップで話し込んでしまいました。
以前からあたしに憑依する何者かがいたけれど、それは宇宙人さんとは無関係らしい。でも、その何者かさんはあたしに警告するために、とうとうあたしの内宇宙に乗り込んできたの。
ちょっとびっくりだけど、あたしの内宇宙には天の川銀河やアンドロメダ銀河があります。よかったら見物してってね。
内なる宇宙にもあたしの住むご町内にも、未知の生命体があふれてる。遭遇の日々ですね。

MMS ~メタル・モンキー・サーガ~
千両文士
SF
エネルギー問題、環境問題、経済格差、疫病、収まらぬ紛争に戦争、少子高齢化・・・人類が直面するありとあらゆる問題を科学の力で解決すべく世界政府が協力して始まった『プロジェクト・エデン』
洋上に建造された大型研究施設人工島『エデン』に招致された若き大天才学者ミクラ・フトウは自身のサポートメカとしてその人格と知能を完全電子化複製した人工知能『ミクラ・ブレイン』を建造。
その迅速で的確な技術開発力と問題解決能力で矢継ぎ早に改善されていく世界で人類はバラ色の未来が確約されていた・・・はずだった。
突如人類に牙を剥き、暴走したミクラ・ブレインによる『人類救済計画』。
その指揮下で人類を滅ぼさんとする軍事戦闘用アンドロイドと直属配下の上位管理者アンドロイド6体を倒すべく人工島エデンに乗り込むのは・・・宿命に導かれた天才学者ミクラ・フトウの愛娘にしてレジスタンス軍特殊エージェント科学者、サン・フトウ博士とその相棒の戦闘用人型アンドロイドのモンキーマンであった!!
機械と人間のSF西遊記、ここに開幕!!

学園都市型超弩級宇宙戦闘艦『つくば』
佐野信人
SF
学園都市型超弩級宇宙戦闘艦『つくば』の艦長である仮面の男タイラーは、とある病室で『その少年』の目覚めを待っていた。4000年の時を超え少年が目覚めたとき、宇宙歴の物語が幕を開ける。
少年を出迎えるタイラーとの出会いが、遥かな時を超えて彼を追いかけて来た幼馴染の少女ミツキとの再会が、この時代の根底を覆していく。
常識を常識で覆す遥かな未来の「彼ら」の物語。避けようのない「戦い」と向き合った時、彼らは彼らの「日常」でそれを乗り越えていく。
彼らの敵は目に見える確かな敵などではなく、その瞬間を生き抜くという事実なのだった。
――――ただひたすらに生き残れ!
※小説家になろう様、待ラノ様、ツギクル様、カクヨム様、ノベルアップ+様、エブリスタ様、セルバンテス様、ツギクル様、LINEノベル様にて同時公開中

【完結】最弱テイマーの最強テイム~スライム1匹でどうしろと!?~
成実ミナルるみな
SF
四鹿(よつしか)跡永賀(あとえか)には、古家(ふるや)実夏(みか)という初恋の人がいた。出会いは幼稚園時代である。家が近所なのもあり、会ってから仲良くなるのにそう時間はかからなかった。実夏の家庭環境は劣悪を極めており、それでも彼女は文句の一つもなく理不尽な両親を尊敬していたが、ある日、実夏の両親は娘には何も言わずに蒸発してしまう。取り残され、茫然自失となっている実夏をどうにかしようと、跡永賀は自分の家へ連れて行くのだった。
それからというもの、跡永賀は実夏と共同生活を送ることになり、彼女は大切な家族の一員となった。
時は流れ、跡永賀と実夏は高校生になっていた。高校生活が始まってすぐの頃、跡永賀には赤山(あかやま)あかりという彼女ができる。
あかりを実夏に紹介した跡永賀は愕然とした。実夏の対応は冷淡で、あろうことかあかりに『跡永賀と別れて』とまで言う始末。祝福はしないまでも、受け入れてくれるとばかり考えていた跡永賀は驚くしか術がなかった。
後に理由を尋ねると、実夏は幼稚園児の頃にした結婚の約束がまだ有効だと思っていたという。当時の彼女の夢である〝すてきなおよめさん〟。それが同級生に両親に捨てられたことを理由に無理だといわれ、それに泣いた彼女を慰めるべく、何の非もない彼女を救うべく、跡永賀は自分が実夏を〝すてきなおよめさん〟にすると約束したのだ。しかし家族になったのを機に、初恋の情は家族愛に染まり、取って代わった。そしていつからか、家族となった少女に恋慕することさえよからぬことと考えていた。
跡永賀がそういった事情を話しても、実夏は諦めなかった。また、あかりも実夏からなんと言われようと、跡永賀と別れようとはしなかった。
そんなとき、跡永賀のもとにあるゲームの情報が入ってきて……!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















