240 / 1,035
第二章 第二節 電幽霊(サイバー・ゴースト)戦
第239話 ヤマトは『ドラゴンズ・ボール』を見つめた
しおりを挟む
ヤマトは階段を駆け上がりながら、貴重な時間をずいぶんうしなったことに苛立っていた。理想通りいったなら今ごろ『ドラゴンズ・ボール』を奪取して、この危険な階層からの移動をしていたはずだ。もしかしたら、国連軍の武装戦を沈めるなどという無謀な作戦は中止させて、レイもユウキもひきあげさせているかもしれない。
さきほど、内側から半魚人に襲いかかられた入り口がある階まであがってくると、クララがすぐそばの空中に逆さまに浮いたまま待機していた。
「タケルさん大丈夫ですの?」
「ああ、クララ、心配かけた。アスカの光の矢に助けられた」
「ええ。わたしも身を持って知ってますわ」
「なにがあった?」
クララはなにも言わずに下のほうを指さした。ヤマトはその指さす方向、自分の頭上をみあげた。
そこにおおきな穴がぽっかり空いていた。
その入り口は、ひとがひとり通れる程度だったが、その上の穴は数人まとめて通れるほどだった。
「アスカさんが言うには、狙いが狂った……だそうですわ」
クララはさりげなく言ったが、自分がここまで駆けあがっている最中に、二人の間でなにかがあったのだと、なんとなく悟った。
「ずいぶん、またすごく狙いが狂ったもんだな。きみは大丈夫だったのか?」
「えぇ。まぁ……。それよりタケルさん。はやく中へ」
クララがすこしばつが悪そうな顔で先を急がしてきたので、ヤマトはそのおおきな穴の縁に手をかけて、塔の中に足を踏み入れた。
塔の内部は直径十メートルほどの空間で、その内周には外階段とおなじような形で、螺旋階段が設えられていた。ただ外階段にあったような鎖の防護柵や手摺りはない。
足を踏み外せば、間違いなく真っ逆さまにおちてしまう。階段の横幅は一メートル程度はあったが、万が一ここで戦いを強いられたら、その幅では体をかわすことすら困難だ。
ヤマトは下を見おろした。
百メートルほど下に煌々と光を放つ物体があった。
目がくらむ光のせいではっきり見えなかったが、それが『ドラゴンズ・ボール』であることに間違いなかった。ボールは塔の内径の真ん中に浮いていた。
モンスターどもがいない——。
ヤマトは階段を降りようとして、すぐにその違和感に気づいた。目で見えないだけではない。気配そのものが感じられなかった。さきほど突然、この塔のなかから襲いかかられたことを考えると、一抹の痕跡もなく消えうせていること自体が不自然すぎる。
ヤマトは入り口から顔をだして、そとにいるクララに声をかけた。
「クララ。モンスターが一匹もいない」
「一匹も?」
「あぁ、不自然すぎる。きみの霊覚でそこから探れるか?」
「それなら、あの大きな穴からなかを覗いてみます」
クララはそう言うなり、アスカが空けた大穴にむかった。ヤマトはそれを目で追いながら自分のすこし上の穴を見あげた。すぐにクララは穴から顔を覗かせたが、ほぼそれと同時に大きな声で叫んできた。
「タケルさん。ほんとうになにもいませんわ!」
「きみの霊感でも、なにも感じられないんだね」
「えぇ。すくなくとも、今、この穴の近辺には電幽霊の霊気のようなものはありません。もしかしたらアスカさんが全部退治されたのではないですか?」
このエリアの電幽霊を完全に駆逐——?。
ヤマトは楽感的な考え方は好きではなかったが、今ここで逡巡している時間はなかった。
これは楽観的ではなく、前向きの考え方だ——。
ヤマトは踊り場から一歩踏み出し、慎重に階段を降りはじめた。不測の襲撃だけは避けたかったので、手のひらは内壁に吸い付かせるようにして、指でレンガをまさぐりながら歩を進めた。
階段を降りていくに従って、光の輝きが強くなってきた。それと同時に光る物体の全体像もしだいにはっきりと見えてくる。ヤマトがその光る物体が『ドラゴンズ・ボール』と認識できる距離まで近づく。
手を伸ばせば、手に掴めそうなところまで来て、実はどんなに頑張っても手が届かないことに気づいた。直径十メートルほどの内径の中心に浮いているのだから、どこから手を伸ばしても五メートルは離れているということだ。
ヤマトは『ドラゴンズ・ボール』を見つめた。二百年ほど前まであった『ベースボール』という球技で使われていたボールほどの大きさ。その表面に六個の星マークが記されている。デジタルデータに変換されて、元の容器とは異なるが、これが『ドラゴンズボール』であることに間違いはなかった。手に収まるようなサイズ感にアイコン化されているが、実際は数エクサバイト(テラバイトの100万倍)分のデータの塊だ。
どうやってこれを手にする——。
ジャンプして掴もうとしても、この狭い階段から助走なしで、ボールに飛びつくのはリスクが高かった。誤って一番下まで落下してしまっては、損傷によるマナの減数も深刻だろうし、ふたたび大きく時間のロスをもたらせてしまう。
陸エリアとちがって、この海エリアでは現実の人間の身の丈レベルの力しかもてないのだから、そうなる可能性はきわめて高い。
現実と等身大ではないのは、剣さばきや格闘の腕前が達人しベルなことと、マナがなくならなければ、死なないということくらいだ。
ふいにヤマトはアスカが開けた大穴を思いだした。ヤマトはテレパシーを使った。
「クララ、今、どこにいる?」
「タケルさん。先ほどの大穴のそばで待機していますわ」
「クララ、君に無理させたくないんだが、その穴からこの塔の中を下降するのはできないだろうか。もちろん塔のどんな場所に絶対ふれないという条件で」
「タケルさん。塔の内部の情報を教えてください?」
「塔の内部の直経は十メートル。内周に螺旋階段があるが、それ以外に塔の中には何もない。その塔の中心部にドラゴンボールが浮いている。手をのばしても届かない。飛びついてもとれるかどうかわからない」
クララはすぐに返事を返してこなかった。
突然、クララが沈思黙考したことで、ヤマトは自分がクララに無茶な要求をしてしまったのではないかと感じた。時間を費やしてしまった思いに、性急が過ぎてしまったのか。
「今、いきます」
ヤマトは顔を上にむけた。すぐ間近にある『ドラゴンズ・ボール』が放つ光が邪魔して、見づらかったが、はるか頭上からなにかが降りてきているのが見えた。
「タケルさん、下で光ってるその光ですね」
「あぁ、ぼくはそのすぐ近くにいる」
セイはそう言いながら、周りの様子に変化がないか気を配った。クララを危険な場所に飛び込ませたのだ、細心の注意をはらわねばならない。
しばらくしてクララの姿が見えてきはじめた。
ダイバーが垂直降下で潜ってきているような姿勢で、脇目もふらずに自分のほうだけを見つめて降りてきている。こちらの顔がみえて安堵したように見える。
「タケルさん」
「クララ、悪いね。危険だが、これが一番てっとり早いという判断をした」
クララの顔がヤマトの顔のすぐ間近でとまった。クララの顔がヤマトとは逆向きのまま見つめあう。クララの表情がすこし戸惑ったものに変わった。
「あのぅ……、このあとどうすれば……」
ヤマトはクララの目の前に手をさしだした。突然、顔の真ん前に差し出された手に、クララはすこし面食らった様子でじっとヤマトの手を見つめた。
「ぼくをひきあげて、あの『ドラゴンズ・ボール』のところまで連れていってくれ」
さきほど、内側から半魚人に襲いかかられた入り口がある階まであがってくると、クララがすぐそばの空中に逆さまに浮いたまま待機していた。
「タケルさん大丈夫ですの?」
「ああ、クララ、心配かけた。アスカの光の矢に助けられた」
「ええ。わたしも身を持って知ってますわ」
「なにがあった?」
クララはなにも言わずに下のほうを指さした。ヤマトはその指さす方向、自分の頭上をみあげた。
そこにおおきな穴がぽっかり空いていた。
その入り口は、ひとがひとり通れる程度だったが、その上の穴は数人まとめて通れるほどだった。
「アスカさんが言うには、狙いが狂った……だそうですわ」
クララはさりげなく言ったが、自分がここまで駆けあがっている最中に、二人の間でなにかがあったのだと、なんとなく悟った。
「ずいぶん、またすごく狙いが狂ったもんだな。きみは大丈夫だったのか?」
「えぇ。まぁ……。それよりタケルさん。はやく中へ」
クララがすこしばつが悪そうな顔で先を急がしてきたので、ヤマトはそのおおきな穴の縁に手をかけて、塔の中に足を踏み入れた。
塔の内部は直径十メートルほどの空間で、その内周には外階段とおなじような形で、螺旋階段が設えられていた。ただ外階段にあったような鎖の防護柵や手摺りはない。
足を踏み外せば、間違いなく真っ逆さまにおちてしまう。階段の横幅は一メートル程度はあったが、万が一ここで戦いを強いられたら、その幅では体をかわすことすら困難だ。
ヤマトは下を見おろした。
百メートルほど下に煌々と光を放つ物体があった。
目がくらむ光のせいではっきり見えなかったが、それが『ドラゴンズ・ボール』であることに間違いなかった。ボールは塔の内径の真ん中に浮いていた。
モンスターどもがいない——。
ヤマトは階段を降りようとして、すぐにその違和感に気づいた。目で見えないだけではない。気配そのものが感じられなかった。さきほど突然、この塔のなかから襲いかかられたことを考えると、一抹の痕跡もなく消えうせていること自体が不自然すぎる。
ヤマトは入り口から顔をだして、そとにいるクララに声をかけた。
「クララ。モンスターが一匹もいない」
「一匹も?」
「あぁ、不自然すぎる。きみの霊覚でそこから探れるか?」
「それなら、あの大きな穴からなかを覗いてみます」
クララはそう言うなり、アスカが空けた大穴にむかった。ヤマトはそれを目で追いながら自分のすこし上の穴を見あげた。すぐにクララは穴から顔を覗かせたが、ほぼそれと同時に大きな声で叫んできた。
「タケルさん。ほんとうになにもいませんわ!」
「きみの霊感でも、なにも感じられないんだね」
「えぇ。すくなくとも、今、この穴の近辺には電幽霊の霊気のようなものはありません。もしかしたらアスカさんが全部退治されたのではないですか?」
このエリアの電幽霊を完全に駆逐——?。
ヤマトは楽感的な考え方は好きではなかったが、今ここで逡巡している時間はなかった。
これは楽観的ではなく、前向きの考え方だ——。
ヤマトは踊り場から一歩踏み出し、慎重に階段を降りはじめた。不測の襲撃だけは避けたかったので、手のひらは内壁に吸い付かせるようにして、指でレンガをまさぐりながら歩を進めた。
階段を降りていくに従って、光の輝きが強くなってきた。それと同時に光る物体の全体像もしだいにはっきりと見えてくる。ヤマトがその光る物体が『ドラゴンズ・ボール』と認識できる距離まで近づく。
手を伸ばせば、手に掴めそうなところまで来て、実はどんなに頑張っても手が届かないことに気づいた。直径十メートルほどの内径の中心に浮いているのだから、どこから手を伸ばしても五メートルは離れているということだ。
ヤマトは『ドラゴンズ・ボール』を見つめた。二百年ほど前まであった『ベースボール』という球技で使われていたボールほどの大きさ。その表面に六個の星マークが記されている。デジタルデータに変換されて、元の容器とは異なるが、これが『ドラゴンズボール』であることに間違いはなかった。手に収まるようなサイズ感にアイコン化されているが、実際は数エクサバイト(テラバイトの100万倍)分のデータの塊だ。
どうやってこれを手にする——。
ジャンプして掴もうとしても、この狭い階段から助走なしで、ボールに飛びつくのはリスクが高かった。誤って一番下まで落下してしまっては、損傷によるマナの減数も深刻だろうし、ふたたび大きく時間のロスをもたらせてしまう。
陸エリアとちがって、この海エリアでは現実の人間の身の丈レベルの力しかもてないのだから、そうなる可能性はきわめて高い。
現実と等身大ではないのは、剣さばきや格闘の腕前が達人しベルなことと、マナがなくならなければ、死なないということくらいだ。
ふいにヤマトはアスカが開けた大穴を思いだした。ヤマトはテレパシーを使った。
「クララ、今、どこにいる?」
「タケルさん。先ほどの大穴のそばで待機していますわ」
「クララ、君に無理させたくないんだが、その穴からこの塔の中を下降するのはできないだろうか。もちろん塔のどんな場所に絶対ふれないという条件で」
「タケルさん。塔の内部の情報を教えてください?」
「塔の内部の直経は十メートル。内周に螺旋階段があるが、それ以外に塔の中には何もない。その塔の中心部にドラゴンボールが浮いている。手をのばしても届かない。飛びついてもとれるかどうかわからない」
クララはすぐに返事を返してこなかった。
突然、クララが沈思黙考したことで、ヤマトは自分がクララに無茶な要求をしてしまったのではないかと感じた。時間を費やしてしまった思いに、性急が過ぎてしまったのか。
「今、いきます」
ヤマトは顔を上にむけた。すぐ間近にある『ドラゴンズ・ボール』が放つ光が邪魔して、見づらかったが、はるか頭上からなにかが降りてきているのが見えた。
「タケルさん、下で光ってるその光ですね」
「あぁ、ぼくはそのすぐ近くにいる」
セイはそう言いながら、周りの様子に変化がないか気を配った。クララを危険な場所に飛び込ませたのだ、細心の注意をはらわねばならない。
しばらくしてクララの姿が見えてきはじめた。
ダイバーが垂直降下で潜ってきているような姿勢で、脇目もふらずに自分のほうだけを見つめて降りてきている。こちらの顔がみえて安堵したように見える。
「タケルさん」
「クララ、悪いね。危険だが、これが一番てっとり早いという判断をした」
クララの顔がヤマトの顔のすぐ間近でとまった。クララの顔がヤマトとは逆向きのまま見つめあう。クララの表情がすこし戸惑ったものに変わった。
「あのぅ……、このあとどうすれば……」
ヤマトはクララの目の前に手をさしだした。突然、顔の真ん前に差し出された手に、クララはすこし面食らった様子でじっとヤマトの手を見つめた。
「ぼくをひきあげて、あの『ドラゴンズ・ボール』のところまで連れていってくれ」
0
お気に入りに追加
26
あなたにおすすめの小説

❤️レムールアーナ人の遺産❤️
apusuking
SF
アランは、神代記の伝説〈宇宙が誕生してから40億年後に始めての知性体が誕生し、更に20億年の時を経てから知性体は宇宙に進出を始める。
神々の申し子で有るレムルアーナ人は、数億年を掛けて宇宙の至る所にレムルアーナ人の文明を築き上げて宇宙は人々で溢れ平和で共存共栄で発展を続ける。
時を経てレムルアーナ文明は予知せぬ謎の種族の襲来を受け、宇宙を二分する戦いとなる。戦争終焉頃にはレムルアーナ人は誕生星系を除いて衰退し滅亡するが、レムルアーナ人は後世の為に科学的資産と数々の奇跡的な遺産を残した。
レムールアーナ人に代わり3大種族が台頭して、やがてレムルアーナ人は伝説となり宇宙に蔓延する。
宇宙の彼方の隠蔽された星系に、レムルアーナ文明の輝かしい遺産が眠る。其の遺産を手にした者は宇宙を征するで有ろ。但し、辿り付くには3つの鍵と7つの試練を乗り越えねばならない。
3つの鍵は心の中に眠り、開けるには心の目を開いて真実を見よ。心の鍵は3つ有り、3つの鍵を開けて真実の鍵が開く〉を知り、其の神代記時代のレムールアーナ人が残した遺産を残した場所が暗示されていると悟るが、闇の勢力の陰謀に巻き込まれゴーストリアンが破壊さ
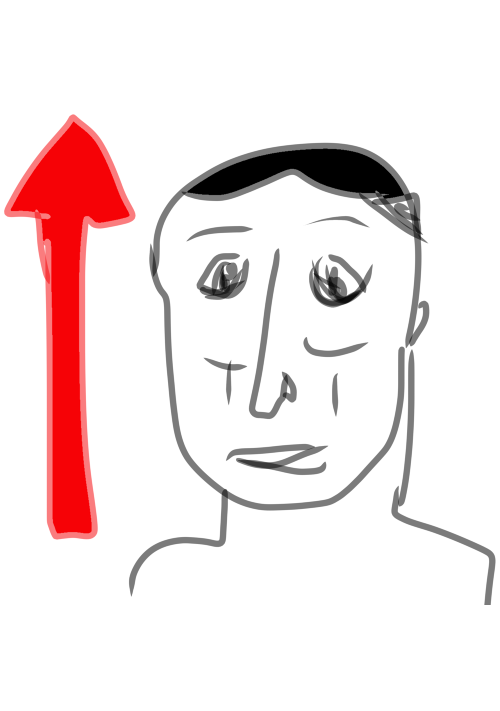
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。

決戦の夜が明ける ~第3堡塁の側壁~
独立国家の作り方
SF
ドグミス国連軍陣地に立て籠もり、全滅の危機にある島民と共に戦おうと、再上陸を果たした陸上自衛隊警備中隊は、条約軍との激戦を戦い抜き、遂には玉砕してしまいます。
今より少し先の未来、第3次世界大戦が終戦しても、世界は統一政府を樹立出来ていません。
南太平洋の小国をめぐり、新世界秩序は、新国連軍とS条約同盟軍との拮抗状態により、4度目の世界大戦を待逃れています。
そんな最中、ドグミス島で警備中隊を率いて戦った、旧陸上自衛隊1等陸尉 三枝啓一の弟、三枝龍二は、兄の志を継ぐべく「国防大学校」と名称が変更されたばかりの旧防衛大学校へと進みます。
しかし、その弟で三枝家三男、陸軍工科学校1学年の三枝昭三は、駆け落ち騒動の中で、共に協力してくれた同期生たちと、駐屯地の一部を占拠し、反乱を起こして徹底抗戦を宣言してしまいます。
龍二達防大学生たちは、そんな状況を打破すべく、駆け落ちの相手の父親、東京第1師団長 上条中将との交渉に挑みますが、関係者全員の軍籍剥奪を賭けた、訓練による決戦を申し出られるのです。
力を持たない学生や生徒達が、大人に対し、一歩に引くことなく戦いを挑んで行きますが、彼らの選択は、正しかったと世論が認めるでしょうか?
是非、ご一読ください。

シーフードミックス
黒はんぺん
SF
ある日あたしはロブスターそっくりの宇宙人と出会いました。出会ったその日にハンバーガーショップで話し込んでしまいました。
以前からあたしに憑依する何者かがいたけれど、それは宇宙人さんとは無関係らしい。でも、その何者かさんはあたしに警告するために、とうとうあたしの内宇宙に乗り込んできたの。
ちょっとびっくりだけど、あたしの内宇宙には天の川銀河やアンドロメダ銀河があります。よかったら見物してってね。
内なる宇宙にもあたしの住むご町内にも、未知の生命体があふれてる。遭遇の日々ですね。

MMS ~メタル・モンキー・サーガ~
千両文士
SF
エネルギー問題、環境問題、経済格差、疫病、収まらぬ紛争に戦争、少子高齢化・・・人類が直面するありとあらゆる問題を科学の力で解決すべく世界政府が協力して始まった『プロジェクト・エデン』
洋上に建造された大型研究施設人工島『エデン』に招致された若き大天才学者ミクラ・フトウは自身のサポートメカとしてその人格と知能を完全電子化複製した人工知能『ミクラ・ブレイン』を建造。
その迅速で的確な技術開発力と問題解決能力で矢継ぎ早に改善されていく世界で人類はバラ色の未来が確約されていた・・・はずだった。
突如人類に牙を剥き、暴走したミクラ・ブレインによる『人類救済計画』。
その指揮下で人類を滅ぼさんとする軍事戦闘用アンドロイドと直属配下の上位管理者アンドロイド6体を倒すべく人工島エデンに乗り込むのは・・・宿命に導かれた天才学者ミクラ・フトウの愛娘にしてレジスタンス軍特殊エージェント科学者、サン・フトウ博士とその相棒の戦闘用人型アンドロイドのモンキーマンであった!!
機械と人間のSF西遊記、ここに開幕!!


【完結】最弱テイマーの最強テイム~スライム1匹でどうしろと!?~
成実ミナルるみな
SF
四鹿(よつしか)跡永賀(あとえか)には、古家(ふるや)実夏(みか)という初恋の人がいた。出会いは幼稚園時代である。家が近所なのもあり、会ってから仲良くなるのにそう時間はかからなかった。実夏の家庭環境は劣悪を極めており、それでも彼女は文句の一つもなく理不尽な両親を尊敬していたが、ある日、実夏の両親は娘には何も言わずに蒸発してしまう。取り残され、茫然自失となっている実夏をどうにかしようと、跡永賀は自分の家へ連れて行くのだった。
それからというもの、跡永賀は実夏と共同生活を送ることになり、彼女は大切な家族の一員となった。
時は流れ、跡永賀と実夏は高校生になっていた。高校生活が始まってすぐの頃、跡永賀には赤山(あかやま)あかりという彼女ができる。
あかりを実夏に紹介した跡永賀は愕然とした。実夏の対応は冷淡で、あろうことかあかりに『跡永賀と別れて』とまで言う始末。祝福はしないまでも、受け入れてくれるとばかり考えていた跡永賀は驚くしか術がなかった。
後に理由を尋ねると、実夏は幼稚園児の頃にした結婚の約束がまだ有効だと思っていたという。当時の彼女の夢である〝すてきなおよめさん〟。それが同級生に両親に捨てられたことを理由に無理だといわれ、それに泣いた彼女を慰めるべく、何の非もない彼女を救うべく、跡永賀は自分が実夏を〝すてきなおよめさん〟にすると約束したのだ。しかし家族になったのを機に、初恋の情は家族愛に染まり、取って代わった。そしていつからか、家族となった少女に恋慕することさえよからぬことと考えていた。
跡永賀がそういった事情を話しても、実夏は諦めなかった。また、あかりも実夏からなんと言われようと、跡永賀と別れようとはしなかった。
そんなとき、跡永賀のもとにあるゲームの情報が入ってきて……!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















