お気に入りに追加
26
あなたにおすすめの小説

❤️レムールアーナ人の遺産❤️
apusuking
SF
アランは、神代記の伝説〈宇宙が誕生してから40億年後に始めての知性体が誕生し、更に20億年の時を経てから知性体は宇宙に進出を始める。
神々の申し子で有るレムルアーナ人は、数億年を掛けて宇宙の至る所にレムルアーナ人の文明を築き上げて宇宙は人々で溢れ平和で共存共栄で発展を続ける。
時を経てレムルアーナ文明は予知せぬ謎の種族の襲来を受け、宇宙を二分する戦いとなる。戦争終焉頃にはレムルアーナ人は誕生星系を除いて衰退し滅亡するが、レムルアーナ人は後世の為に科学的資産と数々の奇跡的な遺産を残した。
レムールアーナ人に代わり3大種族が台頭して、やがてレムルアーナ人は伝説となり宇宙に蔓延する。
宇宙の彼方の隠蔽された星系に、レムルアーナ文明の輝かしい遺産が眠る。其の遺産を手にした者は宇宙を征するで有ろ。但し、辿り付くには3つの鍵と7つの試練を乗り越えねばならない。
3つの鍵は心の中に眠り、開けるには心の目を開いて真実を見よ。心の鍵は3つ有り、3つの鍵を開けて真実の鍵が開く〉を知り、其の神代記時代のレムールアーナ人が残した遺産を残した場所が暗示されていると悟るが、闇の勢力の陰謀に巻き込まれゴーストリアンが破壊さ

CREATED WORLD
猫手水晶
SF
惑星アケラは、大気汚染や森林伐採により、いずれ人類が住み続けることができなくなってしまう事がわかった。
惑星アケラに住む人類は絶滅を免れる為に、安全に生活を送れる場所を探す事が必要となった。
宇宙に人間が住める惑星を探そうという提案もあったが、惑星アケラの周りに人が住めるような環境の星はなく、見つける前に人類が絶滅してしまうだろうという理由で、現実性に欠けるものだった。
「人間が住めるような場所を自分で作ろう」という提案もあったが、資材や重力の方向の問題により、それも現実性に欠ける。
そこで科学者は「自分達で世界を構築するのなら、世界をそのまま宇宙に作るのではなく、自分達で『宇宙』にあたる空間を新たに作り出し、その空間で人間が生活できるようにすれば良いのではないか。」と。
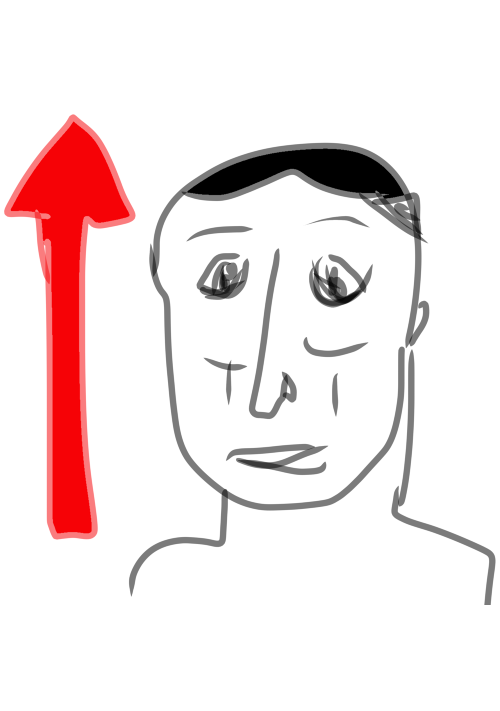
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

決戦の夜が明ける ~第3堡塁の側壁~
独立国家の作り方
SF
ドグミス国連軍陣地に立て籠もり、全滅の危機にある島民と共に戦おうと、再上陸を果たした陸上自衛隊警備中隊は、条約軍との激戦を戦い抜き、遂には玉砕してしまいます。
今より少し先の未来、第3次世界大戦が終戦しても、世界は統一政府を樹立出来ていません。
南太平洋の小国をめぐり、新世界秩序は、新国連軍とS条約同盟軍との拮抗状態により、4度目の世界大戦を待逃れています。
そんな最中、ドグミス島で警備中隊を率いて戦った、旧陸上自衛隊1等陸尉 三枝啓一の弟、三枝龍二は、兄の志を継ぐべく「国防大学校」と名称が変更されたばかりの旧防衛大学校へと進みます。
しかし、その弟で三枝家三男、陸軍工科学校1学年の三枝昭三は、駆け落ち騒動の中で、共に協力してくれた同期生たちと、駐屯地の一部を占拠し、反乱を起こして徹底抗戦を宣言してしまいます。
龍二達防大学生たちは、そんな状況を打破すべく、駆け落ちの相手の父親、東京第1師団長 上条中将との交渉に挑みますが、関係者全員の軍籍剥奪を賭けた、訓練による決戦を申し出られるのです。
力を持たない学生や生徒達が、大人に対し、一歩に引くことなく戦いを挑んで行きますが、彼らの選択は、正しかったと世論が認めるでしょうか?
是非、ご一読ください。

MMS ~メタル・モンキー・サーガ~
千両文士
SF
エネルギー問題、環境問題、経済格差、疫病、収まらぬ紛争に戦争、少子高齢化・・・人類が直面するありとあらゆる問題を科学の力で解決すべく世界政府が協力して始まった『プロジェクト・エデン』
洋上に建造された大型研究施設人工島『エデン』に招致された若き大天才学者ミクラ・フトウは自身のサポートメカとしてその人格と知能を完全電子化複製した人工知能『ミクラ・ブレイン』を建造。
その迅速で的確な技術開発力と問題解決能力で矢継ぎ早に改善されていく世界で人類はバラ色の未来が確約されていた・・・はずだった。
突如人類に牙を剥き、暴走したミクラ・ブレインによる『人類救済計画』。
その指揮下で人類を滅ぼさんとする軍事戦闘用アンドロイドと直属配下の上位管理者アンドロイド6体を倒すべく人工島エデンに乗り込むのは・・・宿命に導かれた天才学者ミクラ・フトウの愛娘にしてレジスタンス軍特殊エージェント科学者、サン・フトウ博士とその相棒の戦闘用人型アンドロイドのモンキーマンであった!!
機械と人間のSF西遊記、ここに開幕!!



幻想遊撃隊ブレイド・ダンサーズ
黒陽 光
SF
その日、1973年のある日。空から降りてきたのは神の祝福などではなく、終わりのない戦いをもたらす招かれざる来訪者だった。
現れた地球外の不明生命体、"幻魔"と名付けられた異形の怪異たちは地球上の六ヶ所へ巣を落着させ、幻基巣と呼ばれるそこから無尽蔵に湧き出て地球人類に対しての侵略行動を開始した。コミュニケーションを取ることすら叶わぬ異形を相手に、人類は嘗てない絶滅戦争へと否応なく突入していくこととなる。
そんな中、人類は全高8mの人型機動兵器、T.A.M.S(タムス)の開発に成功。遂に人類は幻魔と対等に渡り合えるようにはなったものの、しかし戦いは膠着状態に陥り。四十年あまりの長きに渡り続く戦いは、しかし未だにその終わりが見えないでいた。
――――これは、絶望に抗う少年少女たちの物語。多くの犠牲を払い、それでも生きて。いなくなってしまった愛しい者たちの遺した想いを道標とし、抗い続ける少年少女たちの物語だ。
表紙は頂き物です、ありがとうございます。
※カクヨムさんでも重複掲載始めました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















