お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説
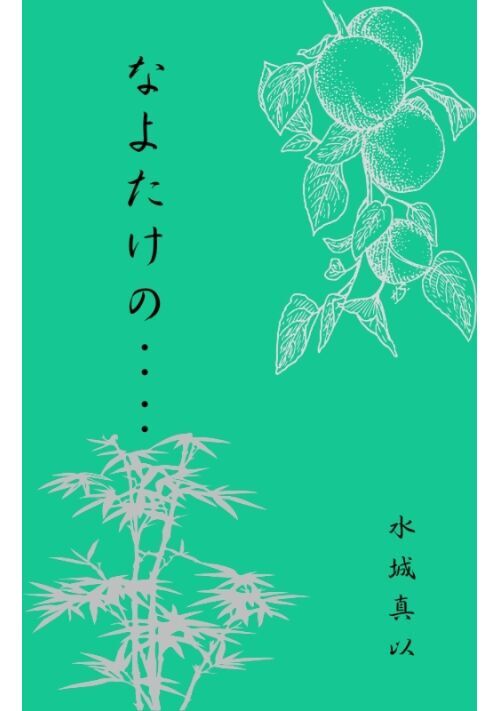

仇討ちの娘
サクラ近衛将監
歴史・時代
父の仇を追う姉弟と従者、しかしながらその行く手には暗雲が広がる。藩の闇が仇討ちを様々に妨害するが、仇討の成否や如何に?娘をヒロインとして思わぬ人物が手助けをしてくれることになる。
毎週木曜日22時の投稿を目指します。

風呂屋旗本・勘太郎
ご隠居
歴史・時代
風呂屋の新入り、勘太郎(かんたろう)、後の巨勢(こせ)六左衛門(ろくざえもん)が八代将軍吉宗の縁者という事で、江戸城に召し出され、旗本に取り立てられるまでの物語。
《主な登場人物》
勘太郎…本作の主人公
十左衛門…勘太郎の叔父、養父。
善之助…十左衛門の倅、勘太郎の従兄。病弱。
徳川吉宗…八代将軍。十左衛門(じゅうざえもん)の甥。
加納遠江守久通…御用懸御側衆。
有馬兵庫頭恒治…御用懸御側衆、後の氏倫。
本目権左衛門親良…奥右筆組頭。
河内山宗久…時斗之間肝煎坊主、恒治付。
一部、差別的な表現がありますが、この時代の風俗上、どうしてもやむを得ぬもので、ご諒承下さい。

日日晴朗 ―異性装娘お助け日記―
優木悠
歴史・時代
―男装の助け人、江戸を駈ける!―
栗栖小源太が女であることを隠し、兄の消息を追って江戸に出てきたのは慶安二年の暮れのこと。
それから三カ月、助っ人稼業で糊口をしのぎながら兄をさがす小源太であったが、やがて由井正雪一党の陰謀に巻き込まれてゆく。

漂泊
ムギ。
歴史・時代
妖怪、幽霊が当たり前のように身近で囁かれていた時代。
江戸は薬研堀に店を構える商人、嘉助は巷では有名な妖怪馬鹿。
ある日、お供の六弥太を連れて諸国漫遊の旅に出た。もちろん目当ては各地の妖怪。
二人を待ち受ける妖怪は如何に。
※数年前になろうで笹山菖蒲の名前で連載していたものを加筆修正したものです※


Battle of Black Gate 〜上野戦争、その激戦〜
四谷軒
歴史・時代
【あらすじ】
慶応四年。上野の山に立てこもる彰義隊に対し、新政府の司令官・大村益次郎は、ついに宣戦布告した。降りしきる雨の中、新政府軍は午前七時より攻撃開始。そして――その最も激しい戦闘が予想される上野の山――寛永寺の正門、黒門口の攻撃を任されたのは、薩摩藩兵であり、率いるは西郷吉之助(西郷隆盛)、中村半次郎(桐野利秋)である。
後世、己の像が立つことになる山王台からの砲撃をかいくぐり、西郷は、そして半次郎は――薩摩はどう攻めるのか。
そして――戦いの中、黒門へ斬り込む半次郎は、幕末の狼の生き残りと対峙する。
【登場人物】
中村半次郎:薩摩藩兵の将校、のちの桐野利秋
西郷吉之助:薩摩藩兵の指揮官、のちの西郷隆盛
篠原国幹:薩摩藩兵の将校、半次郎の副将
川路利良:薩摩藩兵の将校、半次郎の副官、のちの大警視(警視総監)
海江田信義:東海道先鋒総督参謀
大村益次郎:軍務官監判事、江戸府判事
江藤新平:軍監、佐賀藩兵を率いる
原田左之助:壬生浪(新撰組)の十番組隊長、槍の名手

空蝉
横山美香
歴史・時代
薩摩藩島津家の分家の娘として生まれながら、将軍家御台所となった天璋院篤姫。孝明天皇の妹という高貴な生まれから、第十四代将軍・徳川家定の妻となった和宮親子内親王。
二人の女性と二組の夫婦の恋と人生の物語です。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















