43 / 134
9.伊勢の残滓
9-2. 従兄弟の意地
しおりを挟む
天正二年七月。忠三郎は信長の命により、柴田勝家の軍勢とともに再び伊勢へと攻め入った。
かつてないほどの大掛かりな戦さだ。一益によって各処にはすでに諸将が本陣を置くために寺や家が抑えられており、長期戦に備えて荷駄衆が兵糧を運び込む。
大川の向こうに見えるのは難攻の地・長島。
(いよいよ長島に攻め入る)
小木江で信長の弟・織田彦七郎が討たれてから四年。度々長島願証寺に煮え湯を飲まされ、信長の憎悪の念は募る一方だった。
大湊衆を従えた一益は、九鬼嘉隆とともに志摩・伊勢・尾張の海賊衆を率いて大湊から大船団を率いてくる。そしてあの大きな阿武船に兵を乗せ、長島に上陸させる手筈になっている。
長島を前にして陣を張ると、従兄弟の関四郎が意気揚々と現れた。
「鶴。此度はなんとしても手柄を立て、日野に幽閉されている父上をお救いしたい。力を貸してくれ」
四郎の末の弟は柴田勝家の元に留められたままだ。今や関家の居城・亀山城は信長の三男・神戸三七のものとなり、このままでは鎌倉時代から続く名門・関家がなくなってしまうと焦りを募らせる。
「そう焦るな。今、焦っても上様の御心が変わるとは思えぬ」
常の笑顔でそう言って四郎を落ち着かせようとしたが、予想に反し、四郎は目をむいて怒った。
「所詮、上様に気に入られ、娘婿となった鶴には、わしの思いなど、分からぬか」
信長の怒りは神戸家の養子にした神戸三七をないがしろにしたとの理由による。一益にも勝家にも相談したが、勝家は渋い顔をして今日・明日に信長の怒りを解くことは難しいと言い、一益は少し辛抱して待てと言う。
忠三郎自身も、同じようには思っていたが、父を幽閉され、弟を人質に取られ、居城まで奪われた四郎には伝わらない。
「城も奪われ、家臣たちは行く宛もなく困り果て、百姓をして生計をたてている者もおる。それならばまだよい。離散したまま時がたち、他家に仕官されては、父上の幽閉が解けたとしても我が家はもはや成り立たぬ。早く上様のお怒りを解き、城と父上を返してもらわねば…」
四郎の焦りが伝わってきた。
(四郎は四郎で、関家を守ろうと必死なのか)
忠三郎は自分とそう年の変わらない従兄弟の気持ちを察して心を決めた。
「では、叔父上のため、関家再興のために、ここで大手柄を立てよう」
笑顔でそういうと、四郎は忠三郎の手を取り、
「まことか!鶴!忝い」
深々と頭を下げる。
「まずは我等で長島一番乗りを果たしては如何であろう。さすれば、そのまま一番槍を狙うこともできる」
味方は総勢十二万。その中で、あの大川の真中にある長島に、誰よりも先に上陸し、名乗りをあげれば敵味方にその名は知れ渡る。
「一番乗り?では船を用意せねば…」
「いや、馬を連れて行かねば砦に近づくことも容易ではない。船で行けば騎乗して渡ることはかなうまい。この辺りには松之木の渡りなる道があり、引き潮のときには陸路で長島に渡れると聞き及んだ。まずは物見を出して松之木の渡りを探し出し、掛かり太鼓の合図とともに松之木の渡りを使って長島へ行き、松之木砦を攻略しよう」
信長は尾張方面から南下してくる。そして一益は船に乗ってくる。いつもであれば、先陣を務めたいと言うと、決まって止めに入る信長や一益はいない。唯一いるのは柴田勝家だけであり、今回こそ、手柄を立てる絶好の機会ともいえた。
実直な勝家が相手であれば、熱心に訴えれば許してくれる。そう思い、勝家本陣まで出向いて先陣を願い出ると、当初、渋ってはいたが、何度も頼み込み、なんとか説き伏せ、ようやく許してもらうことができた。
「四郎!明日は必ず、我等で長島一番乗りを果たそうぞ!」
忠三郎がいつにも増して力を入れて言うと、四郎も頷き、
「必ず、必ず手柄を立てて、家を再興する」
思いつめたように忠三郎を見て、そう言った。
いよいよ明朝、攻めかかると決まり、関四郎とともに支度を整えていると、町野左近が滝川助太郎を伴って現れる。
「若殿。滝川家より使者が参り、一揆勢に根来・雑賀の者たちが加わっているゆえ、軽挙妄動は控えるようにとのことでござりますが…」
忠三郎の顔色を伺いながらそう告げる。一益は何かを察したように釘をさしてきた。今回、先陣を仰せつかったと言っても嬉しそうではなかった町野左近は、一益からの忠告を聞いてますます不安になったらしい。
忠三郎はそんな町野左近を見て微笑を浮かべる。
「爺、敵を恐れていては手柄など立てることはできぬ。此度、新しく我が家に召し抱えた家臣たちをこの場へ集めよ」
「ハハッ」
何がはじまるのかと町野左近は首を傾げながら、声をかけて歩き、六角家の旧臣を含め、新しく家臣の列に加わった武将たちが集めた。
忠三郎はずらりと並んだ家臣たちの前に意気揚々と立ち、笑顔を見せる。
「皆、よう聞け。明朝、松之木の渡りを越え、長島へ入り、松之木砦へと向かう。我が家には銀の鯰尾の兜を被り、先陣を駆ける武者がおる。皆もその者に後れを取らぬように励め」
家臣たちが誰のことかと互いに顔を見合わせる。忠三郎はそんな家臣たちを尻目に、満面笑顔で帷幕の中へ戻っていった。
翌朝、忠三郎は関四郎と二人で誰よりも先に馬に乗り、掛かり太鼓が鳴り響くのを待った。
まもなく鳴り物が鳴り響く。
「四郎、参ろうぞ!」
忠三郎はいち早く馬を走らせ、松之木の渡りを目指した。その頭にあるのは無論、鯰尾の兜。関四郎がなんとか遅れまいと後に従い、更にその後ろを家臣たちが追いかけてくるのが分かる。
松之木の渡りにさしかかったあたりで、早くも銃声が聞こえてきた。
(砦から撃っているのだろうか)
砦にはまだ少し距離がある。矢も弾も届かない筈だ。忠三郎はわき目も降らず、長島目指して突き進み、ついに長島の地に足を踏み入れた。
「蒲生忠三郎、長島一番乗り!」
声高らかにそう叫ぶと、松之木砦目指して突き進んだ。近づいてみると、思ったよりもしっかりとした砦が組まれており、土塁の上には土壁まで見える。
「鶴!」
ようやく追いついた四郎が大声で呼ぶと、土壁の向こうに隠れ潜んでいた鉄砲隊がこちらに向かって一斉射撃を浴びせた。
目の前の木の枝に弾がかすめる。
(これは思うていたよりも狙いが確かじゃ)
さして警戒もしなかった戦闘慣れしていない一揆勢の鉄砲隊が、狙い定めて撃ってくるとは考えもしなかった。
「四郎、足軽共がくるのを待って、攻めかかろう」
このまま砦に向かっても狙い撃ちされてしまう。砦から少し離れて兵が追い付いてくるのを待つことにした。
(根来・雑賀の者たちが加わっていると、そう言っていた)
根来・雑賀衆とは、前回の長島攻めの退却時に後ろから襲ってきた一群のことだろう。忠三郎は話に聞くだけで、実際に目で見たことがない。
(もしや、銃の扱いに慣れたものがいると、義兄上はそう言っていたのか)
これは思ったよりも手ごわいかもしれない。
では、あの砦をどうやって落とすかと考えていると、家臣たちが集まってきて、足軽がそれに続いてきた。その後ろには、先陣を申し出たとはいえ、まさか忠三郎が一人で飛び出していくとは思いもよらなかった柴田勝家が大慌てで兵を率いてくるのが見える。
「鶴。このままここに留まっていては手柄を横取りされてしまう。急ぎ、砦へ向かわねば」
功を焦る四郎が馬首を返そうとする。
「待て、四郎。迂闊に近づくのは危ない。まずは兵を纏めて…」
と忠三郎が言い終わるのを待たずに、四郎が砦目指して馬を走らせていってしまう。
「四郎!」
関家の旧臣たちが慌てて後に従う。そこへ町野左近が現れ、
「若殿、お待ちくだされ。ここは我らが参りましょう」
忠三郎を押しとどめようとした。
「それには及ばぬ。あれなる林からであれば砦まで届く。木陰に弓隊を連れて行き、土壁に隠れる敵を狙って矢を放て」
忠三郎はそう言って四郎を追いかけた。
砦から放たれる弾丸が兜をかすめるのが分かる。
(かようなときは…)
まっすぐに走らず、ジグザグに馬を走らせて被弾を避ける。
銃を構えて狙い定め、実際に撃つまでは間があり、間合いを取ることで、敵が引き金を引く前から前提上の射線を避けることができる。この練習は義太夫の水鉄砲で何度もやらされた。
その時は実戦で役に立つとは思っていなかったが。
(思うたよりも、役立ってくれるではないか)
兵を引き連れ、砦へと近づくと、町野左近率いる弓兵が土壁の向こう側めがけて矢を放つのが見えた。
「よし、今じゃ!者ども、土塁を乗り越えよ!」
鬨の声が響き渡り、足軽が土塁に殺到すると、敵兵が門を目指して逃げるのが見えた。忠三郎も土塁を乗り越え、逃げ遅れた敵兵をなぎ倒す。
「忠三郎殿!ここは我らに任せてお引きくだされ」
勝家の軍勢が追い付いてきたようだ。振り返ると、さらにその後ろには佐久間信盛の軍勢も見える。
「されど、四郎が…」
鉄砲隊を突き崩すことに気を取られ、四郎を見失っている。
「若殿、我らが向かいまする」
町野左近が槍を携え、兵を率いて城門へと向かおうとするが、すでに万を超える兵が雪崩のように小さな砦に押し寄せ、城門付近は味方の兵で溢れている。
「四郎を探さねば…」
忠三郎は味方を押しのけながら城門へと向かった。
重傷を負った関四郎が陣営に運ばれてきたのは、松ノ木砦が落ちた後だった。四郎は兜首ふたつを取って、従者に持たせていた。
戸板に寝かされた四郎は、苦しそうにうめきながらも
「鶴…この首を上様に…」
信長に見せれば関家再興が叶うかもしれない。そう思って一縷の望みをかけ、敵中深くまで攻め入ったのだろう。
「確かに、受け取った。これより上様本陣へ向かい、おぬしの手柄を伝えてくる。それゆえ、気をしっかり持て」
家臣たちは懸命に手当しているが、複数個所に被弾していて、出血が止まらない。最初の突撃で、四郎だけではなく、何人もの家臣が怪我をし、少なからず命を落としたものいた。
いずれも皆、鉄砲傷によるもので、よくよく見ると銃弾が兜や鎧を貫通していた。
(ここまで狙い撃ちされていたとは)
何故、忠三郎だけ被弾しなかったのだろうか。鎧を脱ぎ、あちこち観察してみると、弾傷はあるが、貫通はしていない。
(もしや…)
思い当ることがあった。
岐阜の最終評定のあとのことだ。
『銃により、これまでの戦さのやり方は通用しなくなった。これは攻めるだけではなく、守りにおいても同様である』
一益はそう言った。
『守り、とは?土塁に鉄砲隊を配備させるということで?』
言わんとしていることがよくわからず、忠三郎がなんとなく思い描くことを口にすると、
『無論、それもあるが、それだけでは足りぬ。まずは城を守るには土塁だけでは足りぬ。堅固な石垣を四方に巡らせること。そして、甲冑』
『甲冑?』
銃と弓矢の違いは、その貫通力にある。これまでの当世具足は弓矢や槍での戦いを想定したもの。しかしそれでは銃弾を防ぐことができない、と一益は言った。
『では、如何様にすればよろしいので?』
忠三郎の問いに対し、一益は
『日野の鉄砲鍛冶に命じて、いくつか用意させておる。そのうちの一つを届けるようにと命じておいた。直に日野の城に届くであろう』
何が届くのかと思っていると、届けられたのは銃弾をも通さぬという鎧、そして忠三郎を現す象徴ともいえる銀の鯰尾の兜も鉄製のものが用意された。
『ポルトガル商人から手に入れた鎧を、さらに滝川様から改良するようにと申し付けられ、あつらえたもので。人呼んで、南蛮具足、南蛮兜』
鉄砲鍛冶はそう言った。
(南蛮具足?)
南蛮の鉄板のような鎧に、さらに腰から太ももまでを覆う草褶を取り付けた鎧だった。試しに着用してみると、鉄でできているだけあって相当に重く、馬に乗るのも家臣の手を借りなければならなかった。
(これで銃弾が防げるのか)
であれば、いざ攻めかかるときには便利かもしれない。そう考え、南蛮具足を身に着けても動けるようにと、何度も着ては馬を走らせたり、家臣と相撲をとったりして少しずつ慣れていった。
(当世具足では銃弾から身を守ることができなかったのか)
城から狙いの確かな弾が撃たれていることは気づいていた。それなのに何故、皆が被弾し、倒れていることに気づけなかったのか。
(あのときは…見えなかった)
激しい銃声を耳にしてから、筒の中を覗き込むようにまっすぐ前しか見えなくなり、目指す城門が実際よりも近くに感じられた。あれは一体なんだろうか。
考えても分からなかったが、四郎の手柄を広く、織田家の諸将に伝えなければならない。
忠三郎は四郎とともにいた従者を連れて寄親である柴田勝家の本陣へ行った。
勝家に事と次第を話すと、
「此度は蒲生勢の突撃により難なく砦を落とすことができた。上様にお伝えすれば、あるいは関殿の幽閉も解け、亀山城を返していただくことができるやもしれぬ。さ、早う上様本陣へ向かいなされ」
背中を押され、忠三郎は意気揚々と船に乗り、大川を越えて信長本陣へ向かった。
しかし予想に反して信長の反応は冷ややかなものだった。
「葉武者の如き振る舞いじゃ」
不機嫌そうにただ一言、そう言って忠三郎を下がらせた。
長島一番乗りを果たし、数多の犠牲を払って立てた手柄は見向きもされず、関家再興を願い出る隙もなかった。
(四郎に何と言えば…)
とぼとぼと自陣に戻ると、関家の旧臣たちが一人、二人、肩を落として荷物を纏めている姿が目に入る。
「みな、如何した?四郎の容態は?」
声をかけても反応がない。聞こえていないかのように陣営を後にする者、涙する者がいて、もしやと思い、町野左近を呼んだ。
少し待っていると、町野左近が暗い顔をして現れた。
「爺。四郎は?」
「それが…」
思った以上に深手を負っていた四郎は、忠三郎が勝家の本陣に向かったころにはすでに息絶えていた。
「殿が日野に幽閉されている関殿に知らせを送り、四郎様の亡骸は荼毘に付して日野に持ち帰ることとなりました」
「四郎が死んだ…」
関家再興を願い、命を賭して戦い続けたにもかかわらず、その功名は認められることなく、関四郎は戦場に散り、静かに命を終えた。
(これでは四郎は無意味なことをして、無駄死にしただけ)
戦いは始まったばかり。落とした砦は無数にある砦の一つにしかすぎない。この戦さが終われば、四郎の働きも忘れられていく。四郎の心に燃えた覚悟と忠義は、風に舞う落ち葉のように消え去り、誰にも知られることはない。
名を残すこともなく、ただ冷たい土に還る四郎の姿は、無常な運命に翻弄された一人の武士の儚さを物語っている。四郎が抱いた夢も、まるで霧のように消え失せ、四郎の犠牲はただ静かに、歴史の片隅に埋もれていく。
残酷で無残な結末に、忠三郎は一人、床几に座ったまま動けなくなった。落とした砦の周辺から悲鳴や怒声が聞こえてくる。砦周辺の村落への執拗な乱捕りが行われているようだ。幾度も繰り返されてきた光景で、もう慣れてしまった。この分では明日の明朝、明るくなって戦闘が再開されるまで、乱捕りが続くだろう。
かつてないほどの大掛かりな戦さだ。一益によって各処にはすでに諸将が本陣を置くために寺や家が抑えられており、長期戦に備えて荷駄衆が兵糧を運び込む。
大川の向こうに見えるのは難攻の地・長島。
(いよいよ長島に攻め入る)
小木江で信長の弟・織田彦七郎が討たれてから四年。度々長島願証寺に煮え湯を飲まされ、信長の憎悪の念は募る一方だった。
大湊衆を従えた一益は、九鬼嘉隆とともに志摩・伊勢・尾張の海賊衆を率いて大湊から大船団を率いてくる。そしてあの大きな阿武船に兵を乗せ、長島に上陸させる手筈になっている。
長島を前にして陣を張ると、従兄弟の関四郎が意気揚々と現れた。
「鶴。此度はなんとしても手柄を立て、日野に幽閉されている父上をお救いしたい。力を貸してくれ」
四郎の末の弟は柴田勝家の元に留められたままだ。今や関家の居城・亀山城は信長の三男・神戸三七のものとなり、このままでは鎌倉時代から続く名門・関家がなくなってしまうと焦りを募らせる。
「そう焦るな。今、焦っても上様の御心が変わるとは思えぬ」
常の笑顔でそう言って四郎を落ち着かせようとしたが、予想に反し、四郎は目をむいて怒った。
「所詮、上様に気に入られ、娘婿となった鶴には、わしの思いなど、分からぬか」
信長の怒りは神戸家の養子にした神戸三七をないがしろにしたとの理由による。一益にも勝家にも相談したが、勝家は渋い顔をして今日・明日に信長の怒りを解くことは難しいと言い、一益は少し辛抱して待てと言う。
忠三郎自身も、同じようには思っていたが、父を幽閉され、弟を人質に取られ、居城まで奪われた四郎には伝わらない。
「城も奪われ、家臣たちは行く宛もなく困り果て、百姓をして生計をたてている者もおる。それならばまだよい。離散したまま時がたち、他家に仕官されては、父上の幽閉が解けたとしても我が家はもはや成り立たぬ。早く上様のお怒りを解き、城と父上を返してもらわねば…」
四郎の焦りが伝わってきた。
(四郎は四郎で、関家を守ろうと必死なのか)
忠三郎は自分とそう年の変わらない従兄弟の気持ちを察して心を決めた。
「では、叔父上のため、関家再興のために、ここで大手柄を立てよう」
笑顔でそういうと、四郎は忠三郎の手を取り、
「まことか!鶴!忝い」
深々と頭を下げる。
「まずは我等で長島一番乗りを果たしては如何であろう。さすれば、そのまま一番槍を狙うこともできる」
味方は総勢十二万。その中で、あの大川の真中にある長島に、誰よりも先に上陸し、名乗りをあげれば敵味方にその名は知れ渡る。
「一番乗り?では船を用意せねば…」
「いや、馬を連れて行かねば砦に近づくことも容易ではない。船で行けば騎乗して渡ることはかなうまい。この辺りには松之木の渡りなる道があり、引き潮のときには陸路で長島に渡れると聞き及んだ。まずは物見を出して松之木の渡りを探し出し、掛かり太鼓の合図とともに松之木の渡りを使って長島へ行き、松之木砦を攻略しよう」
信長は尾張方面から南下してくる。そして一益は船に乗ってくる。いつもであれば、先陣を務めたいと言うと、決まって止めに入る信長や一益はいない。唯一いるのは柴田勝家だけであり、今回こそ、手柄を立てる絶好の機会ともいえた。
実直な勝家が相手であれば、熱心に訴えれば許してくれる。そう思い、勝家本陣まで出向いて先陣を願い出ると、当初、渋ってはいたが、何度も頼み込み、なんとか説き伏せ、ようやく許してもらうことができた。
「四郎!明日は必ず、我等で長島一番乗りを果たそうぞ!」
忠三郎がいつにも増して力を入れて言うと、四郎も頷き、
「必ず、必ず手柄を立てて、家を再興する」
思いつめたように忠三郎を見て、そう言った。
いよいよ明朝、攻めかかると決まり、関四郎とともに支度を整えていると、町野左近が滝川助太郎を伴って現れる。
「若殿。滝川家より使者が参り、一揆勢に根来・雑賀の者たちが加わっているゆえ、軽挙妄動は控えるようにとのことでござりますが…」
忠三郎の顔色を伺いながらそう告げる。一益は何かを察したように釘をさしてきた。今回、先陣を仰せつかったと言っても嬉しそうではなかった町野左近は、一益からの忠告を聞いてますます不安になったらしい。
忠三郎はそんな町野左近を見て微笑を浮かべる。
「爺、敵を恐れていては手柄など立てることはできぬ。此度、新しく我が家に召し抱えた家臣たちをこの場へ集めよ」
「ハハッ」
何がはじまるのかと町野左近は首を傾げながら、声をかけて歩き、六角家の旧臣を含め、新しく家臣の列に加わった武将たちが集めた。
忠三郎はずらりと並んだ家臣たちの前に意気揚々と立ち、笑顔を見せる。
「皆、よう聞け。明朝、松之木の渡りを越え、長島へ入り、松之木砦へと向かう。我が家には銀の鯰尾の兜を被り、先陣を駆ける武者がおる。皆もその者に後れを取らぬように励め」
家臣たちが誰のことかと互いに顔を見合わせる。忠三郎はそんな家臣たちを尻目に、満面笑顔で帷幕の中へ戻っていった。
翌朝、忠三郎は関四郎と二人で誰よりも先に馬に乗り、掛かり太鼓が鳴り響くのを待った。
まもなく鳴り物が鳴り響く。
「四郎、参ろうぞ!」
忠三郎はいち早く馬を走らせ、松之木の渡りを目指した。その頭にあるのは無論、鯰尾の兜。関四郎がなんとか遅れまいと後に従い、更にその後ろを家臣たちが追いかけてくるのが分かる。
松之木の渡りにさしかかったあたりで、早くも銃声が聞こえてきた。
(砦から撃っているのだろうか)
砦にはまだ少し距離がある。矢も弾も届かない筈だ。忠三郎はわき目も降らず、長島目指して突き進み、ついに長島の地に足を踏み入れた。
「蒲生忠三郎、長島一番乗り!」
声高らかにそう叫ぶと、松之木砦目指して突き進んだ。近づいてみると、思ったよりもしっかりとした砦が組まれており、土塁の上には土壁まで見える。
「鶴!」
ようやく追いついた四郎が大声で呼ぶと、土壁の向こうに隠れ潜んでいた鉄砲隊がこちらに向かって一斉射撃を浴びせた。
目の前の木の枝に弾がかすめる。
(これは思うていたよりも狙いが確かじゃ)
さして警戒もしなかった戦闘慣れしていない一揆勢の鉄砲隊が、狙い定めて撃ってくるとは考えもしなかった。
「四郎、足軽共がくるのを待って、攻めかかろう」
このまま砦に向かっても狙い撃ちされてしまう。砦から少し離れて兵が追い付いてくるのを待つことにした。
(根来・雑賀の者たちが加わっていると、そう言っていた)
根来・雑賀衆とは、前回の長島攻めの退却時に後ろから襲ってきた一群のことだろう。忠三郎は話に聞くだけで、実際に目で見たことがない。
(もしや、銃の扱いに慣れたものがいると、義兄上はそう言っていたのか)
これは思ったよりも手ごわいかもしれない。
では、あの砦をどうやって落とすかと考えていると、家臣たちが集まってきて、足軽がそれに続いてきた。その後ろには、先陣を申し出たとはいえ、まさか忠三郎が一人で飛び出していくとは思いもよらなかった柴田勝家が大慌てで兵を率いてくるのが見える。
「鶴。このままここに留まっていては手柄を横取りされてしまう。急ぎ、砦へ向かわねば」
功を焦る四郎が馬首を返そうとする。
「待て、四郎。迂闊に近づくのは危ない。まずは兵を纏めて…」
と忠三郎が言い終わるのを待たずに、四郎が砦目指して馬を走らせていってしまう。
「四郎!」
関家の旧臣たちが慌てて後に従う。そこへ町野左近が現れ、
「若殿、お待ちくだされ。ここは我らが参りましょう」
忠三郎を押しとどめようとした。
「それには及ばぬ。あれなる林からであれば砦まで届く。木陰に弓隊を連れて行き、土壁に隠れる敵を狙って矢を放て」
忠三郎はそう言って四郎を追いかけた。
砦から放たれる弾丸が兜をかすめるのが分かる。
(かようなときは…)
まっすぐに走らず、ジグザグに馬を走らせて被弾を避ける。
銃を構えて狙い定め、実際に撃つまでは間があり、間合いを取ることで、敵が引き金を引く前から前提上の射線を避けることができる。この練習は義太夫の水鉄砲で何度もやらされた。
その時は実戦で役に立つとは思っていなかったが。
(思うたよりも、役立ってくれるではないか)
兵を引き連れ、砦へと近づくと、町野左近率いる弓兵が土壁の向こう側めがけて矢を放つのが見えた。
「よし、今じゃ!者ども、土塁を乗り越えよ!」
鬨の声が響き渡り、足軽が土塁に殺到すると、敵兵が門を目指して逃げるのが見えた。忠三郎も土塁を乗り越え、逃げ遅れた敵兵をなぎ倒す。
「忠三郎殿!ここは我らに任せてお引きくだされ」
勝家の軍勢が追い付いてきたようだ。振り返ると、さらにその後ろには佐久間信盛の軍勢も見える。
「されど、四郎が…」
鉄砲隊を突き崩すことに気を取られ、四郎を見失っている。
「若殿、我らが向かいまする」
町野左近が槍を携え、兵を率いて城門へと向かおうとするが、すでに万を超える兵が雪崩のように小さな砦に押し寄せ、城門付近は味方の兵で溢れている。
「四郎を探さねば…」
忠三郎は味方を押しのけながら城門へと向かった。
重傷を負った関四郎が陣営に運ばれてきたのは、松ノ木砦が落ちた後だった。四郎は兜首ふたつを取って、従者に持たせていた。
戸板に寝かされた四郎は、苦しそうにうめきながらも
「鶴…この首を上様に…」
信長に見せれば関家再興が叶うかもしれない。そう思って一縷の望みをかけ、敵中深くまで攻め入ったのだろう。
「確かに、受け取った。これより上様本陣へ向かい、おぬしの手柄を伝えてくる。それゆえ、気をしっかり持て」
家臣たちは懸命に手当しているが、複数個所に被弾していて、出血が止まらない。最初の突撃で、四郎だけではなく、何人もの家臣が怪我をし、少なからず命を落としたものいた。
いずれも皆、鉄砲傷によるもので、よくよく見ると銃弾が兜や鎧を貫通していた。
(ここまで狙い撃ちされていたとは)
何故、忠三郎だけ被弾しなかったのだろうか。鎧を脱ぎ、あちこち観察してみると、弾傷はあるが、貫通はしていない。
(もしや…)
思い当ることがあった。
岐阜の最終評定のあとのことだ。
『銃により、これまでの戦さのやり方は通用しなくなった。これは攻めるだけではなく、守りにおいても同様である』
一益はそう言った。
『守り、とは?土塁に鉄砲隊を配備させるということで?』
言わんとしていることがよくわからず、忠三郎がなんとなく思い描くことを口にすると、
『無論、それもあるが、それだけでは足りぬ。まずは城を守るには土塁だけでは足りぬ。堅固な石垣を四方に巡らせること。そして、甲冑』
『甲冑?』
銃と弓矢の違いは、その貫通力にある。これまでの当世具足は弓矢や槍での戦いを想定したもの。しかしそれでは銃弾を防ぐことができない、と一益は言った。
『では、如何様にすればよろしいので?』
忠三郎の問いに対し、一益は
『日野の鉄砲鍛冶に命じて、いくつか用意させておる。そのうちの一つを届けるようにと命じておいた。直に日野の城に届くであろう』
何が届くのかと思っていると、届けられたのは銃弾をも通さぬという鎧、そして忠三郎を現す象徴ともいえる銀の鯰尾の兜も鉄製のものが用意された。
『ポルトガル商人から手に入れた鎧を、さらに滝川様から改良するようにと申し付けられ、あつらえたもので。人呼んで、南蛮具足、南蛮兜』
鉄砲鍛冶はそう言った。
(南蛮具足?)
南蛮の鉄板のような鎧に、さらに腰から太ももまでを覆う草褶を取り付けた鎧だった。試しに着用してみると、鉄でできているだけあって相当に重く、馬に乗るのも家臣の手を借りなければならなかった。
(これで銃弾が防げるのか)
であれば、いざ攻めかかるときには便利かもしれない。そう考え、南蛮具足を身に着けても動けるようにと、何度も着ては馬を走らせたり、家臣と相撲をとったりして少しずつ慣れていった。
(当世具足では銃弾から身を守ることができなかったのか)
城から狙いの確かな弾が撃たれていることは気づいていた。それなのに何故、皆が被弾し、倒れていることに気づけなかったのか。
(あのときは…見えなかった)
激しい銃声を耳にしてから、筒の中を覗き込むようにまっすぐ前しか見えなくなり、目指す城門が実際よりも近くに感じられた。あれは一体なんだろうか。
考えても分からなかったが、四郎の手柄を広く、織田家の諸将に伝えなければならない。
忠三郎は四郎とともにいた従者を連れて寄親である柴田勝家の本陣へ行った。
勝家に事と次第を話すと、
「此度は蒲生勢の突撃により難なく砦を落とすことができた。上様にお伝えすれば、あるいは関殿の幽閉も解け、亀山城を返していただくことができるやもしれぬ。さ、早う上様本陣へ向かいなされ」
背中を押され、忠三郎は意気揚々と船に乗り、大川を越えて信長本陣へ向かった。
しかし予想に反して信長の反応は冷ややかなものだった。
「葉武者の如き振る舞いじゃ」
不機嫌そうにただ一言、そう言って忠三郎を下がらせた。
長島一番乗りを果たし、数多の犠牲を払って立てた手柄は見向きもされず、関家再興を願い出る隙もなかった。
(四郎に何と言えば…)
とぼとぼと自陣に戻ると、関家の旧臣たちが一人、二人、肩を落として荷物を纏めている姿が目に入る。
「みな、如何した?四郎の容態は?」
声をかけても反応がない。聞こえていないかのように陣営を後にする者、涙する者がいて、もしやと思い、町野左近を呼んだ。
少し待っていると、町野左近が暗い顔をして現れた。
「爺。四郎は?」
「それが…」
思った以上に深手を負っていた四郎は、忠三郎が勝家の本陣に向かったころにはすでに息絶えていた。
「殿が日野に幽閉されている関殿に知らせを送り、四郎様の亡骸は荼毘に付して日野に持ち帰ることとなりました」
「四郎が死んだ…」
関家再興を願い、命を賭して戦い続けたにもかかわらず、その功名は認められることなく、関四郎は戦場に散り、静かに命を終えた。
(これでは四郎は無意味なことをして、無駄死にしただけ)
戦いは始まったばかり。落とした砦は無数にある砦の一つにしかすぎない。この戦さが終われば、四郎の働きも忘れられていく。四郎の心に燃えた覚悟と忠義は、風に舞う落ち葉のように消え去り、誰にも知られることはない。
名を残すこともなく、ただ冷たい土に還る四郎の姿は、無常な運命に翻弄された一人の武士の儚さを物語っている。四郎が抱いた夢も、まるで霧のように消え失せ、四郎の犠牲はただ静かに、歴史の片隅に埋もれていく。
残酷で無残な結末に、忠三郎は一人、床几に座ったまま動けなくなった。落とした砦の周辺から悲鳴や怒声が聞こえてくる。砦周辺の村落への執拗な乱捕りが行われているようだ。幾度も繰り返されてきた光景で、もう慣れてしまった。この分では明日の明朝、明るくなって戦闘が再開されるまで、乱捕りが続くだろう。
0
お気に入りに追加
16
あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した
若き日の滝川一益と滝川義太夫、
尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として
天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が
からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う
ピコサイクス
歴史・時代
1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

蒼雷の艦隊
和蘭芹わこ
歴史・時代
第五回歴史時代小説大賞に応募しています。
よろしければ、お気に入り登録と投票是非宜しくお願いします。
一九四二年、三月二日。
スラバヤ沖海戦中に、英国の軍兵四二二人が、駆逐艦『雷』によって救助され、その命を助けられた。
雷艦長、その名は「工藤俊作」。
身長一八八センチの大柄な身体……ではなく、その姿は一三○センチにも満たない身体であった。
これ程までに小さな身体で、一体どういう風に指示を送ったのか。
これは、史実とは少し違う、そんな小さな艦長の物語。
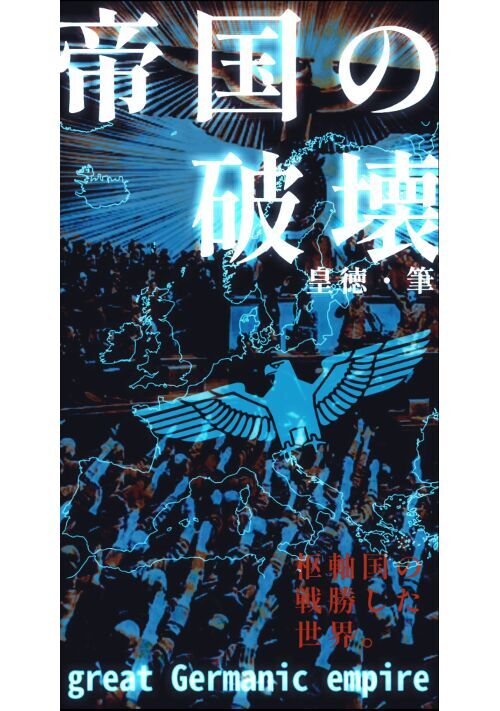
『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−
皇徳❀twitter
歴史・時代
この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。
二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

独裁者・武田信玄
いずもカリーシ
歴史・時代
歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!
平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。
『事実は小説よりも奇なり』
この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……
歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。
過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。
【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い
【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形
【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人
【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある
【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である
この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。
(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

本能のままに
揚羽
歴史・時代
1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった
もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!
※更新は不定期になると思います。

我らの輝かしきとき ~拝啓、坂の上から~
城闕崇華研究所(呼称は「えねこ」でヨロ
歴史・時代
講和内容の骨子は、以下の通りである。
一、日本の朝鮮半島に於ける優越権を認める。
二、日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。
三、ロシアは樺太を永久に日本へ譲渡する。
四、ロシアは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。
五、ロシアは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する。
六、ロシアは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える。
そして、1907年7月30日のことである。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















