お気に入りに追加
10
あなたにおすすめの小説


蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。
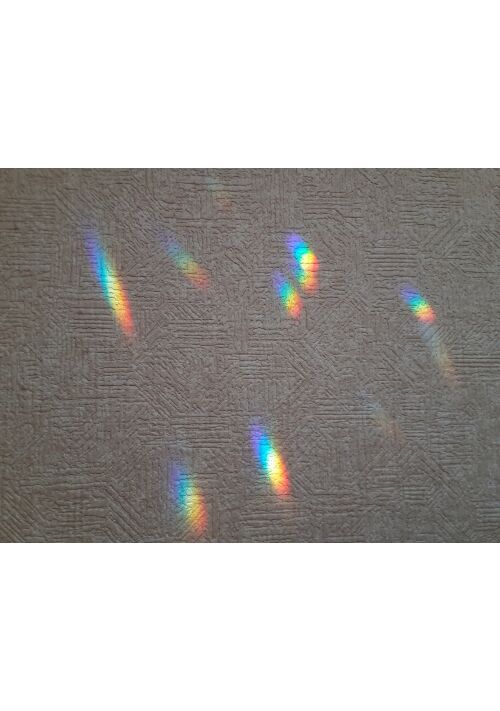

悲しみの向こう側
雲龍神楽
青春
18歳にして病魔と戦い余命5年と言われたが、10年生きてこの世を去った麻耶。
麻耶を襲ったのは、現代の医学では治療法のない病魔だった。
親友の杏奈は、麻耶の死を受け入れることが出来なかった。杏奈は麻耶の死以前に杏奈のお姉ちゃんの佑奈の死があったからだ。
麻耶は自分の余命が残り僅かだとわかった時麻耶が杏奈に残したものとは。
杏奈に降りそそぐ運命とはーー。

姉らぶるっ!!
藍染惣右介兵衛
青春
俺には二人の容姿端麗な姉がいる。
自慢そうに聞こえただろうか?
それは少しばかり誤解だ。
この二人の姉、どちらも重大な欠陥があるのだ……
次女の青山花穂は高校二年で生徒会長。
外見上はすべて完璧に見える花穂姉ちゃん……
「花穂姉ちゃん! 下着でウロウロするのやめろよなっ!」
「んじゃ、裸ならいいってことねっ!」
▼物語概要
【恋愛感情欠落、解離性健忘というトラウマを抱えながら、姉やヒロインに囲まれて成長していく話です】
47万字以上の大長編になります。(2020年11月現在)
【※不健全ラブコメの注意事項】
この作品は通常のラブコメより下品下劣この上なく、ドン引き、ドシモ、変態、マニアック、陰謀と陰毛渦巻くご都合主義のオンパレードです。
それをウリにして、ギャグなどをミックスした作品です。一話(1部分)1800~3000字と短く、四コマ漫画感覚で手軽に読めます。
全編47万字前後となります。読みごたえも初期より増し、ガッツリ読みたい方にもお勧めです。
また、執筆・原作・草案者が男性と女性両方なので、主人公が男にもかかわらず、男性目線からややずれている部分があります。
【元々、小説家になろうで連載していたものを大幅改訂して連載します】
【なろう版から一部、ストーリー展開と主要キャラの名前が変更になりました】
【2017年4月、本幕が完結しました】
序幕・本幕であらかたの謎が解け、メインヒロインが確定します。
【2018年1月、真幕を開始しました】
ここから読み始めると盛大なネタバレになります(汗)


萬倶楽部のお話(仮)
きよし
青春
ここは、奇妙なしきたりがある、とある高校。
それは、新入生の中からひとり、生徒会の庶務係を選ばなければならないというものであった。
そこに、春から通うことになるさる新入生は、ひょんなことからそのひとりに選ばれてしまった。
そして、少年の学園生活が、淡々と始まる。はずであった、のだが……。

[1分読書]彼女を寝取られたので仕返しします・・・
無責任
青春
僕は武田信長。高校2年生だ。
僕には、中学1年生の時から付き合っている彼女が・・・。
隣の小学校だった上杉愛美だ。
部活中、軽い熱中症で倒れてしまった。
その時、助けてくれたのが愛美だった。
その後、夏休みに愛美から告白されて、彼氏彼女の関係に・・・。
それから、5年。
僕と愛美は、愛し合っていると思っていた。
今日、この状況を見るまでは・・・。
その愛美が、他の男と、大人の街に・・・。
そして、一時休憩の派手なホテルに入って行った。
僕はどうすれば・・・。
この作品の一部に、法令違反の部分がありますが、法令違反を推奨するものではありません。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















