2 / 20
02
しおりを挟む
「お前だな。この村にいる、平民らしからぬ娘というのは」
うららかな陽が昇る、よく晴れた日の昼。レイチェルの働く飯屋に、一目で貴族とわかる豪奢な服を着た男がやってきた。
蛇のように鋭く冷たい眼をした壮年の男は、入るなりレイチェルに詰め寄り、上から下までじっとりとした視線で舐めまわす。
(何ですのこの方。貴族なら女性を不躾に見ることがどれほど失礼なのか、当然知っているでしょうに)
後から知ったことだが、貴族男性の中には平民女性を人間だと思っていない人も多いらしい。この男がそうだった。
「――確かに瓜二つだな。それに、身のこなしには淑女のような気品もある。よかろう、ついてこい。今日からお前は私の娘“クリスティーナ”だ。いいな?」
「いえ、全然良くありませんわ。わたくしはレイチェルよ。あなたの娘では――」
反論しかけたところで、男の大きな手にガッと顔を掴まれる。すぐさま村の男たちが立ち上がったが、連れの護衛達が素早く剣を抜いて牽制した。
「お前は今日からクリスティーナだ。拒否は許さん」
「な、ん……!」
両頬に食い込む指が痛い。レイチェルが男の腕を叩くとようやく離してくれたが、その瞳は冷たく、一言も彼女の反論を許していないのがわかる。
「いいかクリスティーナ。私には、お前やお前の両親を潰すことぐらい、簡単にできるんだ。――だが大人しくついてくれば、両親の面倒は見てやろう。聞くところによると、定期的に薬が必要なんだろう?」
母のことを出されて、レイチェルは黙るしかなかった。この男、腹立たしいことにちゃんと弱点を調べ上げていたらしい。
「今日の夜に迎えをよこす。いいか、決して逃げるでないぞ。もし逃げたら必ず探し出して、死んだ方がマシだと思う目に遭わせるからな」
ギラギラと底光りする瞳を見ながらレイチェルはコクコクと頷いた。この男は本気だ。なら、今は決して逆らってはいけない。いつか必ず逃げ出すチャンスはあるのだから、と自分に言い聞かせながら。
それからレイチェルは慌てて自宅に帰り、父と母に事情を説明した。二人ともひどく怒って一緒に逃げようと言ってくれたが、それはできない。あの男はきっと言葉通り、地の果てまで追いかけてくるだろう。悔しくとも素直に従った方が、少なくとも両親は守れるはずだ。
「いつか必ず帰るから、待っていて……」
レイチェルには、そう言うのがやっとだった。
うららかな陽が昇る、よく晴れた日の昼。レイチェルの働く飯屋に、一目で貴族とわかる豪奢な服を着た男がやってきた。
蛇のように鋭く冷たい眼をした壮年の男は、入るなりレイチェルに詰め寄り、上から下までじっとりとした視線で舐めまわす。
(何ですのこの方。貴族なら女性を不躾に見ることがどれほど失礼なのか、当然知っているでしょうに)
後から知ったことだが、貴族男性の中には平民女性を人間だと思っていない人も多いらしい。この男がそうだった。
「――確かに瓜二つだな。それに、身のこなしには淑女のような気品もある。よかろう、ついてこい。今日からお前は私の娘“クリスティーナ”だ。いいな?」
「いえ、全然良くありませんわ。わたくしはレイチェルよ。あなたの娘では――」
反論しかけたところで、男の大きな手にガッと顔を掴まれる。すぐさま村の男たちが立ち上がったが、連れの護衛達が素早く剣を抜いて牽制した。
「お前は今日からクリスティーナだ。拒否は許さん」
「な、ん……!」
両頬に食い込む指が痛い。レイチェルが男の腕を叩くとようやく離してくれたが、その瞳は冷たく、一言も彼女の反論を許していないのがわかる。
「いいかクリスティーナ。私には、お前やお前の両親を潰すことぐらい、簡単にできるんだ。――だが大人しくついてくれば、両親の面倒は見てやろう。聞くところによると、定期的に薬が必要なんだろう?」
母のことを出されて、レイチェルは黙るしかなかった。この男、腹立たしいことにちゃんと弱点を調べ上げていたらしい。
「今日の夜に迎えをよこす。いいか、決して逃げるでないぞ。もし逃げたら必ず探し出して、死んだ方がマシだと思う目に遭わせるからな」
ギラギラと底光りする瞳を見ながらレイチェルはコクコクと頷いた。この男は本気だ。なら、今は決して逆らってはいけない。いつか必ず逃げ出すチャンスはあるのだから、と自分に言い聞かせながら。
それからレイチェルは慌てて自宅に帰り、父と母に事情を説明した。二人ともひどく怒って一緒に逃げようと言ってくれたが、それはできない。あの男はきっと言葉通り、地の果てまで追いかけてくるだろう。悔しくとも素直に従った方が、少なくとも両親は守れるはずだ。
「いつか必ず帰るから、待っていて……」
レイチェルには、そう言うのがやっとだった。
2
お気に入りに追加
357
あなたにおすすめの小説

乙女ゲームの世界だと、いつから思い込んでいた?
シナココ
ファンタジー
母親違いの妹をいじめたというふわふわした冤罪で婚約破棄された上に、最北の辺境地に流された公爵令嬢ハイデマリー。勝ち誇る妹・ゲルダは転生者。この世界のヒロインだと豪語し、王太子妃に成り上がる。乙女ゲームのハッピーエンドの確定だ。
……乙女ゲームが終わったら、戦争ストラテジーゲームが始まるのだ。

転生悪役令嬢に仕立て上げられた幸運の女神様は家門から勘当されたので、自由に生きるため、もう、ほっといてください。今更戻ってこいは遅いです
青の雀
ファンタジー
公爵令嬢ステファニー・エストロゲンは、学園の卒業パーティで第2王子のマリオットから突然、婚約破棄を告げられる
それも事実ではない男爵令嬢のリリアーヌ嬢を苛めたという冤罪を掛けられ、問答無用でマリオットから殴り飛ばされ意識を失ってしまう
そのショックで、ステファニーは前世社畜OL だった記憶を思い出し、日本料理を提供するファミリーレストランを開業することを思いつく
公爵令嬢として、持ち出せる宝石をなぜか物心ついたときには、すでに貯めていて、それを原資として開業するつもりでいる
この国では婚約破棄された令嬢は、キズモノとして扱われることから、なんとか自立しようと修道院回避のために幼いときから貯金していたみたいだった
足取り重く公爵邸に帰ったステファニーに待ち構えていたのが、父からの勘当宣告で……
エストロゲン家では、昔から異能をもって生まれてくるということを当然としている家柄で、異能を持たないステファニーは、前から肩身の狭い思いをしていた
修道院へ行くか、勘当を甘んじて受け入れるか、二者択一を迫られたステファニーは翌早朝にこっそり、家を出た
ステファニー自身は忘れているが、実は女神の化身で何代前の過去に人間との恋でいさかいがあり、無念が残っていたので、神界に帰らず、人間界の中で転生を繰り返すうちに、自分自身が女神であるということを忘れている
エストロゲン家の人々は、ステファニーの恩恵を受け異能を覚醒したということを知らない
ステファニーを追い出したことにより、次々に異能が消えていく……
4/20ようやく誤字チェックが完了しました
もしまだ、何かお気づきの点がありましたら、ご報告お待ち申し上げておりますm(_)m
いったん終了します
思いがけずに長くなってしまいましたので、各単元ごとはショートショートなのですが(笑)
平民女性に転生して、下剋上をするという話も面白いかなぁと
気が向いたら書きますね

【完結】もう…我慢しなくても良いですよね?
アノマロカリス
ファンタジー
マーテルリア・フローレンス公爵令嬢は、幼い頃から自国の第一王子との婚約が決まっていて幼少の頃から厳しい教育を施されていた。
泣き言は許されず、笑みを浮かべる事も許されず、お茶会にすら参加させて貰えずに常に完璧な淑女を求められて教育をされて来た。
16歳の成人の義を過ぎてから王子との婚約発表の場で、事あろうことか王子は聖女に選ばれたという男爵令嬢を連れて来て私との婚約を破棄して、男爵令嬢と婚約する事を選んだ。
マーテルリアの幼少からの血の滲むような努力は、一瞬で崩壊してしまった。
あぁ、今迄の苦労は一体なんの為に…
もう…我慢しなくても良いですよね?
この物語は、「虐げられる生活を曽祖母の秘術でざまぁして差し上げますわ!」の続編です。
前作の登場人物達も多数登場する予定です。
マーテルリアのイラストを変更致しました。

タイムリープ〜悪女の烙印を押された私はもう二度と失敗しない
結城芙由奈@コミカライズ発売中
恋愛
<もうあなた方の事は信じません>―私が二度目の人生を生きている事は誰にも内緒―
私の名前はアイリス・イリヤ。王太子の婚約者だった。2年越しにようやく迎えた婚約式の発表の日、何故か<私>は大観衆の中にいた。そして婚約者である王太子の側に立っていたのは彼に付きまとっていたクラスメイト。この国の国王陛下は告げた。
「アイリス・イリヤとの婚約を解消し、ここにいるタバサ・オルフェンを王太子の婚約者とする!」
その場で身に覚えの無い罪で悪女として捕らえられた私は島流しに遭い、寂しい晩年を迎えた・・・はずが、守護神の力で何故か婚約式発表の2年前に逆戻り。タイムリープの力ともう一つの力を手に入れた二度目の人生。目の前には私を騙した人達がいる。もう騙されない。同じ失敗は繰り返さないと私は心に誓った。
※カクヨム・小説家になろうにも掲載しています

どうも、死んだはずの悪役令嬢です。
西藤島 みや
ファンタジー
ある夏の夜。公爵令嬢のアシュレイは王宮殿の舞踏会で、婚約者のルディ皇子にいつも通り罵声を浴びせられていた。
皇子の罵声のせいで、男にだらしなく浪費家と思われて王宮殿の使用人どころか通っている学園でも遠巻きにされているアシュレイ。
アシュレイの誕生日だというのに、エスコートすら放棄して、皇子づきのメイドのミュシャに気を遣うよう求めてくる皇子と取り巻き達に、呆れるばかり。
「幼馴染みだかなんだかしらないけれど、もう限界だわ。あの人達に罰があたればいいのに」
こっそり呟いた瞬間、
《願いを聞き届けてあげるよ!》
何故か全くの別人になってしまっていたアシュレイ。目の前で、アシュレイが倒れて意識不明になるのを見ることになる。
「よくも、義妹にこんなことを!皇子、婚約はなかったことにしてもらいます!」
義父と義兄はアシュレイが状況を理解する前に、アシュレイの体を持ち去ってしまう。
今までミュシャを崇めてアシュレイを冷遇してきた取り巻き達は、次々と不幸に巻き込まれてゆき…ついには、ミュシャや皇子まで…
ひたすら一人づつざまあされていくのを、呆然と見守ることになってしまった公爵令嬢と、怒り心頭の義父と義兄の物語。
はたしてアシュレイは元に戻れるのか?
剣と魔法と妖精の住む世界の、まあまあよくあるざまあメインの物語です。
ざまあが書きたかった。それだけです。
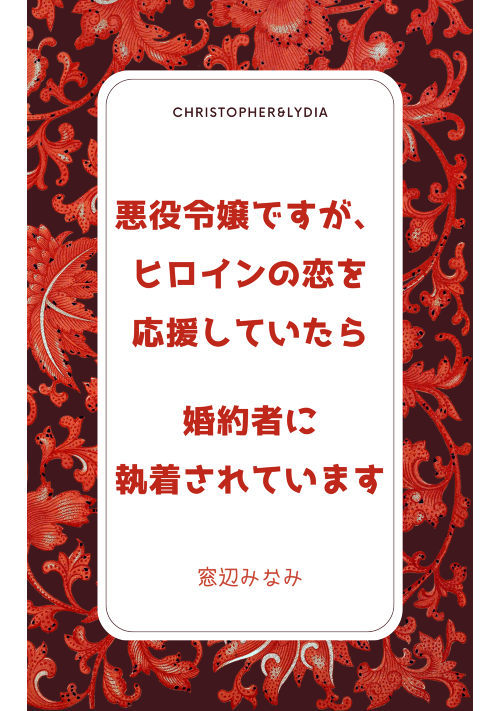
悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています
窓辺ミナミ
ファンタジー
悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。
シナリオ通りなら、死ぬ運命。
だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!
騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!
というわけで、私、悪役やりません!
来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。
あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!
気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。
悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

罠にはめられた公爵令嬢~今度は私が報復する番です
結城芙由奈@コミカライズ発売中
ファンタジー
【私と私の家族の命を奪ったのは一体誰?】
私には婚約中の王子がいた。
ある夜のこと、内密で王子から城に呼び出されると、彼は見知らぬ女性と共に私を待ち受けていた。
そして突然告げられた一方的な婚約破棄。しかし二人の婚約は政略的なものであり、とてもでは無いが受け入れられるものではなかった。そこで婚約破棄の件は持ち帰らせてもらうことにしたその帰り道。突然馬車が襲われ、逃げる途中で私は滝に落下してしまう。
次に目覚めた場所は粗末な小屋の中で、私を助けたという青年が側にいた。そして彼の話で私は驚愕の事実を知ることになる。
目覚めた世界は10年後であり、家族は反逆罪で全員処刑されていた。更に驚くべきことに蘇った身体は全く別人の女性であった。
名前も素性も分からないこの身体で、自分と家族の命を奪った相手に必ず報復することに私は決めた――。
※他サイトでも投稿中

【完結】悪役令嬢に転生したけど、王太子妃にならない方が幸せじゃない?
みちこ
ファンタジー
12歳の時に前世の記憶を思い出し、自分が悪役令嬢なのに気が付いた主人公。
ずっと王太子に片思いしていて、将来は王太子妃になることしか頭になかった主人公だけど、前世の記憶を思い出したことで、王太子の何が良かったのか疑問に思うようになる
色々としがらみがある王太子妃になるより、このまま公爵家の娘として暮らす方が幸せだと気が付く
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















