2 / 6
一.雪豹のいる山脈
エマ
しおりを挟む
「母さん!」
一心不乱に走りながら、少年は叫ぶ。
母親の口が動く。
――逃げて、オレグ。
「アセル!」
母親に庇われながら、妹は赤ら顔で泣きじゃくる。
ふたりは二体のうちの一体に囚われてしまっていた。
不甲斐なさと悔しさで涙が滲ませながら少年――オレグは走る。
汚れた頬にはかすり傷がいくつもついていた。
俺がもっと大人だったら。
父さんのように力が強く、勇敢な大人でさえあれば。
だが、この手は大切なものを取りこぼしてしまうほどに小さく、今できることは逃げることだけだ。
「うわっ!」
足もとの石にけつまずいて、オレグは派手に転ぶ。
まだ柔らかく軽い身体は、地面に叩きつけられながらも擦り傷程度で済む。
「くそっ、畜生……!」
悔しさで拳を地面に叩きつけた。
だが感傷に浸る暇はなかった。
背後から物音がする。
振り返ると、二本脚の薄汚れた白い機械が迫っていた。
細い脚部には、アンバランスなほど大きい六角柱の本体が載っている。
おかげでそこまでの速度はでないが、不思議と転ぶこともない。
その機械は型番SIL-02、通称セイレーノス二型といった。
セイレーノス二型がオレグを見下ろす。
本体の中央には一眼がついていてそこから外界を認識した。
迫る機械のレンズには非力な少年が映りこんでいる。
(――俺は、俺は……!)
山肌を撫でる風はまだ雪の気配が残っていたが、心地良い爽やかさだった。
ごつごつとした岩ばかりの地面にも草は生し、小ぶりの花を咲かせ、短い盛夏を待っている。
切りだった山脈は空を貫くように峻厳だ。
その合間を縫うように川は穏やかに流れている。
雪解け水を含んだ川はいつもより水深があるようだ。
ゆらゆらと輝く水面を見ながら、エマはこの世界は不思議だと感じる。
水面が青く見えるのは、空の青を映しているからだ。
空が青く見えるのは、太陽光の光の散乱によるもので、光の波長が長いと赤くなり短いと青くなるのだが、昼間の光の波長が短いからだ。
では、この『青』という認識はどこからくるのだろう。
ゆったりと飛ぶ白い蝶を目で追いながら考える。
蝶の複眼には紫外線も見えるという。
それならば蝶にとってこの川は何色で空は何色なんだろう。
肉食動物には世界は二色に見えるという。
肉食動物にとっての川や空は味気ない色なのだろうか。
そもそもこの空の青は、同じ人間であったとしても同じ青色なのだろうか。
見上げると空高く太陽が輝いている。
目の痛くなるほどの強烈な光はときに神として崇められた。
そんな太陽はなぜ生まれ、この地球に恵みをもたらしたのか。
なぜ地球には生命が存在するに至ったのか。
それは偶然にしてはできすぎている気がした。
そもそも生きるとはなんなのだろう。
生きているとは?
どうして人間はこんなことを考えるのだろう。
人間が考えなければ生も死もだれも意識しなかったかもしれない。
人間が考えなければ、生という認識すら世界にはなく、生きているという概念も生じず、生きるという言葉も存在しなかったのかもしれない。
それならば死もなかったのかもしれない。
両手を持ち上げ光に晒す。
右手の周囲はほんのりと赤く染まり、透け、血が通っているとわかる。
対して左手は光が透けることは一切なく、影を落とす。
替わりに光を反射し青黒く輝いた。金属の輝きだ。
左の肩から指先までと左の膝から下は機械化されていた。
もし、この体のすべてを機械と取り替えたとして、それは生きていると言えるのだろうか。
違うならこの体を一体どこまで機械化したら生きていないと判断されるのだろうか。
心臓が機械でなければ生きているのだろうか。
それとも脳さえ生身であれば生きているのか。
それとも一箇所でも機械化してしまえば生きているとは言えないのか。
ならばこの体はもう死んでいるも同然なのだろうか。
「なにぼんやりしてるんだよ、エマ」
名前を呼ばれ視線を声の先に向ける。
エマは川べりの大きな岩の上に寝そべり四肢を投げだしていた。
焦げ茶色いマントを羽織り、黒いブーツという格好だ。
その視線の先には、使い古されたボロボロのカーキ色のローブを着た小柄な人影が見下ろしている。
ローブを深くかぶっているため、その顔には影が落ち、顔立ちや表情ははっきりとしない。
「空が青いなあって思って」
促されたようにローブの主も空を振り仰ぐ。
「ああ、確かに……。よく百五十八年でここまで復活したよな」
しみじみと答えるその声は変声期前の少年のものだが、吐きだされる言葉はやけに老成していた。
「ねえ、ミケにはこの空はどう見えているんだ?」
エマの問いかけに、ミケこと、ミケランジェロ・オーロは一瞬沈黙する。
「益のないことだ、エマ」
「ちぇっ、ケチ」
エマはうつぶせになると機械の左手を川に浸し、不意に水を掬って唇に近づけた。
「おい」
「うん?」
「生水はやめとけ。きれいに見えたってここは化学兵器やら細菌兵器やらで土壌汚染があった元大国の一部だ。携帯浄水器だってあるだろ」
「心配症だなあ。元大国の一部って言っても首都だった場所からは何千キロも離れてるんだし」
「僕は用心しろと言っているんだ。大体、なんでこんな寄り道。いるかどうかもわからない雪豹を見たいだなんて酔狂が過ぎるよ」
「いいじゃん。たまには……さっ!」
掬った水は飲み干さず、エマはミケランジェロにかける。
「おいっ!」
「あははっ!」
エマは目を細めて口を目一杯広げて笑う。
鳶色の瞳がいたずらっぽく細められ、栗色の短い髪の毛は光に晒され輝く。
美人とは言えないが、人目を惹きつける感情豊かな表情の持ち主だ。
「勘弁しろよ、エマ」
ローブにかかった水を手で払いながらミケランジェロは辟易していた。
エマは身体に反動をつけて一瞬で立ち上がる。
「怒った?」
「怒ってはいなけど」
「よしよし」
「頭を撫でるな!」
乱暴に手を払いながら、ミケランジェロは不服そうだ。
「僕より少し大きくなったからって、生意気だよ」
「少しじゃないよー。もう十センチ近くわたしのほうが上じゃん」
「まだ九センチだ。それにエマだって小柄なことに変わりないだろ」
「わたしにはまだ成長と言う名の可能性があるんですう」
「ああ言えばこういう」
「怒った?」
「呆れてるんだよ、馬鹿」
「ふふっ」
両手を上げ気持ちよさそうにエマは伸びをする。
「息抜きはだいじだよ、ミケ。あんまり根を詰めたってこの旅はあてがあってないようなものだからさ」
山間を抜ける突風が不意にエマの焦げ茶色のマントを翻した。
エマは少しもよろけることなくしっかりとその場に立っていた。
だがミケランジェロにはその風がエマをさらってしまうようにも思え背筋が冷たくなる。
「気長に行くべきだよ」
エマは静かに笑った。
ミケランジェロは眉を顰めながらも気を取り直す。
なんだったのだろう、今のは。
認識のエラーだろうか。
「気長ねえ。哨戒機ARG-11やいたるところに潜む巡廻ロボットに見つかったら面倒だってことわかっているのか」
「哨戒機の軌道がここを通過するのにはまだ時間があるでしょ。それにそのときのためのネブラなんだし」
空を見上げると、くるくると巡回する鳥影がある。
あれは、哨戒機の映像にも衛星のレーダーにも探知されないステルス機能を持つ自律思考型の機械だ。
フクロウの形をしている。
「そういう問題じゃないだろ。可能性がゼロじゃない限り、万が一はどこにだってあるってことを言っているんだよ。大体、奴らに見つかれば人間は――」
「わかってる。それにわたしの目標は一秒だって長く生きることだしね」
「それは知ってるけど」
「だから大丈夫だって」
能天気にエマが言う。
いつもなら嫌味の応酬がくるはずのタイミングだったが、ミケランジェロは沈黙したままだった。
エマはミケランジェロのローブの下を覗きこむ。
「ミケ? 怒った?」
「しっ。静かに」
事態を察知したエマの表情は一瞬で引き締まる。
物音を捉えると、荷物のザックを手にし、ミケランジェロとともに素早く木陰に身を隠す。
音が近づいてくる。
川べりをなにかが走っているようだ。
足音はふたつだ。
まず視界に入ってきたのは少年だった。
汚れた貫頭衣を着ている。
昔ここらに暮らしていたという民族の特徴とは異なる。
もし、人間なのだとしたら、どこからか流れ着いたのだろう。
その後ろから見えたのは機械だ。
六角柱の平べったい本体を細い脚部が支え、岩場を器用に歩行している。
そのさまは脚の長い蟹にも似ている。
「追われているみたいだね。こんなところに人間?」
「の、ようだな。バイオロイドにしては不完全な見た目だ」
「あれは……」
「旧型だな。終末直後の製造だ。山野用巡回機、型番SIL-02――通称セイレーノス二型。セイレーノスの主な任務は山野で植物のサンプリングをすることだ」
「人間を見つけ、機械の本能を思いだしたってところか」
セイレーノス二型は少年に追いつこうとしていた。
足場の悪い岩場は一見少年に有利にも思えたが、実際は逆だったようだ。
その距離はどんどん詰まっていく。
十分に少年に近づいたと判断したのか、セイレーノス二型の上部が口を開け、そこからアームが伸びてくる。
気配に気づき少年は振り向く。
機械音とともにアームは迫り、目前で花のように大きく開いた。
(もうダメだ! だれか! ……父さん!)
つぎの瞬間、少年に迫っていたアームは宙を舞っていた。
と、同時に少年のすぐ横の岩も真っ二つに斬れている。
「ひっ……!」
「お。悪いな。加減が難しいんだ」
ガタガタと足踏みするセイレーノス二型の本体の上にひとが立っていた。
逆光で少年からは顔がよく見えない。
その人影は無造作にセイレーノス二型に手にしたなにかを叩きこんだ。
つぎの瞬間、カッとセイレーノス二型の内側が輝き、ガシャンとその場に崩れる。
なにが起こったのか少年にはわからなかった。
あまりのことにしばし呆然とする。
「よっと」
エマはセイレーノス二型から飛び降りると、手にしていた柄をマントの下にしまう。
オレンジ色の球体が柄の中心部で輝いていた。
「大丈夫か?」
「あんた、人間か? いや、違う……」
エマが差しだした左手を見た少年は恐怖で顔を歪ませる。
グラブの下から覗くのは硬質な金属の輝きだ。
「ああ、これか」
左手をひらひらとさせながらエマは笑った。
そのたびに光が反射して黒っぽい青色がチカチカと瞬く。
「確かに一部機械だけど、わたしの大半は人間だ。ずいぶん昔に大怪我しちゃって、傭兵をしてることもあってパーツがないと困るからね」
「傭兵……」
「ああ。噂とかでは聞いたことがあるだろ? 初めて見たか?」
少年は頷く。
エマは右手を差しだした。
恐る恐る少年は触れる。
「人間……」
触れた場所からひとの体温の温かさと柔らかさが伝わってくる。
指紋があり、血管が透けている。
機械にはないものだ。
気づくと涙が溢れていた。
恐怖と緊張から解き放たれ、安堵で嗚咽が漏れる。
「助けて」
エマとミケランジェロは顔を見合わせた。
「母さんと妹が機械に連れ去られたんだ。あんたならきっと助けられる。さっきあの機械を倒したその武器さえあれば。アセルは――妹は病気なんだ。きっと苦しんでる。お願いだ。助けてくれ」
少年はエマの手にすがりつく。
だがエマは力のこもったその手を振りほどいた。
驚いた少年が顔をあげると、冷たい視線が降り注いでいた。
「わかってるよな、少年」
声は低く諭す。
「おまえはそこから逃げだしたんだろうが。その責任をおまえはわたしになすりつけようとしている。おまえができなかったことをわたしにやらせようとしている。善意と同情を盾にわたしにおまえの代わりに命を懸けろと言っている。それは弱者の強者への搾取だ」
叩きつけられた言葉に少年はビクリと身体を震わせた。
「わかっているよな。自分のことは自分でやらなければならない。できないのなら、この世界では死ぬだけだ」
「だ、だったら、 なんで俺を助けたんだ!」
エマに代わって答えたのはミケランジェロだ。
「……セイレーノスは自律型だ。通信は基本定期のみで、常時ケルーブ・ハイ・ネットワークに繋がっているわけじゃない。だから、そいつが壊れたところですぐに追っ手はやってこない。逃げる時間は十分に稼げる」
「つまり、気まぐれだ」
エマはミケランジェロが持っていたザックのなかから何かを取り出し、少年に向かって投げた。
ボトリと目の前に転がったのは干し肉の塊だ。
「これは善意だ。三日分あるだろう。あとは自分でなんとかしろ。こっちは急いでいるんだ。雪豹が私を待ってるんだからな」
エマとミケランジェロは背中を見せると歩き始めた。
少年は干し肉を手に取りじっと見つめる。
口のなかは自然と唾が溢れていた。
ぐうと腹も鳴る。
そういえばここ二、三日まともに食べていない。
あの機械がうろつくようになって、ひっそりと息をこらして近くに生えている草ばかり食べていた。
しかも、肉なんていつぶりだろう。
もう最後に食べた日が思い出せない。
干し肉を握りしめた手に力がこもる。
少年は駆けだした。
エマの背中に体当りするようにぶつける。
「こんなのいらない!」
「なんだよ」
「俺、知ってる!」
「はあ?」
「あんた、雪豹って言ったよな! 俺、そいつの居場所を知ってる。見たんだ!」
「雪豹を?」
「そうだ。あんたたちはここの山脈の広さと雪豹の用心深さを知っているのか。むやみに探したって絶対に見つからない。何ヶ月も無駄足になるぞ。あんた傭兵だって言ったよな。だったら取引だ。母さんと妹を助けてくれたら、雪豹を見た場所に連れて行ってやる」
まくし立てる少年の言葉に、エマはくるりと振り向いた。
身体を折り、少年に顔を近づけてじっと目を見つめる。
「おまえ、本当に知っているのか? 苦しまぎれに嘘をついているんじゃないのか」
「し、知ってるさ」
「特徴は?」
「え?」
「雪豹の特徴。見たんだったら知ってるだろ」
「……白い毛で、身体に斑の模様……」
「目の色は?」
「と、遠目でそこまでは見えなかったよ」
「ふーん?」
ジロジロと値踏みするような視線だ。
少年は背中に冷や汗が伝うのを感じていた。
「取引か。ふん。おまえいい度胸しているな」
にやりとエマは笑った。
ミケランジェロはこの後の結末を予期して、これみよがしのため息をつく。
「わたしはエマだ。あっちのローブを着ているのが通称ミケ。で、おまえ名前は?」
「お……俺は、オレグだ!」
そのまばゆい光景は最初は鮮やかに美しく、だがすぐにただならぬことが起きていると恐怖を抱かせた。
西暦2353年2月23日、後日わずかに生き残った人類によって終末と呼称されるようになるそれはその日起きた。
核ミサイルの一斉発射の皮切りはインドだったと言われている。
それに続くようにパキスタン、中国、ロシア、イスラエル等の国からもミサイルが発射され、その数は百をゆうに超える。
標的のうちの一国であった米国の首都は真夜中だった。
予兆もなく起きた想定外の危機に対処が間に合わず都市は壊滅し、国としての機能を一瞬で失った。
他国の大都市も同様だったという。
それはミサイルを放った当事国さえも免れなかった。
多くの命は一瞬で失われ、同時に放射能汚染は広がり、オゾン層は破壊され、電磁波の嵐が吹き荒れた。
社会機能は麻痺し、巻き上がった粉塵により厚い雲が地球を長期間覆うこととなる。
それは明けない冬の始まりだった。
核の直撃を受けることなく辛うじて命を繋ぐ生物たちも、その長い冬によって徐々に命を手放していく。
植物は芽をだすことなく枯れ、糧を失った昆虫や草食動物も大量に死に、それらを食料としていた肉食動物もまた死に絶えた。
地球は壊滅的な打撃を蒙り、人類だけではなく多くの生物が命を落とす。
だが、そんななか生物に代わり台頭する存在が現れる。
それは人工知能を有した機械だった。
数を減らしそれでもどうにか生き延びていた人類だったが、その多くはさらに機械によって殺されることとなる。
機械は人間を見つけると容赦なくその生命を奪っていった。
そして、いつしか地上には機械による国が築かれる。
それから約百五十年後。
人類は百五十年前に起きた災厄を終末と呼び、だが実際にそこでなにが起きたかをはっきりと把握するものは最早いなかった。
ただわかっているのは現在世界を支配するのは機械で、機械に見つかれば殺されてしまうということだけだ。
しかし、大幅に数を減らし、その生活水準を大きく後退させてもなお、機械に見つからないよう散り散りに隠れるように暮らし、まだどうにかその種を繋いでいた。
一心不乱に走りながら、少年は叫ぶ。
母親の口が動く。
――逃げて、オレグ。
「アセル!」
母親に庇われながら、妹は赤ら顔で泣きじゃくる。
ふたりは二体のうちの一体に囚われてしまっていた。
不甲斐なさと悔しさで涙が滲ませながら少年――オレグは走る。
汚れた頬にはかすり傷がいくつもついていた。
俺がもっと大人だったら。
父さんのように力が強く、勇敢な大人でさえあれば。
だが、この手は大切なものを取りこぼしてしまうほどに小さく、今できることは逃げることだけだ。
「うわっ!」
足もとの石にけつまずいて、オレグは派手に転ぶ。
まだ柔らかく軽い身体は、地面に叩きつけられながらも擦り傷程度で済む。
「くそっ、畜生……!」
悔しさで拳を地面に叩きつけた。
だが感傷に浸る暇はなかった。
背後から物音がする。
振り返ると、二本脚の薄汚れた白い機械が迫っていた。
細い脚部には、アンバランスなほど大きい六角柱の本体が載っている。
おかげでそこまでの速度はでないが、不思議と転ぶこともない。
その機械は型番SIL-02、通称セイレーノス二型といった。
セイレーノス二型がオレグを見下ろす。
本体の中央には一眼がついていてそこから外界を認識した。
迫る機械のレンズには非力な少年が映りこんでいる。
(――俺は、俺は……!)
山肌を撫でる風はまだ雪の気配が残っていたが、心地良い爽やかさだった。
ごつごつとした岩ばかりの地面にも草は生し、小ぶりの花を咲かせ、短い盛夏を待っている。
切りだった山脈は空を貫くように峻厳だ。
その合間を縫うように川は穏やかに流れている。
雪解け水を含んだ川はいつもより水深があるようだ。
ゆらゆらと輝く水面を見ながら、エマはこの世界は不思議だと感じる。
水面が青く見えるのは、空の青を映しているからだ。
空が青く見えるのは、太陽光の光の散乱によるもので、光の波長が長いと赤くなり短いと青くなるのだが、昼間の光の波長が短いからだ。
では、この『青』という認識はどこからくるのだろう。
ゆったりと飛ぶ白い蝶を目で追いながら考える。
蝶の複眼には紫外線も見えるという。
それならば蝶にとってこの川は何色で空は何色なんだろう。
肉食動物には世界は二色に見えるという。
肉食動物にとっての川や空は味気ない色なのだろうか。
そもそもこの空の青は、同じ人間であったとしても同じ青色なのだろうか。
見上げると空高く太陽が輝いている。
目の痛くなるほどの強烈な光はときに神として崇められた。
そんな太陽はなぜ生まれ、この地球に恵みをもたらしたのか。
なぜ地球には生命が存在するに至ったのか。
それは偶然にしてはできすぎている気がした。
そもそも生きるとはなんなのだろう。
生きているとは?
どうして人間はこんなことを考えるのだろう。
人間が考えなければ生も死もだれも意識しなかったかもしれない。
人間が考えなければ、生という認識すら世界にはなく、生きているという概念も生じず、生きるという言葉も存在しなかったのかもしれない。
それならば死もなかったのかもしれない。
両手を持ち上げ光に晒す。
右手の周囲はほんのりと赤く染まり、透け、血が通っているとわかる。
対して左手は光が透けることは一切なく、影を落とす。
替わりに光を反射し青黒く輝いた。金属の輝きだ。
左の肩から指先までと左の膝から下は機械化されていた。
もし、この体のすべてを機械と取り替えたとして、それは生きていると言えるのだろうか。
違うならこの体を一体どこまで機械化したら生きていないと判断されるのだろうか。
心臓が機械でなければ生きているのだろうか。
それとも脳さえ生身であれば生きているのか。
それとも一箇所でも機械化してしまえば生きているとは言えないのか。
ならばこの体はもう死んでいるも同然なのだろうか。
「なにぼんやりしてるんだよ、エマ」
名前を呼ばれ視線を声の先に向ける。
エマは川べりの大きな岩の上に寝そべり四肢を投げだしていた。
焦げ茶色いマントを羽織り、黒いブーツという格好だ。
その視線の先には、使い古されたボロボロのカーキ色のローブを着た小柄な人影が見下ろしている。
ローブを深くかぶっているため、その顔には影が落ち、顔立ちや表情ははっきりとしない。
「空が青いなあって思って」
促されたようにローブの主も空を振り仰ぐ。
「ああ、確かに……。よく百五十八年でここまで復活したよな」
しみじみと答えるその声は変声期前の少年のものだが、吐きだされる言葉はやけに老成していた。
「ねえ、ミケにはこの空はどう見えているんだ?」
エマの問いかけに、ミケこと、ミケランジェロ・オーロは一瞬沈黙する。
「益のないことだ、エマ」
「ちぇっ、ケチ」
エマはうつぶせになると機械の左手を川に浸し、不意に水を掬って唇に近づけた。
「おい」
「うん?」
「生水はやめとけ。きれいに見えたってここは化学兵器やら細菌兵器やらで土壌汚染があった元大国の一部だ。携帯浄水器だってあるだろ」
「心配症だなあ。元大国の一部って言っても首都だった場所からは何千キロも離れてるんだし」
「僕は用心しろと言っているんだ。大体、なんでこんな寄り道。いるかどうかもわからない雪豹を見たいだなんて酔狂が過ぎるよ」
「いいじゃん。たまには……さっ!」
掬った水は飲み干さず、エマはミケランジェロにかける。
「おいっ!」
「あははっ!」
エマは目を細めて口を目一杯広げて笑う。
鳶色の瞳がいたずらっぽく細められ、栗色の短い髪の毛は光に晒され輝く。
美人とは言えないが、人目を惹きつける感情豊かな表情の持ち主だ。
「勘弁しろよ、エマ」
ローブにかかった水を手で払いながらミケランジェロは辟易していた。
エマは身体に反動をつけて一瞬で立ち上がる。
「怒った?」
「怒ってはいなけど」
「よしよし」
「頭を撫でるな!」
乱暴に手を払いながら、ミケランジェロは不服そうだ。
「僕より少し大きくなったからって、生意気だよ」
「少しじゃないよー。もう十センチ近くわたしのほうが上じゃん」
「まだ九センチだ。それにエマだって小柄なことに変わりないだろ」
「わたしにはまだ成長と言う名の可能性があるんですう」
「ああ言えばこういう」
「怒った?」
「呆れてるんだよ、馬鹿」
「ふふっ」
両手を上げ気持ちよさそうにエマは伸びをする。
「息抜きはだいじだよ、ミケ。あんまり根を詰めたってこの旅はあてがあってないようなものだからさ」
山間を抜ける突風が不意にエマの焦げ茶色のマントを翻した。
エマは少しもよろけることなくしっかりとその場に立っていた。
だがミケランジェロにはその風がエマをさらってしまうようにも思え背筋が冷たくなる。
「気長に行くべきだよ」
エマは静かに笑った。
ミケランジェロは眉を顰めながらも気を取り直す。
なんだったのだろう、今のは。
認識のエラーだろうか。
「気長ねえ。哨戒機ARG-11やいたるところに潜む巡廻ロボットに見つかったら面倒だってことわかっているのか」
「哨戒機の軌道がここを通過するのにはまだ時間があるでしょ。それにそのときのためのネブラなんだし」
空を見上げると、くるくると巡回する鳥影がある。
あれは、哨戒機の映像にも衛星のレーダーにも探知されないステルス機能を持つ自律思考型の機械だ。
フクロウの形をしている。
「そういう問題じゃないだろ。可能性がゼロじゃない限り、万が一はどこにだってあるってことを言っているんだよ。大体、奴らに見つかれば人間は――」
「わかってる。それにわたしの目標は一秒だって長く生きることだしね」
「それは知ってるけど」
「だから大丈夫だって」
能天気にエマが言う。
いつもなら嫌味の応酬がくるはずのタイミングだったが、ミケランジェロは沈黙したままだった。
エマはミケランジェロのローブの下を覗きこむ。
「ミケ? 怒った?」
「しっ。静かに」
事態を察知したエマの表情は一瞬で引き締まる。
物音を捉えると、荷物のザックを手にし、ミケランジェロとともに素早く木陰に身を隠す。
音が近づいてくる。
川べりをなにかが走っているようだ。
足音はふたつだ。
まず視界に入ってきたのは少年だった。
汚れた貫頭衣を着ている。
昔ここらに暮らしていたという民族の特徴とは異なる。
もし、人間なのだとしたら、どこからか流れ着いたのだろう。
その後ろから見えたのは機械だ。
六角柱の平べったい本体を細い脚部が支え、岩場を器用に歩行している。
そのさまは脚の長い蟹にも似ている。
「追われているみたいだね。こんなところに人間?」
「の、ようだな。バイオロイドにしては不完全な見た目だ」
「あれは……」
「旧型だな。終末直後の製造だ。山野用巡回機、型番SIL-02――通称セイレーノス二型。セイレーノスの主な任務は山野で植物のサンプリングをすることだ」
「人間を見つけ、機械の本能を思いだしたってところか」
セイレーノス二型は少年に追いつこうとしていた。
足場の悪い岩場は一見少年に有利にも思えたが、実際は逆だったようだ。
その距離はどんどん詰まっていく。
十分に少年に近づいたと判断したのか、セイレーノス二型の上部が口を開け、そこからアームが伸びてくる。
気配に気づき少年は振り向く。
機械音とともにアームは迫り、目前で花のように大きく開いた。
(もうダメだ! だれか! ……父さん!)
つぎの瞬間、少年に迫っていたアームは宙を舞っていた。
と、同時に少年のすぐ横の岩も真っ二つに斬れている。
「ひっ……!」
「お。悪いな。加減が難しいんだ」
ガタガタと足踏みするセイレーノス二型の本体の上にひとが立っていた。
逆光で少年からは顔がよく見えない。
その人影は無造作にセイレーノス二型に手にしたなにかを叩きこんだ。
つぎの瞬間、カッとセイレーノス二型の内側が輝き、ガシャンとその場に崩れる。
なにが起こったのか少年にはわからなかった。
あまりのことにしばし呆然とする。
「よっと」
エマはセイレーノス二型から飛び降りると、手にしていた柄をマントの下にしまう。
オレンジ色の球体が柄の中心部で輝いていた。
「大丈夫か?」
「あんた、人間か? いや、違う……」
エマが差しだした左手を見た少年は恐怖で顔を歪ませる。
グラブの下から覗くのは硬質な金属の輝きだ。
「ああ、これか」
左手をひらひらとさせながらエマは笑った。
そのたびに光が反射して黒っぽい青色がチカチカと瞬く。
「確かに一部機械だけど、わたしの大半は人間だ。ずいぶん昔に大怪我しちゃって、傭兵をしてることもあってパーツがないと困るからね」
「傭兵……」
「ああ。噂とかでは聞いたことがあるだろ? 初めて見たか?」
少年は頷く。
エマは右手を差しだした。
恐る恐る少年は触れる。
「人間……」
触れた場所からひとの体温の温かさと柔らかさが伝わってくる。
指紋があり、血管が透けている。
機械にはないものだ。
気づくと涙が溢れていた。
恐怖と緊張から解き放たれ、安堵で嗚咽が漏れる。
「助けて」
エマとミケランジェロは顔を見合わせた。
「母さんと妹が機械に連れ去られたんだ。あんたならきっと助けられる。さっきあの機械を倒したその武器さえあれば。アセルは――妹は病気なんだ。きっと苦しんでる。お願いだ。助けてくれ」
少年はエマの手にすがりつく。
だがエマは力のこもったその手を振りほどいた。
驚いた少年が顔をあげると、冷たい視線が降り注いでいた。
「わかってるよな、少年」
声は低く諭す。
「おまえはそこから逃げだしたんだろうが。その責任をおまえはわたしになすりつけようとしている。おまえができなかったことをわたしにやらせようとしている。善意と同情を盾にわたしにおまえの代わりに命を懸けろと言っている。それは弱者の強者への搾取だ」
叩きつけられた言葉に少年はビクリと身体を震わせた。
「わかっているよな。自分のことは自分でやらなければならない。できないのなら、この世界では死ぬだけだ」
「だ、だったら、 なんで俺を助けたんだ!」
エマに代わって答えたのはミケランジェロだ。
「……セイレーノスは自律型だ。通信は基本定期のみで、常時ケルーブ・ハイ・ネットワークに繋がっているわけじゃない。だから、そいつが壊れたところですぐに追っ手はやってこない。逃げる時間は十分に稼げる」
「つまり、気まぐれだ」
エマはミケランジェロが持っていたザックのなかから何かを取り出し、少年に向かって投げた。
ボトリと目の前に転がったのは干し肉の塊だ。
「これは善意だ。三日分あるだろう。あとは自分でなんとかしろ。こっちは急いでいるんだ。雪豹が私を待ってるんだからな」
エマとミケランジェロは背中を見せると歩き始めた。
少年は干し肉を手に取りじっと見つめる。
口のなかは自然と唾が溢れていた。
ぐうと腹も鳴る。
そういえばここ二、三日まともに食べていない。
あの機械がうろつくようになって、ひっそりと息をこらして近くに生えている草ばかり食べていた。
しかも、肉なんていつぶりだろう。
もう最後に食べた日が思い出せない。
干し肉を握りしめた手に力がこもる。
少年は駆けだした。
エマの背中に体当りするようにぶつける。
「こんなのいらない!」
「なんだよ」
「俺、知ってる!」
「はあ?」
「あんた、雪豹って言ったよな! 俺、そいつの居場所を知ってる。見たんだ!」
「雪豹を?」
「そうだ。あんたたちはここの山脈の広さと雪豹の用心深さを知っているのか。むやみに探したって絶対に見つからない。何ヶ月も無駄足になるぞ。あんた傭兵だって言ったよな。だったら取引だ。母さんと妹を助けてくれたら、雪豹を見た場所に連れて行ってやる」
まくし立てる少年の言葉に、エマはくるりと振り向いた。
身体を折り、少年に顔を近づけてじっと目を見つめる。
「おまえ、本当に知っているのか? 苦しまぎれに嘘をついているんじゃないのか」
「し、知ってるさ」
「特徴は?」
「え?」
「雪豹の特徴。見たんだったら知ってるだろ」
「……白い毛で、身体に斑の模様……」
「目の色は?」
「と、遠目でそこまでは見えなかったよ」
「ふーん?」
ジロジロと値踏みするような視線だ。
少年は背中に冷や汗が伝うのを感じていた。
「取引か。ふん。おまえいい度胸しているな」
にやりとエマは笑った。
ミケランジェロはこの後の結末を予期して、これみよがしのため息をつく。
「わたしはエマだ。あっちのローブを着ているのが通称ミケ。で、おまえ名前は?」
「お……俺は、オレグだ!」
そのまばゆい光景は最初は鮮やかに美しく、だがすぐにただならぬことが起きていると恐怖を抱かせた。
西暦2353年2月23日、後日わずかに生き残った人類によって終末と呼称されるようになるそれはその日起きた。
核ミサイルの一斉発射の皮切りはインドだったと言われている。
それに続くようにパキスタン、中国、ロシア、イスラエル等の国からもミサイルが発射され、その数は百をゆうに超える。
標的のうちの一国であった米国の首都は真夜中だった。
予兆もなく起きた想定外の危機に対処が間に合わず都市は壊滅し、国としての機能を一瞬で失った。
他国の大都市も同様だったという。
それはミサイルを放った当事国さえも免れなかった。
多くの命は一瞬で失われ、同時に放射能汚染は広がり、オゾン層は破壊され、電磁波の嵐が吹き荒れた。
社会機能は麻痺し、巻き上がった粉塵により厚い雲が地球を長期間覆うこととなる。
それは明けない冬の始まりだった。
核の直撃を受けることなく辛うじて命を繋ぐ生物たちも、その長い冬によって徐々に命を手放していく。
植物は芽をだすことなく枯れ、糧を失った昆虫や草食動物も大量に死に、それらを食料としていた肉食動物もまた死に絶えた。
地球は壊滅的な打撃を蒙り、人類だけではなく多くの生物が命を落とす。
だが、そんななか生物に代わり台頭する存在が現れる。
それは人工知能を有した機械だった。
数を減らしそれでもどうにか生き延びていた人類だったが、その多くはさらに機械によって殺されることとなる。
機械は人間を見つけると容赦なくその生命を奪っていった。
そして、いつしか地上には機械による国が築かれる。
それから約百五十年後。
人類は百五十年前に起きた災厄を終末と呼び、だが実際にそこでなにが起きたかをはっきりと把握するものは最早いなかった。
ただわかっているのは現在世界を支配するのは機械で、機械に見つかれば殺されてしまうということだけだ。
しかし、大幅に数を減らし、その生活水準を大きく後退させてもなお、機械に見つからないよう散り散りに隠れるように暮らし、まだどうにかその種を繋いでいた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説



【完結】竜人が番と出会ったのに、誰も幸せにならなかった
凛蓮月
恋愛
【感想をお寄せ頂きありがとうございました(*^^*)】
竜人のスオウと、酒場の看板娘のリーゼは仲睦まじい恋人同士だった。
竜人には一生かけて出会えるか分からないとされる番がいるが、二人は番では無かった。
だがそんな事関係無いくらいに誰から見ても愛し合う二人だったのだ。
──ある日、スオウに番が現れるまでは。
全8話。
※他サイトで同時公開しています。
※カクヨム版より若干加筆修正し、ラストを変更しています。
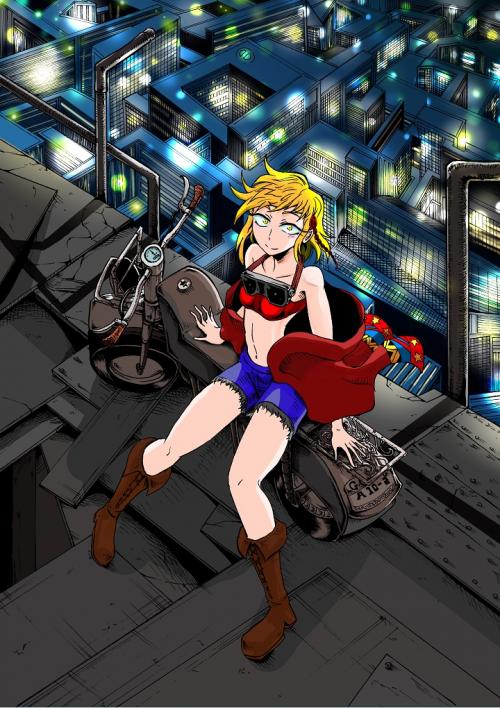


ルーインド東京
SHUNJU
SF
2025年(令和7年)
東京オリンピックの開催から4年。
日本は疫病流行の完全終息を経て、今まで通りの日常へと戻っていった。
巣鴨に住むごく一般的な女子中学生、平井 遥は
ゴールデンウィークに家族みんなで大阪万博へ行く計画を立てていたが、
しかし、その前日に東京でM8.8の大規模な巨大地震が発生した。
首都機能存亡の危機に、彼女達は無事に生きられるのか・・・?
東京で大震災が発生し、首都機能が停止したら
どうなってしまうのかを知っていただくための震災シミュレーション小説。
※本作品は関東地方での巨大地震や首都機能麻痺を想定し、
膨大なリサーチと検証に基づいて制作された小説です。
尚、この物語はフィクションです。
実在の人物、団体、出来事等とは一切関係ありません。
※本作は複数の小説投稿サイトとの同時掲載となりますが、
当サイトの制限により、一部文章やセリフが他サイトと多少異なる場合があります。
©2021 SHUNJUPROJECT


だいたい全部、聖女のせい。
荒瀬ヤヒロ
恋愛
「どうして、こんなことに……」
異世界よりやってきた聖女と出会い、王太子は変わってしまった。
いや、王太子の側近の令息達まで、変わってしまったのだ。
すでに彼らには、婚約者である令嬢達の声も届かない。
これはとある王国に降り立った聖女との出会いで見る影もなく変わってしまった男達に苦しめられる少女達の、嘆きの物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















