12 / 21
第十一章 双葉の記憶 ―― 対杉戸商業戦・その3 ――
しおりを挟む
1
「シャクのいう通り! こっち戻ってくんなよ、ピヴォのくせに!」
九頭柚葉は、新堂良子の言葉に乗っかってまた高木双葉へとプレッシャーをかけた。
やかましい! ごたごたうるさいわ!
双葉は心の中で怒鳴りながら、ボールを踏み付け、3番と向かい合った。
一瞬の躊躇の後、勝負してやろうとボールをちょんと蹴るが、すっと伸びてきた3番の足につまずいて転びそうになった。
咄嗟に右足を前に出して身体を支えたが、既に彼女の足元にボールはなかった。
3番に奪われていたのだ。
「だからあ、躊躇ってっから取られるんだよ、分かってんのかよこのタコ焼き屋あ! ここはお前の訓練の場じゃあないんだよ、ちったあ真面目にやれよ! 能無し!」
柚葉の罵声。
「やっとるわ!」
くそう、あのアホ女め。
なんでうちにだけきつく当たってくるんや。
あったまくるわ、ほんまに。
別にヘマしてんのは、うちだけやないやろ。そら、確かにうちが一番酷いかも知れへんけど。
まあ仲が悪いんやしボロカスゆうてくるんも当然か。顔に本気でボールをぶつけ合うたこともあるしなあ。
双葉はボールを追い掛けて走り回りながら、そんなことを考えていた。正確には、考えたくもないのに勝手に愚痴の言葉が脳裏に浮かんでいた。
練習やないんや。
ええとこ褒めろや。
自信なくすことばかり、それでどうなるんや。
ユズ公め。
九頭柚葉が上げる怒声の酷さしつこさに、双葉はすっかり辟易していた。
一番技術レベルの低いはずの新堂良子が頑張って実力の何倍もの力を発揮してそこそこの活躍を見せたと思った矢先に負傷交代、双葉が入った。
だから良子以上にガッツを見せて頑張らなければならないし、基本能力の差を考えれば良子以上に活躍することが期待されるということ、誰にいわれるまでもなく分かっている。
しかし、歯車が回り出してきたか杉戸商業の守備がやたらと硬く、前へボールを運ぶことがなかなか容易ではない状態になっていたのだ。
守備の堅さだけではない。
速攻もなかなか鋭く、そういった意味でも双葉は攻めることに躊躇してしまっていたのだ。
ピヴォなのだから多少はリスクを冒して攻め上がっても問題ないはずであるが、さすがはチームワークの杉戸商業というべきかポジショニングがなかなかにいやらしく、変な奪われ方をするとあっという間にボールをゴール前まで運ばれてしまう。
だから闇雲に仕掛ければ良いというものではないというのが双葉の考えであり、だから何故自分だけが怒鳴られるのかが理解出来ない。
理解出来ない以上は、ただ怒鳴りやすい相手だから怒鳴っているのだろう、嫌いだから怒鳴っているのだろう、としか思えない。
くそユズに理解されなかろうとやるしかない。
攻撃には躊躇やミスは許されても、守備でそれをやったら失点だ。相手のパスワークに上手く対応出来るようになるまで、自分が前目からの守備で頑張るしかない。
双葉はそう信じ、正確には信じ込もうとし、走り回り、前線から堅実に守備を続けた。
そして、ついに攻撃のチャンスを掴んだ。相手のパスを予測して軌道へと入り込み、ボールを奪い取ったのだ。
「よし、行けえ!」
最後方から柚葉の叫び声。
だが、杉戸商業のチームワークによる守備は絶妙で、あっという間にパスの出しどころを塞がれてしまった。
双葉は次の行動に迷っているうちにボールを奪われそうになり、再びフォローに下がってきた鈍台洋子へと慌てて横パスを出してとりあえずの難をしのいだ。
「だーかーらー、それじゃあいつまでも押し上げられないだろっての! ドンちゃん、いちいち戻んなくていいよ! 助けなくていい」
という柚葉の身勝手な怒鳴り声に、双葉のフラストレーションは限界を超えようとしていた。
どん、と床を踏み鳴らした。
「いつか殺したる……」
ぼそり呟いた。
ったく、むかつくわ。
人の気も知らんで。
そりゃあ前が点を取ってくれれば後ろは楽やろ。
当たり前や。
うちに留美のような実力があれば、どんどん仕掛けたるわい。いくらだって点を取ってやるわい。
自身の能力や周囲の現状を冷静に判断して、精一杯やっとるだけや。きっとテバもドンもおんなじや。ただ後先を考えとるだけや。
リードされているわけやないのに、無茶してどうすんねん。
いちいち文句いうな。
ほんならお前が点を取れ!
などと荒れまくる双葉の心の声など聞こえるはずもなく、柚葉の罵声は続く。
「タコ! ボケ! 仕掛けろ! ビビってんな!」
ただでさえこの程度。もし双葉の心の声が聞こえていたとしたら、反撃の反撃でもっと凄まじい罵詈雑言が返っていたかも知れない。
「誰もビビっとらへんわ! 勝手に決めつけんな! テバ、こっちや!」
双葉は前へと走りながら、反対サイドにいる茨崎悠希にボールを要求した。
それに気がついた6番が、すかさず悠希に密着し、身動きを封じた。
仮に悠希が強引に前へ出そうとしたところで、鈍台洋子のマークについている7番に簡単に奪われてしまうだろう。
杉戸商業のポジショニングは実に絶妙であった。一か八かのパスを出さざるを得ない状態へと追い込んで、楽々と奪ってしまうのだから。
「テバちゃん!」
洋子の声だ。
7番との駆け引きを制して、上手にマークをかい潜っていた。
茨崎悠希は6番をかわして、洋子へとボールを送った。いや、伸びた足に邪魔をされボールは真上へと高く跳ねた。
悠希は見上げながら、素早く落下地点真下に入り込んだ。
6番に密着されまいと腕を使って押し退け、ヘディングで上手に落とした。
洋子が拾い、右サイドにいる双葉へとパス。
ちょっと強く飛んでしまったが、ラインを割る直前に双葉はなんとか追いついて、甲で受けて落とし、足裏で踏んで止めた。
既に5番、杉戸商業主将の勝山優梨が斜め前から猛然と走り込んできていた。
「見とれや、くそユズ!」
双葉は怒鳴り声を張り上げると、軽く腰を落として勝山優梨と向かい合った。
ころり、と左へとボールを転がすと、一気に加速した。
ボールを奪おうと伸ばす相手の足に突っ掛かって転びそうになったがなんとか踏ん張り、ボールに追いついた。
ドリブルでボールを運び、斜めから杉戸商業ゴールへ。
ゴレイロが腰を落として構えている。
その前にはフィクソもいる。洋子のマークから外れて、ゴール前をゴレイロと共に固めている。
正面から突っ込むことも出来ず、シュートを狙おうにも角度のない状態へと追いやられてしまったが、それでも双葉は強引にシュートを狙うべく、大きく蹴り足を振り上げて、振り下ろした。
身構えるゴレイロとフィクソであるが、だが双葉の足からシュートは放たれなかった。
打つ振りをしただけで、斜め後ろにいる鈍台洋子へ戻すようにパスを出したのである。
ゴールを固める二人の乱れを誘いタイミングをずらすことに成功し、後は決めるだけであった。
だがしかし、いきなりそのようなパスを受けても実戦経験がないに等しい洋子にはどうしていいのか分からなかったようで、動けず呆っとしてしまっていた。
それを感じ取ったフィクソが、一気に洋子へと間合いを詰めた。
だがフィクソは、突っ立っている洋子からボールを奪うことは出来なかった。
二人の間を、双葉がボールを拾いながら駆け抜けたのだ。
至近距離のゴール前にゴレイロ一人。
双葉は足を止めてくるりゴールへと身体を向けた瞬間、思い切り右足を振った。爪先をボールに叩きつけた。
決定的であったが、ゴレイロが咄嗟に手を伸ばして跳ね上げた。
落下するボールをゴレイロが抱えるようにキャッチしようとしたところへ、鈍台洋子が頭から突っ込んだ。
ゴールネットが揺れた。
鈍台洋子が、ゴレイロごと、自らの身体ごと、ボールを押し込んだのだ。
しかしというべきか当然というべきか、ゴールは認められなかった。審判が笛を鳴らし、鈍台洋子のファールを取ったのである。
佐原南のベンチからは一斉に落胆の声が上がった。
2
「いまの攻撃、気持ちよかったね」
落胆を作り出した本人である鈍台洋子は、まったく気にするふうもなく本当に気持ちよさそうに笑った。
「タコ焼き屋、悪くなかった! ドンちゃんも、残念だったけどでもナイスファイト! これで分かったかタコ焼き屋! おどおどしてるだけの奴にチャンスなんか生まれないんだよ!」
反対側ゴール前から、佐原南ゴレイロの大声が聞こえてきた。
「分かっとるわ! うちは単に状況を冷静に考えてるだけや!」
鬱陶しいその声を掻き消してやろうと、高木双葉は怒鳴った。
新堂良子が先ほど必死に訴えていたリスク管理、それを徹底していただけだ。妙な色気出して失点したら元も子もない。今のは、行けると思ったから行った、ただそれだけだ。
別にあいつにいわれたからではない。
それよりも、こうして決定的なチャンスを作ったんだから少しは褒めろ。
ボケ。
アホ。
カス。
などと心で文句をいいながらも、なんだか不思議な気持ちが湧き上がってくるのを感じていた。
柚葉の言葉は、悔しいけれど間違っていなかった。
あまりにボロカスにいってくるものだからムカついて仕方なかったけれど、でも、間違ってはいなかった。
確かに相手を過剰に恐れ過ぎていた。
今、挑戦してみせたことで、自分にもやれるんだという自信を持つことが出来た。
まだ不安は多分にあるものの、でも、その自信がなんだかくすぐったく、心地よかった。
だが、湧き上がる不思議な感覚というのは、そのことではなかった。
なんだか先ほどから……
なんだろうか。
懐かしいのだ。
でも、一体なにが懐かしいのか、皆目見当がつかないのだ。
悪いイメージか良いイメージか、どちらなのかといわれれば良いイメージのある感覚なのだが、それがなんなのか思い出せない。
気持ち悪かった。
なんだろう、この感覚。
九頭柚葉の顔をふと遠目に見た瞬間、すうっと疑問が晴れていた。
ただしそれは、新たな疑問が生じるきっかけでもあった。
「仕掛けろ、ビビってんな!」など、先ほどから柚葉が投げ掛けていた罵倒の言葉、随分と前にも掛けられた記憶があったのだ。
うちは、あいつと以前に会うている?
まさか。
仮にそうやとしても、いつ?
どこで?
あ……
もしかしたら。
「まさか、あの時の!」
双葉の感じていたもやもやは、一瞬にして弾け飛んでいた。
ため息だか乾いた呼気だかを吐くと、改めて遥か後方のゴール前にいる佐原南のゴレイロへと目を向けるのだった。
3
確か、雲一つないからりと晴れた日だったと記憶している。
季節は春。
小学一年生になったばかりの高木双葉は、自宅から歩いて十分ほどのところにある児童公園で、フットサル用のボールを蹴って練習をしていた。
三号球のためサッカーボールどころかフットサル一般球よりも小さく、誰もが子供用サッカーボールと思うかも知れないが、れっきとしたフットサル仕様の低反発ボールだ。
兄と従兄弟以外とは一緒にボールを蹴ったことがなく、したがって試合などもまったく経験がない。それなのにフットサルボールを蹴ることにこだわっているのは、母親の影響だ。
母親である高木梨乃は、現在フットサルの名門として有名な佐原南高校女子フットサル部の、その名門たる礎を築いた人間である。
それのみならず、一度きりではあるもののフットサル女子日本代表に選出されたこともあるのだ。
双葉はまだ六年間という短い人生しか送っていないが、心から尊敬する人物が三人いる。そのうちの一人が自分の母親、高木梨乃なのである。
話は横道にそれるが、尊敬する一人は遠藤裕子という名で、母親の高校時代の後輩だ。
いまでもよく双葉の自宅に母親を訪ねて来ては、日本酒の講釈をたれて帰っていく。酒がとにかく大好きなのだが、双葉には酔っていない時の方がよっぽど面白い。
好きが高じて日本酒ソムリエを業にしており、雑誌や新聞にコラムを連載したりラジオやテレビに出演したこともあるらしい。
双葉が何故彼女のことを尊敬しているのかというと、別に酒好きで面白いからではない。
高校の大会で酷い怪我を負っている身で出場して、自分の足を犠牲にして部を初優勝へと導いたからだ。
骨も靭帯も完全に壊れて、まともに歩くことの出来ない身体になってしまったのだが、運命や他人、自分、誰を恨むこともなく、いつも笑顔を絶やさずバカみたいなことばかりいっている。
とってもカッコイイ生き方だと、双葉は心から思う。
それほどの怪我をしていたら、自分なんか痛みに泣いてしまって身動き一つ取れなくなってしまうだろうけど、彼女のような自分を信じて突き進むような生き方を少しでも真似出来たならいいなと思う。
尊敬する人物の残り一人は、佐治ケ江優である。
いわずと知れたフットサル女子日本代表の代名詞とも呼べる存在であり、フットサルに携わる女子ならば知らない者はおらず、したがって尊敬していてもなんら不思議なことではないだろう。
なお佐治ケ江優もまた、母親の高校時代の後輩だ。
人生で心から尊敬する三人といっても一人は自分の母親で残りはその後輩であり、なんとも狭い世間のようにも感じるが、みながみなテレビの仕事をしていたり、日本を代表するアスリートであったりするわけで、改めて狭いか広いかを問われれば返答に困るところであろう。
さて、話を戻そう。
双葉は最近、いつも一人で練習をしている。
以前は兄や、すぐ近所に住む従兄弟とよく一緒に蹴っていた。
差をつけようと一人で隠れて練習しているうちに、兄も従兄弟もいつしか野球にのめり込むようになってしまい、隠れるまでもなく一人で練習するしかなくなってしまったのである。
友達はいるものの、みな女の子らしく人形遊びなどを好むような子ばかりで、公園で一緒に泥まみれになってボールを追ってくれるような子は一人もいなかったし。
足裏でボールを引いては爪先で浮かせて宙にあるうちに蹴り、あらかじめ置いた小石と小石の間を通す。そんな練習を二十回ほど行うと、今度は小石をたくさん一列に置いて、その間をドリブルでジグザグに進んだ。
と、タッチミスでボールが足元から離れて、ころりころりと転がった。
小走りで寄って、スタート地点へと蹴って戻すとまたドリブルを開始した。
今度はいい調子だぞ、と思ったものの、あと小石三つというところでまたタッチミスが出て、ボールがころり転がっていってしまった。
「下手くそ」
背後から声が聞こえ、双葉は振り向いた。
公園の入口に男の子が三人、ガードパイプの間を縫って敷地に入ってきた。
背が高いのと、小太りのと、ガリガリで弱そうなのと、まるで漫画のような三人組だ。
弱そうといっても、みな双葉より遥かに大きく、ずっと強いだろう。おそらくは小学校上級生だ。
いきなりそのようなことをいわれ、他人との接触の苦手な双葉はどのような反応をすればいいのか分からずに突っ立っていた。
すると、背の高い男の子がまた、
「下手くそ」
同じことをいってきた。
「……下手だから……練習してるんだよ」
意地の悪そうな笑みに、なんか嫌だなと思いながらも、二度も声を掛けられて無視するわけにもいかず、ボールを屈み拾いながらそう応えた。
練習再開をしたものの、三人にじーっと見られていてはどうにもやりにくく、だからといって追い払うわけにもいかず、居心地悪そうにちょこちょことボールを撫でるように蹴ることしか出来なかった。
だがそれすらも蹴り損じて、明後日の方向へ転がしてしまう。それを見て、三人は大きな声で笑った。
「そんな下手なんじゃあ、練習なんかしたって意味ねえよな。そんなボールなんか持ってたって、意味ねえよな」
また、背の高い男の子が意地の悪そうな笑みを浮かべた。
「だから……下手だから、練習してるんだって」
いまのはそっちがじーっと見ているから失敗したんだ。本当はそう思ったのだが、正直にいうことも出来なかった。
早くどこかいって欲しいなあ。
困っちゃうなあ。
などと胸の中でもじもじとし、もごもごと呟きながら、撫でるようにボールを蹴り続ける双葉であったが、三人は公園から立ち去ることもしなければ、自分たちだけでの遊びを始めることもせず、ただ楽しそうな表情で双葉を見ているだけだった。
からかわれているみたいで嫌だったけれど、だからといって自分からこの場を去るのもなんだか癪で、いつまでも一人でボールを撫で続けていた。
「おいお前、勝負しようぜ」
唐突にそんな言葉を掛けられ、びくりと肩を震わせた。
4
「勝負……って」
双葉は俯き加減に、おずおずとした表情を男の子たちに向けた。
「勝負は勝負だよ。で、お前が負けたら、そのボールはおれたちがもらう」
背の高い男の子は、双葉の足元にある三号球を指差した。
「え? え?」
なにをいっているのか日本語としては理解出来たが、そのような身勝手な理屈をこうして聞くなどと覚悟しておらず、双葉はすっかり狼狽していた。
「えじゃないよ。勝ったんなら、当然の権利だろ。もしおれたちの方が負けたんなら、ボールもらうのやめといてやるよ」
なんなんだ、その条件は。
あまりにも酷すぎる。
ただでさえ相手が上級生で、なおかつ男子だというのに……
と、そんな双葉の表情に男の子は気づいたのか、次のように続けた。
「別にズルくはないぞ。おれさあ、野球やってて足だって速いけど、サッカーボールを蹴ったことなんてほとんどないんだから」
男の子は自らの正当性を主張するが、双葉が納得出来るはずもなかった。
勝負なんかしたくもないのに、一方的に損失が出るだけの不合理な条件を押し付けられているのだから当然だ。
「それで充分にハンデになるだろ。やんないんだったらいいよ。不戦勝で、そのサッカーボールはおれたちの戦利品とする」
フセンショウとかセンリヒンとか、難しい言葉は双葉にはさっぱり分からなかったが、現在どうしようもない状況に自分が陥っていることは理解出来た。
勝負に勝たないと、母に買ってもらった大切なフットサルボールをこのようなサッカーボールとの区別もつかないような連中に奪われてしまうのだ。
他の物ならいいけど(もちろん物によるが)、このフットサルボールだけは絶対に渡したくない。
仕事で忙しい母と、自分とを繋ぐ宝物なんだから。
「分かった」
双葉は唇を小さく震わせるように動かした。
こうして双葉は、生まれて初めて身内以外とフットサルボールを蹴ることになったのである。
残念ながらそれは楽しい気分のものではなく、むしろ正反対といえるものであったが、でもこの戦いを受けなければ母親から買ってもらったボールを守れない。不本意ではあるが、やるしかなかった。
勝負の内容は一対一でボールを奪い合い、お互いのゴールへとシュートを打ち、時間内により多く決めた方が勝ちというものだ。
靴で地面を引っ掻いて作った、数メートル四方の少しいびつな長方形がコートだ。
その中央に、背の高い男の子と双葉は立ち、ボールを挟んで向かい合った。
男の子は楽しそうににやにやと笑みを浮かべている。
双葉はその視線を受けて畏縮しそうになりながらも、なんとか己の心を奮いたたせて顔を上げ、その場に踏み止まっていた。
残る二人の男の子が、それぞれ長方形の短辺側に大きく足を開いて立った。この足の間にボールを通せばゴールというわけだ。
「そんじゃいくぞ、試合開始。ピーッ!」
男の子がボールを蹴った。
フェイントもなにもなく、ただドリブルで双葉の脇を抜けようとする。
そんな単純な行動に対して、双葉は対応することが出来なかった。呆然としたような表情で、立っていた。
はっとしたように目を見開くと、後ろを振り向いて男の子の背中を追い掛けた。
負けたら母親から買ってもらったボールを奪われてしまう。
その危機感に、双葉は恐怖と戦いながら必死に走った。
男の子は先ほど自分でもいっていた通りサッカーは上手でないらしく、シュートを狙おうとしてボールタッチにもたついた。
その間に、双葉はなんとか正面に回り込んでシュートを阻止した。
ちょんと出した爪先でボールを引っ張って奪い取ると、敵陣へ向けてドリブル開始。
と、その瞬間に双葉の身体は真横になぎ倒されるように崩れていた。後ろから襟首を掴まれて、引っ張られたのだ。
明らかな反則だ。
でも、男の子はセルフジャッジでプレーを止めることもなく、双葉の足元にあるボールを奪おうとした。
双葉は倒れながらもなんとかそのボールを大きく蹴り、ラインの外へ出して難を逃れた。
立ち上がると、男の子をちらりと見た。
「なあんだよ、その顔は?」
男の子が、批難するような言葉で凄み、威嚇してきた。
その顔は、などといわれても、双葉には自分がどんな顔をしているのか分からなかった。
この不条理さに対する不満が、知らず表情に出てしまっているのだろうか。
でも、決してその不満を口に出すことはなかった。なにをされるのか怖くて、意志を主張することなどとても出来なかったのである。
勝負に勝てばボールを守れる。ならばその勝負を、ただ黙々とやるしかなかった。
いくら不利な条件であろうとも。
不利であればこそ、勝負に対しては気をしっかり強く持たなければならないのだろうが、双葉は元来気弱で温厚な性格であり、なおかつ他人との接触経験がほとんどない。先ほど襟首を掴まれ引き倒されたことで、すっかりと怖じけづいてしまっていた。
なんとか失点だけは避けようと頑張るものの、反撃を躊躇して向かい合っているうちに奪われて必死に戻り、大きく蹴り出して逃げる。と、その繰り返しになっていた。
男の子は、先ほどのような暴力で簡単に得点してしまうことだって出来るだろうに、何故そうしないのか。
からかっているのだろうか。
勝負を面白くしようとしているのだろうか。
双葉は、必死に守りながらそんなことを考えていた。
それならそれで、相手が余裕を見せている間に、こっちこそ奪ったボールで一気にゴールを狙えばいい。
でも……
どうせまた後ろから首を掴まれたり、蹴られたりして転ばされてしまうんだ。ただ痛い思いをするだけなんだ。
だからって、点を取らないと勝てない。
負けたらボールが……お母さんから買ってもらったボールが……
双葉は、すっかりと泣きそうな表情になっていた。
「奪ってみろよお」
男の子はボールを足の裏でころころ転がしながら、楽しそうな笑みを浮かべ挑発した。
双葉と男の子は、またボールを挟んで向き合った。
一体、何度目の対峙の時であっただろうか。どこからか、大きな声が聞こえてきたのである。
「仕掛けろ! ビビってんな!」
幼い、女の子の声であった。
その声に突き動かされるように、双葉は男の子の隙をついてボールを奪い、横を駆け抜けていた。
男の子の手が襟首を掴もうと伸びてきたが、双葉は無意識に、すっとしゃがむようにかわしていた。
双葉は、男の子がバランスを崩している間に小さくドリブルでボールを前へ運び、シュートを打った。
ボールは、小太りの子の足の間を転がり抜けた。
ゴール。
ついに双葉が得点、先制である。
息を切らせ肩を上下させながら、双葉は呆然と突っ立っていた。
やがて、自覚が芽生えたのか拳を握り、小さく口を開いた。
「やった……」
不安に押し潰されそうであった双葉の表情に、じんわりと笑みが広がっていった。
安堵? 自信?
自分の内部にゆっくりと花開くように広がるその感情、笑みの正体、自分のことであるというのに双葉にはまったく分からなかった。
「ほおら、やりゃ出来んじゃん」
また、どこからか女の子の声が聞こえてきた。
男の子たち、そして双葉は辺りをきょろきょろと見回すが誰一人として姿など見えなかった。
隣の民家の塀の上を、太った猫が歩いているくらいだ。
まさか猫の声とも思えないし。
「あー、あそこ!」
小太りの男の子が、公園内に生えているブナの木の上の方を指差した。
高さ四メートルはあるだろうか。木の枝の上、葉っぱをベッドに幼い女の子が横になっていたのである。
5
「あ、ばれた?」
女の子は歯を見せて笑うと、上体を起こして枝に座り、お尻を前へずらすようにして木から飛び降りた。素早く両手を上げて自分のいた枝を掴みしならせて、低いところの枝に飛び移り、ぐにゃりふわりと地面に着地した。
ようやくその顔がはっきり見えた。
幼いといっても双葉より一回りは大きいが、顔立ちからすると同じくらいの年齢だろう。
長い髪の毛を、後ろで束ねている。
いつも男の子のような遊びでもしているのか、服は泥だらけで、腕も、ショートパンツからすらりと伸びた足も擦り傷だらけだ。
女の子は双葉へと歩み寄った。
「負けたらボールを取られちゃうんだろ? でも相手、下手だからさ、ビビんなきゃ余裕で勝てるって。ほら、続き続きっ!」
女の子は笑いながら、双葉のお尻を両手でぺしぺしぺしぺしと叩いた。
「なんだよお前、余計なこといってんじゃねえよ! くそっ、絶対に逆転すっからな!」
背の高い男の子は険しい顔で怒鳴り声を上げると、ボールをコート中央に置くなり合図もなしにドリブルを開始した。
これまではこいつが困るのを楽しむために手加減をしていただけだ。
男の子はそう思っていたのかも知れない。
確かに運動神経はよさそうであるし、年齢、体格や性別といった差を考えればそのような自信を持ってもなんら不思議ではないだろう。
いくら自分がサッカー素人で、相手が少しばかりの経験があろうとも、それを補って遥かに余るものが自分にはあるのだ、と。
しかし現実はそうはいかなかった。
勇気を振り絞って仕掛け、結果を出したことで自信を得つつある幼い少女から、簡単にボールを奪うことが出来なくなっていた。
幼い少女、高木双葉はくるり反転して男の子をかわすと、一気にゴール前へと向かい、二本目のシュートを放った。
狙いは完璧であった。
しかし、決まらなかった。
ゴール代わりに立っている小太りの男の子が、すっと身を真横に動かしてボールの軌道から逃げたのだ。
ずるい……
と思う双葉であるが、言葉には出来ず喉元に飲み込んだだけであった。
「汚ねえぞ!」
代弁するかのように、女の子が怒鳴り声を上げた。
「ハンデハンデ。だってお前、サッカーやってんだろ? ケンジはやってないんだから」
小太りの男の子は、にっと笑った。
確かにボールを蹴る経験だけを考えればその通りかも知れない。
でも、こちらはやりたくもないことを無理矢理やらされているわけで、それにもともとの運動神経とか、男子と女子との違いとか、双葉にはどう考えてもずるいとしか思えなかった。
同時に、なんだか自分が恥ずかしく惨めな気持ちになっていた。
突然現れた(最初からそこにいたのだが)名も知らない女の子は、この件に関しては赤の他人だというのに、男の子たちの理不尽さに憤慨して戦ってくれている。だというのに、自分は……
もっと強くなりたい。
強い心が欲しい。
負けようとも挑めるような、勇気が欲しい。
双葉は、六年間の人生の中でこの時ほど真剣に強くなりたいと思ったことはなかった。
「おい彼女、勝とうぜ絶対! そう、そこ! かわせ! いけえ!」
女の子が、大きな声で双葉を応援する。
双葉も、弱気になりそうになる中で精一杯頑張ったが、またしてもハンデが出て、同点に追い付かれてしまった。男の子、ケンジが打ったシュート自体は思い切り狙いが外れたのだが、ゴール代わりの男の子が大股で真横へ移動し、自らボールを招き入れたのである。
「やったあ」
男の子たちは、手を打ち合い、喜んでいる。
「なんだこれ、ふざけんな! ただのいじめじゃねえか!」
女の子が地を踏み鳴らし、怒鳴った。
「はあ? なにいってんだ、お前。木の上でずっと見てたんだろ? これは立派な勝負だよ。『分かった』、ってこいつは承諾して勝負を始めてるんだから、ちゃんと成立してんだよ」
背の高い男の子、ケンジは恥ずかしい気持ちなど微塵も感じられない実にすっきりとした顔で、自分だけの理論を展開した。詭弁にすらなっていない理論であるが、民主的に正しいことであるかどうかなど、彼にとってどうでもいいのだろう。
「よし、いつまでやっててもきりがないから、次にシュート決めた方が勝ちだ!」
ケンジは、自信満々に笑った。
自信があるのは当然であろう。絶対的ともいえるハンデを考えれば。
双葉は唇をきゅっと噛み締めた。
悔しかった。
理不尽さをしっかりと突っぱねずに、こんなことに付き合ってしまっている、弱い自分が。
強くなりたい。
もっと、強い心を持ちたい。
そんな気持ちが、無意識に背中を押したのだろうか。
もしくはボールを奪われたくないという思いからなのか、それとも見ず知らずの女の子が現れて自分を応援してくれることに勇気をもらえたということなのか。
自分でも分からない。
分からないが、双葉の身体は自然に動いていた。
一瞬の隙をついてケンジからボールを奪うと、ゴールへ。
「よし、いけえ!」
女の子が腕を振り上げ、叫んだ。
「させねえよ」
小太りの男の子ががっちりと足を閉じてゴールを塞いだ。
だが双葉は必死の形相で、その隙間にボールをねじ込んでいた。
一瞬足を引いて、さらに爪先で蹴った。
とと、とよろけて倒れそうになる男の子の足の間を、ついにボールが突き抜けた。
双葉の得点だ。
「やったぜ!」
女の子が叫び、指をパチンと鳴らした。
こうして、男の子たちは自分で勝手に作ったばかりのルールによって自滅したのである。
ふう、と安堵の息を漏らした双葉は、自分のことのように跳びはね喜んでいる女の子を見て、柔らかな笑みを浮かべた。
その瞬間であった。
双葉は頭部にガツンと衝撃を受け、横へ吹っ飛ばされていた。
ケンジの容赦ない平手打ちを顔面に受けたのである。
年齢や男女の違いからの体格差に、双葉の身体はひとたまりもなかった。
「てめえ、生意気なんだよ! 女のくせに!」
地面に倒れている双葉は、脇腹を思い切り蹴飛ばされて激痛に悲鳴を上げた。
「やめろよ!」
女の子が叫びながらケンジに突進、肩で体当たりをした。
不意をつかれてケンジはぐらりよろけるが、倒れぬよう踏ん張り、女の子の胸倉を掴み引き寄せた。
「お前は関係ないだろ! 正義の味方気取ってんじゃねえよ!」
「正義の味方じゃない。いつも頑張る光り輝く女の子の味方だ!」
テレビアニメ魔法天使プリムラビーンに登場する戦士の一人、シェルミーケミーの決め台詞だ。
「フラワーハートトライアングル!」
女の子はケンジをどんと突き飛ばし逃れて距離を取ると、両手で作ったハートマークを胸の前にかざした。
ハートチャージ完了。雄叫びを上げ、腕を振り上げた。
だけどシェルミーケミーの魔法術は、魔界獣には届かなかった。
「バカじゃねーのか!」
小太りの男の子に横から顔を殴りつけられ、吹っ飛ばされていたのである。
ごろり転がったところを、胸を踏み付けられ、巨体に馬乗りになられていた。
「関係ないくせにでしゃばりやがって! 謝れよ!」
小太りの男の子は、女の子の顔面を殴りつけた。
女の子はそれでたじろぐことなく、きっと男の子を睨みつけた。
「悪いのそっちだろ!」
「弱いくせに生意気いってんじゃねえぞ」
「うるせえ! シェルミーは悪党なんかに負けねーんだ。今日は負けても明日は勝つ!」
「いま勝ってみろよ! ほら、やり返してみろよ!」
小太りの男の子は、女の子の顔を容赦なく何度も殴った。
鼻血が出ていた。
それでも、すっかり興奮状態にあった男の子たちは、女の子の顔を殴り、身体を蹴り続けた。
双葉は、涙ぐんでいた。
全身をぶるぶると震わせていた。
目の前で殴り合いの喧嘩をしているという恐怖。
自分が原因の一つであるという罪悪感。
我慢の限界に達した時、双葉は大きく口を開き、暴力を振るっている男の子たちへと走り寄っていた。
「もう、やめてください! この子、関係ないじゃないですかあ」
双葉は泣きながら、太った男の子の肩に手を掛けて女の子から引きはがそうとした。
「邪魔すんな!」
腕を掴まれ投げられ、双葉は地面に転がったが、すぐ起き上がるとまた男の子を引きはがしにかかった。
「殺すぞお前え!」
男の子たちが興奮気味に叫んだ時である、
「なにやってるの、あんたたち! 警察呼ぶよ!」
女性の怒鳴り声が、ぴしゃり雷のように空気を震わせた。
すぐ横にある家のベランダから、年取った白髪の女性が見下ろしていた。
「やべえ、逃げろ!」
ケンジとガリガリが、脱兎のごとき勢いで逃げ出した。
小太りも、女の子に馬乗りになっている体勢から慌てて立ち上がろうとするが、
「逃がすか悪党!」
女の子が左手で服の裾を強く掴み、引っ張った。
「離せよてめえ!」
と、叫び睨みつけた瞬間、女の子が、いつの間にか右手にかき集めていた砂を、その顔を目掛けてぶちまけた。
ぎゃっ、という悲鳴が上がった。
小太りは、咄嗟のことに反応出来ずに砂を浴び、それが目に入ってしまったのだ。
ごろり倒れて地面をのたうちまわっているところを蹴飛ばしやっつける。と、女の子はそのような算段でいたのかも知れないが、現実は異なっていた。
「ふざけんなあっ!」
小太りは、腕を文字通り盲滅法にぶんぶん振り回した。
そのうちの一発が女の子の顔面を捉えると、そのまま胸倉を掴み引き寄せ、拳で何度も何度も殴ったのである。
やがて女の子がぐったりして倒れてしまうと、小太りはようやく我に返ったようで、目をこすりながら仲間を追って走り出した。
こうして、ようやく三人の不良小学生は、双葉たちの前から姿を消したのだった。
6
温厚で殴り合いの喧嘩などとはやるのも見るのも無縁に生きてきた双葉は、かつて経験したことのない恐怖に全身を震わせ、すっかりと呼吸が浅く荒くなっていた。
横たわってぐったりとしている女の子の姿に気づくと、またじわりと目に涙が滲んだ。
双葉は自分を責めた。
すべては自分のせいだ。
自分に勇気がなかったからだ。
「ごめんね」
双葉は、女の子の顔を覗き込んだ。
どうやら、気を失っているようであった。
「ごめんね」
もう一度謝った。
ぽたりと落ちた涙が、女の子の頬を打った。
女の子の目が突然かっと見開かれた。
「まだ負けてねえぞ!」
跳ねるように上体を起こすと、双葉の胸倉を掴みぐいと引き寄せ自分の顔へ引き寄せた。
その迫力に恐怖し、ひっと息を飲んだ双葉の目にまた涙が滲み、つうとこぼれた。
「あ、ごめん……。あいつらかと思っちゃった。ほんとごめんね」
女の子は、双葉の襟から手を放した。
双葉は咳き込みながら、
「気にしてないから。それよりそっちこそ大丈夫なの?」
尋ねた。
「平気平気。ちょっぴり痛いけどね。そうだ、ボールはどうしたの? あいつらに取られなかった?」
その問いに、双葉は黙って頷いた。
「そう。よかったね」
女の子は歯を見せて笑った。
「よくないよ! あたしなんかのためにこんなに殴られちゃって……こっちこそ、本当にごめんなさい」
双葉は申し訳なさそうな表情で頭を下げた。
「いいってことよ。こっちの好きでやったことなんだし。しっかし、見事にのされちゃったなー、あたし。気絶なんかしたの六年間の人生で初めてだよ」
六歳、同年代だろうとは思っていたが、まったく同じだ。言葉使いが妙におとなびているため、なんだか違和感はあるが。
「空手でも習おうかなー。そしたら、あんな奴らぶっとばしてやれるのに」
なにげない発言ではあったのだろうが、双葉にはなんとも意外に感じられた。
同じような目にあって、双葉は心の強さを求めたが、この子は肉体的な強さを求めているということが。
でも、考えてみるまでもなく当然か。
だってこの子の心は、もうこれ以上はないくらいに強いのだから。でなければ、他人のために上級生の男子三人に立ち向かっていかれるはずがない。
単に恐れ知らずなだけかも知れないけれど。
双葉は、心さえ強くなれるのならば、身体の強さなどいらない。フットサルをやる上での肉体の強さは欲しいけれど、喧嘩なんか強くならなくていい。
「フットサル、好きなんだ?」
女の子の質問に、双葉は驚いた。
双葉は足で土を引っ掻いて作った数メートル四方のコートでボールの奪い合いをしただけであり、であれば通常はサッカーだと思うはずだからだ。
大人が四号球を蹴っていれば、ぴんと来る者もいるかも知れないが、双葉のボールは三号球。子供がサッカーに使うサイズでもある。
つまり女の子は、サイズによらずフットサルボールと見抜いたことになる。
「よく分かったね。フットサルのボールって」
「弾み具合や、音でね。あたしもフットサルやってっから」
「え、ほ、ほんとに?」
双葉は目を輝かせ、身を乗り出すように女の子に接近した。
母やその友達以外で、フットサルをやっている者に出会ったことなどなかったからだ。
「うん。自慢じゃないけどねえ、いやちょっと自慢かなあ、あたしのお母さんね、佐原南高校で全国大会に出て優勝したことあるんだよ。エースだったんだよ」
女の子は、どんなもんだとばかりの笑みを満面に浮かべた。
なお佐原南高校とは、この近くにある、女子フットサル部がとにかく強いことで知られている県立高校だ。
「そうなんだあ。あたしのお母さんもね、佐原南にいたんだよ。この間ね、代表にも呼ばれたんだよ」
別に自慢をしたつもりはまったくない。
世界で尊敬する三人のうちの一人の話であるだけに、普通に話しているだけでも自慢っぽく思われるかも知れないが。
「ほんとそれえ? うわああああ、負けたあああ! くそおおお、悔しいなあ。お母さん、なんて名前なの?」
「高木梨乃」
双葉は答えた。
「聞いたことないなあ。あとでお母さんに聞いてみよっと」
「そっちのお母さんの名前は?」
「代表じゃあなかったし、高校出てフットサルやめちゃったから知らないと思うよ。……九頭葉月、聞いたことないでしょ」
「うーん。ごめんね。あたしも、お母さんに聞いてみるよ」
「もし同じくらいの歳だったら、お母さん同士二人で試合に出てたりしたかも知れないもんね。……あたしたちも、いつか佐原南で一緒にフットサルをやったりしてね。そうなったら、よろしくね」
女の子は、照れたような笑みを浮かべて手を差し出してきた。
「こちらこそ、よろしくね」
双葉は、ちょっと身体をもじもじとさせながらも手を伸ばした。
二人は小さく柔らかなお互いの手を、がっちりと握り合った。
「じゃ、あたしもう行くね! バイバイ!」
女の子はくるり踵を返すと、走り出した。
双葉は呆気にとられて、その後ろ姿を無言で見つめていた。
「なんだったんだろ」
などと一人ぼそりと口を開いたのは、どれほどの時が流れた後であったか。
そういえば、名前も知らないままだった。
母親の名前を教え合ったのみで。
クズ……なんだっけ。難しい響きだったものだから、もう忘れてしまった。なんだかとてもかっこいい名前だった気がする。
でも別に、名前など知る必要はないだろう。
これからフットサルをやっていく上で、あの子にたくさんの元気や勇気をもらったことに違いはないのだし、それに、もう会うこともないだろうからだ。
7
などと考えたのは、完全に双葉の予想違いであった。
そもそも別に根拠があってそう思ったわけではなく、公園に一人残ってただ風に吹かれていたら、なんとなくそんな気持ちになったというだけなのだ。
一体なんの話であるのか分からないだろうから説明をすると、要するにあの後も女の子はちょくちょくと公園にやって来ていたのである。
そして、二人は一緒にボールを蹴って練習するような仲になっていたのである。
再会時に、またもや名前を聞く機会を逃してしまって、お互いに知ることのないまま。
二人きりであるため、ねえでもおいでも呼び掛けとしては問題なく成立するわけで、名前など知らなくても特に不便はなかったから。
特に待ち合わせの約束をするでもなく、どちらからともなくふらり公園に現れて、はしゃぎながらボールを追い掛け、合間合間の休息時間には木陰のベンチで肩を寄せ合って色々な話をした。
なんでもこの子には幼なじみの友達がおり、一緒に空手を習うことにしたそうである。
初めて会った時に男の子と喧嘩をして思い切り叩きのめされ、空手を習いたいなどといっていたけれども、あれは本気の言葉だったのだ。
「……それじゃあ、フットサル、やめちゃうの?」
双葉は尋ねた。
「やめるわけない。まだ習ってないからよく分からないけど、空手の技をフットサルにも生かすんだよ。喧嘩には強くなるし、一石二鳥だぜ」
女の子は、手を組んで指をぽきぽき鳴らそうとしたが鳴らなかったので、ごまかすようにふふふと不敵に笑った。
「そう、なんだ」
イッセキニチョーってどういう意味だろう。
この子、たびたび難しい言葉を使うよな。親が頭いいのかなあ。それともわたしがバカなのかな。
とにかく、フットサルをやめないというのはよかった。
わたし、フットサル友達なんて全然いないからな。
一緒に蹴って、色々と勉強になるし。
幼なじみと空手を習うっていってたけど、どんな子なのかな。
会ってみたい気もするけれど、この子とおんなじくらい元気だったら、囲まれるこっちがへとへとに疲れちゃうなあ。
などと、双葉が心配するのも無理はなかった。
この女の子の個性が、あまり世間を知らずに過ごしてきた双葉にとってあまりにぶっ飛んでいたからだ。
ぶっ飛んでいるといっても、別に身勝手というわけではないし、どちらかといえば気が利く方ではある。
妥協せずきっちり主張をしたり、ぐいぐいと引っ張っていく我の強さといったところが、おとなしい性格の双葉としてはなんとも気疲れしてしまうということだ。
疲れはするけれど別に不満はなく、この子のこと自体は大好きであった。
ただ公園でボールを蹴るだけの仲だから、悪いところが見えないということかも知れないが、とにかくそのボールを蹴る技術が凄くて一緒にいてとってもためになるし、その性格も魅力的だった。
自分にないものをたくさん持っており、ただ一緒にいるだけでなんだか自分まで強くなった気がした。
小学校の学区が異なるため公園で会うことしか出来なかったが、でも三日に一回は会っていた。これまでスポーツをやる友達がいなかった双葉にとっては、濃密で最高に楽しい時間だった。
だが初めて会ってからちょうど二ヶ月を向かえた日を境に、二人が会うことはなくなった。
ある事件が起きたのである。
8
その日、あの男の子たちがまた公園にやってきたのだ。
ケンジという背の高い子と、小太りと、ガリガリ、三人の男の子が。
挑発に女の子が乗って、また殴り合いの喧嘩になってしまった。
その殴り合いであるが、男の子たちにとっては不本意以外のなにものでもない結果であったことだろう。
女の子が、習い始めの空手でなんとケンジをやっつけてしまったのだ。
小学一年生の女子が、上級生を。
しかし、上級生しかも男子をやっつけたんだなどと武勇に浸っている暇はなかった。
喧嘩なんか強くなったところで争いに際限がなくなるだけだ、という双葉の恐れていたことが起きてしまったのである。
逃げ出したケンジが、自宅から獰猛そうな大型犬を連れて戻ってきたのだ。
そして女の子を襲うように、けしかけたのである。
けしかけたはいいが、女の子には犬に食いつかれてやらねばならぬ義理はなく、木に登ったり滑り台に上ったりと素早く逃げ回った。
イラついたケンジは、標的を変えて双葉を襲わせた。
ケンジも本来ならば脅かすだけだったのかも知れない。女の子が恐怖に泣きわめいて謝ってくれれば、許してやっていたのかも知れない。
しかし、あまりのままならなさに怒りの感情の逃げ場所がなく、すっかりと我を忘れてしまっていたのだろう。
突然標的にされた双葉は目を見開いてひっと息を飲んだだけ、逃げようとしないばかりか身動き一つしなかった。恐怖に立ちすくんで、動けなかったのだ。
犬に飛び掛かられ、双葉はぎゅっと目を閉じた。
どうん、
激しくぶつかってきたのは、犬ではなくもっと柔らかな感触であった。
女の子が、双葉を庇うように前に立ち塞がって、犬の突進を真正面から受けて吹っ飛ばされたのだ。
ぶつかられて双葉は後ろへ倒れ、その瞬間、すぐ横に女の子が倒れてきた。
顔をしかめ、ぐ、と声を漏らす双葉。次の瞬間、その目が恐怖に見開かれていた。
目の前で起きている光景に、甲高い悲鳴を上げた。
双葉の眼前で、犬が女の子の右腕に食らいついていたのである。
「離せよ、てめえ!」
女の子は叫びもがくが、食らいついた犬は唸り声を上げ、首を振りながらますます獲物に歯を食い込ませた。
空手を習い始めようとも小一の女の子であり腕は木の枝のように細く、食いちぎられもがれ落ちても不思議ではなかった。
双葉はあまりの恐怖になにも出来ず、大声で泣き出してしまった。
その泣き声に、ようやくケンジもやり過ぎであることに気がついたようで、
「ジョン、やめろ!」
と制止しようとしたのであるが、女の子が左手に拾った石でジョンの顔面を殴りつけているものだから、ジョンとしても怒り狂うばかりで攻撃をやめるはずがなかった。
女の子は、足をジョンの胴体に巻きつかせてぎゅうっと全力で締め付けた。
ジョンはもがき逃れようと、女の子のお腹を両の前足でバリバリと引っ掻いた。
女の子が痛みに悲鳴を上げ、石で何度もジョンの顔を殴りつけるが、それは逃れるどころか自分自身をさらに痛めつけることに他ならなかった。
つまりは、ジョンの方こそ攻撃から必死に逃れようとして、ますます女の子の腕に食らい付き、そしてお腹に深く爪を食い込ませ引っ掻き続けたのである。
大型犬ともなれば、その爪も腕力も充分に凶器である。女の子の服の袖やお腹の部分は完全に破れて肌が見えている。肌色ではなく、血に染まり真っ赤であった。
そんな泥沼の惨状から女の子を救ったのは、ケンジでも双葉でもなく、またしても隣の民家の老婆だった。
以前の時と同じようにベランダから一喝。それによりケンジは我に返り、強引にジョンの首輪を掴み引っ張って女の子から引きはがしたのだ。
男の子たちは今度こそ本当に老婆に通報されて、警察に補導された。
引き起こしてしまった惨状を考えれば当然だろう。
なおも女の子は錯乱したように手足を振り回し怒鳴り散らしていたが、腕やお腹からは大量の血が流れており顔面は蒼白で、どう考えても元気などとはいえない状態であり、やだやだと抵抗するものの数人の大人にがっちりと抑えつけられて病院へと運ばれて行った。
残された双葉は警察の事情聴取を二時間ほど受け、解放された。
連絡を受けて駆け付けた母親、梨乃と一緒に家に帰った。
それから女の子には一度も会っていない。
女の子の方が、それきり公園に姿を見せなくなったのだ。
そのことは、双葉を落ち込ませた。
わたしを恨んでいるから? だから、来ないの?
大怪我を負わされたことを、恨んでいるから?
いや、そうじゃない。
むしろあの子の方が、責任を感じているんだ。
一緒にいると、またわたしを危ない目にあわせてしまう。そう思っているんだ。
本当は、悪いのはわたしなのに。
なのに、
あれだけの大怪我を負ったというのに、
あの子は絶対にわたしを恨んだりなんかしていない。
たった二ヶ月しか、それもこの公園でしか会わなかったから、あの子の性格をすべて理解しているわけではない。でも、それだけは自信を持っていえる。
あの子は、そういう子なんだ。
それに比べて、わたしは……
「シャクのいう通り! こっち戻ってくんなよ、ピヴォのくせに!」
九頭柚葉は、新堂良子の言葉に乗っかってまた高木双葉へとプレッシャーをかけた。
やかましい! ごたごたうるさいわ!
双葉は心の中で怒鳴りながら、ボールを踏み付け、3番と向かい合った。
一瞬の躊躇の後、勝負してやろうとボールをちょんと蹴るが、すっと伸びてきた3番の足につまずいて転びそうになった。
咄嗟に右足を前に出して身体を支えたが、既に彼女の足元にボールはなかった。
3番に奪われていたのだ。
「だからあ、躊躇ってっから取られるんだよ、分かってんのかよこのタコ焼き屋あ! ここはお前の訓練の場じゃあないんだよ、ちったあ真面目にやれよ! 能無し!」
柚葉の罵声。
「やっとるわ!」
くそう、あのアホ女め。
なんでうちにだけきつく当たってくるんや。
あったまくるわ、ほんまに。
別にヘマしてんのは、うちだけやないやろ。そら、確かにうちが一番酷いかも知れへんけど。
まあ仲が悪いんやしボロカスゆうてくるんも当然か。顔に本気でボールをぶつけ合うたこともあるしなあ。
双葉はボールを追い掛けて走り回りながら、そんなことを考えていた。正確には、考えたくもないのに勝手に愚痴の言葉が脳裏に浮かんでいた。
練習やないんや。
ええとこ褒めろや。
自信なくすことばかり、それでどうなるんや。
ユズ公め。
九頭柚葉が上げる怒声の酷さしつこさに、双葉はすっかり辟易していた。
一番技術レベルの低いはずの新堂良子が頑張って実力の何倍もの力を発揮してそこそこの活躍を見せたと思った矢先に負傷交代、双葉が入った。
だから良子以上にガッツを見せて頑張らなければならないし、基本能力の差を考えれば良子以上に活躍することが期待されるということ、誰にいわれるまでもなく分かっている。
しかし、歯車が回り出してきたか杉戸商業の守備がやたらと硬く、前へボールを運ぶことがなかなか容易ではない状態になっていたのだ。
守備の堅さだけではない。
速攻もなかなか鋭く、そういった意味でも双葉は攻めることに躊躇してしまっていたのだ。
ピヴォなのだから多少はリスクを冒して攻め上がっても問題ないはずであるが、さすがはチームワークの杉戸商業というべきかポジショニングがなかなかにいやらしく、変な奪われ方をするとあっという間にボールをゴール前まで運ばれてしまう。
だから闇雲に仕掛ければ良いというものではないというのが双葉の考えであり、だから何故自分だけが怒鳴られるのかが理解出来ない。
理解出来ない以上は、ただ怒鳴りやすい相手だから怒鳴っているのだろう、嫌いだから怒鳴っているのだろう、としか思えない。
くそユズに理解されなかろうとやるしかない。
攻撃には躊躇やミスは許されても、守備でそれをやったら失点だ。相手のパスワークに上手く対応出来るようになるまで、自分が前目からの守備で頑張るしかない。
双葉はそう信じ、正確には信じ込もうとし、走り回り、前線から堅実に守備を続けた。
そして、ついに攻撃のチャンスを掴んだ。相手のパスを予測して軌道へと入り込み、ボールを奪い取ったのだ。
「よし、行けえ!」
最後方から柚葉の叫び声。
だが、杉戸商業のチームワークによる守備は絶妙で、あっという間にパスの出しどころを塞がれてしまった。
双葉は次の行動に迷っているうちにボールを奪われそうになり、再びフォローに下がってきた鈍台洋子へと慌てて横パスを出してとりあえずの難をしのいだ。
「だーかーらー、それじゃあいつまでも押し上げられないだろっての! ドンちゃん、いちいち戻んなくていいよ! 助けなくていい」
という柚葉の身勝手な怒鳴り声に、双葉のフラストレーションは限界を超えようとしていた。
どん、と床を踏み鳴らした。
「いつか殺したる……」
ぼそり呟いた。
ったく、むかつくわ。
人の気も知らんで。
そりゃあ前が点を取ってくれれば後ろは楽やろ。
当たり前や。
うちに留美のような実力があれば、どんどん仕掛けたるわい。いくらだって点を取ってやるわい。
自身の能力や周囲の現状を冷静に判断して、精一杯やっとるだけや。きっとテバもドンもおんなじや。ただ後先を考えとるだけや。
リードされているわけやないのに、無茶してどうすんねん。
いちいち文句いうな。
ほんならお前が点を取れ!
などと荒れまくる双葉の心の声など聞こえるはずもなく、柚葉の罵声は続く。
「タコ! ボケ! 仕掛けろ! ビビってんな!」
ただでさえこの程度。もし双葉の心の声が聞こえていたとしたら、反撃の反撃でもっと凄まじい罵詈雑言が返っていたかも知れない。
「誰もビビっとらへんわ! 勝手に決めつけんな! テバ、こっちや!」
双葉は前へと走りながら、反対サイドにいる茨崎悠希にボールを要求した。
それに気がついた6番が、すかさず悠希に密着し、身動きを封じた。
仮に悠希が強引に前へ出そうとしたところで、鈍台洋子のマークについている7番に簡単に奪われてしまうだろう。
杉戸商業のポジショニングは実に絶妙であった。一か八かのパスを出さざるを得ない状態へと追い込んで、楽々と奪ってしまうのだから。
「テバちゃん!」
洋子の声だ。
7番との駆け引きを制して、上手にマークをかい潜っていた。
茨崎悠希は6番をかわして、洋子へとボールを送った。いや、伸びた足に邪魔をされボールは真上へと高く跳ねた。
悠希は見上げながら、素早く落下地点真下に入り込んだ。
6番に密着されまいと腕を使って押し退け、ヘディングで上手に落とした。
洋子が拾い、右サイドにいる双葉へとパス。
ちょっと強く飛んでしまったが、ラインを割る直前に双葉はなんとか追いついて、甲で受けて落とし、足裏で踏んで止めた。
既に5番、杉戸商業主将の勝山優梨が斜め前から猛然と走り込んできていた。
「見とれや、くそユズ!」
双葉は怒鳴り声を張り上げると、軽く腰を落として勝山優梨と向かい合った。
ころり、と左へとボールを転がすと、一気に加速した。
ボールを奪おうと伸ばす相手の足に突っ掛かって転びそうになったがなんとか踏ん張り、ボールに追いついた。
ドリブルでボールを運び、斜めから杉戸商業ゴールへ。
ゴレイロが腰を落として構えている。
その前にはフィクソもいる。洋子のマークから外れて、ゴール前をゴレイロと共に固めている。
正面から突っ込むことも出来ず、シュートを狙おうにも角度のない状態へと追いやられてしまったが、それでも双葉は強引にシュートを狙うべく、大きく蹴り足を振り上げて、振り下ろした。
身構えるゴレイロとフィクソであるが、だが双葉の足からシュートは放たれなかった。
打つ振りをしただけで、斜め後ろにいる鈍台洋子へ戻すようにパスを出したのである。
ゴールを固める二人の乱れを誘いタイミングをずらすことに成功し、後は決めるだけであった。
だがしかし、いきなりそのようなパスを受けても実戦経験がないに等しい洋子にはどうしていいのか分からなかったようで、動けず呆っとしてしまっていた。
それを感じ取ったフィクソが、一気に洋子へと間合いを詰めた。
だがフィクソは、突っ立っている洋子からボールを奪うことは出来なかった。
二人の間を、双葉がボールを拾いながら駆け抜けたのだ。
至近距離のゴール前にゴレイロ一人。
双葉は足を止めてくるりゴールへと身体を向けた瞬間、思い切り右足を振った。爪先をボールに叩きつけた。
決定的であったが、ゴレイロが咄嗟に手を伸ばして跳ね上げた。
落下するボールをゴレイロが抱えるようにキャッチしようとしたところへ、鈍台洋子が頭から突っ込んだ。
ゴールネットが揺れた。
鈍台洋子が、ゴレイロごと、自らの身体ごと、ボールを押し込んだのだ。
しかしというべきか当然というべきか、ゴールは認められなかった。審判が笛を鳴らし、鈍台洋子のファールを取ったのである。
佐原南のベンチからは一斉に落胆の声が上がった。
2
「いまの攻撃、気持ちよかったね」
落胆を作り出した本人である鈍台洋子は、まったく気にするふうもなく本当に気持ちよさそうに笑った。
「タコ焼き屋、悪くなかった! ドンちゃんも、残念だったけどでもナイスファイト! これで分かったかタコ焼き屋! おどおどしてるだけの奴にチャンスなんか生まれないんだよ!」
反対側ゴール前から、佐原南ゴレイロの大声が聞こえてきた。
「分かっとるわ! うちは単に状況を冷静に考えてるだけや!」
鬱陶しいその声を掻き消してやろうと、高木双葉は怒鳴った。
新堂良子が先ほど必死に訴えていたリスク管理、それを徹底していただけだ。妙な色気出して失点したら元も子もない。今のは、行けると思ったから行った、ただそれだけだ。
別にあいつにいわれたからではない。
それよりも、こうして決定的なチャンスを作ったんだから少しは褒めろ。
ボケ。
アホ。
カス。
などと心で文句をいいながらも、なんだか不思議な気持ちが湧き上がってくるのを感じていた。
柚葉の言葉は、悔しいけれど間違っていなかった。
あまりにボロカスにいってくるものだからムカついて仕方なかったけれど、でも、間違ってはいなかった。
確かに相手を過剰に恐れ過ぎていた。
今、挑戦してみせたことで、自分にもやれるんだという自信を持つことが出来た。
まだ不安は多分にあるものの、でも、その自信がなんだかくすぐったく、心地よかった。
だが、湧き上がる不思議な感覚というのは、そのことではなかった。
なんだか先ほどから……
なんだろうか。
懐かしいのだ。
でも、一体なにが懐かしいのか、皆目見当がつかないのだ。
悪いイメージか良いイメージか、どちらなのかといわれれば良いイメージのある感覚なのだが、それがなんなのか思い出せない。
気持ち悪かった。
なんだろう、この感覚。
九頭柚葉の顔をふと遠目に見た瞬間、すうっと疑問が晴れていた。
ただしそれは、新たな疑問が生じるきっかけでもあった。
「仕掛けろ、ビビってんな!」など、先ほどから柚葉が投げ掛けていた罵倒の言葉、随分と前にも掛けられた記憶があったのだ。
うちは、あいつと以前に会うている?
まさか。
仮にそうやとしても、いつ?
どこで?
あ……
もしかしたら。
「まさか、あの時の!」
双葉の感じていたもやもやは、一瞬にして弾け飛んでいた。
ため息だか乾いた呼気だかを吐くと、改めて遥か後方のゴール前にいる佐原南のゴレイロへと目を向けるのだった。
3
確か、雲一つないからりと晴れた日だったと記憶している。
季節は春。
小学一年生になったばかりの高木双葉は、自宅から歩いて十分ほどのところにある児童公園で、フットサル用のボールを蹴って練習をしていた。
三号球のためサッカーボールどころかフットサル一般球よりも小さく、誰もが子供用サッカーボールと思うかも知れないが、れっきとしたフットサル仕様の低反発ボールだ。
兄と従兄弟以外とは一緒にボールを蹴ったことがなく、したがって試合などもまったく経験がない。それなのにフットサルボールを蹴ることにこだわっているのは、母親の影響だ。
母親である高木梨乃は、現在フットサルの名門として有名な佐原南高校女子フットサル部の、その名門たる礎を築いた人間である。
それのみならず、一度きりではあるもののフットサル女子日本代表に選出されたこともあるのだ。
双葉はまだ六年間という短い人生しか送っていないが、心から尊敬する人物が三人いる。そのうちの一人が自分の母親、高木梨乃なのである。
話は横道にそれるが、尊敬する一人は遠藤裕子という名で、母親の高校時代の後輩だ。
いまでもよく双葉の自宅に母親を訪ねて来ては、日本酒の講釈をたれて帰っていく。酒がとにかく大好きなのだが、双葉には酔っていない時の方がよっぽど面白い。
好きが高じて日本酒ソムリエを業にしており、雑誌や新聞にコラムを連載したりラジオやテレビに出演したこともあるらしい。
双葉が何故彼女のことを尊敬しているのかというと、別に酒好きで面白いからではない。
高校の大会で酷い怪我を負っている身で出場して、自分の足を犠牲にして部を初優勝へと導いたからだ。
骨も靭帯も完全に壊れて、まともに歩くことの出来ない身体になってしまったのだが、運命や他人、自分、誰を恨むこともなく、いつも笑顔を絶やさずバカみたいなことばかりいっている。
とってもカッコイイ生き方だと、双葉は心から思う。
それほどの怪我をしていたら、自分なんか痛みに泣いてしまって身動き一つ取れなくなってしまうだろうけど、彼女のような自分を信じて突き進むような生き方を少しでも真似出来たならいいなと思う。
尊敬する人物の残り一人は、佐治ケ江優である。
いわずと知れたフットサル女子日本代表の代名詞とも呼べる存在であり、フットサルに携わる女子ならば知らない者はおらず、したがって尊敬していてもなんら不思議なことではないだろう。
なお佐治ケ江優もまた、母親の高校時代の後輩だ。
人生で心から尊敬する三人といっても一人は自分の母親で残りはその後輩であり、なんとも狭い世間のようにも感じるが、みながみなテレビの仕事をしていたり、日本を代表するアスリートであったりするわけで、改めて狭いか広いかを問われれば返答に困るところであろう。
さて、話を戻そう。
双葉は最近、いつも一人で練習をしている。
以前は兄や、すぐ近所に住む従兄弟とよく一緒に蹴っていた。
差をつけようと一人で隠れて練習しているうちに、兄も従兄弟もいつしか野球にのめり込むようになってしまい、隠れるまでもなく一人で練習するしかなくなってしまったのである。
友達はいるものの、みな女の子らしく人形遊びなどを好むような子ばかりで、公園で一緒に泥まみれになってボールを追ってくれるような子は一人もいなかったし。
足裏でボールを引いては爪先で浮かせて宙にあるうちに蹴り、あらかじめ置いた小石と小石の間を通す。そんな練習を二十回ほど行うと、今度は小石をたくさん一列に置いて、その間をドリブルでジグザグに進んだ。
と、タッチミスでボールが足元から離れて、ころりころりと転がった。
小走りで寄って、スタート地点へと蹴って戻すとまたドリブルを開始した。
今度はいい調子だぞ、と思ったものの、あと小石三つというところでまたタッチミスが出て、ボールがころり転がっていってしまった。
「下手くそ」
背後から声が聞こえ、双葉は振り向いた。
公園の入口に男の子が三人、ガードパイプの間を縫って敷地に入ってきた。
背が高いのと、小太りのと、ガリガリで弱そうなのと、まるで漫画のような三人組だ。
弱そうといっても、みな双葉より遥かに大きく、ずっと強いだろう。おそらくは小学校上級生だ。
いきなりそのようなことをいわれ、他人との接触の苦手な双葉はどのような反応をすればいいのか分からずに突っ立っていた。
すると、背の高い男の子がまた、
「下手くそ」
同じことをいってきた。
「……下手だから……練習してるんだよ」
意地の悪そうな笑みに、なんか嫌だなと思いながらも、二度も声を掛けられて無視するわけにもいかず、ボールを屈み拾いながらそう応えた。
練習再開をしたものの、三人にじーっと見られていてはどうにもやりにくく、だからといって追い払うわけにもいかず、居心地悪そうにちょこちょことボールを撫でるように蹴ることしか出来なかった。
だがそれすらも蹴り損じて、明後日の方向へ転がしてしまう。それを見て、三人は大きな声で笑った。
「そんな下手なんじゃあ、練習なんかしたって意味ねえよな。そんなボールなんか持ってたって、意味ねえよな」
また、背の高い男の子が意地の悪そうな笑みを浮かべた。
「だから……下手だから、練習してるんだって」
いまのはそっちがじーっと見ているから失敗したんだ。本当はそう思ったのだが、正直にいうことも出来なかった。
早くどこかいって欲しいなあ。
困っちゃうなあ。
などと胸の中でもじもじとし、もごもごと呟きながら、撫でるようにボールを蹴り続ける双葉であったが、三人は公園から立ち去ることもしなければ、自分たちだけでの遊びを始めることもせず、ただ楽しそうな表情で双葉を見ているだけだった。
からかわれているみたいで嫌だったけれど、だからといって自分からこの場を去るのもなんだか癪で、いつまでも一人でボールを撫で続けていた。
「おいお前、勝負しようぜ」
唐突にそんな言葉を掛けられ、びくりと肩を震わせた。
4
「勝負……って」
双葉は俯き加減に、おずおずとした表情を男の子たちに向けた。
「勝負は勝負だよ。で、お前が負けたら、そのボールはおれたちがもらう」
背の高い男の子は、双葉の足元にある三号球を指差した。
「え? え?」
なにをいっているのか日本語としては理解出来たが、そのような身勝手な理屈をこうして聞くなどと覚悟しておらず、双葉はすっかり狼狽していた。
「えじゃないよ。勝ったんなら、当然の権利だろ。もしおれたちの方が負けたんなら、ボールもらうのやめといてやるよ」
なんなんだ、その条件は。
あまりにも酷すぎる。
ただでさえ相手が上級生で、なおかつ男子だというのに……
と、そんな双葉の表情に男の子は気づいたのか、次のように続けた。
「別にズルくはないぞ。おれさあ、野球やってて足だって速いけど、サッカーボールを蹴ったことなんてほとんどないんだから」
男の子は自らの正当性を主張するが、双葉が納得出来るはずもなかった。
勝負なんかしたくもないのに、一方的に損失が出るだけの不合理な条件を押し付けられているのだから当然だ。
「それで充分にハンデになるだろ。やんないんだったらいいよ。不戦勝で、そのサッカーボールはおれたちの戦利品とする」
フセンショウとかセンリヒンとか、難しい言葉は双葉にはさっぱり分からなかったが、現在どうしようもない状況に自分が陥っていることは理解出来た。
勝負に勝たないと、母に買ってもらった大切なフットサルボールをこのようなサッカーボールとの区別もつかないような連中に奪われてしまうのだ。
他の物ならいいけど(もちろん物によるが)、このフットサルボールだけは絶対に渡したくない。
仕事で忙しい母と、自分とを繋ぐ宝物なんだから。
「分かった」
双葉は唇を小さく震わせるように動かした。
こうして双葉は、生まれて初めて身内以外とフットサルボールを蹴ることになったのである。
残念ながらそれは楽しい気分のものではなく、むしろ正反対といえるものであったが、でもこの戦いを受けなければ母親から買ってもらったボールを守れない。不本意ではあるが、やるしかなかった。
勝負の内容は一対一でボールを奪い合い、お互いのゴールへとシュートを打ち、時間内により多く決めた方が勝ちというものだ。
靴で地面を引っ掻いて作った、数メートル四方の少しいびつな長方形がコートだ。
その中央に、背の高い男の子と双葉は立ち、ボールを挟んで向かい合った。
男の子は楽しそうににやにやと笑みを浮かべている。
双葉はその視線を受けて畏縮しそうになりながらも、なんとか己の心を奮いたたせて顔を上げ、その場に踏み止まっていた。
残る二人の男の子が、それぞれ長方形の短辺側に大きく足を開いて立った。この足の間にボールを通せばゴールというわけだ。
「そんじゃいくぞ、試合開始。ピーッ!」
男の子がボールを蹴った。
フェイントもなにもなく、ただドリブルで双葉の脇を抜けようとする。
そんな単純な行動に対して、双葉は対応することが出来なかった。呆然としたような表情で、立っていた。
はっとしたように目を見開くと、後ろを振り向いて男の子の背中を追い掛けた。
負けたら母親から買ってもらったボールを奪われてしまう。
その危機感に、双葉は恐怖と戦いながら必死に走った。
男の子は先ほど自分でもいっていた通りサッカーは上手でないらしく、シュートを狙おうとしてボールタッチにもたついた。
その間に、双葉はなんとか正面に回り込んでシュートを阻止した。
ちょんと出した爪先でボールを引っ張って奪い取ると、敵陣へ向けてドリブル開始。
と、その瞬間に双葉の身体は真横になぎ倒されるように崩れていた。後ろから襟首を掴まれて、引っ張られたのだ。
明らかな反則だ。
でも、男の子はセルフジャッジでプレーを止めることもなく、双葉の足元にあるボールを奪おうとした。
双葉は倒れながらもなんとかそのボールを大きく蹴り、ラインの外へ出して難を逃れた。
立ち上がると、男の子をちらりと見た。
「なあんだよ、その顔は?」
男の子が、批難するような言葉で凄み、威嚇してきた。
その顔は、などといわれても、双葉には自分がどんな顔をしているのか分からなかった。
この不条理さに対する不満が、知らず表情に出てしまっているのだろうか。
でも、決してその不満を口に出すことはなかった。なにをされるのか怖くて、意志を主張することなどとても出来なかったのである。
勝負に勝てばボールを守れる。ならばその勝負を、ただ黙々とやるしかなかった。
いくら不利な条件であろうとも。
不利であればこそ、勝負に対しては気をしっかり強く持たなければならないのだろうが、双葉は元来気弱で温厚な性格であり、なおかつ他人との接触経験がほとんどない。先ほど襟首を掴まれ引き倒されたことで、すっかりと怖じけづいてしまっていた。
なんとか失点だけは避けようと頑張るものの、反撃を躊躇して向かい合っているうちに奪われて必死に戻り、大きく蹴り出して逃げる。と、その繰り返しになっていた。
男の子は、先ほどのような暴力で簡単に得点してしまうことだって出来るだろうに、何故そうしないのか。
からかっているのだろうか。
勝負を面白くしようとしているのだろうか。
双葉は、必死に守りながらそんなことを考えていた。
それならそれで、相手が余裕を見せている間に、こっちこそ奪ったボールで一気にゴールを狙えばいい。
でも……
どうせまた後ろから首を掴まれたり、蹴られたりして転ばされてしまうんだ。ただ痛い思いをするだけなんだ。
だからって、点を取らないと勝てない。
負けたらボールが……お母さんから買ってもらったボールが……
双葉は、すっかりと泣きそうな表情になっていた。
「奪ってみろよお」
男の子はボールを足の裏でころころ転がしながら、楽しそうな笑みを浮かべ挑発した。
双葉と男の子は、またボールを挟んで向き合った。
一体、何度目の対峙の時であっただろうか。どこからか、大きな声が聞こえてきたのである。
「仕掛けろ! ビビってんな!」
幼い、女の子の声であった。
その声に突き動かされるように、双葉は男の子の隙をついてボールを奪い、横を駆け抜けていた。
男の子の手が襟首を掴もうと伸びてきたが、双葉は無意識に、すっとしゃがむようにかわしていた。
双葉は、男の子がバランスを崩している間に小さくドリブルでボールを前へ運び、シュートを打った。
ボールは、小太りの子の足の間を転がり抜けた。
ゴール。
ついに双葉が得点、先制である。
息を切らせ肩を上下させながら、双葉は呆然と突っ立っていた。
やがて、自覚が芽生えたのか拳を握り、小さく口を開いた。
「やった……」
不安に押し潰されそうであった双葉の表情に、じんわりと笑みが広がっていった。
安堵? 自信?
自分の内部にゆっくりと花開くように広がるその感情、笑みの正体、自分のことであるというのに双葉にはまったく分からなかった。
「ほおら、やりゃ出来んじゃん」
また、どこからか女の子の声が聞こえてきた。
男の子たち、そして双葉は辺りをきょろきょろと見回すが誰一人として姿など見えなかった。
隣の民家の塀の上を、太った猫が歩いているくらいだ。
まさか猫の声とも思えないし。
「あー、あそこ!」
小太りの男の子が、公園内に生えているブナの木の上の方を指差した。
高さ四メートルはあるだろうか。木の枝の上、葉っぱをベッドに幼い女の子が横になっていたのである。
5
「あ、ばれた?」
女の子は歯を見せて笑うと、上体を起こして枝に座り、お尻を前へずらすようにして木から飛び降りた。素早く両手を上げて自分のいた枝を掴みしならせて、低いところの枝に飛び移り、ぐにゃりふわりと地面に着地した。
ようやくその顔がはっきり見えた。
幼いといっても双葉より一回りは大きいが、顔立ちからすると同じくらいの年齢だろう。
長い髪の毛を、後ろで束ねている。
いつも男の子のような遊びでもしているのか、服は泥だらけで、腕も、ショートパンツからすらりと伸びた足も擦り傷だらけだ。
女の子は双葉へと歩み寄った。
「負けたらボールを取られちゃうんだろ? でも相手、下手だからさ、ビビんなきゃ余裕で勝てるって。ほら、続き続きっ!」
女の子は笑いながら、双葉のお尻を両手でぺしぺしぺしぺしと叩いた。
「なんだよお前、余計なこといってんじゃねえよ! くそっ、絶対に逆転すっからな!」
背の高い男の子は険しい顔で怒鳴り声を上げると、ボールをコート中央に置くなり合図もなしにドリブルを開始した。
これまではこいつが困るのを楽しむために手加減をしていただけだ。
男の子はそう思っていたのかも知れない。
確かに運動神経はよさそうであるし、年齢、体格や性別といった差を考えればそのような自信を持ってもなんら不思議ではないだろう。
いくら自分がサッカー素人で、相手が少しばかりの経験があろうとも、それを補って遥かに余るものが自分にはあるのだ、と。
しかし現実はそうはいかなかった。
勇気を振り絞って仕掛け、結果を出したことで自信を得つつある幼い少女から、簡単にボールを奪うことが出来なくなっていた。
幼い少女、高木双葉はくるり反転して男の子をかわすと、一気にゴール前へと向かい、二本目のシュートを放った。
狙いは完璧であった。
しかし、決まらなかった。
ゴール代わりに立っている小太りの男の子が、すっと身を真横に動かしてボールの軌道から逃げたのだ。
ずるい……
と思う双葉であるが、言葉には出来ず喉元に飲み込んだだけであった。
「汚ねえぞ!」
代弁するかのように、女の子が怒鳴り声を上げた。
「ハンデハンデ。だってお前、サッカーやってんだろ? ケンジはやってないんだから」
小太りの男の子は、にっと笑った。
確かにボールを蹴る経験だけを考えればその通りかも知れない。
でも、こちらはやりたくもないことを無理矢理やらされているわけで、それにもともとの運動神経とか、男子と女子との違いとか、双葉にはどう考えてもずるいとしか思えなかった。
同時に、なんだか自分が恥ずかしく惨めな気持ちになっていた。
突然現れた(最初からそこにいたのだが)名も知らない女の子は、この件に関しては赤の他人だというのに、男の子たちの理不尽さに憤慨して戦ってくれている。だというのに、自分は……
もっと強くなりたい。
強い心が欲しい。
負けようとも挑めるような、勇気が欲しい。
双葉は、六年間の人生の中でこの時ほど真剣に強くなりたいと思ったことはなかった。
「おい彼女、勝とうぜ絶対! そう、そこ! かわせ! いけえ!」
女の子が、大きな声で双葉を応援する。
双葉も、弱気になりそうになる中で精一杯頑張ったが、またしてもハンデが出て、同点に追い付かれてしまった。男の子、ケンジが打ったシュート自体は思い切り狙いが外れたのだが、ゴール代わりの男の子が大股で真横へ移動し、自らボールを招き入れたのである。
「やったあ」
男の子たちは、手を打ち合い、喜んでいる。
「なんだこれ、ふざけんな! ただのいじめじゃねえか!」
女の子が地を踏み鳴らし、怒鳴った。
「はあ? なにいってんだ、お前。木の上でずっと見てたんだろ? これは立派な勝負だよ。『分かった』、ってこいつは承諾して勝負を始めてるんだから、ちゃんと成立してんだよ」
背の高い男の子、ケンジは恥ずかしい気持ちなど微塵も感じられない実にすっきりとした顔で、自分だけの理論を展開した。詭弁にすらなっていない理論であるが、民主的に正しいことであるかどうかなど、彼にとってどうでもいいのだろう。
「よし、いつまでやっててもきりがないから、次にシュート決めた方が勝ちだ!」
ケンジは、自信満々に笑った。
自信があるのは当然であろう。絶対的ともいえるハンデを考えれば。
双葉は唇をきゅっと噛み締めた。
悔しかった。
理不尽さをしっかりと突っぱねずに、こんなことに付き合ってしまっている、弱い自分が。
強くなりたい。
もっと、強い心を持ちたい。
そんな気持ちが、無意識に背中を押したのだろうか。
もしくはボールを奪われたくないという思いからなのか、それとも見ず知らずの女の子が現れて自分を応援してくれることに勇気をもらえたということなのか。
自分でも分からない。
分からないが、双葉の身体は自然に動いていた。
一瞬の隙をついてケンジからボールを奪うと、ゴールへ。
「よし、いけえ!」
女の子が腕を振り上げ、叫んだ。
「させねえよ」
小太りの男の子ががっちりと足を閉じてゴールを塞いだ。
だが双葉は必死の形相で、その隙間にボールをねじ込んでいた。
一瞬足を引いて、さらに爪先で蹴った。
とと、とよろけて倒れそうになる男の子の足の間を、ついにボールが突き抜けた。
双葉の得点だ。
「やったぜ!」
女の子が叫び、指をパチンと鳴らした。
こうして、男の子たちは自分で勝手に作ったばかりのルールによって自滅したのである。
ふう、と安堵の息を漏らした双葉は、自分のことのように跳びはね喜んでいる女の子を見て、柔らかな笑みを浮かべた。
その瞬間であった。
双葉は頭部にガツンと衝撃を受け、横へ吹っ飛ばされていた。
ケンジの容赦ない平手打ちを顔面に受けたのである。
年齢や男女の違いからの体格差に、双葉の身体はひとたまりもなかった。
「てめえ、生意気なんだよ! 女のくせに!」
地面に倒れている双葉は、脇腹を思い切り蹴飛ばされて激痛に悲鳴を上げた。
「やめろよ!」
女の子が叫びながらケンジに突進、肩で体当たりをした。
不意をつかれてケンジはぐらりよろけるが、倒れぬよう踏ん張り、女の子の胸倉を掴み引き寄せた。
「お前は関係ないだろ! 正義の味方気取ってんじゃねえよ!」
「正義の味方じゃない。いつも頑張る光り輝く女の子の味方だ!」
テレビアニメ魔法天使プリムラビーンに登場する戦士の一人、シェルミーケミーの決め台詞だ。
「フラワーハートトライアングル!」
女の子はケンジをどんと突き飛ばし逃れて距離を取ると、両手で作ったハートマークを胸の前にかざした。
ハートチャージ完了。雄叫びを上げ、腕を振り上げた。
だけどシェルミーケミーの魔法術は、魔界獣には届かなかった。
「バカじゃねーのか!」
小太りの男の子に横から顔を殴りつけられ、吹っ飛ばされていたのである。
ごろり転がったところを、胸を踏み付けられ、巨体に馬乗りになられていた。
「関係ないくせにでしゃばりやがって! 謝れよ!」
小太りの男の子は、女の子の顔面を殴りつけた。
女の子はそれでたじろぐことなく、きっと男の子を睨みつけた。
「悪いのそっちだろ!」
「弱いくせに生意気いってんじゃねえぞ」
「うるせえ! シェルミーは悪党なんかに負けねーんだ。今日は負けても明日は勝つ!」
「いま勝ってみろよ! ほら、やり返してみろよ!」
小太りの男の子は、女の子の顔を容赦なく何度も殴った。
鼻血が出ていた。
それでも、すっかり興奮状態にあった男の子たちは、女の子の顔を殴り、身体を蹴り続けた。
双葉は、涙ぐんでいた。
全身をぶるぶると震わせていた。
目の前で殴り合いの喧嘩をしているという恐怖。
自分が原因の一つであるという罪悪感。
我慢の限界に達した時、双葉は大きく口を開き、暴力を振るっている男の子たちへと走り寄っていた。
「もう、やめてください! この子、関係ないじゃないですかあ」
双葉は泣きながら、太った男の子の肩に手を掛けて女の子から引きはがそうとした。
「邪魔すんな!」
腕を掴まれ投げられ、双葉は地面に転がったが、すぐ起き上がるとまた男の子を引きはがしにかかった。
「殺すぞお前え!」
男の子たちが興奮気味に叫んだ時である、
「なにやってるの、あんたたち! 警察呼ぶよ!」
女性の怒鳴り声が、ぴしゃり雷のように空気を震わせた。
すぐ横にある家のベランダから、年取った白髪の女性が見下ろしていた。
「やべえ、逃げろ!」
ケンジとガリガリが、脱兎のごとき勢いで逃げ出した。
小太りも、女の子に馬乗りになっている体勢から慌てて立ち上がろうとするが、
「逃がすか悪党!」
女の子が左手で服の裾を強く掴み、引っ張った。
「離せよてめえ!」
と、叫び睨みつけた瞬間、女の子が、いつの間にか右手にかき集めていた砂を、その顔を目掛けてぶちまけた。
ぎゃっ、という悲鳴が上がった。
小太りは、咄嗟のことに反応出来ずに砂を浴び、それが目に入ってしまったのだ。
ごろり倒れて地面をのたうちまわっているところを蹴飛ばしやっつける。と、女の子はそのような算段でいたのかも知れないが、現実は異なっていた。
「ふざけんなあっ!」
小太りは、腕を文字通り盲滅法にぶんぶん振り回した。
そのうちの一発が女の子の顔面を捉えると、そのまま胸倉を掴み引き寄せ、拳で何度も何度も殴ったのである。
やがて女の子がぐったりして倒れてしまうと、小太りはようやく我に返ったようで、目をこすりながら仲間を追って走り出した。
こうして、ようやく三人の不良小学生は、双葉たちの前から姿を消したのだった。
6
温厚で殴り合いの喧嘩などとはやるのも見るのも無縁に生きてきた双葉は、かつて経験したことのない恐怖に全身を震わせ、すっかりと呼吸が浅く荒くなっていた。
横たわってぐったりとしている女の子の姿に気づくと、またじわりと目に涙が滲んだ。
双葉は自分を責めた。
すべては自分のせいだ。
自分に勇気がなかったからだ。
「ごめんね」
双葉は、女の子の顔を覗き込んだ。
どうやら、気を失っているようであった。
「ごめんね」
もう一度謝った。
ぽたりと落ちた涙が、女の子の頬を打った。
女の子の目が突然かっと見開かれた。
「まだ負けてねえぞ!」
跳ねるように上体を起こすと、双葉の胸倉を掴みぐいと引き寄せ自分の顔へ引き寄せた。
その迫力に恐怖し、ひっと息を飲んだ双葉の目にまた涙が滲み、つうとこぼれた。
「あ、ごめん……。あいつらかと思っちゃった。ほんとごめんね」
女の子は、双葉の襟から手を放した。
双葉は咳き込みながら、
「気にしてないから。それよりそっちこそ大丈夫なの?」
尋ねた。
「平気平気。ちょっぴり痛いけどね。そうだ、ボールはどうしたの? あいつらに取られなかった?」
その問いに、双葉は黙って頷いた。
「そう。よかったね」
女の子は歯を見せて笑った。
「よくないよ! あたしなんかのためにこんなに殴られちゃって……こっちこそ、本当にごめんなさい」
双葉は申し訳なさそうな表情で頭を下げた。
「いいってことよ。こっちの好きでやったことなんだし。しっかし、見事にのされちゃったなー、あたし。気絶なんかしたの六年間の人生で初めてだよ」
六歳、同年代だろうとは思っていたが、まったく同じだ。言葉使いが妙におとなびているため、なんだか違和感はあるが。
「空手でも習おうかなー。そしたら、あんな奴らぶっとばしてやれるのに」
なにげない発言ではあったのだろうが、双葉にはなんとも意外に感じられた。
同じような目にあって、双葉は心の強さを求めたが、この子は肉体的な強さを求めているということが。
でも、考えてみるまでもなく当然か。
だってこの子の心は、もうこれ以上はないくらいに強いのだから。でなければ、他人のために上級生の男子三人に立ち向かっていかれるはずがない。
単に恐れ知らずなだけかも知れないけれど。
双葉は、心さえ強くなれるのならば、身体の強さなどいらない。フットサルをやる上での肉体の強さは欲しいけれど、喧嘩なんか強くならなくていい。
「フットサル、好きなんだ?」
女の子の質問に、双葉は驚いた。
双葉は足で土を引っ掻いて作った数メートル四方のコートでボールの奪い合いをしただけであり、であれば通常はサッカーだと思うはずだからだ。
大人が四号球を蹴っていれば、ぴんと来る者もいるかも知れないが、双葉のボールは三号球。子供がサッカーに使うサイズでもある。
つまり女の子は、サイズによらずフットサルボールと見抜いたことになる。
「よく分かったね。フットサルのボールって」
「弾み具合や、音でね。あたしもフットサルやってっから」
「え、ほ、ほんとに?」
双葉は目を輝かせ、身を乗り出すように女の子に接近した。
母やその友達以外で、フットサルをやっている者に出会ったことなどなかったからだ。
「うん。自慢じゃないけどねえ、いやちょっと自慢かなあ、あたしのお母さんね、佐原南高校で全国大会に出て優勝したことあるんだよ。エースだったんだよ」
女の子は、どんなもんだとばかりの笑みを満面に浮かべた。
なお佐原南高校とは、この近くにある、女子フットサル部がとにかく強いことで知られている県立高校だ。
「そうなんだあ。あたしのお母さんもね、佐原南にいたんだよ。この間ね、代表にも呼ばれたんだよ」
別に自慢をしたつもりはまったくない。
世界で尊敬する三人のうちの一人の話であるだけに、普通に話しているだけでも自慢っぽく思われるかも知れないが。
「ほんとそれえ? うわああああ、負けたあああ! くそおおお、悔しいなあ。お母さん、なんて名前なの?」
「高木梨乃」
双葉は答えた。
「聞いたことないなあ。あとでお母さんに聞いてみよっと」
「そっちのお母さんの名前は?」
「代表じゃあなかったし、高校出てフットサルやめちゃったから知らないと思うよ。……九頭葉月、聞いたことないでしょ」
「うーん。ごめんね。あたしも、お母さんに聞いてみるよ」
「もし同じくらいの歳だったら、お母さん同士二人で試合に出てたりしたかも知れないもんね。……あたしたちも、いつか佐原南で一緒にフットサルをやったりしてね。そうなったら、よろしくね」
女の子は、照れたような笑みを浮かべて手を差し出してきた。
「こちらこそ、よろしくね」
双葉は、ちょっと身体をもじもじとさせながらも手を伸ばした。
二人は小さく柔らかなお互いの手を、がっちりと握り合った。
「じゃ、あたしもう行くね! バイバイ!」
女の子はくるり踵を返すと、走り出した。
双葉は呆気にとられて、その後ろ姿を無言で見つめていた。
「なんだったんだろ」
などと一人ぼそりと口を開いたのは、どれほどの時が流れた後であったか。
そういえば、名前も知らないままだった。
母親の名前を教え合ったのみで。
クズ……なんだっけ。難しい響きだったものだから、もう忘れてしまった。なんだかとてもかっこいい名前だった気がする。
でも別に、名前など知る必要はないだろう。
これからフットサルをやっていく上で、あの子にたくさんの元気や勇気をもらったことに違いはないのだし、それに、もう会うこともないだろうからだ。
7
などと考えたのは、完全に双葉の予想違いであった。
そもそも別に根拠があってそう思ったわけではなく、公園に一人残ってただ風に吹かれていたら、なんとなくそんな気持ちになったというだけなのだ。
一体なんの話であるのか分からないだろうから説明をすると、要するにあの後も女の子はちょくちょくと公園にやって来ていたのである。
そして、二人は一緒にボールを蹴って練習するような仲になっていたのである。
再会時に、またもや名前を聞く機会を逃してしまって、お互いに知ることのないまま。
二人きりであるため、ねえでもおいでも呼び掛けとしては問題なく成立するわけで、名前など知らなくても特に不便はなかったから。
特に待ち合わせの約束をするでもなく、どちらからともなくふらり公園に現れて、はしゃぎながらボールを追い掛け、合間合間の休息時間には木陰のベンチで肩を寄せ合って色々な話をした。
なんでもこの子には幼なじみの友達がおり、一緒に空手を習うことにしたそうである。
初めて会った時に男の子と喧嘩をして思い切り叩きのめされ、空手を習いたいなどといっていたけれども、あれは本気の言葉だったのだ。
「……それじゃあ、フットサル、やめちゃうの?」
双葉は尋ねた。
「やめるわけない。まだ習ってないからよく分からないけど、空手の技をフットサルにも生かすんだよ。喧嘩には強くなるし、一石二鳥だぜ」
女の子は、手を組んで指をぽきぽき鳴らそうとしたが鳴らなかったので、ごまかすようにふふふと不敵に笑った。
「そう、なんだ」
イッセキニチョーってどういう意味だろう。
この子、たびたび難しい言葉を使うよな。親が頭いいのかなあ。それともわたしがバカなのかな。
とにかく、フットサルをやめないというのはよかった。
わたし、フットサル友達なんて全然いないからな。
一緒に蹴って、色々と勉強になるし。
幼なじみと空手を習うっていってたけど、どんな子なのかな。
会ってみたい気もするけれど、この子とおんなじくらい元気だったら、囲まれるこっちがへとへとに疲れちゃうなあ。
などと、双葉が心配するのも無理はなかった。
この女の子の個性が、あまり世間を知らずに過ごしてきた双葉にとってあまりにぶっ飛んでいたからだ。
ぶっ飛んでいるといっても、別に身勝手というわけではないし、どちらかといえば気が利く方ではある。
妥協せずきっちり主張をしたり、ぐいぐいと引っ張っていく我の強さといったところが、おとなしい性格の双葉としてはなんとも気疲れしてしまうということだ。
疲れはするけれど別に不満はなく、この子のこと自体は大好きであった。
ただ公園でボールを蹴るだけの仲だから、悪いところが見えないということかも知れないが、とにかくそのボールを蹴る技術が凄くて一緒にいてとってもためになるし、その性格も魅力的だった。
自分にないものをたくさん持っており、ただ一緒にいるだけでなんだか自分まで強くなった気がした。
小学校の学区が異なるため公園で会うことしか出来なかったが、でも三日に一回は会っていた。これまでスポーツをやる友達がいなかった双葉にとっては、濃密で最高に楽しい時間だった。
だが初めて会ってからちょうど二ヶ月を向かえた日を境に、二人が会うことはなくなった。
ある事件が起きたのである。
8
その日、あの男の子たちがまた公園にやってきたのだ。
ケンジという背の高い子と、小太りと、ガリガリ、三人の男の子が。
挑発に女の子が乗って、また殴り合いの喧嘩になってしまった。
その殴り合いであるが、男の子たちにとっては不本意以外のなにものでもない結果であったことだろう。
女の子が、習い始めの空手でなんとケンジをやっつけてしまったのだ。
小学一年生の女子が、上級生を。
しかし、上級生しかも男子をやっつけたんだなどと武勇に浸っている暇はなかった。
喧嘩なんか強くなったところで争いに際限がなくなるだけだ、という双葉の恐れていたことが起きてしまったのである。
逃げ出したケンジが、自宅から獰猛そうな大型犬を連れて戻ってきたのだ。
そして女の子を襲うように、けしかけたのである。
けしかけたはいいが、女の子には犬に食いつかれてやらねばならぬ義理はなく、木に登ったり滑り台に上ったりと素早く逃げ回った。
イラついたケンジは、標的を変えて双葉を襲わせた。
ケンジも本来ならば脅かすだけだったのかも知れない。女の子が恐怖に泣きわめいて謝ってくれれば、許してやっていたのかも知れない。
しかし、あまりのままならなさに怒りの感情の逃げ場所がなく、すっかりと我を忘れてしまっていたのだろう。
突然標的にされた双葉は目を見開いてひっと息を飲んだだけ、逃げようとしないばかりか身動き一つしなかった。恐怖に立ちすくんで、動けなかったのだ。
犬に飛び掛かられ、双葉はぎゅっと目を閉じた。
どうん、
激しくぶつかってきたのは、犬ではなくもっと柔らかな感触であった。
女の子が、双葉を庇うように前に立ち塞がって、犬の突進を真正面から受けて吹っ飛ばされたのだ。
ぶつかられて双葉は後ろへ倒れ、その瞬間、すぐ横に女の子が倒れてきた。
顔をしかめ、ぐ、と声を漏らす双葉。次の瞬間、その目が恐怖に見開かれていた。
目の前で起きている光景に、甲高い悲鳴を上げた。
双葉の眼前で、犬が女の子の右腕に食らいついていたのである。
「離せよ、てめえ!」
女の子は叫びもがくが、食らいついた犬は唸り声を上げ、首を振りながらますます獲物に歯を食い込ませた。
空手を習い始めようとも小一の女の子であり腕は木の枝のように細く、食いちぎられもがれ落ちても不思議ではなかった。
双葉はあまりの恐怖になにも出来ず、大声で泣き出してしまった。
その泣き声に、ようやくケンジもやり過ぎであることに気がついたようで、
「ジョン、やめろ!」
と制止しようとしたのであるが、女の子が左手に拾った石でジョンの顔面を殴りつけているものだから、ジョンとしても怒り狂うばかりで攻撃をやめるはずがなかった。
女の子は、足をジョンの胴体に巻きつかせてぎゅうっと全力で締め付けた。
ジョンはもがき逃れようと、女の子のお腹を両の前足でバリバリと引っ掻いた。
女の子が痛みに悲鳴を上げ、石で何度もジョンの顔を殴りつけるが、それは逃れるどころか自分自身をさらに痛めつけることに他ならなかった。
つまりは、ジョンの方こそ攻撃から必死に逃れようとして、ますます女の子の腕に食らい付き、そしてお腹に深く爪を食い込ませ引っ掻き続けたのである。
大型犬ともなれば、その爪も腕力も充分に凶器である。女の子の服の袖やお腹の部分は完全に破れて肌が見えている。肌色ではなく、血に染まり真っ赤であった。
そんな泥沼の惨状から女の子を救ったのは、ケンジでも双葉でもなく、またしても隣の民家の老婆だった。
以前の時と同じようにベランダから一喝。それによりケンジは我に返り、強引にジョンの首輪を掴み引っ張って女の子から引きはがしたのだ。
男の子たちは今度こそ本当に老婆に通報されて、警察に補導された。
引き起こしてしまった惨状を考えれば当然だろう。
なおも女の子は錯乱したように手足を振り回し怒鳴り散らしていたが、腕やお腹からは大量の血が流れており顔面は蒼白で、どう考えても元気などとはいえない状態であり、やだやだと抵抗するものの数人の大人にがっちりと抑えつけられて病院へと運ばれて行った。
残された双葉は警察の事情聴取を二時間ほど受け、解放された。
連絡を受けて駆け付けた母親、梨乃と一緒に家に帰った。
それから女の子には一度も会っていない。
女の子の方が、それきり公園に姿を見せなくなったのだ。
そのことは、双葉を落ち込ませた。
わたしを恨んでいるから? だから、来ないの?
大怪我を負わされたことを、恨んでいるから?
いや、そうじゃない。
むしろあの子の方が、責任を感じているんだ。
一緒にいると、またわたしを危ない目にあわせてしまう。そう思っているんだ。
本当は、悪いのはわたしなのに。
なのに、
あれだけの大怪我を負ったというのに、
あの子は絶対にわたしを恨んだりなんかしていない。
たった二ヶ月しか、それもこの公園でしか会わなかったから、あの子の性格をすべて理解しているわけではない。でも、それだけは自信を持っていえる。
あの子は、そういう子なんだ。
それに比べて、わたしは……
0
お気に入りに追加
2
あなたにおすすめの小説

小学生最後の夏休みに近所に住む2つ上のお姉さんとお風呂に入った話
矢木羽研
青春
「……もしよかったら先輩もご一緒に、どうですか?」
「あら、いいのかしら」
夕食を作りに来てくれた近所のお姉さんを冗談のつもりでお風呂に誘ったら……?
微笑ましくも甘酸っぱい、ひと夏の思い出。
※性的なシーンはありませんが裸体描写があるのでR15にしています。
※小説家になろうでも同内容で投稿しています。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

新ブストサル
かつたけい
青春
山野裕子(やまのゆうこ)は佐原南高校に通う二年生。
女子フットサル部の部長だ。
パワフルかつ変態的な裕子であるが、それなりに上手く部をまとめ上げ、大会に臨む。
しかし試合中に、部員であり親友である佐治ケ江優(さじがえゆう)が倒れてしまう。
エースを失った佐原南は……
佐治ケ江が倒れた理由とは……
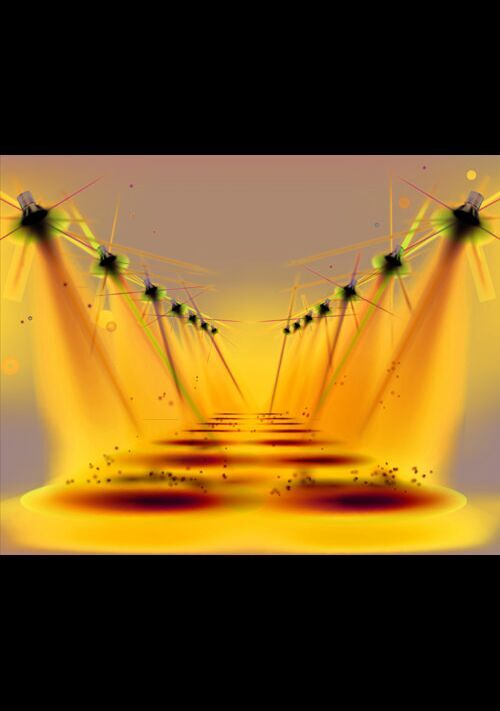
私のなかの、なにか
ちがさき紗季
青春
中学三年生の二月のある朝、川奈莉子の両親は消えた。叔母の曜子に引き取られて、大切に育てられるが、心に刻まれた深い傷は癒えない。そればかりか両親失踪事件をあざ笑う同級生によって、ネットに残酷な書きこみが連鎖し、対人恐怖症になって引きこもる。
やがて自分のなかに芽生える〝なにか〟に気づく莉子。かつては気持ちを満たす幸せの象徴だったそれが、不穏な負の象徴に変化しているのを自覚する。同時に両親が大好きだったビートルズの名曲『Something』を聴くことすらできなくなる。
春が訪れる。曜子の勧めで、独自の教育方針の私立高校に入学。修と咲南に出会い、音楽を通じてどこかに生きているはずの両親に想いを届けようと考えはじめる。
大学一年の夏、莉子は修と再会する。特別な歌声と特異の音域を持つ莉子の才能に気づいていた修の熱心な説得により、ふたたび歌うようになる。その後、修はネットの音楽配信サービスに楽曲をアップロードする。間もなく、二人の世界が動きはじめた。
大手レコード会社の新人発掘プロデューサー澤と出会い、修とともにライブに出演する。しかし、両親の失踪以来、莉子のなかに巣食う不穏な〝なにか〟が膨張し、大勢の観客を前にしてパニックに陥り、倒れてしまう。それでも奮起し、ぎりぎりのメンタルで歌いつづけるものの、さらに難題がのしかかる。音楽フェスのオープニングアクトの出演が決定した。直後、おぼろげに悟る両親の死によって希望を失いつつあった莉子は、プレッシャーからついに心が折れ、プロデビューを辞退するも、曜子から耳を疑う内容の電話を受ける。それは、両親が生きている、という信じがたい話だった。
歌えなくなった莉子は、葛藤や混乱と闘いながら――。

真夏の温泉物語
矢木羽研
青春
山奥の温泉にのんびり浸かっていた俺の前に現れた謎の少女は何者……?ちょっとエッチ(R15)で切ない、真夏の白昼夢。
※2022年8月の「第5回ほっこり・じんわり大賞」にエントリーしていました。

最高の楽園〜私が過ごした3年間の場所〜
Himeri
青春
あなたにとって、1番安心できる場所はどこですか?一緒にいて1番安心できる人は誰ですか?
両親からも見捨てられ、親友にも裏切られた主人公「川峰美香」は中学デビューをしようと張り切っていた。
そして、学園一最高で最強の教師「桜山莉緒」と出会う。
果たして、美香の人生はどんなものになるのか⁉︎性格真逆の2人の物語が始まる

きんのさじ 上巻
かつたけい
青春
時は西暦2023年。
佐治ケ江優(さじがえゆう)は、ベルメッカ札幌に所属し、現役日本代表の女子フットサル選手である。
FWリーグで優勝を果たした彼女は、マイクを突き付けられ頭を真っ白にしながらも過去を回想する。
内気で、陰湿ないじめを受け続け、人間を信じられなかった彼女が、
木村梨乃、
山野裕子、
遠山美奈子、
素晴らしい仲間たちと出会い、心のつぼみを開かせ、強くなっていく。
これは、そんな物語である。

おてんばプロレスの女神たち ~男子で、女子大生で、女子プロレスラーのジュリーという生き方~
ちひろ
青春
おてんば女子大学初の“男子の女子大生”ジュリー。憧れの大学生活では想定外のジレンマを抱えながらも、涼子先輩が立ち上げた女子プロレスごっこ団体・おてんばプロレスで開花し、地元のプロレスファン(特にオッさん連中!)をとりこに。青春派プロレスノベル「おてんばプロレスの女神たち」のアナザーストーリー。

女子高生は卒業間近の先輩に告白する。全裸で。
矢木羽研
恋愛
図書委員の女子高生(小柄ちっぱい眼鏡)が、卒業間近の先輩男子に告白します。全裸で。
女の子が裸になるだけの話。それ以上の行為はありません。
取って付けたようなバレンタインネタあり。
カクヨムでも同内容で公開しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















