お気に入りに追加
72
あなたにおすすめの小説


日本列島、時震により転移す!
黄昏人
ファンタジー
2023年(現在)、日本列島が後に時震と呼ばれる現象により、500年以上の時を超え1492年(過去)の世界に転移した。移転したのは本州、四国、九州とその周辺の島々であり、現在の日本は過去の時代に飛ばされ、過去の日本は現在の世界に飛ばされた。飛ばされた現在の日本はその文明を支え、国民を食わせるためには早急に莫大な資源と食料が必要である。過去の日本は現在の世界を意識できないが、取り残された北海道と沖縄は国富の大部分を失い、戦国日本を抱え途方にくれる。人々は、政府は何を思いどうふるまうのか。

クラス転移で無能判定されて追放されたけど、努力してSSランクのチートスキルに進化しました~【生命付与】スキルで異世界を自由に楽しみます~
いちまる
ファンタジー
ある日、クラスごと異世界に召喚されてしまった少年、天羽イオリ。
他のクラスメートが強力なスキルを発現させてゆく中、イオリだけが最低ランクのEランクスキル【生命付与】の持ち主だと鑑定される。
「無能は不要だ」と判断した他の生徒や、召喚した張本人である神官によって、イオリは追放され、川に突き落とされた。
しかしそこで、川底に沈んでいた謎の男の力でスキルを強化するチャンスを得た――。
1千年の努力とともに、イオリのスキルはSSランクへと進化!
自分を拾ってくれた田舎町のアイテムショップで、チートスキルをフル稼働!
「転移者が世界を良くする?」
「知らねえよ、俺は異世界を自由気ままに楽しむんだ!」
追放された少年の第2の人生が、始まる――!
※本作品は他サイト様でも掲載中です。

ユーヤのお気楽異世界転移
暇野無学
ファンタジー
死因は神様の当て逃げです! 地震による事故で死亡したのだが、原因は神社の扁額が当たっての即死。問題の神様は気まずさから俺を輪廻の輪から外し、異世界の神に俺をゆだねた。異世界への移住を渋る俺に、神様特典付きで異世界へ招待されたが・・・ この神様が超適当な健忘症タイプときた。

【完結】結婚前から愛人を囲う男の種などいりません!
つくも茄子
ファンタジー
伯爵令嬢のフアナは、結婚式の一ヶ月前に婚約者の恋人から「私達愛し合っているから婚約を破棄しろ」と怒鳴り込まれた。この赤毛の女性は誰?え?婚約者のジョアンの恋人?初耳です。ジョアンとは従兄妹同士の幼馴染。ジョアンの父親である侯爵はフアナの伯父でもあった。怒り心頭の伯父。されどフアナは夫に愛人がいても一向に構わない。というよりも、結婚一ヶ月前に破棄など常識に考えて無理である。無事に結婚は済ませたものの、夫は新妻を蔑ろにする。何か勘違いしているようですが、伯爵家の世継ぎは私から生まれた子供がなるんですよ?父親?別に書類上の夫である必要はありません。そんな、フアナに最高の「種」がやってきた。
他サイトにも公開中。
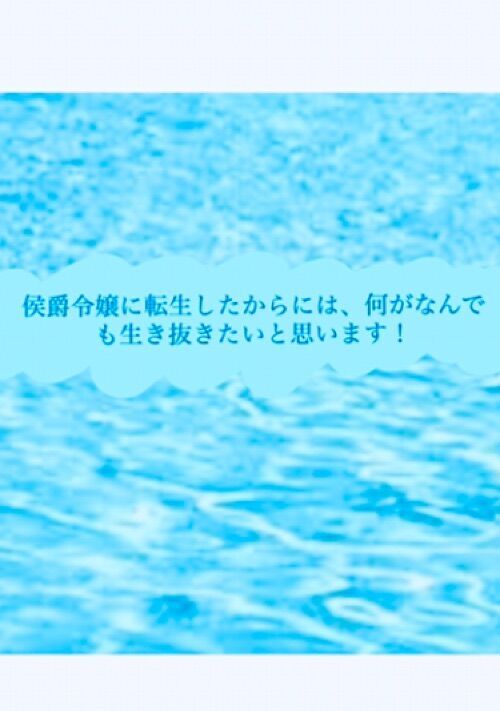
侯爵令嬢に転生したからには、何がなんでも生き抜きたいと思います!
珂里
ファンタジー
侯爵令嬢に生まれた私。
3歳のある日、湖で溺れて前世の記憶を思い出す。
高校に入学した翌日、川で溺れていた子供を助けようとして逆に私が溺れてしまった。
これからハッピーライフを満喫しようと思っていたのに!!
転生したからには、2度目の人生何がなんでも生き抜いて、楽しみたいと思います!!!

【完結】剣聖の娘はのんびりと後宮暮らしを楽しむ
O.T.I
ファンタジー
かつて王国騎士団にその人ありと言われた剣聖ジスタルは、とある事件をきっかけに引退して辺境の地に引き籠もってしまった。
それから時が過ぎ……彼の娘エステルは、かつての剣聖ジスタルをも超える剣の腕を持つ美少女だと、辺境の村々で噂になっていた。
ある時、その噂を聞きつけた辺境伯領主に呼び出されたエステル。
彼女の実力を目の当たりにした領主は、彼女に王国の騎士にならないか?と誘いかける。
剣術一筋だった彼女は、まだ見ぬ強者との出会いを夢見てそれを了承するのだった。
そして彼女は王都に向かい、騎士となるための試験を受けるはずだったのだが……

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















