お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説


白雉の微睡
葛西秋
歴史・時代
中大兄皇子と中臣鎌足による古代律令制度への政治改革、大化の改新。乙巳の変前夜から近江大津宮遷都までを辿る古代飛鳥の物語。
――馬が足りない。兵が足りない。なにもかも、戦のためのものが全て足りない。
飛鳥の宮廷で中臣鎌子が受け取った葛城王の木簡にはただそれだけが書かれていた。唐と新羅の連合軍によって滅亡が目前に迫る百済。その百済からの援軍要請を満たすための数千騎が揃わない。百済が完全に滅亡すれば唐は一気に倭国に攻めてくるだろう。だがその唐の軍勢を迎え撃つだけの戦力を倭国は未だ備えていなかった。古代に起きた国家存亡の危機がどのように回避されたのか、中大兄皇子と中臣鎌足の視点から描く古代飛鳥の歴史物語。
主要な登場人物:
葛城王(かつらぎおう)……中大兄皇子。のちの天智天皇、中臣鎌子(なかとみ かまこ)……中臣鎌足。藤原氏の始祖。王族の祭祀を司る中臣連を出自とする


夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~
恩地玖
歴史・時代
位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。
一体、これまで成してきたことは何だったのか。
医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。
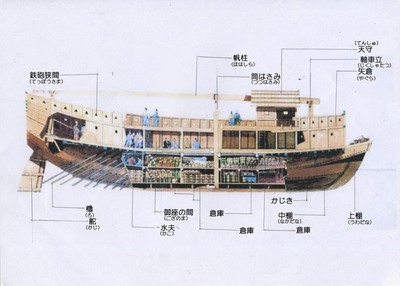

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記
颯野秋乃
歴史・時代
1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。
ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。
また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。
その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。
この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。
またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。
この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…
大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。
【重要】
不定期更新。超絶不定期更新です。

江戸時代改装計画
華研えねこ
歴史・時代
皇紀2603年7月4日、大和甲板にて。皮肉にもアメリカが独立したとされる日にアメリカ史上最も屈辱的である条約は結ばれることになった。
「では大統領、この降伏文書にサインして貰いたい。まさかペリーを派遣した君等が嫌とは言うまいね?」
頭髪を全て刈り取った男が日本代表として流暢なキングズ・イングリッシュで話していた。後に「白人から世界を解放した男」として讃えられる有名人、石原莞爾だ。
ここはトラック、言うまでも無く日本の内南洋であり、停泊しているのは軍艦大和。その後部甲板でルーズベルトは憤死せんがばかりに震えていた。
(何故だ、どうしてこうなった……!!)
自問自答するも答えは出ず、一年以内には火刑に処される彼はその人生最期の一年を巧妙に憤死しないように体調を管理されながら過ごすことになる。
トラック講和条約と称される講和条約の内容は以下の通り。
・アメリカ合衆国は満州国を承認
・アメリカ合衆国は、ウェーキ島、グアム島、アリューシャン島、ハワイ諸島、ライン諸島を大日本帝国へ割譲
・アメリカ合衆国はフィリピンの国際連盟委任独立準備政府設立の承認
・アメリカ合衆国は大日本帝国に戦費賠償金300億ドルの支払い
・アメリカ合衆国の軍備縮小
・アメリカ合衆国の関税自主権の撤廃
・アメリカ合衆国の移民法の撤廃
・アメリカ合衆国首脳部及び戦争煽動者は国際裁判の判決に従うこと
確かに、多少は苛酷な内容であったが、「最も屈辱」とは少々大げさであろう。何せ、彼らの我々の世界に於ける悪行三昧に比べたら、この程度で済んだことに感謝するべきなのだから……。

日本が危機に?第二次日露戦争
杏
歴史・時代
2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。
なろう、カクヨムでも連載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















