21 / 210
一の段 あやめも知らぬ 動揺(一)
しおりを挟む
「御寮人さま、春はまだ来ませぬか。」
トクがあきれ果てたような声を出した。丁稚とはいえその聡さを認められつつある少年は、人の目のないところでは、大好きな女主人に、少し狎れた物言いで話しかけてしまう。
「まだまだとのことじゃ。近江の冬も長かったであろう?」
「左様ではございますが……。儂は、いえ、トクは、あまりそんなことを考える暇もございませんでした。」
この孤児らしい少年の、小僧ですらない、寺の単なる奴婢として雨露だけようやく凌げていた暮らしを想像して、あやめは胸がふさがる思いがしたが、
「おやおや? お前、いまは、暇かえ?」
と釘をさした。女主人がふと倉を見に来たのを邪魔して、油を売るようではいけないだろう。
「滅相もございませぬ。お許しください。今日のお店のお仕事は、片をつけられたもので。……」
(この子は頭の巡りが早く、器用なのだな。あてがうべき仕事が、もっと要るか。)
「トクのような者が、早く春が来てほしいなどと考えられるようになりましたのは、御寮人さまのおかげというのを、申したかったので。」
頭をあげ、あやめをまっすぐに見上げた。なにか命じて欲しい様子だ。
あやめは寒気の中で頬が赤らむのを感じたが、よい、手が空いてはいるようだが、なにか仕事はないかと店の中をまず自分でさがすくらいになりなさい、と訓戒を垂れた。
「御寮人さまにお客様でございますわ。」と小女のひとり、ミツがやってきた。「御曹司さまにございます。」
「御曹司さまか。」
トクは喜んだ。少年はひどくませているようで、まだ子どもであったから、御寮人さまと大の仲良しの御曹司さまも大好きなのだ。
「お前には言うておらん。」
ミツはもうそうした面では大人になってしまっているので、若い男女の仲に興味がある。女主人の顔を盗み見た。
そして、なんとまあ、大店の御主人さまのくせにお可愛らしいことよ、と内心で舌を出した。御寮人さまは普段、渋面をつくるときもあり、使用人にも決して無闇に甘くはないのだが……。
だが、いつものように書院の上座に座った十四郎が、どこかうつろな表情だ。笑みも固い。
(これは不機嫌なのか。こんな御曹司さまは、はじめてみるのではないか。)
それに、抱えてきたらしい、長い袱紗の包みは、あれは鉄砲ではないのか。
人目をはばかる様子だ。気を回して、茶室に案内する。
火の気が絶え、寒い室内だが、今のあやめは十四郎の只事ならぬ様子に気をとられている。十四郎も寒気は気にならないようだ。
「御寮人殿に、御検分いただきたい。」
包みをほどくと、やはり一丁の古びた火縄銃であった。
(しかし、……これは?)
一礼して受け取ったあやめははっとしたが、十四郎の緊張した表情に、決して何かの戯れではないのだとあらためて考えた。
「お見知りおきいただいております、コハルという家の者にも見せてよろしいでしょうか。」
「コハル殿か。……ということは、使えるものであろうか?」
この鉄砲は、というのである。
「それを、確かめさせましょう。」
念のために、という言葉をのみこんで、あやめはコハルを呼ばせようと立ち上がりかけたが、案の定、上り口の外にコハルはすでに控えていた。
手回しのよいことに、もう一人いる。店には見たことのない顔である。
「この者は、こうした道具に詳しうございまして。」
(道具だけではあるまい。おそらく、撃つ方も手練れの男。)
あやめは、コハルが短期間に多くの容易ならぬ技能をもった者を呼び寄せ、この地にそうした者たちの組織をひそかに作ってしまったことに、あらためて舌を巻いている。
思えば、堺で急速に頭角を現した今井宗久が、他の豪商たちに勝っていたのは、こうした情報と謀略を駆使する点であった。
あやめにいわせれば、もとは武家の出だったという父にせよその養父たる祖父にせよ、商いの仕方にまともでないところがあるのだと思っていた。はたして自分にそれができるか、というのがあやめの秘かに深刻な悩みだった。
だが、いまはとりあえずコハルの仕事は役に立つ。
糸のように目の細い男は、それを一層細くして火縄銃をただためつ、すがめつするばかりだったが、やがて銃身を折るようにして簡単な解体を目にも留まらぬ速さで行い、すぐに銃を元のように組み立て直した。それをコハルに丁寧に渡すと、あやめに一礼して一人出ていく。
「お使いにはなれぬ、ということでございます。」
コハルが、男の代わりにいった。コハルにもわかっていたし、正直のところ、あやめですら、すぐにこの鉄砲が使い物にならぬ品だと感づいていた。
「やはり、壊れておったか。そして、今井殿といえども、なおせぬのだな。」
「いえ、なおす、なおさぬ、というものではなく……」
「御曹司さまは、このようなものをどこで?」
「すまぬ。それはいえぬ。」
「では、結構でございます。御曹司さま、納屋の考えでは、これは一度もまともに使えたものではございますまい。よくできておりますが、鉄砲の恰好をしているだけのものでございます。」
十四郎の表情が苦笑いに落ち着くまでに、随分時間がかかった。まがい物を売りつけられ、騙されて口惜しい、というのとももっと違う、憤りに似た感情が渦巻いたようであった。
(ああ、この御表情は見たことがある。アイノの話をしているときに、ときに抑えられず出るものではないか。)
協約が和人の手で破られ、アイノが取引で不当に扱われることがあるという話、和人商人がアイノの無知につけこんでうまくやったと自慢した話のときに、ときどき十四郎の顔に浮かぶものだ。
(義憤、という言葉があるが……)と、そんなときにあやめはひそかに思った。(この人のは、それとも少し違うな。やはり、こんなお顔をした人ゆえか? 蝦夷の血を引いているから、他人事とは思えないのじゃろうか。つまり、怨み……?)
「アイノが誰か和人の商人に売りつけられていたものだったのでしょうか。」
「……そのようなところでござる。まったく、悪い奴もいるものよ。拙者も、まんまと」
「十四郎さまっ。」
あやめは、叱咤するように叫んだ。しかも、子どもを呼ぶように武家をその名で呼んでしまったが、その無礼にも気づかない。
「これからは、決してその商家から出た鉄砲にはお手を出されませんように。」
「……? は、うむ、そう、いたそう。」
「鉄砲なら、納屋が、いくらでもご用立ていたしまする。」
立ち上がった。いや、とまた座り、コハル、とやや高くなった声で命じた。
「弥兵衛に伝えなさい。いまあるだけの鉄砲をお出しせよ。」
「御寮人さま?」
「構わぬ。すべてお渡しする。」
「そう申されましても、今でも、お倉に」声を潜めた。「二、三丁では済みますまい。さらにあるところから持って参れますが、この御茶室に積み上げるのも、なりますまい。」
「左様よの。では、倉までご足労いただく。……じゅ、いえ、……御曹司さま。」
「いや、それほどの持ち合わせはござらぬ。それに、御寮人殿、今まではさんざん出し惜しみされていたものが、急に……」
「急でなければならないのでは、ござりませぬか?」
「……。」
「御曹司さま。納屋は鉄砲をご用立てするとお約束いたしましたので、お待たせいたしましたが、今、いくらでもお入用の分をお渡しいたします。お代は無論、後からで結構でござります。」
「御寮人さま。鉄砲は一丁百貫文を下りませぬ。」
「知らぬわけではない。控えよ。……御曹司さまもその時、お約束なさいました。なぜ、鉄砲がお入用なのか、お教えくださると。」
「……」
「五十丁でも百丁でも、もしも購えるものなら厭わぬご様子。備えや楽しみに一丁が持ちたいというご様子でもない。なぜ、それほどの数がお入用なのです。」
「……」
「お代官さまのお倉にお納めになろうというのではありますまい。お教えくださいましたら、いつでも何丁でもお持ちになられましても、結構で。ではござりますが、……」
「承知した。申し上げよう。……コハル殿もここにおられよ。」
あやめは知らず、躰を十四郎に傾けて近づく。
「拙者は、アイノに鉄砲を持たせたい。」
あやめは息を呑み、あらかたのことがわかってしまったと思った。
かつて、アイノの武力は和人を圧倒してきた。兵の数といい、その短弓の威力といい、渡党などの「和人」は、まるで及ぶところではなかった。鋼の刀と馬をもってしても、堂々たる武力衝突では常にアイノに敗北してきた。
蠣崎家は、常に戦後処理の騙し討ちでしか、息を接げなかった。戦闘ではさんざんに敗れ、賠償と講和の宴会の席で首長を謀殺してしまい、なんとかしたのが常である。
近くは蠣崎季広の歴史的な妥協の背景も、この弱さにあった。
それが急転換しようとしているのは、「和人」側の鉄砲の導入である。火縄銃という武器の性能、ということもあるが、それだけではない。
銃を集団的に使用しようと試みること自体が、戦術をこえて戦略を変えていき、やがて武家集団のありかたにも根本的な変化をもたらしている。その端的なあらわれが、諸地方の群雄割拠であり、そしてそこからこそ飛躍できた結末といえる中央新政権の台頭、すなわち上方を抑えた織田家権力の成立であったといえる。
蝦夷島のこの半島の南部に張りついた渡党の勢力にも、戦術的なものを越えた変化が生じている。まだ後年ほどでもない鉄砲の威力がもたらすものなど以上に、それは大きい。
そこにあるのは、天下の情勢に急き立てられ、蝦夷島にも統一的な軍事権力を確立しようとする意志そのものであった。現在の蝦夷代官名代・蠣崎慶広の政治姿勢が、まさにそのあらわれである。
蠣崎慶広は個人的には刀槍の武術に優れていたが、その反面で、まとまった数の鉄砲を使用したがっている。現に松前納屋からは、できる限りの鉄砲を買い集めつつある。これを軸にする、蠣崎家中の戦闘集団としての再編と強化を、代官名代はすでに図りつつあった。(その成果を、ほどなくあやめは自分の身に降りかかる災難として生々しく経験してしまうが、このときは想像だにできないことだった。)
一方でアイノは、毒矢の短弓の性能を信じて、誇り高い戦士はなかなか鉄砲を使おうとしないのだという。
十四郎が、アイノに鉄砲を持たせたいというのは、そのあたりのことであろう。アイノに、伸びつつある和人の組織的な武力に対抗できる、新鮮な力を与えたいに違いない。
だが、それはつまり、次代の当主であろう蠣崎新三郎慶広と対決することになるではないのか。
(謀反……っ?)
ということにもなる。あやめは、次の言葉を待った。
しかし、十四郎は何もいわない。
「お聞きいたします。……持たせて、どうなさいますか? 何をなさるおつもりで?」
「それまでも、いわねばならぬか。」
「お願い申し上げまする。決して、決して他言申すものではござりませぬ。」
「……」
「堺の商人は口が堅いが信条。今井をご信用くださりませんか。」
「……」
「手前を……あやめをお信じくださりませっ。」
「御寮人殿は、ご存じになるべきにもあらず。」
(巻き込みたくないというのか……?)
そういえばある時から、十四郎が冗談にも鉄砲の話をしなくなっていたことをあやめは思い出していた。
ふとコハルの控えているほうをふりむくと、頷いてみせる。
十四郎は立ち上がった。畳の上の鉄砲―の形をしたもの―に気づくと、袋だけとって、
「今日もお構いくださり、まことに痛み入った。これは差し上げる。なにかのお役に立つといいが、……まあ、ごみだな。あい済まぬ、捨てておいてくださいますよう。」
「御曹司さま。」
「ああ、十四郎とお呼びくだされ。その方が、うれしかった。」
「それは、……はい。十四郎さま……十四郎さま、また、必ずお越しくださいっ。」
小さく叫んだ。これで二度と会えなくなるかもしれない、と思うと、気が狂いそうだ。
「忙しくなるかもしれぬが、必ず、左様いたそう。」
笑った。そして、では、と立ち上がったとき、あやめは顔をみつめられた気がしてならない。
十四郎を見送ると、後ろに立っているだろうコハルに、そのままの姿勢で問う。
「なにか、わかっていたか。」
「ぬかりました。お許しくださいませ。」
「いや。なんといっても、蠣崎のお家―大舘のなかのことじゃ。だが、わたくしも同じ。浮かれておった。」
寂しく笑ったようだ。後姿だが、それは以前のあやめがよくみせた表情だから、コハルにはそれが見える。
「御寮人さま。どうかお許しくだされ。」
コハルは自分を責めている。どうして、この冬にも十四郎を今井に婿入りさせなかったか。
あの二人がいかに雅くとも躰は大人、のっぴきならぬところに若い男女を追い込んで、奥手の女主人が、異相長躯の想い人を松前納屋の婿にとるようにしてしまうことも、自分たちの術ならば不可能ではなかったのに……。蝦夷地の寒さに震えながら、花鳥の使い(恋の仲立ち役)を気取って暢気に見守るつもりでいた自分は呆けていたと思った。
(しかし、もはや、遅いかも知れぬ。)
「遅くはないぞ。」
「はい。」
「あのお方をお助けするために、松前納屋が、いや堺の今井家ができることはあろう。なにであろうと、これから、それをみつける。」
「蠣崎のお家の中なれど、手はないではない。コハルに既に考えがございます。」
「大儀。」
「それにしても、しばし、動きを待たねばなりますまい。よろしうございましょうか。」
「やむをえぬ。間に合えばよい。……それに、何に間に合えばよいのかすら、まだわからんのではな。」
夕闇が、女主人の背中を包みはじめた。
トクがあきれ果てたような声を出した。丁稚とはいえその聡さを認められつつある少年は、人の目のないところでは、大好きな女主人に、少し狎れた物言いで話しかけてしまう。
「まだまだとのことじゃ。近江の冬も長かったであろう?」
「左様ではございますが……。儂は、いえ、トクは、あまりそんなことを考える暇もございませんでした。」
この孤児らしい少年の、小僧ですらない、寺の単なる奴婢として雨露だけようやく凌げていた暮らしを想像して、あやめは胸がふさがる思いがしたが、
「おやおや? お前、いまは、暇かえ?」
と釘をさした。女主人がふと倉を見に来たのを邪魔して、油を売るようではいけないだろう。
「滅相もございませぬ。お許しください。今日のお店のお仕事は、片をつけられたもので。……」
(この子は頭の巡りが早く、器用なのだな。あてがうべき仕事が、もっと要るか。)
「トクのような者が、早く春が来てほしいなどと考えられるようになりましたのは、御寮人さまのおかげというのを、申したかったので。」
頭をあげ、あやめをまっすぐに見上げた。なにか命じて欲しい様子だ。
あやめは寒気の中で頬が赤らむのを感じたが、よい、手が空いてはいるようだが、なにか仕事はないかと店の中をまず自分でさがすくらいになりなさい、と訓戒を垂れた。
「御寮人さまにお客様でございますわ。」と小女のひとり、ミツがやってきた。「御曹司さまにございます。」
「御曹司さまか。」
トクは喜んだ。少年はひどくませているようで、まだ子どもであったから、御寮人さまと大の仲良しの御曹司さまも大好きなのだ。
「お前には言うておらん。」
ミツはもうそうした面では大人になってしまっているので、若い男女の仲に興味がある。女主人の顔を盗み見た。
そして、なんとまあ、大店の御主人さまのくせにお可愛らしいことよ、と内心で舌を出した。御寮人さまは普段、渋面をつくるときもあり、使用人にも決して無闇に甘くはないのだが……。
だが、いつものように書院の上座に座った十四郎が、どこかうつろな表情だ。笑みも固い。
(これは不機嫌なのか。こんな御曹司さまは、はじめてみるのではないか。)
それに、抱えてきたらしい、長い袱紗の包みは、あれは鉄砲ではないのか。
人目をはばかる様子だ。気を回して、茶室に案内する。
火の気が絶え、寒い室内だが、今のあやめは十四郎の只事ならぬ様子に気をとられている。十四郎も寒気は気にならないようだ。
「御寮人殿に、御検分いただきたい。」
包みをほどくと、やはり一丁の古びた火縄銃であった。
(しかし、……これは?)
一礼して受け取ったあやめははっとしたが、十四郎の緊張した表情に、決して何かの戯れではないのだとあらためて考えた。
「お見知りおきいただいております、コハルという家の者にも見せてよろしいでしょうか。」
「コハル殿か。……ということは、使えるものであろうか?」
この鉄砲は、というのである。
「それを、確かめさせましょう。」
念のために、という言葉をのみこんで、あやめはコハルを呼ばせようと立ち上がりかけたが、案の定、上り口の外にコハルはすでに控えていた。
手回しのよいことに、もう一人いる。店には見たことのない顔である。
「この者は、こうした道具に詳しうございまして。」
(道具だけではあるまい。おそらく、撃つ方も手練れの男。)
あやめは、コハルが短期間に多くの容易ならぬ技能をもった者を呼び寄せ、この地にそうした者たちの組織をひそかに作ってしまったことに、あらためて舌を巻いている。
思えば、堺で急速に頭角を現した今井宗久が、他の豪商たちに勝っていたのは、こうした情報と謀略を駆使する点であった。
あやめにいわせれば、もとは武家の出だったという父にせよその養父たる祖父にせよ、商いの仕方にまともでないところがあるのだと思っていた。はたして自分にそれができるか、というのがあやめの秘かに深刻な悩みだった。
だが、いまはとりあえずコハルの仕事は役に立つ。
糸のように目の細い男は、それを一層細くして火縄銃をただためつ、すがめつするばかりだったが、やがて銃身を折るようにして簡単な解体を目にも留まらぬ速さで行い、すぐに銃を元のように組み立て直した。それをコハルに丁寧に渡すと、あやめに一礼して一人出ていく。
「お使いにはなれぬ、ということでございます。」
コハルが、男の代わりにいった。コハルにもわかっていたし、正直のところ、あやめですら、すぐにこの鉄砲が使い物にならぬ品だと感づいていた。
「やはり、壊れておったか。そして、今井殿といえども、なおせぬのだな。」
「いえ、なおす、なおさぬ、というものではなく……」
「御曹司さまは、このようなものをどこで?」
「すまぬ。それはいえぬ。」
「では、結構でございます。御曹司さま、納屋の考えでは、これは一度もまともに使えたものではございますまい。よくできておりますが、鉄砲の恰好をしているだけのものでございます。」
十四郎の表情が苦笑いに落ち着くまでに、随分時間がかかった。まがい物を売りつけられ、騙されて口惜しい、というのとももっと違う、憤りに似た感情が渦巻いたようであった。
(ああ、この御表情は見たことがある。アイノの話をしているときに、ときに抑えられず出るものではないか。)
協約が和人の手で破られ、アイノが取引で不当に扱われることがあるという話、和人商人がアイノの無知につけこんでうまくやったと自慢した話のときに、ときどき十四郎の顔に浮かぶものだ。
(義憤、という言葉があるが……)と、そんなときにあやめはひそかに思った。(この人のは、それとも少し違うな。やはり、こんなお顔をした人ゆえか? 蝦夷の血を引いているから、他人事とは思えないのじゃろうか。つまり、怨み……?)
「アイノが誰か和人の商人に売りつけられていたものだったのでしょうか。」
「……そのようなところでござる。まったく、悪い奴もいるものよ。拙者も、まんまと」
「十四郎さまっ。」
あやめは、叱咤するように叫んだ。しかも、子どもを呼ぶように武家をその名で呼んでしまったが、その無礼にも気づかない。
「これからは、決してその商家から出た鉄砲にはお手を出されませんように。」
「……? は、うむ、そう、いたそう。」
「鉄砲なら、納屋が、いくらでもご用立ていたしまする。」
立ち上がった。いや、とまた座り、コハル、とやや高くなった声で命じた。
「弥兵衛に伝えなさい。いまあるだけの鉄砲をお出しせよ。」
「御寮人さま?」
「構わぬ。すべてお渡しする。」
「そう申されましても、今でも、お倉に」声を潜めた。「二、三丁では済みますまい。さらにあるところから持って参れますが、この御茶室に積み上げるのも、なりますまい。」
「左様よの。では、倉までご足労いただく。……じゅ、いえ、……御曹司さま。」
「いや、それほどの持ち合わせはござらぬ。それに、御寮人殿、今まではさんざん出し惜しみされていたものが、急に……」
「急でなければならないのでは、ござりませぬか?」
「……。」
「御曹司さま。納屋は鉄砲をご用立てするとお約束いたしましたので、お待たせいたしましたが、今、いくらでもお入用の分をお渡しいたします。お代は無論、後からで結構でござります。」
「御寮人さま。鉄砲は一丁百貫文を下りませぬ。」
「知らぬわけではない。控えよ。……御曹司さまもその時、お約束なさいました。なぜ、鉄砲がお入用なのか、お教えくださると。」
「……」
「五十丁でも百丁でも、もしも購えるものなら厭わぬご様子。備えや楽しみに一丁が持ちたいというご様子でもない。なぜ、それほどの数がお入用なのです。」
「……」
「お代官さまのお倉にお納めになろうというのではありますまい。お教えくださいましたら、いつでも何丁でもお持ちになられましても、結構で。ではござりますが、……」
「承知した。申し上げよう。……コハル殿もここにおられよ。」
あやめは知らず、躰を十四郎に傾けて近づく。
「拙者は、アイノに鉄砲を持たせたい。」
あやめは息を呑み、あらかたのことがわかってしまったと思った。
かつて、アイノの武力は和人を圧倒してきた。兵の数といい、その短弓の威力といい、渡党などの「和人」は、まるで及ぶところではなかった。鋼の刀と馬をもってしても、堂々たる武力衝突では常にアイノに敗北してきた。
蠣崎家は、常に戦後処理の騙し討ちでしか、息を接げなかった。戦闘ではさんざんに敗れ、賠償と講和の宴会の席で首長を謀殺してしまい、なんとかしたのが常である。
近くは蠣崎季広の歴史的な妥協の背景も、この弱さにあった。
それが急転換しようとしているのは、「和人」側の鉄砲の導入である。火縄銃という武器の性能、ということもあるが、それだけではない。
銃を集団的に使用しようと試みること自体が、戦術をこえて戦略を変えていき、やがて武家集団のありかたにも根本的な変化をもたらしている。その端的なあらわれが、諸地方の群雄割拠であり、そしてそこからこそ飛躍できた結末といえる中央新政権の台頭、すなわち上方を抑えた織田家権力の成立であったといえる。
蝦夷島のこの半島の南部に張りついた渡党の勢力にも、戦術的なものを越えた変化が生じている。まだ後年ほどでもない鉄砲の威力がもたらすものなど以上に、それは大きい。
そこにあるのは、天下の情勢に急き立てられ、蝦夷島にも統一的な軍事権力を確立しようとする意志そのものであった。現在の蝦夷代官名代・蠣崎慶広の政治姿勢が、まさにそのあらわれである。
蠣崎慶広は個人的には刀槍の武術に優れていたが、その反面で、まとまった数の鉄砲を使用したがっている。現に松前納屋からは、できる限りの鉄砲を買い集めつつある。これを軸にする、蠣崎家中の戦闘集団としての再編と強化を、代官名代はすでに図りつつあった。(その成果を、ほどなくあやめは自分の身に降りかかる災難として生々しく経験してしまうが、このときは想像だにできないことだった。)
一方でアイノは、毒矢の短弓の性能を信じて、誇り高い戦士はなかなか鉄砲を使おうとしないのだという。
十四郎が、アイノに鉄砲を持たせたいというのは、そのあたりのことであろう。アイノに、伸びつつある和人の組織的な武力に対抗できる、新鮮な力を与えたいに違いない。
だが、それはつまり、次代の当主であろう蠣崎新三郎慶広と対決することになるではないのか。
(謀反……っ?)
ということにもなる。あやめは、次の言葉を待った。
しかし、十四郎は何もいわない。
「お聞きいたします。……持たせて、どうなさいますか? 何をなさるおつもりで?」
「それまでも、いわねばならぬか。」
「お願い申し上げまする。決して、決して他言申すものではござりませぬ。」
「……」
「堺の商人は口が堅いが信条。今井をご信用くださりませんか。」
「……」
「手前を……あやめをお信じくださりませっ。」
「御寮人殿は、ご存じになるべきにもあらず。」
(巻き込みたくないというのか……?)
そういえばある時から、十四郎が冗談にも鉄砲の話をしなくなっていたことをあやめは思い出していた。
ふとコハルの控えているほうをふりむくと、頷いてみせる。
十四郎は立ち上がった。畳の上の鉄砲―の形をしたもの―に気づくと、袋だけとって、
「今日もお構いくださり、まことに痛み入った。これは差し上げる。なにかのお役に立つといいが、……まあ、ごみだな。あい済まぬ、捨てておいてくださいますよう。」
「御曹司さま。」
「ああ、十四郎とお呼びくだされ。その方が、うれしかった。」
「それは、……はい。十四郎さま……十四郎さま、また、必ずお越しくださいっ。」
小さく叫んだ。これで二度と会えなくなるかもしれない、と思うと、気が狂いそうだ。
「忙しくなるかもしれぬが、必ず、左様いたそう。」
笑った。そして、では、と立ち上がったとき、あやめは顔をみつめられた気がしてならない。
十四郎を見送ると、後ろに立っているだろうコハルに、そのままの姿勢で問う。
「なにか、わかっていたか。」
「ぬかりました。お許しくださいませ。」
「いや。なんといっても、蠣崎のお家―大舘のなかのことじゃ。だが、わたくしも同じ。浮かれておった。」
寂しく笑ったようだ。後姿だが、それは以前のあやめがよくみせた表情だから、コハルにはそれが見える。
「御寮人さま。どうかお許しくだされ。」
コハルは自分を責めている。どうして、この冬にも十四郎を今井に婿入りさせなかったか。
あの二人がいかに雅くとも躰は大人、のっぴきならぬところに若い男女を追い込んで、奥手の女主人が、異相長躯の想い人を松前納屋の婿にとるようにしてしまうことも、自分たちの術ならば不可能ではなかったのに……。蝦夷地の寒さに震えながら、花鳥の使い(恋の仲立ち役)を気取って暢気に見守るつもりでいた自分は呆けていたと思った。
(しかし、もはや、遅いかも知れぬ。)
「遅くはないぞ。」
「はい。」
「あのお方をお助けするために、松前納屋が、いや堺の今井家ができることはあろう。なにであろうと、これから、それをみつける。」
「蠣崎のお家の中なれど、手はないではない。コハルに既に考えがございます。」
「大儀。」
「それにしても、しばし、動きを待たねばなりますまい。よろしうございましょうか。」
「やむをえぬ。間に合えばよい。……それに、何に間に合えばよいのかすら、まだわからんのではな。」
夕闇が、女主人の背中を包みはじめた。
0
お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説


白雉の微睡
葛西秋
歴史・時代
中大兄皇子と中臣鎌足による古代律令制度への政治改革、大化の改新。乙巳の変前夜から近江大津宮遷都までを辿る古代飛鳥の物語。
――馬が足りない。兵が足りない。なにもかも、戦のためのものが全て足りない。
飛鳥の宮廷で中臣鎌子が受け取った葛城王の木簡にはただそれだけが書かれていた。唐と新羅の連合軍によって滅亡が目前に迫る百済。その百済からの援軍要請を満たすための数千騎が揃わない。百済が完全に滅亡すれば唐は一気に倭国に攻めてくるだろう。だがその唐の軍勢を迎え撃つだけの戦力を倭国は未だ備えていなかった。古代に起きた国家存亡の危機がどのように回避されたのか、中大兄皇子と中臣鎌足の視点から描く古代飛鳥の歴史物語。
主要な登場人物:
葛城王(かつらぎおう)……中大兄皇子。のちの天智天皇、中臣鎌子(なかとみ かまこ)……中臣鎌足。藤原氏の始祖。王族の祭祀を司る中臣連を出自とする


夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~
恩地玖
歴史・時代
位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。
一体、これまで成してきたことは何だったのか。
医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。
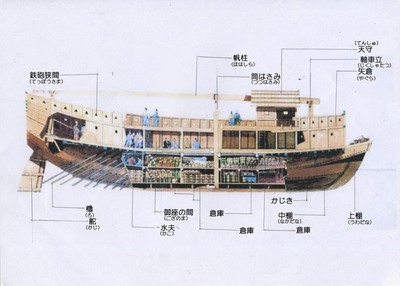

世界はあるべき姿へ戻される 第二次世界大戦if戦記
颯野秋乃
歴史・時代
1929年に起きた、世界を巻き込んだ大恐慌。世界の大国たちはそれからの脱却を目指し、躍起になっていた。第一次世界大戦の敗戦国となったドイツ第三帝国は多額の賠償金に加えて襲いかかる恐慌に国の存続の危機に陥っていた。援助の約束をしたアメリカは恐慌を理由に賠償金の支援を破棄。フランスは、自らを救うために支払いの延期は認めない姿勢を貫く。
ドイツ第三帝国は自らの存続のために、世界に隠しながら軍備の拡張に奔走することになる。
また、極東の国大日本帝国。関係の悪化の一途を辿る日米関係によって受ける経済的打撃に苦しんでいた。
その解決法として提案された大東亜共栄圏。東南アジア諸国及び中国を含めた大経済圏、生存圏の構築に力を注ごうとしていた。
この小説は、ドイツ第三帝国と大日本帝国の2視点で進んでいく。現代では有り得なかった様々なイフが含まれる。それを楽しんで貰えたらと思う。
またこの小説はいかなる思想を賛美、賞賛するものでは無い。
この小説は現代とは似て非なるもの。登場人物は史実には沿わないので悪しからず…
大日本帝国視点は都合上休止中です。気分により再開するらもしれません。
【重要】
不定期更新。超絶不定期更新です。

江戸時代改装計画
華研えねこ
歴史・時代
皇紀2603年7月4日、大和甲板にて。皮肉にもアメリカが独立したとされる日にアメリカ史上最も屈辱的である条約は結ばれることになった。
「では大統領、この降伏文書にサインして貰いたい。まさかペリーを派遣した君等が嫌とは言うまいね?」
頭髪を全て刈り取った男が日本代表として流暢なキングズ・イングリッシュで話していた。後に「白人から世界を解放した男」として讃えられる有名人、石原莞爾だ。
ここはトラック、言うまでも無く日本の内南洋であり、停泊しているのは軍艦大和。その後部甲板でルーズベルトは憤死せんがばかりに震えていた。
(何故だ、どうしてこうなった……!!)
自問自答するも答えは出ず、一年以内には火刑に処される彼はその人生最期の一年を巧妙に憤死しないように体調を管理されながら過ごすことになる。
トラック講和条約と称される講和条約の内容は以下の通り。
・アメリカ合衆国は満州国を承認
・アメリカ合衆国は、ウェーキ島、グアム島、アリューシャン島、ハワイ諸島、ライン諸島を大日本帝国へ割譲
・アメリカ合衆国はフィリピンの国際連盟委任独立準備政府設立の承認
・アメリカ合衆国は大日本帝国に戦費賠償金300億ドルの支払い
・アメリカ合衆国の軍備縮小
・アメリカ合衆国の関税自主権の撤廃
・アメリカ合衆国の移民法の撤廃
・アメリカ合衆国首脳部及び戦争煽動者は国際裁判の判決に従うこと
確かに、多少は苛酷な内容であったが、「最も屈辱」とは少々大げさであろう。何せ、彼らの我々の世界に於ける悪行三昧に比べたら、この程度で済んだことに感謝するべきなのだから……。

日本が危機に?第二次日露戦争
杏
歴史・時代
2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。
なろう、カクヨムでも連載しています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















