お気に入りに追加
1,525
あなたにおすすめの小説

婚約破棄された検品令嬢ですが、冷酷辺境伯の子を身籠りました。 でも本当はお優しい方で毎日幸せです
青空あかな
恋愛
旧題:「荷物検査など誰でもできる」と婚約破棄された検品令嬢ですが、極悪非道な辺境伯の子を身籠りました。でも本当はお優しい方で毎日心が癒されています
チェック男爵家長女のキュリティは、貴重な闇魔法の解呪師として王宮で荷物検査の仕事をしていた。
しかし、ある日突然婚約破棄されてしまう。
婚約者である伯爵家嫡男から、キュリティの義妹が好きになったと言われたのだ。
さらには、婚約者の権力によって検査係の仕事まで義妹に奪われる。
失意の中、キュリティは辺境へ向かうと、極悪非道と噂される辺境伯が魔法実験を行っていた。
目立たず通り過ぎようとしたが、魔法事故が起きて辺境伯の子を身ごもってしまう。
二人は形式上の夫婦となるが、辺境伯は存外優しい人でキュリティは温かい日々に心を癒されていく。
一方、義妹は仕事でミスばかり。
闇魔法を解呪することはおろか見破ることさえできない。
挙句の果てには、闇魔法に呪われた荷物を王宮内に入れてしまう――。
※おかげさまでHOTランキング1位になりました! ありがとうございます!
※ノベマ!様で短編版を掲載中でございます。

落ちぶれて捨てられた侯爵令嬢は辺境伯に求愛される~今からは俺の溺愛ターンだから覚悟して~
しましまにゃんこ
恋愛
年若い辺境伯であるアレクシスは、大嫌いな第三王子ダマスから、自分の代わりに婚約破棄したセシルと新たに婚約を結ぶように頼まれる。実はセシルはアレクシスが長年恋焦がれていた令嬢で。アレクシスは突然のことにとまどいつつも、この機会を逃してたまるかとセシルとの婚約を引き受けることに。
とんとん拍子に話はまとまり、二人はロイター辺境で甘く穏やかな日々を過ごす。少しずつ距離は縮まるものの、時折どこか悲し気な表情を見せるセシルの様子が気になるアレクシス。
「セシルは絶対に俺が幸せにしてみせる!」
だがそんなある日、ダマスからセシルに王都に戻るようにと伝令が来て。セシルは一人王都へ旅立ってしまうのだった。
追いかけるアレクシスと頑なな態度を崩さないセシル。二人の恋の行方は?
すれ違いからの溺愛ハッピーエンドストーリーです。
小説家になろう、他サイトでも掲載しています。
麗しすぎるイラストは汐の音様からいただきました!
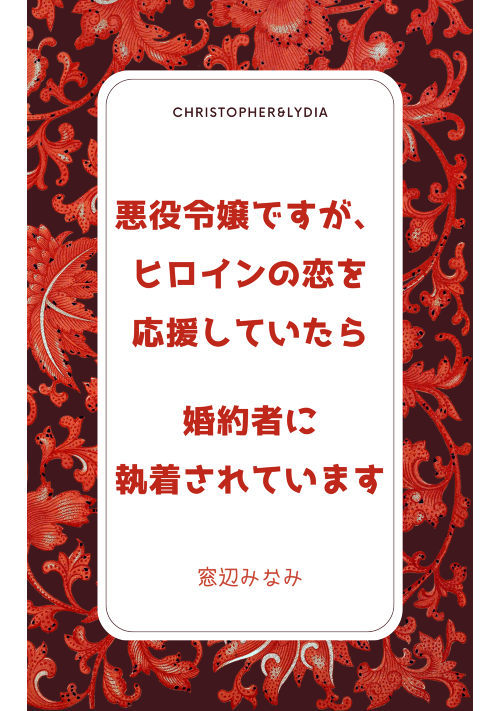
悪役令嬢ですが、ヒロインの恋を応援していたら婚約者に執着されています
窓辺ミナミ
ファンタジー
悪役令嬢の リディア・メイトランド に転生した私。
シナリオ通りなら、死ぬ運命。
だけど、ヒロインと騎士のストーリーが神エピソード! そのスチルを生で見たい!
騎士エンドを見学するべく、ヒロインの恋を応援します!
というわけで、私、悪役やりません!
来たるその日の為に、シナリオを改変し努力を重ねる日々。
あれれ、婚約者が何故か甘く見つめてきます……!
気付けば婚約者の王太子から溺愛されて……。
悪役令嬢だったはずのリディアと、彼女を愛してやまない執着系王子クリストファーの甘い恋物語。はじまりはじまり!

【完結】「聖女として召喚された女子高生、イケメン王子に散々利用されて捨てられる。傷心の彼女を拾ってくれたのは心優しい木こりでした」
まほりろ
恋愛
聖女として召喚された女子高生は、王子との結婚を餌に修行と瘴気の浄化作業に青春の全てを捧げる。
だが瘴気の浄化作業が終わると王子は彼女をあっさりと捨て、若い女に乗
り換えた。
「この世界じゃ十九歳を過ぎて独り身の女は行き遅れなんだよ!」
聖女は「青春返せーー!」と叫ぶがあとの祭り……。
そんな彼女を哀れんだ神が彼女を元の世界に戻したのだが……。
「神様登場遅すぎ! 余計なことしないでよ!」
※無断転載を禁止します。
※朗読動画の無断配信も禁止します。
※他サイトにも投稿しています。
※カクヨム版やpixiv版とは多少ラストが違います。
※小説家になろう版にラスト部分を加筆した物です。
※二章に王子と自称神様へのざまぁがあります。
※二章はアルファポリス先行投稿です!
※表紙素材はあぐりりんこ様よりお借りしております。
「Copyright(C)2022-九頭竜坂まほろん」
※小説家になろうにて、2022/12/14、異世界転生/転移・恋愛・日間ランキング2位まで上がりました! ありがとうございます!
※感想で続編を望む声を頂いたので、続編の投稿を始めました!2022/12/17
※アルファポリス、12/15総合98位、12/15恋愛65位、12/13女性向けホット36位まで上がりました。ありがとうございました。

処刑される未来をなんとか回避したい公爵令嬢と、その公爵令嬢を絶対に処刑したい男爵令嬢のお話
真理亜
恋愛
公爵令嬢のイライザには夢という形で未来を予知する能力があった。その夢の中でイライザは冤罪を着せられ処刑されてしまう。そんな未来を絶対に回避したいイライザは、予知能力を使って未来を変えようと奮闘する。それに対して、男爵令嬢であるエミリアは絶対にイライザを処刑しようと画策する。実は彼女にも譲れない理由があって...

悪役令嬢ってこれでよかったかしら?
砂山一座
恋愛
第二王子の婚約者、テレジアは、悪役令嬢役を任されたようだ。
場に合わせるのが得意な令嬢は、婚約者の王子に、場の流れに、ヒロインの要求に、流されまくっていく。
全11部 完結しました。
サクッと読める悪役令嬢(役)。

【完結】「第一王子に婚約破棄されましたが平気です。私を大切にしてくださる男爵様に一途に愛されて幸せに暮らしますので」
まほりろ
恋愛
学園の食堂で第一王子に冤罪をかけられ、婚約破棄と国外追放を命じられた。
食堂にはクラスメイトも生徒会の仲間も先生もいた。
だが面倒なことに関わりたくないのか、皆見てみぬふりをしている。
誰か……誰か一人でもいい、私の味方になってくれたら……。
そんなとき颯爽?と私の前に現れたのは、ボサボサ頭に瓶底眼鏡のひょろひょろの男爵だった。
彼が私を守ってくれるの?
※ヒーローは最初弱くてかっこ悪いですが、回を重ねるごとに強くかっこよくなっていきます。
※ざまぁ有り、死ネタ有り
※他サイトにも投稿予定。
「Copyright(C)2021-九頭竜坂まほろん」

【完結済】平凡令嬢はぼんやり令息の世話をしたくない
天知 カナイ
恋愛
【完結済 全24話】ヘイデン侯爵の嫡男ロレアントは容姿端麗、頭脳明晰、魔法力に満ちた超優良物件だ。周りの貴族子女はこぞって彼に近づきたがる。だが、ロレアントの傍でいつも世話を焼いているのは、見た目も地味でとりたてて特長もないリオ―チェだ。ロレアントは全てにおいて秀でているが、少し生活能力が薄く、いつもぼんやりとしている。国都にあるタウンハウスが隣だった縁で幼馴染として育ったのだが、ロレアントの母が亡くなる時「ロレンはぼんやりしているから、リオが面倒見てあげてね」と頼んだので、律義にリオ―チェはそれを守り何くれとなくロレアントの世話をしていた。
だが、それが気にくわない人々はたくさんいて様々にリオ―チェに対し嫌がらせをしてくる。だんだんそれに疲れてきたリオーチェは‥。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















