20 / 20
第五章
四、
しおりを挟む
大橋屋敷の櫓の上で、三郎(三法師)は燃え尽きた天王社を見つめていた。
数日前の評定を思いだす。ひと月の猶予を与えたにも関わらず、こちらから反故にするとは何事かと怒りをあらわにする弾正を、五郎左は頑として撥ね付けた。猶予を与えた末に条件を付けられでもしたら不利になるのは我らだ、と言って期日より前の夜討ちを断行したのである。
四半刻ほど櫓に居座った三郎はようやく櫓を降り、梯子の下で待ち受けていた五郎左に率直に言った。
「夜がこんなに明るいとは」
天王社だけではなく、火は津島の町を焼き尽くしている。
毎日のように手習いに通っている三郎の事である、心の奥では悲しみもあるだろうに、それを隠して強がりを言う三郎が、五郎左には愛おしかった。
対して弾正は決して櫓に登ろうとはしなかった。目で見れば感傷的にならざるを得ない。それを排除し、耳からの情報を頼りに冷静に判断が出来るよう努めていた。
津島衆が早尾に向かったと知った弾正は、夜明け前に津島の町も燃やしてしまえと命じた。天王橋を渡ったらその先は敵の領域である。建物に隠れて攻められたら確実に負ける。
口には出さぬが、家中の誰もがこの戦に不安を抱えていた。神の社に火をかけ、神に仕える津島衆に刃を向けることで神の怒りを招かぬかと。
夜が明ければ奴野を出て早尾に向かう。
三郎は櫓を降りた後、屋敷の中で休めと言う五郎左を振り切って、雑兵に交じって屋敷の外で雑魚寝をした。その際三郎は皆を集め、膝を突き合わせて話をした。
「俺らは天王様や津島の町を燃やしたが、あれは神様が作ったもんやないぞ。家も社も、全部人間が勝手に作ったもんや。賢くてずるい人間が神様の家を勝手に作って、そこに人を集め、銭を儲けとる。神様と聞けばみんな手出しできへんで、何百年もの間、富を独り占めしてきた。それが津島衆や」
三郎の言葉を、雑兵たちは食い入るように聞いている。雑兵たちは領内の百姓で、触れが出たためこうして奴野に戦に来たが、なぜ戦をするのかは知らされていない。幼い頃から評定に出続けた三郎は、知らぬことの怖さをよくわかっていた。三郎は続ける。
「津島衆は尾張に住んどるのに、神様のおわす場所やと言うて年貢を納めとらへん。そりゃおかしゅうないか?住んどるのはお前ら百姓と同じ、人間だで。それを神様にかこつけて、自分たちだけ得をしとる」
「そうやそうや」
「そりゃずるいで」
「三郎様の言う通りや」
水を得た魚のように、三郎は尾張弁で続ける。
「神様が尾張に来たなら、尾張のみんなで富を分けあって当然や。だで俺らは戦をしに行く。津島衆がみんなで分け合う言うて約束したら、父上がもう一遍ちゃんとしたお社を建てるで、心配せんでええ。津島衆を打ち負かさんと、ずっと不公平なまんまや。だで、俺らは絶対に勝たなあかんのや」
雑兵たちの目は輝き、笑顔を見せるものさえいた。
神様に対する畏れは正義の戦いへと変わり、皆が抱いていた不安やためらいは見る間に消え去った。
「だで、明日の戦は気張ってや。津島衆は日の本で一番うまい天野酒いう酒を隠し持っとる。勝ったらみんなで飲もうや、天野酒を」
雑兵たちはそろって感嘆の声を上げた。その声は希望と勇気に溢れていた。
三郎が話をしただけで雑兵たちは心を一つにし、士気は一気に高まった。
その様子を屋敷の中からひそかに眺めていた五郎左は、駄々をこねて手を焼かせた幼い頃の三郎の事を思い出し、そっと涙を流した。
翌早暁、弾正は家中総勢三百人ほどの手勢を率い、天王橋を渡った。早尾までは歩いて四半刻ほどである。
津島の町は一面が焦土となっていた。次郎大夫の屋敷も焼け落ちて跡形もない。いつもは参拝や買い物などで早朝から出歩く者が少なからずいるが、今日は人影さえもない。しかしそのおかげでずいぶん遠くまで見渡せるようになっていた。
遠目に早尾の塁が見えてきた。集まった津島衆は二百人ほどで、塁の全面に柵を設けている。弾正勢に気づいた津島衆は矢を番え始めた。
早尾の塁の少し手前で行軍を止めた弾正勢は、先頭に隙間なく盾を並べ、その後ろで雑兵たちが投石の支度を始める。昨夜の三郎のおかげで弾正勢の士気は高い。
軍勢の一番後ろには、騎馬の五郎左と弾正、そして三郎がいる。馬上の五郎左は、塁の中に次郎大夫がいることにいち早く気づいていた。
―あいつ、なんでおるんじゃ。隠れておればいいものを。
動揺を押し殺して、じっと弾正の指図を待った。
「いざ、かかれーっ」
弾正の掛け声を合図に、弾正勢はゆっくりと大股で前進を始めた。
塁の柵から津島衆が一気に矢を浴びせかける。しかし弾正勢の盾に阻まれ、矢は次々に弾正勢の足元に落ちた。
弾正勢は前進しながら石と矢を交互に放ち、ついに塁のすぐ側まで辿り着いた。雑兵に代わり長槍を持った家臣が前に出て、柵の中に槍を突っ込み、津島衆の腹を突き刺した。
やがて弾正勢は雑兵の背中を階にして柵を超え、次々に塁の中へと入り始めた。
混乱に乗じて柵に近づいた与三が怪力で柵を引っこ抜き、ついに塁が開けた。
「皆、続けやー!」
与三の掛け声に付き従い、弾正勢が一気に塁の中へとなだれ込む。
塁の中の接近戦で津島衆と弾正勢がもみくちゃになりながら、斬り合い、殴り合い、取っ組み合う。その中で、一人柵の外に出ようとする裸の男がいた。次郎大夫である。
次郎大夫は柵の外の馬上の三人に向かって、真っすぐに歩いていく。
「あれは、次郎か」
弾正であった。
元服前に会ったきりの弾正は、御師となった次郎大夫の姿を見るのはこれが初めてであった。
「俺が参ります」
五郎左は弾正が何か物を申すのを遮って、馬を降りた。
次郎大夫と正面で対峙した五郎左は、次郎大夫の佇まいに刹那、怯んだ。憤怒の形相であった。
「御師のお前がなんでここにおる」
「なんで俺をだました?なんでこんなことをする?」
「尾張をよくするためじゃ」
「詭弁を申すな。最初から仕組んでおったんやろ」
次郎大夫は鉾を五郎左に向けた。五郎左は槍を持つが、構えない。
「何百年もかけて築かれたものを、お前らがすべて壊した。どうしてくれる」
「また一から作りゃええだけじゃ」
「いやじゃ、俺が守ってきたものを返せ」
次郎大夫が五郎左に向けて鉾を突き出した。が、五郎左は槍でそれを翻して避け、次郎大夫の鉾の柄をつかんだ。次郎大夫は鉾を動かせない。
「次郎大夫、新たな弾正忠家にはお前が要る。このまま寺へ逃れろ」
「ふざけるな」
次郎大夫は五郎左に蹴りを食らわすが、五郎左に突き返され、倒れこんだ。
「俺がやる」
急に、五郎左の左手の鉾がふわっと宙に浮いた。
次の瞬間、鉾は次郎大夫の腹に深く突き刺さり、次郎大夫の腹に穴が開いた。血がごぼごぼと音を立てて流れ出る。
五郎左が驚いて振り向くと、鉾を手にした三郎が、間髪入れずに次郎大夫の首元に鉾を突き刺した。
次郎大夫はごほっ、と一つ咳をして、息絶えた。
「五郎左、お前が出来ぬことは俺がやる」
三郎が五郎左の肩に手をかけた。
「ああ、次郎大夫よ」
五郎左はその場に崩れ落ちた。
馬を降りた弾正が、二人の傍へとやってきた。
「父上、初陣で手柄を取りました。凄いでしょう」
三郎が嬉々として弾正に言う。
「そうか…鉾持を。ようやったの、三郎」
弾正の声が、震えていた。
了
数日前の評定を思いだす。ひと月の猶予を与えたにも関わらず、こちらから反故にするとは何事かと怒りをあらわにする弾正を、五郎左は頑として撥ね付けた。猶予を与えた末に条件を付けられでもしたら不利になるのは我らだ、と言って期日より前の夜討ちを断行したのである。
四半刻ほど櫓に居座った三郎はようやく櫓を降り、梯子の下で待ち受けていた五郎左に率直に言った。
「夜がこんなに明るいとは」
天王社だけではなく、火は津島の町を焼き尽くしている。
毎日のように手習いに通っている三郎の事である、心の奥では悲しみもあるだろうに、それを隠して強がりを言う三郎が、五郎左には愛おしかった。
対して弾正は決して櫓に登ろうとはしなかった。目で見れば感傷的にならざるを得ない。それを排除し、耳からの情報を頼りに冷静に判断が出来るよう努めていた。
津島衆が早尾に向かったと知った弾正は、夜明け前に津島の町も燃やしてしまえと命じた。天王橋を渡ったらその先は敵の領域である。建物に隠れて攻められたら確実に負ける。
口には出さぬが、家中の誰もがこの戦に不安を抱えていた。神の社に火をかけ、神に仕える津島衆に刃を向けることで神の怒りを招かぬかと。
夜が明ければ奴野を出て早尾に向かう。
三郎は櫓を降りた後、屋敷の中で休めと言う五郎左を振り切って、雑兵に交じって屋敷の外で雑魚寝をした。その際三郎は皆を集め、膝を突き合わせて話をした。
「俺らは天王様や津島の町を燃やしたが、あれは神様が作ったもんやないぞ。家も社も、全部人間が勝手に作ったもんや。賢くてずるい人間が神様の家を勝手に作って、そこに人を集め、銭を儲けとる。神様と聞けばみんな手出しできへんで、何百年もの間、富を独り占めしてきた。それが津島衆や」
三郎の言葉を、雑兵たちは食い入るように聞いている。雑兵たちは領内の百姓で、触れが出たためこうして奴野に戦に来たが、なぜ戦をするのかは知らされていない。幼い頃から評定に出続けた三郎は、知らぬことの怖さをよくわかっていた。三郎は続ける。
「津島衆は尾張に住んどるのに、神様のおわす場所やと言うて年貢を納めとらへん。そりゃおかしゅうないか?住んどるのはお前ら百姓と同じ、人間だで。それを神様にかこつけて、自分たちだけ得をしとる」
「そうやそうや」
「そりゃずるいで」
「三郎様の言う通りや」
水を得た魚のように、三郎は尾張弁で続ける。
「神様が尾張に来たなら、尾張のみんなで富を分けあって当然や。だで俺らは戦をしに行く。津島衆がみんなで分け合う言うて約束したら、父上がもう一遍ちゃんとしたお社を建てるで、心配せんでええ。津島衆を打ち負かさんと、ずっと不公平なまんまや。だで、俺らは絶対に勝たなあかんのや」
雑兵たちの目は輝き、笑顔を見せるものさえいた。
神様に対する畏れは正義の戦いへと変わり、皆が抱いていた不安やためらいは見る間に消え去った。
「だで、明日の戦は気張ってや。津島衆は日の本で一番うまい天野酒いう酒を隠し持っとる。勝ったらみんなで飲もうや、天野酒を」
雑兵たちはそろって感嘆の声を上げた。その声は希望と勇気に溢れていた。
三郎が話をしただけで雑兵たちは心を一つにし、士気は一気に高まった。
その様子を屋敷の中からひそかに眺めていた五郎左は、駄々をこねて手を焼かせた幼い頃の三郎の事を思い出し、そっと涙を流した。
翌早暁、弾正は家中総勢三百人ほどの手勢を率い、天王橋を渡った。早尾までは歩いて四半刻ほどである。
津島の町は一面が焦土となっていた。次郎大夫の屋敷も焼け落ちて跡形もない。いつもは参拝や買い物などで早朝から出歩く者が少なからずいるが、今日は人影さえもない。しかしそのおかげでずいぶん遠くまで見渡せるようになっていた。
遠目に早尾の塁が見えてきた。集まった津島衆は二百人ほどで、塁の全面に柵を設けている。弾正勢に気づいた津島衆は矢を番え始めた。
早尾の塁の少し手前で行軍を止めた弾正勢は、先頭に隙間なく盾を並べ、その後ろで雑兵たちが投石の支度を始める。昨夜の三郎のおかげで弾正勢の士気は高い。
軍勢の一番後ろには、騎馬の五郎左と弾正、そして三郎がいる。馬上の五郎左は、塁の中に次郎大夫がいることにいち早く気づいていた。
―あいつ、なんでおるんじゃ。隠れておればいいものを。
動揺を押し殺して、じっと弾正の指図を待った。
「いざ、かかれーっ」
弾正の掛け声を合図に、弾正勢はゆっくりと大股で前進を始めた。
塁の柵から津島衆が一気に矢を浴びせかける。しかし弾正勢の盾に阻まれ、矢は次々に弾正勢の足元に落ちた。
弾正勢は前進しながら石と矢を交互に放ち、ついに塁のすぐ側まで辿り着いた。雑兵に代わり長槍を持った家臣が前に出て、柵の中に槍を突っ込み、津島衆の腹を突き刺した。
やがて弾正勢は雑兵の背中を階にして柵を超え、次々に塁の中へと入り始めた。
混乱に乗じて柵に近づいた与三が怪力で柵を引っこ抜き、ついに塁が開けた。
「皆、続けやー!」
与三の掛け声に付き従い、弾正勢が一気に塁の中へとなだれ込む。
塁の中の接近戦で津島衆と弾正勢がもみくちゃになりながら、斬り合い、殴り合い、取っ組み合う。その中で、一人柵の外に出ようとする裸の男がいた。次郎大夫である。
次郎大夫は柵の外の馬上の三人に向かって、真っすぐに歩いていく。
「あれは、次郎か」
弾正であった。
元服前に会ったきりの弾正は、御師となった次郎大夫の姿を見るのはこれが初めてであった。
「俺が参ります」
五郎左は弾正が何か物を申すのを遮って、馬を降りた。
次郎大夫と正面で対峙した五郎左は、次郎大夫の佇まいに刹那、怯んだ。憤怒の形相であった。
「御師のお前がなんでここにおる」
「なんで俺をだました?なんでこんなことをする?」
「尾張をよくするためじゃ」
「詭弁を申すな。最初から仕組んでおったんやろ」
次郎大夫は鉾を五郎左に向けた。五郎左は槍を持つが、構えない。
「何百年もかけて築かれたものを、お前らがすべて壊した。どうしてくれる」
「また一から作りゃええだけじゃ」
「いやじゃ、俺が守ってきたものを返せ」
次郎大夫が五郎左に向けて鉾を突き出した。が、五郎左は槍でそれを翻して避け、次郎大夫の鉾の柄をつかんだ。次郎大夫は鉾を動かせない。
「次郎大夫、新たな弾正忠家にはお前が要る。このまま寺へ逃れろ」
「ふざけるな」
次郎大夫は五郎左に蹴りを食らわすが、五郎左に突き返され、倒れこんだ。
「俺がやる」
急に、五郎左の左手の鉾がふわっと宙に浮いた。
次の瞬間、鉾は次郎大夫の腹に深く突き刺さり、次郎大夫の腹に穴が開いた。血がごぼごぼと音を立てて流れ出る。
五郎左が驚いて振り向くと、鉾を手にした三郎が、間髪入れずに次郎大夫の首元に鉾を突き刺した。
次郎大夫はごほっ、と一つ咳をして、息絶えた。
「五郎左、お前が出来ぬことは俺がやる」
三郎が五郎左の肩に手をかけた。
「ああ、次郎大夫よ」
五郎左はその場に崩れ落ちた。
馬を降りた弾正が、二人の傍へとやってきた。
「父上、初陣で手柄を取りました。凄いでしょう」
三郎が嬉々として弾正に言う。
「そうか…鉾持を。ようやったの、三郎」
弾正の声が、震えていた。
了
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説
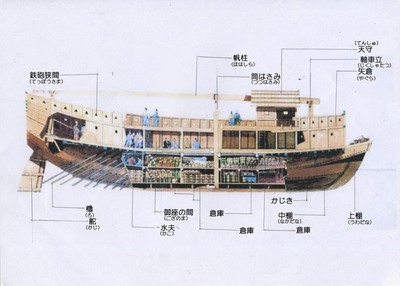

鬼嫁物語
楠乃小玉
歴史・時代
織田信長家臣筆頭である佐久間信盛の弟、佐久間左京亮(さきょうのすけ)。
自由奔放な兄に加え、きっつい嫁に振り回され、
フラフラになりながらも必死に生き延びようとする彼にはたして
未来はあるのか?

天狗斬りの乙女
真弓創
歴史・時代
剣豪・柳生宗厳がかつて天狗と一戦交えたとき、刀で巨岩を両断したという。その神業に憧れ、姉の仇討ちのために天狗斬りを会得したいと願う少女がいた。
※なろう、カクヨム、アルファポリス、ノベルアップ+の各サイトに同作を掲載しています。

夢のまた夢~豊臣秀吉回顧録~
恩地玖
歴史・時代
位人臣を極めた豊臣秀吉も病には勝てず、只々豊臣家の行く末を案じるばかりだった。
一体、これまで成してきたことは何だったのか。
医師、施薬院との対話を通じて、己の人生を振り返る豊臣秀吉がそこにいた。

覇者開闢に抗いし謀聖~宇喜多直家~
海土竜
歴史・時代
毛利元就・尼子経久と並び、三大謀聖に数えられた、その男の名は宇喜多直家。
強大な敵のひしめく中、生き残るために陰謀を巡らせ、守るために人を欺き、目的のためには手段を択ばず、力だけが覇を唱える戦国の世を、知略で生き抜いた彼の夢見た天下はどこにあったのか。


御懐妊
戸沢一平
歴史・時代
戦国時代の末期、出羽の国における白鳥氏と最上氏によるこの地方の覇権をめぐる物語である。
白鳥十郎長久は、最上義光の娘布姫を正室に迎えており最上氏とは表面上は良好な関係であったが、最上氏に先んじて出羽国の領主となるべく虎視淡々と準備を進めていた。そして、天下の情勢は織田信長に勢いがあると見るや、名馬白雲雀を献上して、信長に出羽国領主と認めてもらおうとする。
信長からは更に鷹を献上するよう要望されたことから、出羽一の鷹と評判の逸物を手に入れようとするが持ち主は白鳥氏に恨みを持つ者だった。鷹は譲れないという。
そんな中、布姫が懐妊する。めでたい事ではあるが、生まれてくる子は最上義光の孫でもあり、白鳥にとっては相応の対応が必要となった。

直違の紋に誓って
篠川翠
歴史・時代
かつて、二本松には藩のために戦った少年たちがいた。
故郷を守らんと十四で戦いに臨み、生き延びた少年は、長じて何を学んだのか。
二本松少年隊最後の生き残りである武谷剛介。彼が子孫に残された話を元に、二本松少年隊の実像に迫ります。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















