79 / 138
78. エミール、締められる
しおりを挟む
レイラの家での合宿も半分は過ぎた。レイラやロラン、ペール、アルフォンス、クリストフはエミールに魅了術を習っていた。またその合間でエミールは魅了石を使った魔道具を作成していた。
「これは使用者個人の魔力で起動するように出来てるんだ」
少年たちとアルフォンス、そしてジークはそんな作業も感心して見ている。テオもその中に入りたがっているがちょくちょく宮廷師団とこの屋敷をいったりきたりしている。時にはエミールもテオに引きずって行かれることもある。
エミールはヴィヴィアンヌにかなり絞られたらしい。またお忍びで隣国の魔術師がエミールの元を訪れて、これもかなり絞られたようだった。
「ロッドバルトまで出さなくても」
エミールは少し涙目だ。
「お前のあの魔草でうちの国もこまってんだよ」
半分白で半分黒という左右で髪の色の違う中年の男がエミールを睨む。
「うちの国は中毒者が出てんだよ。……最初は医療用で輸入していた医者がいたらっしい。だがな。ある草と一緒に刻んでタバコとして吸う、なんて事が流行ってな」
隣の国ではあの先が紫の魔草を麻薬と一緒に吸う事が早って中毒者を出しているらしい。
「あれの供給を止めたら死ぬぞ」
「知ってる。それで王族が数人、な」
ロッドバルドは難しい顔になっている。このエミールが見つけたのが悪いと言えば悪い。ただ研究して見つけてそれを悪用していたのはフィールズ老なのだ。
「供給元はわかったが一気に引き抜けない相手なのは分かった。ってかあの野郎しぶといな。ヴィヴィアンヌを狙ってるのかね、まだ?」
ヴィヴィアンヌは急に自分の名前が出てきて驚いている。
「は?」
「あいつはガキの頃からヴィヴとやりたくてしょうがないんだよ。……一時期王都で流行ったヴィヴがモデルだって騒がれた官能小説、あれの作者があいつだよ」
「はぁ?」
確かにそういう小説が貴族に出回って迷惑を被った事はある。12歳になった自分の息子の友人との愛欲の日々、最初は息子の友人が責められる役で息子の友人が十代後半からは女主人公が息子の友人にメロメロになって、息子の友人が結婚してからは不倫の愛を貫くという筋書きをこれでもかとありとあらゆる性愛を絡めて書き綴った長編かつ偏執狂的な小説だった。
「あの小説はヴィヴを自由にしたいっていうフィールズの坊やの欲望の結晶だよ」
ヴィヴィアンヌは苦笑いをしている。
「フィールズの坊や、って言われると今ここにいるペールを連想してむずむずしちゃうね」
「お、どれがフィールズ家の?」
「白金の髪に青い瞳がロラン。ライン公爵の息子だ。金の髪にエメラルドの瞳が」
「ああ、この国の王子だろ。あの子は母親と何度か我が国に来てるよ」
ロッドバルトがいう。
「じゃあの麦わら色の髪に水色の瞳か、現役のフィールズの坊主は」
「そそ」
エミールが言う。
「悪い子じゃないぞ。高い水属性の魔力を持っている。今は土属性も使えるようになってるから3属性の魔術の使い手だな。水、氷、土な」
幼馴染で元同僚の3人は打合せを済ませる。隣国にエドガーが逃げないようにこちらからも魔力障壁をはるが、ロッドバルトの国でも一応防御はしておいて欲しい事等をヴィヴィアンヌは告げる。
「ロッドの得意な土魔法で高い障壁を作っておいて欲しい。それとあの石碑の場所に近い国境辺りに一応精鋭を秘密裡に待機させておいて欲しい」
「俺が出張るよ」
ロッドがヴィヴィアンヌが一番望んだ答えを返してくれる。
「うちの国王には漏らしておくけど、近衛とか騎士団には内緒にする。来週の今日、この時間にまた来るからそれまでに『現状』の吸精鬼の情報をそれまでに欲しい」
「了解した」
エミールはロッドの言葉にうなずいた。
「これは使用者個人の魔力で起動するように出来てるんだ」
少年たちとアルフォンス、そしてジークはそんな作業も感心して見ている。テオもその中に入りたがっているがちょくちょく宮廷師団とこの屋敷をいったりきたりしている。時にはエミールもテオに引きずって行かれることもある。
エミールはヴィヴィアンヌにかなり絞られたらしい。またお忍びで隣国の魔術師がエミールの元を訪れて、これもかなり絞られたようだった。
「ロッドバルトまで出さなくても」
エミールは少し涙目だ。
「お前のあの魔草でうちの国もこまってんだよ」
半分白で半分黒という左右で髪の色の違う中年の男がエミールを睨む。
「うちの国は中毒者が出てんだよ。……最初は医療用で輸入していた医者がいたらっしい。だがな。ある草と一緒に刻んでタバコとして吸う、なんて事が流行ってな」
隣の国ではあの先が紫の魔草を麻薬と一緒に吸う事が早って中毒者を出しているらしい。
「あれの供給を止めたら死ぬぞ」
「知ってる。それで王族が数人、な」
ロッドバルドは難しい顔になっている。このエミールが見つけたのが悪いと言えば悪い。ただ研究して見つけてそれを悪用していたのはフィールズ老なのだ。
「供給元はわかったが一気に引き抜けない相手なのは分かった。ってかあの野郎しぶといな。ヴィヴィアンヌを狙ってるのかね、まだ?」
ヴィヴィアンヌは急に自分の名前が出てきて驚いている。
「は?」
「あいつはガキの頃からヴィヴとやりたくてしょうがないんだよ。……一時期王都で流行ったヴィヴがモデルだって騒がれた官能小説、あれの作者があいつだよ」
「はぁ?」
確かにそういう小説が貴族に出回って迷惑を被った事はある。12歳になった自分の息子の友人との愛欲の日々、最初は息子の友人が責められる役で息子の友人が十代後半からは女主人公が息子の友人にメロメロになって、息子の友人が結婚してからは不倫の愛を貫くという筋書きをこれでもかとありとあらゆる性愛を絡めて書き綴った長編かつ偏執狂的な小説だった。
「あの小説はヴィヴを自由にしたいっていうフィールズの坊やの欲望の結晶だよ」
ヴィヴィアンヌは苦笑いをしている。
「フィールズの坊や、って言われると今ここにいるペールを連想してむずむずしちゃうね」
「お、どれがフィールズ家の?」
「白金の髪に青い瞳がロラン。ライン公爵の息子だ。金の髪にエメラルドの瞳が」
「ああ、この国の王子だろ。あの子は母親と何度か我が国に来てるよ」
ロッドバルトがいう。
「じゃあの麦わら色の髪に水色の瞳か、現役のフィールズの坊主は」
「そそ」
エミールが言う。
「悪い子じゃないぞ。高い水属性の魔力を持っている。今は土属性も使えるようになってるから3属性の魔術の使い手だな。水、氷、土な」
幼馴染で元同僚の3人は打合せを済ませる。隣国にエドガーが逃げないようにこちらからも魔力障壁をはるが、ロッドバルトの国でも一応防御はしておいて欲しい事等をヴィヴィアンヌは告げる。
「ロッドの得意な土魔法で高い障壁を作っておいて欲しい。それとあの石碑の場所に近い国境辺りに一応精鋭を秘密裡に待機させておいて欲しい」
「俺が出張るよ」
ロッドがヴィヴィアンヌが一番望んだ答えを返してくれる。
「うちの国王には漏らしておくけど、近衛とか騎士団には内緒にする。来週の今日、この時間にまた来るからそれまでに『現状』の吸精鬼の情報をそれまでに欲しい」
「了解した」
エミールはロッドの言葉にうなずいた。
2
お気に入りに追加
83
あなたにおすすめの小説

転生貴族の移動領地~家族から見捨てられた三子の俺、万能な【スライド】スキルで最強領地とともに旅をする~
名無し
ファンタジー
とある男爵の三子として転生した主人公スラン。美しい海辺の辺境で暮らしていたが、海賊やモンスターを寄せ付けなかった頼りの父が倒れ、意識不明に陥ってしまう。兄姉もまた、スランの得たスキル【スライド】が外れと見るや、彼を見捨ててライバル貴族に寝返る。だが、そこから【スライド】スキルの真価を知ったスランの逆襲が始まるのであった。
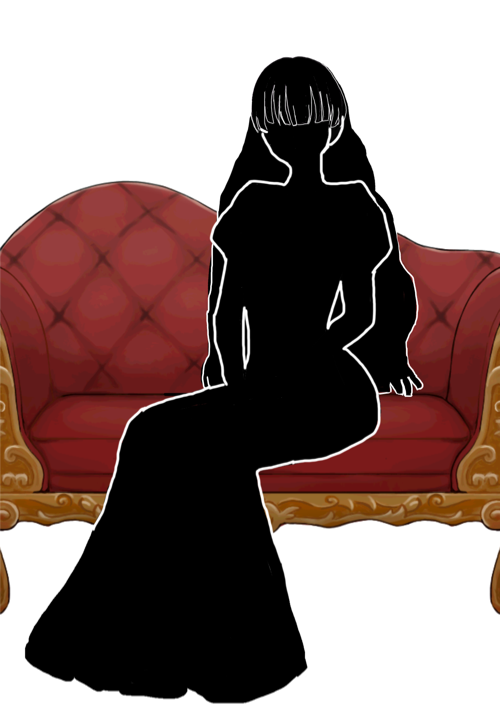


護国の鳥
凪子
ファンタジー
異世界×士官学校×サスペンス!!
サイクロイド士官学校はエスペラント帝国北西にある、国内最高峰の名門校である。
周囲を海に囲われた孤島を学び舎とするのは、十五歳の選りすぐりの少年達だった。
首席の問題児と呼ばれる美貌の少年ルート、天真爛漫で無邪気な子供フィン、軽薄で余裕綽々のレッド、大貴族の令息ユリシス。
同じ班に編成された彼らは、教官のルベリエや医務官のラグランジュ達と共に、士官候補生としての苛酷な訓練生活を送っていた。
外の世界から厳重に隔離され、治外法権下に置かれているサイクロイドでは、生徒の死すら明るみに出ることはない。
ある日同級生の突然死を目の当たりにし、ユリシスは不審を抱く。
校内に潜む闇と秘められた事実に近づいた四人は、否応なしに事件に巻き込まれていく……!

【完結】初級魔法しか使えない低ランク冒険者の少年は、今日も依頼を達成して家に帰る。
アノマロカリス
ファンタジー
少年テッドには、両親がいない。
両親は低ランク冒険者で、依頼の途中で魔物に殺されたのだ。
両親の少ない保険でやり繰りしていたが、もう金が尽きかけようとしていた。
テッドには、妹が3人いる。
両親から「妹達を頼む!」…と出掛ける前からいつも約束していた。
このままでは家族が離れ離れになると思ったテッドは、冒険者になって金を稼ぐ道を選んだ。
そんな少年テッドだが、パーティーには加入せずにソロ活動していた。
その理由は、パーティーに参加するとその日に家に帰れなくなるからだ。
両親は、小さいながらも持ち家を持っていてそこに住んでいる。
両親が生きている頃は、父親の部屋と母親の部屋、子供部屋には兄妹4人で暮らしていたが…
両親が死んでからは、父親の部屋はテッドが…
母親の部屋は、長女のリットが、子供部屋には、次女のルットと三女のロットになっている。
今日も依頼をこなして、家に帰るんだ!
この少年テッドは…いや、この先は本編で語ろう。
お楽しみくださいね!
HOTランキング20位になりました。
皆さん、有り難う御座います。

冤罪で山に追放された令嬢ですが、逞しく生きてます
里見知美
ファンタジー
王太子に呪いをかけたと断罪され、神の山と恐れられるセントポリオンに追放された公爵令嬢エリザベス。その姿は老婆のように皺だらけで、魔女のように醜い顔をしているという。
だが実は、誰にも言えない理由があり…。
※もともとなろう様でも投稿していた作品ですが、手を加えちょっと長めの話になりました。作者としては抑えた内容になってるつもりですが、流血ありなので、ちょっとエグいかも。恋愛かファンタジーか迷ったんですがひとまず、ファンタジーにしてあります。
全28話で完結。

城で侍女をしているマリアンネと申します。お給金の良いお仕事ありませんか?
甘寧
ファンタジー
「武闘家貴族」「脳筋貴族」と呼ばれていた元子爵令嬢のマリアンネ。
友人に騙され多額の借金を作った脳筋父のせいで、屋敷、領土を差し押さえられ事実上の没落となり、その借金を返済する為、城で侍女の仕事をしつつ得意な武力を活かし副業で「便利屋」を掛け持ちしながら借金返済の為、奮闘する毎日。
マリアンネに執着するオネエ王子やマリアンネを取り巻く人達と様々な試練を越えていく。借金返済の為に……
そんなある日、便利屋の上司ゴリさんからの指令で幽霊屋敷を調査する事になり……
武闘家令嬢と呼ばれいたマリアンネの、借金返済までを綴った物語

【完結】あなたに知られたくなかった
ここ
ファンタジー
セレナの幸せな生活はあっという間に消え去った。新しい継母と異母妹によって。
5歳まで令嬢として生きてきたセレナは6歳の今は、小さな手足で必死に下女見習いをしている。もう自分が令嬢だということは忘れていた。
そんなセレナに起きた奇跡とは?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















