12 / 15
第十二話「オズの悪魔は倒せない」
しおりを挟む
ーー第十二話「オズの悪魔は倒せない」
「ようやく君たちの前に出ることが出来た」オズの悪魔は久々津の口を動かしてそう言う。「そう固い表情を見せるな。右の彼は薄々気づいていたんじゃないか? 久々津は久々津ではないということを」
「まぁ、そうだが、中身が何であるかは見当もついていなかった。まさか本物の悪魔なんて」
「そう、本物の悪魔。君たちが見た中で一番尊い存在、たぶん。だって、まだ神は見たことがないだろう? 彼はどこで何をしているかわからないしなぁ、悪魔の方が人材は多いから、こうして人間が謁見する機会はそう少なくない。ただ、悪魔の姿を見て生きて帰る人間がいないから、語り部はただの妄想的人間になってしまうのだ。そのせいで、悪魔がオカルト的な低俗ななんというか娯楽に落ちてしまっている。それは嘆かわしい事実だ。どうすればこの問題を解決できるかと、頭を悩ませてみたけれど、まったく答えは出なかったよ。どうしてか? それが悪魔の在り方だからだ。会った人間は殺す。例外はない」オズの悪魔はそう言うと、久々津の身体を破り始めた。腕は二本ではなく、脚も二本ではなく、眼も、耳も二を超えていた。
御堂たちは長口上をただ座して聞いていたわけではない。その間も、じっくりと魔力と策を練っていた。無防備になるのは変身の瞬間である。彼らはオズの瞳が像を映す前に、互いの腕をギロチンに変えオズの首を切り落とした。魔力のこもった腕の刃は、血肉を綺麗に切断し、オズの悪魔の首は部屋の中を高く飛んだ。その血は黒く、死んでいるようだった。
「だがね、私は死んでいないんだよ。御堂君の次の科白は『やっぱり……だがどう殺せばいいんだ』、だ!」
「やっぱり……だがどう殺せばいいんだ……は!」御堂はオズの悪魔の顔を見上げる。「なんて、茶番に付き合えばいいのか? 今度は本気で行く、というか、符丁はもうついた」オズの悪魔の首の断面が紫色に光り始めた。「そこから情報を入れ込む。生物が寿命の内で刻み込まれる以上の情報を。すると細胞は老化し、そして朽ちていく」
「符丁か」オズの悪魔はそう言うがその顔は余裕である。「君のやりたいことは理解した。だから私には効かない」断面の光は徐々に薄れ、胴体から肉の腕が伸び、頭部をあるべき場所へと戻した。「私には理解できる。君の考えも、君の考えも。だから、私には術は効かないよ。策を労しても無駄、無駄、無駄だよ」
「だとしても」
「君は背後から私を殴る」オズの悪魔は御堂の右拳を第六の腕で受け止めた。「そして、三歩さがりクアンと交代する」その間に御堂はオズの悪魔を倒す算段をたてようとした。だが、クアンの手の内はもちろんオズの悪魔には筒抜けで、クアンの両腕はオズの悪魔の第一第二の手に掴まれてしまう。クアンは「地面を蹴り上げて左側腹部を狙うが」その腹は鋼鉄のように固く、視認できる効果は出ない。そしてオズの悪魔は体勢の崩れたクアンのみぞおちを第三の腕で殴る。クアンの体は御堂めがけて飛んでいく。「御堂は魔力でそれを受け止めるが」オズの悪魔が施した魔法には気づいていない。「そして、ボンッ」クアンの体は外部から爆破される。御堂は火の気が立った瞬間に後ろに跳んだ。「それはまさにジャストタイミング」オズの悪魔は、思い切り第一第三第五の腕を振るった。御堂は壁に打ち付けられた。
研究棟が音を立てて揺れた。
・・・
「御堂君、あそこにいるんじゃない?」
「あぁ、あたりの魔力が濃くてわからないが、たぶんな」そう水守が答えた時、二度目の揺れが辺りを襲った。それは先ほどとは比べ物にならない揺れであった。土煙は水守らの背後で起きた。小さな隕石が地面にぶつかったような鋭い縦揺れであり、刹那的に解放されたエネルギーが周囲の木々を薙ぎ倒した。その中央には一人の男が立っていた。長髪の男であった。白い髪を赤い紐のようなものでまとめている。白い甚平のような装いをして、男はあたりを見回した。その何気ない視線は、まるで高エネルギーの光線を放っているかのようで、その場にいる耐性のない人間はバタバタと倒れていった。
「劣等種が」そうあたりを一瞥した男は司馬キッショウその人であった。「こんな低俗な生物に後れを取るなど、貴様らも劣等種に他ならない」
草木の影で「親玉の登場は効いてないぜ」と東がつぶやく。
西城は「仕方ありません」と深刻な表情を浮かべる。「柊さんは無事でしょうか」
「あいつなら大丈夫だろう。それよりも、北島たちに連絡をとれ。前線は一度引かせる。体制を立て直す。そのために、水守たちに戻ってきてもらわないと」
「それには及びません。俺が行きますよ」
「冗談だろう? 未発現者」
「水守さんたちはどうやら事情があるみたいですし、京都払魔からの応援は望めそうにありません」西城は立ち上がって言う。「東第一班長。武器使用の無制限許可を願います」
東は顔を上げた。彼の名前を呼ぶ暇がないことは目の端で分かった。「許可する」そう東が言うと、目の前は空気の空洞になっていた。
「無知の人間が」司馬は煽る。その瞳は空隙を眺める。
「いいや、未知の人間だ」西城は口上を述べる。「これは月の繭だ」彼の手には汎用携行魔道具が握られている。それは銃をかたどり、銃口は司馬の目を捉える。
無音が空気を裂き、水の弾は目標に向かって飛んでいく。司馬はそれを掌で受け止める。「くだらない」司馬は言う。「貴様らの可能性など、取るに足らない。貴様ら劣等種は、胡坐をかく質である。苦痛など知らぬ豚である」
西城は司馬を睨んだ。唇は固く閉ざされて、手の平の武器はすでに入れ替わっていた。
「劣等種の男。貴様は何を望む?」
「俺は何も望まない」西城は言う。彼の口は東から遠く離れている。「俺はあの人のために生きる。あの人の幸せのために。そして、あの人の大切な人のために」
「つまらない男だな」
「それがつまらないと思うのは、お前の心の幼さのせいだ」東は右手を強く握りしめる。そこにはひとつのボタンがある。その瞬間に多様で無数の弾が司馬に向かって飛んでいく。
「ようやく君たちの前に出ることが出来た」オズの悪魔は久々津の口を動かしてそう言う。「そう固い表情を見せるな。右の彼は薄々気づいていたんじゃないか? 久々津は久々津ではないということを」
「まぁ、そうだが、中身が何であるかは見当もついていなかった。まさか本物の悪魔なんて」
「そう、本物の悪魔。君たちが見た中で一番尊い存在、たぶん。だって、まだ神は見たことがないだろう? 彼はどこで何をしているかわからないしなぁ、悪魔の方が人材は多いから、こうして人間が謁見する機会はそう少なくない。ただ、悪魔の姿を見て生きて帰る人間がいないから、語り部はただの妄想的人間になってしまうのだ。そのせいで、悪魔がオカルト的な低俗ななんというか娯楽に落ちてしまっている。それは嘆かわしい事実だ。どうすればこの問題を解決できるかと、頭を悩ませてみたけれど、まったく答えは出なかったよ。どうしてか? それが悪魔の在り方だからだ。会った人間は殺す。例外はない」オズの悪魔はそう言うと、久々津の身体を破り始めた。腕は二本ではなく、脚も二本ではなく、眼も、耳も二を超えていた。
御堂たちは長口上をただ座して聞いていたわけではない。その間も、じっくりと魔力と策を練っていた。無防備になるのは変身の瞬間である。彼らはオズの瞳が像を映す前に、互いの腕をギロチンに変えオズの首を切り落とした。魔力のこもった腕の刃は、血肉を綺麗に切断し、オズの悪魔の首は部屋の中を高く飛んだ。その血は黒く、死んでいるようだった。
「だがね、私は死んでいないんだよ。御堂君の次の科白は『やっぱり……だがどう殺せばいいんだ』、だ!」
「やっぱり……だがどう殺せばいいんだ……は!」御堂はオズの悪魔の顔を見上げる。「なんて、茶番に付き合えばいいのか? 今度は本気で行く、というか、符丁はもうついた」オズの悪魔の首の断面が紫色に光り始めた。「そこから情報を入れ込む。生物が寿命の内で刻み込まれる以上の情報を。すると細胞は老化し、そして朽ちていく」
「符丁か」オズの悪魔はそう言うがその顔は余裕である。「君のやりたいことは理解した。だから私には効かない」断面の光は徐々に薄れ、胴体から肉の腕が伸び、頭部をあるべき場所へと戻した。「私には理解できる。君の考えも、君の考えも。だから、私には術は効かないよ。策を労しても無駄、無駄、無駄だよ」
「だとしても」
「君は背後から私を殴る」オズの悪魔は御堂の右拳を第六の腕で受け止めた。「そして、三歩さがりクアンと交代する」その間に御堂はオズの悪魔を倒す算段をたてようとした。だが、クアンの手の内はもちろんオズの悪魔には筒抜けで、クアンの両腕はオズの悪魔の第一第二の手に掴まれてしまう。クアンは「地面を蹴り上げて左側腹部を狙うが」その腹は鋼鉄のように固く、視認できる効果は出ない。そしてオズの悪魔は体勢の崩れたクアンのみぞおちを第三の腕で殴る。クアンの体は御堂めがけて飛んでいく。「御堂は魔力でそれを受け止めるが」オズの悪魔が施した魔法には気づいていない。「そして、ボンッ」クアンの体は外部から爆破される。御堂は火の気が立った瞬間に後ろに跳んだ。「それはまさにジャストタイミング」オズの悪魔は、思い切り第一第三第五の腕を振るった。御堂は壁に打ち付けられた。
研究棟が音を立てて揺れた。
・・・
「御堂君、あそこにいるんじゃない?」
「あぁ、あたりの魔力が濃くてわからないが、たぶんな」そう水守が答えた時、二度目の揺れが辺りを襲った。それは先ほどとは比べ物にならない揺れであった。土煙は水守らの背後で起きた。小さな隕石が地面にぶつかったような鋭い縦揺れであり、刹那的に解放されたエネルギーが周囲の木々を薙ぎ倒した。その中央には一人の男が立っていた。長髪の男であった。白い髪を赤い紐のようなものでまとめている。白い甚平のような装いをして、男はあたりを見回した。その何気ない視線は、まるで高エネルギーの光線を放っているかのようで、その場にいる耐性のない人間はバタバタと倒れていった。
「劣等種が」そうあたりを一瞥した男は司馬キッショウその人であった。「こんな低俗な生物に後れを取るなど、貴様らも劣等種に他ならない」
草木の影で「親玉の登場は効いてないぜ」と東がつぶやく。
西城は「仕方ありません」と深刻な表情を浮かべる。「柊さんは無事でしょうか」
「あいつなら大丈夫だろう。それよりも、北島たちに連絡をとれ。前線は一度引かせる。体制を立て直す。そのために、水守たちに戻ってきてもらわないと」
「それには及びません。俺が行きますよ」
「冗談だろう? 未発現者」
「水守さんたちはどうやら事情があるみたいですし、京都払魔からの応援は望めそうにありません」西城は立ち上がって言う。「東第一班長。武器使用の無制限許可を願います」
東は顔を上げた。彼の名前を呼ぶ暇がないことは目の端で分かった。「許可する」そう東が言うと、目の前は空気の空洞になっていた。
「無知の人間が」司馬は煽る。その瞳は空隙を眺める。
「いいや、未知の人間だ」西城は口上を述べる。「これは月の繭だ」彼の手には汎用携行魔道具が握られている。それは銃をかたどり、銃口は司馬の目を捉える。
無音が空気を裂き、水の弾は目標に向かって飛んでいく。司馬はそれを掌で受け止める。「くだらない」司馬は言う。「貴様らの可能性など、取るに足らない。貴様ら劣等種は、胡坐をかく質である。苦痛など知らぬ豚である」
西城は司馬を睨んだ。唇は固く閉ざされて、手の平の武器はすでに入れ替わっていた。
「劣等種の男。貴様は何を望む?」
「俺は何も望まない」西城は言う。彼の口は東から遠く離れている。「俺はあの人のために生きる。あの人の幸せのために。そして、あの人の大切な人のために」
「つまらない男だな」
「それがつまらないと思うのは、お前の心の幼さのせいだ」東は右手を強く握りしめる。そこにはひとつのボタンがある。その瞬間に多様で無数の弾が司馬に向かって飛んでいく。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説
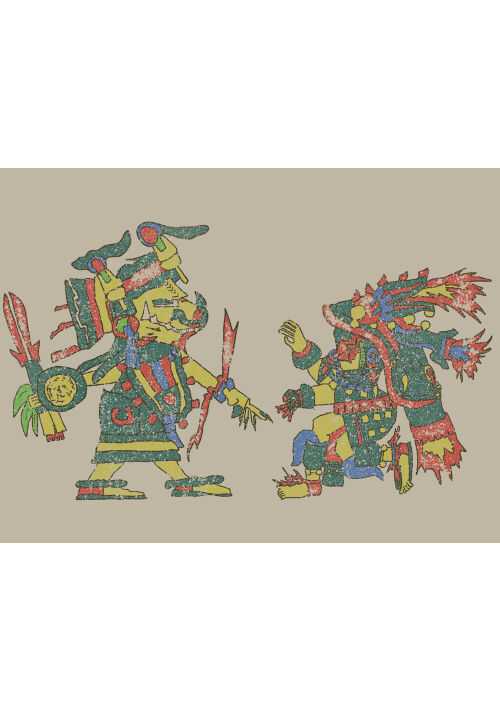
愛をこめてカンニバル
ムサキ
SF
「これが持つ者の責任だ」水の束と星々が辺りの魔法犯罪者を掃討していく。彼らのうつろな顔とは対照的に、そう言う男の顔ははっきりと前を見つめていた。「柊、これがお前の進むべき道だ」
これは、魔法黎明期直後の物語である。そして、魔法を取り締まる魔導警備の隊員、柊このみと食人鬼カンニバルとの闘いの物語である。
*毎日0:00更新 全8話


【完結済み】VRゲームで遊んでいたら、謎の微笑み冒険者に捕獲されましたがイロイロおかしいです。<長編>
BBやっこ
SF
会社に、VRゲーム休があってゲームをしていた私。
自身の店でエンチャント付き魔道具の売れ行きもなかなか好調で。なかなか充実しているゲームライフ。
招待イベで魔術士として、冒険者の仕事を受けていた。『ミッションは王族を守れ』
同僚も招待され、大規模なイベントとなっていた。ランダムで配置された場所で敵を倒すお仕事だったのだが?
電脳神、カプセル。精神を異世界へ送るって映画の話ですか?!

SEVEN TRIGGER
匿名BB
SF
20xx年、科学のほかに魔術も発展した現代世界、伝説の特殊部隊「SEVEN TRIGGER」通称「S.T」は、かつて何度も世界を救ったとされる世界最強の特殊部隊だ。
隊員はそれぞれ1つの銃器「ハンドガン」「マシンガン」「ショットガン」「アサルトライフル」「スナイパーライフル」「ランチャー」「リボルバー」を極めたスペシャリストによって構成された部隊である。
その中で「ハンドガン」を極め、この部隊の隊長を務めていた「フォルテ・S・エルフィー」は、ある事件をきっかけに日本のとある港町に住んでいた。
長年の戦場での生活から離れ、珈琲カフェを営みながら静かに暮らしていたフォルテだったが、「セイナ・A・アシュライズ」との出会いをきっかけに、再び戦いの世界に身を投じていくことになる。
マイペースなフォルテ、生真面目すぎるセイナ、性格の合わない2人はケンカしながらも、互いに背中を預けて悪に立ち向かう。現代SFアクション&ラブコメディー


World War Ⅲ
Primrose
SF
1999年、ナノマシンの開発によって危機に瀕した人類は、人間にナノマシンを移植したサイボーグを作り出した。そして人類と機械との間で、第三次世界大戦が始まる。


蘇生魔法を授かった僕は戦闘不能の前衛(♀)を何度も復活させる
フルーツパフェ
大衆娯楽
転移した異世界で唯一、蘇生魔法を授かった僕。
一緒にパーティーを組めば絶対に死ぬ(死んだままになる)ことがない。
そんな口コミがいつの間にか広まって、同じく異世界転移した同業者(多くは女子)から引っ張りだこに!
寛容な僕は彼女達の申し出に快諾するが条件が一つだけ。
――実は僕、他の戦闘スキルは皆無なんです
そういうわけでパーティーメンバーが前衛に立って死ぬ気で僕を守ることになる。
大丈夫、一度死んでも蘇生魔法で復活させてあげるから。
相互利益はあるはずなのに、どこか鬼畜な匂いがするファンタジー、ここに開幕。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















