1 / 1
最初から、好きだったふたり
しおりを挟む
「吉野くんのことは嫌いじゃないけど、恋人っていうか付き合うっていうのは、なんというか」
公平は桜の言葉を遮るように
「なんというか、違う、って、こと?」
「うん、まぁ。そう。違うってこと」
吉野公平は同じ子に五回告白して、三回ともほぼ同じ口上でお断りされた。これはテンプレートなのかというくらいに。まぁ、一年で五回も告白されたら、桜じゃなくても誰だって迷惑千万だろう。千万だ、千なのか万なのかはたまた千×万なのか。
世の中は不公平だ。だから、せめてこの子は誰彼《だれかれ》分け隔てなく大らかな心で、という想いを込めて“公平”と名付けられた。
ややこしいのは名づけ親が親じゃなくて、隣の書道家の高蔵の爺さんということだった。自分の親がわが子の命名を放棄した、と公平は両親にいつも食ってかかっていた。
というような自分の名前の由来を思い返すことで、目の前の桜からフラれた事実を見ないように認識しないようにと、公平は努めていた。
「わたし、吹部行くだから。じゃぁ」
桜は申し訳なさそうに、その場を走り去った。高校一年の夏に告白したのが最初だった。今が二年生の夏休み前。一年経ってない。その間に五回という告白頻度は、友人から言わせればストーカーの域に達しているとのことだった。音楽室からチューバ―の個人練習の音が聞こえる。桜の演奏だ。野太《のぶと》い。
公平は桜のどこが好きなのか、ひとつずつあげながら、駐輪場に向かった。帰宅部二年目、高校で部活に入っているのは八割。帰宅部は二割。二割のうちほとんどが、受験のためらしい。公平は学業不良、勉強は得意でなかったし、将来は父親の左官屋を継ぐつもりだった。大学進学を諦め、かといって高校生活を楽しむわけでもなく、ただ繰り返しし続けていることといえば、桜への告白ぐらいだった。桜のどこが好きなのか。自転車の鍵を探しながら、考えていた。思い浮かばなかった。そもそもなぜ桜のことを好きになり始めたのか、きっかけすら思い出せなかった。
澤井桜はもともとチューバ志望だったが、思いのほかチューバが重い。中学時代はトロンボーンだった。チューバは音全体を創る、と中学時代の先輩が言っていた。憧れの先輩だった。先輩の顔は思い出せないが、この言葉は忘れられない。高校に入ってセレクションに合格し、念願のチューバ。恋人はチューバと言っても過言ではなかった。
毎日の学校生活も部活も楽しい、これ以上に望むものはない。気がかりなことは公平のことだった。何がいいのか、五回も告白してきている。厳密に言えば、六回だ。公平は忘れているかもしれないが。初めての告白をカウントするかどうかが問題だからだ。私は在日韓国人だ。十六歳になる頃、市役所で指紋を取られた。窓口では大きな声で韓国での名前を呼ばれた。私の家は、ほとんど日本人として暮らしている家だ。
祖母はキムチを漬けたり、トックをふるまったり、ベタ焼きを焼いたりと、テレビで観る日本のおばあちゃんとはちょっと違う気がしていた。法事にたくさんの食事が出て、長い銀色のお箸をいろんなお皿に置きなおす、手を三角の形にして床にそのまま手をついてお辞儀をする。何度すれば、終わるのかよくわからなかったが、父の兄がこれで最後ね、というとその後は食事にありつける。
私が公平のことを意識したのは、視聴覚室に集められて奨学金制度について学校から説明があった時のことだ。今から一年前。高校生になって夏休み前の頃。
学年全員が集まるには狭い視聴覚室。私は事前に担任から奨学金についての話をされて、受ける受けないに関わらず、説明会に出席するように言われていた。一学年、三百人ぐらいいるマンモス校、視聴覚室に集まったのは十人程度だった。
それは、在日韓国人・朝鮮人向けの奨学金の説明会だった。誰もが自分の素性・国籍をカミングアウトしているわけではない。日本では通称名を名乗っている人の方が多かった。私の苗字は「鄭」だった。韓国語読みではチョンらしい。
大切にしてきたわけではないが、国籍や自分の出生に誇りを持って生きているほどまだ人生経験はない。それは、これからのことだ。だから、ここでデリカシーなく自分がどこのもの、なのかを他人には知られたくなかった。
説明会はみんなうつむきがちだった。先生が質問ありますか?と尋ねたが、こんな場面で質問する人はいなかった。不意打ちのようなやり方に納得がいかなかったが、怒りよりも誰かに知られたくない、という気持ちが強かった。
視聴覚室を出ると、何人かの女子が説明会の趣旨を聞きつけて待ち伏せしていた。誰が在日なのか知りたかったのだろう。この説明会に集められたのが在日韓国人・朝鮮人ということをどうして知りえたのか、それも怖い話だった。
視聴覚室を小走りに出ると、待ち伏せしている女子四人組が見ている。そこへ、公平が大声を出しながら走ってきた。公平はヒーローだった。あの日から私にとって、ヒーローだった。
「お前ら!俺の名前を知ってるか!!!」
女子四人組は鳩が豆鉄砲《まめでっぽう》を食ったような顔で
「なんなのよ」
と言うのが精いっぱいだった。
公平はチャンスと見るや
「いいか、俺の名前は吉野公平。公平ってのは、隣の書道家の高蔵の爺さんが名付けたんだけど、そんなことはいいや」
「ちょっと、邪魔しないでよ」
女子四人組の誰かが強い語気《ごき》で言い放った。
「何を邪魔するって?いいか、世の中は不公平なんだ。だけどこれは不平等って意味じゃない。世の中は平等だ。だから、誰かが誰かのことを上に見たり、下に見たりなんてない」
「だからなんなのよ!」
別の女子が息巻いて前に出てきた。眼鏡には公平と奥に桜が小さく映っていた。
「だから、平等は前提なんだよ。差別なんてあっちゃぁいけない。わかる?だけど、世の中は不公平だ。できること、できないことで受ける待遇が変わる」
女子四人組が静まり返る。人だかりができていた。
「この説明会の趣旨はわからないけれど、世の中が公平にしようとして、取り組んだものなんだろ。だけど、この公平さを与えるチャンスをお前たちが違う方向で捻じ曲げるのは俺は許せないね」
パチパチとまばらに拍手が起こる。他の在日韓国人の同級生たちがその場を離れずに、公平の話を聞き拍手をしていた。それを見つけた説明会を行った先生がここから解散するように怒り始めた。
「公平公平って、自分の名前ばっか連呼してんじゃねーよ。覚えとけよ」
女子四人組が捨て台詞を吐いて、その場を去った。雑魚たちが逃げるように、仕返しする気もないくせに、と公平は思った。
「吉野くん、ありがとう」
「いや、あいつら昼休みに一緒にメシ食ってるだろ。馬鹿みたいに大声で。なのに、突然ヒソヒソ声で話してさ。なんか放課後で面白いことあるからって言ってたから、寝たふりして聞いてたんだよ」
「それで、どうして?あの子たちを待ち伏せしてたの?」
「当たり前だろ、どんな悪さするかわからないのに、お仕置きするわけにもいかないし」
公平は淡々《たんたん》と桜の目を見ながら返事した。
「そっか、ありがと」
「まぁ、好きな子がさぁ、ピンチにならないようにするのって、大切だろ」
公平は無意識に告白していた。桜はこれを一回目とカウントしていた。公平は、無意識ゆえにこの告白を数にいれていなかった。
「でさぁ、お母さんは告白を何回目でオッケーしたの?」
汐里《しおり》は母の話を興味深そうに聞いている。友人よりも母の恋愛話の方が面白い。友人の恋愛話は、万に一つ、自分と好きな人がかぶってしまうなんてこともある。だが、母なら安心だ。絶対にかぶることはない。安心感をもって、恋愛話を聞ける。そもそも、恋愛話を聞けるというのはそれほど親身な間柄ってことだ。親身であればあるほど、“好きな人かぶり”のリスクは少なからずある。
「何回目かなぁ。お母さんさぁ、告白はオッケーしなかったのよ」
「そうなの?どうして、好きだったんじゃないの?」
汐里は覗き込むようにして母の変化を伺った。母は相変わらずのポーカーフェイスだった。動じない。
「私から好きって言いたかったのよ。公平さん、なかなか言わせてくれないし」
「だよね、一年で六回の告白、二カ月に一回かぁ。通販のサブスクみたいじゃん」
「公平さんの誕生日にね、私から呼び出して、その、視聴覚室に。で、告白したの」
汐里はホッとした、笑顔がこぼれる。無意識に。
「よかったぁ。その話が聞きたかったのよね」
「ごめんねぇ、心配させちゃって。ちょっと、汐里がグズッてるみたい」
ベビーベッドで、赤ん坊の汐里が泣いている。
「ほんとゴメンねお母さん。赤ちゃんの私って、お父さんに似てるんだねぇ。凛々しい。じゃぁ、そろそろ帰るね。アッチの時代でお父さんとお母さん待ってるから」
汐里はピピッと腕時計を操作し、リビングに現れた黒い穴、タイムホールに飛び込んだ。
タイムホールを遊泳しながら、汐里は二十年後に戻っていった。
「どっちから告白したかで言い争う親って、まぁ平和だけど。最初はお父さんで、付き合い始めの告白はお母さんってことね」
たった一日のタイムトラベルだったが早く父と母に会いたい、と汐里は胸を躍らせた。
おわり
公平は桜の言葉を遮るように
「なんというか、違う、って、こと?」
「うん、まぁ。そう。違うってこと」
吉野公平は同じ子に五回告白して、三回ともほぼ同じ口上でお断りされた。これはテンプレートなのかというくらいに。まぁ、一年で五回も告白されたら、桜じゃなくても誰だって迷惑千万だろう。千万だ、千なのか万なのかはたまた千×万なのか。
世の中は不公平だ。だから、せめてこの子は誰彼《だれかれ》分け隔てなく大らかな心で、という想いを込めて“公平”と名付けられた。
ややこしいのは名づけ親が親じゃなくて、隣の書道家の高蔵の爺さんということだった。自分の親がわが子の命名を放棄した、と公平は両親にいつも食ってかかっていた。
というような自分の名前の由来を思い返すことで、目の前の桜からフラれた事実を見ないように認識しないようにと、公平は努めていた。
「わたし、吹部行くだから。じゃぁ」
桜は申し訳なさそうに、その場を走り去った。高校一年の夏に告白したのが最初だった。今が二年生の夏休み前。一年経ってない。その間に五回という告白頻度は、友人から言わせればストーカーの域に達しているとのことだった。音楽室からチューバ―の個人練習の音が聞こえる。桜の演奏だ。野太《のぶと》い。
公平は桜のどこが好きなのか、ひとつずつあげながら、駐輪場に向かった。帰宅部二年目、高校で部活に入っているのは八割。帰宅部は二割。二割のうちほとんどが、受験のためらしい。公平は学業不良、勉強は得意でなかったし、将来は父親の左官屋を継ぐつもりだった。大学進学を諦め、かといって高校生活を楽しむわけでもなく、ただ繰り返しし続けていることといえば、桜への告白ぐらいだった。桜のどこが好きなのか。自転車の鍵を探しながら、考えていた。思い浮かばなかった。そもそもなぜ桜のことを好きになり始めたのか、きっかけすら思い出せなかった。
澤井桜はもともとチューバ志望だったが、思いのほかチューバが重い。中学時代はトロンボーンだった。チューバは音全体を創る、と中学時代の先輩が言っていた。憧れの先輩だった。先輩の顔は思い出せないが、この言葉は忘れられない。高校に入ってセレクションに合格し、念願のチューバ。恋人はチューバと言っても過言ではなかった。
毎日の学校生活も部活も楽しい、これ以上に望むものはない。気がかりなことは公平のことだった。何がいいのか、五回も告白してきている。厳密に言えば、六回だ。公平は忘れているかもしれないが。初めての告白をカウントするかどうかが問題だからだ。私は在日韓国人だ。十六歳になる頃、市役所で指紋を取られた。窓口では大きな声で韓国での名前を呼ばれた。私の家は、ほとんど日本人として暮らしている家だ。
祖母はキムチを漬けたり、トックをふるまったり、ベタ焼きを焼いたりと、テレビで観る日本のおばあちゃんとはちょっと違う気がしていた。法事にたくさんの食事が出て、長い銀色のお箸をいろんなお皿に置きなおす、手を三角の形にして床にそのまま手をついてお辞儀をする。何度すれば、終わるのかよくわからなかったが、父の兄がこれで最後ね、というとその後は食事にありつける。
私が公平のことを意識したのは、視聴覚室に集められて奨学金制度について学校から説明があった時のことだ。今から一年前。高校生になって夏休み前の頃。
学年全員が集まるには狭い視聴覚室。私は事前に担任から奨学金についての話をされて、受ける受けないに関わらず、説明会に出席するように言われていた。一学年、三百人ぐらいいるマンモス校、視聴覚室に集まったのは十人程度だった。
それは、在日韓国人・朝鮮人向けの奨学金の説明会だった。誰もが自分の素性・国籍をカミングアウトしているわけではない。日本では通称名を名乗っている人の方が多かった。私の苗字は「鄭」だった。韓国語読みではチョンらしい。
大切にしてきたわけではないが、国籍や自分の出生に誇りを持って生きているほどまだ人生経験はない。それは、これからのことだ。だから、ここでデリカシーなく自分がどこのもの、なのかを他人には知られたくなかった。
説明会はみんなうつむきがちだった。先生が質問ありますか?と尋ねたが、こんな場面で質問する人はいなかった。不意打ちのようなやり方に納得がいかなかったが、怒りよりも誰かに知られたくない、という気持ちが強かった。
視聴覚室を出ると、何人かの女子が説明会の趣旨を聞きつけて待ち伏せしていた。誰が在日なのか知りたかったのだろう。この説明会に集められたのが在日韓国人・朝鮮人ということをどうして知りえたのか、それも怖い話だった。
視聴覚室を小走りに出ると、待ち伏せしている女子四人組が見ている。そこへ、公平が大声を出しながら走ってきた。公平はヒーローだった。あの日から私にとって、ヒーローだった。
「お前ら!俺の名前を知ってるか!!!」
女子四人組は鳩が豆鉄砲《まめでっぽう》を食ったような顔で
「なんなのよ」
と言うのが精いっぱいだった。
公平はチャンスと見るや
「いいか、俺の名前は吉野公平。公平ってのは、隣の書道家の高蔵の爺さんが名付けたんだけど、そんなことはいいや」
「ちょっと、邪魔しないでよ」
女子四人組の誰かが強い語気《ごき》で言い放った。
「何を邪魔するって?いいか、世の中は不公平なんだ。だけどこれは不平等って意味じゃない。世の中は平等だ。だから、誰かが誰かのことを上に見たり、下に見たりなんてない」
「だからなんなのよ!」
別の女子が息巻いて前に出てきた。眼鏡には公平と奥に桜が小さく映っていた。
「だから、平等は前提なんだよ。差別なんてあっちゃぁいけない。わかる?だけど、世の中は不公平だ。できること、できないことで受ける待遇が変わる」
女子四人組が静まり返る。人だかりができていた。
「この説明会の趣旨はわからないけれど、世の中が公平にしようとして、取り組んだものなんだろ。だけど、この公平さを与えるチャンスをお前たちが違う方向で捻じ曲げるのは俺は許せないね」
パチパチとまばらに拍手が起こる。他の在日韓国人の同級生たちがその場を離れずに、公平の話を聞き拍手をしていた。それを見つけた説明会を行った先生がここから解散するように怒り始めた。
「公平公平って、自分の名前ばっか連呼してんじゃねーよ。覚えとけよ」
女子四人組が捨て台詞を吐いて、その場を去った。雑魚たちが逃げるように、仕返しする気もないくせに、と公平は思った。
「吉野くん、ありがとう」
「いや、あいつら昼休みに一緒にメシ食ってるだろ。馬鹿みたいに大声で。なのに、突然ヒソヒソ声で話してさ。なんか放課後で面白いことあるからって言ってたから、寝たふりして聞いてたんだよ」
「それで、どうして?あの子たちを待ち伏せしてたの?」
「当たり前だろ、どんな悪さするかわからないのに、お仕置きするわけにもいかないし」
公平は淡々《たんたん》と桜の目を見ながら返事した。
「そっか、ありがと」
「まぁ、好きな子がさぁ、ピンチにならないようにするのって、大切だろ」
公平は無意識に告白していた。桜はこれを一回目とカウントしていた。公平は、無意識ゆえにこの告白を数にいれていなかった。
「でさぁ、お母さんは告白を何回目でオッケーしたの?」
汐里《しおり》は母の話を興味深そうに聞いている。友人よりも母の恋愛話の方が面白い。友人の恋愛話は、万に一つ、自分と好きな人がかぶってしまうなんてこともある。だが、母なら安心だ。絶対にかぶることはない。安心感をもって、恋愛話を聞ける。そもそも、恋愛話を聞けるというのはそれほど親身な間柄ってことだ。親身であればあるほど、“好きな人かぶり”のリスクは少なからずある。
「何回目かなぁ。お母さんさぁ、告白はオッケーしなかったのよ」
「そうなの?どうして、好きだったんじゃないの?」
汐里は覗き込むようにして母の変化を伺った。母は相変わらずのポーカーフェイスだった。動じない。
「私から好きって言いたかったのよ。公平さん、なかなか言わせてくれないし」
「だよね、一年で六回の告白、二カ月に一回かぁ。通販のサブスクみたいじゃん」
「公平さんの誕生日にね、私から呼び出して、その、視聴覚室に。で、告白したの」
汐里はホッとした、笑顔がこぼれる。無意識に。
「よかったぁ。その話が聞きたかったのよね」
「ごめんねぇ、心配させちゃって。ちょっと、汐里がグズッてるみたい」
ベビーベッドで、赤ん坊の汐里が泣いている。
「ほんとゴメンねお母さん。赤ちゃんの私って、お父さんに似てるんだねぇ。凛々しい。じゃぁ、そろそろ帰るね。アッチの時代でお父さんとお母さん待ってるから」
汐里はピピッと腕時計を操作し、リビングに現れた黒い穴、タイムホールに飛び込んだ。
タイムホールを遊泳しながら、汐里は二十年後に戻っていった。
「どっちから告白したかで言い争う親って、まぁ平和だけど。最初はお父さんで、付き合い始めの告白はお母さんってことね」
たった一日のタイムトラベルだったが早く父と母に会いたい、と汐里は胸を躍らせた。
おわり
0
お気に入りに追加
0
この作品の感想を投稿する
あなたにおすすめの小説

叫びたい青春【声劇台本】【一人用】
マグカップと鋏は使いやすい
ライト文芸
帰り道、先輩に声をかけられたけど、緊張してほとんど何もしゃべれずそのまま別れて帰ることに。
それを後悔してうわーーってなって階段を上って、「好きなのにー!!」って叫んでる台本です。
性別はどちらでと構いません。叫びたい方ぜひどうぞ!!
階段を駆け上って屋上への扉を開けて最後に叫んでるイメージですが、変更していただいても構いません。
性別不問、語尾の変更、セリフの増減アドリブokです。
お好きにアレンジどうぞ。
動画・音声投稿サイトに使用する場合は、使用許可は不要ですが一言いただけると嬉しいです。
大変喜びます。
自作発言、転載はご遠慮ください。
著作権は放棄しておりません。
使用の際は作者名を記載してください。
性別不問、内容や世界観が変わらない程度の変更や語尾の変更、方言等構いません。

MMS ~メタル・モンキー・サーガ~
千両文士
SF
エネルギー問題、環境問題、経済格差、疫病、収まらぬ紛争に戦争、少子高齢化・・・人類が直面するありとあらゆる問題を科学の力で解決すべく世界政府が協力して始まった『プロジェクト・エデン』
洋上に建造された大型研究施設人工島『エデン』に招致された若き大天才学者ミクラ・フトウは自身のサポートメカとしてその人格と知能を完全電子化複製した人工知能『ミクラ・ブレイン』を建造。
その迅速で的確な技術開発力と問題解決能力で矢継ぎ早に改善されていく世界で人類はバラ色の未来が確約されていた・・・はずだった。
突如人類に牙を剥き、暴走したミクラ・ブレインによる『人類救済計画』。
その指揮下で人類を滅ぼさんとする軍事戦闘用アンドロイドと直属配下の上位管理者アンドロイド6体を倒すべく人工島エデンに乗り込むのは・・・宿命に導かれた天才学者ミクラ・フトウの愛娘にしてレジスタンス軍特殊エージェント科学者、サン・フトウ博士とその相棒の戦闘用人型アンドロイドのモンキーマンであった!!
機械と人間のSF西遊記、ここに開幕!!
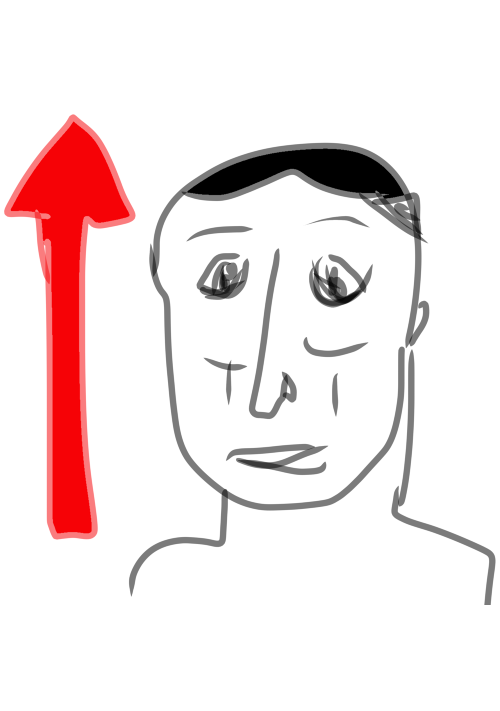
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

『星屑の狭間で』(チャレンジ・ミッション編)
トーマス・ライカー
SF
政・官・財・民・公・軍に拠って構成された複合巨大組織『運営推進委員会』が、超大規模なバーチャル体感サバイバル仮想空間・艦対戦ゲーム大会『サバイバル・スペースバトルシップ』を企画・企図し、準備して開催に及んだ。
そのゲーム大会の1部を『運営推進委員会』にて一席を占める、ネット配信メディア・カンパニー『トゥーウェイ・データ・ネット・ストリーム・ステーション』社が、配信リアル・ライヴ・バラエティー・ショウ『サバイバル・スペースバトルシップ・キャプテン・アンド・クルー』として、順次に公開している。
アドル・エルクを含む20人は艦長として選ばれ、それぞれがスタッフ・クルーを男女の芸能人の中から選抜して、軽巡宙艦に搭乗して操り、ゲーム大会で奮闘する模様を撮影されて、配信リアル・ライヴ・バラエティー・ショウ『サバイバル・スペースバトルシップ・キャプテン・アンド・クルー』の中で出演者のコメント付きで紹介されている。
『運営推進本部』は、1ヶ月に1〜2回の頻度でチャレンジ・ミッションを発表し、それへの参加を強く推奨している。
【『ディファイアント』共闘同盟】は基本方針として、総てのチャレンジ・ミッションには参加すると定めている。
本作はチャレンジ・ミッションに参加し、ミッションクリアを目指して奮闘する彼らを描く…スピンオフ・オムニバス・シリーズです。

CoSMoS ∞ MaCHiNa ≠ ReBiRTH
L0K1
SF
機械仕掛けの宇宙は僕らの夢を見る――
西暦2000年――
Y2K問題が原因となり、そこから引き起こされたとされる遺伝子突然変異によって、異能超人が次々と誕生する。
その中で、元日を起点とし世界がタイムループしていることに気付いた一部の能力者たち。
その原因を探り、ループの阻止を試みる主人公一行。
幾度となく同じ時間を繰り返すたびに、一部の人間にだけ『メメント・デブリ』という記憶のゴミが蓄積されるようになっていき、その記憶のゴミを頼りに、彼らはループする世界を少しずつ変えていった……。
そうして、訪れた最終ループ。果たして、彼らの運命はいかに?
何不自由のない生活を送る高校生『鳳城 さとり』、幼馴染で彼が恋心を抱いている『卯月 愛唯』、もう一人の幼馴染で頼りになる親友の『黒金 銀太』、そして、謎の少女『海風 愛唯』。
オカルト好きな理系女子『水戸 雪音』や、まだ幼さが残るエキゾチック少女『天野 神子』とともに、世界の謎を解き明かしていく。
いずれ、『鳳城 さとり』は、謎の存在である『世界の理』と、謎の人物『鳴神』によって、自らに課せられた残酷な宿命を知ることになるだろう――

ホワイトコード戦記1 シンカナウスより
星白 明
SF
「つまるところ、僕は、僕の存在を、ソウルコードを形作った張本人であろう、この知性体をこう呼ぶことにした。遥か昔に忘れ去られた概念――即ち〝神〟、と」
この宇宙が生まれてから『六十七億年』――ある朝、世界が滅ぶ夢を見た。
軍用に開発された戦闘型アンドロイド、μ(ミュウ)。彼女はその日いつも通り訓練をして過ごすはずが、統率個体のMOTHERから、自分たちを設計した天才科学者エメレオの護衛を突如として命じられる。渋々エメレオを襲いくる刺客ドローンや傭兵から守るμだが、すべては自身の世界が滅ぶ、そのほんの始まりにしか過ぎなかった――!
――まずはひとつ、宇宙が滅ぶ。
すべては最後の宇宙、六度目の果て、『地球』を目指して。
なぜ、ここまで世界は繰り返し滅び続けるのか?
超発展した科学文明の落とし子がゆく、神と悪魔、光と闇、五つの世界の滅亡と輪廻転生をめぐる旅路を描く、大長編SFファンタジーの〝プロローグ〟。
2024.06.24. 完。
8月の次回作公開に向けて執筆進めてます。

コンビニバイト店員ですが、実は特殊公安警察やってます(『僕らの目に見えている世界のこと』より改題)
岡智 みみか
SF
自分たちの信じていた世界が変わる。日常が、常識が変わる。世界が今までと全く違って見えるようになる。もしかしたらそれを、人は『革命』と呼ぶのかもしれない。警視庁サイバー攻撃特別捜査対応専門機動部隊、新入隊員磯部重人の新人教育が始まる。SFだってファンタジーだ!!

Head or Tail ~Akashic Tennis Players~
志々尾美里
SF
テニスでは試合前にコイントスでサーブの順番を決める。
そのときコインを投げる主審が、選手に問う。
「Head or Tail?(表か、裏か)」
東京五輪で日本勢が目覚ましい活躍をみせ、政府主導のもとスポーツ研究が盛んになった近未来の日本。
テニス界では日本人男女ペアによって初のグランドスラム獲得の偉業が達成され、テニスブームが巻き起こっていた。
主人公、若槻聖(わかつきひじり)は一つ上の幼馴染、素襖春菜(すおうはるな)に誘われテニスを始める。
だが春菜の圧倒的な才能は二人がペアでいることを困難にし、聖は劣等感と“ある出来事”からテニスを辞めてしまう。
時は流れ、プロ選手として活動拠点を海外に移そうとしていた春菜の前に聖が現れる。
「今度こそ、春菜に相応しいペアになる」
そう誓った聖は、誰にも話せなかった“秘密のラケット”の封印を解く。
類稀なる才能と果てしない研鑚を重ね、鬼や怪物が棲まう世界の頂上に挑む者たち
プロの世界に夢と希望を抱き、憧れに向かって日々全力で努力する追う者たち
テニスに生き甲斐を見出し、プロさながらに己の限界を超えるべく戦う者たち
勝利への渇望ゆえ歪んだ執念に憑りつかれ、悪事に手を染めて足掻く者たち
夢を絶たれその道を諦め、それでもなお未だ燻り続ける彷徨う者たち
現在・過去・未来、遍く全ての記憶と事象を網羅した「アカシック・レコード」に選ばれた聖は、
現存する全ての選手の技を自在に操る能力を手に、テニスの世界に身を投じる。
そして聖を中心に、テニスに関わる全ての者たちの未来の可能性が、“撹拌”されてゆく――。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















