お気に入りに追加
8
あなたにおすすめの小説

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド
まみ夜
ホラー
ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。
事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。
一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。
その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。
そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。
ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。
そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。
第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。
表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。


小さなことから〜露出〜えみ〜
サイコロ
恋愛
私の露出…
毎日更新していこうと思います
よろしくおねがいします
感想等お待ちしております
取り入れて欲しい内容なども
書いてくださいね
よりみなさんにお近く
考えやすく


ゾンビ発生が台風並みの扱いで報道される中、ニートの俺は普通にゾンビ倒して普通に生活する
黄札
ホラー
朝、何気なくテレビを付けると流れる天気予報。お馴染みの花粉や紫外線情報も流してくれるのはありがたいことだが……ゾンビ発生注意報?……いやいや、それも普通よ。いつものこと。
だが、お気に入りのアニメを見ようとしたところ、母親から買い物に行ってくれという電話がかかってきた。
どうする俺? 今、ゾンビ発生してるんですけど? 注意報、発令されてるんですけど??
ニートである立場上、断れずしぶしぶ重い腰を上げ外へ出る事に──
家でアニメを見ていても、同人誌を売りに行っても、バイトへ出ても、ゾンビに襲われる主人公。
何で俺ばかりこんな目に……嘆きつつもだんだん耐性ができてくる。
しまいには、サバゲーフィールドにゾンビを放って遊んだり、ゾンビ災害ボランティアにまで参加する始末。
友人はゾンビをペットにし、効率よくゾンビを倒すためエアガンを改造する。
ゾンビのいることが日常となった世界で、当たり前のようにゾンビと戦う日常的ゾンビアクション。ノベルアッププラス、ツギクル、小説家になろうでも公開中。
表紙絵は姫嶋ヤシコさんからいただきました、
©2020黄札

隠せぬ心臓
MPE事業部
ホラー
これは江戸川乱歩の命名の元にもなったアメリカの作家 エドガー アラン ポーの短すぎる短編 The Tell-Tale Heart をわかりやすい日本語に翻訳したものです。
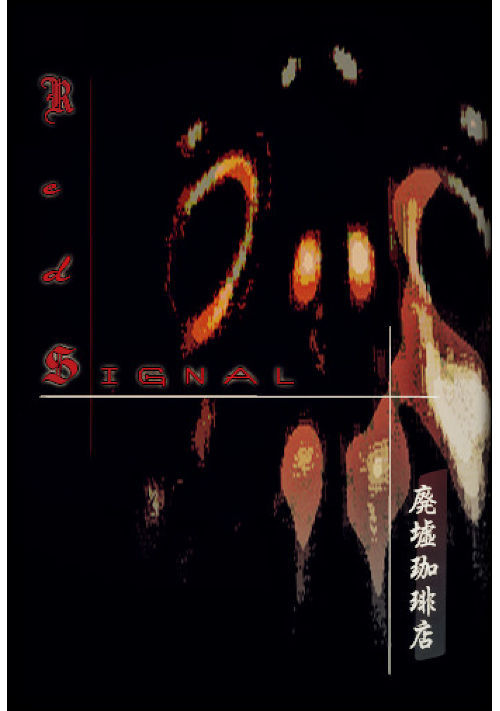

オサキ怪異相談所
てくす
ホラー
ある街の、ある処に、其処は存在する。
怪異……
そんな不可思議な世界に迷い込んだ人を助ける者がいた。
不可思議な世界に迷い込んだ者が今日もまた、助けを求めにやってきたようだ。
【オサキ怪異相談所】
憑物筋の家系により、幼少から霊と関わりがある尾先と、ある一件をきっかけに、尾先と関わることになった茜を中心とした物語。
【オサキ外伝】
物語の進行上、あまり関わりがない物語。基本的には尾先以外が中心。メインキャラクター以外の掘り下げだったりが多めかも?
【怪異蒐集譚】
外伝。本編登場人物の骸に焦点を当てた物語。本編オサキの方にも関わりがあったりするので本編に近い外伝。
【夕刻跳梁跋扈】
鳳とその友人(?)の夕凪に焦点を当てた物語。
【怪異戯曲】
天満と共に生きる喜邏。そして、ある一件から関わることになった叶芽が、ある怪異を探す話。
※非商用時は連絡不要ですが、投げ銭機能のある配信媒体等で記録が残る場合はご一報と、概要欄等にクレジット表記をお願いします。
過度なアドリブ、改変、無許可での男女表記のあるキャラの性別変更は御遠慮ください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















