22 / 94
第一章 鳥に追われる
マモル
しおりを挟む
オゼ
「マモル!」
オオミが凝視している窓の外を見て、懐かしさのあまり大きな声を上げてしまった。
今にも「兄ちゃん」と言いそうなかわいらしい顔で俺を見ているマモルがいた。躊躇うことなく窓に駆け寄った。
「オゼさん! 戻って」
後ろでオオミが止めようとしているが、関係ない。
窓に貼りつくように手を置いた時、マモルの姿がすっと消えた。
「あれ……」
恋し過ぎて幻影を見たのだろうか。でもオオミだってしっかり認識していたはずだ。
「オオミ、今、ここに、いたよな?」
後ろを振り返って確認する。カクカクと頷きながらオオミが言った。
「オゼさん、窓の外にデッキがあると思ってませんか? ここの窓の外はすぐ海なんですよ」
震え声でそう言うが、俺にとってはどうでも良いことだ。
「別に不思議でもないだろ、死人なんだから。浮くということもあるんじゃないのか。死んだことがないから知らないけど」
「お前ら、本当にそこにその子がいたのか」
アオチの声を久しぶりに聞いて、存在を思い出した。
「なんだ、いたのか」
俺が敢えて言わなかった言葉を回収人がさらりと口にした。
少し話をしただけだが、こいつに対する警戒心はすっかり何処かに行ってしまった。
今見ても、俺より背が高くて肩幅も広く、胸板も厚い体格には威圧感がある。
一方で白い長髪を束ねたシワの深い横顔には最初に会った時よりもずっと人間らしい優しさが滲んでいた。
この回収人に異常にびびっているアオチと、異常に先輩思いのオオミは未だに異常な警戒を続けているが。
オオミがいつもより低い声でアオチに説明する。
「僕とオゼさんには死んだ少年が見えていたんです。今は消えてしまいましたが、確かにさっき僕の部屋にいた子です。回収人さん、あの子はどこに行ったんでしょうか」
落ち着いているのは口調だけで、良く見るとテーブルに置いた手首から下は白く、小刻みに揺れていた。
死人だとしても、あんなにかわいいマモルを怖がるなんておかしい。
尋ねられた回収人のほうは「回収人さん」と呼ばれて少し嬉しそうだ。こういう所は憎めない。
「全員の所在までわかる訳じゃないが、あの子ならもう直ぐここに来るんじゃないか。足音が聞こえる」
本当か? 俺には聞こえない。迎えに行ってやろう。身体が自然にドアの方へ向かった。急に大きな手で腕を掴まえられた。回収人の手だ。想像していたのより冷たくない。
「お前たちにルールを教えておく。俺にはどいつが死人でどいつが生きてるのか区別がつかない。だが自分が死んだと認識しているやつを追うのも迎えに行くのも駄目だ。死人に呑まれるぞ」
どういう意味だ? こいつらは理解できているだろうか、二人を確認すると、アオチがオオミをかばうように背中に隠して壁際に立っていた。
オオミは回収人からアオチを守り、アオチは死人からオオミを守る。勝手にやってろ。俺はどちらも怖くない。
その時ドアがぎいっと重い音を立てた。
マモルか? 扉が重すぎるのか、少し開いては閉じ、開いては閉じを繰り返している。健気で泣きそうだ。回収人に尋ねた。
「開けてやるのは迎えに行くうちに入るのか」
回収人は俺を片手で制して、もう片方の手でドアを開いた。
やっぱり俺では駄目なのか……。
まず小さな手が見えて、はち切れそうな笑顔のマモルを見た瞬間、床に膝をついていた。
「兄ちゃん」
懐かしい幼い声に、嗚咽を押さえるため自分の口に手を当てた。
何も言えない俺の顔にマモルがそっと手を伸ばしてきた。
――指先が凍っているように冷たい。そのせいで堪えていた涙がこぼれ落ちた。
「マモル、寒くないか」
胸がいっぱいで、死人には意味がなさそうなことを尋ねてしまう。
「兄ちゃん、大丈夫?」
質問は無視して泣いている俺を気遣ってくれるなんて、相変わらずいい子だ。顔に置かれた冷たい手を握りしめて答えた。
「ごめんな、兄ちゃんは大丈夫だ。お前にまた会えて凄く嬉しいだけだ」
「あの……」
後ろからめちゃくちゃ小さな声でオオミに話しかけられた。
「マモルくん、ごめんね。僕、君くらいの歳の頃、この人……回収人さんと会ってから死んだ人が見えるようになって、何度も怖い思いをしてきたんだよ。だから君を見て逃げ出してしまった」
「会った、というのかあれ? 見捨てたんだろ」
余程根に持つタイプらしく、回収人が呟いた。
「このおじさんは怖くないよ」
マモルは本当に出来た子だ。不気味な回収人に気を遣って、怖いと言わないばかりか、殆んどおじいさんなのにおじさんと呼んでやっている。
「お兄さんは兄ちゃんの弟?」
オオミに小首をかしげながら聞く。
「僕は、兄ちゃんの後輩だよ。わかるかな? オオミと呼んでよ」
「オオミさん……」
恥ずかしそうにオオミに向かって笑った。良かった、この二人は仲良くできそうだ。問題は――
「そこに何がいるんだ」
だめだ、アオチは本当に何も見えてない。
「そっちのかっこいいお兄さんには僕が見えないんだね」
マモルがしょんぼりした顔で言った。
急にアオチが嫌いになった。困惑した表情で突っ立てるだけのくせに「かっこいい」なんて言われて。子どもはこんなのが好きなのか? 大したことのないお前を気に入ってくれた、こんなかわいい子が目に入らないなんて、どうかしている。
「このお兄さんはちょっと鈍いんだ。気にしなくていいから」
「そんな言い方するなよ」
そんな俺たちにマモルがキラキラした目で言った。
「兄ちゃん達、ブリッジに行こうよ」
「マモル!」
オオミが凝視している窓の外を見て、懐かしさのあまり大きな声を上げてしまった。
今にも「兄ちゃん」と言いそうなかわいらしい顔で俺を見ているマモルがいた。躊躇うことなく窓に駆け寄った。
「オゼさん! 戻って」
後ろでオオミが止めようとしているが、関係ない。
窓に貼りつくように手を置いた時、マモルの姿がすっと消えた。
「あれ……」
恋し過ぎて幻影を見たのだろうか。でもオオミだってしっかり認識していたはずだ。
「オオミ、今、ここに、いたよな?」
後ろを振り返って確認する。カクカクと頷きながらオオミが言った。
「オゼさん、窓の外にデッキがあると思ってませんか? ここの窓の外はすぐ海なんですよ」
震え声でそう言うが、俺にとってはどうでも良いことだ。
「別に不思議でもないだろ、死人なんだから。浮くということもあるんじゃないのか。死んだことがないから知らないけど」
「お前ら、本当にそこにその子がいたのか」
アオチの声を久しぶりに聞いて、存在を思い出した。
「なんだ、いたのか」
俺が敢えて言わなかった言葉を回収人がさらりと口にした。
少し話をしただけだが、こいつに対する警戒心はすっかり何処かに行ってしまった。
今見ても、俺より背が高くて肩幅も広く、胸板も厚い体格には威圧感がある。
一方で白い長髪を束ねたシワの深い横顔には最初に会った時よりもずっと人間らしい優しさが滲んでいた。
この回収人に異常にびびっているアオチと、異常に先輩思いのオオミは未だに異常な警戒を続けているが。
オオミがいつもより低い声でアオチに説明する。
「僕とオゼさんには死んだ少年が見えていたんです。今は消えてしまいましたが、確かにさっき僕の部屋にいた子です。回収人さん、あの子はどこに行ったんでしょうか」
落ち着いているのは口調だけで、良く見るとテーブルに置いた手首から下は白く、小刻みに揺れていた。
死人だとしても、あんなにかわいいマモルを怖がるなんておかしい。
尋ねられた回収人のほうは「回収人さん」と呼ばれて少し嬉しそうだ。こういう所は憎めない。
「全員の所在までわかる訳じゃないが、あの子ならもう直ぐここに来るんじゃないか。足音が聞こえる」
本当か? 俺には聞こえない。迎えに行ってやろう。身体が自然にドアの方へ向かった。急に大きな手で腕を掴まえられた。回収人の手だ。想像していたのより冷たくない。
「お前たちにルールを教えておく。俺にはどいつが死人でどいつが生きてるのか区別がつかない。だが自分が死んだと認識しているやつを追うのも迎えに行くのも駄目だ。死人に呑まれるぞ」
どういう意味だ? こいつらは理解できているだろうか、二人を確認すると、アオチがオオミをかばうように背中に隠して壁際に立っていた。
オオミは回収人からアオチを守り、アオチは死人からオオミを守る。勝手にやってろ。俺はどちらも怖くない。
その時ドアがぎいっと重い音を立てた。
マモルか? 扉が重すぎるのか、少し開いては閉じ、開いては閉じを繰り返している。健気で泣きそうだ。回収人に尋ねた。
「開けてやるのは迎えに行くうちに入るのか」
回収人は俺を片手で制して、もう片方の手でドアを開いた。
やっぱり俺では駄目なのか……。
まず小さな手が見えて、はち切れそうな笑顔のマモルを見た瞬間、床に膝をついていた。
「兄ちゃん」
懐かしい幼い声に、嗚咽を押さえるため自分の口に手を当てた。
何も言えない俺の顔にマモルがそっと手を伸ばしてきた。
――指先が凍っているように冷たい。そのせいで堪えていた涙がこぼれ落ちた。
「マモル、寒くないか」
胸がいっぱいで、死人には意味がなさそうなことを尋ねてしまう。
「兄ちゃん、大丈夫?」
質問は無視して泣いている俺を気遣ってくれるなんて、相変わらずいい子だ。顔に置かれた冷たい手を握りしめて答えた。
「ごめんな、兄ちゃんは大丈夫だ。お前にまた会えて凄く嬉しいだけだ」
「あの……」
後ろからめちゃくちゃ小さな声でオオミに話しかけられた。
「マモルくん、ごめんね。僕、君くらいの歳の頃、この人……回収人さんと会ってから死んだ人が見えるようになって、何度も怖い思いをしてきたんだよ。だから君を見て逃げ出してしまった」
「会った、というのかあれ? 見捨てたんだろ」
余程根に持つタイプらしく、回収人が呟いた。
「このおじさんは怖くないよ」
マモルは本当に出来た子だ。不気味な回収人に気を遣って、怖いと言わないばかりか、殆んどおじいさんなのにおじさんと呼んでやっている。
「お兄さんは兄ちゃんの弟?」
オオミに小首をかしげながら聞く。
「僕は、兄ちゃんの後輩だよ。わかるかな? オオミと呼んでよ」
「オオミさん……」
恥ずかしそうにオオミに向かって笑った。良かった、この二人は仲良くできそうだ。問題は――
「そこに何がいるんだ」
だめだ、アオチは本当に何も見えてない。
「そっちのかっこいいお兄さんには僕が見えないんだね」
マモルがしょんぼりした顔で言った。
急にアオチが嫌いになった。困惑した表情で突っ立てるだけのくせに「かっこいい」なんて言われて。子どもはこんなのが好きなのか? 大したことのないお前を気に入ってくれた、こんなかわいい子が目に入らないなんて、どうかしている。
「このお兄さんはちょっと鈍いんだ。気にしなくていいから」
「そんな言い方するなよ」
そんな俺たちにマモルがキラキラした目で言った。
「兄ちゃん達、ブリッジに行こうよ」
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

ガイアセイバーズ spin-off -T大理学部生の波乱-
独楽 悠
青春
優秀な若い頭脳が集う都内の旧帝大へ、新入生として足を踏み入れた川崎 諒。
国内最高峰の大学に入学したものの、目的も展望もあまり描けておらずモチベーションが冷めていたが、入学式で式場中の注目を集める美青年・髙城 蒼矢と鮮烈な出会いをする。
席が隣のよしみで言葉を交わす機会を得たが、それだけに留まらず、同じく意気投合した沖本 啓介をはじめクラスメイトの理学部生たちも巻き込んで、目立ち過ぎる蒼矢にまつわるひと騒動に巻き込まれていく――
およそ1年半前の大学入学当初、蒼矢と川崎&沖本との出会いを、川崎視点で追った話。
※大学生の日常ものです。ヒーロー要素、ファンタジー要素はありません。
◆更新日時・間隔…2023/7/28から、20:40に毎日更新(第2話以降は1ページずつ更新)
◆注意事項
・ナンバリング作品群『ガイアセイバーズ』のスピンオフ作品になります。
時系列はメインストーリーから1年半ほど過去の話になります。
・作品群『ガイアセイバーズ』のいち作品となりますが、メインテーマであるヒーロー要素,ファンタジー要素はありません。また、他作品との関連性はほぼありません。
他作からの予備知識が無くても今作単体でお楽しみ頂けますが、他ナンバリング作品へお目通し頂けていますとより詳細な背景をご理頂いた上でお読み頂けます。
・年齢制限指定はありません。他作品はあらかた年齢制限有ですので、お読みの際はご注意下さい。

僕の目の前の魔法少女がつかまえられません!
兵藤晴佳
ライト文芸
「ああ、君、魔法使いだったんだっけ?」というのが結構当たり前になっている日本で、その割合が他所より多い所に引っ越してきた佐々四十三(さっさ しとみ)17歳。
ところ変われば品も水も変わるもので、魔法使いたちとの付き合い方もちょっと違う。
不思議な力を持っているけど、デリケートにできていて、しかも妙にプライドが高い人々は、独自の文化と学校生活を持っていた。
魔法高校と普通高校の間には、見えない溝がある。それを埋めようと努力する人々もいるというのに、表に出てこない人々の心ない行動は、危機のレベルをどんどん上げていく……。
(『小説家になろう』様『魔法少女が学園探偵の相棒になります!』、『カクヨム』様の同名小説との重複掲載です)

よくできた"妻"でして
真鳥カノ
ライト文芸
ある日突然、妻が亡くなった。
単身赴任先で妻の訃報を聞いた主人公は、帰り着いた我が家で、妻の重大な秘密と遭遇する。
久しぶりに我が家に戻った主人公を待ち受けていたものとは……!?
※こちらの作品はエブリスタにも掲載しております。

一か月ちょっとの願い
full moon
ライト文芸
【第8位獲得】心温まる、涙の物語。
大切な人が居なくなる前に、ちゃんと愛してください。
〈あらすじ〉
今まで、かかあ天下そのものだった妻との関係がある時を境に変わった。家具や食器の場所を夫に教えて、いかにも、もう家を出ますと言わんばかり。夫を捨てて新しい良い人のもとへと行ってしまうのか。
人の温かさを感じるミステリー小説です。
これはバッドエンドか、ハッピーエンドか。皆さんはどう思いますか。
<一言>
世にも奇妙な物語の脚本を書きたい。

もう一度『初めまして』から始めよう
シェリンカ
ライト文芸
『黄昏刻の夢うてな』ep.0 WAKANA
母の再婚を機に、長年会っていなかった父と暮らすと決めた和奏(わかな)
しかし芸術家で田舎暮らしの父は、かなり変わった人物で……
新しい生活に不安を覚えていたところ、とある『不思議な場所』の話を聞く
興味本位に向かった場所で、『椿(つばき)』という同い年の少女と出会い、ようやくその土地での暮らしに慣れ始めるが、実は彼女は……
ごく平凡を自負する少女――和奏が、自分自身と家族を見つめ直す、少し不思議な成長物語
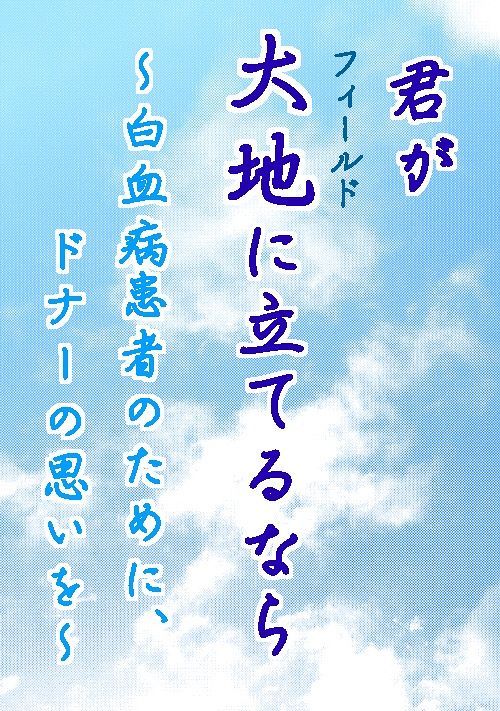
君が大地(フィールド)に立てるなら〜白血病患者の為に、ドナーの思いを〜
長岡更紗
ライト文芸
独身の頃、なんとなくやってみた骨髄のドナー登録。
それから六年。結婚して所帯を持った今、適合通知がやってくる。
骨髄を提供する気満々の主人公晃と、晃の体を心配して反対する妻の美乃梨。
ドナー登録ってどんなのだろう?
ドナーってどんなことをするんだろう?
どんなリスクがあるんだろう?
少しでも興味がある方は、是非、覗いてみてください。
小説家になろうにも投稿予定です。

古屋さんバイト辞めるって
四宮 あか
ライト文芸
ライト文芸大賞で奨励賞いただきました~。
読んでくださりありがとうございました。
「古屋さんバイト辞めるって」
おしゃれで、明るくて、話しも面白くて、仕事もすぐに覚えた。これからバイトの中心人物にだんだんなっていくのかな? と思った古屋さんはバイトをやめるらしい。
学部は違うけれど同じ大学に通っているからって理由で、石井ミクは古屋さんにバイトを辞めないように説得してと店長に頼まれてしまった。
バイト先でちょろっとしか話したことがないのに、辞めないように説得を頼まれたことで困ってしまった私は……
こういう嫌なタイプが貴方の職場にもいることがあるのではないでしょうか?
表紙の画像はフリー素材サイトの
https://activephotostyle.biz/さまからお借りしました。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















