68 / 73
第二十三章 烏川
二
しおりを挟む
高崎への進学を目指す旨は、家族にも伝わった。悠太郎が積極的に伝えたというよりも、何となく伝わってしまったのである。千代次は極度に細い近視の目をしばたたきながら、「ユウ、よく腹を括った! おめえがその気になりさえすりゃあ、はあ受かったも同じことだ!」と言って相好を崩した。高崎の商業学校で学んだ千代次にとって、そこは懐かしい地であったに違いない。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、悠太郎が高崎に受かればねえ、わが家はどこのうちにも引けを取らなくなるよ! 学芸村のインテリ連中どもだって、開拓の屯匪どもだってウッフフ、はあ恐れるに足りないよ!」と言って喜色を満面に浮かべた。高崎の正子伯母様にも、電話でその旨は伝えられた。高校生になる悠太郎を預けることについて、家族はいろいろと相談しているようであった。
三年生になった悠太郎たちの担任は、再び尾池賢一先生に決まった(始業式で尾池先生の名前が読み上げられたとき、新三年生のみんなは歓声を上げたから、昨年度の担任であった市川悟先生には、実に気の毒なことであった)。新年度最初の三者面談で、悠太郎は高崎行きの志望を尾池先生に伝えた。「そうか悠太郎くん、ついに決心したか!」と尾池先生は顎を引きつけながら、キューピー人形を思わせるぱっちりした両目で悠太郎を見ながら言ったが、弛んだその顎はそのとき二重にも三重にもだぶついていた。「きみほどの学力がある生徒には、やはり大学まで行ってほしい。大学を目指すとなると、このあたりでは渋川を目指さないといけない。だが高崎からなら、もっと上の大学だって狙える。東大だって夢じゃないんだぜ。もし東大に受かれば、ありとあらゆる職業を選べるようになるんだ」と尾池先生は語った。「でも、そんなことがうちの子にできるでしょうか」と秀子は、下膨れの顔に憂いを浮かべた。しかし尾池先生は、「お母さんもおひとりでご苦労されたでしょう。でも悠太郎くんが高崎に受かれば、すべての苦労が報われるんですよ」と秀子に言った。受かれば、すべてが報われる。すべての苦労が報われる――。「思えばあの言葉を聞いてからだったな、目に見えて母の人が変わったのは」と悠太郎は、夕映えの烏川を眺めながら考えた。
定期試験でも全県の学力テストも、悠太郎は学内の学年首位を一度も譲らなかった。それどころか五教科の総得点は、四八〇点台を突破して四九〇点台を記録するようにもなり、あるときなどはこの県でトップであったと尾池先生が告げた。大柴映二も「ゲターンの野郎を引きずり下ろせ!」とは、もう言わなかった。とてもそんなことが不可能な境地へと、悠太郎が踏み入ってしまったのは明らかであった。だがその代わり、奇妙な戯れ歌のようなものが聞こえてくることがあった。発信源は映二とも神川直矢とも言われたその戯れ歌は、「ギターの弦をきりきり張れば、いつかぷつりと切れちまう」というものであった。「切れるなら切れるがいい、どうなっても俺はやり抜くのみだ」と悠太郎は、夜毎の勉強にますます力を入れていった。それでも学力テストでの予期せぬ失点がないわけではなかった。夏休み中に実施されたその学力テストは、なんと教室前の廊下に机を並べて実施されたのである。それは教室の補修工事のためで、テストが行なわれるあいだにも、業者が電動ドリルでひどい騒音を立てていた。そこへ持ってきて数学で二次関数の難問が出た。そのときの数学は全県で見ても平均点が著しく下がっており、悠太郎もまた大きく得点を落とした。六〇点台にまで落ち込んだ試験結果は、悠太郎の中学校時代にはこれだけであった。それでも合計得点は学年首位で変わらなかったが、悠太郎にとっても家族にとっても衝撃は大きかった。「平均点なんざ下がったって、おめえが下がったら駄目だろう! 馬鹿奴等ができねえったって、おめえだけはできなけりゃ駄目だろう!」と千代次は怒りを発した。秀子は悠太郎の部屋のピアノに鍵をかけると、その鍵を照月湖に投げ込んだ。「あの湖が干上がって、鍵が見つかることでもなければ、おまえの罪は赦されないと思いなさい!」と秀子はぶるぶるふるえながら叫んだ。「あれからだ、俺が鍵盤に触れなくなったのは。与えておいて、なぜ奪うんだろうな。どうせ奪うなら、なぜ与えるんだろうな」と悠太郎は、夕映えの烏川を眺めながら考えた。
そんなことがあって二学期になってからは、音楽の時間に発する悠太郎の歌声は、めっきり元気がなくなった。これをデア・ノイエこと野家宏先生が心配したのは当然であった。野家先生が話しかけてきたのは、音楽の時間が終わった後であったか、それとも昼休みであったか、悠太郎はもうほとんど記憶がなかった。ただはっきり憶えているのは、その日の朝食の席で、梅子がパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、今日はねえ、田茂さんのうちの幸男ちゃんが来てくれるよ。裏庭にある栗の樹の伸びすぎた大枝をウッフフ、伐ってもらうだよ」と言ったことである。悠太郎はその瞬間、いつもの水っぽい野菜炒めに入っているキャベツの芯が、急に口のなかで咀嚼できないものに変わってしまったように感じた。家族や友達に思い出を与えてくれたその栗の樹が、悠太郎はとても好きであった。「痛え! 栗の毬が指にぶっさ刺さった!」という直矢の声は、今もありありと思い出された。もともと樹を伐ることを嫌う千代次はすでに老齢であり、田茂さんの家の者が樹を伐りにくることは間々あったとはいえ、なぜかその日は鈍重な牡牛のような風貌の幸男さんが、何か途方もない失敗をやらかしはしないかと悠太郎は恐れた。
そうしたわけで悠太郎の歌声はますます揮わなかった。だから野家先生は悠太郎を気遣い、「何やらひどい目に遭ったようだな、ユダス・マカベウス。きみの青春の戦いは、いきなり戦況不利と見える」と語りかけた。「戦いは私の本領ではありません。降りかかる火の粉は払わなければなりませんが、本来は穏やかに夢見ていたいのです。そうも言っていられなくなってしまいましたが」と悠太郎は応じた。「そうかな? きみは戦士の名を帯びている」と野家先生は言い、「きみは戦士だ、ユダス・マカベウス。きっと難局を切り抜けるよ。戦士といっても、乱暴者という意味ではない。生存競争に勝ち抜くということとも違う。戦士とは、真の実在に直接触れることができる人を言うのだ。人はナルシシズムの段階を脱却しなければならない。水の鏡に映った自分自身を見つめている段階から、想像力の外の真実に触れる段階へと進まねばならない。きみを優しく包み込んでいる母性的なものを切り裂いて、その外にある真の実在に触れなければならない。真の実在はきみのことをえこひいきして大事にはしない。真の実在はきみに優しくないし、容赦がない。しかしきみをえこひいきして大事にしないもの、きみに優しくないもの、きみに容赦ないものが、実は大いなるものの愛なのだよ。それに直接触れる人は、だから戦士のようでなければならない。この世から戦争がまったくなくなっても、心の在り方としての戦士の比喩は残るだろう。だからヘンデルのあのオラトリオも、また不滅というわけさ」と語った。「私に容赦ないものが、私を愛している……?」と悠太郎は半信半疑で言い、「それでは親の愛や恋人の愛はどうなるのですか?」と問うた。「取るに足らないものだよ」と野家先生は即答し、「大いなるものの愛に比べればの話だがね。もちろん人間は限界のある生き物だ。善人も悪人も等しく照らす太陽のような愛し方はできない。だから人間は、対象を選んで愛するという愛し方に留まるべきだろう。だがそういう愛がすべてではないということさ」と言い添えた。「私に容赦ないものが、私を愛している……」と悠太郎は、なおも自分を納得させるように言った。「もしきみが高崎に受かったら、そのときには俺がチェロで〈「見よ勇者の帰れるを」の主題による変奏曲〉を弾いてやろう」と野家先生は思いついたように言った。「そうだ、場所は観光ホテル明鏡閣の大食堂がいい。きみが旅立つのなら、是非ともあの湖畔からでなければならないだろう。きみならきっと、この難局を切り抜ける。健闘を祈るよ、ユダス・マカベウス。高崎からでも、晴れた日には浅間山が見えるだろう……」
そんなことがあって学校から帰った悠太郎は、裏庭で幹を伐られた栗の樹を見て呆然とした。「何だ、これは」と思いながら宵闇のなかに立ち尽くした悠太郎であったが、すぐさま家に駆け込むと、「お祖母様、何ですか、あの樹は! どういうことですか!」と梅子に問い質した。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、幸男ちゃんがねえ、間違えただよ。大枝を切ってくれと言ったつもりだったんだけどねえ、幹を伐っただよ」と答えた。「間違えた? 間違えたで済む話ですか? これでもう栗の実は採れなくなっていしまいました! 幸男さんはわが家の財産を損壊したんです! 賠償をさせなければなりません! さもなければ、報復を!」と悠太郎は叫んだ。「ウッフフ、いいかい悠太郎、何よりの報復はねえ、おまえが高崎の高校に見事受かってみせることだよ。そうすれば屯匪ごときにウッフフ、わったしたちが侮られることはなくなるものを」と梅子は言った。悠太郎はまた玄関から駆け出すと、無残に伐られた栗の樹の前で跪き、その切り株に頬を当てて、「盗賊め、赦してはおかないぞ」とひとりごちながら涙を流した。いま夕映えの烏川を眺めながら、悠太郎は考えていた。「今にして思えば、あれは祖母の芝居だったのかもしれないな。俺の憎しみを燃え立たせ、闘争心を燃え上がらせるための猿芝居だったのかもしれない。だがそのために俺の大切なものを、平気で犠牲に供したのだとすれば恐ろしい。思えば祖母は、いつもそうだったではないか……」
やがて最後の合唱コンクールに向けた体育館練習が始まった。ホームルームで担任の尾池先生が勧めたこともあって、自由曲は〈大地讃頌〉に決していた。なんと神川直矢が指揮をするというのである。体育館のステージ上のグランドピアノには、彫りの深い愁いがちな顔をして黒岩梨々子が向かっていた。残りのみんなはステージに立ち並んだ。すると直矢が、「練習の前に話がある。真壁悠太郎、前に出ろ。これから裁判を始める」と宣言して、ピアノがある側の脇へ退いた。悠太郎は意表を突かれて驚きはしたが、とうとう来るべきものが来たという思いがあったのも事実であった。被告人たる悠太郎は歩み出ると、直矢が立っていた場所に立ってみんなと向かい合った。親しく懐かしい顔また顔がそこにあった。幼稚園からずっと一緒にいた顔もあれば、小学校のあいだだけ別れた顔もあった。その顔また顔が、今やほとんど例外なく敵意を帯びて悠太郎に向けられていた。「真壁悠太郎の罪状は以下のごとし」と直矢が始めた。「こいつは二年前の合唱コンクールに際し、女の色香に惑わされて敵に味方した。俺たちの競争相手だった先輩たちのために、その力を惜しみなく使い、俺たちの合唱を改善することは怠って、利敵行為を働いたのだ。みんなも憶えているだろう。当時の二年生が披露した、あの完璧な合唱を。あれはこいつが裏で糸を引いていたというのだから、呆れた話だ。先輩たちにしたような助言を俺たちにしてくれていれば、俺たちが金賞を獲れたかもしれないのに、それをこいつは怠ったのだ。こいつは裏切り者のユダだ。あまつさえ今また高校受験に際し、ひとり学区を飛び越えて高崎を目指すなんぞ、学年の和を乱すこと甚だしい。よって今この場にて、こいつは裁かれる。みんな、言いたいことを言え!」
「ユウ、おまえは姉の心を傷つけた。深く深く傷つけたんだ。俺としてはそのことだけで、万死に値すると言いたい」と、隼平が険のある顔つきで言った。「あんたは長いあいだ、よく走ってきたよ。あさってのほうを目指して、よく走った。これからはもう、ゆっくりお休み。お望みとあらば、永遠にね」と、黒曜石のような目を光らせながら金谷涼子が言った。「残念だけど、俺には庇いようがないね」と芹沢カイが、雀斑の散った顔に深刻な表情を浮かべて言った。「いつも自分だけは特別だと思いやがって。ユウはもう俺たちの仲間じゃない」と、発育のよい体つきをした戸井田一輝が言った。「精神の大地の開拓民が、とんだ無駄働きをしたもんだ。ユウはもう拓友じゃない。おまえは追放だ」と、荒れた唇で佐原康雄が言った。「可能性を現実化する方向を、間違えたのですな。追放はやむなしですな」と、生まれたばかりの怪獣のような岡崎冬美が言った。「こんなことになるなんて残念。あとはひとりで存分に《冬の旅》を歩んで」と、ピアノの椅子に座った黒岩梨々子が言った。「ゲターンの命運もここに尽きたな。ざまあ見ろ! 俺たちの恨みを思い知ったか!」と、細長い目を笑わせながら大柴映二が言った。「判決を言い渡す」と直矢が告げた。「真壁悠太郎は、俺たちと一緒に歌ってはならない。俺たちが最後に歌う〈大地讃頌〉は、このふるさとの大地を祝福するものである。裏切り者の歌声が混じれば、神聖な歌が穢れる。よって口パクを命じる。息継ぎだけはみんなと合わせろよ。歌ってねえことがばれねえようにな。この六里ヶ原の大地は、真壁悠太郎を退ける」
裁かれた悠太郎は、突然低く笑い出した。その笑い声は徐々に高まり、ついには地獄の底から響くような哄笑に変わった。「何がおかしい! 気が狂ったか!」と問う直矢に、悠太郎は「下郎め!」と罵声を浴びせた。「なんと卑しいことを考えてくれるのだ。裁くだと? おまえが俺を? 思い上がるな、薄汚い下郎め! 皆も聞け! 大地、大地、大地、大地、大地! そんなに大地を愛するなら、今すぐ土に還るがいい! 屯匪の孫どもめ! 盗賊の裔どもめ! うぬらの祖父母が清らかなこの六里ヶ原を穢し、大地に生きる農民を気取って五十年。その孫どもが俺を惑わし、愚弄しおる! 一緒に歌ってはならないだと? 上等だ! うぬらごときにこの声を貸すのは、豚に真珠を投げ与えるようなものだ! 豚どもめ! 汚らしい豚どもめ! 裁きは必ずやうぬらに下されよう! うぬらはこの地より絶たれよう! ああ、その権能さえあったなら、俺がうぬらをひとり残らず焼き滅ぼしてくれようものを……」
そのとき諸星真花名が歩み出て悠太郎に近づくと、片手の甲を悠太郎の額に当てて、「わあ、すごい熱」と言ったので、みんなは毒気を抜かれた。「悠太郎くんは受験勉強を頑張りすぎて、熱を出しました。それでちょっと変になっただけ。私が保健室に連れていきます。だからみんなは、どうか練習を続けてください」と、ふるえがちな声を励まして真花名は言った。悠太郎は言われるがまま、真花名に連れられて体育館を退出した。
ふたりはしばし無言で廊下を歩いていた。「俺は熱などない」と悠太郎が言えば、「知ってるよ」と真花名が応じた。「なぜ俺を助けた?」と悠太郎が問えば、「そうしたかったから」と真花名は答え、「あいつらには分からないんだよ。ユウちゃんの憧れの切実さも、理想の高さも、あいつらには何も分からないんだよ。だからユウちゃんはあいつらと分かり合おうとしなくていいんだよ」と続けた。「俺を庇ったからには、真花名さんもただでは済まないだろう。孤立無援になるぞ」と悠太郎が憂慮すると、「それなら孤立無援同士、仲良くしようよ」と真花名は言い、「ねえユウちゃん、こうなったからには、私と付き合ってみない? 受験まで孤立無援はつらいでしょう? 同盟を結んだと思って、支え合うのはどう? 誰かさんのことが忘れられないのは知ってる。でも失われたものは失われたものだよ。現に今あるものや、現に今いる人のなかで、ベターな選択をすることを学ばなくちゃ。どう?」と、驚くべき提案をした。「どうやらその話には乗ったほうがよさそうだな。幼稚園のとき名前のことで散々にからかわれてから、もう十年か。言う通りにしよう。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれだな」と悠太郎が応じると、「またそれを言う。前にもそれを言われたとき、私ちょっと傷ついたんだよ。それがいつのことだったか、ユウちゃんは憶えてないだろうけど」と真花名は膨れてみせた。「ごめんよ。考えてみれば失礼だね。しかし俺は前にもそんなことを言ったかな?」と悠太郎が言うと、「思い出さなくていいよ。過去はもう置いていこうよ。重たい過去はみんなこの六里ヶ原に投げ捨てて、私たちはそれぞれの新しい人生を始めようよ。今日はもうこのまま帰ろう。一緒に帰ろう」と真花名は言った。きらきら光る茶色いその目の目尻には、やはり笑い皺が刻まれていた。
「そんなことがあってからだったな、真花名さんといろいろなことを話すようになったのは。もっと早くそうならなかったことが不思議なほど、それは自然なことだった」と、悠太郎は夕映えの烏川を眺めながら思った。真花名と並んで歩きながら言葉を交わすことは、留夏子とそうすることとは全然違っていた。真花名がよく見抜いて言った通り、悠太郎が留夏子に感じていたのは、切実な憧れであり、高い理想であった。高い理想に向かって切なる憧れを向けるとき、その通り道に留夏子がいるような感じがした。たとえ――幼稚園時代は別にして――手を繋いだ数分間があったにせよ、悠太郎にとって年上の留夏子は、どこか浮世離れした精神的な存在であった。夏の湖のほとりで永遠について語り合ったあの日、留夏子は悠太郎を高みへと導く精神的な存在として、ひとつの極みに達していた。だが悠太郎に手を差し伸べた真花名は、もっと馴染み深い自然な存在であった。留夏子はあまりに鋭利な知性で、しばしば自分自身を傷つけていた。そうした自傷的な知性の閃きには、どこか華やかなところさえあった。しかし真花名の知性には、そのように度を過ごしたところはなかった。もしかしたら、俺が留夏子さんと永遠について語り合っていたあの日の湖畔にも、レンゲショウマの可憐な花はうつむくように咲いていたのかもしれない。ただ俺にそれが見えていなかっただけではないか?――六里ヶ原界隈一の美人で通っていた真花名の母親と、父親の母親である祖母との関係は、どうやら険悪であるらしかった。真花名がしっかりしなければ、あの幸薄そうな美雪さんを祖母が責めるということらしい。電気機械を扱う仕事の父親も、家庭内のスパークまでは直せないのだと、真花名はあるとき少しおどけて悠太郎に語ったことがあった。そうした家庭の問題によっても、真花名は華やかに傷つくのではなく、慎ましやかに傷ついていた。
「私ね、ユウちゃんといられるあいだに、笑顔の練習をしたいの。私なんだか昔から、どう笑っていいか分からなくて。私の笑顔って、何となくぎこちないでしょう? だから自然にうまく笑えるようになりたいんだ。ユウちゃんが面白い話をしてくれたら、私きっと自然に笑えるようになると思う」とあるとき真花名は言った。だが悠太郎にとって笑えるような話といえば、観光ホテル明鏡閣の従業員のことくらいしか思い浮かばなかったから、そんな話をしてみた。明鏡閣の社員食堂は狭苦しい従業員詰所で、そこには煙草の煙が充満していたこと。前支配人の南塚亮平さんが「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いをしたこと。市川先生の従兄弟である現支配人の黒岩栄作さんは、煙草の煙を輪っかの形にして連続で吐き出すという特技を持っていること。死んでしまったゲジゲジ眉毛の橋爪進吉さんが、食器棚から茶托を一枚取り出して自分の頭に乗せ、「照月湖から河童が出てきて、カッパッパー!」と言ったこと。樹氷まつりの件で橋爪さんが謝りに行った温泉旅館の女将が、十二単を着て出てきたこと。引退してひばりが丘へ引っ越した三池光子さんが、「水仙」とか「スイカ」とか「ピアノ」とか言うときのイントネーションのこと。ブロッコリーのような髪型をした森山伸代さんが、しばしば社員食堂へ遊びに来たこと。その伸代さんがポメラニアンのアンちゃんを、袋に入れて歩いていたこと。そのアンちゃんは馬刺しが好物で、栄養過多と運動不足のために早死にしたこと。光子さんが伸代さんと麻雀をしているとき、梅子が熱いお茶を雀卓の上に吐き出したこと。これもよく遊びに来ていた西軽井沢物産流通の営業の兄貴が、その光景を見て「へえ、へえ、へえ、まあずこりゃカオスだつうこと! 麻雀牌をぐちゃぐちゃに掻き回したようなカオスだつうこと!」と評したこと。ボート番小屋の桜井謙助老人が、ライサクさんと呼ばれていること。ライサクさんがギョロ目を見開くと、額に三筋の皺が寄ること。林浩一さんの顔が平たいこと。弁舌爽やかなおロク婆さんが、唐の国のお茶と称して空っ茶を飲ませたこと。沖縄旅行で花笠を被って幸せそうにしていたおタキ婆さんのこと。そのおタキ婆さんが尊敬していた春藤秋男さんは狐目であったこと。狐目の春藤さんがスキー旅行のとき、南国のビーチをレンズに描いたトロピカルグラスをくれたこと。真理教事件のときには黒岩サカエさんが、「俺たちは尊師のおかげでおめえ、損したよ」と吐き捨てるように駄洒落を言ったこと。板前の新海岳史さんは、包丁よりも鋏を使うほうが得意なこと。その奥さんでたらこ唇ののマッちゃんは、レストラン照月湖ガーデンで乾燥そばを茹でてお客さんに出していたこと。そのマッちゃんが、あるときお客さんに「そば湯をください」と言われ、お湯は捨ててしまっていたので狼狽したこと。夏のアルバイトとして来ていた久世利文さんは、この六里ヶ原が気に入って株式会社浅間観光に就職したこと。いかり肩の久世さんは、昼時になると社員食堂にのっそりと姿を現し、「腹が減りました」と言っては首を急激に後ろへ「くぜっ! くぜっ!」とばかり反らせること。レストラン照月湖ガーデンを〈ポカラ〉にした、食えない登原聖司店主のこと。その愛人らしい幽霊じみた手島妙子さんが、奇妙にゆっくりした動きをすること。店主の虐待に耐えかねたネパール人青年のチャンドラカルナ・ムリ・ギリさんが、「ミスター・トバラ、マフィア、マフィア!」と言い捨てて脱走したこと――。そうしたことどもを悠太郎は、折に触れて真花名に話して聞かせた。真花名はそのいちいちを面白がり、きらきら光る茶色の目に涙を浮かべて可憐に笑った。「私も小学校のテニス部の合宿で、明鏡閣に泊まったことがあるよ。でも内部にいる人たちが、そんなだなんて知らなかった。みんなユウちゃんにとって大切な人たちなんだね。ユウちゃんの大切な人たちが、私の大切な人たちになったみたいで、なんだか嬉しい」と真花名が言ったので、悠太郎は話してよかったと思った。
ふたりはCDの貸し借りもした。真花名はある女性シンガーのラブソングばかりを集めた《Loving You》というアルバムを悠太郎に貸してくれた。そして前から聴きたがっていたヘンデルの《マカベウスのユダ》を、悠太郎の手から受け取りもした。「五年生のときだっけ、ユウちゃんは話してくれたもんね。ユウちゃんの大切な曲は、私も聴いておきたいの」と真花名は言った。「聴くのはいいけど、三単現のsをthで綴るんじゃないよ。英語の試験でそれはまずい」と悠太郎が案ずると、「ユウちゃんじゃあるまいし、そういう影響の受け方はしないよ」と真花名は応じた。悠太郎の好きな「この悲嘆の嵐のすべては無駄ではない」という歌詞が、改めて真花名の気に入ったようであった。いつしかふたりは学校で顔を合わせるたび、その英語のフレーズを合言葉のように交わし合うようになった。ふたりはまた《Loving You》についても語り合った。真花名が特に好きなのは〈想い出のリボン〉で、季節が過ぎてゆくことの切なさが胸に迫るということであった。悠太郎は何より〈涙の天使に微笑みを〉を好んでいた。「通常のイントロの前に、緩やかで重々しいテンポのイントロを置いて、二段構えにしているのがいいね。歌詞の内容といい、曲想といい、楽曲の規模といい、全曲中の圧巻だろう。でも歌い出しの歌詞は、ちょっと変だね。手先が不器用な人なんだろうか。女の人の髪くらい、俺にだって結えるぜ。……昔は、結えたんだ。誰かの髪を結んだことがあるような気がする。誰だったかなあ……」と悠太郎が言えば、「そんなことは、もう思い出さなくていいんだよ。結えないのは、失恋して髪を切ったからに決まってるでしょう。眼光紙背に徹する読解力はどこへ行ったの? 国語の先生をも恐れさせるユウちゃんらしくもない。そんなことじゃ、入試に落ちるよ」と真花名が応じた。「落ちるか。そうさっぱりと言ってもらえると、覚悟ができる。そうだよね、無理な学区外受験をするからには、落ちることも考えておかないとね」と悠太郎が言えば、「たとえ入試に落ちたって、ユウちゃんはユウちゃんだよ。私にとっては、何も変わらない。でも受験の先にユウちゃんにとっていいことが待っているなら、きっと受かってほしいな」と真花名は応じ、「ユウちゃんが受かって帰ってくるとき、私はあの歌で迎えてあげる」と言って、
見よ 勝利の勇者がやって来る!
トランペットを吹き鳴らせ 太鼓を打ち鳴らせ
祝祭の支度をせよ 月桂冠を持ってこい
勝利の歌を彼にうたえ
と、いわゆる〈得賞歌〉口ずさんだ。「おいおい、いま歌ったら気が早いよ」と悠太郎が言えば、「景気づけだよ。前祝いだよ」と真花名は応じた。「いつか祖母が俺に言ったんだ。それは俺のように虚弱でのろまな子には、一生縁のない音楽だってね。ところが野家先生も、俺が入試に受かったら、チェロでその主題による変奏曲を弾いてくださると言っている。人生どうなるか分からないものだね。でも戦士だの勇者だの、本当は俺の柄じゃない……」と悠太郎はしみじみ言った。「そういえば」と真花名は思い出したように話題を変え、「《マカベウスのユダ》には勇ましくて壮大な曲もたくさんあるけど、私はイスラエルの女が歌う自由のアリアが好きだな。ほら、第一幕にあったでしょう?」と言って、
おお自由よ 汝こよなき宝よ
美徳の座にして喜びの泉よ!
と歌ったが、そのときの真花名の声は少しもふるえていなかった。「おお、俺たちは気が合うね。俺も全曲のなかで、実はそのアリアが特別に好きなんだ。瞑想的で静謐なアリアだよね。伴奏のチェンバロの音は、静まって動かない湖の明るい水面に、花びらを撒くようだ。小学生のときね、俺はラジカセを抱き締めるようにして、その曲を聴いたんだ」と悠太郎は語った。「そうなんだ。私たちは気が合うね。じゃあ私もラジカセを抱き締めるようにして、あの曲を聴く」と言った真花名は、「ユウちゃん、私たちも自由を求めようよ。受験戦争なんて言うけどさ、受験が戦争なら、それは自由を求めるための戦いだよ。私たちは自由になるんだよ。家庭からも、このふるさとからも、ふるさとに積み重なった過去からも」と続けた。バスを待つ人のための屋根つきベンチには、枯葉が舞い込んできた。もっとも互いの孤立無援を支え合うふたりにとっては、校舎のなかであれ外であれ、どこでも枯葉が舞っているようなものであった。
三年生になった悠太郎たちの担任は、再び尾池賢一先生に決まった(始業式で尾池先生の名前が読み上げられたとき、新三年生のみんなは歓声を上げたから、昨年度の担任であった市川悟先生には、実に気の毒なことであった)。新年度最初の三者面談で、悠太郎は高崎行きの志望を尾池先生に伝えた。「そうか悠太郎くん、ついに決心したか!」と尾池先生は顎を引きつけながら、キューピー人形を思わせるぱっちりした両目で悠太郎を見ながら言ったが、弛んだその顎はそのとき二重にも三重にもだぶついていた。「きみほどの学力がある生徒には、やはり大学まで行ってほしい。大学を目指すとなると、このあたりでは渋川を目指さないといけない。だが高崎からなら、もっと上の大学だって狙える。東大だって夢じゃないんだぜ。もし東大に受かれば、ありとあらゆる職業を選べるようになるんだ」と尾池先生は語った。「でも、そんなことがうちの子にできるでしょうか」と秀子は、下膨れの顔に憂いを浮かべた。しかし尾池先生は、「お母さんもおひとりでご苦労されたでしょう。でも悠太郎くんが高崎に受かれば、すべての苦労が報われるんですよ」と秀子に言った。受かれば、すべてが報われる。すべての苦労が報われる――。「思えばあの言葉を聞いてからだったな、目に見えて母の人が変わったのは」と悠太郎は、夕映えの烏川を眺めながら考えた。
定期試験でも全県の学力テストも、悠太郎は学内の学年首位を一度も譲らなかった。それどころか五教科の総得点は、四八〇点台を突破して四九〇点台を記録するようにもなり、あるときなどはこの県でトップであったと尾池先生が告げた。大柴映二も「ゲターンの野郎を引きずり下ろせ!」とは、もう言わなかった。とてもそんなことが不可能な境地へと、悠太郎が踏み入ってしまったのは明らかであった。だがその代わり、奇妙な戯れ歌のようなものが聞こえてくることがあった。発信源は映二とも神川直矢とも言われたその戯れ歌は、「ギターの弦をきりきり張れば、いつかぷつりと切れちまう」というものであった。「切れるなら切れるがいい、どうなっても俺はやり抜くのみだ」と悠太郎は、夜毎の勉強にますます力を入れていった。それでも学力テストでの予期せぬ失点がないわけではなかった。夏休み中に実施されたその学力テストは、なんと教室前の廊下に机を並べて実施されたのである。それは教室の補修工事のためで、テストが行なわれるあいだにも、業者が電動ドリルでひどい騒音を立てていた。そこへ持ってきて数学で二次関数の難問が出た。そのときの数学は全県で見ても平均点が著しく下がっており、悠太郎もまた大きく得点を落とした。六〇点台にまで落ち込んだ試験結果は、悠太郎の中学校時代にはこれだけであった。それでも合計得点は学年首位で変わらなかったが、悠太郎にとっても家族にとっても衝撃は大きかった。「平均点なんざ下がったって、おめえが下がったら駄目だろう! 馬鹿奴等ができねえったって、おめえだけはできなけりゃ駄目だろう!」と千代次は怒りを発した。秀子は悠太郎の部屋のピアノに鍵をかけると、その鍵を照月湖に投げ込んだ。「あの湖が干上がって、鍵が見つかることでもなければ、おまえの罪は赦されないと思いなさい!」と秀子はぶるぶるふるえながら叫んだ。「あれからだ、俺が鍵盤に触れなくなったのは。与えておいて、なぜ奪うんだろうな。どうせ奪うなら、なぜ与えるんだろうな」と悠太郎は、夕映えの烏川を眺めながら考えた。
そんなことがあって二学期になってからは、音楽の時間に発する悠太郎の歌声は、めっきり元気がなくなった。これをデア・ノイエこと野家宏先生が心配したのは当然であった。野家先生が話しかけてきたのは、音楽の時間が終わった後であったか、それとも昼休みであったか、悠太郎はもうほとんど記憶がなかった。ただはっきり憶えているのは、その日の朝食の席で、梅子がパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、今日はねえ、田茂さんのうちの幸男ちゃんが来てくれるよ。裏庭にある栗の樹の伸びすぎた大枝をウッフフ、伐ってもらうだよ」と言ったことである。悠太郎はその瞬間、いつもの水っぽい野菜炒めに入っているキャベツの芯が、急に口のなかで咀嚼できないものに変わってしまったように感じた。家族や友達に思い出を与えてくれたその栗の樹が、悠太郎はとても好きであった。「痛え! 栗の毬が指にぶっさ刺さった!」という直矢の声は、今もありありと思い出された。もともと樹を伐ることを嫌う千代次はすでに老齢であり、田茂さんの家の者が樹を伐りにくることは間々あったとはいえ、なぜかその日は鈍重な牡牛のような風貌の幸男さんが、何か途方もない失敗をやらかしはしないかと悠太郎は恐れた。
そうしたわけで悠太郎の歌声はますます揮わなかった。だから野家先生は悠太郎を気遣い、「何やらひどい目に遭ったようだな、ユダス・マカベウス。きみの青春の戦いは、いきなり戦況不利と見える」と語りかけた。「戦いは私の本領ではありません。降りかかる火の粉は払わなければなりませんが、本来は穏やかに夢見ていたいのです。そうも言っていられなくなってしまいましたが」と悠太郎は応じた。「そうかな? きみは戦士の名を帯びている」と野家先生は言い、「きみは戦士だ、ユダス・マカベウス。きっと難局を切り抜けるよ。戦士といっても、乱暴者という意味ではない。生存競争に勝ち抜くということとも違う。戦士とは、真の実在に直接触れることができる人を言うのだ。人はナルシシズムの段階を脱却しなければならない。水の鏡に映った自分自身を見つめている段階から、想像力の外の真実に触れる段階へと進まねばならない。きみを優しく包み込んでいる母性的なものを切り裂いて、その外にある真の実在に触れなければならない。真の実在はきみのことをえこひいきして大事にはしない。真の実在はきみに優しくないし、容赦がない。しかしきみをえこひいきして大事にしないもの、きみに優しくないもの、きみに容赦ないものが、実は大いなるものの愛なのだよ。それに直接触れる人は、だから戦士のようでなければならない。この世から戦争がまったくなくなっても、心の在り方としての戦士の比喩は残るだろう。だからヘンデルのあのオラトリオも、また不滅というわけさ」と語った。「私に容赦ないものが、私を愛している……?」と悠太郎は半信半疑で言い、「それでは親の愛や恋人の愛はどうなるのですか?」と問うた。「取るに足らないものだよ」と野家先生は即答し、「大いなるものの愛に比べればの話だがね。もちろん人間は限界のある生き物だ。善人も悪人も等しく照らす太陽のような愛し方はできない。だから人間は、対象を選んで愛するという愛し方に留まるべきだろう。だがそういう愛がすべてではないということさ」と言い添えた。「私に容赦ないものが、私を愛している……」と悠太郎は、なおも自分を納得させるように言った。「もしきみが高崎に受かったら、そのときには俺がチェロで〈「見よ勇者の帰れるを」の主題による変奏曲〉を弾いてやろう」と野家先生は思いついたように言った。「そうだ、場所は観光ホテル明鏡閣の大食堂がいい。きみが旅立つのなら、是非ともあの湖畔からでなければならないだろう。きみならきっと、この難局を切り抜ける。健闘を祈るよ、ユダス・マカベウス。高崎からでも、晴れた日には浅間山が見えるだろう……」
そんなことがあって学校から帰った悠太郎は、裏庭で幹を伐られた栗の樹を見て呆然とした。「何だ、これは」と思いながら宵闇のなかに立ち尽くした悠太郎であったが、すぐさま家に駆け込むと、「お祖母様、何ですか、あの樹は! どういうことですか!」と梅子に問い質した。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、幸男ちゃんがねえ、間違えただよ。大枝を切ってくれと言ったつもりだったんだけどねえ、幹を伐っただよ」と答えた。「間違えた? 間違えたで済む話ですか? これでもう栗の実は採れなくなっていしまいました! 幸男さんはわが家の財産を損壊したんです! 賠償をさせなければなりません! さもなければ、報復を!」と悠太郎は叫んだ。「ウッフフ、いいかい悠太郎、何よりの報復はねえ、おまえが高崎の高校に見事受かってみせることだよ。そうすれば屯匪ごときにウッフフ、わったしたちが侮られることはなくなるものを」と梅子は言った。悠太郎はまた玄関から駆け出すと、無残に伐られた栗の樹の前で跪き、その切り株に頬を当てて、「盗賊め、赦してはおかないぞ」とひとりごちながら涙を流した。いま夕映えの烏川を眺めながら、悠太郎は考えていた。「今にして思えば、あれは祖母の芝居だったのかもしれないな。俺の憎しみを燃え立たせ、闘争心を燃え上がらせるための猿芝居だったのかもしれない。だがそのために俺の大切なものを、平気で犠牲に供したのだとすれば恐ろしい。思えば祖母は、いつもそうだったではないか……」
やがて最後の合唱コンクールに向けた体育館練習が始まった。ホームルームで担任の尾池先生が勧めたこともあって、自由曲は〈大地讃頌〉に決していた。なんと神川直矢が指揮をするというのである。体育館のステージ上のグランドピアノには、彫りの深い愁いがちな顔をして黒岩梨々子が向かっていた。残りのみんなはステージに立ち並んだ。すると直矢が、「練習の前に話がある。真壁悠太郎、前に出ろ。これから裁判を始める」と宣言して、ピアノがある側の脇へ退いた。悠太郎は意表を突かれて驚きはしたが、とうとう来るべきものが来たという思いがあったのも事実であった。被告人たる悠太郎は歩み出ると、直矢が立っていた場所に立ってみんなと向かい合った。親しく懐かしい顔また顔がそこにあった。幼稚園からずっと一緒にいた顔もあれば、小学校のあいだだけ別れた顔もあった。その顔また顔が、今やほとんど例外なく敵意を帯びて悠太郎に向けられていた。「真壁悠太郎の罪状は以下のごとし」と直矢が始めた。「こいつは二年前の合唱コンクールに際し、女の色香に惑わされて敵に味方した。俺たちの競争相手だった先輩たちのために、その力を惜しみなく使い、俺たちの合唱を改善することは怠って、利敵行為を働いたのだ。みんなも憶えているだろう。当時の二年生が披露した、あの完璧な合唱を。あれはこいつが裏で糸を引いていたというのだから、呆れた話だ。先輩たちにしたような助言を俺たちにしてくれていれば、俺たちが金賞を獲れたかもしれないのに、それをこいつは怠ったのだ。こいつは裏切り者のユダだ。あまつさえ今また高校受験に際し、ひとり学区を飛び越えて高崎を目指すなんぞ、学年の和を乱すこと甚だしい。よって今この場にて、こいつは裁かれる。みんな、言いたいことを言え!」
「ユウ、おまえは姉の心を傷つけた。深く深く傷つけたんだ。俺としてはそのことだけで、万死に値すると言いたい」と、隼平が険のある顔つきで言った。「あんたは長いあいだ、よく走ってきたよ。あさってのほうを目指して、よく走った。これからはもう、ゆっくりお休み。お望みとあらば、永遠にね」と、黒曜石のような目を光らせながら金谷涼子が言った。「残念だけど、俺には庇いようがないね」と芹沢カイが、雀斑の散った顔に深刻な表情を浮かべて言った。「いつも自分だけは特別だと思いやがって。ユウはもう俺たちの仲間じゃない」と、発育のよい体つきをした戸井田一輝が言った。「精神の大地の開拓民が、とんだ無駄働きをしたもんだ。ユウはもう拓友じゃない。おまえは追放だ」と、荒れた唇で佐原康雄が言った。「可能性を現実化する方向を、間違えたのですな。追放はやむなしですな」と、生まれたばかりの怪獣のような岡崎冬美が言った。「こんなことになるなんて残念。あとはひとりで存分に《冬の旅》を歩んで」と、ピアノの椅子に座った黒岩梨々子が言った。「ゲターンの命運もここに尽きたな。ざまあ見ろ! 俺たちの恨みを思い知ったか!」と、細長い目を笑わせながら大柴映二が言った。「判決を言い渡す」と直矢が告げた。「真壁悠太郎は、俺たちと一緒に歌ってはならない。俺たちが最後に歌う〈大地讃頌〉は、このふるさとの大地を祝福するものである。裏切り者の歌声が混じれば、神聖な歌が穢れる。よって口パクを命じる。息継ぎだけはみんなと合わせろよ。歌ってねえことがばれねえようにな。この六里ヶ原の大地は、真壁悠太郎を退ける」
裁かれた悠太郎は、突然低く笑い出した。その笑い声は徐々に高まり、ついには地獄の底から響くような哄笑に変わった。「何がおかしい! 気が狂ったか!」と問う直矢に、悠太郎は「下郎め!」と罵声を浴びせた。「なんと卑しいことを考えてくれるのだ。裁くだと? おまえが俺を? 思い上がるな、薄汚い下郎め! 皆も聞け! 大地、大地、大地、大地、大地! そんなに大地を愛するなら、今すぐ土に還るがいい! 屯匪の孫どもめ! 盗賊の裔どもめ! うぬらの祖父母が清らかなこの六里ヶ原を穢し、大地に生きる農民を気取って五十年。その孫どもが俺を惑わし、愚弄しおる! 一緒に歌ってはならないだと? 上等だ! うぬらごときにこの声を貸すのは、豚に真珠を投げ与えるようなものだ! 豚どもめ! 汚らしい豚どもめ! 裁きは必ずやうぬらに下されよう! うぬらはこの地より絶たれよう! ああ、その権能さえあったなら、俺がうぬらをひとり残らず焼き滅ぼしてくれようものを……」
そのとき諸星真花名が歩み出て悠太郎に近づくと、片手の甲を悠太郎の額に当てて、「わあ、すごい熱」と言ったので、みんなは毒気を抜かれた。「悠太郎くんは受験勉強を頑張りすぎて、熱を出しました。それでちょっと変になっただけ。私が保健室に連れていきます。だからみんなは、どうか練習を続けてください」と、ふるえがちな声を励まして真花名は言った。悠太郎は言われるがまま、真花名に連れられて体育館を退出した。
ふたりはしばし無言で廊下を歩いていた。「俺は熱などない」と悠太郎が言えば、「知ってるよ」と真花名が応じた。「なぜ俺を助けた?」と悠太郎が問えば、「そうしたかったから」と真花名は答え、「あいつらには分からないんだよ。ユウちゃんの憧れの切実さも、理想の高さも、あいつらには何も分からないんだよ。だからユウちゃんはあいつらと分かり合おうとしなくていいんだよ」と続けた。「俺を庇ったからには、真花名さんもただでは済まないだろう。孤立無援になるぞ」と悠太郎が憂慮すると、「それなら孤立無援同士、仲良くしようよ」と真花名は言い、「ねえユウちゃん、こうなったからには、私と付き合ってみない? 受験まで孤立無援はつらいでしょう? 同盟を結んだと思って、支え合うのはどう? 誰かさんのことが忘れられないのは知ってる。でも失われたものは失われたものだよ。現に今あるものや、現に今いる人のなかで、ベターな選択をすることを学ばなくちゃ。どう?」と、驚くべき提案をした。「どうやらその話には乗ったほうがよさそうだな。幼稚園のとき名前のことで散々にからかわれてから、もう十年か。言う通りにしよう。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれだな」と悠太郎が応じると、「またそれを言う。前にもそれを言われたとき、私ちょっと傷ついたんだよ。それがいつのことだったか、ユウちゃんは憶えてないだろうけど」と真花名は膨れてみせた。「ごめんよ。考えてみれば失礼だね。しかし俺は前にもそんなことを言ったかな?」と悠太郎が言うと、「思い出さなくていいよ。過去はもう置いていこうよ。重たい過去はみんなこの六里ヶ原に投げ捨てて、私たちはそれぞれの新しい人生を始めようよ。今日はもうこのまま帰ろう。一緒に帰ろう」と真花名は言った。きらきら光る茶色いその目の目尻には、やはり笑い皺が刻まれていた。
「そんなことがあってからだったな、真花名さんといろいろなことを話すようになったのは。もっと早くそうならなかったことが不思議なほど、それは自然なことだった」と、悠太郎は夕映えの烏川を眺めながら思った。真花名と並んで歩きながら言葉を交わすことは、留夏子とそうすることとは全然違っていた。真花名がよく見抜いて言った通り、悠太郎が留夏子に感じていたのは、切実な憧れであり、高い理想であった。高い理想に向かって切なる憧れを向けるとき、その通り道に留夏子がいるような感じがした。たとえ――幼稚園時代は別にして――手を繋いだ数分間があったにせよ、悠太郎にとって年上の留夏子は、どこか浮世離れした精神的な存在であった。夏の湖のほとりで永遠について語り合ったあの日、留夏子は悠太郎を高みへと導く精神的な存在として、ひとつの極みに達していた。だが悠太郎に手を差し伸べた真花名は、もっと馴染み深い自然な存在であった。留夏子はあまりに鋭利な知性で、しばしば自分自身を傷つけていた。そうした自傷的な知性の閃きには、どこか華やかなところさえあった。しかし真花名の知性には、そのように度を過ごしたところはなかった。もしかしたら、俺が留夏子さんと永遠について語り合っていたあの日の湖畔にも、レンゲショウマの可憐な花はうつむくように咲いていたのかもしれない。ただ俺にそれが見えていなかっただけではないか?――六里ヶ原界隈一の美人で通っていた真花名の母親と、父親の母親である祖母との関係は、どうやら険悪であるらしかった。真花名がしっかりしなければ、あの幸薄そうな美雪さんを祖母が責めるということらしい。電気機械を扱う仕事の父親も、家庭内のスパークまでは直せないのだと、真花名はあるとき少しおどけて悠太郎に語ったことがあった。そうした家庭の問題によっても、真花名は華やかに傷つくのではなく、慎ましやかに傷ついていた。
「私ね、ユウちゃんといられるあいだに、笑顔の練習をしたいの。私なんだか昔から、どう笑っていいか分からなくて。私の笑顔って、何となくぎこちないでしょう? だから自然にうまく笑えるようになりたいんだ。ユウちゃんが面白い話をしてくれたら、私きっと自然に笑えるようになると思う」とあるとき真花名は言った。だが悠太郎にとって笑えるような話といえば、観光ホテル明鏡閣の従業員のことくらいしか思い浮かばなかったから、そんな話をしてみた。明鏡閣の社員食堂は狭苦しい従業員詰所で、そこには煙草の煙が充満していたこと。前支配人の南塚亮平さんが「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いをしたこと。市川先生の従兄弟である現支配人の黒岩栄作さんは、煙草の煙を輪っかの形にして連続で吐き出すという特技を持っていること。死んでしまったゲジゲジ眉毛の橋爪進吉さんが、食器棚から茶托を一枚取り出して自分の頭に乗せ、「照月湖から河童が出てきて、カッパッパー!」と言ったこと。樹氷まつりの件で橋爪さんが謝りに行った温泉旅館の女将が、十二単を着て出てきたこと。引退してひばりが丘へ引っ越した三池光子さんが、「水仙」とか「スイカ」とか「ピアノ」とか言うときのイントネーションのこと。ブロッコリーのような髪型をした森山伸代さんが、しばしば社員食堂へ遊びに来たこと。その伸代さんがポメラニアンのアンちゃんを、袋に入れて歩いていたこと。そのアンちゃんは馬刺しが好物で、栄養過多と運動不足のために早死にしたこと。光子さんが伸代さんと麻雀をしているとき、梅子が熱いお茶を雀卓の上に吐き出したこと。これもよく遊びに来ていた西軽井沢物産流通の営業の兄貴が、その光景を見て「へえ、へえ、へえ、まあずこりゃカオスだつうこと! 麻雀牌をぐちゃぐちゃに掻き回したようなカオスだつうこと!」と評したこと。ボート番小屋の桜井謙助老人が、ライサクさんと呼ばれていること。ライサクさんがギョロ目を見開くと、額に三筋の皺が寄ること。林浩一さんの顔が平たいこと。弁舌爽やかなおロク婆さんが、唐の国のお茶と称して空っ茶を飲ませたこと。沖縄旅行で花笠を被って幸せそうにしていたおタキ婆さんのこと。そのおタキ婆さんが尊敬していた春藤秋男さんは狐目であったこと。狐目の春藤さんがスキー旅行のとき、南国のビーチをレンズに描いたトロピカルグラスをくれたこと。真理教事件のときには黒岩サカエさんが、「俺たちは尊師のおかげでおめえ、損したよ」と吐き捨てるように駄洒落を言ったこと。板前の新海岳史さんは、包丁よりも鋏を使うほうが得意なこと。その奥さんでたらこ唇ののマッちゃんは、レストラン照月湖ガーデンで乾燥そばを茹でてお客さんに出していたこと。そのマッちゃんが、あるときお客さんに「そば湯をください」と言われ、お湯は捨ててしまっていたので狼狽したこと。夏のアルバイトとして来ていた久世利文さんは、この六里ヶ原が気に入って株式会社浅間観光に就職したこと。いかり肩の久世さんは、昼時になると社員食堂にのっそりと姿を現し、「腹が減りました」と言っては首を急激に後ろへ「くぜっ! くぜっ!」とばかり反らせること。レストラン照月湖ガーデンを〈ポカラ〉にした、食えない登原聖司店主のこと。その愛人らしい幽霊じみた手島妙子さんが、奇妙にゆっくりした動きをすること。店主の虐待に耐えかねたネパール人青年のチャンドラカルナ・ムリ・ギリさんが、「ミスター・トバラ、マフィア、マフィア!」と言い捨てて脱走したこと――。そうしたことどもを悠太郎は、折に触れて真花名に話して聞かせた。真花名はそのいちいちを面白がり、きらきら光る茶色の目に涙を浮かべて可憐に笑った。「私も小学校のテニス部の合宿で、明鏡閣に泊まったことがあるよ。でも内部にいる人たちが、そんなだなんて知らなかった。みんなユウちゃんにとって大切な人たちなんだね。ユウちゃんの大切な人たちが、私の大切な人たちになったみたいで、なんだか嬉しい」と真花名が言ったので、悠太郎は話してよかったと思った。
ふたりはCDの貸し借りもした。真花名はある女性シンガーのラブソングばかりを集めた《Loving You》というアルバムを悠太郎に貸してくれた。そして前から聴きたがっていたヘンデルの《マカベウスのユダ》を、悠太郎の手から受け取りもした。「五年生のときだっけ、ユウちゃんは話してくれたもんね。ユウちゃんの大切な曲は、私も聴いておきたいの」と真花名は言った。「聴くのはいいけど、三単現のsをthで綴るんじゃないよ。英語の試験でそれはまずい」と悠太郎が案ずると、「ユウちゃんじゃあるまいし、そういう影響の受け方はしないよ」と真花名は応じた。悠太郎の好きな「この悲嘆の嵐のすべては無駄ではない」という歌詞が、改めて真花名の気に入ったようであった。いつしかふたりは学校で顔を合わせるたび、その英語のフレーズを合言葉のように交わし合うようになった。ふたりはまた《Loving You》についても語り合った。真花名が特に好きなのは〈想い出のリボン〉で、季節が過ぎてゆくことの切なさが胸に迫るということであった。悠太郎は何より〈涙の天使に微笑みを〉を好んでいた。「通常のイントロの前に、緩やかで重々しいテンポのイントロを置いて、二段構えにしているのがいいね。歌詞の内容といい、曲想といい、楽曲の規模といい、全曲中の圧巻だろう。でも歌い出しの歌詞は、ちょっと変だね。手先が不器用な人なんだろうか。女の人の髪くらい、俺にだって結えるぜ。……昔は、結えたんだ。誰かの髪を結んだことがあるような気がする。誰だったかなあ……」と悠太郎が言えば、「そんなことは、もう思い出さなくていいんだよ。結えないのは、失恋して髪を切ったからに決まってるでしょう。眼光紙背に徹する読解力はどこへ行ったの? 国語の先生をも恐れさせるユウちゃんらしくもない。そんなことじゃ、入試に落ちるよ」と真花名が応じた。「落ちるか。そうさっぱりと言ってもらえると、覚悟ができる。そうだよね、無理な学区外受験をするからには、落ちることも考えておかないとね」と悠太郎が言えば、「たとえ入試に落ちたって、ユウちゃんはユウちゃんだよ。私にとっては、何も変わらない。でも受験の先にユウちゃんにとっていいことが待っているなら、きっと受かってほしいな」と真花名は応じ、「ユウちゃんが受かって帰ってくるとき、私はあの歌で迎えてあげる」と言って、
見よ 勝利の勇者がやって来る!
トランペットを吹き鳴らせ 太鼓を打ち鳴らせ
祝祭の支度をせよ 月桂冠を持ってこい
勝利の歌を彼にうたえ
と、いわゆる〈得賞歌〉口ずさんだ。「おいおい、いま歌ったら気が早いよ」と悠太郎が言えば、「景気づけだよ。前祝いだよ」と真花名は応じた。「いつか祖母が俺に言ったんだ。それは俺のように虚弱でのろまな子には、一生縁のない音楽だってね。ところが野家先生も、俺が入試に受かったら、チェロでその主題による変奏曲を弾いてくださると言っている。人生どうなるか分からないものだね。でも戦士だの勇者だの、本当は俺の柄じゃない……」と悠太郎はしみじみ言った。「そういえば」と真花名は思い出したように話題を変え、「《マカベウスのユダ》には勇ましくて壮大な曲もたくさんあるけど、私はイスラエルの女が歌う自由のアリアが好きだな。ほら、第一幕にあったでしょう?」と言って、
おお自由よ 汝こよなき宝よ
美徳の座にして喜びの泉よ!
と歌ったが、そのときの真花名の声は少しもふるえていなかった。「おお、俺たちは気が合うね。俺も全曲のなかで、実はそのアリアが特別に好きなんだ。瞑想的で静謐なアリアだよね。伴奏のチェンバロの音は、静まって動かない湖の明るい水面に、花びらを撒くようだ。小学生のときね、俺はラジカセを抱き締めるようにして、その曲を聴いたんだ」と悠太郎は語った。「そうなんだ。私たちは気が合うね。じゃあ私もラジカセを抱き締めるようにして、あの曲を聴く」と言った真花名は、「ユウちゃん、私たちも自由を求めようよ。受験戦争なんて言うけどさ、受験が戦争なら、それは自由を求めるための戦いだよ。私たちは自由になるんだよ。家庭からも、このふるさとからも、ふるさとに積み重なった過去からも」と続けた。バスを待つ人のための屋根つきベンチには、枯葉が舞い込んできた。もっとも互いの孤立無援を支え合うふたりにとっては、校舎のなかであれ外であれ、どこでも枯葉が舞っているようなものであった。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
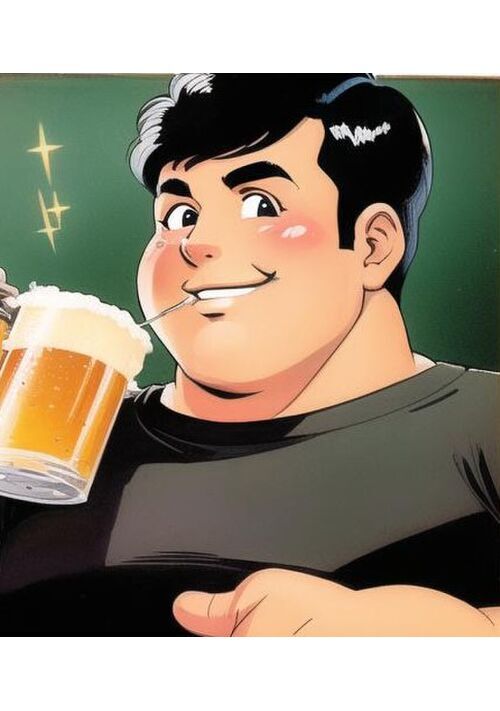
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















