66 / 73
第二十二章 秋晴れの野に
三
しおりを挟む
九月のある日、愛人の美久さんを伴って六里ヶ原を訪れていた松並木社長は、観光ホテル明鏡閣の社員食堂に従業員たちを呼び集めた。窓の反対側に取りつけられた長方形の鏡は、円形の花壇に植えられた豪奢なダリアの花々を映していた。「いやはや、みなさんご苦労様です。明鏡閣もキャンプ場も、弓道場もランニングコースもカレー屋さんも、実にうまく行きました。本当に皆さんは、これまで本当によくやってくれました。ありがとう。ありがとう。それなのにこんな話をしなければならないのは、本当に惜しいなあ」と、太鼓腹の五十男である松並木社長は、左目の下に大きなほくろのある顔に満面の笑みを浮かべた。「よくやってくれましたって、なんで過去形なんですか?」と問うた黒岩栄作支配人の表情が暗かったのは、薄黒いサングラスのせいばかりではなく、不吉な予感を覚えたからでもあった。そう訊かれた松並木社長は、隣にいる美久さんの顔を困ったように見た。長い黒髪を大輪の薔薇のように巻いていた美久さんは、瞼と唇の厚い肉感的な顔を微笑ませた。その微笑みに励まされてか、松並木社長は厄介事を早く済ませたい人のように、言うべきことを口にした。「それはね、この会社が、なくなるからです」
松並木社長によれば、それは先代の社長であった鈴木オーナーの意向だという。鈴木オーナーは増田ケンポウ社長の娘婿であった関係で、株式会社浅間観光の三代目の社長を務め、社長職を松並木現社長に譲った後も、会社のオーナーであり続けていた。その鈴木オーナーのひとり娘は、幸福な結婚をして芦屋夫人となり、子供にも恵まれて、前途に何の憂いもないはずであった。ところが先の大震災で芦屋は被災し、その娘の夫の事業は破綻した。被災地でのままならぬ暮らしから来る心労のためか、夫は急死したというのである。寡婦となったその娘は、子供を抱えて途方に暮れている――。「ついては」と松並木社長は言った。「大して儲からないこの会社を売却してだね、そのお金で娘さんとお孫さんのためにマンションを一棟建てて、一生心配のないようにしてやりたいということです。いやあ、親心というものじゃありませんか、皆さん。まあね、なくなるといっても、今日明日にというわけじゃありませんよ。まだまだ決めなきゃならないことや、整理しなければならないことがたくさんありますから、あと何年かはかかるでしょう。そういうわけですから皆さん、どうか最後までひとつよろしくお願いしますね」そう話し終えると松並木さんは、美久さんと一緒に社員食堂を出て客室へ消えていった。
衝撃の後の重苦しい沈黙が社員食堂を浸していた。「時勢かのう。始まったものは終わってゆく。この会社も例外じゃなかんべえ」とライサク老人こと桜井謙助さんは、ギョロ目を見開いて額に三筋の皺を寄せた。「時勢で片づけていい問題っすか? 完全にオーナーの個人的な事情じゃないっすか! 私利私欲でみんなの会社を廃業するんすか? ふざけてますよ!」と、いかり型の久世利文さんは鋭い喉仏のような語気で言うと、「くぜっ! くぜっ!」とばかりに首を急激に後ろへ反らせた。「あんた、次の仕事はどうするよ?」と、たらこ唇のマッちゃんがだみ声で言えば、板前の新海岳史さんはにかっと歯を見せて泣き笑いのような顔をした。蒼白な顔のおタキ婆さんは苦しげに目を細めながら、「春藤さんがいなくなってから、あたしたちはついてないねえ」と言った。紫色の三角巾を被ったおロク婆さんは、「あたしたちはずいぶん楽しい思いをさせてもらったけど、それもいよいよこれまでかねえ」と、活力を失った声で言った。林浩一さんもまた、平たい顔からにこやかな笑みを消していたが、「でもちょっとまってくださいよ。要するに鈴木さんがマンションを建てられればいいわけでしょう? ぼくらがもっと工夫して売り上げれば、その利益でマンションが建つんじゃないですか?」と言った。「鈴木さんは嫌になったんだろう。なまじ増田ケンポウの娘と結婚したばかりに、別段思い入れもない地域の浮き沈みを背負い込んじまった。はあそれが面倒になっていたんだよ。娘の旦那が死んだことで、それが顕在化しただけだんべえ」と黒岩サカエ支配人は暗い声で言った。「でも私は納得できない」と秀子は、下膨れの顔をぶるぶるとふるわせながら言った。「浅間観光があればこそ、この地域が支えられて潤うんじゃない。鈴木さんにはそのことを、どうしても思い出していただかなきゃ」
真壁の家に帰宅した秀子は、激しく叩きつけるように自動車のドアを閉め、玄関のドアをがばと開けバタンと閉め、廊下をドスン・ドスン・ドスン・ドスン・ドスンと五歩踏み鳴らして、居間への引き戸をガラガラと開けると、職場での出来事を洗いざらい悠太郎にぶちまけた。そしてその夜、鈴木オーナーに宛てた長い手紙を書いていた。私の父は今は亡き増田ケンポウ社長に重んじられ、株式会社浅間観光の永久名誉顧問を務めている。私もまた浅間観光に就職する機会をいただき、それ以来充実感をもって働き続けてきた。この会社に勤める従業員たちも、やり甲斐を感じながら献身的に勤めている。ところで従業員には様々な人がいる。学生のアルバイトとして働きに来たら、ここが気に入ってしまったので就職した人がいる。農作業を息子に継がせた開拓農民が、ボート番小屋で働いている。また浅間観光に雇用されているわけではないが、照月湖のほとりに売店を出して野菜を売っている農家の人もいる。この売店で売られている高原野菜は、浅間観光の夏にとって欠かせないものになっている。さらに視野を広げれば、様々な業種の人々が浅間観光を支え、また浅間観光に支えられている。スーパーマーケットの〈ダイマルヤ〉は、浅間観光の仕入れだけで、ひと夏二千万円を売り上げるという。これだけの売り上げがなくなれば、〈ダイマルヤ〉は一年じゅう開店していることができなくなり、潰れることも考えられる。そうなれば、浅間観光を蛇蝎のように嫌う別荘村の人々だって、日々の買い物に困ることになり、別荘を捨てるかもしれない。結果として地域は荒廃する。クリーニング店だって、浅間観光のリネン類の洗濯だけで、どれほどの売り上げになるか計り知れない。その仕事が奪われるなら、やはり地域は荒廃する。照月湖であれ明鏡閣であれ、湖畔や河畔のキャンプ場であれ、弓道場であれランニングコースであれ〈ポカラ〉であれ、それらを目当てに六里ヶ原を訪れる人がいなくなれば、バス会社もタクシー会社も売り上げを落とす。問題はお金のことばかりではない。多くのお客様がこの高原の風光を愛し、泊まりに来てくれる。全国にいるお客様たちの生きる喜びは、奪われてよいものではない。御令嬢と御令孫の苦衷はお察しする。しかしそのような個人的な事情によって、六里ヶ原の一画を占めるこの一地域を荒廃せしめることは、一社員として、また会社の永久名誉顧問の娘として、断固承服し難い――。そんな手紙を母は書いているのであろうと、悠太郎は想像した。浅間観光がなくなる――。今日明日のことではないと自分に言い聞かせながらも、悠太郎は目の前が暗くなるような、自分が底なし沼に吸い込まれてゆくような思いであった。「浅間観光が危ないそうね」と言った留夏子は、こうしたことの概要を知っていたわけであった。
その留夏子は悠太郎と並んで自転車を押しながら、「私もできる限り動いてみる。浅間観光がなくなったら、農家は野菜や果物の消費者を失うことになるもの。開拓の人たちの声を集めて、浅間観光の偉い人に届けられないか、祖父母と相談してみる」と言った。「ありがとうございます。しかし母の手紙にだって、今のところ何の反応もありません。農家の声が届くかどうか……」と悠太郎が懸念すると、「やってみなければ分からないでしょう。できることがあるのに、やらないよりはましよ。座して地域の滅びを待つべき道理はないもの」と留夏子は言い切った。星が瞬き始める薄闇のなかでも、なんとこの人は凛々として美しいのだろうと悠太郎は思った。そうだ、明日は英語の郡大会だ。この人は県大会への期待を背負いながら、俺のことを気に懸けてくれている。俺のほうこそ、この人の支えにならなければ――。そう念じた悠太郎は、秋の星空の話を留夏子とした。アンドロメダ座のこと、ペルセウス座のこと、カシオペア座のこと、白鳥座のこと――。並んで自転車を押すふたりは、しばし天空に思いを馳せて地上の些事を忘れた。それでもすっかり忘れてしまうわけにはゆかなかった。「英語の大会も、高校受験も、会社の危機も考えずに、ふたりでいつまでも星空を見ていたい」と留夏子が漏らした。
いつしかふたりは、四つの厳めしい石碑がある甘楽のバス停までやって来た。「満洲報国隊記念碑」「満洲開拓記念碑」「開拓者供養塔」「甘楽入植三十年記念碑」という文字は、すでにして闇に没していた。秋の夜風に樹々がざわざわと不吉な音を立てていた。闇に没したその文字に、留夏子はしばし思いを凝らすかのようであった。高校生になっていた中島猛夫が母親を殴って逮捕され、取り調べでバネットの殺害をも供述したという知らせが、留夏子の心を暗くしているに違いないと悠太郎は考えていた。「ねえ真壁、宮沢賢治がもっと長生きしていたら、どうなっていたと思う?」と留夏子は不意に言った。「もっと長生きしていたら……それは童話でも詩でも、素晴らしい作品をもっとたくさん書いたでしょう」と悠太郎は答えた。「それだけかしら? あるいは満蒙開拓移民の旗振り役になっていたかもしれない。そうは考えられない?」と留夏子は問うた。「賢治がですか? まさか!」と驚く悠太郎に、「賢治が亡くなったのは何年?」と留夏子はなおも問うた。「一九三三年です……あっ!」と悠太郎は答えるそばから驚いた。「そう。そのときにはもう満洲事変は起こっていたの。私たちは〈流浪の民〉に取り組んだわね。明治時代から詩に歌われてきた楽土ということが、昭和の満蒙開拓移民によって最悪の形で実現された。そこまでは私たちが一緒に確かめたことでしょう。ところがね、賢治のイーハトーブもまた、楽土のひとつなの。詩的な楽土であり、内なる楽土ね。農業技師として農民の生活向上に尽くした賢治が、外なる楽土の建設運動とされた満蒙開拓移民に、無関心でいられたかしら? そんな賢治を、私は見たくなかった。時宜を得た死に方って、あるのかもしれないわね」と留夏子は言った。さっき美帆が賢治の名前を出したから思い出したのかもしれないが、この考えは昨日や今日の思いつきではなさそうであった。「……何も愛する作品や作者のことを、そんなふうに考えなくてもいいのでは」と悠太郎が言うと、「認識するってそういうことなの。認識は苦いものなの」と留夏子は応じた。「今夜はもうこれらの碑の前で思い詰めずに、帰って休んでください。明日の朝は、いつもより少し早いですから」と悠太郎が言うと、「そうね。もう帰る。さようなら。また明日ね」と留夏子は自転車に跨った。だがすぐにブレーキをかけて振り返ると、「真壁、あなたはいつか私のことで、自分を責めるかもしれない。でも私はそんなこと、少しも望んでないから」と言い残して去っていった。しかし悠太郎はこの言葉を聞き取ることができなかった。秋の夜風に樹々がざわざわと不吉な音を立てたからである。
翌朝はほかの生徒たちが朝練習を始める前に、三人の代表は学校に集まった。見上げれば雲ひとつない秋晴れの空が広がっていた。清らかな朝の空気が、いつもより早い分だけいっそう清らかに澄んでいて、悠太郎は早起きの鳥たちと兄弟にでもなったような気がした。三人はイワトビペンギンのような金子先生が運転する自動車に乗り込んだ。留夏子が助手席に座り、悠太郎がその真後ろに、美帆がその右に座った。留夏子と金子先生の話が弾んでいた。「へえ、そうかい。佐藤さんのお母さんがピアノの先生で、真壁くんがその教室の生徒かい。それじゃおふたりを結びつけているのは、音楽というわけか。道理で話が合うわけだ。俺もいろいろと納得が行ったよ。佐藤さんにしても真壁くんにしても、その英語の優れているところは、やはり音楽性だな。アクセントやイントネーションやリズム感といったことだ。中学生の英語を普通に勉強しているだけでは、そこまでのことはなかなか身に着くものじゃない。しかし音楽が基礎にあれば話は別だよ。なるほどな……。しかしあれだな、誰も彼もがきみたちみたいな生徒だったらと考えると、ぞっとするよ。そうなったら俺のような英語教師は仕事がなくなる。小文字のbとdの区別もつかない生徒に手を焼いているうちが、英語教師の幸せなのかもしれないな」と金子先生は言った。「先生、私がいなくなっても、真壁のことをお願いしますね。私が見出した才能を、どうか磨いてあげてください」と留夏子は言った。「幼稚園の園庭で、私たちは無邪気に遊んでいました。よく一緒に〈アルプス一万尺〉の手遊びをしました。そのとき私は、彼の歌がうまいと思ったんです。彼の音楽の才能を、母は自分が見出したと思っていますけど、見出したのは私のほうが早いんですよ。もちろん彼が六里ヶ原の明鏡なんて呼ばれるようになる前のことです。そうして小学校二年生のときに、彼はピアノを始めました。いい生徒に恵まれて、母は幸せそうでした。真壁が来てくれる日には、母は朝から楽しそうでした。もし私がピアノを続けていれば、彼と一緒に弾くこともできたでしょう。でも私は父の不興を買うことを恐れて、バイエルも終わらせずに練習を放り出してしまいました。それはそれで仕方がなかったんです。でも発表会で母が彼と連弾しているのを見ると、なんだか羨ましくて。だから今日こうして同じ大会に出られることが、本当に夢のようです。卒業前に恵まれた幸せですね。でもだからといって、このまま時が止まるわけではありません。私は卒業してしまいます。その後のことを、先生、どうかよろしくお願いします」
悠太郎は留夏子の真後ろで、うつむきながらその言葉を聞いていた。自分のことをそんなふうに考えてくれていたのかと思えば、胸が熱くなりはした。しかしいつになく饒舌であるとも思った。今この場で話すべきことかどうか、疑問なしとはしなかった。あるいは斜め後ろの美帆に言い聞かせているのかもしれなかった。本番直前にこれほどの情感に浸っているのは、いかにも危ういと思われた。「おう、分かった。引き受けよう。学校一の俊英と謳われる佐藤さんに頼まれては、引き受けざるを得ないな。まあ俺はただの英語教師だから、できることに限りはあるが、精一杯指導して真壁くんの才能を開花させよう」と金子先生は応じた。そのあいだにも三人の代表を乗せた自動車は古森の坂を下り、吾妻川に沿うようにして原町を目指していた。
原町のとある文化会館を会場にして、英語暗唱大会の郡大会は粛々と戦われた。制服姿の中学生たちはホールに集い、ひとりまたひとりと演台に立った。一年生の部があり、二年生の部があり、三年生の部があった。各学校から選りすぐられた代表たちが暗唱する英語のように、流暢に時は流れた。その時の流れのなかに、美帆は静寂に満ちた言葉を、悠太郎は蚊に刺されてどうのこうのという重い言葉を、留夏子はハックルベリーの実のように甘酸っぱい言葉を浮かべた。差し当たり三人の代表たちは、練習の成果を大過なく出すことができた。あとは昼休憩明けに行なわれる結果発表を待つばかりであった。そして昼休憩には金子先生が、自動車で三人を近くの食堂まで連れていった。その食堂の名ははその日の空模様に相応しく〈あおぞら〉といった。金子先生の奢りでか、はたまた経費で落ちるのか、中学生たちにとって定かではなかったが、ともかくみんなは〈あおぞら〉で焼肉を食べるというわけであった。炭火が赤々と熾り、金網で肉が焼かれて煙と香ばしい匂いを立てた。四人の食欲は旺盛であった。英語暗唱大会の時間のように、楽しい昼食の時間もまた流れ過ぎていった。みんなが洗面所で歯を磨くと、金子先生が会計を済ませて、一行は〈あおぞら〉を後にした。
ところが駐車場では奇妙なことが起こった。「佐藤さん、真壁くん。俺と赤木さんは先に車で戻るから、ゆっくり歩いて帰っておいで。こんなにいい天気だしさ。会場の場所は分かるよね? 時間に遅れなければ、それでいいから」と言い残した金子先生は、美帆を乗せた自動車を運転して、さっさと行ってしまったのである。留夏子と悠太郎は〈あおぞら〉の駐車場に取り残された。「置いていくなんてひどいな。どういうつもりでしょう。そりゃ会場まで帰れないことはありませんが」と悠太郎はこぼした。「いいじゃないの。せっかくなんだから、一緒にゆっくり歩きましょう」と留夏子は愉快そうに応じた。大会の本番がとりあえず終わって、解放的になっているのかもしれないなと悠太郎は考えた。ふたりは並んで広い国道の歩道を歩いた。晴れ渡る青空から降り注ぐ秋の日射しに照らされて、若いふたりは並んだその影をアスファルトに落としていた。
北軽井沢市街地とは比べ物にならないほど活気のある町であった。国道を往来する自動車は多かった。しかしふたりは異様な静けさに包まれたように感じていた。あたかも日の光の微粒子が、ふたりのまわりで円環をなして聞こえない合唱を歌っており、その歌う微粒子の配列を変えることなしには、どんな言葉も発することができないかのようであった。
「とりあえず無事に終わってよかったですね。食事をして、ようやく人心地がつきました。留夏子さん、お疲れではありませんか?」
「ありがとう。ちょっと疲れていたけど、お肉を食べて回復したから、もう大丈夫。真壁こそ、心労との戦いだったでしょう?」
「浅間観光の一件で、留夏子さんに心配をかけてしまいました」
「その件だけど、祖父母は動いてくれる。戸井田さんをはじめとする開拓農家の人たちに、話を広げてみるって言ってた。だからまだあまり悲観しないで」
「何とお礼を言ったらいいか……。今回は余計な心配をかけただけでした。合唱のときのようには、力になれませんでした」
「そんなことはないでしょう。私ね、放課後の練習がとても楽しみだったの。あの宿直室に行けば、あなたに会える。あなたと一緒に英語の練習ができる。私には、ただそれだけでよかった」
「思い起こせば、何かと一緒にいましたね」
「出会ってから、もう十年近くになるもの。いろいろなことがあったね」
「はい。いろいろありました。本当にいろいろなことが……」
「あなたがいてくれなかったら、私の日々はもっと殺伐としていたでしょう」
「私のほうこそ、留夏子さんがいてくれなければ、もっといじけていたでしょう」
「最後にもう一度〈アマデウス〉へ行く。真壁の演奏を聴きに。それを楽しみに、受験勉強を頑張る」
「楽しみにしていてください。留夏子さんのことを思いながら選んだ曲です」
「真壁のピアノはもちろん楽しみ。それからアマデウスおじさんのフルートも」
「モーツァルトが好きすぎて、髪の毛の生え際がM字型に」
「泣きたいほど面白い」
「ええ。今という時が不思議に思えるような面白さです」
「私たちの日々は、こうして過ぎてゆくのね」
「はい。こうして過ぎてゆきます。幼い頃から、そのことがとても悲しかったです」
「……ねえ悠太郎、手を繋がない? 幼かったあの頃のように」
「……さすがにそれは不可能ですよ。私たちはもう無邪気な幼児ではないのですから」
「……それなら中学生として、手を繋ぎましょう」
「……喜んで」
留夏子のひんやりとした手を、悠太郎の手は感じた。ふたつの手の指が絡み合った。手を繋いだふたりは、しばし無言で歩んだ。
「留夏子さんはノリくんのことが……入江先輩のことが好きでしたね」
「ええ、好きだった。あなたが彼のことを好きだったのと、ちょうど同じくらいに」
「嬉しいです」
「妬かないの?」
「いいえ。同じほうを見ていたんだと思えて、嬉しいんです」
「手応えのない男ね」
悠太郎はいつしかふたりが地上を離れ、雲ひとつない秋晴れの青空を歩んでいるような気がした。あたかも昼間の青空から、次々と星が落ちるかのように思われた。何か言わなければ、悠太郎の意識は青空のなかに溶け入ってしまいそうであった。何か言わなければ、何か言わなければ。青空、青空、秋晴れ――。そう考えた悠太郎は、
うれしさや秋晴れの野に部下と共
という句を知っているかと留夏子に尋ねた。「何それ、知らない」と留夏子は答えた。「ある軍人の辞世の句だそうです。何でも満蒙開拓移民の父とか呼ばれた人だそうで、中国で戦死するとき、そういう句を詠んだんだそうです。いつだったか一輝が教えてくれました。遠い昔のことです」と悠太郎は説明した。「まったくもう。何でもよく知ってるのは結構だけど、時と場合を考えて思い出しなさいよ。せっかくの雰囲気が台無しじゃないの」と留夏子は呆れたように言った。若いふたりが手を繋いで歩む秋の日の午後に、すべては明るく暖かく優しかった。不吉なものは少しもそこに影を落としてはいなかった。
松並木社長によれば、それは先代の社長であった鈴木オーナーの意向だという。鈴木オーナーは増田ケンポウ社長の娘婿であった関係で、株式会社浅間観光の三代目の社長を務め、社長職を松並木現社長に譲った後も、会社のオーナーであり続けていた。その鈴木オーナーのひとり娘は、幸福な結婚をして芦屋夫人となり、子供にも恵まれて、前途に何の憂いもないはずであった。ところが先の大震災で芦屋は被災し、その娘の夫の事業は破綻した。被災地でのままならぬ暮らしから来る心労のためか、夫は急死したというのである。寡婦となったその娘は、子供を抱えて途方に暮れている――。「ついては」と松並木社長は言った。「大して儲からないこの会社を売却してだね、そのお金で娘さんとお孫さんのためにマンションを一棟建てて、一生心配のないようにしてやりたいということです。いやあ、親心というものじゃありませんか、皆さん。まあね、なくなるといっても、今日明日にというわけじゃありませんよ。まだまだ決めなきゃならないことや、整理しなければならないことがたくさんありますから、あと何年かはかかるでしょう。そういうわけですから皆さん、どうか最後までひとつよろしくお願いしますね」そう話し終えると松並木さんは、美久さんと一緒に社員食堂を出て客室へ消えていった。
衝撃の後の重苦しい沈黙が社員食堂を浸していた。「時勢かのう。始まったものは終わってゆく。この会社も例外じゃなかんべえ」とライサク老人こと桜井謙助さんは、ギョロ目を見開いて額に三筋の皺を寄せた。「時勢で片づけていい問題っすか? 完全にオーナーの個人的な事情じゃないっすか! 私利私欲でみんなの会社を廃業するんすか? ふざけてますよ!」と、いかり型の久世利文さんは鋭い喉仏のような語気で言うと、「くぜっ! くぜっ!」とばかりに首を急激に後ろへ反らせた。「あんた、次の仕事はどうするよ?」と、たらこ唇のマッちゃんがだみ声で言えば、板前の新海岳史さんはにかっと歯を見せて泣き笑いのような顔をした。蒼白な顔のおタキ婆さんは苦しげに目を細めながら、「春藤さんがいなくなってから、あたしたちはついてないねえ」と言った。紫色の三角巾を被ったおロク婆さんは、「あたしたちはずいぶん楽しい思いをさせてもらったけど、それもいよいよこれまでかねえ」と、活力を失った声で言った。林浩一さんもまた、平たい顔からにこやかな笑みを消していたが、「でもちょっとまってくださいよ。要するに鈴木さんがマンションを建てられればいいわけでしょう? ぼくらがもっと工夫して売り上げれば、その利益でマンションが建つんじゃないですか?」と言った。「鈴木さんは嫌になったんだろう。なまじ増田ケンポウの娘と結婚したばかりに、別段思い入れもない地域の浮き沈みを背負い込んじまった。はあそれが面倒になっていたんだよ。娘の旦那が死んだことで、それが顕在化しただけだんべえ」と黒岩サカエ支配人は暗い声で言った。「でも私は納得できない」と秀子は、下膨れの顔をぶるぶるとふるわせながら言った。「浅間観光があればこそ、この地域が支えられて潤うんじゃない。鈴木さんにはそのことを、どうしても思い出していただかなきゃ」
真壁の家に帰宅した秀子は、激しく叩きつけるように自動車のドアを閉め、玄関のドアをがばと開けバタンと閉め、廊下をドスン・ドスン・ドスン・ドスン・ドスンと五歩踏み鳴らして、居間への引き戸をガラガラと開けると、職場での出来事を洗いざらい悠太郎にぶちまけた。そしてその夜、鈴木オーナーに宛てた長い手紙を書いていた。私の父は今は亡き増田ケンポウ社長に重んじられ、株式会社浅間観光の永久名誉顧問を務めている。私もまた浅間観光に就職する機会をいただき、それ以来充実感をもって働き続けてきた。この会社に勤める従業員たちも、やり甲斐を感じながら献身的に勤めている。ところで従業員には様々な人がいる。学生のアルバイトとして働きに来たら、ここが気に入ってしまったので就職した人がいる。農作業を息子に継がせた開拓農民が、ボート番小屋で働いている。また浅間観光に雇用されているわけではないが、照月湖のほとりに売店を出して野菜を売っている農家の人もいる。この売店で売られている高原野菜は、浅間観光の夏にとって欠かせないものになっている。さらに視野を広げれば、様々な業種の人々が浅間観光を支え、また浅間観光に支えられている。スーパーマーケットの〈ダイマルヤ〉は、浅間観光の仕入れだけで、ひと夏二千万円を売り上げるという。これだけの売り上げがなくなれば、〈ダイマルヤ〉は一年じゅう開店していることができなくなり、潰れることも考えられる。そうなれば、浅間観光を蛇蝎のように嫌う別荘村の人々だって、日々の買い物に困ることになり、別荘を捨てるかもしれない。結果として地域は荒廃する。クリーニング店だって、浅間観光のリネン類の洗濯だけで、どれほどの売り上げになるか計り知れない。その仕事が奪われるなら、やはり地域は荒廃する。照月湖であれ明鏡閣であれ、湖畔や河畔のキャンプ場であれ、弓道場であれランニングコースであれ〈ポカラ〉であれ、それらを目当てに六里ヶ原を訪れる人がいなくなれば、バス会社もタクシー会社も売り上げを落とす。問題はお金のことばかりではない。多くのお客様がこの高原の風光を愛し、泊まりに来てくれる。全国にいるお客様たちの生きる喜びは、奪われてよいものではない。御令嬢と御令孫の苦衷はお察しする。しかしそのような個人的な事情によって、六里ヶ原の一画を占めるこの一地域を荒廃せしめることは、一社員として、また会社の永久名誉顧問の娘として、断固承服し難い――。そんな手紙を母は書いているのであろうと、悠太郎は想像した。浅間観光がなくなる――。今日明日のことではないと自分に言い聞かせながらも、悠太郎は目の前が暗くなるような、自分が底なし沼に吸い込まれてゆくような思いであった。「浅間観光が危ないそうね」と言った留夏子は、こうしたことの概要を知っていたわけであった。
その留夏子は悠太郎と並んで自転車を押しながら、「私もできる限り動いてみる。浅間観光がなくなったら、農家は野菜や果物の消費者を失うことになるもの。開拓の人たちの声を集めて、浅間観光の偉い人に届けられないか、祖父母と相談してみる」と言った。「ありがとうございます。しかし母の手紙にだって、今のところ何の反応もありません。農家の声が届くかどうか……」と悠太郎が懸念すると、「やってみなければ分からないでしょう。できることがあるのに、やらないよりはましよ。座して地域の滅びを待つべき道理はないもの」と留夏子は言い切った。星が瞬き始める薄闇のなかでも、なんとこの人は凛々として美しいのだろうと悠太郎は思った。そうだ、明日は英語の郡大会だ。この人は県大会への期待を背負いながら、俺のことを気に懸けてくれている。俺のほうこそ、この人の支えにならなければ――。そう念じた悠太郎は、秋の星空の話を留夏子とした。アンドロメダ座のこと、ペルセウス座のこと、カシオペア座のこと、白鳥座のこと――。並んで自転車を押すふたりは、しばし天空に思いを馳せて地上の些事を忘れた。それでもすっかり忘れてしまうわけにはゆかなかった。「英語の大会も、高校受験も、会社の危機も考えずに、ふたりでいつまでも星空を見ていたい」と留夏子が漏らした。
いつしかふたりは、四つの厳めしい石碑がある甘楽のバス停までやって来た。「満洲報国隊記念碑」「満洲開拓記念碑」「開拓者供養塔」「甘楽入植三十年記念碑」という文字は、すでにして闇に没していた。秋の夜風に樹々がざわざわと不吉な音を立てていた。闇に没したその文字に、留夏子はしばし思いを凝らすかのようであった。高校生になっていた中島猛夫が母親を殴って逮捕され、取り調べでバネットの殺害をも供述したという知らせが、留夏子の心を暗くしているに違いないと悠太郎は考えていた。「ねえ真壁、宮沢賢治がもっと長生きしていたら、どうなっていたと思う?」と留夏子は不意に言った。「もっと長生きしていたら……それは童話でも詩でも、素晴らしい作品をもっとたくさん書いたでしょう」と悠太郎は答えた。「それだけかしら? あるいは満蒙開拓移民の旗振り役になっていたかもしれない。そうは考えられない?」と留夏子は問うた。「賢治がですか? まさか!」と驚く悠太郎に、「賢治が亡くなったのは何年?」と留夏子はなおも問うた。「一九三三年です……あっ!」と悠太郎は答えるそばから驚いた。「そう。そのときにはもう満洲事変は起こっていたの。私たちは〈流浪の民〉に取り組んだわね。明治時代から詩に歌われてきた楽土ということが、昭和の満蒙開拓移民によって最悪の形で実現された。そこまでは私たちが一緒に確かめたことでしょう。ところがね、賢治のイーハトーブもまた、楽土のひとつなの。詩的な楽土であり、内なる楽土ね。農業技師として農民の生活向上に尽くした賢治が、外なる楽土の建設運動とされた満蒙開拓移民に、無関心でいられたかしら? そんな賢治を、私は見たくなかった。時宜を得た死に方って、あるのかもしれないわね」と留夏子は言った。さっき美帆が賢治の名前を出したから思い出したのかもしれないが、この考えは昨日や今日の思いつきではなさそうであった。「……何も愛する作品や作者のことを、そんなふうに考えなくてもいいのでは」と悠太郎が言うと、「認識するってそういうことなの。認識は苦いものなの」と留夏子は応じた。「今夜はもうこれらの碑の前で思い詰めずに、帰って休んでください。明日の朝は、いつもより少し早いですから」と悠太郎が言うと、「そうね。もう帰る。さようなら。また明日ね」と留夏子は自転車に跨った。だがすぐにブレーキをかけて振り返ると、「真壁、あなたはいつか私のことで、自分を責めるかもしれない。でも私はそんなこと、少しも望んでないから」と言い残して去っていった。しかし悠太郎はこの言葉を聞き取ることができなかった。秋の夜風に樹々がざわざわと不吉な音を立てたからである。
翌朝はほかの生徒たちが朝練習を始める前に、三人の代表は学校に集まった。見上げれば雲ひとつない秋晴れの空が広がっていた。清らかな朝の空気が、いつもより早い分だけいっそう清らかに澄んでいて、悠太郎は早起きの鳥たちと兄弟にでもなったような気がした。三人はイワトビペンギンのような金子先生が運転する自動車に乗り込んだ。留夏子が助手席に座り、悠太郎がその真後ろに、美帆がその右に座った。留夏子と金子先生の話が弾んでいた。「へえ、そうかい。佐藤さんのお母さんがピアノの先生で、真壁くんがその教室の生徒かい。それじゃおふたりを結びつけているのは、音楽というわけか。道理で話が合うわけだ。俺もいろいろと納得が行ったよ。佐藤さんにしても真壁くんにしても、その英語の優れているところは、やはり音楽性だな。アクセントやイントネーションやリズム感といったことだ。中学生の英語を普通に勉強しているだけでは、そこまでのことはなかなか身に着くものじゃない。しかし音楽が基礎にあれば話は別だよ。なるほどな……。しかしあれだな、誰も彼もがきみたちみたいな生徒だったらと考えると、ぞっとするよ。そうなったら俺のような英語教師は仕事がなくなる。小文字のbとdの区別もつかない生徒に手を焼いているうちが、英語教師の幸せなのかもしれないな」と金子先生は言った。「先生、私がいなくなっても、真壁のことをお願いしますね。私が見出した才能を、どうか磨いてあげてください」と留夏子は言った。「幼稚園の園庭で、私たちは無邪気に遊んでいました。よく一緒に〈アルプス一万尺〉の手遊びをしました。そのとき私は、彼の歌がうまいと思ったんです。彼の音楽の才能を、母は自分が見出したと思っていますけど、見出したのは私のほうが早いんですよ。もちろん彼が六里ヶ原の明鏡なんて呼ばれるようになる前のことです。そうして小学校二年生のときに、彼はピアノを始めました。いい生徒に恵まれて、母は幸せそうでした。真壁が来てくれる日には、母は朝から楽しそうでした。もし私がピアノを続けていれば、彼と一緒に弾くこともできたでしょう。でも私は父の不興を買うことを恐れて、バイエルも終わらせずに練習を放り出してしまいました。それはそれで仕方がなかったんです。でも発表会で母が彼と連弾しているのを見ると、なんだか羨ましくて。だから今日こうして同じ大会に出られることが、本当に夢のようです。卒業前に恵まれた幸せですね。でもだからといって、このまま時が止まるわけではありません。私は卒業してしまいます。その後のことを、先生、どうかよろしくお願いします」
悠太郎は留夏子の真後ろで、うつむきながらその言葉を聞いていた。自分のことをそんなふうに考えてくれていたのかと思えば、胸が熱くなりはした。しかしいつになく饒舌であるとも思った。今この場で話すべきことかどうか、疑問なしとはしなかった。あるいは斜め後ろの美帆に言い聞かせているのかもしれなかった。本番直前にこれほどの情感に浸っているのは、いかにも危ういと思われた。「おう、分かった。引き受けよう。学校一の俊英と謳われる佐藤さんに頼まれては、引き受けざるを得ないな。まあ俺はただの英語教師だから、できることに限りはあるが、精一杯指導して真壁くんの才能を開花させよう」と金子先生は応じた。そのあいだにも三人の代表を乗せた自動車は古森の坂を下り、吾妻川に沿うようにして原町を目指していた。
原町のとある文化会館を会場にして、英語暗唱大会の郡大会は粛々と戦われた。制服姿の中学生たちはホールに集い、ひとりまたひとりと演台に立った。一年生の部があり、二年生の部があり、三年生の部があった。各学校から選りすぐられた代表たちが暗唱する英語のように、流暢に時は流れた。その時の流れのなかに、美帆は静寂に満ちた言葉を、悠太郎は蚊に刺されてどうのこうのという重い言葉を、留夏子はハックルベリーの実のように甘酸っぱい言葉を浮かべた。差し当たり三人の代表たちは、練習の成果を大過なく出すことができた。あとは昼休憩明けに行なわれる結果発表を待つばかりであった。そして昼休憩には金子先生が、自動車で三人を近くの食堂まで連れていった。その食堂の名ははその日の空模様に相応しく〈あおぞら〉といった。金子先生の奢りでか、はたまた経費で落ちるのか、中学生たちにとって定かではなかったが、ともかくみんなは〈あおぞら〉で焼肉を食べるというわけであった。炭火が赤々と熾り、金網で肉が焼かれて煙と香ばしい匂いを立てた。四人の食欲は旺盛であった。英語暗唱大会の時間のように、楽しい昼食の時間もまた流れ過ぎていった。みんなが洗面所で歯を磨くと、金子先生が会計を済ませて、一行は〈あおぞら〉を後にした。
ところが駐車場では奇妙なことが起こった。「佐藤さん、真壁くん。俺と赤木さんは先に車で戻るから、ゆっくり歩いて帰っておいで。こんなにいい天気だしさ。会場の場所は分かるよね? 時間に遅れなければ、それでいいから」と言い残した金子先生は、美帆を乗せた自動車を運転して、さっさと行ってしまったのである。留夏子と悠太郎は〈あおぞら〉の駐車場に取り残された。「置いていくなんてひどいな。どういうつもりでしょう。そりゃ会場まで帰れないことはありませんが」と悠太郎はこぼした。「いいじゃないの。せっかくなんだから、一緒にゆっくり歩きましょう」と留夏子は愉快そうに応じた。大会の本番がとりあえず終わって、解放的になっているのかもしれないなと悠太郎は考えた。ふたりは並んで広い国道の歩道を歩いた。晴れ渡る青空から降り注ぐ秋の日射しに照らされて、若いふたりは並んだその影をアスファルトに落としていた。
北軽井沢市街地とは比べ物にならないほど活気のある町であった。国道を往来する自動車は多かった。しかしふたりは異様な静けさに包まれたように感じていた。あたかも日の光の微粒子が、ふたりのまわりで円環をなして聞こえない合唱を歌っており、その歌う微粒子の配列を変えることなしには、どんな言葉も発することができないかのようであった。
「とりあえず無事に終わってよかったですね。食事をして、ようやく人心地がつきました。留夏子さん、お疲れではありませんか?」
「ありがとう。ちょっと疲れていたけど、お肉を食べて回復したから、もう大丈夫。真壁こそ、心労との戦いだったでしょう?」
「浅間観光の一件で、留夏子さんに心配をかけてしまいました」
「その件だけど、祖父母は動いてくれる。戸井田さんをはじめとする開拓農家の人たちに、話を広げてみるって言ってた。だからまだあまり悲観しないで」
「何とお礼を言ったらいいか……。今回は余計な心配をかけただけでした。合唱のときのようには、力になれませんでした」
「そんなことはないでしょう。私ね、放課後の練習がとても楽しみだったの。あの宿直室に行けば、あなたに会える。あなたと一緒に英語の練習ができる。私には、ただそれだけでよかった」
「思い起こせば、何かと一緒にいましたね」
「出会ってから、もう十年近くになるもの。いろいろなことがあったね」
「はい。いろいろありました。本当にいろいろなことが……」
「あなたがいてくれなかったら、私の日々はもっと殺伐としていたでしょう」
「私のほうこそ、留夏子さんがいてくれなければ、もっといじけていたでしょう」
「最後にもう一度〈アマデウス〉へ行く。真壁の演奏を聴きに。それを楽しみに、受験勉強を頑張る」
「楽しみにしていてください。留夏子さんのことを思いながら選んだ曲です」
「真壁のピアノはもちろん楽しみ。それからアマデウスおじさんのフルートも」
「モーツァルトが好きすぎて、髪の毛の生え際がM字型に」
「泣きたいほど面白い」
「ええ。今という時が不思議に思えるような面白さです」
「私たちの日々は、こうして過ぎてゆくのね」
「はい。こうして過ぎてゆきます。幼い頃から、そのことがとても悲しかったです」
「……ねえ悠太郎、手を繋がない? 幼かったあの頃のように」
「……さすがにそれは不可能ですよ。私たちはもう無邪気な幼児ではないのですから」
「……それなら中学生として、手を繋ぎましょう」
「……喜んで」
留夏子のひんやりとした手を、悠太郎の手は感じた。ふたつの手の指が絡み合った。手を繋いだふたりは、しばし無言で歩んだ。
「留夏子さんはノリくんのことが……入江先輩のことが好きでしたね」
「ええ、好きだった。あなたが彼のことを好きだったのと、ちょうど同じくらいに」
「嬉しいです」
「妬かないの?」
「いいえ。同じほうを見ていたんだと思えて、嬉しいんです」
「手応えのない男ね」
悠太郎はいつしかふたりが地上を離れ、雲ひとつない秋晴れの青空を歩んでいるような気がした。あたかも昼間の青空から、次々と星が落ちるかのように思われた。何か言わなければ、悠太郎の意識は青空のなかに溶け入ってしまいそうであった。何か言わなければ、何か言わなければ。青空、青空、秋晴れ――。そう考えた悠太郎は、
うれしさや秋晴れの野に部下と共
という句を知っているかと留夏子に尋ねた。「何それ、知らない」と留夏子は答えた。「ある軍人の辞世の句だそうです。何でも満蒙開拓移民の父とか呼ばれた人だそうで、中国で戦死するとき、そういう句を詠んだんだそうです。いつだったか一輝が教えてくれました。遠い昔のことです」と悠太郎は説明した。「まったくもう。何でもよく知ってるのは結構だけど、時と場合を考えて思い出しなさいよ。せっかくの雰囲気が台無しじゃないの」と留夏子は呆れたように言った。若いふたりが手を繋いで歩む秋の日の午後に、すべては明るく暖かく優しかった。不吉なものは少しもそこに影を落としてはいなかった。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
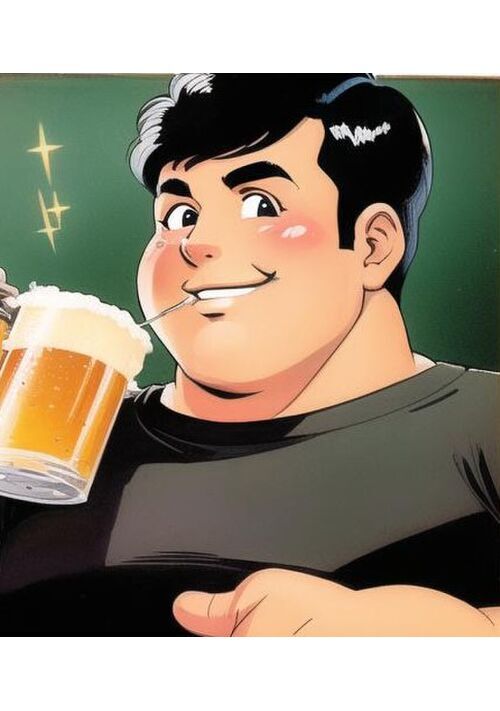
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!




ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















