56 / 73
第十九章 荒涼楽土
二
しおりを挟む
次の日曜日の午後に悠太郎のピアノのレッスンが終わると、ふたりは自転車で国道を北上して中学校のほうを目指した。四つの車輪はあるときはなだらかな、あるときは急な下り坂を、アレグロの速度で転がっていった。水色のガラスのように割れそうな空の下で、白根山を越えて吹く冷たい烈風が、若いふたりの熱い頬を切り裂かんばかりであった。ふたりは中学校を通り過ぎ、僻地診療所と幼稚園を通り過ぎて郵便局のほうへ向かった。そのあいだの路傍には、裸木の木立に抱かれるようにして「吾妻牧場碑」が立っていた。碑のまわりには枯葉が厚く散り敷き、ところどころに栗の毬が落ちていた。「これね、埴谷先生が教えてくれたのは。こんなところに碑があるなんて知らなかった」と言いながら、留夏子は自転車を停めてヘルメットを脱ぐと、悠太郎を連れて石碑の裏面へ回った。そこには牧の宮神社に祀られている親王殿下について、驚くべきことが記されていた。吾妻牧場なるものは明治十五年すなわち一八八二年、牧の宮殿下のお考えによってこの地に創始されたと碑文は語り始めた。留夏子はそれを声に出して読んでいったが、一文読むと驚きのあまりそこで絶句した。悠太郎もまた同じ驚きに打たれながら黙っていた。乾いた冷たい北風が、足許に重なった枯葉を騒がせた。「最初の一文からして、ただ事じゃないわね。何よこれ、情報量が多すぎる。ひとりの人間の一生は、これだけでも充分すぎるほどじゃない。輪王寺宮って何? 還俗したということは、僧侶だったの? 僧侶だった人が、軍人になったの? ドイツに八年も留学したの?」と留夏子は、切れ長の目を鋭く碑文に当てたまま言った。「輪王寺宮……。その言葉を小学生の頃に聞いたことがあります。そうでした、あれは私が四年生のときの遠足でした。隣町の観音堂で、草壁敬子先生がこんなお話をしてくれました。〈いいですか。皆さんが生まれる二百年ほど前、日本はまだ江戸時代でしたが、浅間山が大噴火を起こしました。それはもう歴史に残る物凄い噴火でした。天明三年の浅間焼けと呼ばれています。恐ろしい火砕流が発生しました。火砕流は山の北斜面を抉りながら流れ下って、川の水を蒸発させながら岩屑なだれとなり、麓の村々を飲み込みました。いちばんひどい被害を受けたのは、ここにあった村です。五百七十人いた村人が、九十三人だけを残してみんな死んでしまいました。その九十三人はどうして助かったかというと、この石段の上のお堂に集まっていたから、岩屑なだれに飲み込まれずに済んだのです。火砕流の後で溶岩が流れ出して、皆さんも知っているあの鬼押出しのごつごつした溶岩台地ができました。火砕流で千数百人もの犠牲者が出ただけではありません。噴き上がった火山灰は関東地方全体に降り注ぎ、また長らく太陽の光を遮って、天明の大飢饉を引き起こしました。農作物が被害を受けたわけですね。この災害が起こったことは江戸にも伝えられました。上野の寛永寺というお寺にいた輪王寺宮様という、当時いちばん偉かったお坊様が直々にここまでおいでくださり、亡くなった人たちを供養したということです……〉」
「さすがは真壁、すごい記憶力ね」と留夏子は少しおかしがるように応じ、「輪王寺宮というポストがあったと分かっただけでも助かる。江戸から離れた田舎の人たちにも敬愛されるほどの僧侶だったのね。天明三年は一七八三年で、明治元年は一八六八年だから、浅間焼けのときの輪王寺宮は牧の宮殿下と同一人物ではないけれど、きっと代々引き継がれていた高い役職だったのね。それほどの僧侶が、幕末騒乱の渦中に流転した……? 何があったのかしら。もしかしたら、戊辰戦争に巻き込まれて……」と続けた。「詳しいことは知りませんが、あり得ないことはないと思います」と悠太郎は応じ、「上野寛永寺は徳川将軍家の菩提寺だったと聞いたことがあります。その寺のトップにいる高位の僧侶は、当然徳川幕府の安泰を祈る役割を果たしていたでしょう。そこへ西国から新政府軍が、幕府を倒そうと攻め寄せる。時の輪王寺宮もただでは済まなかったであろうことは、想像に難くありません」と考えを述べた。留夏子は切れ長の目を細めながら、碑文に見入りつつ言った。「そして徳川幕府の時代は終わり、殿下は僧侶から俗人に戻った。というよりも、きっと戻らされたのね。それまで積み重ねてきた生き方が、明治維新によって全否定されたということね。それだけでもこの人には重大な試練だったでしょう。そのうえドイツで八年も過ごしたなんて。その淋しさたるや、いかばかりだったでしょうね」
今度は悠太郎が碑文を読み上げていった。この地に牧場が開かれたいきさつを、悠太郎は区切りのよいところまで続けた。「明治十五年か」と留夏子は言い、「西郷隆盛の西南戦争が明治十年の役だから、維新に伴う混乱がひとまず落ち着いて、日本が富国強兵や殖産興業に血道を上げる時期ね。長いドイツ留学での見聞が、牧場で馬を育てる計画とどう結びついたのかしら。プロイセン王国には、立派な王立牧場があったのかな。二千町歩に余る大牧場……。古い単位からはちょっと想像できない。吾妻牧場って、今の浅間牧場とイコールではないの? この碑がある応桑は、浅間牧場からはずいぶん離れているけど……」と続けた。「おそらくは、この町の高原地帯は、ほとんど全域が牧場だったのではないでしょうか」と悠太郎は言い、「浅間牧場があるあたりはもちろん、北軽井沢の市街地も、学芸村も、開拓地も、この応桑も」と続けながら、それぞれの地区にあるいは牧草が緑に波打ち、あるいは厩舎が建ち並び、あるいは畑が広がっていた様子を思い描いた。留夏子もまた同じことを思い描きながら、「この殿下が見た夢のなかで、私たちは育ってきたようなものね」と言った。今度は留夏子が碑文を読み上げていった。明治二十八年すなわち一八九五年、日清戦争に際して牧の宮殿下は、近衛師団長として吾妻牧場に育った薙野号という愛馬を駆り、大陸に進んだと石碑は物語った。転じて台湾征討中に悪疫に冒された殿下は、四十九歳で亡くなったのだという。殿下を失って吾妻牧場も廃されたのだという。
留夏子が読み終えると、ふたりはしばらく黙っていた。明治の昔から吹いてきたかのような冷たい風のなか、駿馬に跨った高貴な軍人の幻が、淋しげな光芒を残して荒涼たる高原を駆け抜けてゆくのを、ふたりは見たような気がした。「たしか台湾は、日本が獲得した最初の海外領土だったはず。いわば大日本帝国の事始めね。その台湾の征服に、私たちのふるさとが関わっていたなんて。この高原にゆかりの人が、かの地に軍を進めたなんて……。旧幕府の時代には、殿下はまさかそんな生涯を送ることになるとは思わなかったでしょうね。文明開化して急成長する近代日本の闇を、一身に背負って殿下は亡くなったのね。たとえこの地が戦争のために軍馬を育てる牧場であったとしても、殿下はここに来ているあいだだけは、別天地にでもいるように安らげたと思う。そうだったらいいな」と留夏子は言った。「なんという波乱に満ちた生涯でしょう。この碑に書かれていることを、数式でも展開するように押し広げたら、長篇小説にでもなりそうですね」と悠太郎は、牧の宮殿下の運命に心打たれながら言った。「真壁が書けばいいじゃない」と留夏子は挑発するように言った。「私が? 無理ですよ、そんなこと」と悠太郎は自嘲するようにそれを打ち消した。「それじゃあ一緒に考えましょうよ」と留夏子はまた華やいだような声で言った。「宮様だから、生まれはきっと京の都ね。春には桜の花びらがはらはらと散る王朝ものとして、その小説は始まるの。緑輝く初夏には、葵祭の行列に神馬がいるでしょう。夢のなかの葵祭で、宮の母親が神馬のお告げを受けるというのはどう? 宮はどんな幼年期を過ごしたのかしら。年少にして出家した宮は、どこでどんな修行をしたのかしら。そして江戸に着任するも、内外の情勢は緊迫していた。最後の将軍徳川慶喜と、どんなやりとりがあったのかしら。そして戊辰戦争が起こり、宮は流転した。そしてどういう成り行きでか、ドイツに留学することになった。ドイツでの殿下の記録なんて、残っているのかな? 真壁がそれを掘り起こせたら、面白いじゃない。プロイセン貴族の令嬢との悲恋なんかあったりして……」
「ずいぶん想像力を逞しくするんですね。留夏子さんは想像力を罪だと考えていると思っていました」と悠太郎は意外そうに言った。「ある種の想像力は、たしかに罪だと思う」と留夏子は答え、「罪であるのは、他者を自分に都合よく作り変えてしまう想像力よ。自分に都合よく想像された神を信じるよりは、無神論のほうがまだましだって『重力と恩寵』にも書いてあった。でも事実に即した想像力は、それとは違うでしょう。他者をよりよく理解するための想像力だもの、まだしも罪が軽いはず」と続けた。「葵祭の神馬はいいですね。殿下が馬を好きになった原体験かもしれません」と悠太郎は応じ、「しかしプロイセン貴族の令嬢との悲恋は……。いくらなんでも、そんな小説のような事実は出てこないと思いますよ。仮にそんなことがあったとして、公式の記録に残るでしょうか」と続けた。「まあとにかくいろいろ調べてみたら面白そう。ひょうたんから駒の諺もあるわよ」と留夏子が言ったので、「ひょうたんから駒ですか。いかにも吾妻牧場に相応しいですね。薙野号のような駿馬が躍り出そうです」と悠太郎は愉快がった。「そうだ、牧の宮神社の由緒書はどうなっていたかしら」と留夏子が疑問を呈したので、悠太郎は「帰りに調べてみましょう。これまで読んだこともありませんでした」と答えた。
上り坂の国道を自転車で再び南下してきたふたりは、北軽井沢駅前にある牧の宮神社に立ち寄った。鳥居をくぐることは、留夏子にとって別段どうということもないのかと悠太郎は少し気になった。茅葺き屋根の社殿に寄り添うように、「牧の宮神社の由来」が石に刻まれていた。学芸村が開かれたことにより、北軽井沢地区の人口も増加しつつあった昭和七年九月三日、当神社本殿等が造営されたと石碑は語り始めた。悠太郎は碑文を読み上げていった。昭和二十年八月十五日に太平洋戦争は終結した。版図外になった台湾神宮の祭神だった例の親王殿下は、明治十五年より明治二十八年十一月五日に薨去されるまで、浅間高原二千町歩余りの広大な地域に、馬を主とした吾妻牧場を経営された当地ゆかりの宮様であるので、地域住民の願望によって当神社に合祀され、社号は牧の宮神社と改めた……といったようなことがそこには記されていた。昭和六十一年九月二十八日の日付を悠太郎が読み上げると、「私たちが生まれた後じゃない。今まで見てきたもののなかでは、新しいほうね」と留夏子が言った。「敗戦によって台湾が版図外になったことで、ここに祀られたことが読み取れます。植民地の神として祀られていた宮は、大日本帝国が御破算になったことで、こよなく愛したこの高原に、ようやく帰れたのですね」と悠太郎は言った。「牧の宮って、いいお名前ね。牧草が豊かに波打つ高原で、馬を愛したひとりの高貴な人。戦争が終わってようやく、ただそれだけの人に戻れたのね」と留夏子は碑文を見ながら言った。悠太郎は碑文の日付を見ながら、九月二十八日は秋の例大祭だなと思った。悠太郎はもうお祭りに浮かれるような年頃を過ぎていた。しかしいつかの日、涼やかに高くなりゆく青空のもと、悠太郎は戸井田一輝とともに幼稚園からの帰りに、金属製の鳥居をくぐって茅葺き屋根の社殿に参拝し、それぞれ秀子やアオイさんに教わるがまま、鈴緒を揺り動かして本坪鈴を鳴らし、柏手を打ったものであった。それから子供たちふたりは境内の出店で綿菓子を食べたものであった。すべては遠い遠い昔のように思われた。また来週の約束をして、悠太郎と留夏子は別れた。
次の週の日曜日が記念碑めぐりの総仕上げとなった。留夏子の希望で最後に残してあった、甘楽のバス停近くにある一群の碑を読もうと、ふたりは自転車でやって来た。四つの厳めしい石碑には国道に近いほうから、それぞれ「満洲報国隊記念碑」「満洲開拓記念碑」「開拓者供養塔」「甘楽入植三十年記念碑」という文字が刻まれていた。石碑の傍らには廃車になった草軽バスが、錆びつくままに放置されていた。薄曇りの空の下で、枯葉と笹叢を騒がせる北風は吹き募っていた。石碑とバスの廃車を取り巻いて揺曳する禍々しい気配が、悠太郎にはいつにも増して濃くなったように感じられた。
留夏子に導かれるまま悠太郎は、「甘楽入植三十年記念碑」の裏面から読み始めた。かつて大陸で鍬を振るった猛者たちが、悪条件と戦いながらこの六里ヶ原を開拓したことが物語られていた。その後には略年表の形式で、開拓進展のあらましが記されていた。それから関係者の氏名が列挙され、昭和五十四年四月二十日という日付で結ばれていた。留夏子は切れ長の目を細めながらそれらの文字を追っていたが、「今まで捨ておかれていた未開地とあったけど、吾妻牧場の時代は無視されたの?」と疑問を呈した。「そこは私も引っ掛かったところでした」と悠太郎は答え、「牧の宮殿下を失って牧場は廃されたと、応桑の碑にはありました。それが正確にいつのことなのかは知りませんが、吾妻牧場が廃止になってから戦後まで、打ち捨てられていた土地がたしかにあったのでしょう」と続けた。長いあいだ忘れられ見棄てられていた牧場跡を思うふたりに、荒涼たる北風が冷たかった。「大屋原の三十年記念碑と同じような作りだけど、こっちのほうが少しばかり謙虚ね。拓魂なんていう言葉は一度も出てこなかった」と留夏子が言うと、悠太郎は「同じことを考えていました」と応じた。
その隣の「開拓者供養塔」の裏側には、大陸で亡くなった人や引き揚げ中に亡くなった人々の氏名が刻み込まれていた。ひとりひとりの名前を目で追いながら、ふたりはそれぞれの苦難に思いを馳せた。その隣には「満洲開拓記念碑」があった。今度は留夏子が碑文を読み上げていった。開拓のための移民が全国各地から募集され、年々多くの日本人が海を渡っていったのは、日中戦争が太平洋戦争に拡大しつつあるさなかであったことや、この県のある郡からも開拓団が北満に入植したことを石碑は物語っていた。敗戦後の危機と、引き揚げと、六里ヶ原の開拓のことが記されていた。「これもまた破綻したような文章ですね」と悠太郎が言えば、「ここも大屋原とあまり変わらないのかな」と留夏子が応じ、「満洲開拓記念碑って、文字通り満洲の開拓を記念する碑だものね。大陸を開拓したことと、この六里ヶ原を開拓したことが、あたかもひと続きであるかのように捉えられている。それとこれとは、本来別々のはずなのに。犠牲者の冥福というけど、そのなかには日本人しか入っていないでしょうね。自分たちはあくまで国策の巻き添えを食った被害者で、その被害を乗り越えてここを拓いたという物語しかない」と言葉を継いだ。「残るひとつの碑も、そんなものでしょうか」と悠太郎が言うと、「とにかく見てみましょう」と留夏子が応じた。
ふたりが「満洲報国隊記念碑」の正面に立つと、白根山を越えて吹き募る冷たい北風が、冬枯れた笹叢を騒がせた。ほかの三つの石碑よりも、やや北側に引っ込んだように立っているその石碑の冒頭には、何やら草書体の文字が連ねられていた。「ずっと気になっていたのは、実はこれだったの」と留夏子は言った。「幼稚園の頃ここを通って帰るとき、何だか変な模様があるなと思っていた。これが文字だということが分からなかったのね。祖父母に訊いても読めないと言うの。私がこの碑を最後にしたいと言ったのは、ほかの碑を読んゆくうちに、この草書体の解読のヒントが少しは見つかるかもしれないと思ったからなの。でもやっぱり私には無理ね。真壁はどう? いかに六里ヶ原の明鏡でも、さすがにこれは読めないでしょうね」
ところが悠太郎は淋しげに微笑むと「懐かしいな」と言い、石碑に刻まれた草書体の文字をなぞるように、右手の人差し指を空中で動かし始めた。「幼い頃から祖父に見せられてきた書道の本には、こういう字がたくさん載っていました。祖父はしばしば自分の部屋に私を入れて習字を教えたばかりでなく、行書や草書の名跡を鑑賞することまで強制しましたから。まったく読めないというわけではなさそうですよ。戦い……北満……荒野……」と悠太郎が解読を始めると、留夏子は「嘘でしょう」と言って驚き、悠太郎の横顔を見て眩しいものでも見るように切れ長の目を細めた。やがて虚空で文字をなぞる悠太郎の指が、ある一箇所だけを繰り返すようになったのを留夏子は認めた。ああ、あのト音記号のようなパーツね。あの字さえ読めれば、解読できるのね――。留夏子は息を詰めてその時を待っていた。やがて悠太郎が「ああ、そうだった」と言った。「歯を磨く、顔を洗う――助詞の〈を〉の字を越後の越で書くのは、変体仮名では珍しいことではないんだった……。読めましたよ、留夏子さん。やっと読めました。こう書いてあります」
戦いに勝つことを信じ、北満の荒野を拓いて青春を捧げた――。その歌の意味するところは、そういうことであった。
笹叢を騒がせて冷たい風が過ぎていった。留夏子もまた空中で人差し指を動かして、いましがた悠太郎から聞いた音声を、碑に刻まれた文字と一致させようとしていた。「〈ひらきて〉の〈きて〉は幾つもの天で、〈捧げぬ〉の〈ぬ〉は怒りという字ね。文字の選び方に、ただならぬ思いが込められていそう」と言った留夏子は、歌に続く碑文を読み上げていった。戦争は最大の罪悪であると切り出した碑文は、食糧難と開拓移民政策を物語った。祖国の危急存亡に直面した昭和十九年の三月から二十年の四月まで、選抜された報国隊は満洲国に派遣され、大平原を開拓して報国農場を建設し、食糧確保と北の守りに渾身の力を尽くして奉仕したのだという。そして敗戦の悲惨と夥しい犠牲と、戦争への痛恨と恒久平和への祈念が記されていた。
荒涼たる風が枯葉を弄んで吹き過ぎるのを、しばし沈黙しながらふたりは感じていた。やがて悠太郎は、「これまでに見た開拓関係のどの碑とも、全然違いますね。国策とはいえ開拓の行為が、国際平和共存のための営みではなかったことを、苦渋の思いで認めています。夜郎自大に拓魂とやらを誇る態度とは正反対ですね」と評した。留夏子はしかし「これほどのものの前を」と言ったきり言葉を切り、ほとんどふるえ出さんばかりであった。風は冷たく吹き荒んでいた。「これほどのものの前を、幼かった私はスキップしながら通り過ぎていたのね。親の親たちの時代にあったことなんか、何も知らずに」と留夏子は、われとわが身を責めるように言った。「石は待っていてくれました。あの日々から今までずっと変わらずに、私たちが文字を読めるようになるまで」と悠太郎は言葉をかけた。「なんて無邪気で幸せな日々だったことでしょう。でも無邪気なままでいることは罪ね。私は大きくなることが怖かったの。今が昔になって、また次の今が今になって、その今もまたすぐに昔になる。このことは、なんて悲しいんだろうと思っていた。一生がほんの一瞬のきらめきにすぎないなら、なぜ人はわざわざ苦しみながら成長しなければいけないのか、なぜあどけないままでいられないのかと思っていた。でもこうして石碑を読んできた今では、もう違う。私たちは私たちの永遠の子孫たちに責任を負っている。次の世代に平和な世界を手渡さなければならない。そのことがはっきりと分かった今、私はもう大人になることを恐れない。学びましょう真壁。ともにしっかり学んで、責任を果たす大人になりましょう」留夏子がそう言ったので、悠太郎は心を打たれて頷いた。荒涼たる冷たい風が吹き募るなかで、ふたりの向学の意気は火のように燃えていた。
「さすがは真壁、すごい記憶力ね」と留夏子は少しおかしがるように応じ、「輪王寺宮というポストがあったと分かっただけでも助かる。江戸から離れた田舎の人たちにも敬愛されるほどの僧侶だったのね。天明三年は一七八三年で、明治元年は一八六八年だから、浅間焼けのときの輪王寺宮は牧の宮殿下と同一人物ではないけれど、きっと代々引き継がれていた高い役職だったのね。それほどの僧侶が、幕末騒乱の渦中に流転した……? 何があったのかしら。もしかしたら、戊辰戦争に巻き込まれて……」と続けた。「詳しいことは知りませんが、あり得ないことはないと思います」と悠太郎は応じ、「上野寛永寺は徳川将軍家の菩提寺だったと聞いたことがあります。その寺のトップにいる高位の僧侶は、当然徳川幕府の安泰を祈る役割を果たしていたでしょう。そこへ西国から新政府軍が、幕府を倒そうと攻め寄せる。時の輪王寺宮もただでは済まなかったであろうことは、想像に難くありません」と考えを述べた。留夏子は切れ長の目を細めながら、碑文に見入りつつ言った。「そして徳川幕府の時代は終わり、殿下は僧侶から俗人に戻った。というよりも、きっと戻らされたのね。それまで積み重ねてきた生き方が、明治維新によって全否定されたということね。それだけでもこの人には重大な試練だったでしょう。そのうえドイツで八年も過ごしたなんて。その淋しさたるや、いかばかりだったでしょうね」
今度は悠太郎が碑文を読み上げていった。この地に牧場が開かれたいきさつを、悠太郎は区切りのよいところまで続けた。「明治十五年か」と留夏子は言い、「西郷隆盛の西南戦争が明治十年の役だから、維新に伴う混乱がひとまず落ち着いて、日本が富国強兵や殖産興業に血道を上げる時期ね。長いドイツ留学での見聞が、牧場で馬を育てる計画とどう結びついたのかしら。プロイセン王国には、立派な王立牧場があったのかな。二千町歩に余る大牧場……。古い単位からはちょっと想像できない。吾妻牧場って、今の浅間牧場とイコールではないの? この碑がある応桑は、浅間牧場からはずいぶん離れているけど……」と続けた。「おそらくは、この町の高原地帯は、ほとんど全域が牧場だったのではないでしょうか」と悠太郎は言い、「浅間牧場があるあたりはもちろん、北軽井沢の市街地も、学芸村も、開拓地も、この応桑も」と続けながら、それぞれの地区にあるいは牧草が緑に波打ち、あるいは厩舎が建ち並び、あるいは畑が広がっていた様子を思い描いた。留夏子もまた同じことを思い描きながら、「この殿下が見た夢のなかで、私たちは育ってきたようなものね」と言った。今度は留夏子が碑文を読み上げていった。明治二十八年すなわち一八九五年、日清戦争に際して牧の宮殿下は、近衛師団長として吾妻牧場に育った薙野号という愛馬を駆り、大陸に進んだと石碑は物語った。転じて台湾征討中に悪疫に冒された殿下は、四十九歳で亡くなったのだという。殿下を失って吾妻牧場も廃されたのだという。
留夏子が読み終えると、ふたりはしばらく黙っていた。明治の昔から吹いてきたかのような冷たい風のなか、駿馬に跨った高貴な軍人の幻が、淋しげな光芒を残して荒涼たる高原を駆け抜けてゆくのを、ふたりは見たような気がした。「たしか台湾は、日本が獲得した最初の海外領土だったはず。いわば大日本帝国の事始めね。その台湾の征服に、私たちのふるさとが関わっていたなんて。この高原にゆかりの人が、かの地に軍を進めたなんて……。旧幕府の時代には、殿下はまさかそんな生涯を送ることになるとは思わなかったでしょうね。文明開化して急成長する近代日本の闇を、一身に背負って殿下は亡くなったのね。たとえこの地が戦争のために軍馬を育てる牧場であったとしても、殿下はここに来ているあいだだけは、別天地にでもいるように安らげたと思う。そうだったらいいな」と留夏子は言った。「なんという波乱に満ちた生涯でしょう。この碑に書かれていることを、数式でも展開するように押し広げたら、長篇小説にでもなりそうですね」と悠太郎は、牧の宮殿下の運命に心打たれながら言った。「真壁が書けばいいじゃない」と留夏子は挑発するように言った。「私が? 無理ですよ、そんなこと」と悠太郎は自嘲するようにそれを打ち消した。「それじゃあ一緒に考えましょうよ」と留夏子はまた華やいだような声で言った。「宮様だから、生まれはきっと京の都ね。春には桜の花びらがはらはらと散る王朝ものとして、その小説は始まるの。緑輝く初夏には、葵祭の行列に神馬がいるでしょう。夢のなかの葵祭で、宮の母親が神馬のお告げを受けるというのはどう? 宮はどんな幼年期を過ごしたのかしら。年少にして出家した宮は、どこでどんな修行をしたのかしら。そして江戸に着任するも、内外の情勢は緊迫していた。最後の将軍徳川慶喜と、どんなやりとりがあったのかしら。そして戊辰戦争が起こり、宮は流転した。そしてどういう成り行きでか、ドイツに留学することになった。ドイツでの殿下の記録なんて、残っているのかな? 真壁がそれを掘り起こせたら、面白いじゃない。プロイセン貴族の令嬢との悲恋なんかあったりして……」
「ずいぶん想像力を逞しくするんですね。留夏子さんは想像力を罪だと考えていると思っていました」と悠太郎は意外そうに言った。「ある種の想像力は、たしかに罪だと思う」と留夏子は答え、「罪であるのは、他者を自分に都合よく作り変えてしまう想像力よ。自分に都合よく想像された神を信じるよりは、無神論のほうがまだましだって『重力と恩寵』にも書いてあった。でも事実に即した想像力は、それとは違うでしょう。他者をよりよく理解するための想像力だもの、まだしも罪が軽いはず」と続けた。「葵祭の神馬はいいですね。殿下が馬を好きになった原体験かもしれません」と悠太郎は応じ、「しかしプロイセン貴族の令嬢との悲恋は……。いくらなんでも、そんな小説のような事実は出てこないと思いますよ。仮にそんなことがあったとして、公式の記録に残るでしょうか」と続けた。「まあとにかくいろいろ調べてみたら面白そう。ひょうたんから駒の諺もあるわよ」と留夏子が言ったので、「ひょうたんから駒ですか。いかにも吾妻牧場に相応しいですね。薙野号のような駿馬が躍り出そうです」と悠太郎は愉快がった。「そうだ、牧の宮神社の由緒書はどうなっていたかしら」と留夏子が疑問を呈したので、悠太郎は「帰りに調べてみましょう。これまで読んだこともありませんでした」と答えた。
上り坂の国道を自転車で再び南下してきたふたりは、北軽井沢駅前にある牧の宮神社に立ち寄った。鳥居をくぐることは、留夏子にとって別段どうということもないのかと悠太郎は少し気になった。茅葺き屋根の社殿に寄り添うように、「牧の宮神社の由来」が石に刻まれていた。学芸村が開かれたことにより、北軽井沢地区の人口も増加しつつあった昭和七年九月三日、当神社本殿等が造営されたと石碑は語り始めた。悠太郎は碑文を読み上げていった。昭和二十年八月十五日に太平洋戦争は終結した。版図外になった台湾神宮の祭神だった例の親王殿下は、明治十五年より明治二十八年十一月五日に薨去されるまで、浅間高原二千町歩余りの広大な地域に、馬を主とした吾妻牧場を経営された当地ゆかりの宮様であるので、地域住民の願望によって当神社に合祀され、社号は牧の宮神社と改めた……といったようなことがそこには記されていた。昭和六十一年九月二十八日の日付を悠太郎が読み上げると、「私たちが生まれた後じゃない。今まで見てきたもののなかでは、新しいほうね」と留夏子が言った。「敗戦によって台湾が版図外になったことで、ここに祀られたことが読み取れます。植民地の神として祀られていた宮は、大日本帝国が御破算になったことで、こよなく愛したこの高原に、ようやく帰れたのですね」と悠太郎は言った。「牧の宮って、いいお名前ね。牧草が豊かに波打つ高原で、馬を愛したひとりの高貴な人。戦争が終わってようやく、ただそれだけの人に戻れたのね」と留夏子は碑文を見ながら言った。悠太郎は碑文の日付を見ながら、九月二十八日は秋の例大祭だなと思った。悠太郎はもうお祭りに浮かれるような年頃を過ぎていた。しかしいつかの日、涼やかに高くなりゆく青空のもと、悠太郎は戸井田一輝とともに幼稚園からの帰りに、金属製の鳥居をくぐって茅葺き屋根の社殿に参拝し、それぞれ秀子やアオイさんに教わるがまま、鈴緒を揺り動かして本坪鈴を鳴らし、柏手を打ったものであった。それから子供たちふたりは境内の出店で綿菓子を食べたものであった。すべては遠い遠い昔のように思われた。また来週の約束をして、悠太郎と留夏子は別れた。
次の週の日曜日が記念碑めぐりの総仕上げとなった。留夏子の希望で最後に残してあった、甘楽のバス停近くにある一群の碑を読もうと、ふたりは自転車でやって来た。四つの厳めしい石碑には国道に近いほうから、それぞれ「満洲報国隊記念碑」「満洲開拓記念碑」「開拓者供養塔」「甘楽入植三十年記念碑」という文字が刻まれていた。石碑の傍らには廃車になった草軽バスが、錆びつくままに放置されていた。薄曇りの空の下で、枯葉と笹叢を騒がせる北風は吹き募っていた。石碑とバスの廃車を取り巻いて揺曳する禍々しい気配が、悠太郎にはいつにも増して濃くなったように感じられた。
留夏子に導かれるまま悠太郎は、「甘楽入植三十年記念碑」の裏面から読み始めた。かつて大陸で鍬を振るった猛者たちが、悪条件と戦いながらこの六里ヶ原を開拓したことが物語られていた。その後には略年表の形式で、開拓進展のあらましが記されていた。それから関係者の氏名が列挙され、昭和五十四年四月二十日という日付で結ばれていた。留夏子は切れ長の目を細めながらそれらの文字を追っていたが、「今まで捨ておかれていた未開地とあったけど、吾妻牧場の時代は無視されたの?」と疑問を呈した。「そこは私も引っ掛かったところでした」と悠太郎は答え、「牧の宮殿下を失って牧場は廃されたと、応桑の碑にはありました。それが正確にいつのことなのかは知りませんが、吾妻牧場が廃止になってから戦後まで、打ち捨てられていた土地がたしかにあったのでしょう」と続けた。長いあいだ忘れられ見棄てられていた牧場跡を思うふたりに、荒涼たる北風が冷たかった。「大屋原の三十年記念碑と同じような作りだけど、こっちのほうが少しばかり謙虚ね。拓魂なんていう言葉は一度も出てこなかった」と留夏子が言うと、悠太郎は「同じことを考えていました」と応じた。
その隣の「開拓者供養塔」の裏側には、大陸で亡くなった人や引き揚げ中に亡くなった人々の氏名が刻み込まれていた。ひとりひとりの名前を目で追いながら、ふたりはそれぞれの苦難に思いを馳せた。その隣には「満洲開拓記念碑」があった。今度は留夏子が碑文を読み上げていった。開拓のための移民が全国各地から募集され、年々多くの日本人が海を渡っていったのは、日中戦争が太平洋戦争に拡大しつつあるさなかであったことや、この県のある郡からも開拓団が北満に入植したことを石碑は物語っていた。敗戦後の危機と、引き揚げと、六里ヶ原の開拓のことが記されていた。「これもまた破綻したような文章ですね」と悠太郎が言えば、「ここも大屋原とあまり変わらないのかな」と留夏子が応じ、「満洲開拓記念碑って、文字通り満洲の開拓を記念する碑だものね。大陸を開拓したことと、この六里ヶ原を開拓したことが、あたかもひと続きであるかのように捉えられている。それとこれとは、本来別々のはずなのに。犠牲者の冥福というけど、そのなかには日本人しか入っていないでしょうね。自分たちはあくまで国策の巻き添えを食った被害者で、その被害を乗り越えてここを拓いたという物語しかない」と言葉を継いだ。「残るひとつの碑も、そんなものでしょうか」と悠太郎が言うと、「とにかく見てみましょう」と留夏子が応じた。
ふたりが「満洲報国隊記念碑」の正面に立つと、白根山を越えて吹き募る冷たい北風が、冬枯れた笹叢を騒がせた。ほかの三つの石碑よりも、やや北側に引っ込んだように立っているその石碑の冒頭には、何やら草書体の文字が連ねられていた。「ずっと気になっていたのは、実はこれだったの」と留夏子は言った。「幼稚園の頃ここを通って帰るとき、何だか変な模様があるなと思っていた。これが文字だということが分からなかったのね。祖父母に訊いても読めないと言うの。私がこの碑を最後にしたいと言ったのは、ほかの碑を読んゆくうちに、この草書体の解読のヒントが少しは見つかるかもしれないと思ったからなの。でもやっぱり私には無理ね。真壁はどう? いかに六里ヶ原の明鏡でも、さすがにこれは読めないでしょうね」
ところが悠太郎は淋しげに微笑むと「懐かしいな」と言い、石碑に刻まれた草書体の文字をなぞるように、右手の人差し指を空中で動かし始めた。「幼い頃から祖父に見せられてきた書道の本には、こういう字がたくさん載っていました。祖父はしばしば自分の部屋に私を入れて習字を教えたばかりでなく、行書や草書の名跡を鑑賞することまで強制しましたから。まったく読めないというわけではなさそうですよ。戦い……北満……荒野……」と悠太郎が解読を始めると、留夏子は「嘘でしょう」と言って驚き、悠太郎の横顔を見て眩しいものでも見るように切れ長の目を細めた。やがて虚空で文字をなぞる悠太郎の指が、ある一箇所だけを繰り返すようになったのを留夏子は認めた。ああ、あのト音記号のようなパーツね。あの字さえ読めれば、解読できるのね――。留夏子は息を詰めてその時を待っていた。やがて悠太郎が「ああ、そうだった」と言った。「歯を磨く、顔を洗う――助詞の〈を〉の字を越後の越で書くのは、変体仮名では珍しいことではないんだった……。読めましたよ、留夏子さん。やっと読めました。こう書いてあります」
戦いに勝つことを信じ、北満の荒野を拓いて青春を捧げた――。その歌の意味するところは、そういうことであった。
笹叢を騒がせて冷たい風が過ぎていった。留夏子もまた空中で人差し指を動かして、いましがた悠太郎から聞いた音声を、碑に刻まれた文字と一致させようとしていた。「〈ひらきて〉の〈きて〉は幾つもの天で、〈捧げぬ〉の〈ぬ〉は怒りという字ね。文字の選び方に、ただならぬ思いが込められていそう」と言った留夏子は、歌に続く碑文を読み上げていった。戦争は最大の罪悪であると切り出した碑文は、食糧難と開拓移民政策を物語った。祖国の危急存亡に直面した昭和十九年の三月から二十年の四月まで、選抜された報国隊は満洲国に派遣され、大平原を開拓して報国農場を建設し、食糧確保と北の守りに渾身の力を尽くして奉仕したのだという。そして敗戦の悲惨と夥しい犠牲と、戦争への痛恨と恒久平和への祈念が記されていた。
荒涼たる風が枯葉を弄んで吹き過ぎるのを、しばし沈黙しながらふたりは感じていた。やがて悠太郎は、「これまでに見た開拓関係のどの碑とも、全然違いますね。国策とはいえ開拓の行為が、国際平和共存のための営みではなかったことを、苦渋の思いで認めています。夜郎自大に拓魂とやらを誇る態度とは正反対ですね」と評した。留夏子はしかし「これほどのものの前を」と言ったきり言葉を切り、ほとんどふるえ出さんばかりであった。風は冷たく吹き荒んでいた。「これほどのものの前を、幼かった私はスキップしながら通り過ぎていたのね。親の親たちの時代にあったことなんか、何も知らずに」と留夏子は、われとわが身を責めるように言った。「石は待っていてくれました。あの日々から今までずっと変わらずに、私たちが文字を読めるようになるまで」と悠太郎は言葉をかけた。「なんて無邪気で幸せな日々だったことでしょう。でも無邪気なままでいることは罪ね。私は大きくなることが怖かったの。今が昔になって、また次の今が今になって、その今もまたすぐに昔になる。このことは、なんて悲しいんだろうと思っていた。一生がほんの一瞬のきらめきにすぎないなら、なぜ人はわざわざ苦しみながら成長しなければいけないのか、なぜあどけないままでいられないのかと思っていた。でもこうして石碑を読んできた今では、もう違う。私たちは私たちの永遠の子孫たちに責任を負っている。次の世代に平和な世界を手渡さなければならない。そのことがはっきりと分かった今、私はもう大人になることを恐れない。学びましょう真壁。ともにしっかり学んで、責任を果たす大人になりましょう」留夏子がそう言ったので、悠太郎は心を打たれて頷いた。荒涼たる冷たい風が吹き募るなかで、ふたりの向学の意気は火のように燃えていた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
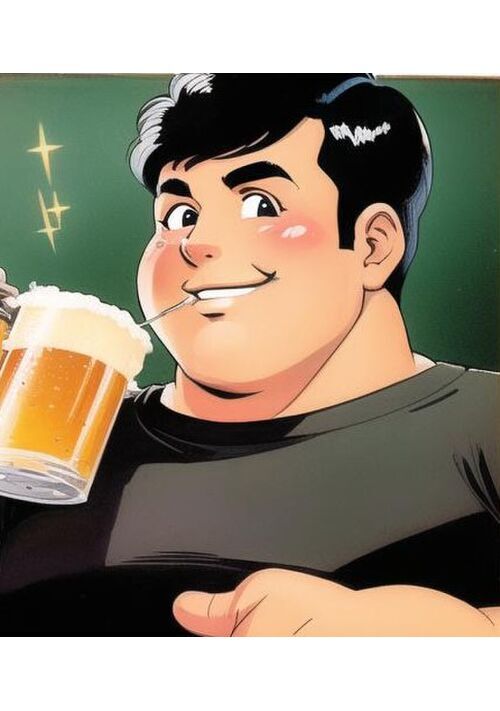
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















