55 / 73
第十九章 荒涼楽土
一
しおりを挟む
古タイヤの山のそばの犬小屋を出たらしいコリー犬のバネットが、夜のあいだ何者かによってめった打ちに撲殺されたのは、合唱コンクールの直後のことであった。毛並み豊かなその体は、もはや猛然たる吠え声を響かせることもなく、ただひとり懐いていた留夏子にじゃれつくこともなく、背骨も肋骨も頭蓋骨も砕かれ、血まみれになって転がっていた。朝になって餌をやろうと犬小屋に近づいた留夏子が、悲しみと怒りに身をふるわせながら愛犬の亡骸を見つめていると、開拓地を吹き渡る晩秋の荒涼たる風が、ライオンのたてがみに似ていたその毛をなびかせた。
陽奈子先生のレッスンを受けに佐藤農園を訪れた悠太郎は、畑の外れに作られたバネットの墓の前に片膝をつき、手を合わせてしばし瞑目した。かつて留夏子に導かれながら、海を割って進む人のようにトウモロコシの畑道を歩んだあの夏の日、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第一五番《田園》に負けじと、猛烈に吠えまくっていたバネットが思い出された。また別の夏の日、陽奈子先生がバッハの〈主よ、人の望みの喜びよ〉を弾きながら、凛とした澄んだ声でドイツ語のコラールを歌ったとき、吠え疲れて眠っていたバネットが思い出された。猛然たるその吠え声は、レッスンを受けに通う悠太郎をいつも迎え、また送った。悠太郎がピアノで鳴らそうと努めている調和にとっては、それは騒音であり混沌の声であった。しかしその吠え声を聞きながらピアノを弾くうちに、かれも音響ならこれも音響だという思いが、悠太郎の胸中に育っていた。人間が作り出す音楽は、無機物や動植物が生じさせる音響の一部でしかないことをバネットは教えていた。その声が突然惨たらしい仕方で永遠に失われてしまったと思うと、淋しさと恐怖が悠太郎の胸に去来した。
「お悔みします。残念なことでした。私にはけっして懐いてはくれませんでしたが、それでも憎めない犬でした」と悠太郎が目を開いて低い声で言うと、傍らに立っていた留夏子はしばしの沈黙の後で、「バネットは私の身代わりになって死んだのかもしれない。合唱コンクールがうまく行って調子に乗った私を、神様が罰したのかもしれない」と沈痛な声で言った。「誰がこんなことをしたのか分からない。三年生の先輩の誰かかもしれないし、もしかしたらお父さんかもしれない」と続けた留夏子に、悠太郎は「まさか」と答えた。「そのまさかがあり得るのよ。お父さんはいつもバネットの声をうるさがって舌打ちをしていたから」と留夏子が言うと、開拓地を吹き渡る荒涼たる風に枯葉が舞った。悠太郎は留夏子の父親のことを考えた。滅多に姿を見せないその父親に出くわしたとき、悠太郎は挨拶して頭を下げるのだが、返ってくるのは冷淡な無視か、さもなければ敵意ある舌打ちであった。いつも無精ひげを生やしたようなその父親は、血走った暗い目で悠太郎に一瞥を与えると、何も言わずに顔を背けてどこかへ行ってしまうのである。
「なんという荒んだものが、私たちを取り巻いていることでしょう。この六里ヶ原を覆う血塗られたもの、酷薄なもの、荒涼たるもの――そうしたものがバネットを死に至らしめたように思われてなりません」と悠太郎は立ち上がって言ったが、その身長は留夏子をわずかに超えていた。「私も似たようなことを考えていた」と応じた留夏子は、「その血塗られたものや酷薄なものや荒涼たるものの正体を、私はこの機会に自分で確かめておきたいと思うの。それはきっと暗いものでしょう。目を背けたくなるようなおぞましいものでしょう。でもふるさとの過去について見極めることなしには、私はここを巣立ってゆけないような気がするの」と続けた。「何か具体的な考えがおありですか?」と悠太郎が問うと、留夏子は「石碑を読もうと思う」と答えた。「文化祭からこのかた、祖父母が少しだけ話してくれるようになったの。大陸でのことや、引き揚げのことや、六里ヶ原の開拓のことを。でもそうしたことを本人たちから根掘り葉掘り聞き出すのは、何か残酷なことのような気がして。それに個人としては知っていることに限りや偏りもあるでしょう。それならいくつかある石碑を読んでゆくのはどうかと思ったの。現在よりも敗戦や六里ヶ原入植に近い時点で、開拓民たちの共通の見解が石に彫り込まれたのだとすれば、生身の人間からは聞き出しにくい事柄を、そこから読み取ることもできるでしょう」
「よい考えだと思います」と悠太郎が言うと、荒んだ風が枯れ草の匂いを運んできた。「そう思ってくれる真壁に、ひとつ相談なのだけど」と留夏子は応じ、「よかったら私と一緒に来てくれない? 石碑には難しい言葉や古い字体もあるでしょう。真壁がいてくれると、とても助かる。付き合ってくれない?」と求めた。悠太郎は留夏子の胸中を思った。少なからぬ恐怖を味わいながら、なおも屈することなく認識を深めようとするその闘志に悠太郎は打たれた。そんな留夏子が自分を必要としてくれることを、悠太郎は誇らしく思いもした。古い時代の漢字の使い方なら、お祖父様のおかげでそれなりに知っている。あれは小学校何年生のときだったか、漢字ドリルで「付属」という字を習ったとき、お祖父様は怒って「附属」とこざとへんをつけて書くように命じた。それで学校のテストのときには、こざとへんをつけて「附属」と書いたら減点された。ところがお祖父様は減点されたことでまた怒るのだから、俺はどうしたらいいのか途方に暮れた。「本当はこうに書くだぞ」と言いながら、戦前に使われていた旧字体をお祖父様は俺に教え込んだ。俺は混乱して学校のテストで旧字体を書いてしまうことがあった。すると竹内ひろみ先生も、富里豊先生も、関ダンベヤー先生も、松本冴子先生も当然のように減点した。そしてお祖父様は減点されたことで怒るのだ。お祖父様の言うことを聞いても怒られ、聞かなくても怒られた。そんなことが何度もあった。俺は漢字の勉強がほとほと嫌になったものだった。それがいま役に立つかもしれないとは、人生何が幸いするか分からないものだ――。そんなことを考えた悠太郎は、「分かりました。一緒に行きます。早めに実行したほうがよさそうですね」と言った。「ありがとう。心強い味方ができたわ」と礼を述べた留夏子は、「そうね。早いところ済ませましょう。六里ヶ原を雪が覆う前に」と言った。すでに浅間山は三度の冠雪で、山裾近くまで白く染まっていた。里に雪が降るまで、もう幾許もあるまいと思われた。
中学校の休み時間に留夏子は埴谷高志先生を訪ね、主だった記念碑の所在を聞き出そうとした。この県の年中行事についてまとめた本に、執筆者として名を連ねる埴谷先生であってみれば――埴谷先生はその本をあるときは留夏子たちのホームルームで、またあるときは悠太郎たちの社会科の時間に宣伝していた――、勤務する学校がある地域の郷土誌的なことには、鼻が利くに違いないと考えたからであった。「そうかそうか。ついに佐藤さんはふるさとの歴史に目醒めたか。合唱コンクールからまた一段と飛躍しようとしているな。感心なことだ。意欲ある優秀な生徒を持つこと以上の喜びはなしだ。がっはっは!」と埴谷先生は、職員室の机の椅子にふんぞり返って破れ鐘のようなでかい声で言うと、モアイ像のような四角張った大きな顔に喜色を浮かべながら、手近な藁半紙に簡単な地図を描き、いくつかの記念碑を地図上にプロットした。そこには留夏子が知っているものもあれば、知らないものもあった。「教えていただいてありがとうございます」と留夏子がその地図を受け取って頭を下げると、「こういうことには俺も興味があるからな。まあ役に立ててくれ。しかしいくら佐藤さんが優秀だといっても、石碑には読むのが難しい字も刻まれているぞ」と埴谷先生は言った。留夏子は「心強い味方が一緒にいてくれます」と言いたい思いを抑えると、「対策は考えてあります」と応じた。「そうかそうか、ますますもってそれは感心だ」と言った埴谷先生は、「ときに佐藤さん、俺の故郷の子持村に興味はないかい? 前にも話したが、例の年中行事の本のなかに、子持村の馬頭観音について書いてある。俺が書いた記事だ。どうだ、興味はないかい?」と勧めた。口許に微笑みを浮かべた留夏子は、「では一冊購入します」と答えた。「さすがは佐藤さん! 話が分かる!」とますますでかい声で喜んだ埴谷先生は、「お礼にとっておきの話を教えてやろう。俺が大学生だった頃、ある集まりで出身地の話になった。〈きみはどこの出身かね?〉と訊かれたので〈私は子持です〉と答えた。すると何て言われたと思う? 〈若いのに大変だね〉とこう来たよ。がっはっは!……」
「その子持の話は本当なんでしょうか。私には埴谷先生の作り話のように思えてなりません。あの人はそういう冗談を言いたがる人ですから」と悠太郎は、次の日曜日の午後にレッスンが終わると、留夏子と落ち合って話した。「真壁の読みもそうなのね。私もそう思う。きっと生殖に関わる冗談を言いたいがために、架空の人物を捏造したのよ」と留夏子はおかしそうに応じた。これから冷たい風に枯葉が舞う晩秋の六里ヶ原を、ふたりは一緒に自転車で駆け回ろうというのである。留夏子は茶色のダッフルコートを着てグレーのマフラーを巻き、白いヘルメットを被って前を走った。悠太郎は小学校以来の黒いウインドブレーカーを着て、梅子が編んだ重たい紫色の毛糸の襟巻きを着け、やはり白いヘルメットを被って後ろを走ったが、見る人が見ればその身なりは、明らかに先輩に見劣りがした。甘楽のバス停の近くにある四つの厳めしい石碑は、留夏子の希望で最後に回すことになっていた。その日はまず北軽井沢のバス停の近くにある「北軽井沢開発之碑」にたどり着いた。
悠太郎は留夏子の求めに応じ、低音の声で碑文を読み上げていったが、その際やはり旧字体の知識が大いに役立った。そこに記されていたのは、白い口ひげと山羊ひげを蓄えたあの枢密顧問官の事績であった。枢密顧問官がこの地を避暑に最適であると判断したことや、彼自身が鷹山荘を構えて住んだことや、自身が学長を務める私立大学の教職員たちのために、読書自適の別荘地たる学芸村を開いたことが記されていた。五百坪単位百二十区の別荘地が坪一円で分譲されたことや、道路が開かれたことや、水道が引かれたことや、熊川のほとりに学芸村倶楽部が建てられたことが記されていた。そして照月湖に関するくだりを読んだとき悠太郎の心は、愛する湖を過ぎていった時の姿を映して妖しく揺らめいた。そして悠太郎が終わりまで読み上げると、留夏子は首を傾げていた。「軽井沢の浮わついた華やぎを追わずって何よ。軽井沢のほうが先に別荘地として有名だったから、それにあやかろうとして名前を借りたんじゃない。自分たちは勝手に北軽井沢と称しておいて、本家本元の軽井沢を浮わついた華やぎだと貶している。なんだかひどい話ね。真壁は学芸村に住んでいるけど、古くからの村民たちにあまりいい印象を持っていないのよね?」と留夏子が言うと、「はい。浅間観光を攻撃するあの人たちには、どこか夜郎自大なところが感じられます。自分たちさえ静かに読書や書き物ができれば、地元民の生活なんかどうなってもいいとでもいうような、自分たちが静寂を得るためならば、地元民の暮らしを平気で壊しにかかるような――そういうところが感じられます。軽井沢の浮わついた華やぎという文言にも、それがよく表れています。よくもまあ照月湖の名を刻んだものだと思います。浅間観光が嫌いなら、楢沢の池と記せばよかったのに」と答えた。
それからふたりはまたそれぞれの自転車に跨ると、山のデパートの前を通り過ぎて悠太郎の下校路を走り、変電所を右手に見ながら三本辻を通過してハイロン集落に入った。いつものことながら開拓集落に踏み入ると、悠太郎にはそこが少しものどかな田園とは見えなかった。石井観光農園のあるハイロン集落にも、神川直矢の家がある大屋原第三集落にも感じられる禍々しい気配は、いつもながら悠太郎を総毛立たせた。ふたりはなおも自転車を漕ぎに漕ぎ、だだっ広い開拓地に伸びる直線の道路を進んで、いくつもの直角のクランクを曲がった。探していたものは、大屋原第一集落の公民館の隣に見出された。それは赤茶けた煉瓦で造られた基底部に、「満蒙拓魂之塔」と刻まれた四角い石柱を戴いていた。塔の正面には、墓にあるような線香台と献花台が設けられていた。比較的新しく――平成になってから――付け加えられたらしい、白いプレートに黒い文字で書かれた案内板からふたりは読み始めた。
悠太郎はまた文字を読み上げていった。国策として推進された旧満洲国への移民は夥しい犠牲者を出したが、この県から送り出された開拓団や青少年義勇隊もその例外ではなく、多くが命を落として大陸の土と化したとそこには記されていた。幸い生き残った者は肉親や同志を弔い、ここに哀悼の意を示す云々と悠太郎が読み上げると、切れ長の目を細めながら文字を追っていた留夏子は、「なんだか破綻したような文章ね。悲惨なことは分かるけど」と突き放すように言った。「厳寒の異郷で八万人の犠牲者とは、想像できないような規模の惨劇です。留夏子さんはもっと心を痛めるかと思いました」と悠太郎が言うと、留夏子は答えた。「安易に心を痛めてはいけないと思っているの。開拓民の苦労話の裏には、日本人が大陸の人たちに対して行なった侵略と加害行為が隠されている。開拓民たちは当然それを隠したい。だから自分たちの犠牲や苦労を表に出す。私自身が開拓民の血を引いているからこそ、そういうことにはいっそう注意したいの」
建立の由来は塔の裏面にあるというので、ふたりは裏側に回った。果たして由来は黒い御影石の地に白く彫り込まれていた。今度は留夏子がどこか冷ややかな声で、その文章を読み上げていった。途中で留夏子はふと言葉を切って黙り込んだ。それからふたりは黙ったまま、文章を目で追っていった。敗戦から時は流れて二十数年後に、ようやく日中の国交が正常化されたことや、両国親善友好の証として旧満洲で亡くなった人々の遺骨が返還されたことや、そのなかにこの県から送り出された十四人が含まれていたことが続いていた。関係者が集まって慎重に協議した結果、この県から送り出された物故者を祀る拓魂之塔をこの地に建立し、返還された遺骨の十四人をも合祀して拓魂を顕彰し、慰霊供養を行なうことになったというのである。「五族協和の王道楽土創建を目標としたって何よ。鉤括弧もつけずにそんなことを言い切ってしまっていいの? 開拓民たちは日本の侵略行為のお先棒を担がされた。彼らはやむを得ず大陸へ渡ったのかもしれない。だからって敗戦した後までも、自分たちのしたことを美化するのは違うでしょう。この文章からは血の臭いがする。どこもかしこも血にまみれている。その血は日本人だけが流したものではない。それなのに、すべては拓魂とやらの顕彰で美化されてしまう。これもまた夜郎自大ね。開拓民の夜郎自大」と留夏子は冷たい声で言った。
隣にある公民館の敷地内には「大屋原開拓記念碑」という石碑があった。大きな長方形の黒い石板を、左右から荒くれた岩が支えていた。「開拓三十年」と題する詩のような文章を留夏子は音読し始めたが、最初の一行ですぐにつかえてしまった。そこにある奇妙な漢字をどうしても読めない留夏子に、悠太郎は「笹です。祖父が持っている顔真卿の書の本で、似たような字の似たような書体を見たことがあります」と助け舟を出した。「笹という字をこんなふうに書くの? まあたしかに意味は通るわね。このあたりには笹が多いから」と納得した留夏子は、改めて冒頭から詩を読んでいった。しばらくしてまた留夏子は行き詰まった。「また変な字が出てきた。これは何?」と問う留夏子に、悠太郎は「野菜です」と答え、「埜」の字は「野」の字にほぼ等しいのだと説明した。しばらくするとまた留夏子は行き詰まり、悠太郎に助けを求めた。しかし悠太郎は「これは読めるはずです」と言っただけであった。「どういうこと? 教えてくれないの?」と怪しむ留夏子に、悠太郎は「これまで読んできたなかにヒントがあります」と告げた。留夏子は切れ長の目を細めながら、読み進めてきた文字列を注意深く再読した。程なくその顔がぱっと明るくなった。いま読めずにいる漢字は、ついさっき読めるようになったばかりの「笹」の異体字のパーツと同じではないか! 「読めた! 人の世!」と留夏子は、いつになく華やいだような声で言った。悠太郎は留夏子の昂った声に、いくらかの奇異の念を覚えた。六里ヶ原始まって以来の逸材と謳われるこの人は、かくも強烈に知的な興奮を感じながら勉強しているのかと思いつつ、悠太郎は語った。「担任の尾池先生が、いつか教えてくれたんです。〈おまえたち、試験のときはな、分からない問題があっても諦めるな。問題用紙を隅から隅まで注意深く読めば、そこにヒントや答えが書いてある場合があるんだ。例えば国語の試験に、ある漢字を書けという問題があるとするだろう。おまえたちがその字を忘れて書けなかったとしよう。ところが試験問題を作った綿貫先生はうっかりして、その漢字を別の問題文のなかで使ってしまっている。例えばの話だ。そういうことがあり得るんだ。試験問題を作るのは教員で、教員だって人間だから、うっかりミスをする。おまえたちがそれに気づいて裏をかけば、一点か二点は儲かるわけだ。学校の定期試験だけじゃない。高校入試だって同じことだ。そうして儲けた一点か二点のために合格できるということがあるんだ。注意深くあって損することはないぞ〉って」
「尾池先生はいい先生ね。その貴い教えを心に刻みましょう。この石碑に刻まれた文字のように」と微笑みながら言った留夏子は、再び詩の続きを読んでいった。「中国東北部に生まれ育ったひとりの人の重さも、今さらにして知ったのかしらね、この詩を書いた人は」と留夏子は、また冷たい声に戻って突き放すように言った。「牛乳と林檎と野菜の村か。この高原に楽土を拓いたとでも言いたげね。それなのに現実は、こんなに荒んでいる。詩を書いて美化しようとすればするほど、ここに暮らす人々の心の荒廃は、隠しようもなく現れてくる。ねえ真壁、なぜ誰も彼もこの六里ヶ原に、ありもしない楽土を求めてやって来るの? できもしない楽土を作ろうとするの?」と留夏子は、思い詰めたような眼差しを石板に刻まれた詩に向けながら言った。「たしかに楽土を求めてきたのは、開拓農民たちばかりではありませんね」と悠太郎は、物問いたげな大きな目で詩を見ながら答えた。「浮世離れした高原の風土が、よそから来た人々に夢を見せるのかもしれません。よそへ出掛けて帰ってくるといつも感じるのですが、この高原では人の気配が希薄なんです。おそらくは歴史の問題でしょう。人跡稀だった高原は、これからどうにでも変えられるという自由の可能性を、入植者に感じさせたのかもしれません。六里ヶ原学芸村の人たちも、この六里ヶ原を桃源郷だと言います。株式会社浅間観光を創業した増田ケンポウ社長も、この六里ヶ原にユートピアを作るんだと言っていたそうです。それぞれがそれぞれの楽土を求めて歳月を重ねてきました。ある人々が思い描いた楽土は、別の人々にとっては楽土ではありませんでした。それぞれの楽土が相争い、わが楽土尊しとばかり他者の楽土を否定し、それぞれの楽土は内輪でばかり力を合わせ助け合い、自分を守ろうとしてきたのではないでしょうか。三つの楽土は三者三様に、戦争の記憶を背負っています。学芸村が作られたのは、日本が戦争へと向かっていった時代のことで、太平洋戦争末期には、村は疎開者で溢れ返ったそうです。浅間観光の増田ケンポウ社長は、軍事工業の新聞を通じて積極的に戦争を推進した人でした。そして開拓民の皆さんについては、改めて言うまでもありません。誰も彼もそれぞれに、戦争の痛みから癒えたいのではないでしょうか。ところが癒えようとしてもがけばもがくほど、痛みのほうで私たちを逃がしてはくれなくなります。実際に戦争を体験した祖父母たちの世代も、その子や孫たちの世代も、痛みから逃れることはできません。この高原の別荘地でどれほど豊かな本が書かれても、湖畔の観光地がどれほど賑わっても、畑でどれほどおいしい野菜や果物が採れても、楽土はやっぱりいつまでも荒涼としているのかもしれません」
「それならやっぱり、目を背けずに過去を見極めなくてはね」と言いながら、留夏子は悠太郎とともに石碑の裏面へ回った。そこには「開拓記念碑建立にあたって」と題する文章が刻まれていた。悠太郎は低音の声で碑文を音読していった。入植開始の年や、道路建設の年や、電気と水道の導入の年が、略年表として記されてもいた。三十年にして入植当初からの目標がほぼ達せられたことを宣言し、昭和五十一年某日の日付をもって碑文は結ばれていた。「私たちが生まれる前ね。将来ここに生きる者って、私たちの世代のことね」と留夏子は独り言のように言った。悠太郎はその言葉に返事をしながらも、「拓友」の一語が呼び起こしたある思い出に浸っていた。かつて大屋原第一集落の佐原康雄は、悠太郎のことをそう呼んでくれた。「ユウちゃんだって今に足が速くなるよ。今日だって休みもせずに五キロ歩けたじゃないか。俺の祖父ちゃん祖母ちゃんたちはここらを開拓したさ。でもユウちゃんが開拓するのは、もっと別のものだよ。何て言ったらいいのかな……?」と励ましがてら言葉を探す康雄に、悠太郎がふと思いついて「目に見えない精神の大地かい?」と助け船を出すと、康雄は「それだよ! まったくユウちゃんはいつもうまいことを言うなあ。ユウちゃんは目に見えない大地の開拓民だ。立派な拓魂の持ち主だよ。俺たちは拓友だぜ!」と言ってくれたのであった。あるいは康雄は小学校一年生の頃から、この碑を読まされていたのかもしれなかった。悠太郎が懐かしい思い出に浸っていると、荒涼たる風が開拓地の枯れ草を騒がせた。「お互い疲れたわね。暗くならないうちに帰りましょう。今日はありがとう。またよろしくね」と留夏子が言った。ふたりはそれぞれの自転車に乗ると、それぞれの家を目指してペダルを漕いだ。
陽奈子先生のレッスンを受けに佐藤農園を訪れた悠太郎は、畑の外れに作られたバネットの墓の前に片膝をつき、手を合わせてしばし瞑目した。かつて留夏子に導かれながら、海を割って進む人のようにトウモロコシの畑道を歩んだあの夏の日、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第一五番《田園》に負けじと、猛烈に吠えまくっていたバネットが思い出された。また別の夏の日、陽奈子先生がバッハの〈主よ、人の望みの喜びよ〉を弾きながら、凛とした澄んだ声でドイツ語のコラールを歌ったとき、吠え疲れて眠っていたバネットが思い出された。猛然たるその吠え声は、レッスンを受けに通う悠太郎をいつも迎え、また送った。悠太郎がピアノで鳴らそうと努めている調和にとっては、それは騒音であり混沌の声であった。しかしその吠え声を聞きながらピアノを弾くうちに、かれも音響ならこれも音響だという思いが、悠太郎の胸中に育っていた。人間が作り出す音楽は、無機物や動植物が生じさせる音響の一部でしかないことをバネットは教えていた。その声が突然惨たらしい仕方で永遠に失われてしまったと思うと、淋しさと恐怖が悠太郎の胸に去来した。
「お悔みします。残念なことでした。私にはけっして懐いてはくれませんでしたが、それでも憎めない犬でした」と悠太郎が目を開いて低い声で言うと、傍らに立っていた留夏子はしばしの沈黙の後で、「バネットは私の身代わりになって死んだのかもしれない。合唱コンクールがうまく行って調子に乗った私を、神様が罰したのかもしれない」と沈痛な声で言った。「誰がこんなことをしたのか分からない。三年生の先輩の誰かかもしれないし、もしかしたらお父さんかもしれない」と続けた留夏子に、悠太郎は「まさか」と答えた。「そのまさかがあり得るのよ。お父さんはいつもバネットの声をうるさがって舌打ちをしていたから」と留夏子が言うと、開拓地を吹き渡る荒涼たる風に枯葉が舞った。悠太郎は留夏子の父親のことを考えた。滅多に姿を見せないその父親に出くわしたとき、悠太郎は挨拶して頭を下げるのだが、返ってくるのは冷淡な無視か、さもなければ敵意ある舌打ちであった。いつも無精ひげを生やしたようなその父親は、血走った暗い目で悠太郎に一瞥を与えると、何も言わずに顔を背けてどこかへ行ってしまうのである。
「なんという荒んだものが、私たちを取り巻いていることでしょう。この六里ヶ原を覆う血塗られたもの、酷薄なもの、荒涼たるもの――そうしたものがバネットを死に至らしめたように思われてなりません」と悠太郎は立ち上がって言ったが、その身長は留夏子をわずかに超えていた。「私も似たようなことを考えていた」と応じた留夏子は、「その血塗られたものや酷薄なものや荒涼たるものの正体を、私はこの機会に自分で確かめておきたいと思うの。それはきっと暗いものでしょう。目を背けたくなるようなおぞましいものでしょう。でもふるさとの過去について見極めることなしには、私はここを巣立ってゆけないような気がするの」と続けた。「何か具体的な考えがおありですか?」と悠太郎が問うと、留夏子は「石碑を読もうと思う」と答えた。「文化祭からこのかた、祖父母が少しだけ話してくれるようになったの。大陸でのことや、引き揚げのことや、六里ヶ原の開拓のことを。でもそうしたことを本人たちから根掘り葉掘り聞き出すのは、何か残酷なことのような気がして。それに個人としては知っていることに限りや偏りもあるでしょう。それならいくつかある石碑を読んでゆくのはどうかと思ったの。現在よりも敗戦や六里ヶ原入植に近い時点で、開拓民たちの共通の見解が石に彫り込まれたのだとすれば、生身の人間からは聞き出しにくい事柄を、そこから読み取ることもできるでしょう」
「よい考えだと思います」と悠太郎が言うと、荒んだ風が枯れ草の匂いを運んできた。「そう思ってくれる真壁に、ひとつ相談なのだけど」と留夏子は応じ、「よかったら私と一緒に来てくれない? 石碑には難しい言葉や古い字体もあるでしょう。真壁がいてくれると、とても助かる。付き合ってくれない?」と求めた。悠太郎は留夏子の胸中を思った。少なからぬ恐怖を味わいながら、なおも屈することなく認識を深めようとするその闘志に悠太郎は打たれた。そんな留夏子が自分を必要としてくれることを、悠太郎は誇らしく思いもした。古い時代の漢字の使い方なら、お祖父様のおかげでそれなりに知っている。あれは小学校何年生のときだったか、漢字ドリルで「付属」という字を習ったとき、お祖父様は怒って「附属」とこざとへんをつけて書くように命じた。それで学校のテストのときには、こざとへんをつけて「附属」と書いたら減点された。ところがお祖父様は減点されたことでまた怒るのだから、俺はどうしたらいいのか途方に暮れた。「本当はこうに書くだぞ」と言いながら、戦前に使われていた旧字体をお祖父様は俺に教え込んだ。俺は混乱して学校のテストで旧字体を書いてしまうことがあった。すると竹内ひろみ先生も、富里豊先生も、関ダンベヤー先生も、松本冴子先生も当然のように減点した。そしてお祖父様は減点されたことで怒るのだ。お祖父様の言うことを聞いても怒られ、聞かなくても怒られた。そんなことが何度もあった。俺は漢字の勉強がほとほと嫌になったものだった。それがいま役に立つかもしれないとは、人生何が幸いするか分からないものだ――。そんなことを考えた悠太郎は、「分かりました。一緒に行きます。早めに実行したほうがよさそうですね」と言った。「ありがとう。心強い味方ができたわ」と礼を述べた留夏子は、「そうね。早いところ済ませましょう。六里ヶ原を雪が覆う前に」と言った。すでに浅間山は三度の冠雪で、山裾近くまで白く染まっていた。里に雪が降るまで、もう幾許もあるまいと思われた。
中学校の休み時間に留夏子は埴谷高志先生を訪ね、主だった記念碑の所在を聞き出そうとした。この県の年中行事についてまとめた本に、執筆者として名を連ねる埴谷先生であってみれば――埴谷先生はその本をあるときは留夏子たちのホームルームで、またあるときは悠太郎たちの社会科の時間に宣伝していた――、勤務する学校がある地域の郷土誌的なことには、鼻が利くに違いないと考えたからであった。「そうかそうか。ついに佐藤さんはふるさとの歴史に目醒めたか。合唱コンクールからまた一段と飛躍しようとしているな。感心なことだ。意欲ある優秀な生徒を持つこと以上の喜びはなしだ。がっはっは!」と埴谷先生は、職員室の机の椅子にふんぞり返って破れ鐘のようなでかい声で言うと、モアイ像のような四角張った大きな顔に喜色を浮かべながら、手近な藁半紙に簡単な地図を描き、いくつかの記念碑を地図上にプロットした。そこには留夏子が知っているものもあれば、知らないものもあった。「教えていただいてありがとうございます」と留夏子がその地図を受け取って頭を下げると、「こういうことには俺も興味があるからな。まあ役に立ててくれ。しかしいくら佐藤さんが優秀だといっても、石碑には読むのが難しい字も刻まれているぞ」と埴谷先生は言った。留夏子は「心強い味方が一緒にいてくれます」と言いたい思いを抑えると、「対策は考えてあります」と応じた。「そうかそうか、ますますもってそれは感心だ」と言った埴谷先生は、「ときに佐藤さん、俺の故郷の子持村に興味はないかい? 前にも話したが、例の年中行事の本のなかに、子持村の馬頭観音について書いてある。俺が書いた記事だ。どうだ、興味はないかい?」と勧めた。口許に微笑みを浮かべた留夏子は、「では一冊購入します」と答えた。「さすがは佐藤さん! 話が分かる!」とますますでかい声で喜んだ埴谷先生は、「お礼にとっておきの話を教えてやろう。俺が大学生だった頃、ある集まりで出身地の話になった。〈きみはどこの出身かね?〉と訊かれたので〈私は子持です〉と答えた。すると何て言われたと思う? 〈若いのに大変だね〉とこう来たよ。がっはっは!……」
「その子持の話は本当なんでしょうか。私には埴谷先生の作り話のように思えてなりません。あの人はそういう冗談を言いたがる人ですから」と悠太郎は、次の日曜日の午後にレッスンが終わると、留夏子と落ち合って話した。「真壁の読みもそうなのね。私もそう思う。きっと生殖に関わる冗談を言いたいがために、架空の人物を捏造したのよ」と留夏子はおかしそうに応じた。これから冷たい風に枯葉が舞う晩秋の六里ヶ原を、ふたりは一緒に自転車で駆け回ろうというのである。留夏子は茶色のダッフルコートを着てグレーのマフラーを巻き、白いヘルメットを被って前を走った。悠太郎は小学校以来の黒いウインドブレーカーを着て、梅子が編んだ重たい紫色の毛糸の襟巻きを着け、やはり白いヘルメットを被って後ろを走ったが、見る人が見ればその身なりは、明らかに先輩に見劣りがした。甘楽のバス停の近くにある四つの厳めしい石碑は、留夏子の希望で最後に回すことになっていた。その日はまず北軽井沢のバス停の近くにある「北軽井沢開発之碑」にたどり着いた。
悠太郎は留夏子の求めに応じ、低音の声で碑文を読み上げていったが、その際やはり旧字体の知識が大いに役立った。そこに記されていたのは、白い口ひげと山羊ひげを蓄えたあの枢密顧問官の事績であった。枢密顧問官がこの地を避暑に最適であると判断したことや、彼自身が鷹山荘を構えて住んだことや、自身が学長を務める私立大学の教職員たちのために、読書自適の別荘地たる学芸村を開いたことが記されていた。五百坪単位百二十区の別荘地が坪一円で分譲されたことや、道路が開かれたことや、水道が引かれたことや、熊川のほとりに学芸村倶楽部が建てられたことが記されていた。そして照月湖に関するくだりを読んだとき悠太郎の心は、愛する湖を過ぎていった時の姿を映して妖しく揺らめいた。そして悠太郎が終わりまで読み上げると、留夏子は首を傾げていた。「軽井沢の浮わついた華やぎを追わずって何よ。軽井沢のほうが先に別荘地として有名だったから、それにあやかろうとして名前を借りたんじゃない。自分たちは勝手に北軽井沢と称しておいて、本家本元の軽井沢を浮わついた華やぎだと貶している。なんだかひどい話ね。真壁は学芸村に住んでいるけど、古くからの村民たちにあまりいい印象を持っていないのよね?」と留夏子が言うと、「はい。浅間観光を攻撃するあの人たちには、どこか夜郎自大なところが感じられます。自分たちさえ静かに読書や書き物ができれば、地元民の生活なんかどうなってもいいとでもいうような、自分たちが静寂を得るためならば、地元民の暮らしを平気で壊しにかかるような――そういうところが感じられます。軽井沢の浮わついた華やぎという文言にも、それがよく表れています。よくもまあ照月湖の名を刻んだものだと思います。浅間観光が嫌いなら、楢沢の池と記せばよかったのに」と答えた。
それからふたりはまたそれぞれの自転車に跨ると、山のデパートの前を通り過ぎて悠太郎の下校路を走り、変電所を右手に見ながら三本辻を通過してハイロン集落に入った。いつものことながら開拓集落に踏み入ると、悠太郎にはそこが少しものどかな田園とは見えなかった。石井観光農園のあるハイロン集落にも、神川直矢の家がある大屋原第三集落にも感じられる禍々しい気配は、いつもながら悠太郎を総毛立たせた。ふたりはなおも自転車を漕ぎに漕ぎ、だだっ広い開拓地に伸びる直線の道路を進んで、いくつもの直角のクランクを曲がった。探していたものは、大屋原第一集落の公民館の隣に見出された。それは赤茶けた煉瓦で造られた基底部に、「満蒙拓魂之塔」と刻まれた四角い石柱を戴いていた。塔の正面には、墓にあるような線香台と献花台が設けられていた。比較的新しく――平成になってから――付け加えられたらしい、白いプレートに黒い文字で書かれた案内板からふたりは読み始めた。
悠太郎はまた文字を読み上げていった。国策として推進された旧満洲国への移民は夥しい犠牲者を出したが、この県から送り出された開拓団や青少年義勇隊もその例外ではなく、多くが命を落として大陸の土と化したとそこには記されていた。幸い生き残った者は肉親や同志を弔い、ここに哀悼の意を示す云々と悠太郎が読み上げると、切れ長の目を細めながら文字を追っていた留夏子は、「なんだか破綻したような文章ね。悲惨なことは分かるけど」と突き放すように言った。「厳寒の異郷で八万人の犠牲者とは、想像できないような規模の惨劇です。留夏子さんはもっと心を痛めるかと思いました」と悠太郎が言うと、留夏子は答えた。「安易に心を痛めてはいけないと思っているの。開拓民の苦労話の裏には、日本人が大陸の人たちに対して行なった侵略と加害行為が隠されている。開拓民たちは当然それを隠したい。だから自分たちの犠牲や苦労を表に出す。私自身が開拓民の血を引いているからこそ、そういうことにはいっそう注意したいの」
建立の由来は塔の裏面にあるというので、ふたりは裏側に回った。果たして由来は黒い御影石の地に白く彫り込まれていた。今度は留夏子がどこか冷ややかな声で、その文章を読み上げていった。途中で留夏子はふと言葉を切って黙り込んだ。それからふたりは黙ったまま、文章を目で追っていった。敗戦から時は流れて二十数年後に、ようやく日中の国交が正常化されたことや、両国親善友好の証として旧満洲で亡くなった人々の遺骨が返還されたことや、そのなかにこの県から送り出された十四人が含まれていたことが続いていた。関係者が集まって慎重に協議した結果、この県から送り出された物故者を祀る拓魂之塔をこの地に建立し、返還された遺骨の十四人をも合祀して拓魂を顕彰し、慰霊供養を行なうことになったというのである。「五族協和の王道楽土創建を目標としたって何よ。鉤括弧もつけずにそんなことを言い切ってしまっていいの? 開拓民たちは日本の侵略行為のお先棒を担がされた。彼らはやむを得ず大陸へ渡ったのかもしれない。だからって敗戦した後までも、自分たちのしたことを美化するのは違うでしょう。この文章からは血の臭いがする。どこもかしこも血にまみれている。その血は日本人だけが流したものではない。それなのに、すべては拓魂とやらの顕彰で美化されてしまう。これもまた夜郎自大ね。開拓民の夜郎自大」と留夏子は冷たい声で言った。
隣にある公民館の敷地内には「大屋原開拓記念碑」という石碑があった。大きな長方形の黒い石板を、左右から荒くれた岩が支えていた。「開拓三十年」と題する詩のような文章を留夏子は音読し始めたが、最初の一行ですぐにつかえてしまった。そこにある奇妙な漢字をどうしても読めない留夏子に、悠太郎は「笹です。祖父が持っている顔真卿の書の本で、似たような字の似たような書体を見たことがあります」と助け舟を出した。「笹という字をこんなふうに書くの? まあたしかに意味は通るわね。このあたりには笹が多いから」と納得した留夏子は、改めて冒頭から詩を読んでいった。しばらくしてまた留夏子は行き詰まった。「また変な字が出てきた。これは何?」と問う留夏子に、悠太郎は「野菜です」と答え、「埜」の字は「野」の字にほぼ等しいのだと説明した。しばらくするとまた留夏子は行き詰まり、悠太郎に助けを求めた。しかし悠太郎は「これは読めるはずです」と言っただけであった。「どういうこと? 教えてくれないの?」と怪しむ留夏子に、悠太郎は「これまで読んできたなかにヒントがあります」と告げた。留夏子は切れ長の目を細めながら、読み進めてきた文字列を注意深く再読した。程なくその顔がぱっと明るくなった。いま読めずにいる漢字は、ついさっき読めるようになったばかりの「笹」の異体字のパーツと同じではないか! 「読めた! 人の世!」と留夏子は、いつになく華やいだような声で言った。悠太郎は留夏子の昂った声に、いくらかの奇異の念を覚えた。六里ヶ原始まって以来の逸材と謳われるこの人は、かくも強烈に知的な興奮を感じながら勉強しているのかと思いつつ、悠太郎は語った。「担任の尾池先生が、いつか教えてくれたんです。〈おまえたち、試験のときはな、分からない問題があっても諦めるな。問題用紙を隅から隅まで注意深く読めば、そこにヒントや答えが書いてある場合があるんだ。例えば国語の試験に、ある漢字を書けという問題があるとするだろう。おまえたちがその字を忘れて書けなかったとしよう。ところが試験問題を作った綿貫先生はうっかりして、その漢字を別の問題文のなかで使ってしまっている。例えばの話だ。そういうことがあり得るんだ。試験問題を作るのは教員で、教員だって人間だから、うっかりミスをする。おまえたちがそれに気づいて裏をかけば、一点か二点は儲かるわけだ。学校の定期試験だけじゃない。高校入試だって同じことだ。そうして儲けた一点か二点のために合格できるということがあるんだ。注意深くあって損することはないぞ〉って」
「尾池先生はいい先生ね。その貴い教えを心に刻みましょう。この石碑に刻まれた文字のように」と微笑みながら言った留夏子は、再び詩の続きを読んでいった。「中国東北部に生まれ育ったひとりの人の重さも、今さらにして知ったのかしらね、この詩を書いた人は」と留夏子は、また冷たい声に戻って突き放すように言った。「牛乳と林檎と野菜の村か。この高原に楽土を拓いたとでも言いたげね。それなのに現実は、こんなに荒んでいる。詩を書いて美化しようとすればするほど、ここに暮らす人々の心の荒廃は、隠しようもなく現れてくる。ねえ真壁、なぜ誰も彼もこの六里ヶ原に、ありもしない楽土を求めてやって来るの? できもしない楽土を作ろうとするの?」と留夏子は、思い詰めたような眼差しを石板に刻まれた詩に向けながら言った。「たしかに楽土を求めてきたのは、開拓農民たちばかりではありませんね」と悠太郎は、物問いたげな大きな目で詩を見ながら答えた。「浮世離れした高原の風土が、よそから来た人々に夢を見せるのかもしれません。よそへ出掛けて帰ってくるといつも感じるのですが、この高原では人の気配が希薄なんです。おそらくは歴史の問題でしょう。人跡稀だった高原は、これからどうにでも変えられるという自由の可能性を、入植者に感じさせたのかもしれません。六里ヶ原学芸村の人たちも、この六里ヶ原を桃源郷だと言います。株式会社浅間観光を創業した増田ケンポウ社長も、この六里ヶ原にユートピアを作るんだと言っていたそうです。それぞれがそれぞれの楽土を求めて歳月を重ねてきました。ある人々が思い描いた楽土は、別の人々にとっては楽土ではありませんでした。それぞれの楽土が相争い、わが楽土尊しとばかり他者の楽土を否定し、それぞれの楽土は内輪でばかり力を合わせ助け合い、自分を守ろうとしてきたのではないでしょうか。三つの楽土は三者三様に、戦争の記憶を背負っています。学芸村が作られたのは、日本が戦争へと向かっていった時代のことで、太平洋戦争末期には、村は疎開者で溢れ返ったそうです。浅間観光の増田ケンポウ社長は、軍事工業の新聞を通じて積極的に戦争を推進した人でした。そして開拓民の皆さんについては、改めて言うまでもありません。誰も彼もそれぞれに、戦争の痛みから癒えたいのではないでしょうか。ところが癒えようとしてもがけばもがくほど、痛みのほうで私たちを逃がしてはくれなくなります。実際に戦争を体験した祖父母たちの世代も、その子や孫たちの世代も、痛みから逃れることはできません。この高原の別荘地でどれほど豊かな本が書かれても、湖畔の観光地がどれほど賑わっても、畑でどれほどおいしい野菜や果物が採れても、楽土はやっぱりいつまでも荒涼としているのかもしれません」
「それならやっぱり、目を背けずに過去を見極めなくてはね」と言いながら、留夏子は悠太郎とともに石碑の裏面へ回った。そこには「開拓記念碑建立にあたって」と題する文章が刻まれていた。悠太郎は低音の声で碑文を音読していった。入植開始の年や、道路建設の年や、電気と水道の導入の年が、略年表として記されてもいた。三十年にして入植当初からの目標がほぼ達せられたことを宣言し、昭和五十一年某日の日付をもって碑文は結ばれていた。「私たちが生まれる前ね。将来ここに生きる者って、私たちの世代のことね」と留夏子は独り言のように言った。悠太郎はその言葉に返事をしながらも、「拓友」の一語が呼び起こしたある思い出に浸っていた。かつて大屋原第一集落の佐原康雄は、悠太郎のことをそう呼んでくれた。「ユウちゃんだって今に足が速くなるよ。今日だって休みもせずに五キロ歩けたじゃないか。俺の祖父ちゃん祖母ちゃんたちはここらを開拓したさ。でもユウちゃんが開拓するのは、もっと別のものだよ。何て言ったらいいのかな……?」と励ましがてら言葉を探す康雄に、悠太郎がふと思いついて「目に見えない精神の大地かい?」と助け船を出すと、康雄は「それだよ! まったくユウちゃんはいつもうまいことを言うなあ。ユウちゃんは目に見えない大地の開拓民だ。立派な拓魂の持ち主だよ。俺たちは拓友だぜ!」と言ってくれたのであった。あるいは康雄は小学校一年生の頃から、この碑を読まされていたのかもしれなかった。悠太郎が懐かしい思い出に浸っていると、荒涼たる風が開拓地の枯れ草を騒がせた。「お互い疲れたわね。暗くならないうちに帰りましょう。今日はありがとう。またよろしくね」と留夏子が言った。ふたりはそれぞれの自転車に乗ると、それぞれの家を目指してペダルを漕いだ。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
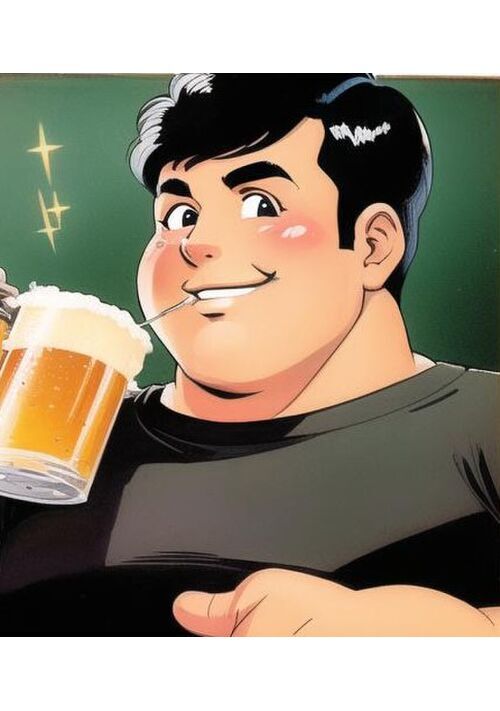
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















