54 / 73
第十八章 森の葉隠れ
三
しおりを挟む
五十一年前の八月、五族協和の王道楽土と呼ばれていた旧満洲国に、まだ若かった田茂喜三郎さんとヨシノさんはいた。ふたりが入植した地方は北満も北満で、ハルビンよりもっと北の、ソヴィエト連邦との国境に近いあたりであった。遠く東の彼方には小興安嶺の山脈が望まれた。西の果てに大きな夕日が真っ赤に燃えて沈むのを見ながら、ふたりは歳月を重ねていた。寒いところではあったが、その地方は北満でも有数の穀倉地帯とて地味は肥沃であった。小麦でも大豆でも小豆でもトウモロコシでも、ただ蒔くだけで肥料をほとんど与えずに収獲できた。家が建ち、病院が建ち、神社ができていた。醸造場が建ち、穀物加工場が建ち、倉庫が建ち、蹄鉄工場が建ち、鍛工場が建ち、立派な煉瓦造りの小学校ができていた。道路や橋も完備し、人員およそ五百名の開拓村は栄えていた。入植当初の見渡す限りの草原は黒々とした畑に変わり、水田も開かれて稲穂は豊かに実っていた。しかるに一九四五年の八月十五日、海倫県公署警務課より、祖国日本の無条件降伏が伝えられたのである。
しばらく前から奇妙な兆候はあった。二ヶ月前の六月から、開拓団の団長や幹部や団員たちが百名近く、関東軍の現地要員として次々と召集された。農地に種を蒔くべき時期に、ごっそりと男手を奪われるのは、やはりただ事ではなかった。喜三郎さんとヨシノさんは、残った団員たちと励まし合いながら食糧増産に努めた。しかし八月も九日を過ぎると、恐れていたソ連参戦の噂が、現地人の口から口へと伝わるのが聞こえた。そして十五日、日本は敗れた。こうなったらもう満洲最北の地で孤立無援である。自分たちの身は自分たちで護るよりほかにない。団にある武器はといえば、小銃が三百丁、軽機関銃が二丁、追撃砲が一門、手榴弾が六百個であった。翌日団員たちは各集落から、これらの武器を持ち寄って団本部に集結した。ヨシノさんはほかの女や子供たちとともに、団本部の建物内に収容された。喜三郎さんは男たちとともに銃を持って土壁の内外を固め、昼夜を問わず暴徒の襲撃を警戒した。
ところが唯一頼みとするそれらの武器は、すべて没収されることになった。侵入してきて周辺をうろついていたソ連の軍隊が二十八日に至って、団が保有する武器の一切を差し出すよう命じたのである。ただでさえ多くの男手を取られ弱体化していた開拓団が、このうえ武器まで奪われてはまったくの無防備になってしまう。しかし日本は戦争に敗れたのである。敗戦国の民が反抗でもすれば、命はないものと思ってよかった。団員たちは皮でも剝がされるような思いで、すべての武器を大車九台に載せて現地人側に引き渡した。これでもはや団員たちには身を護るすべはなくなったわけであった。ところがその頃になると、どこそこで日本人開拓民が暴徒に襲われたという噂がしきりと伝えられ、団員たちの不安は募るばかりであった。
九月に入ると恐ろしいことが起こり始めた。満洲に長雨が降る月初めの頃、すぐ南隣の開拓団が暴徒の襲撃を受け、徹底的に痛めつけられたらしいのである。生き残った人々は、怪我人を肩に担いで海倫村に逃げ込んできた。村では棒切れを拾い集めて先端を尖らせ、急拵えの手槍を作っては見たものの、そんなもので暴徒を防ぎ切れるかと不安は募るばかりであった。連日連夜雨は降り続き、団の周辺は泥沼と化して身動きもならず、喜三郎さんもヨシノさんも息をひそめて生きた心地もしない日々を送っていた。ところが頼みの手槍さえ、持っていることは許されなかった。ソ連兵が五、六人でやって来ては屋内を物色し、金目のものを奪い、手槍を片端からへし折って、銃弾一発でも持っている者は銃殺だと言い捨ててゆくのであった。
そして九月十一日の早暁、団本部の展望台に備えつけてあったサイレンが鳴り響いたので、ヨシノさんも喜三郎さんも跳ね起きた。ふたりは急いで身支度をすると、ヨシノさんはかねて打ち合わせてあった通り女たちと窓を閉め固め、喜三郎さんは男たちとともに外へ飛び出した。ヨシノさんも喜三郎さんもわが目を疑った。本部南門のほうから、人・人・人・人・人――。その数一千人はいるかと思われる暴徒たちが、手に手に銃や槍を持ち、狂乱したような叫び声を上げながら、雲霞のごとく押し寄せてくるではないか! 匪襲だ! 匪襲だ! 匪襲だ!――そんな声が口から口へと瞬時に伝わった。団にはもう武器はなかった。急拵えの手槍もなかった。身を護るのに使えそうなものといえば、農作業用の鎌くらいしかなかった。そこへ暴徒たちは雨あられと銃弾を打ち込んだから、窓ガラスは粉微塵に砕け散り、団員たちは弾に当たって次々と倒れた。ヨシノさんの左目の下を銃弾がかすめていった。喜三郎さんも左肩を撃たれた。死者は三十名を超え、銃弾で蜂の巣にされた死骸があり、槍でめった刺しにされた死骸があった。
みんなは煉瓦造りの学校へ逃げ、なおも廊下に米俵を積んでそれを境に敵と戦ったが、銃弾によって開けられた穴から米粒がさらさらとこぼれ、ついには降参のやむなきに至って白旗を上げた。みんなは現地人たちによって引き出され、雨が降る庭の泥濘のなかに座らされ、衣服を脱がされて裸にされ……。衣服も金銭も建具も敷物も、現地人たちは何台もの大車に満載して、きれいさっぱり持ち去ってしまった。喜三郎さんもヨシノさんも、裸の背に冷たい雨を受けていた。死んだ者たちの服を脱がせて身に着けた頃には、はや日も暮れようとしていた。翌十二日の夜明け、ヨシノさんも喜三郎さんもみんなを手伝って、死んだ者たちを本部の建物のなかに横たえた。火をかけられた建物は、たちまち炎上して遺体を荼毘に付した。それから大車九台に負傷者や子供を載せ、みんなは一路海北の駅を目指した。五族協和の王道楽土を建設せんと理想に燃えた約七年の、それは無残な結末であった。祖国へ帰る唯一の活路たる海北駅は、三十キロの彼方であった。その道々にも暴徒は現れ、わずかに身に着けているものまでも奪っていった。海北駅に着いたのが夕刻で、それからは無蓋貨車の荷物となり、雨風を身に受けながら揺られ揺られて長春を目指した。引揚収容所に入っての生活は困苦を極めた。栄養失調と疫病のために死ぬ者は百名を超えた。みんながようやく葫蘆島から出た引揚船で佐世保港に帰れたのは、敗戦の翌年の九月であった。
それに比べれば佐藤今朝次さんの属していた開拓団の脱出は、悲惨ではあったがまだしも犠牲の少ないものであった。比較的遅くに発足したその開拓団が、畑地いっぱい豊かに実る大豆やトウモロコシに加え、郷里の牧場からジャージー牛を取り寄せて酪農にも乗り出したその矢先、敗戦の悲報は突如として一同を襲ったのである。それは八月二十日になってからのことであった。その日開拓団国民学校の校長は、職員の給料を受領しようと、中心街の満拓公社へ出向いた。ところがその途中で校長は、現地の公安局に拘禁されたのである。そこで校長は恐るべき話を聞かされた。日本は敗戦した。日本関係筋の機関や団体はすべて自発的に武装解除し、武器弾薬を公安局に提出した。しかるに貴殿らの開拓団はいまだに武装を解いていない。かくなるうえは即刻包囲してこれを殲滅する――。寝耳に水の話に校長は戦慄した。言われてみれば十日頃から開拓地の上空を、見慣れない飛行機が飛んでいたが、あれはソ連参戦の前触れだったのだと校長は気づいた。彼は公安局の釈放を得て団に走り戻り、一切を団長に知らせた。団長の決断は素早かった。小銃も機関銃も手榴弾も、その日のうちに洗いざらい公安局に提出した。
それでも九月に入る頃に、報国農場は襲撃を受けた。夜陰に乗じた十数名の暴徒たちは、草かきを改造した槍や草刈り鎌を手に来襲し、たまたま居合わせた場長をめった打ちにして半殺しの目に遭わせた。そうしたことがあってから、開拓団は警戒を強めた。暴徒が残していった武器を真似て草かきを改造し、槍を作って武装した。暴徒の襲撃は繰り返され、敵の数は四百人にも五百人にものぼることがあった。今朝次さんは急拵えの槍を手にした少年たちをまとめて、日ごと警備に当たった。日暮れになると遠い稜線の彼方から、オーイ、オーイと喚声に似た声が聞こえた。敵襲かと殺気立ち身構えて耳を澄ませば、それは狼が仲間と呼び交わす声であった。団長の判断によって無闇と彷徨しないことに決め、敗戦から一年後に帰国命令が出るまで現地に留まった団員たちは、六百名のうち三十名ばかりを死なせただけで、残りの大半は無事に博多港へ帰り着くことができたとはいえ、孤立無援で敵襲を防ぎ続けた引き揚げまでの日々は、やはり生きた心地もしないものであった。
小野屋ツギさんは女子高等師範学校時代に、〈流浪の民〉を女声合唱で歌ったことがあった。本当だ、私たちは楽土を求めたね。まずは大陸に、次にはこの六里ヶ原に――。ツギさんが属していた開拓団もまた、敗戦とともに潰滅した。八月二十日に村を脱出して以来、一年以上にわたった満洲での逃避行では、暴徒の襲撃と病によって夥しい犠牲者が出た。思い起こせば血と雨と泥ばかりであった。命からがら故郷に帰れたのは、翌年の九月であった。大陸に王道楽土を建設するという理想は潰えたが、帰還した者たちにとっては、焦土と化した祖国の土を拓くほかに再起の道はなかった。入植先として選ばれた六里ヶ原は、みんなが一度は骨を埋めようと決意した満洲の地に似ていた。みんなは開墾地に生い茂る唐松を伐り倒して柱とし、刈り取ったクマザサを屋根や壁として家を作った。夜ともなれば屋根の笹の葉の隙間から、冴え冴えと星の光が見えた。みんなと一緒にツギさんも、来る日も来る日も樹を伐り、切り株を取り除き、土を掘り起こして開墾した。そうして作られた畑に初めて粟が実ったとき、「はあ死なねえのう」と大屋原集落のある男性が言ったことを、ツギさんは昨日のことのように憶えていた。私の一生が楽土ということにつきまとわれようとは、師範学校時代には夢にも思わなかったねえ。楽土を求めるのは、夢のなかだけにしておけばよかったねえ。しょっぱい海を渡って満洲へなんか行ったのは、間違いだったのかもしれないねえ。私たちの開拓団では、現地の人たちに開墾させた畑で、大豆やトウモロコシを作っていた。私たちはあの人たちを匪賊なんて言ったけど、果たしてどちらが匪賊だったのか分からない。私たちはあの人たちから屯匪と呼ばれるようなことをやっていた。その報いを受けたのかねえ。私たちが受けた苦しみも、私たちが与えた苦しみも、時が経とうが消えはしないねえ――。
老人たちの脳裏にそんな思いが去来するあいだに、音楽は冒頭を再現させていた。ペトラがアウフタクトに始まる二音の律動を提示するあいだ、留夏子はまたスカートの裾をふわりと翻し、ポニーテールをぴょこりと弾ませながら素早く半回転して合唱のほうを向いた。
■■■■■■■
と弱音で囁くように歌い始める合唱を、留夏子は小さな手振りで指揮した。「しかし今東に朝が目醒めると」という原詩の大意の通り、ざわめく森のなかで夢から醒める人々のように動き出した合唱は、
■■■■■■■■
でいよいよ現実に戻るかのようにクレッシェンドした。「夜の美しい姿は消え失せ」というのが原詩の大意であるから、ここはほとんど直訳といってよかった。Gebildeという単語が表すのは、夜の夢が産出する様々な姿形であろうというのが、ドイツ語の辞書を引いた悠太郎の理解であったし、留夏子もペトラも二年生のみんなも、その理解を共有していた。
■■■■■■■■■■
と合唱が歌うところは、「一日の始まりに騾馬は声高く鳴く」という原詩の大意に相応しい活気を秘めて歌われ、
■■■■■■■■■
では、ついに旅立つ流浪の民の活動開始を表して、クレッシェンドしデクレッシェンドした。「人影は先へと進む――どこへ行くのか誰がおまえに教えてくれよう?」という原詩を的確に表した訳詞であった。流浪の民が示されるときに伴奏に出た運動的な動機が、合唱が歌わないあいだにまた現れたから、ペトラはツインテールの髪を躍らせながら、オクターヴの上行が特徴的なその動機に巧みなアクセントをつけた。
■■■■■■■■■
と合唱は弱音からクレッシェンドして盛り上がった。最後には振幅の大きな留夏子の指揮につれて、
■■■■■■■■■ ■■■■
とピアニシモからフォルティシモまで大きく盛り上がり、崩れ落ちるようなピアノの後奏と、遠ざかりゆく人影を見送るようなアルペジオが鳴らされた。
ホ短調の主音を根音に持たないアルペジオが寄る辺なさそうに鳴らされ、その響きが消えた後しばらくは体育館は静寂に包まれていた。両手を軽く握って演奏を止めていた留夏子が、その姿勢を解いて指揮台から降りると、割れんばかりの拍手喝采が沸き起こった。老人たちのなかには半ば椅子から立ち上がり、目に涙を溜めて拍手を送る人もいた。ピアノの椅子を立ったペトラとともに、留夏子は聴衆に一礼すると、その切れ長の目で悠太郎の視線を捉えた。「真壁、どう? 見てくれた? 聴いてくれた?」と留夏子は頬を紅潮させ、わずかに肩で息をしながら悠太郎に視線で問うた。「留夏子さん、見ました。聴きました。お見事でした」と悠太郎は頷きながら視線で答えた。
それからはもう大変なことが起こった。二年生たちの合唱のあまりの見事さに、三年生たちは動揺し、驚き呆れ、浮き足立って軽挙妄動した。髪の生え際に鬼の角のような剃り込みを入れたあの男子は、「おい何だあの鳴り物は。ふざけんじゃねえぞ!」とかすれたような声で言った。中島猛夫は鼻の穴を膨らませて粗野な声で、「指揮者が声を出していいのかよ。なめてんじゃねえぞ!」と喚き散らし、眉間に皺を寄せて産毛だらけの猿めいた顔を歪め、中指を突き上げた。そこへ横から三年生の担任の市川悟先生が、「おい、おまえたち、うるせえぞ! 起きたことは起きたことだ! ごちゃごちゃぬかすな! おまえたちはおまえたちの歌をしっかりと歌って、最高学年の矜持を見せろ、矜持を!」と諫めた。この市川先生は尾池賢一先生と同じく理科の担当で、時には数学も教えていたが、驚くべきことには観光ホテル明鏡閣の黒岩栄作支配人の従兄弟なのである。野球部を指導しているだけあって、中年ながら小柄な体はよく引き締まり、顔は浅黒く日焼けしていた。かけている眼鏡が薄黒いサングラスであったなら、あるいはサカエさんによく似ているかもしれなかった。この中学校で市川先生は、何かと損な役回りを引き受けることが多かったが、このときの合唱コンクールではまさにそうした目に遭った。三年生はステージに登って歌い始めたが、その演奏はまあ実にひどいものであった。あたかも猿山の猿たちが、それぞれ好き勝手に喚き叫んでいるかのようであった。悠太郎は愉快な思いで猿たちの叫喚に耳を傾けていたが、その歌詞はほとんど聞き取れなかった。「汽笛が」と歌っているのか「軌跡が」と歌っているのか分からなかったとき、これはどう見ても留夏子さんたちの勝ちだなと悠太郎は考えた。同じことを大岡越前こと剣持校長も考えた。三年生が発表を終えてステージから降りるとき、剣持校長は棚橋晶子先生に近づくと、「これはもう明らかに勝負ありましたな」と渋みのある低い声で言った。二年生によって様々に出し抜かれた棚橋先生は悔しかった。歌詞のプリントのことといい、タンバリンやトライアングルのことといい、あたかも森の葉隠れに得体の知れない何者かが潜んで暗躍していたかのようであった。しかし合唱の出来栄えの違いが歴然たるものであることを、自暴自棄の棚橋先生とて認めないわけにはゆかなかった。
休憩時間のあいだ、何人かの老人たちが剣持校長に近づいた。「素晴らしいものを聴かせてもらいました」と頬のこけたひょうたん顔の田茂喜三郎さんは言った。「流浪のなんとかは素晴らしかったねえ」とヨシノさんが、左目の下の傷跡に手をやりながら言い添えた。「夢に楽土を求めた。それはまさしく私たちのことでした」と小野屋ツギさんは銀歯を見せながら言った。「俺たちの苦しみが、これでなかったことになるわけじゃねえ。だが俺たちの苦しみは別の世界に置き移されて、別の世界の光に照らされたわけだ。この現実とは別の現実を音楽は見せてくれると、ある生徒に言われたことがありましてね。それはこういうことかと思い知りましたよ。今日この日まで生き延びた甲斐があったってもんですね」と、いくらか斜視気味の目を校長に当てながら佐藤今朝次さんは言った。剣持校長は重々しい態度で、「皆さんのご苦労が、あの子たちを育てたのです。私も校長として、あの子たちを誇りに思います」と言った。
そんな休憩時間のあいだ、タヌキ先生こと綿貫正先生は、思うところあって職員室にある自分の机に戻った。机の上には悠太郎から返却された『最新名曲解説全集』の声楽曲の巻が積んだままになっていた。綿貫先生はそのなかからシューマンのページを探した。すると果たしてそこには〈流浪の民〉の解説が載っていた。タンバリンとトライアングルを任意で加えてもよいという一文も見つかった。色眼鏡の奥で綿貫先生の目が光った。職員室を出たタヌキ先生は、廊下を通りかかった悠太郎を呼びとめ、「真壁くん。きみは俺から『最新名曲解説全集』を借りていたことがあったね。いったい何の曲を調べていたんだい?」と問うた。しかし悠太郎もさるもので、そんな場合に備えて答えをちゃんと用意していた。「シューベルトの歌曲について調べていました。とりわけ《美しき水車小屋の娘》と《冬の旅》と《白鳥の歌》の三大歌曲集について」と悠太郎は落ち着き払って答えた。すると綿貫先生はニヤリと笑って、内心こう考えた。「どうしてなかなか、きみはタヌキだ。きみは俺のことをタヌキだと思っているだろう。だがきみだって俺くらいの年になれば、今の俺以上に立派な古狸になるだろうよ」
さて休憩時間が終わり、剣持校長先生が渋みのある低い声で「えー、金賞は、えー、二年生」と結果を発表したとき、沸き起こる拍手のなかで二年生たちはしかし、喚声を上げることもなく躍り上がることもなく、ガッツポーズひとつ決めることもなく静かに居住まいを正していた。これは予め留夏子が、もし勝つことがあっても勝ち誇ってはならないと、みんなに言っておいたからであった。そうした態度を先生方も親たちも老人たちも立派だと感じた。千代次は珍しく相好を崩して手を打ちながら、「あの留夏子ちゅう娘は豪儀なもんだな」と言った。梅子はしかし喜色を満面に浮かべながら、何かを知っているぞと言わんばかりに、パンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしていた。陽奈子先生は娘の活躍を見届けた。合唱コンクールが終わった後で陽奈子先生は、スパルタ式の神川協子さんからも、富山訛りのイントネーションで喋る芹沢美智子さんからも、幸薄そうな諸星美雪さんからも、地母神のような戸井田アオイさんからも、彫りの深い愁いがちな顔の黒岩芙美子さんからも、留夏子のことで称讃された。しかし陽奈子先生はある種の戸惑いと淋しさを感じていた。娘が自分の与り知らないところでこれほどの快挙を成し遂げたことに、陽奈子先生は驚きもすれば戸惑いもしたのである。「私にもあんな年頃があった。あの子はこれからどんな人生を送るだろう」と陽奈子先生はしみじみと思った。秀子もまた陽奈子先生に言葉をかけはした。しかしわが子の競争相手として留夏子を厭わしく思う気持ちは、いかんともし難かった。そして沸き起こる拍手のなかで二年生たちが居住まいを正していたとき、三年生の中島猛夫が屈辱に身をふるわせながら「あのクソアマ、ぶっ殺す」と呟いたのを聞いた者は誰もいなかった。佐藤留夏子が指揮した〈流浪の民〉の名演は「めぐし乙女の勲し」として、なお数年のあいだ六里ヶ原とその近隣地域に語り伝えられた。
しばらく前から奇妙な兆候はあった。二ヶ月前の六月から、開拓団の団長や幹部や団員たちが百名近く、関東軍の現地要員として次々と召集された。農地に種を蒔くべき時期に、ごっそりと男手を奪われるのは、やはりただ事ではなかった。喜三郎さんとヨシノさんは、残った団員たちと励まし合いながら食糧増産に努めた。しかし八月も九日を過ぎると、恐れていたソ連参戦の噂が、現地人の口から口へと伝わるのが聞こえた。そして十五日、日本は敗れた。こうなったらもう満洲最北の地で孤立無援である。自分たちの身は自分たちで護るよりほかにない。団にある武器はといえば、小銃が三百丁、軽機関銃が二丁、追撃砲が一門、手榴弾が六百個であった。翌日団員たちは各集落から、これらの武器を持ち寄って団本部に集結した。ヨシノさんはほかの女や子供たちとともに、団本部の建物内に収容された。喜三郎さんは男たちとともに銃を持って土壁の内外を固め、昼夜を問わず暴徒の襲撃を警戒した。
ところが唯一頼みとするそれらの武器は、すべて没収されることになった。侵入してきて周辺をうろついていたソ連の軍隊が二十八日に至って、団が保有する武器の一切を差し出すよう命じたのである。ただでさえ多くの男手を取られ弱体化していた開拓団が、このうえ武器まで奪われてはまったくの無防備になってしまう。しかし日本は戦争に敗れたのである。敗戦国の民が反抗でもすれば、命はないものと思ってよかった。団員たちは皮でも剝がされるような思いで、すべての武器を大車九台に載せて現地人側に引き渡した。これでもはや団員たちには身を護るすべはなくなったわけであった。ところがその頃になると、どこそこで日本人開拓民が暴徒に襲われたという噂がしきりと伝えられ、団員たちの不安は募るばかりであった。
九月に入ると恐ろしいことが起こり始めた。満洲に長雨が降る月初めの頃、すぐ南隣の開拓団が暴徒の襲撃を受け、徹底的に痛めつけられたらしいのである。生き残った人々は、怪我人を肩に担いで海倫村に逃げ込んできた。村では棒切れを拾い集めて先端を尖らせ、急拵えの手槍を作っては見たものの、そんなもので暴徒を防ぎ切れるかと不安は募るばかりであった。連日連夜雨は降り続き、団の周辺は泥沼と化して身動きもならず、喜三郎さんもヨシノさんも息をひそめて生きた心地もしない日々を送っていた。ところが頼みの手槍さえ、持っていることは許されなかった。ソ連兵が五、六人でやって来ては屋内を物色し、金目のものを奪い、手槍を片端からへし折って、銃弾一発でも持っている者は銃殺だと言い捨ててゆくのであった。
そして九月十一日の早暁、団本部の展望台に備えつけてあったサイレンが鳴り響いたので、ヨシノさんも喜三郎さんも跳ね起きた。ふたりは急いで身支度をすると、ヨシノさんはかねて打ち合わせてあった通り女たちと窓を閉め固め、喜三郎さんは男たちとともに外へ飛び出した。ヨシノさんも喜三郎さんもわが目を疑った。本部南門のほうから、人・人・人・人・人――。その数一千人はいるかと思われる暴徒たちが、手に手に銃や槍を持ち、狂乱したような叫び声を上げながら、雲霞のごとく押し寄せてくるではないか! 匪襲だ! 匪襲だ! 匪襲だ!――そんな声が口から口へと瞬時に伝わった。団にはもう武器はなかった。急拵えの手槍もなかった。身を護るのに使えそうなものといえば、農作業用の鎌くらいしかなかった。そこへ暴徒たちは雨あられと銃弾を打ち込んだから、窓ガラスは粉微塵に砕け散り、団員たちは弾に当たって次々と倒れた。ヨシノさんの左目の下を銃弾がかすめていった。喜三郎さんも左肩を撃たれた。死者は三十名を超え、銃弾で蜂の巣にされた死骸があり、槍でめった刺しにされた死骸があった。
みんなは煉瓦造りの学校へ逃げ、なおも廊下に米俵を積んでそれを境に敵と戦ったが、銃弾によって開けられた穴から米粒がさらさらとこぼれ、ついには降参のやむなきに至って白旗を上げた。みんなは現地人たちによって引き出され、雨が降る庭の泥濘のなかに座らされ、衣服を脱がされて裸にされ……。衣服も金銭も建具も敷物も、現地人たちは何台もの大車に満載して、きれいさっぱり持ち去ってしまった。喜三郎さんもヨシノさんも、裸の背に冷たい雨を受けていた。死んだ者たちの服を脱がせて身に着けた頃には、はや日も暮れようとしていた。翌十二日の夜明け、ヨシノさんも喜三郎さんもみんなを手伝って、死んだ者たちを本部の建物のなかに横たえた。火をかけられた建物は、たちまち炎上して遺体を荼毘に付した。それから大車九台に負傷者や子供を載せ、みんなは一路海北の駅を目指した。五族協和の王道楽土を建設せんと理想に燃えた約七年の、それは無残な結末であった。祖国へ帰る唯一の活路たる海北駅は、三十キロの彼方であった。その道々にも暴徒は現れ、わずかに身に着けているものまでも奪っていった。海北駅に着いたのが夕刻で、それからは無蓋貨車の荷物となり、雨風を身に受けながら揺られ揺られて長春を目指した。引揚収容所に入っての生活は困苦を極めた。栄養失調と疫病のために死ぬ者は百名を超えた。みんながようやく葫蘆島から出た引揚船で佐世保港に帰れたのは、敗戦の翌年の九月であった。
それに比べれば佐藤今朝次さんの属していた開拓団の脱出は、悲惨ではあったがまだしも犠牲の少ないものであった。比較的遅くに発足したその開拓団が、畑地いっぱい豊かに実る大豆やトウモロコシに加え、郷里の牧場からジャージー牛を取り寄せて酪農にも乗り出したその矢先、敗戦の悲報は突如として一同を襲ったのである。それは八月二十日になってからのことであった。その日開拓団国民学校の校長は、職員の給料を受領しようと、中心街の満拓公社へ出向いた。ところがその途中で校長は、現地の公安局に拘禁されたのである。そこで校長は恐るべき話を聞かされた。日本は敗戦した。日本関係筋の機関や団体はすべて自発的に武装解除し、武器弾薬を公安局に提出した。しかるに貴殿らの開拓団はいまだに武装を解いていない。かくなるうえは即刻包囲してこれを殲滅する――。寝耳に水の話に校長は戦慄した。言われてみれば十日頃から開拓地の上空を、見慣れない飛行機が飛んでいたが、あれはソ連参戦の前触れだったのだと校長は気づいた。彼は公安局の釈放を得て団に走り戻り、一切を団長に知らせた。団長の決断は素早かった。小銃も機関銃も手榴弾も、その日のうちに洗いざらい公安局に提出した。
それでも九月に入る頃に、報国農場は襲撃を受けた。夜陰に乗じた十数名の暴徒たちは、草かきを改造した槍や草刈り鎌を手に来襲し、たまたま居合わせた場長をめった打ちにして半殺しの目に遭わせた。そうしたことがあってから、開拓団は警戒を強めた。暴徒が残していった武器を真似て草かきを改造し、槍を作って武装した。暴徒の襲撃は繰り返され、敵の数は四百人にも五百人にものぼることがあった。今朝次さんは急拵えの槍を手にした少年たちをまとめて、日ごと警備に当たった。日暮れになると遠い稜線の彼方から、オーイ、オーイと喚声に似た声が聞こえた。敵襲かと殺気立ち身構えて耳を澄ませば、それは狼が仲間と呼び交わす声であった。団長の判断によって無闇と彷徨しないことに決め、敗戦から一年後に帰国命令が出るまで現地に留まった団員たちは、六百名のうち三十名ばかりを死なせただけで、残りの大半は無事に博多港へ帰り着くことができたとはいえ、孤立無援で敵襲を防ぎ続けた引き揚げまでの日々は、やはり生きた心地もしないものであった。
小野屋ツギさんは女子高等師範学校時代に、〈流浪の民〉を女声合唱で歌ったことがあった。本当だ、私たちは楽土を求めたね。まずは大陸に、次にはこの六里ヶ原に――。ツギさんが属していた開拓団もまた、敗戦とともに潰滅した。八月二十日に村を脱出して以来、一年以上にわたった満洲での逃避行では、暴徒の襲撃と病によって夥しい犠牲者が出た。思い起こせば血と雨と泥ばかりであった。命からがら故郷に帰れたのは、翌年の九月であった。大陸に王道楽土を建設するという理想は潰えたが、帰還した者たちにとっては、焦土と化した祖国の土を拓くほかに再起の道はなかった。入植先として選ばれた六里ヶ原は、みんなが一度は骨を埋めようと決意した満洲の地に似ていた。みんなは開墾地に生い茂る唐松を伐り倒して柱とし、刈り取ったクマザサを屋根や壁として家を作った。夜ともなれば屋根の笹の葉の隙間から、冴え冴えと星の光が見えた。みんなと一緒にツギさんも、来る日も来る日も樹を伐り、切り株を取り除き、土を掘り起こして開墾した。そうして作られた畑に初めて粟が実ったとき、「はあ死なねえのう」と大屋原集落のある男性が言ったことを、ツギさんは昨日のことのように憶えていた。私の一生が楽土ということにつきまとわれようとは、師範学校時代には夢にも思わなかったねえ。楽土を求めるのは、夢のなかだけにしておけばよかったねえ。しょっぱい海を渡って満洲へなんか行ったのは、間違いだったのかもしれないねえ。私たちの開拓団では、現地の人たちに開墾させた畑で、大豆やトウモロコシを作っていた。私たちはあの人たちを匪賊なんて言ったけど、果たしてどちらが匪賊だったのか分からない。私たちはあの人たちから屯匪と呼ばれるようなことをやっていた。その報いを受けたのかねえ。私たちが受けた苦しみも、私たちが与えた苦しみも、時が経とうが消えはしないねえ――。
老人たちの脳裏にそんな思いが去来するあいだに、音楽は冒頭を再現させていた。ペトラがアウフタクトに始まる二音の律動を提示するあいだ、留夏子はまたスカートの裾をふわりと翻し、ポニーテールをぴょこりと弾ませながら素早く半回転して合唱のほうを向いた。
■■■■■■■
と弱音で囁くように歌い始める合唱を、留夏子は小さな手振りで指揮した。「しかし今東に朝が目醒めると」という原詩の大意の通り、ざわめく森のなかで夢から醒める人々のように動き出した合唱は、
■■■■■■■■
でいよいよ現実に戻るかのようにクレッシェンドした。「夜の美しい姿は消え失せ」というのが原詩の大意であるから、ここはほとんど直訳といってよかった。Gebildeという単語が表すのは、夜の夢が産出する様々な姿形であろうというのが、ドイツ語の辞書を引いた悠太郎の理解であったし、留夏子もペトラも二年生のみんなも、その理解を共有していた。
■■■■■■■■■■
と合唱が歌うところは、「一日の始まりに騾馬は声高く鳴く」という原詩の大意に相応しい活気を秘めて歌われ、
■■■■■■■■■
では、ついに旅立つ流浪の民の活動開始を表して、クレッシェンドしデクレッシェンドした。「人影は先へと進む――どこへ行くのか誰がおまえに教えてくれよう?」という原詩を的確に表した訳詞であった。流浪の民が示されるときに伴奏に出た運動的な動機が、合唱が歌わないあいだにまた現れたから、ペトラはツインテールの髪を躍らせながら、オクターヴの上行が特徴的なその動機に巧みなアクセントをつけた。
■■■■■■■■■
と合唱は弱音からクレッシェンドして盛り上がった。最後には振幅の大きな留夏子の指揮につれて、
■■■■■■■■■ ■■■■
とピアニシモからフォルティシモまで大きく盛り上がり、崩れ落ちるようなピアノの後奏と、遠ざかりゆく人影を見送るようなアルペジオが鳴らされた。
ホ短調の主音を根音に持たないアルペジオが寄る辺なさそうに鳴らされ、その響きが消えた後しばらくは体育館は静寂に包まれていた。両手を軽く握って演奏を止めていた留夏子が、その姿勢を解いて指揮台から降りると、割れんばかりの拍手喝采が沸き起こった。老人たちのなかには半ば椅子から立ち上がり、目に涙を溜めて拍手を送る人もいた。ピアノの椅子を立ったペトラとともに、留夏子は聴衆に一礼すると、その切れ長の目で悠太郎の視線を捉えた。「真壁、どう? 見てくれた? 聴いてくれた?」と留夏子は頬を紅潮させ、わずかに肩で息をしながら悠太郎に視線で問うた。「留夏子さん、見ました。聴きました。お見事でした」と悠太郎は頷きながら視線で答えた。
それからはもう大変なことが起こった。二年生たちの合唱のあまりの見事さに、三年生たちは動揺し、驚き呆れ、浮き足立って軽挙妄動した。髪の生え際に鬼の角のような剃り込みを入れたあの男子は、「おい何だあの鳴り物は。ふざけんじゃねえぞ!」とかすれたような声で言った。中島猛夫は鼻の穴を膨らませて粗野な声で、「指揮者が声を出していいのかよ。なめてんじゃねえぞ!」と喚き散らし、眉間に皺を寄せて産毛だらけの猿めいた顔を歪め、中指を突き上げた。そこへ横から三年生の担任の市川悟先生が、「おい、おまえたち、うるせえぞ! 起きたことは起きたことだ! ごちゃごちゃぬかすな! おまえたちはおまえたちの歌をしっかりと歌って、最高学年の矜持を見せろ、矜持を!」と諫めた。この市川先生は尾池賢一先生と同じく理科の担当で、時には数学も教えていたが、驚くべきことには観光ホテル明鏡閣の黒岩栄作支配人の従兄弟なのである。野球部を指導しているだけあって、中年ながら小柄な体はよく引き締まり、顔は浅黒く日焼けしていた。かけている眼鏡が薄黒いサングラスであったなら、あるいはサカエさんによく似ているかもしれなかった。この中学校で市川先生は、何かと損な役回りを引き受けることが多かったが、このときの合唱コンクールではまさにそうした目に遭った。三年生はステージに登って歌い始めたが、その演奏はまあ実にひどいものであった。あたかも猿山の猿たちが、それぞれ好き勝手に喚き叫んでいるかのようであった。悠太郎は愉快な思いで猿たちの叫喚に耳を傾けていたが、その歌詞はほとんど聞き取れなかった。「汽笛が」と歌っているのか「軌跡が」と歌っているのか分からなかったとき、これはどう見ても留夏子さんたちの勝ちだなと悠太郎は考えた。同じことを大岡越前こと剣持校長も考えた。三年生が発表を終えてステージから降りるとき、剣持校長は棚橋晶子先生に近づくと、「これはもう明らかに勝負ありましたな」と渋みのある低い声で言った。二年生によって様々に出し抜かれた棚橋先生は悔しかった。歌詞のプリントのことといい、タンバリンやトライアングルのことといい、あたかも森の葉隠れに得体の知れない何者かが潜んで暗躍していたかのようであった。しかし合唱の出来栄えの違いが歴然たるものであることを、自暴自棄の棚橋先生とて認めないわけにはゆかなかった。
休憩時間のあいだ、何人かの老人たちが剣持校長に近づいた。「素晴らしいものを聴かせてもらいました」と頬のこけたひょうたん顔の田茂喜三郎さんは言った。「流浪のなんとかは素晴らしかったねえ」とヨシノさんが、左目の下の傷跡に手をやりながら言い添えた。「夢に楽土を求めた。それはまさしく私たちのことでした」と小野屋ツギさんは銀歯を見せながら言った。「俺たちの苦しみが、これでなかったことになるわけじゃねえ。だが俺たちの苦しみは別の世界に置き移されて、別の世界の光に照らされたわけだ。この現実とは別の現実を音楽は見せてくれると、ある生徒に言われたことがありましてね。それはこういうことかと思い知りましたよ。今日この日まで生き延びた甲斐があったってもんですね」と、いくらか斜視気味の目を校長に当てながら佐藤今朝次さんは言った。剣持校長は重々しい態度で、「皆さんのご苦労が、あの子たちを育てたのです。私も校長として、あの子たちを誇りに思います」と言った。
そんな休憩時間のあいだ、タヌキ先生こと綿貫正先生は、思うところあって職員室にある自分の机に戻った。机の上には悠太郎から返却された『最新名曲解説全集』の声楽曲の巻が積んだままになっていた。綿貫先生はそのなかからシューマンのページを探した。すると果たしてそこには〈流浪の民〉の解説が載っていた。タンバリンとトライアングルを任意で加えてもよいという一文も見つかった。色眼鏡の奥で綿貫先生の目が光った。職員室を出たタヌキ先生は、廊下を通りかかった悠太郎を呼びとめ、「真壁くん。きみは俺から『最新名曲解説全集』を借りていたことがあったね。いったい何の曲を調べていたんだい?」と問うた。しかし悠太郎もさるもので、そんな場合に備えて答えをちゃんと用意していた。「シューベルトの歌曲について調べていました。とりわけ《美しき水車小屋の娘》と《冬の旅》と《白鳥の歌》の三大歌曲集について」と悠太郎は落ち着き払って答えた。すると綿貫先生はニヤリと笑って、内心こう考えた。「どうしてなかなか、きみはタヌキだ。きみは俺のことをタヌキだと思っているだろう。だがきみだって俺くらいの年になれば、今の俺以上に立派な古狸になるだろうよ」
さて休憩時間が終わり、剣持校長先生が渋みのある低い声で「えー、金賞は、えー、二年生」と結果を発表したとき、沸き起こる拍手のなかで二年生たちはしかし、喚声を上げることもなく躍り上がることもなく、ガッツポーズひとつ決めることもなく静かに居住まいを正していた。これは予め留夏子が、もし勝つことがあっても勝ち誇ってはならないと、みんなに言っておいたからであった。そうした態度を先生方も親たちも老人たちも立派だと感じた。千代次は珍しく相好を崩して手を打ちながら、「あの留夏子ちゅう娘は豪儀なもんだな」と言った。梅子はしかし喜色を満面に浮かべながら、何かを知っているぞと言わんばかりに、パンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしていた。陽奈子先生は娘の活躍を見届けた。合唱コンクールが終わった後で陽奈子先生は、スパルタ式の神川協子さんからも、富山訛りのイントネーションで喋る芹沢美智子さんからも、幸薄そうな諸星美雪さんからも、地母神のような戸井田アオイさんからも、彫りの深い愁いがちな顔の黒岩芙美子さんからも、留夏子のことで称讃された。しかし陽奈子先生はある種の戸惑いと淋しさを感じていた。娘が自分の与り知らないところでこれほどの快挙を成し遂げたことに、陽奈子先生は驚きもすれば戸惑いもしたのである。「私にもあんな年頃があった。あの子はこれからどんな人生を送るだろう」と陽奈子先生はしみじみと思った。秀子もまた陽奈子先生に言葉をかけはした。しかしわが子の競争相手として留夏子を厭わしく思う気持ちは、いかんともし難かった。そして沸き起こる拍手のなかで二年生たちが居住まいを正していたとき、三年生の中島猛夫が屈辱に身をふるわせながら「あのクソアマ、ぶっ殺す」と呟いたのを聞いた者は誰もいなかった。佐藤留夏子が指揮した〈流浪の民〉の名演は「めぐし乙女の勲し」として、なお数年のあいだ六里ヶ原とその近隣地域に語り伝えられた。
0
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
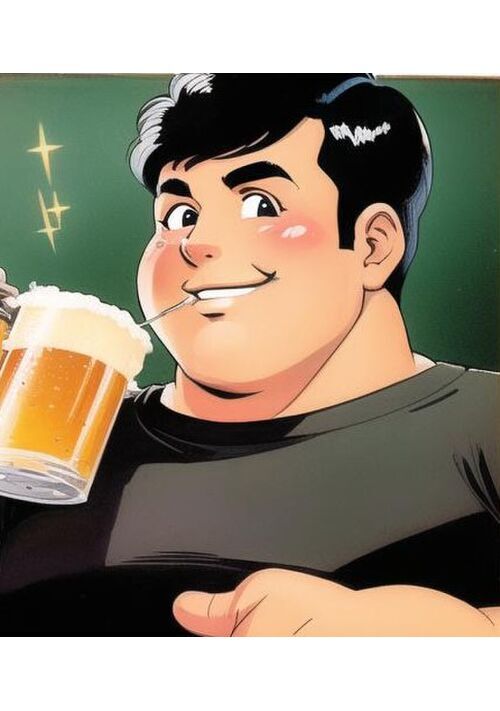
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















