45 / 73
第十五章 筆記体
三
しおりを挟む
さて水仙が花咲くゴールデンウィークの湖畔は、久し振りの輝かしい賑わいを取り戻していた。湖を一周する一キロの遊歩道は平らに整地され、スタート地点からの距離を示すポールが百メートルごとに立てられていた。その遊歩道をランニングコースとして緑萌える樹々の枝の下を、ランナーたちが薫る風を切って走っていた。ゆっくりと散策を楽しむ人々を、ランナーが追い抜いてゆく様はどこか異様であった。湖とランニングコースのあいだに、ガードレールは設けられていなかった。いつか事故でも起こりはしないかと日曜日の朝、悠太郎は千代次に懸念を表明した。千代次は眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、「そうさな、それも心配といえば心配だ」と言った。「しかしなあ、そもそもの話として、照月湖でタイムを計るとは」と千代次は続けた。「いや、サカエくんや明鏡閣のみんなの思いつきを、悪く言うつもりはねえ。現にまたこうして湖畔は賑やかになっているんだからな。秀子の話じゃあ弓道場も大好評で、袴姿の連中が大勢弓を執っているちゅうじゃねえか。この不景気な世のなかで、みんな実によくやっている。だが照月湖でタイムを計るちゅうのは、どういうものかな。時代かのう。熊川の水と照月湖の水を見て、昔俺は考えたもんだよ。水が流れるように、時も流れてゆく。時を留めるちゅうことが、大昔からの人間の夢だったんじゃねえか。中国の古い詩のなかにはのう、そういう文句があるだよ。夜が来て朝が来て、また夜が来てまた朝が来て、時は留めることができねえちゅう意味さ。とどむちゅう字は、お茶を淹れるちゅう字と同じだから、水を溜めるイメージに繋がるんべえ。熊川が勢いよく活動する水なら、照月湖は安らぐ水よ。この湖は誰にとっても安らぎの場であるはずだった。そして月も日もここで安らぐはずだった。人は時を留めることができねえまでも、せめて湖畔で時を忘れてほしかった。ところが今では、スピードアップを目指すランナーたちが湖畔を走っている。一分一秒でも縮めようとタイムを計っている。これも時代かのう……。そうだユウ、おめえガーデンへ行ってこお。今日のお昼はガーデンで食って、新しい店主に挨拶してこお。そうしてこれで払ってこお」そう言って千代次は悠太郎に千円札を渡した。
それで悠太郎は、浅緑に若葉し始めた林間の道を歩んで、湖の向こうの正面に近々と迫る鷹繋山を眺めながら、急な坂道を降りていった。インド・ネパール料理店として生まれ変わったレストラン照月湖ポカラ・ガーデンは、魔を祓い福を招くブッダ・アイの装飾と、エキゾティックなインド音楽と、薬草を混ぜ合わせたような不思議なお香の匂いで悠太郎を迎えた。「イラッサイマッセ」と片言の日本語で店員の青年が呼びかけた。その際に彼は冒頭の「イ」の音を前倒しにして発音したので、悠太郎はそれをアウフタクトのようだと感じた。頬骨が張った顔をした小麦色の肌のその青年は、一重瞼の大きな目を怯えたように泳がせていた。湖に面した窓に近い席に案内された悠太郎は、賑わう店内を見渡すとランチセットを注文しがてら、「店主の登原さんにご挨拶したいのですが。私は真壁と申します」と青年に言ったが、どうやら日本語があまり通じないらしく要領を得なかった。そこで悠太郎は同じことを英語で言ってみた。中学校では習い始めたばかりとはいえ、幼い頃から学ばされてきた英語で、悠太郎にはそれくらいのことが言えたのである。果たして用件は通じたらしく、青年は厨房へと引っ込んでいった。
「これはこれは、真壁永久名誉顧問のお孫さんですか。ようこそいらっしゃいました。私が店主の登原聖司です」と地を這うような声で言いながら歩み寄ってきたのは、小柄ながら筋肉質の体を料理人の白衣に包んだ中年の男であった。登原さんは猛禽のような目で値踏みするように悠太郎を見ると、白い和帽子を脱いでオールバックにセットした頭を下げた。悠太郎も椅子から立ち上がって一礼し、「この度は開店おめでとうございます」と言った。「ありがとうございます。まあまあ、お座りください。まずはご紹介しておきましょう。今あそこのソフトクリームのカウンターにいるのが、手島妙子です」と登原さんが伸ばした手で示しながら言うと、ソフトクリームのコーナーから腫れぼったい顔をした色白の女性が、奇妙にゆっくりした動作でお辞儀をした。手島さんは腰まで届きそうな長い髪を横結びにしてひとつに束ねていたから、色白の肌や奇妙にゆっくりした動作と相俟って、その風貌にはどこか幽霊じみたところがあった。「それから先程のネパール人青年が、チャンドラカルナ・ムリ・ギリです。カトマンズの私の店で働き始めたのを連れてきたのですな。おっと、話が先走りました。私はネパールの首都カトマンズでレストランをやっています。温泉つきの日本料理店です。カトマンズは賑やかな都会ですが実に埃っぽい。車が水牛の群れのように道路を走っていますから、渡ろうにも渡れないほどですよ。まあそんなごみごみした都会の埃を温泉で洗い流して、日本料理を楽しんでゆこうというお客様は少なくない。ちなみに向こうでは温泉に入るときにも全裸にはなりません。水着を着ていただきます。とにかくそんなこんなで私の店は結構繁盛しております。しかし四月ともなれば春霞でヒマラヤが見えにくくなりますし、スコールも多くなる。六月ともなれば雨季が始まる。そうなれば観光客は減りますから店は暇になります。オフシーズンの商売は、もっとほかにやりようがあると考えていました。そこへ浅間観光から私にお話があったのです。主にネパールが雨季のあいだ日本へ来て、この六里ヶ原で店をやらないかとね。私はもともと工業新聞社に勤めていた人間ですから、そういう話が舞い込んだのですな。ところで真壁さん、いかがですか、このお店は」
「物心ついた頃からこのガーデンを存じておりましたが、変われば変わるものですね。コンセプトと申しますか、世界観がこれまでとは全然違います」と悠太郎が答えると、登原さんはわが意を得たりとばかり「そうです、世界観ですよ、コンセプトですよ、これまでのガーデンに欠落していたのは! いやはやさすがは永久名誉顧問のお孫さんだ。まだお若いのによく分かっていらっしゃる。まったく前任者ときたら、世界観以前の問題ですよ。掃除すらまともにできていなかったのですからな。開店準備のために来てみれば、まあなんと汚い汚い! 大きな声では言えませんが、黒い汚れが床にこびりついて、どうしても落ちない。こうなったら最後の手段ですよ。どうしたと思います? 石油を撒きましたよ! 石油を床にぶちまけて磨いたのですよ!」と上機嫌で苦労話を披露した。「ところでポカラというのはどういう意味ですか?」と悠太郎が問うと、「よくぞ訊いてくれました。それこそ世界観に関わる問題なのです。ポカラというのは地名です。首都カトマンズから西へ二百キロのところに位置するポカラは、ネパール第二の観光都市です。市内のどこからでも、ヒマラヤの連峰を仰ぎ見ることができます。当店にも写真を飾っておりますが(と言いながら登原さんは壁に飾られたパノラマ写真を指さした)、左からダウラギリ、アンナプルナ南峰、アンナプルナⅠ、右からマナスル、アンナプルナⅡ、アンナプルナⅣ、アンナプルナⅢ、そして真ん中の尖った山が霊峰マチャプチャレ。マチャプチャレというのは、魚の尾という意味だそうですよ。言われてみればそう見えなくもありませんな。そして神々の座と呼ばれるヒマラヤの名峰を、満々と水を湛えたフェワ湖の水が映しているわけです。もうお分かりですな? 浅間隠の連山や鷹繋山や浅間山に囲まれたこの照月湖のほとりを、ポカラになぞらえたわけですよ」と登原さんは上機嫌で答えた。「もちろんいくら景色が美しくたって、料理がまずければ食い物屋は駄目です。しかし開店早々嬉しい事件が起こりましたよ」と登原さんは続けた。「インド人のお客様が来店されたのです。宝石商をしているという男性で、いかにもマハラジャといった感じのカイゼルひげを生やし、手にはサファイアの指環を嵌めていました。さてそのお客様は食事を終えると、チャンドラカルナを呼んで言うのです。店主を出せと。呼ばれて私は出てきました。お客様は言います。〈なんというものをあなたは私に食べさせたのか〉と。私はお叱りを覚悟して、〈お口に合いませんでしたか?〉とこう申しました。するとお客様は言うのです。〈なんというものをあなたは私に食べさせたのか。こんなおいしいカレーは生まれて初めて食べた。ついてはレシピを教えてほしい。企業秘密だというなら、ヒントだけでもいいから〉というわけですよ。私は嬉しくて、スパイスの使い方などいくらか教えてあげました。インド人をカレーで感激させたのですからな。これは私の食い物屋人生のなかでも、忘れ難い思い出になりそうですよ。おお、そうこうするうちに、チャンドラが食事を運んできました。ではどうぞ、ごゆっくりお召し上がりください」
真鍮のプレートに盛られたランチセットがテーブルに置かれた。野菜カレーと豆カレーとマトンカレーの手前には大きなナンがあった。ほうれん草の炒め物とタンドリーチキンも一緒についていた。それらを載せたワンプレートのほかには、ラッシーと呼ばれる白いヨーグルト飲料のグラスも置かれた。悠太郎はまずスプーンで三種類のカレーをそれぞれ味わってみた。想像していたほど辛いわけではなかったが、深く謎めいた味と香りに体の奥まで温まるような感じがした。それから感謝しつつ手でナンを裂いてカレーに浸し、口へ運んだ。バターの香りがする柔らかな食感のナンにカレーの味が融け合い、こんなおいしいものは食べたことがないと思えるほどおいしかった。よく煮込まれた野菜や羊肉をフォークで口へ運び、口直しに爽やかな甘さのラッシーをストローから飲んでは、またカレーに浸したナンを食べ、あるいはニンニクが効いたスパイシーなほうれん草の炒め物や、見るからに辛そうな赤いタンドリーチキンを味わった。窓から眺める湖はきらめき揺らめきながら、手漕ぎボートやスワンボートを浮かべていた。プレートに盛られたこの料理が食べ尽くされるように、夢のような美しい時間もまた終わってしまうのだと思うと、悠太郎の胸には切ないような哀惜の念が溢れた。忘れまい、俺はけっして忘れまい。この店のことを、この料理の味を、この湖畔で起こったことのすべてを、俺はいつまでもけっして忘れまい――。涙を堪えながらそんなことを思いつつ、悠太郎は食事を終えた。
伝票を持ってレジへ行き、卓上ベルを鳴らすとチャンドラさんが現れた。悠太郎は千代次から渡された千円札を財布から出した。ところがチャンドラさんは拒否するような身振りをした。不審に思った悠太郎が伝票と千円札を代わる代わる指し示すと、チャンドラさんは「いただけません」と片言の日本語で言った。「なぜですか?」と悠太郎が日本語と英語で問うと、チャンドラさんは英語で「店主の意向です」と言った。その意味を理解した悠太郎は、恥ずかしさと怒りのあまり顔を赤くした。今しがた食べた料理の唐辛子やスパイスが、体の奥でもう一度燃え上がったかのようであった。「冗談ではありません、ミスター・チャンドラカルナ・ムリ・ギリ。お代を受け取らないとは、あまりにもひどいではありませんか。あなたがたは素晴らしいこのお店で、素晴らしい料理を食べさせてくださった。私はそのことに大変感謝しています。それなのにお代を受け取らないとは、いったいどういうおつもりですか? あなたが答えられないなら、ミスター・トバラに訊いてください。私が真壁千代次の孫だからですか? 私は祖父の地位を利用して、このお店にただ飯を食べに来るような人間ではありません。私のことをそういう人間だと思ったのかと、ミスター・トバラに訊いてください。お代はどうあっても受け取っていただきます。もしどうしても受け取らないと仰言るなら、もう二度とこのお店には来ません。ほかの人たちにこのお店を薦めることもしません。ミスター・トバラにそう伝えてください」と悠太郎は日本語混じりの英語と英語混じりの日本語でまくし立てたが、「どうしても受け取らないと仰言るなら」というところでは、金子先生に教わった「拒絶のwill」を早速使うことができた。怒気を含んだ悠太郎の剣幕に、チャンドラさんは一重瞼の大きな目を怯えたように泳がせながら厨房へ引っ込んでいった。ややあって再び出てきたチャンドラさんは、何事もなかったかのように「九百二十円です」と言って、千円札を受け取り釣銭を返した。いたたまれなくなった悠太郎は、「ごちそうさまでした」と言って逃げるように店を出た。
急な坂道を登り切った悠太郎は、改めてレストラン照月湖ポカラ・ガーデンを見下ろした。店主の地を這うような声や、値踏みするような目が思い出された。「登原さんは俺を試したのだろうか。試したとすれば、何を試したのだろう。英語力だろうか、それとも人格だろうか」と悠太郎は考えた。後のほうを考えたとき、悠太郎の背筋を冷たいものが走った。危うく俺はなんという過ちを犯すところだったのだろう!――「食えない男が食い物屋とは……。いや、ひょっとしてみんなぐるだったのではないか。俺がチャンドラさんに必死で思いを伝えようとしていたとき、手島さんとかいうあの幽霊女は助けに来ようともしなかったではないか。予め三人で申し合わせて、ひと芝居打ったのではないか。いや、ひょっとしたら祖父もその一味かもしれない。あの三人は祖父に言われて、こんな茶番をやったのかもしれない。この六里ヶ原にいる限り、俺はいつまでも真壁千代次の孫であることから自由になれない。他人から見れば、そんなことは贅沢な悩みなのだろう。だが俺にとっては本当につらいことだ。いつかこの地を離れたなら、俺はこんな思いをせずに済むようになるだろうか。ああ、若葉するの樹々の枝に夏鳥たちが歌っている。今年もまた夏へと向かってゆく。俺はこの六里ヶ原で、こうしてひとつまたひとつと季節を積み重ねてきた。その終わりはいったいどういうことになるのだろう。俺は季節の階段を昇って、どこへ行くのだろう……」
悠太郎が家に帰ると千代次が居間で、極度に細い近視の目をしばたたきながらテレビを観ていた。「ガーデンはどんな具合だった?」と祖父は孫の顔を見ずに問うた。「とても賑わっていました。これまでのガーデンにはなかった新しい異国情緒がありました。料理もおいしかったです」と孫は、どんな具合か知りたいなら自分で行けばいいのにと思いながら答えた。「そうかそうか。ネパール人とも話ができたか?」と祖父が問うたので、やはり仕組まれていたのかと思いながら孫は「はい」と短く答えた。「英語でか?」となおも祖父が問うたので、「英語も使いました」と孫は答えた。「そうかそうか。話すほうはなかなかできると見えるな」と祖父は初めて孫と目を合わせた。あたかも悠太郎が試練を切り抜けたことを意外に思ってでもいるかのように、千代次の顔には嘲るような笑いが浮かんでいた。「俺は若い頃もっと英語を勉強したかった。だが戦争が始まって、鬼畜米英ということになった。英語は敵性語と見なされたから、勉強を続けるわけにはいかなかった。あのとき日本人が敵を知るために英語の勉強を一生懸命やっていりゃあ、あるいは戦争に負けなかったかもしれねえ。そう思うと残念でならねえよ。ユウ、おめえは俺の分まで一生懸命英語を勉強しなけりゃあならねえぞ」と語った千代次は、「話すほうはまあいいとしよう。それで書くほうはどうだ? はあ筆記体が書けるんべえな?」と問うた。悠太郎は隙を衝かれた人のようにたじろぎながら、「筆記体で書くことは、学校では教わりません。教科書に載ってはいますが、先生も生徒もブロック体で書きます」と睫毛の長い目を伏せながら返答した。ここぞとばかりに千代次は怒りを爆発させた。「何だと! 筆記体が書けねえだと! 俺の孫が中学生にもなって、筆記体も書けねえちゅうのか! 先生が教えねえったって、まわりの馬鹿奴等が使わねえったって、それがおめえの書けねえ理由になるか! まわりの奴等がどうであれ、おめえだけは書けなくてどうする! すぐに筆記体の練習を始めろ!」と千代次は泡を吹き、よだれを垂らしながら孫を怒鳴りつけた。
部屋で学習机に向かった悠太郎は、がっくりとうなだれて頭を抱えた。まだ小文字のbとdの区別もできない同級生がいるのに、なぜ自分にばかり高い要求が課せられるのか分からなかった。こうやって祖父はあの手この手で俺を苦しめるのだと悠太郎は考えた。母子ともども経済的に庇護されていて逆らえないのをいいことに、ありとあらゆる手段を尽くして俺を苦しめ続けるとは、なんという念の入った虐待だろう――。だが悠太郎は言いなりになるよりほかに仕方がなかった。誰より速く走れというのは無理な要求であったが、英語の筆記体ならば習得できないものでもなかった。ふと思い立って悠太郎は、いつか正子伯母様から誕生日プレゼントにもらった《マカベウスのユダ》のCDを棚から取り出した。その箱には黒地に白いアルファベットで作曲家と作品名と演奏家が記され、楕円の枠のなかに勇ましい戦士の姿が描かれていた。黒い馬に跨ったその戦士は左手を天に挙げ、右手では戦斧を振るい、腰には幅広の剣を提げていた。解説と歌詞が記されたブックレットを箱から出した悠太郎は、英語の歌詞を冒頭からノートに筆記体で書き写し始めた。アルファベット別に見て記憶していた筆記体ではあったが、実際に文字と文字を繋げるのは難しかった。不器用な綴り方で悠太郎は、マタティアの死を悼む合唱の歌詞を綴っていった。「俺がこうして苦しんでいるのも、誰かが下手な筆記体で書き綴っているオラトリオの台本通りなのかもしれない」という考えが脳裏に浮かんだ。やがて悠太郎の好きな祭司シモンの言葉が出てきた。
この悲嘆の嵐のすべては無駄ではない
それからしばらくすると、イスラエルの女のアリアがあった。
おお自由よ 汝こよなき宝よ
そしてついに凱旋の勇者ユダを迎える合唱が、
見よ 勝利の勇者がやって来る!
トランペットを吹き鳴らせ 太鼓を打ち鳴らせ
祝祭の支度をせよ 月桂冠を持ってこい
勝利の歌を彼にうたえ
と歌うところに来ると、悠太郎の目から大粒の涙がノートの上にぼたぼたと落ちた。
それで悠太郎は、浅緑に若葉し始めた林間の道を歩んで、湖の向こうの正面に近々と迫る鷹繋山を眺めながら、急な坂道を降りていった。インド・ネパール料理店として生まれ変わったレストラン照月湖ポカラ・ガーデンは、魔を祓い福を招くブッダ・アイの装飾と、エキゾティックなインド音楽と、薬草を混ぜ合わせたような不思議なお香の匂いで悠太郎を迎えた。「イラッサイマッセ」と片言の日本語で店員の青年が呼びかけた。その際に彼は冒頭の「イ」の音を前倒しにして発音したので、悠太郎はそれをアウフタクトのようだと感じた。頬骨が張った顔をした小麦色の肌のその青年は、一重瞼の大きな目を怯えたように泳がせていた。湖に面した窓に近い席に案内された悠太郎は、賑わう店内を見渡すとランチセットを注文しがてら、「店主の登原さんにご挨拶したいのですが。私は真壁と申します」と青年に言ったが、どうやら日本語があまり通じないらしく要領を得なかった。そこで悠太郎は同じことを英語で言ってみた。中学校では習い始めたばかりとはいえ、幼い頃から学ばされてきた英語で、悠太郎にはそれくらいのことが言えたのである。果たして用件は通じたらしく、青年は厨房へと引っ込んでいった。
「これはこれは、真壁永久名誉顧問のお孫さんですか。ようこそいらっしゃいました。私が店主の登原聖司です」と地を這うような声で言いながら歩み寄ってきたのは、小柄ながら筋肉質の体を料理人の白衣に包んだ中年の男であった。登原さんは猛禽のような目で値踏みするように悠太郎を見ると、白い和帽子を脱いでオールバックにセットした頭を下げた。悠太郎も椅子から立ち上がって一礼し、「この度は開店おめでとうございます」と言った。「ありがとうございます。まあまあ、お座りください。まずはご紹介しておきましょう。今あそこのソフトクリームのカウンターにいるのが、手島妙子です」と登原さんが伸ばした手で示しながら言うと、ソフトクリームのコーナーから腫れぼったい顔をした色白の女性が、奇妙にゆっくりした動作でお辞儀をした。手島さんは腰まで届きそうな長い髪を横結びにしてひとつに束ねていたから、色白の肌や奇妙にゆっくりした動作と相俟って、その風貌にはどこか幽霊じみたところがあった。「それから先程のネパール人青年が、チャンドラカルナ・ムリ・ギリです。カトマンズの私の店で働き始めたのを連れてきたのですな。おっと、話が先走りました。私はネパールの首都カトマンズでレストランをやっています。温泉つきの日本料理店です。カトマンズは賑やかな都会ですが実に埃っぽい。車が水牛の群れのように道路を走っていますから、渡ろうにも渡れないほどですよ。まあそんなごみごみした都会の埃を温泉で洗い流して、日本料理を楽しんでゆこうというお客様は少なくない。ちなみに向こうでは温泉に入るときにも全裸にはなりません。水着を着ていただきます。とにかくそんなこんなで私の店は結構繁盛しております。しかし四月ともなれば春霞でヒマラヤが見えにくくなりますし、スコールも多くなる。六月ともなれば雨季が始まる。そうなれば観光客は減りますから店は暇になります。オフシーズンの商売は、もっとほかにやりようがあると考えていました。そこへ浅間観光から私にお話があったのです。主にネパールが雨季のあいだ日本へ来て、この六里ヶ原で店をやらないかとね。私はもともと工業新聞社に勤めていた人間ですから、そういう話が舞い込んだのですな。ところで真壁さん、いかがですか、このお店は」
「物心ついた頃からこのガーデンを存じておりましたが、変われば変わるものですね。コンセプトと申しますか、世界観がこれまでとは全然違います」と悠太郎が答えると、登原さんはわが意を得たりとばかり「そうです、世界観ですよ、コンセプトですよ、これまでのガーデンに欠落していたのは! いやはやさすがは永久名誉顧問のお孫さんだ。まだお若いのによく分かっていらっしゃる。まったく前任者ときたら、世界観以前の問題ですよ。掃除すらまともにできていなかったのですからな。開店準備のために来てみれば、まあなんと汚い汚い! 大きな声では言えませんが、黒い汚れが床にこびりついて、どうしても落ちない。こうなったら最後の手段ですよ。どうしたと思います? 石油を撒きましたよ! 石油を床にぶちまけて磨いたのですよ!」と上機嫌で苦労話を披露した。「ところでポカラというのはどういう意味ですか?」と悠太郎が問うと、「よくぞ訊いてくれました。それこそ世界観に関わる問題なのです。ポカラというのは地名です。首都カトマンズから西へ二百キロのところに位置するポカラは、ネパール第二の観光都市です。市内のどこからでも、ヒマラヤの連峰を仰ぎ見ることができます。当店にも写真を飾っておりますが(と言いながら登原さんは壁に飾られたパノラマ写真を指さした)、左からダウラギリ、アンナプルナ南峰、アンナプルナⅠ、右からマナスル、アンナプルナⅡ、アンナプルナⅣ、アンナプルナⅢ、そして真ん中の尖った山が霊峰マチャプチャレ。マチャプチャレというのは、魚の尾という意味だそうですよ。言われてみればそう見えなくもありませんな。そして神々の座と呼ばれるヒマラヤの名峰を、満々と水を湛えたフェワ湖の水が映しているわけです。もうお分かりですな? 浅間隠の連山や鷹繋山や浅間山に囲まれたこの照月湖のほとりを、ポカラになぞらえたわけですよ」と登原さんは上機嫌で答えた。「もちろんいくら景色が美しくたって、料理がまずければ食い物屋は駄目です。しかし開店早々嬉しい事件が起こりましたよ」と登原さんは続けた。「インド人のお客様が来店されたのです。宝石商をしているという男性で、いかにもマハラジャといった感じのカイゼルひげを生やし、手にはサファイアの指環を嵌めていました。さてそのお客様は食事を終えると、チャンドラカルナを呼んで言うのです。店主を出せと。呼ばれて私は出てきました。お客様は言います。〈なんというものをあなたは私に食べさせたのか〉と。私はお叱りを覚悟して、〈お口に合いませんでしたか?〉とこう申しました。するとお客様は言うのです。〈なんというものをあなたは私に食べさせたのか。こんなおいしいカレーは生まれて初めて食べた。ついてはレシピを教えてほしい。企業秘密だというなら、ヒントだけでもいいから〉というわけですよ。私は嬉しくて、スパイスの使い方などいくらか教えてあげました。インド人をカレーで感激させたのですからな。これは私の食い物屋人生のなかでも、忘れ難い思い出になりそうですよ。おお、そうこうするうちに、チャンドラが食事を運んできました。ではどうぞ、ごゆっくりお召し上がりください」
真鍮のプレートに盛られたランチセットがテーブルに置かれた。野菜カレーと豆カレーとマトンカレーの手前には大きなナンがあった。ほうれん草の炒め物とタンドリーチキンも一緒についていた。それらを載せたワンプレートのほかには、ラッシーと呼ばれる白いヨーグルト飲料のグラスも置かれた。悠太郎はまずスプーンで三種類のカレーをそれぞれ味わってみた。想像していたほど辛いわけではなかったが、深く謎めいた味と香りに体の奥まで温まるような感じがした。それから感謝しつつ手でナンを裂いてカレーに浸し、口へ運んだ。バターの香りがする柔らかな食感のナンにカレーの味が融け合い、こんなおいしいものは食べたことがないと思えるほどおいしかった。よく煮込まれた野菜や羊肉をフォークで口へ運び、口直しに爽やかな甘さのラッシーをストローから飲んでは、またカレーに浸したナンを食べ、あるいはニンニクが効いたスパイシーなほうれん草の炒め物や、見るからに辛そうな赤いタンドリーチキンを味わった。窓から眺める湖はきらめき揺らめきながら、手漕ぎボートやスワンボートを浮かべていた。プレートに盛られたこの料理が食べ尽くされるように、夢のような美しい時間もまた終わってしまうのだと思うと、悠太郎の胸には切ないような哀惜の念が溢れた。忘れまい、俺はけっして忘れまい。この店のことを、この料理の味を、この湖畔で起こったことのすべてを、俺はいつまでもけっして忘れまい――。涙を堪えながらそんなことを思いつつ、悠太郎は食事を終えた。
伝票を持ってレジへ行き、卓上ベルを鳴らすとチャンドラさんが現れた。悠太郎は千代次から渡された千円札を財布から出した。ところがチャンドラさんは拒否するような身振りをした。不審に思った悠太郎が伝票と千円札を代わる代わる指し示すと、チャンドラさんは「いただけません」と片言の日本語で言った。「なぜですか?」と悠太郎が日本語と英語で問うと、チャンドラさんは英語で「店主の意向です」と言った。その意味を理解した悠太郎は、恥ずかしさと怒りのあまり顔を赤くした。今しがた食べた料理の唐辛子やスパイスが、体の奥でもう一度燃え上がったかのようであった。「冗談ではありません、ミスター・チャンドラカルナ・ムリ・ギリ。お代を受け取らないとは、あまりにもひどいではありませんか。あなたがたは素晴らしいこのお店で、素晴らしい料理を食べさせてくださった。私はそのことに大変感謝しています。それなのにお代を受け取らないとは、いったいどういうおつもりですか? あなたが答えられないなら、ミスター・トバラに訊いてください。私が真壁千代次の孫だからですか? 私は祖父の地位を利用して、このお店にただ飯を食べに来るような人間ではありません。私のことをそういう人間だと思ったのかと、ミスター・トバラに訊いてください。お代はどうあっても受け取っていただきます。もしどうしても受け取らないと仰言るなら、もう二度とこのお店には来ません。ほかの人たちにこのお店を薦めることもしません。ミスター・トバラにそう伝えてください」と悠太郎は日本語混じりの英語と英語混じりの日本語でまくし立てたが、「どうしても受け取らないと仰言るなら」というところでは、金子先生に教わった「拒絶のwill」を早速使うことができた。怒気を含んだ悠太郎の剣幕に、チャンドラさんは一重瞼の大きな目を怯えたように泳がせながら厨房へ引っ込んでいった。ややあって再び出てきたチャンドラさんは、何事もなかったかのように「九百二十円です」と言って、千円札を受け取り釣銭を返した。いたたまれなくなった悠太郎は、「ごちそうさまでした」と言って逃げるように店を出た。
急な坂道を登り切った悠太郎は、改めてレストラン照月湖ポカラ・ガーデンを見下ろした。店主の地を這うような声や、値踏みするような目が思い出された。「登原さんは俺を試したのだろうか。試したとすれば、何を試したのだろう。英語力だろうか、それとも人格だろうか」と悠太郎は考えた。後のほうを考えたとき、悠太郎の背筋を冷たいものが走った。危うく俺はなんという過ちを犯すところだったのだろう!――「食えない男が食い物屋とは……。いや、ひょっとしてみんなぐるだったのではないか。俺がチャンドラさんに必死で思いを伝えようとしていたとき、手島さんとかいうあの幽霊女は助けに来ようともしなかったではないか。予め三人で申し合わせて、ひと芝居打ったのではないか。いや、ひょっとしたら祖父もその一味かもしれない。あの三人は祖父に言われて、こんな茶番をやったのかもしれない。この六里ヶ原にいる限り、俺はいつまでも真壁千代次の孫であることから自由になれない。他人から見れば、そんなことは贅沢な悩みなのだろう。だが俺にとっては本当につらいことだ。いつかこの地を離れたなら、俺はこんな思いをせずに済むようになるだろうか。ああ、若葉するの樹々の枝に夏鳥たちが歌っている。今年もまた夏へと向かってゆく。俺はこの六里ヶ原で、こうしてひとつまたひとつと季節を積み重ねてきた。その終わりはいったいどういうことになるのだろう。俺は季節の階段を昇って、どこへ行くのだろう……」
悠太郎が家に帰ると千代次が居間で、極度に細い近視の目をしばたたきながらテレビを観ていた。「ガーデンはどんな具合だった?」と祖父は孫の顔を見ずに問うた。「とても賑わっていました。これまでのガーデンにはなかった新しい異国情緒がありました。料理もおいしかったです」と孫は、どんな具合か知りたいなら自分で行けばいいのにと思いながら答えた。「そうかそうか。ネパール人とも話ができたか?」と祖父が問うたので、やはり仕組まれていたのかと思いながら孫は「はい」と短く答えた。「英語でか?」となおも祖父が問うたので、「英語も使いました」と孫は答えた。「そうかそうか。話すほうはなかなかできると見えるな」と祖父は初めて孫と目を合わせた。あたかも悠太郎が試練を切り抜けたことを意外に思ってでもいるかのように、千代次の顔には嘲るような笑いが浮かんでいた。「俺は若い頃もっと英語を勉強したかった。だが戦争が始まって、鬼畜米英ということになった。英語は敵性語と見なされたから、勉強を続けるわけにはいかなかった。あのとき日本人が敵を知るために英語の勉強を一生懸命やっていりゃあ、あるいは戦争に負けなかったかもしれねえ。そう思うと残念でならねえよ。ユウ、おめえは俺の分まで一生懸命英語を勉強しなけりゃあならねえぞ」と語った千代次は、「話すほうはまあいいとしよう。それで書くほうはどうだ? はあ筆記体が書けるんべえな?」と問うた。悠太郎は隙を衝かれた人のようにたじろぎながら、「筆記体で書くことは、学校では教わりません。教科書に載ってはいますが、先生も生徒もブロック体で書きます」と睫毛の長い目を伏せながら返答した。ここぞとばかりに千代次は怒りを爆発させた。「何だと! 筆記体が書けねえだと! 俺の孫が中学生にもなって、筆記体も書けねえちゅうのか! 先生が教えねえったって、まわりの馬鹿奴等が使わねえったって、それがおめえの書けねえ理由になるか! まわりの奴等がどうであれ、おめえだけは書けなくてどうする! すぐに筆記体の練習を始めろ!」と千代次は泡を吹き、よだれを垂らしながら孫を怒鳴りつけた。
部屋で学習机に向かった悠太郎は、がっくりとうなだれて頭を抱えた。まだ小文字のbとdの区別もできない同級生がいるのに、なぜ自分にばかり高い要求が課せられるのか分からなかった。こうやって祖父はあの手この手で俺を苦しめるのだと悠太郎は考えた。母子ともども経済的に庇護されていて逆らえないのをいいことに、ありとあらゆる手段を尽くして俺を苦しめ続けるとは、なんという念の入った虐待だろう――。だが悠太郎は言いなりになるよりほかに仕方がなかった。誰より速く走れというのは無理な要求であったが、英語の筆記体ならば習得できないものでもなかった。ふと思い立って悠太郎は、いつか正子伯母様から誕生日プレゼントにもらった《マカベウスのユダ》のCDを棚から取り出した。その箱には黒地に白いアルファベットで作曲家と作品名と演奏家が記され、楕円の枠のなかに勇ましい戦士の姿が描かれていた。黒い馬に跨ったその戦士は左手を天に挙げ、右手では戦斧を振るい、腰には幅広の剣を提げていた。解説と歌詞が記されたブックレットを箱から出した悠太郎は、英語の歌詞を冒頭からノートに筆記体で書き写し始めた。アルファベット別に見て記憶していた筆記体ではあったが、実際に文字と文字を繋げるのは難しかった。不器用な綴り方で悠太郎は、マタティアの死を悼む合唱の歌詞を綴っていった。「俺がこうして苦しんでいるのも、誰かが下手な筆記体で書き綴っているオラトリオの台本通りなのかもしれない」という考えが脳裏に浮かんだ。やがて悠太郎の好きな祭司シモンの言葉が出てきた。
この悲嘆の嵐のすべては無駄ではない
それからしばらくすると、イスラエルの女のアリアがあった。
おお自由よ 汝こよなき宝よ
そしてついに凱旋の勇者ユダを迎える合唱が、
見よ 勝利の勇者がやって来る!
トランペットを吹き鳴らせ 太鼓を打ち鳴らせ
祝祭の支度をせよ 月桂冠を持ってこい
勝利の歌を彼にうたえ
と歌うところに来ると、悠太郎の目から大粒の涙がノートの上にぼたぼたと落ちた。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
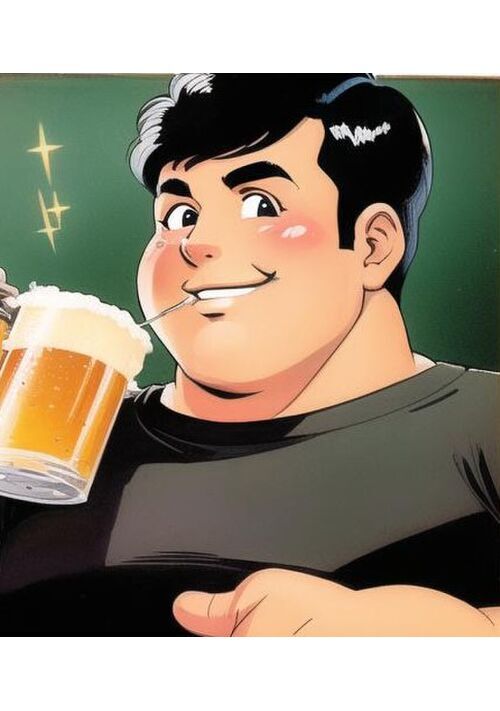
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!




イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















