44 / 73
第十五章 筆記体
二
しおりを挟む
マッシモ先輩たちの学年の担任は、社会科を教える埴谷高志先生であったが、この埴谷先生は破れ鐘のようなでかい声と、お世辞にも上品とはいえないギャグセンスの持ち主であった。「いいかおまえたち、古墳のまわりに置かれた人形は? 埴輪! じゃあ俺は? 埴谷! がっはっは!」と埴谷先生が言いながら、直角に曲げた両腕をそれぞれ天と地に向けると、一年生の生徒たちは大笑いして喜んだが、かく言う埴谷先生は四角張った大きな顔と離れた両目のために、埴輪というよりはむしろモアイ像を思わせた。歴史を教えていても地理を教えていても、埴谷先生のギャグはひとたび興に乗ればとどまるところを知らず、授業はどこまでも脱線していった。「おまえたち、俺がこれから浦島太郎を見せてやろう」と埴谷先生はあるとき言うと、上半身に着ていたジャージのファスナーを開けてそれを脱ぎ始めた。そして脱いだジャージを後ろ前に着た埴谷先生は、背中で再びファスナーを閉めると「裏、閉まったろう! がっはっは!」と言った。これには野球部の佐原康雄も荒れた唇が切れるほど大笑いしたし、テニス部の戸井田一輝も椅子から転がり落ちんばかりに抱腹絶倒した。
ところで埴谷先生は、滾々と湧き出るギャグの泉として生徒たちに注目されていたばかりではなかった。とりわけ六里ヶ原第一小学校から来た生徒たちは、小学校の保健室にいた横沢さやか先生の結婚相手として埴谷先生を見ていた。美人の誉れ高かったさやか先生の怜悧な目を、悠太郎は思い出していた。あれほど知的で美しい女性が、なぜこのような男性を選んだのだろうと悠太郎は訝った。同じようなことを考える生徒たちは少なくなかった。「どこで知り合ったんですか?」と野球部の神川直矢は、白目の冴えた小さな目を面白そうに笑わせながら質問した。この町の小学校が合同で行なう臨海学校の際に、新潟県の海辺で知り合ったのだというのがその答えであった。「何て言ってプロポーズしたんですか?」と直矢は畳みかけるように質問した。「ぼくは死にましぇーん!」というのがその答えであった。一年生の教室には乱反射する湖のような笑いが起こり、直矢もまた機関銃のように高笑いしたが、悠太郎は亡くなった橋爪進吉さんを思い出して、悲しみに胸を痛めた。
そうした埴谷先生のギャグが、悠太郎にとって許し難いような下劣の極みに達したことがあった。「ところでおまえたち、英語の勉強はちゃんとやってるか? もう月曜日から日曜日まで、一週間の曜日を英語で言えるようになったか?」と問うた埴谷先生は、「俺がいい憶え方を教えてやろう。まず月曜日。Mondayは、揉んでー。次は火曜日。Tuesdayは、チューするでー……」と、一週間のそれぞれの曜日に卑猥な駄洒落を割り当てていった。水曜日から木曜日へ、木曜日から金曜日へと話が進むにつれて、教室内の笑い声はいよいよ高まっていった。ところが「土曜日、土曜日は、Saturdayはなあ……」と言葉を切った埴谷先生は、ひとりで身をのけぞらせて爆笑しながら「これは、駄目だ! これはとても言えねえよ! 女の生徒がいるところで、こんなことが言えるかよ!」と、脳内にある駄洒落の面白さに涙を流さんばかりの様子であった。「教えてくださいよ」と直矢が迫った。「教えてくださいよ」と隼平も迫った。「そうかそうか。おまえたちが勉強熱心なのはよく分かった。どうしても知りたい者は、この授業が終わったら俺のところへ来るように。ただし男子限定な。それからおまえたち、俺がこんなことを教えていたなんて、英語の金子先生には言ってくれるなよ。いいな」と言って授業の本題に戻ろうとした埴谷先生であったが、脱線に脱線を重ねたために、何の話をしていたのか思い出すことができなかった。話が逸れる直前まで読んでいた教科書のページ番号と文章を、諸星真花名がふるえがちな声で読み上げてくれたので、先生はどうにか授業を立て直すことができたのである。さてチャイムが鳴って授業が終わり、一同が起立して礼をした後で、興味津々の男子たちは早速埴谷先生のまわりに輪を作った。果たして埴谷先生の言葉は、彼らを大爆笑させた。その輪に加わらず離れていた悠太郎の鋭敏な耳にも、埴谷先生の禁断の言葉は届かずにはいなかった。どんなに音量を落としたつもりでも、もともとが破れ鐘のようなでかい声であるから、それでようやく人並みの音量にしかならなかったのである。秘密めかしたつもりで埴谷先生が告げた言葉は、「Saturdayは、さあ勃ったでー」というものであった。いったいなぜこんな男をさやか先生は選んだのだろうと悠太郎は思った。こんな男が留夏子さんの担任であることは許し難いとも思った。しかしあの汚らわしい言葉を、俺は本当に聞きたくなかったのだろうかと悠太郎は自問した。さやか先生も留夏子も自分も、人間は誰であれ暗い肉であらざるを得ないという考えは、悠太郎の心を限りなく重くした。
さて英語の時間になって、一年生の生徒たちが――とりわけ男子たちが――何かを隠してでもいるかのように嫌らしくにやにやしているのを、金子芳樹先生は怪しんだ。怪しみはしたが、しかしムースで前髪をイワトビペンギンのように逆立てた金子先生は、つまらない怪しみを吹き払おうとでもするかのように、颯爽たる声で「Hello, everyone!」と呼びかけた。だが「Hello, Mr. Kaneko!」と答える生徒たちの声には、やはり嫌らしい笑いが含まれていたので、金子先生は探るように、尋問するように「How are you?」と問うた。しかし「Iʼm fine!」と答える生徒たちの声からは、何事が隠されているのかを知ることはできなかった。疑わしげに首をかしげながら金子先生は、持参したCDラジカセで音楽を流した。授業の最初に英語の歌をうたわせることで、生徒たちをこの言語に親しませようと意図した金子先生が、このとき選んでいたのはビートルズの〈Yesterday〉であった。英語の歌詞とその日本語訳が記された対訳のプリントは、何回か前の授業のときに配られていた。
みんなは歌ったが、大多数の生徒たちにとっては歌をうたうことも恥ずかしければ、外国語を発音することも恥ずかしかった。二重の羞恥心のためにあまり声を出さないみんなのなかにあって、楽しげに歌う悠太郎のバリトンの声は金子先生の注意を引いた。悠太郎にしてみれば、過ぎ去った昨日を懐かしむこの歌の哀愁が好ましく感じられたので、そこに自身が抱いている過去への哀惜を投影することに力を尽くしたのである。ああ、あの頃は困ったことなんて遥か彼方にあるように思われた。照月湖の水は澄んでいて、湖畔は賑やかだった。あの頃はまだバブルが弾けてもいなければ、異常気象もなければ、アオコもなかった。今ではそれらすべての禍が、湖と湖畔に留まっているかのようだ。ああ、あの頃が懐かしい――。そんなことを思いながら悠太郎は、金子先生の日本語訳に頼りつつ、歌詞の意味を音楽と結びつけることに意を用いた。英語の歌詞の上に記された片仮名には、ほとんど頼っていなかった。あるくだりで悠太郎は一語一語段階的にクレッシェンドし、抒情的にややテンポを揺らし、代名詞の母音を短く切り上げて、その分助動詞を緊張感豊かに発音した。
歌が終わると教科書に取りかかる前に金子先生は言った。「真壁くんの〈Yesterday〉はどんどん冴えてくるなあ。特に〈彼女は言おうとしなかった〉のところがよかったよ。一年生の一学期にこんなことを教えるのはまだ早いんだが、みんな一応は聞いてくれ。wouldというのはwillの過去形だ。willというのは何々しようとするという意味だ。その過去形に否定のnotがついて wouldnʼtだ。つまり何々しようとしなかったという意味になる。彼女は言おうとしなかった。こういうwillの使い方は、特に拒絶のwillと呼ばれる。どうしても何々しようとしないという意味だ。ぼくは何か間違ったことを言ったの? もしそうなら、そう言ってほしい。きみがぼくと別れて立ち去らなければならない理由を言ってほしい。彼はそう彼女に頼んだんだろう。懇願し哀願したんだろう。それでも彼女は言おうとしなかった。別れの理由をどうしても言おうとしなかった。それだけの思いが込められている。まさか真壁くんは、もう拒絶のwillを知っていてあんなふうに歌ったのか?」物問いたげな大きな目を黒々と見開く悠太郎に、みんなの注目が集まった。「いいえ。私はそこまでのことは知りませんでした。ただ音楽がそうなっているから、歌詞と曲がそう結びついているから、そう歌うんです」と悠太郎は答えた。「そうか。まあいずれにせよ見事な発音とリズム感だ。これは二年生の佐藤さん以来の英語使いになるかもしれないな」と金子先生は言った。「だが真壁くんの歌いぶりは、ビートルズというよりクラシックの歌曲みたいだな。音楽の棚橋先生も教え甲斐があるだろう」
さて音楽の棚橋晶子先生は、金子先生と同年輩であるにもかかわらず、目は泣き腫らし、頬はむくみ、口角は下がりっぱなしで自暴自棄に陥っており、厚い化粧はしばしば涙に溶けていた。棚橋先生は荒々しく踏み鳴らす足で、ずんぐりむっくりの体を運んで音楽室にやって来ると、内巻きワンカールボブの髪を振り乱しながらピアノを弾いた。荒れに荒れている現在の三年生たちが入学してきたその年度から、この中学校での仕事が始まったことは棚橋先生の不幸であった。何かにつけては中指を突き上げる中島猛夫のような手合いがわんさかいるとあっては、棚橋先生には音楽の授業を成り立たせることができなかった。ピアノを弾いて歌をうたわせることも、アルトリコーダーの指遣いを教えることも、クラシック音楽を鑑賞させることも、文化祭での合唱コンクールに向けて曲を練習させることも、ことごとく失敗に終わった。音楽教師としての職務への熱意を、棚橋先生は急速に失ってしまった。よほどまともな留夏子たちの学年が入学してきても、棚橋先生は生徒たちに心を開こうとはしなかった。どれほどペトラが合唱曲の伴奏を弾いて同級生をピアノのまわりに集めようとも、どれほど留夏子が凛々たるソプラノの声で歌い、またアルトリコーダーで〈「グリーンスリーヴス」による変奏曲〉を巧みな装飾音とともに吹こうとも、棚橋先生にとって生徒たちは十把一絡げに敵でしかなかった。悠太郎が後で知ったところでは、そんな棚橋先生をなお仕事に繋ぎとめていたのが、なんと英語の金子芳樹先生への恋心だというのである。棚橋先生は女子ソフトテニス部を、金子先生は男子ソフトテニス部をそれぞれ顧問として指導していたが、部員たちを引率して大会に出掛けたとき棚橋先生は、ハムとレタスとエッグフィリングがたっぷり挟まったサンドイッチを余分に作ってきて、「ほれ、食え! どんどん食え!」と金子先生に勧めていたという。そうしたことを陽気な戸井田アオイさんや、幸薄そうな諸星美雪さんといったテニス部の生徒の親たちが噂していた。それを聞き知った秀子が悠太郎に教えたのである。サンドイッチの件は一学期もだいぶ進んでからのことであった。ともあれ棚橋先生の恋はどうやら望みがなさそうであった。そうしたわけで棚橋先生は、悠太郎がびっくりするような荒っぽいタッチで〈花の街〉のピアノ伴奏を弾いたのである。色彩豊かな夢を広げるはずの前奏からして、もう台無しであった。それでも悠太郎はめげずに歌った。
有節歌曲という言葉を悠太郎はまだ知らなかったが、それでも同じメロディーの繰り返しのなかで、歌詞の意味に即して各詩節を歌い分けることが、表現上の課題であることは感じ取れた。第一詩節から第二詩節にかけて高まった明るい幸福感が、春の夕暮れを歌う第三詩節で淋しさに変わるところは、とりわけ好ましく思われた。なるほどこれは歌曲なのだと悠太郎は改めて考えた。こうしてみんなで歌ってはいるが、本来これは独唱曲なのだ。みんなで歌おうとか、みんなで旅立とうとか、やたらと「みんな」を押しつけてくるクラス合唱曲とは違って、独唱歌曲はひとりでいることを認めてくれる。「みんな」と一緒に輪になれない「ひとり」の淋しさという内面的な感情を、歌曲は表現できるのだ。そうだとすれば歌曲とは、俺にとって是非とも必要なものではないか――。悠太郎がそんなことを考えていると棚橋先生が、「作曲者の思いが教科書に載っている。各自が適当に読んでおけ!」と乱暴に言った。その声はずんぐりむっくりの体によく共鳴したが、歌うことよりも怒鳴ることによほど多く使われた以上、音楽教師としては使い方を間違えているわけであった。さて悠太郎は教科書に目を走らせた。まだ戦後間もない荒廃のなかで「花の街」を歌う詩人に、作曲家は初め不審を覚えたが、やがてその詩に込められた祈りに共鳴してこの曲を書いたと、そこには述べられていた。悠太郎は作曲家のこの文章から、力強い励ましを受け取ったように思った。芸術表現は、見たり聞いたりできる現実の引き写しであってはならないのだ。芸術表現は、現実を超克するもうひとつの現実であり得るし、もうひとつの現実であらねばならないのだ。ひとつの歌曲でさえもうひとつの現実であり得るし、もうひとつの現実であらねばならないのだ――。
だが悠太郎にとって真に決定的な歌曲体験となったのは、シューベルトの〈魔王〉の鑑賞であった。その曲の不気味なほど静謐で戦慄的な美しさは、ほとんどこの世のものとは思われなかった。いつか夏休みのある日、佐藤陽奈子先生がピアノを弾きながら歌ってくれたバッハの〈主よ、人の望みの喜びよ〉以来、初めて聴くドイツ語の歌であった。教科書には前奏の楽譜と、伴奏を省いた歌声部の楽譜だけが載っていた。前奏から右手にオクターヴで連打される三連符が続いていた。こんなものを弾いたら腱鞘炎になるではないかと悠太郎には思われた。しかしこうして音楽室に再生された録音では、ピアニストは苦もなく弾いているように聞こえる。そして歌い始めたバリトン歌手のなんという声だろう! 硬質な子音と豊かな母音で織り成された冴え渡るドイツ語を響かせながら、伸縮自在なその声は語り手と父親と息子と魔王を、寸分の隙もなく完璧に歌い分けていった。しばしば繰り返される呼びかけのフレーズについては、日本語訳が教科書に載っていた。風の強い夜に、小さな息子を抱いた父親が馬を走らせている。オクターヴで連打される三連符は、その馬の荒々しい蹄の音を表しているということであった。病気の息子は幻覚を見ている。父親は息子を現実に引き戻して落ち着かせようとする。しかし魔王が息子を誘惑する。坊や、一緒に行こう。一緒に楽しい遊びをしよう。岸辺には色とりどりの花が咲いているよ。わしの母さんは綺麗な着物をたくさん持っているよ。わしの娘たちにおまえの子守をさせよう。わしの娘たちに子守歌をうたわせよう――。その誘惑の歌のなんという美しさだろう! しかし三度目に魔王は本性を露わにする。わしはおまえが大好きだ。おまえの美しい姿にそそられる。おまえが乗り気でないなら、わしは力ずくだぞ! いよいよ高まった声で息子は絶叫する。魔王がぼくに痛いことをしたよ! 父親はぞっとして馬を全力で走らせる。どうにか家に着いたときには、腕のなかでその子は死んでいた。最後の「war tot」というのが、「死んでいた」という意味だと教科書には載っていた。ゲーテの詩によるシューベルトの歌曲〈魔王〉は、美しくも暗い嵐のように悠太郎のなかを吹き抜けていった。それを歌ったバリトン歌手の名前もまた教科書に載っていた。長い名前であったが、悠太郎はその名を心に刻み込んだ。ディートリヒ・フィッシャー゠ディースカウ。悠太郎はその名をどこかで見たことがあった。それはどこであったか?
それは梅子が持っていたレコードのコレクションのなかであった。まだ悠太郎が中学校への入学を前にした春休みのうちに、真壁の家にレコードプレーヤーつきのステレオコンポが据えつけられた。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、ふっるーいレコードをまた聴いてみたくなったよ。悠太郎もピアノのお勉強がだいぶ進んだからウッフフ、いろいろな音楽を聴くことはためになるんじゃないのかい?」と希望したのである。西洋音楽をそれほど好まない千代次ではあったが、孫の教育がそういう方向へ進み始めた以上、今さらそれを阻むわけにはゆかなかったから、自分の部屋から遠い悠太郎の部屋にそれを置くという条件で了承した。梅子は喜色を満面に浮かべながら、押入れの奥から古いレコードのコレクションを取り出した。これは実に久し振りのことであった。昔あったステレオレコードプレーヤーは、小さかった悠太郎が歩きまわるのに危ないので処分された。そのとき押入れの奥深くしまい込まれたレコードが、十年以上の歳月を経た今こうして取り出されたのである。そのコレクションはさして膨大というわけではなかったが、田舎の中学生がクラシック音楽の初歩を体験するには、差し当たり充分に役立つものであった。バッハの管弦楽組曲があった。モーツァルトの交響曲第四十一番《ジュピター》があり、歌劇《フィガロの結婚》のハイライトがあり、レクイエムがあった。ベートーヴェンの交響曲第五番《運命》と第六番《田園》と第七番と第九番《合唱つき》があった。メンデルスゾーンの交響曲第三番《スコットランド》と第四番《イタリア》があった。ベルリオーズの《幻想交響曲》があった。ショパンのピアノ協奏曲第一番と第二番があった。ワーグナーの管弦楽曲集があった。ブラームスの交響曲第一番と第四番があった。ブルックナーの交響曲第八番があった。ギリシャの歌姫がうたうイタリア語やフランス語のオペラ・アリア集があった。そうしたレコード盤をしばしば悠太郎は好んで聴いた。回転するターンテーブルに乗ったレコード盤の溝に、トーンアームの先の針が落ちて音楽が鳴り始めると、吸い寄せられるように梅子が部屋にやって来て、孫と一緒にそれを聴いていた。
ステレオコンポが据えつけられたばかりの頃、何から聴き始めたらよいかと悠太郎が尋ねたとき、梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、メンデルスゾーンさんから聴きなさい。ふっるーいお城を訪ねたときの曲」と答えた。それはメンデルスゾーンの交響曲第三番を指していた。梅子はスコットランドという固有名詞を、どうしても憶えられないのであった。悠々たる遅いテンポで奏でられる愁いを帯びたその曲に、梅子も悠太郎も好んで耳を傾けたが、その曲でもほかの多くの曲でも、盤面の傷や黴のために、しばしば音飛びが生じるのは惜しいことであった。またあるときはバッハの管弦楽組曲第二番ロ短調を、ふたりはそうして聴いていたことがあった。序曲がありロンドがありサラバンドがあった。ブーレがありポロネーズがあった。そしてメヌエットが続いた。フルートを主役にしたその組曲は典雅にして骨太であり、華麗にして剛毅であった。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らすことなく、「光子さんを思い出すねえ。ひばりが丘で元気にしているかねえ」と言った。悠太郎の脳裏にも、観光ホテル明鏡閣の社員食堂で初めて会ったときの三池光子さんが思い浮かんだ。優雅な手つきで煙草を吸っていた光子さんは、アイシャドウの濃い目をぱちくりさせながら、月光に照らされた黒天鵞絨のような艶のある低音の声で、「そうだ、ユウちゃん、お花は好き? 湖のほとりに水仙が咲いたわよ。私と一緒に水仙を見にゆきましょう」と言うが早いか、明鏡閣のロゴが入った陶器の灰皿で煙草を揉み消すと、やおら立ち上がったのであった。灰色がかったボブショートの髪をした、ひょろりと背の高い撫で肩の光子さんを、悠太郎はどんなにか慕わしく思ったことであろう。「水仙」と言うとき「ス」の音をいちばん高くして、そこから流れ落ちるようなイントネーションで発音するその言い方も、なんと懐かしいことであろう――。組曲は終曲のバディネリで、午後の湖のように光を撒き散らしていた。
そんなレコード盤のなかにあって奇跡的に無傷で保存されていたのが、ディートリヒ・フィッシャー゠ディースカウによる二枚組のシューベルト歌曲集だったのである。中学校の音楽の時間に起こった圧倒的な〈魔王〉の体験まで、悠太郎はそのレコードを聴いてみたことがなかった。オーケストラの壮麗な響きに比べれば、バリトン独唱にピアノ伴奏なんていかにも地味でつまらなそうに思われたし、いくら歌詞対訳がついているとはいえ、ドイツ語という未知の外国語をわざわざ聴こうとも思わなかった。ところが今や悠太郎にとって、その二枚組はコレクション中の至宝となった。そこには〈野薔薇〉があり〈夜の歌〉があった。〈魔王〉があり〈連祷〉があった。〈さすらい人〉があり〈死と乙女〉があった。〈音楽に寄せて〉があり〈ます〉があった。〈春の信念〉があり〈水面に歌う〉があった。〈きみはわが憩い〉があり〈夕映えのなかで〉があった。〈聴け、聴け、ひばり〉があり〈シルヴィアに〉があった。〈緑野の歌〉があり〈星〉があった。これを要するに、シューベルト歌曲の深遠なる小宇宙がそこにはあったのである。外国語で歌われる声楽曲が苦手だという理由から、梅子が《フィガロの結婚》のハイライトやギリシャの歌姫によるオペラ・アリア集と同様ほとんどこのレコードを聴かず、無傷のままに保っておいてくれたことは僥倖であった。悠太郎は毎日毎晩これを聴いた。食い入るように歌詞対訳を見つめながら、フィッシャー゠ディースカウの伸縮自在なバリトンに聴き入るうちに、いつしかドイツ語の発音規則だけはおぼろげながら見えてきた。そのうち悠太郎はフィッシャー゠ディースカウの歌に声を合わせて一緒に歌うようになっていた。音楽の教科書に載っている〈魔王〉の楽譜に、ドイツ語の歌詞を書き込みさえした。〈魔王〉以外の収録曲でとりわけ悠太郎を喜ばせたのは〈水面で歌う〉であった。夕日を浴びて波立ちきらめく水面を、白鳥のように小舟が滑ってゆく。その小舟のように魂もまた滑ってゆく――。跳ね上がっては滴り落ちるような細やかな十六分音符が連続するピアノ伴奏の右手は、水面のきらめきを絶え間なく描き出しているかのようであった。それは当然のことながら、悠太郎に照月湖を思わせずにはいなかった。今は亡き入江紀之が、まだ小学校一年生だった俺をボートに乗せてくれたのは、もう六年の昔だ。昨日も今日も明日も消えてゆく。あの慕わしい湖の騎士が消えていったように、俺もまたいつかは消えてゆくのだ。どのようにしてかは知らないが、消えてゆくことだけは間違いない。あの懐かしい湖も消えてゆくのだろうか。賑わった湖畔も滅びてしまうのだろうか。湖畔に集った人々がみんな消えてしまったら、誰が照月湖のことを語るのだろうか――。
ところで埴谷先生は、滾々と湧き出るギャグの泉として生徒たちに注目されていたばかりではなかった。とりわけ六里ヶ原第一小学校から来た生徒たちは、小学校の保健室にいた横沢さやか先生の結婚相手として埴谷先生を見ていた。美人の誉れ高かったさやか先生の怜悧な目を、悠太郎は思い出していた。あれほど知的で美しい女性が、なぜこのような男性を選んだのだろうと悠太郎は訝った。同じようなことを考える生徒たちは少なくなかった。「どこで知り合ったんですか?」と野球部の神川直矢は、白目の冴えた小さな目を面白そうに笑わせながら質問した。この町の小学校が合同で行なう臨海学校の際に、新潟県の海辺で知り合ったのだというのがその答えであった。「何て言ってプロポーズしたんですか?」と直矢は畳みかけるように質問した。「ぼくは死にましぇーん!」というのがその答えであった。一年生の教室には乱反射する湖のような笑いが起こり、直矢もまた機関銃のように高笑いしたが、悠太郎は亡くなった橋爪進吉さんを思い出して、悲しみに胸を痛めた。
そうした埴谷先生のギャグが、悠太郎にとって許し難いような下劣の極みに達したことがあった。「ところでおまえたち、英語の勉強はちゃんとやってるか? もう月曜日から日曜日まで、一週間の曜日を英語で言えるようになったか?」と問うた埴谷先生は、「俺がいい憶え方を教えてやろう。まず月曜日。Mondayは、揉んでー。次は火曜日。Tuesdayは、チューするでー……」と、一週間のそれぞれの曜日に卑猥な駄洒落を割り当てていった。水曜日から木曜日へ、木曜日から金曜日へと話が進むにつれて、教室内の笑い声はいよいよ高まっていった。ところが「土曜日、土曜日は、Saturdayはなあ……」と言葉を切った埴谷先生は、ひとりで身をのけぞらせて爆笑しながら「これは、駄目だ! これはとても言えねえよ! 女の生徒がいるところで、こんなことが言えるかよ!」と、脳内にある駄洒落の面白さに涙を流さんばかりの様子であった。「教えてくださいよ」と直矢が迫った。「教えてくださいよ」と隼平も迫った。「そうかそうか。おまえたちが勉強熱心なのはよく分かった。どうしても知りたい者は、この授業が終わったら俺のところへ来るように。ただし男子限定な。それからおまえたち、俺がこんなことを教えていたなんて、英語の金子先生には言ってくれるなよ。いいな」と言って授業の本題に戻ろうとした埴谷先生であったが、脱線に脱線を重ねたために、何の話をしていたのか思い出すことができなかった。話が逸れる直前まで読んでいた教科書のページ番号と文章を、諸星真花名がふるえがちな声で読み上げてくれたので、先生はどうにか授業を立て直すことができたのである。さてチャイムが鳴って授業が終わり、一同が起立して礼をした後で、興味津々の男子たちは早速埴谷先生のまわりに輪を作った。果たして埴谷先生の言葉は、彼らを大爆笑させた。その輪に加わらず離れていた悠太郎の鋭敏な耳にも、埴谷先生の禁断の言葉は届かずにはいなかった。どんなに音量を落としたつもりでも、もともとが破れ鐘のようなでかい声であるから、それでようやく人並みの音量にしかならなかったのである。秘密めかしたつもりで埴谷先生が告げた言葉は、「Saturdayは、さあ勃ったでー」というものであった。いったいなぜこんな男をさやか先生は選んだのだろうと悠太郎は思った。こんな男が留夏子さんの担任であることは許し難いとも思った。しかしあの汚らわしい言葉を、俺は本当に聞きたくなかったのだろうかと悠太郎は自問した。さやか先生も留夏子も自分も、人間は誰であれ暗い肉であらざるを得ないという考えは、悠太郎の心を限りなく重くした。
さて英語の時間になって、一年生の生徒たちが――とりわけ男子たちが――何かを隠してでもいるかのように嫌らしくにやにやしているのを、金子芳樹先生は怪しんだ。怪しみはしたが、しかしムースで前髪をイワトビペンギンのように逆立てた金子先生は、つまらない怪しみを吹き払おうとでもするかのように、颯爽たる声で「Hello, everyone!」と呼びかけた。だが「Hello, Mr. Kaneko!」と答える生徒たちの声には、やはり嫌らしい笑いが含まれていたので、金子先生は探るように、尋問するように「How are you?」と問うた。しかし「Iʼm fine!」と答える生徒たちの声からは、何事が隠されているのかを知ることはできなかった。疑わしげに首をかしげながら金子先生は、持参したCDラジカセで音楽を流した。授業の最初に英語の歌をうたわせることで、生徒たちをこの言語に親しませようと意図した金子先生が、このとき選んでいたのはビートルズの〈Yesterday〉であった。英語の歌詞とその日本語訳が記された対訳のプリントは、何回か前の授業のときに配られていた。
みんなは歌ったが、大多数の生徒たちにとっては歌をうたうことも恥ずかしければ、外国語を発音することも恥ずかしかった。二重の羞恥心のためにあまり声を出さないみんなのなかにあって、楽しげに歌う悠太郎のバリトンの声は金子先生の注意を引いた。悠太郎にしてみれば、過ぎ去った昨日を懐かしむこの歌の哀愁が好ましく感じられたので、そこに自身が抱いている過去への哀惜を投影することに力を尽くしたのである。ああ、あの頃は困ったことなんて遥か彼方にあるように思われた。照月湖の水は澄んでいて、湖畔は賑やかだった。あの頃はまだバブルが弾けてもいなければ、異常気象もなければ、アオコもなかった。今ではそれらすべての禍が、湖と湖畔に留まっているかのようだ。ああ、あの頃が懐かしい――。そんなことを思いながら悠太郎は、金子先生の日本語訳に頼りつつ、歌詞の意味を音楽と結びつけることに意を用いた。英語の歌詞の上に記された片仮名には、ほとんど頼っていなかった。あるくだりで悠太郎は一語一語段階的にクレッシェンドし、抒情的にややテンポを揺らし、代名詞の母音を短く切り上げて、その分助動詞を緊張感豊かに発音した。
歌が終わると教科書に取りかかる前に金子先生は言った。「真壁くんの〈Yesterday〉はどんどん冴えてくるなあ。特に〈彼女は言おうとしなかった〉のところがよかったよ。一年生の一学期にこんなことを教えるのはまだ早いんだが、みんな一応は聞いてくれ。wouldというのはwillの過去形だ。willというのは何々しようとするという意味だ。その過去形に否定のnotがついて wouldnʼtだ。つまり何々しようとしなかったという意味になる。彼女は言おうとしなかった。こういうwillの使い方は、特に拒絶のwillと呼ばれる。どうしても何々しようとしないという意味だ。ぼくは何か間違ったことを言ったの? もしそうなら、そう言ってほしい。きみがぼくと別れて立ち去らなければならない理由を言ってほしい。彼はそう彼女に頼んだんだろう。懇願し哀願したんだろう。それでも彼女は言おうとしなかった。別れの理由をどうしても言おうとしなかった。それだけの思いが込められている。まさか真壁くんは、もう拒絶のwillを知っていてあんなふうに歌ったのか?」物問いたげな大きな目を黒々と見開く悠太郎に、みんなの注目が集まった。「いいえ。私はそこまでのことは知りませんでした。ただ音楽がそうなっているから、歌詞と曲がそう結びついているから、そう歌うんです」と悠太郎は答えた。「そうか。まあいずれにせよ見事な発音とリズム感だ。これは二年生の佐藤さん以来の英語使いになるかもしれないな」と金子先生は言った。「だが真壁くんの歌いぶりは、ビートルズというよりクラシックの歌曲みたいだな。音楽の棚橋先生も教え甲斐があるだろう」
さて音楽の棚橋晶子先生は、金子先生と同年輩であるにもかかわらず、目は泣き腫らし、頬はむくみ、口角は下がりっぱなしで自暴自棄に陥っており、厚い化粧はしばしば涙に溶けていた。棚橋先生は荒々しく踏み鳴らす足で、ずんぐりむっくりの体を運んで音楽室にやって来ると、内巻きワンカールボブの髪を振り乱しながらピアノを弾いた。荒れに荒れている現在の三年生たちが入学してきたその年度から、この中学校での仕事が始まったことは棚橋先生の不幸であった。何かにつけては中指を突き上げる中島猛夫のような手合いがわんさかいるとあっては、棚橋先生には音楽の授業を成り立たせることができなかった。ピアノを弾いて歌をうたわせることも、アルトリコーダーの指遣いを教えることも、クラシック音楽を鑑賞させることも、文化祭での合唱コンクールに向けて曲を練習させることも、ことごとく失敗に終わった。音楽教師としての職務への熱意を、棚橋先生は急速に失ってしまった。よほどまともな留夏子たちの学年が入学してきても、棚橋先生は生徒たちに心を開こうとはしなかった。どれほどペトラが合唱曲の伴奏を弾いて同級生をピアノのまわりに集めようとも、どれほど留夏子が凛々たるソプラノの声で歌い、またアルトリコーダーで〈「グリーンスリーヴス」による変奏曲〉を巧みな装飾音とともに吹こうとも、棚橋先生にとって生徒たちは十把一絡げに敵でしかなかった。悠太郎が後で知ったところでは、そんな棚橋先生をなお仕事に繋ぎとめていたのが、なんと英語の金子芳樹先生への恋心だというのである。棚橋先生は女子ソフトテニス部を、金子先生は男子ソフトテニス部をそれぞれ顧問として指導していたが、部員たちを引率して大会に出掛けたとき棚橋先生は、ハムとレタスとエッグフィリングがたっぷり挟まったサンドイッチを余分に作ってきて、「ほれ、食え! どんどん食え!」と金子先生に勧めていたという。そうしたことを陽気な戸井田アオイさんや、幸薄そうな諸星美雪さんといったテニス部の生徒の親たちが噂していた。それを聞き知った秀子が悠太郎に教えたのである。サンドイッチの件は一学期もだいぶ進んでからのことであった。ともあれ棚橋先生の恋はどうやら望みがなさそうであった。そうしたわけで棚橋先生は、悠太郎がびっくりするような荒っぽいタッチで〈花の街〉のピアノ伴奏を弾いたのである。色彩豊かな夢を広げるはずの前奏からして、もう台無しであった。それでも悠太郎はめげずに歌った。
有節歌曲という言葉を悠太郎はまだ知らなかったが、それでも同じメロディーの繰り返しのなかで、歌詞の意味に即して各詩節を歌い分けることが、表現上の課題であることは感じ取れた。第一詩節から第二詩節にかけて高まった明るい幸福感が、春の夕暮れを歌う第三詩節で淋しさに変わるところは、とりわけ好ましく思われた。なるほどこれは歌曲なのだと悠太郎は改めて考えた。こうしてみんなで歌ってはいるが、本来これは独唱曲なのだ。みんなで歌おうとか、みんなで旅立とうとか、やたらと「みんな」を押しつけてくるクラス合唱曲とは違って、独唱歌曲はひとりでいることを認めてくれる。「みんな」と一緒に輪になれない「ひとり」の淋しさという内面的な感情を、歌曲は表現できるのだ。そうだとすれば歌曲とは、俺にとって是非とも必要なものではないか――。悠太郎がそんなことを考えていると棚橋先生が、「作曲者の思いが教科書に載っている。各自が適当に読んでおけ!」と乱暴に言った。その声はずんぐりむっくりの体によく共鳴したが、歌うことよりも怒鳴ることによほど多く使われた以上、音楽教師としては使い方を間違えているわけであった。さて悠太郎は教科書に目を走らせた。まだ戦後間もない荒廃のなかで「花の街」を歌う詩人に、作曲家は初め不審を覚えたが、やがてその詩に込められた祈りに共鳴してこの曲を書いたと、そこには述べられていた。悠太郎は作曲家のこの文章から、力強い励ましを受け取ったように思った。芸術表現は、見たり聞いたりできる現実の引き写しであってはならないのだ。芸術表現は、現実を超克するもうひとつの現実であり得るし、もうひとつの現実であらねばならないのだ。ひとつの歌曲でさえもうひとつの現実であり得るし、もうひとつの現実であらねばならないのだ――。
だが悠太郎にとって真に決定的な歌曲体験となったのは、シューベルトの〈魔王〉の鑑賞であった。その曲の不気味なほど静謐で戦慄的な美しさは、ほとんどこの世のものとは思われなかった。いつか夏休みのある日、佐藤陽奈子先生がピアノを弾きながら歌ってくれたバッハの〈主よ、人の望みの喜びよ〉以来、初めて聴くドイツ語の歌であった。教科書には前奏の楽譜と、伴奏を省いた歌声部の楽譜だけが載っていた。前奏から右手にオクターヴで連打される三連符が続いていた。こんなものを弾いたら腱鞘炎になるではないかと悠太郎には思われた。しかしこうして音楽室に再生された録音では、ピアニストは苦もなく弾いているように聞こえる。そして歌い始めたバリトン歌手のなんという声だろう! 硬質な子音と豊かな母音で織り成された冴え渡るドイツ語を響かせながら、伸縮自在なその声は語り手と父親と息子と魔王を、寸分の隙もなく完璧に歌い分けていった。しばしば繰り返される呼びかけのフレーズについては、日本語訳が教科書に載っていた。風の強い夜に、小さな息子を抱いた父親が馬を走らせている。オクターヴで連打される三連符は、その馬の荒々しい蹄の音を表しているということであった。病気の息子は幻覚を見ている。父親は息子を現実に引き戻して落ち着かせようとする。しかし魔王が息子を誘惑する。坊や、一緒に行こう。一緒に楽しい遊びをしよう。岸辺には色とりどりの花が咲いているよ。わしの母さんは綺麗な着物をたくさん持っているよ。わしの娘たちにおまえの子守をさせよう。わしの娘たちに子守歌をうたわせよう――。その誘惑の歌のなんという美しさだろう! しかし三度目に魔王は本性を露わにする。わしはおまえが大好きだ。おまえの美しい姿にそそられる。おまえが乗り気でないなら、わしは力ずくだぞ! いよいよ高まった声で息子は絶叫する。魔王がぼくに痛いことをしたよ! 父親はぞっとして馬を全力で走らせる。どうにか家に着いたときには、腕のなかでその子は死んでいた。最後の「war tot」というのが、「死んでいた」という意味だと教科書には載っていた。ゲーテの詩によるシューベルトの歌曲〈魔王〉は、美しくも暗い嵐のように悠太郎のなかを吹き抜けていった。それを歌ったバリトン歌手の名前もまた教科書に載っていた。長い名前であったが、悠太郎はその名を心に刻み込んだ。ディートリヒ・フィッシャー゠ディースカウ。悠太郎はその名をどこかで見たことがあった。それはどこであったか?
それは梅子が持っていたレコードのコレクションのなかであった。まだ悠太郎が中学校への入学を前にした春休みのうちに、真壁の家にレコードプレーヤーつきのステレオコンポが据えつけられた。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、ふっるーいレコードをまた聴いてみたくなったよ。悠太郎もピアノのお勉強がだいぶ進んだからウッフフ、いろいろな音楽を聴くことはためになるんじゃないのかい?」と希望したのである。西洋音楽をそれほど好まない千代次ではあったが、孫の教育がそういう方向へ進み始めた以上、今さらそれを阻むわけにはゆかなかったから、自分の部屋から遠い悠太郎の部屋にそれを置くという条件で了承した。梅子は喜色を満面に浮かべながら、押入れの奥から古いレコードのコレクションを取り出した。これは実に久し振りのことであった。昔あったステレオレコードプレーヤーは、小さかった悠太郎が歩きまわるのに危ないので処分された。そのとき押入れの奥深くしまい込まれたレコードが、十年以上の歳月を経た今こうして取り出されたのである。そのコレクションはさして膨大というわけではなかったが、田舎の中学生がクラシック音楽の初歩を体験するには、差し当たり充分に役立つものであった。バッハの管弦楽組曲があった。モーツァルトの交響曲第四十一番《ジュピター》があり、歌劇《フィガロの結婚》のハイライトがあり、レクイエムがあった。ベートーヴェンの交響曲第五番《運命》と第六番《田園》と第七番と第九番《合唱つき》があった。メンデルスゾーンの交響曲第三番《スコットランド》と第四番《イタリア》があった。ベルリオーズの《幻想交響曲》があった。ショパンのピアノ協奏曲第一番と第二番があった。ワーグナーの管弦楽曲集があった。ブラームスの交響曲第一番と第四番があった。ブルックナーの交響曲第八番があった。ギリシャの歌姫がうたうイタリア語やフランス語のオペラ・アリア集があった。そうしたレコード盤をしばしば悠太郎は好んで聴いた。回転するターンテーブルに乗ったレコード盤の溝に、トーンアームの先の針が落ちて音楽が鳴り始めると、吸い寄せられるように梅子が部屋にやって来て、孫と一緒にそれを聴いていた。
ステレオコンポが据えつけられたばかりの頃、何から聴き始めたらよいかと悠太郎が尋ねたとき、梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、メンデルスゾーンさんから聴きなさい。ふっるーいお城を訪ねたときの曲」と答えた。それはメンデルスゾーンの交響曲第三番を指していた。梅子はスコットランドという固有名詞を、どうしても憶えられないのであった。悠々たる遅いテンポで奏でられる愁いを帯びたその曲に、梅子も悠太郎も好んで耳を傾けたが、その曲でもほかの多くの曲でも、盤面の傷や黴のために、しばしば音飛びが生じるのは惜しいことであった。またあるときはバッハの管弦楽組曲第二番ロ短調を、ふたりはそうして聴いていたことがあった。序曲がありロンドがありサラバンドがあった。ブーレがありポロネーズがあった。そしてメヌエットが続いた。フルートを主役にしたその組曲は典雅にして骨太であり、華麗にして剛毅であった。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らすことなく、「光子さんを思い出すねえ。ひばりが丘で元気にしているかねえ」と言った。悠太郎の脳裏にも、観光ホテル明鏡閣の社員食堂で初めて会ったときの三池光子さんが思い浮かんだ。優雅な手つきで煙草を吸っていた光子さんは、アイシャドウの濃い目をぱちくりさせながら、月光に照らされた黒天鵞絨のような艶のある低音の声で、「そうだ、ユウちゃん、お花は好き? 湖のほとりに水仙が咲いたわよ。私と一緒に水仙を見にゆきましょう」と言うが早いか、明鏡閣のロゴが入った陶器の灰皿で煙草を揉み消すと、やおら立ち上がったのであった。灰色がかったボブショートの髪をした、ひょろりと背の高い撫で肩の光子さんを、悠太郎はどんなにか慕わしく思ったことであろう。「水仙」と言うとき「ス」の音をいちばん高くして、そこから流れ落ちるようなイントネーションで発音するその言い方も、なんと懐かしいことであろう――。組曲は終曲のバディネリで、午後の湖のように光を撒き散らしていた。
そんなレコード盤のなかにあって奇跡的に無傷で保存されていたのが、ディートリヒ・フィッシャー゠ディースカウによる二枚組のシューベルト歌曲集だったのである。中学校の音楽の時間に起こった圧倒的な〈魔王〉の体験まで、悠太郎はそのレコードを聴いてみたことがなかった。オーケストラの壮麗な響きに比べれば、バリトン独唱にピアノ伴奏なんていかにも地味でつまらなそうに思われたし、いくら歌詞対訳がついているとはいえ、ドイツ語という未知の外国語をわざわざ聴こうとも思わなかった。ところが今や悠太郎にとって、その二枚組はコレクション中の至宝となった。そこには〈野薔薇〉があり〈夜の歌〉があった。〈魔王〉があり〈連祷〉があった。〈さすらい人〉があり〈死と乙女〉があった。〈音楽に寄せて〉があり〈ます〉があった。〈春の信念〉があり〈水面に歌う〉があった。〈きみはわが憩い〉があり〈夕映えのなかで〉があった。〈聴け、聴け、ひばり〉があり〈シルヴィアに〉があった。〈緑野の歌〉があり〈星〉があった。これを要するに、シューベルト歌曲の深遠なる小宇宙がそこにはあったのである。外国語で歌われる声楽曲が苦手だという理由から、梅子が《フィガロの結婚》のハイライトやギリシャの歌姫によるオペラ・アリア集と同様ほとんどこのレコードを聴かず、無傷のままに保っておいてくれたことは僥倖であった。悠太郎は毎日毎晩これを聴いた。食い入るように歌詞対訳を見つめながら、フィッシャー゠ディースカウの伸縮自在なバリトンに聴き入るうちに、いつしかドイツ語の発音規則だけはおぼろげながら見えてきた。そのうち悠太郎はフィッシャー゠ディースカウの歌に声を合わせて一緒に歌うようになっていた。音楽の教科書に載っている〈魔王〉の楽譜に、ドイツ語の歌詞を書き込みさえした。〈魔王〉以外の収録曲でとりわけ悠太郎を喜ばせたのは〈水面で歌う〉であった。夕日を浴びて波立ちきらめく水面を、白鳥のように小舟が滑ってゆく。その小舟のように魂もまた滑ってゆく――。跳ね上がっては滴り落ちるような細やかな十六分音符が連続するピアノ伴奏の右手は、水面のきらめきを絶え間なく描き出しているかのようであった。それは当然のことながら、悠太郎に照月湖を思わせずにはいなかった。今は亡き入江紀之が、まだ小学校一年生だった俺をボートに乗せてくれたのは、もう六年の昔だ。昨日も今日も明日も消えてゆく。あの慕わしい湖の騎士が消えていったように、俺もまたいつかは消えてゆくのだ。どのようにしてかは知らないが、消えてゆくことだけは間違いない。あの懐かしい湖も消えてゆくのだろうか。賑わった湖畔も滅びてしまうのだろうか。湖畔に集った人々がみんな消えてしまったら、誰が照月湖のことを語るのだろうか――。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
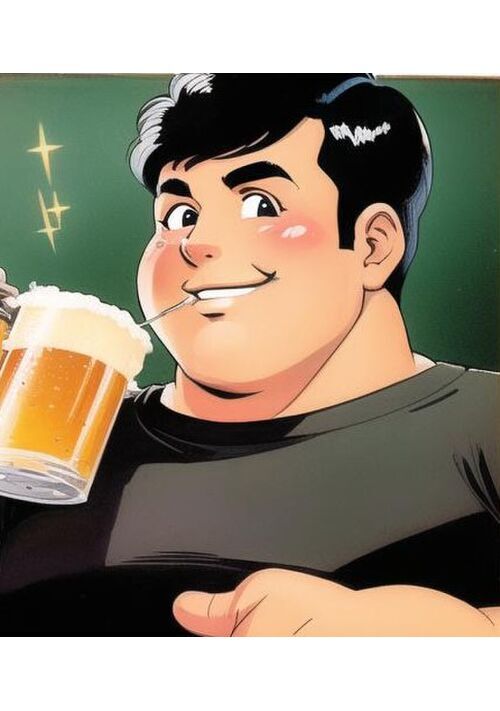
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















