36 / 73
第十二章 人の望み
三
しおりを挟む
そうだった、そんなこともあったと悠太郎は、右手首にあるミサンガの環を見つめながら、人の願いや望みについて、なおもあれこれと考えをめぐらせた。ぼくはお祖父様の望んだような孫ではないと、悠太郎は改めて思い出した。留夏子が鼓笛隊でベルリラを叩いた運動会の後で、例によって成績が振るわなかった悠太郎を、千代次は「俺が跡取りに望んだのは鋼のような男だ!」と叫びながら殴りつけたからである。「俺の跡取りは、誰より頭がよくて、誰より体がよくて、誰より速く走る強え男だ! けっしておめえのような弱え愚図ではねえ!」と千代次は唾を飛ばしながら、殴り倒した孫に罵声を浴びせた。祖母の梅子も母の秀子も、倒れた悠太郎を睨みつけて威圧した。しかし悠太郎は起き上がると、切れた唇から流れる血を手の甲で拭きながら、「鋼は頭がよいのでしょうか。鋼は速く走るのでしょうか」と冷静な声で問うた。悠太郎が物問いたげな目で、千代次の極度に細い目をまっすぐに見据えると、祖父の歪んだ顔がいっそう引きつった。「何だと? おめえはまた俺に口答えしようちゅうのか!」と千代次は、紫色がかった唇をわななかせながら言った。「比喩の適切さについて疑義を呈しているのです」と十一歳の孫は答えた。「うるせえ! 屁理屈を抜かすな!」と祖父は叫んでまた孫を殴り倒し、「走るのは遅え、野球部には入らねえ、空手道場からは突き返される、その弱え愚図が減らず口だけは一人前だ! おめえは俺のことを考えたことがあるのか? おめえがマラソン大会や運動会で駄目なところを見せるたび、どれほど俺に恥をかかせているか考えたことがあるのか? おめえがどれほどわが家の名を辱めているか分かっているのか?」と泡を吹きながら喚き散らした。しかし孫は再び起き直ると祖父の細い目をまっすぐに見据え、冷静な声で言上した。「はい、そのことは幼い頃からしばしば考えております。お望みの孫に恵まれなかったお祖父様は、まことにお気の毒だと存じます。私は精一杯走っておりますが、こういうことは生まれつきで差がつくものではないでしょうか。私がどんなに努力したとて、佐原康雄くんのように走れるものでしょうか。及び難きものは諦めるのも、また肝要かと存じます。どうか私の申し上げることをお聞き分けになり、あるがままの私に安んじていただきたく存じます」
「ふざけるな!」と叫んだ千代次は、悠太郎の胸倉を掴むと壁に叩きつけた。「おめえのその目も減らず口も、思えばおめえの忌々しい父親にそっくりだ! 没落士族が町人を見下しおって! 何があるがままだ! おめえのような者は生まれてきてはならなかったんだ! ああ、早く遺伝子の研究が進んで、おめえのような愚図がひとりも生まれてこねえようにできねえもんかなあ! それより父親の承諾を得ない娘の結婚など厳禁されるように、憲法も民法も改正せにゃならねえ!」とよだれを垂らしながら喚いた千代次は、炬燵板の上から「お墓の下」と悠太郎が密かに名づけた木製の円い茶盆を掴み取った。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、それ見ろ秀子、わったしの言った通り悪魔の性質が出てきたよ! 矯め方が足りなかったよ! それ叩き直せ! こんなもなあ! こんなもなあ! こんなもなあ!」と悠太郎を足蹴にした。秀子は下膨れの顔をぶるぶるとふるわせながら、「お祖父様の血圧が上がったらどうしてくれるの! おまえのせいで私まで悪く言われたらどうしてくれるの! 悠太郎、お願いだからもっと速く走って! お願いだからもっと速く走って!」とひとり息子に繰り返し平手打ちを浴びせた。「泣き叫んで赦しを乞え! お祖父様、申し訳ございませんと泣き叫んでみろ! 言えねえのか? これでもか! これでもか! これでもか!」と千代次は、「お墓の下」の平たい面で悠太郎を叩きまくったが、次の瞬間には薪割りの斧のように、茶盆の縁で鋭い一撃を加えるというひと工夫を案出した。この一撃を脳天に浴びて悠太郎の意識は、湖の明るく澄んだ水面のように揺らめいた。「ふん! 目醒めていても弱えし、ちょいとばかり叩けば気を失うか! こんな愚図には意識なんざ、あってもなくても同じようなもんだ! おい秀子、おめえの与太息子を物置へぶち込んでおけ! 来年の運動会で手柄を立てると誓うまで、けっして出すじゃねえぞ! こいつが来年の運動会で目覚ましい手柄を立てなけりゃあ、おめえたち親子は俺のうちから出ていってもらう。泥水でも小便でも啜って生きろ!」と千代次は、壁際に伸びた孫を指さして吐き捨てた。
そんなことがあってから何日も経たないある日の集団登校では、ハイロン班の班長である石井観光農園の尚美が熱を出して休んだので、スケちゃこと早川大輔が、悠太郎の待機地点である三本辻にひとりで現れた。「悠太郎、ここで会ったが百年目! なぞなぞだ。どこの家にも四つあるもの何だ?」と謎をかけるスケちゃに、悠太郎は物問いたげな目を見開いて一瞬考えた後で「しうち?」と答えた。この答えにスケちゃは、黒いランドセルを背負った身をのけぞらせて大笑いし、「そういう答えは初めて聞いた。まったく考えてもみなかった。仕打ちか、こりゃ傑作だ。俺をここまで笑わせるとは、悠太郎もなかなかやるな」と愉快そうに言った。しかし右手にあるゴルフ場の遥けさがしんとして迫る道で、先に立って歩いていた大輔が立ち止まって悠太郎に向き直った。先程までの笑いはすっかり消え、カモメのように繋がった太い眉毛はひそめられていた。「いや、考えてみれば面白がって笑っている場合ではない。仕打ちなどという言葉は、普通の小学校五年生が日常的に言うものではない。悠太郎、何かあったか? 家の人に何かひどい仕打ちでも受けたか?」と大輔は問うたが、悠太郎は睫毛の長い目を悄然と伏せながら首を横に振るばかりであった。日常茶飯事をスケちゃに話して何になろう? しかもスケちゃは小学校を卒業したら、この町の西の中学校には進まず、どこかの私立中学校へ行くということだから、どの道もうすぐ会えなくなるのであった。家族から受けた仕打ちの痛みにも増して、そのことが心をしんとした淋しさで満たしたので、悠太郎は何も言えなかったのである。
無言のままふたりは三角屋敷ことホテル・スワンズハートの前に立ち止まって、入江いづみを待っていた。これも日常茶飯事であったが、夏休みのラジオ体操に出てこられないいづみは、平素の通学でもなかなか出てこなかった。近くに時計はなかったから、腕時計など持ち合わせない小学生にとっては、これはなかなかに困った事態であった。いったい今まで何分待ったのか、今から学校で朝マラソンが始まる時間まであと何分あるのか、小学生たちは目安もなしに、勘を働かせて判断を下さなければならなかった。ふたりはしばらくのあいだ、まだほとんど緑の樹々のざわめきと鳥の声を聞いていた。通学路に面した通用口のドアから、いづみが眠たげな気怠さを瞼に表して姿を見せるのを、悠太郎は今か今かと待ったが虚しかった。「また寝坊か。早寝早起き病知らずというが、いづみには相変わらずそれができていないようだな。心配だな。悠太郎も来年は班長だろうから、苦労しそうだな」とスケちゃは言い、「よし、今日は班長に代わって俺が判断する。見限って先へ進む」と決断を下した。
さてハイロン班に合流すべき人はもうひとりいた。それは小学校の至近ともいうべき近くに家がある、六年生の竹渕智也であった。今年度から転校してきた智也の両親は、北軽井沢市街地でガソリンスタンドを経営していた。智也もいづみほどではないにせよ、しばしば通学班を待たせた。この場合もやはり寝坊なのであるが、それはいづみの場合ほど病的なものではなく、単に学校が近いことから来る気の緩みであって、中学校に自転車で通うようになれば改善することが見込まれるものであった。楢の樹の林を背にして大輔と悠太郎が待っていると、後から「交通安全」と書かれた黄色い旗を振り振り、大屋原第二集落の通学班を率いてきたマッシモ・ジョルジョが――というのも英語のジョージはイタリア語のジョルジョであることに加えて、マッシモはイタリア語で「最大の」を意味すると、苦学の労働者である芹沢カイの父親が、草軽バスのエンジンの爆音のように言ったことが広まったので、あの真霜譲治はそう呼ばれるようになっていたのである――、どすの利いた大声で「おいブチ公! てめえいつまでも寝てやがると、目ん玉が腐っちまうぞ!」と家に向かって呼びかけ通り過ぎていった。
「オハイオ州からおはようさん!」と言いながら玄関のドアから颯爽と現れたのは、しっかりとした顎の骨格を持ち、シティーボーイ風の前髪をはらりと風に流した少年であった。「待たせたな。化石燃料のような眠りから覚めたところだ。いやあ、いつも思うんだが、石油を持っている国は強い。産油国は実に強い。敵に回すわけにはいかない。サウジアラビアとも仲良くせねばな。アメリカのオハイオ州にも大きな石油会社があるぞ。日本にももっと大きな油田があればなあ!」と、ブチ公と呼ばれた竹渕智也はよく響く声で言った。「智也、きみのは文字通り油断だな。いくら学校が近いとはいえ、油断大敵火がぼうぼうだ」と大輔が得意の諺で混ぜ返し、「ところで智也、なぞなぞだ。どこの家にも四つあるもの何だ?」と問いかけた。智也はちょっと考えてから「東西南北!」と答えたが、果たしてそれが正解であった。悠太郎はしかし、石油はいつ枯渇するのだろうと幼稚園の頃心配したことを思い出していた。
そんなこともあったと思いながら悠太郎は書き終えた日記帳を閉じると、ミサンガを右手首から外して学習机の引き出しにしまった。明日のピアノ発表会に備えて最後の練習をするには、そういうものが手首にあるのは邪魔であった。いったいピアノがうまくなりたいというのもぼくの願いと言えるのかと、悠太郎は小学校の教室での真花名との会話を思い出しながら考えた。真壁の家の名を辱しめまい、お母様に恥をかかすまいとして、懸命に取り組んでいるだけではないのか。そうであればこそ、実力よりはいくらか背伸びして発表曲を選んでしまったのではないか。だがここまで来てしまったからには、悩みも迷いも振り切って指を動かすよりほかになかった。悠太郎は『ソナチネアルバム』を開くと、暗譜したその曲の譜読みに改めて取り組み、音符のフレージングや強弱記号や発想記号を最終確認しつつ、最初から最後まで曲をさらった。それは一九九四年十二月の第二土曜日のことで、学校が休みであった日中にも練習はしており、陽奈子先生と弾くことになっている連弾曲はもう充分だと思えたが、独奏曲のほうには不安が残っていたのである。その不安は単に小さな失敗をするかもしれないということ以上の、家族にまつわる暗く苦いものであった。
だが明くる日曜日の冷え込んだ昼下がりに、秀子の運転する自動車で隣町へと西を目指すあいだ、悠太郎の暗い不安は澄んだ冬の光のなかで、少しずつ薄らいでいった。とうに穫り入れの終わった広いキャベツ畑の向こうに、ほぼ真北から見える浅間山の雪白の山容は、悠太郎たちが住む東北麓の町から見えるよりも大きかった。親子はペンションの案内板から、目指す会場の名前を見て取った。音楽ペンション〈アマデウス〉というのがその宿屋の名であった。噴煙を吐く雪白の浅間山を真南に望む〈アマデウス〉の駐車場に降り立ったとき――その駐車場は十五台分あった――、素晴らしいひとときへの予感で悠太郎の胸は満たされた。コの字型に南へと突き出した東西の翼部を持つ二階建てのペンションの外壁は、ほとんど白に近いグレーであった。樅の樹々が緑色に針葉を茂らせるあいだを通って石段を三段昇れば、二階中央のバルコニーを支える柱のあいだに、白い玄関扉があった。悠太郎はアンティーク風の金色のハンドルを押し下げて扉を開き、発表会が催される食堂ホールを目指した。子供たちやその親たちが、それぞれに着飾って集まってきていた。子供たちが前列で待機し、親たちが後列で鑑賞する客席の左手の明るい窓辺には、飾り棚の上にオーストリア産のワインの空き瓶が一列に並べられ、それらの瓶の青いガラスを透かして黄色い電飾が、いかにもクリスマスを待つ季節に相応しく明滅していた。磨き上げられて黒く光るグランドピアノが置かれた南側の、レースのカーテンで覆われた窓のある壁際には、発表会の開催を祝って贈られたスタンド花が、色とりどりに咲き匂っていた。赤いベルベットのドレスを着た陽奈子先生は、生徒たちやその親たちと挨拶を交わし、また会場設営のために何くれと指図しつつ動きながらも、背筋をまっすぐに伸ばして女王然としていた。ピアノを弾かない留夏子もまた会場に来ていて、白のシャツにベルトのついた黒のロングスカートという地味で清楚な出で立ちで、母親の指図に従って何くれと立ち働いていた。母親のピアノ教室が初めて開く発表会で、留夏子がそうせずにいられないのは、バイエルも終わらせずに練習を放り出したことから来る負い目のゆえに違いなかった。これでも留夏子は陽奈子先生の生徒たちに、よきお姉さんとして結構慕われていたのである。このときも留夏子は大屋原のどこかから習いに来ている女の子に――その子は白のレース襟つきセーターと、ピンクのスカートと、白のハイソックスで着飾って、髪を三つ編みにしていた――、「いつもうちのお母さんと遊んでくれてありがとう。今日はとても可愛いわよ」と言葉をかけては、陽奈子先生から「ちょっとルカ、何を言っているの」と叱られて、その子を笑わせていたものであった。
そんな平和な光に満ちたホールのグランドピアノを次から次へと、スイス民謡の〈静かな湖畔〉や、イギリス民謡の〈灯台守〉や、同じくイギリス民謡の〈ロング・ロング・アゴー〉や、ワルトトイフェルの〈スケーターズ・ワルツ〉や、エステンの〈人形の夢と目ざめ〉や、ベートーヴェンの〈エリーゼのために〉や、ブルグミュラーの〈貴婦人の乗馬〉が、丸々とした幼い手や、青白く静脈の浮き出た繊細な少女の手や、早くも頑丈になりかけた少年の手によって、あるいはたどたどしく、あるいは滑らかに、あるいは華やかに、あるいは力強く通り過ぎていった。出場する生徒としては最年長の悠太郎もまた黒のカーディガン姿で、いくらか緊張しながらベートーヴェンの〈「うつろな心」による変奏曲〉を、毛深いながら美しい手の指で通り過ぎさせた。パイジェッロの歌劇《水車小屋の娘》から主題を取って、ベートーヴェンが作曲したというその変奏曲は、『ソナチネアルバム』に収録されていたのである。まず簡潔に主題を提示し、それを次々に変形し労作してゆく変奏曲という形式に、悠太郎は多大な興味を抱いた。ト長調の主題の音が細分化され、多様に装飾され、同主短調に転調までして積み重ねられてゆく変奏の生成発展の根底に、流れ去らずに留まるものの姿が確かに見えるような気がした。それで悠太郎はこの変奏曲を通じて、変奏曲全般を愛好するようになっていたのである。短調から長調に戻った後での、きらめきが走るような速い音階は、聴く人が聴けば危なっかしくはあったであろうが、それでも悠太郎は手に余りがちなその曲を、堂々と締め括って拍手喝采を浴びた。連弾の部は多くの生徒が陽奈子先生と弾くことになっていたから、独奏の部よりずっと気楽であった。陽奈子先生が悠太郎に与えたのは、ブラームスの〈ハンガリー舞曲第五番〉を易しく編曲したものであった。暗い情念を帯びた二拍子のチャールダーシュを、師弟は息を合わせてテンポと強弱を変化させながら楽しそうに弾いた。この曲で陽奈子先生はハンガリー留学時代を追憶しているのだろうと悠太郎は推察していた。セコンドの低音部で煽り立てる陽奈子先生のリズムに釣り込まれて、悠太郎はプリモの高音部で乗りに乗りながらも、歳月や運命の不思議を思わずにはいられなかった。かつてブダペストでピアノを学んでいた若い女性が、六里ヶ原で母となりピアノ教室を開き年を重ね、今この音楽ペンションでハンガリーの舞曲を、ぼくと連弾しているのだ――。
ペンションのご主人は銀色のフルートを吹く人で、フルート演奏の前にご主人は挨拶を述べた。黒のタキシードに身を固めたアマデウスおじさんは、髪の毛の生え際の後退が目立つ中年男性であったが、皺の寄った目尻をにこにこ笑わせながら言った。「皆さん、本日はお集まりくださってありがとうございます。どなたのピアノも素敵でした。この浅間山の麓で音楽ペンションを開いてよかったと、今日ほど強く思えた日はありません。ところでこのペンションに私がつけたアマデウスというのは、作曲家モーツァルトの名前です。私はいつの頃からかモーツァルトの音楽が好きで好きで、おそらくそのせいでしょう、髪の毛の生え際までほらこの通り、M字型になってしまいました」とアマデウスおじさんが言うと、子供たちにも大人たちにも乱反射する湖のような笑いが広がって光り輝いた。「プログラムにもありますように、これから吹くのはモーツァルトのフルート・ソナタK一二です。Kというのはケッヘル番号といって、ケッヘルさんという植物学者がモーツァルトの作品を研究して、作曲順につけた番号です。一二という番号は若いでしょう? モーツァルトはこのソナタを作曲したとき、なんと八歳でした。まさにアマデウスという名前が意味する通り、神に愛された人です。天才です。しかしK六二六のレクイエムを未完成のまま残して、三十六歳で亡くなりました。それに引き替え私などは平凡に生き長らえた、髪に愛されないM字型です」とアマデウスおじさんが語ると、また湖の乱反射のような笑いが、次いで陽奈子先生のピアノに伴奏された銀色のフルートの響きがホールを満たした。永遠の子供が光のなかで遊ぶようなイ長調のソナタを吹きながら、アマデウスおじさんは歯茎を剥き出しにして息継ぎをしたが、それを見た悠太郎は馬が臭いを嗅ぐときのようだと思った。フルートが終わって、陽奈子先生の講師演奏もアマデウスの名を冠したペンションに相応しく、モーツァルトの〈きらきら星変奏曲〉であった。流れる時のなかに留まるものの姿が見える変奏曲を聴けるとあって悠太郎は喜んだが、今度は主題がどんな子供でも知っているメロディーだけあって、みんなが大いに喜んだのである。陽奈子先生は腕を生き生きと波打たせながら華麗なパッセージを紡ぎ出し、晴れた青空に晴れた青空を重ねるように変奏を積み重ねて大喝采を浴びた。この二曲のモーツァルトの連続を聴きながら悠太郎は、物問いたげな大きな目を見開いて、何かを思い出そうとしていた。忘れていた大切な何かが、思い出せそうな気がしていたのである。
留夏子やみんなが椅子を並べ替えたりテーブルを運び込んだりして、いつしかお茶の会が始まった。アーモンドケーキが皿に切り分けられ、縁に柊の葉やベルが描かれた紙ナプキンがバスケットに敷かれ、そこにチョコレートが盛られ、花柄のティーポットからティーカップへと紅茶が注がれた。やや日の翳った窓辺では、ワインの青いガラス瓶を透かして黄色い電飾が明滅していた。「外は冷えますね。雪になるかもしれません」とアマデウスおじさんが、皺の寄った目尻をにこにこ笑わせながら言った。また真冬が来ると悠太郎は思った。一年生のとき、真冬の体育館掃除はつらかったな。今でこそ掃除の班は学年別になっているけれど、あの頃は縦割り掃除などといってひとつの班を全学年から編成したから、上級生の暴力がひどかった。汚く濁った冷たい水に突っ込んだ手は、今日ここでピアノを弾いた手と同じ手だ。でもこんなに平和で豊かな時間に、ぼくはなぜあんな醜悪なことを思い出すのだろう。なぜぼくはあんなことを乗り越えられただろう。そうだ、あのとき流れていた音楽は、あのとき流れていた音楽は――。
悠太郎は弾かれたように立ち上がると、「もしかしてこういう曲がモーツァルトにありませんか?」とアマデウスおじさんに問い、驚くみんなをよそにしてピアノに向かうと、思い出したイ長調のメロディーを再現して聞かせた。四小節も弾かないうちにアマデウスおじさんが、「ありますよ。正真正銘のモーツァルトです。クラリネット協奏曲ですよ。K六二二ですから、最晩年の傑作です」と即答した。いま悠太郎は燦々たる光が喜戯するような、澄み渡る天空から明るい風が吹き通うようなあの音楽を、はっきりと思い出すことができた。「そうでした。モーツァルト作曲のクラリネット協奏曲でした。ノリくんも……入江先輩も、たしかにそう言っていました」と悠太郎が言うと、留夏子も秀子も陽奈子先生も、紀之のことを知る人はいくらか痛ましげな顔をした。「留夏子さん、ぼくは放送室でこれを探していたんです。探し物が、やっと見つかりました」と報告する悠太郎に、留夏子は「そう。よかったわね。入江先輩との思い出の曲だったのね」と答え、眩しいものでも見るように切れ長の目を細めた。電飾が灯る青いガラス瓶越しに窓の外を見たアマデウスおじさんは、「降ってきました。積もらないうちに散会したほうがいいかもしれません」と提案した。留夏子は陽奈子先生に「お母さん、最後にあれを弾いてよ。主が早く召したもう人の曲、人の望みのなんとか」と要求した。「なんとかってことはないでしょう」と娘をたしなめて立ち上がった陽奈子先生は、「では皆さん、特別にもう一曲お聴きください。バッハ作曲〈主よ、人の望みの喜びよ〉」と言ってピアノに向かった。
鳴り始めたのはなんという浄福の音楽であったことか! 喜びに満ちて空を舞い飛ぶ天使の羽ばたきのように、高音部では三つずつの音が寄り合って音階となり、また離れては分散和音となって、あるときは昇りあるときは降りながら間断なく流れるあいだ、低音部ではほとんど永遠のような悠久の時間が、三拍子の舞曲のステップを踏みながらひとところに留まっているかのようであった。悠太郎も留夏子も、やがて現れる歌詞のないコラール旋律の意味を知っていた。ふたりは今や平明な心境で、ようやく亡き人の非在を受け容れることができた。束の間を生き、出会い、別れ、そして死んでゆく人間が、ともかくも今をこうして生きている。そのことの限りない懐かしさがふたりの胸に溢れた。若死にしたモーツァルトは、バッハのこの曲を聴いたことがあっただろうかと、カトリックとプロテスタントの区別も知らない悠太郎はふと考えた。いや、モーツァルトは永遠の旅の途上で今日この宿屋に留まり、このささやかな音楽の祝祭を初めから終わりまで聴き届けて、また雪の降る天空へと馬車を走らせるのではないか――。窓の外には静かに緩やかに雪が降っていた。あたかもこのペンションのある六里ヶ原が、静かに緩やかに天へと昇ってゆくかのようであった。
ところで悠太郎が誕生日に真花名と話した願い事は、結局叶わずじまいであった。なぜなら色糸が代わる代わる現れるよう巧みに斜め編みされたミサンガが、自然に切れることはなかったからである。悠太郎が発表会で奮闘しているあいだ、真壁の家では梅子がパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、「ウッフフ、家宅捜索」と言いつつ学習机の引き出しを開け、発見した例のミサンガを「お勉強の妨げ」になりそうなほかのものともども、裏庭にあるゴミ燃し場の灰にしてしまったからである。後でこのことを知った悠太郎の虚ろな心には、灰色の冷たい風が吹き過ぎた。
「ふざけるな!」と叫んだ千代次は、悠太郎の胸倉を掴むと壁に叩きつけた。「おめえのその目も減らず口も、思えばおめえの忌々しい父親にそっくりだ! 没落士族が町人を見下しおって! 何があるがままだ! おめえのような者は生まれてきてはならなかったんだ! ああ、早く遺伝子の研究が進んで、おめえのような愚図がひとりも生まれてこねえようにできねえもんかなあ! それより父親の承諾を得ない娘の結婚など厳禁されるように、憲法も民法も改正せにゃならねえ!」とよだれを垂らしながら喚いた千代次は、炬燵板の上から「お墓の下」と悠太郎が密かに名づけた木製の円い茶盆を掴み取った。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、それ見ろ秀子、わったしの言った通り悪魔の性質が出てきたよ! 矯め方が足りなかったよ! それ叩き直せ! こんなもなあ! こんなもなあ! こんなもなあ!」と悠太郎を足蹴にした。秀子は下膨れの顔をぶるぶるとふるわせながら、「お祖父様の血圧が上がったらどうしてくれるの! おまえのせいで私まで悪く言われたらどうしてくれるの! 悠太郎、お願いだからもっと速く走って! お願いだからもっと速く走って!」とひとり息子に繰り返し平手打ちを浴びせた。「泣き叫んで赦しを乞え! お祖父様、申し訳ございませんと泣き叫んでみろ! 言えねえのか? これでもか! これでもか! これでもか!」と千代次は、「お墓の下」の平たい面で悠太郎を叩きまくったが、次の瞬間には薪割りの斧のように、茶盆の縁で鋭い一撃を加えるというひと工夫を案出した。この一撃を脳天に浴びて悠太郎の意識は、湖の明るく澄んだ水面のように揺らめいた。「ふん! 目醒めていても弱えし、ちょいとばかり叩けば気を失うか! こんな愚図には意識なんざ、あってもなくても同じようなもんだ! おい秀子、おめえの与太息子を物置へぶち込んでおけ! 来年の運動会で手柄を立てると誓うまで、けっして出すじゃねえぞ! こいつが来年の運動会で目覚ましい手柄を立てなけりゃあ、おめえたち親子は俺のうちから出ていってもらう。泥水でも小便でも啜って生きろ!」と千代次は、壁際に伸びた孫を指さして吐き捨てた。
そんなことがあってから何日も経たないある日の集団登校では、ハイロン班の班長である石井観光農園の尚美が熱を出して休んだので、スケちゃこと早川大輔が、悠太郎の待機地点である三本辻にひとりで現れた。「悠太郎、ここで会ったが百年目! なぞなぞだ。どこの家にも四つあるもの何だ?」と謎をかけるスケちゃに、悠太郎は物問いたげな目を見開いて一瞬考えた後で「しうち?」と答えた。この答えにスケちゃは、黒いランドセルを背負った身をのけぞらせて大笑いし、「そういう答えは初めて聞いた。まったく考えてもみなかった。仕打ちか、こりゃ傑作だ。俺をここまで笑わせるとは、悠太郎もなかなかやるな」と愉快そうに言った。しかし右手にあるゴルフ場の遥けさがしんとして迫る道で、先に立って歩いていた大輔が立ち止まって悠太郎に向き直った。先程までの笑いはすっかり消え、カモメのように繋がった太い眉毛はひそめられていた。「いや、考えてみれば面白がって笑っている場合ではない。仕打ちなどという言葉は、普通の小学校五年生が日常的に言うものではない。悠太郎、何かあったか? 家の人に何かひどい仕打ちでも受けたか?」と大輔は問うたが、悠太郎は睫毛の長い目を悄然と伏せながら首を横に振るばかりであった。日常茶飯事をスケちゃに話して何になろう? しかもスケちゃは小学校を卒業したら、この町の西の中学校には進まず、どこかの私立中学校へ行くということだから、どの道もうすぐ会えなくなるのであった。家族から受けた仕打ちの痛みにも増して、そのことが心をしんとした淋しさで満たしたので、悠太郎は何も言えなかったのである。
無言のままふたりは三角屋敷ことホテル・スワンズハートの前に立ち止まって、入江いづみを待っていた。これも日常茶飯事であったが、夏休みのラジオ体操に出てこられないいづみは、平素の通学でもなかなか出てこなかった。近くに時計はなかったから、腕時計など持ち合わせない小学生にとっては、これはなかなかに困った事態であった。いったい今まで何分待ったのか、今から学校で朝マラソンが始まる時間まであと何分あるのか、小学生たちは目安もなしに、勘を働かせて判断を下さなければならなかった。ふたりはしばらくのあいだ、まだほとんど緑の樹々のざわめきと鳥の声を聞いていた。通学路に面した通用口のドアから、いづみが眠たげな気怠さを瞼に表して姿を見せるのを、悠太郎は今か今かと待ったが虚しかった。「また寝坊か。早寝早起き病知らずというが、いづみには相変わらずそれができていないようだな。心配だな。悠太郎も来年は班長だろうから、苦労しそうだな」とスケちゃは言い、「よし、今日は班長に代わって俺が判断する。見限って先へ進む」と決断を下した。
さてハイロン班に合流すべき人はもうひとりいた。それは小学校の至近ともいうべき近くに家がある、六年生の竹渕智也であった。今年度から転校してきた智也の両親は、北軽井沢市街地でガソリンスタンドを経営していた。智也もいづみほどではないにせよ、しばしば通学班を待たせた。この場合もやはり寝坊なのであるが、それはいづみの場合ほど病的なものではなく、単に学校が近いことから来る気の緩みであって、中学校に自転車で通うようになれば改善することが見込まれるものであった。楢の樹の林を背にして大輔と悠太郎が待っていると、後から「交通安全」と書かれた黄色い旗を振り振り、大屋原第二集落の通学班を率いてきたマッシモ・ジョルジョが――というのも英語のジョージはイタリア語のジョルジョであることに加えて、マッシモはイタリア語で「最大の」を意味すると、苦学の労働者である芹沢カイの父親が、草軽バスのエンジンの爆音のように言ったことが広まったので、あの真霜譲治はそう呼ばれるようになっていたのである――、どすの利いた大声で「おいブチ公! てめえいつまでも寝てやがると、目ん玉が腐っちまうぞ!」と家に向かって呼びかけ通り過ぎていった。
「オハイオ州からおはようさん!」と言いながら玄関のドアから颯爽と現れたのは、しっかりとした顎の骨格を持ち、シティーボーイ風の前髪をはらりと風に流した少年であった。「待たせたな。化石燃料のような眠りから覚めたところだ。いやあ、いつも思うんだが、石油を持っている国は強い。産油国は実に強い。敵に回すわけにはいかない。サウジアラビアとも仲良くせねばな。アメリカのオハイオ州にも大きな石油会社があるぞ。日本にももっと大きな油田があればなあ!」と、ブチ公と呼ばれた竹渕智也はよく響く声で言った。「智也、きみのは文字通り油断だな。いくら学校が近いとはいえ、油断大敵火がぼうぼうだ」と大輔が得意の諺で混ぜ返し、「ところで智也、なぞなぞだ。どこの家にも四つあるもの何だ?」と問いかけた。智也はちょっと考えてから「東西南北!」と答えたが、果たしてそれが正解であった。悠太郎はしかし、石油はいつ枯渇するのだろうと幼稚園の頃心配したことを思い出していた。
そんなこともあったと思いながら悠太郎は書き終えた日記帳を閉じると、ミサンガを右手首から外して学習机の引き出しにしまった。明日のピアノ発表会に備えて最後の練習をするには、そういうものが手首にあるのは邪魔であった。いったいピアノがうまくなりたいというのもぼくの願いと言えるのかと、悠太郎は小学校の教室での真花名との会話を思い出しながら考えた。真壁の家の名を辱しめまい、お母様に恥をかかすまいとして、懸命に取り組んでいるだけではないのか。そうであればこそ、実力よりはいくらか背伸びして発表曲を選んでしまったのではないか。だがここまで来てしまったからには、悩みも迷いも振り切って指を動かすよりほかになかった。悠太郎は『ソナチネアルバム』を開くと、暗譜したその曲の譜読みに改めて取り組み、音符のフレージングや強弱記号や発想記号を最終確認しつつ、最初から最後まで曲をさらった。それは一九九四年十二月の第二土曜日のことで、学校が休みであった日中にも練習はしており、陽奈子先生と弾くことになっている連弾曲はもう充分だと思えたが、独奏曲のほうには不安が残っていたのである。その不安は単に小さな失敗をするかもしれないということ以上の、家族にまつわる暗く苦いものであった。
だが明くる日曜日の冷え込んだ昼下がりに、秀子の運転する自動車で隣町へと西を目指すあいだ、悠太郎の暗い不安は澄んだ冬の光のなかで、少しずつ薄らいでいった。とうに穫り入れの終わった広いキャベツ畑の向こうに、ほぼ真北から見える浅間山の雪白の山容は、悠太郎たちが住む東北麓の町から見えるよりも大きかった。親子はペンションの案内板から、目指す会場の名前を見て取った。音楽ペンション〈アマデウス〉というのがその宿屋の名であった。噴煙を吐く雪白の浅間山を真南に望む〈アマデウス〉の駐車場に降り立ったとき――その駐車場は十五台分あった――、素晴らしいひとときへの予感で悠太郎の胸は満たされた。コの字型に南へと突き出した東西の翼部を持つ二階建てのペンションの外壁は、ほとんど白に近いグレーであった。樅の樹々が緑色に針葉を茂らせるあいだを通って石段を三段昇れば、二階中央のバルコニーを支える柱のあいだに、白い玄関扉があった。悠太郎はアンティーク風の金色のハンドルを押し下げて扉を開き、発表会が催される食堂ホールを目指した。子供たちやその親たちが、それぞれに着飾って集まってきていた。子供たちが前列で待機し、親たちが後列で鑑賞する客席の左手の明るい窓辺には、飾り棚の上にオーストリア産のワインの空き瓶が一列に並べられ、それらの瓶の青いガラスを透かして黄色い電飾が、いかにもクリスマスを待つ季節に相応しく明滅していた。磨き上げられて黒く光るグランドピアノが置かれた南側の、レースのカーテンで覆われた窓のある壁際には、発表会の開催を祝って贈られたスタンド花が、色とりどりに咲き匂っていた。赤いベルベットのドレスを着た陽奈子先生は、生徒たちやその親たちと挨拶を交わし、また会場設営のために何くれと指図しつつ動きながらも、背筋をまっすぐに伸ばして女王然としていた。ピアノを弾かない留夏子もまた会場に来ていて、白のシャツにベルトのついた黒のロングスカートという地味で清楚な出で立ちで、母親の指図に従って何くれと立ち働いていた。母親のピアノ教室が初めて開く発表会で、留夏子がそうせずにいられないのは、バイエルも終わらせずに練習を放り出したことから来る負い目のゆえに違いなかった。これでも留夏子は陽奈子先生の生徒たちに、よきお姉さんとして結構慕われていたのである。このときも留夏子は大屋原のどこかから習いに来ている女の子に――その子は白のレース襟つきセーターと、ピンクのスカートと、白のハイソックスで着飾って、髪を三つ編みにしていた――、「いつもうちのお母さんと遊んでくれてありがとう。今日はとても可愛いわよ」と言葉をかけては、陽奈子先生から「ちょっとルカ、何を言っているの」と叱られて、その子を笑わせていたものであった。
そんな平和な光に満ちたホールのグランドピアノを次から次へと、スイス民謡の〈静かな湖畔〉や、イギリス民謡の〈灯台守〉や、同じくイギリス民謡の〈ロング・ロング・アゴー〉や、ワルトトイフェルの〈スケーターズ・ワルツ〉や、エステンの〈人形の夢と目ざめ〉や、ベートーヴェンの〈エリーゼのために〉や、ブルグミュラーの〈貴婦人の乗馬〉が、丸々とした幼い手や、青白く静脈の浮き出た繊細な少女の手や、早くも頑丈になりかけた少年の手によって、あるいはたどたどしく、あるいは滑らかに、あるいは華やかに、あるいは力強く通り過ぎていった。出場する生徒としては最年長の悠太郎もまた黒のカーディガン姿で、いくらか緊張しながらベートーヴェンの〈「うつろな心」による変奏曲〉を、毛深いながら美しい手の指で通り過ぎさせた。パイジェッロの歌劇《水車小屋の娘》から主題を取って、ベートーヴェンが作曲したというその変奏曲は、『ソナチネアルバム』に収録されていたのである。まず簡潔に主題を提示し、それを次々に変形し労作してゆく変奏曲という形式に、悠太郎は多大な興味を抱いた。ト長調の主題の音が細分化され、多様に装飾され、同主短調に転調までして積み重ねられてゆく変奏の生成発展の根底に、流れ去らずに留まるものの姿が確かに見えるような気がした。それで悠太郎はこの変奏曲を通じて、変奏曲全般を愛好するようになっていたのである。短調から長調に戻った後での、きらめきが走るような速い音階は、聴く人が聴けば危なっかしくはあったであろうが、それでも悠太郎は手に余りがちなその曲を、堂々と締め括って拍手喝采を浴びた。連弾の部は多くの生徒が陽奈子先生と弾くことになっていたから、独奏の部よりずっと気楽であった。陽奈子先生が悠太郎に与えたのは、ブラームスの〈ハンガリー舞曲第五番〉を易しく編曲したものであった。暗い情念を帯びた二拍子のチャールダーシュを、師弟は息を合わせてテンポと強弱を変化させながら楽しそうに弾いた。この曲で陽奈子先生はハンガリー留学時代を追憶しているのだろうと悠太郎は推察していた。セコンドの低音部で煽り立てる陽奈子先生のリズムに釣り込まれて、悠太郎はプリモの高音部で乗りに乗りながらも、歳月や運命の不思議を思わずにはいられなかった。かつてブダペストでピアノを学んでいた若い女性が、六里ヶ原で母となりピアノ教室を開き年を重ね、今この音楽ペンションでハンガリーの舞曲を、ぼくと連弾しているのだ――。
ペンションのご主人は銀色のフルートを吹く人で、フルート演奏の前にご主人は挨拶を述べた。黒のタキシードに身を固めたアマデウスおじさんは、髪の毛の生え際の後退が目立つ中年男性であったが、皺の寄った目尻をにこにこ笑わせながら言った。「皆さん、本日はお集まりくださってありがとうございます。どなたのピアノも素敵でした。この浅間山の麓で音楽ペンションを開いてよかったと、今日ほど強く思えた日はありません。ところでこのペンションに私がつけたアマデウスというのは、作曲家モーツァルトの名前です。私はいつの頃からかモーツァルトの音楽が好きで好きで、おそらくそのせいでしょう、髪の毛の生え際までほらこの通り、M字型になってしまいました」とアマデウスおじさんが言うと、子供たちにも大人たちにも乱反射する湖のような笑いが広がって光り輝いた。「プログラムにもありますように、これから吹くのはモーツァルトのフルート・ソナタK一二です。Kというのはケッヘル番号といって、ケッヘルさんという植物学者がモーツァルトの作品を研究して、作曲順につけた番号です。一二という番号は若いでしょう? モーツァルトはこのソナタを作曲したとき、なんと八歳でした。まさにアマデウスという名前が意味する通り、神に愛された人です。天才です。しかしK六二六のレクイエムを未完成のまま残して、三十六歳で亡くなりました。それに引き替え私などは平凡に生き長らえた、髪に愛されないM字型です」とアマデウスおじさんが語ると、また湖の乱反射のような笑いが、次いで陽奈子先生のピアノに伴奏された銀色のフルートの響きがホールを満たした。永遠の子供が光のなかで遊ぶようなイ長調のソナタを吹きながら、アマデウスおじさんは歯茎を剥き出しにして息継ぎをしたが、それを見た悠太郎は馬が臭いを嗅ぐときのようだと思った。フルートが終わって、陽奈子先生の講師演奏もアマデウスの名を冠したペンションに相応しく、モーツァルトの〈きらきら星変奏曲〉であった。流れる時のなかに留まるものの姿が見える変奏曲を聴けるとあって悠太郎は喜んだが、今度は主題がどんな子供でも知っているメロディーだけあって、みんなが大いに喜んだのである。陽奈子先生は腕を生き生きと波打たせながら華麗なパッセージを紡ぎ出し、晴れた青空に晴れた青空を重ねるように変奏を積み重ねて大喝采を浴びた。この二曲のモーツァルトの連続を聴きながら悠太郎は、物問いたげな大きな目を見開いて、何かを思い出そうとしていた。忘れていた大切な何かが、思い出せそうな気がしていたのである。
留夏子やみんなが椅子を並べ替えたりテーブルを運び込んだりして、いつしかお茶の会が始まった。アーモンドケーキが皿に切り分けられ、縁に柊の葉やベルが描かれた紙ナプキンがバスケットに敷かれ、そこにチョコレートが盛られ、花柄のティーポットからティーカップへと紅茶が注がれた。やや日の翳った窓辺では、ワインの青いガラス瓶を透かして黄色い電飾が明滅していた。「外は冷えますね。雪になるかもしれません」とアマデウスおじさんが、皺の寄った目尻をにこにこ笑わせながら言った。また真冬が来ると悠太郎は思った。一年生のとき、真冬の体育館掃除はつらかったな。今でこそ掃除の班は学年別になっているけれど、あの頃は縦割り掃除などといってひとつの班を全学年から編成したから、上級生の暴力がひどかった。汚く濁った冷たい水に突っ込んだ手は、今日ここでピアノを弾いた手と同じ手だ。でもこんなに平和で豊かな時間に、ぼくはなぜあんな醜悪なことを思い出すのだろう。なぜぼくはあんなことを乗り越えられただろう。そうだ、あのとき流れていた音楽は、あのとき流れていた音楽は――。
悠太郎は弾かれたように立ち上がると、「もしかしてこういう曲がモーツァルトにありませんか?」とアマデウスおじさんに問い、驚くみんなをよそにしてピアノに向かうと、思い出したイ長調のメロディーを再現して聞かせた。四小節も弾かないうちにアマデウスおじさんが、「ありますよ。正真正銘のモーツァルトです。クラリネット協奏曲ですよ。K六二二ですから、最晩年の傑作です」と即答した。いま悠太郎は燦々たる光が喜戯するような、澄み渡る天空から明るい風が吹き通うようなあの音楽を、はっきりと思い出すことができた。「そうでした。モーツァルト作曲のクラリネット協奏曲でした。ノリくんも……入江先輩も、たしかにそう言っていました」と悠太郎が言うと、留夏子も秀子も陽奈子先生も、紀之のことを知る人はいくらか痛ましげな顔をした。「留夏子さん、ぼくは放送室でこれを探していたんです。探し物が、やっと見つかりました」と報告する悠太郎に、留夏子は「そう。よかったわね。入江先輩との思い出の曲だったのね」と答え、眩しいものでも見るように切れ長の目を細めた。電飾が灯る青いガラス瓶越しに窓の外を見たアマデウスおじさんは、「降ってきました。積もらないうちに散会したほうがいいかもしれません」と提案した。留夏子は陽奈子先生に「お母さん、最後にあれを弾いてよ。主が早く召したもう人の曲、人の望みのなんとか」と要求した。「なんとかってことはないでしょう」と娘をたしなめて立ち上がった陽奈子先生は、「では皆さん、特別にもう一曲お聴きください。バッハ作曲〈主よ、人の望みの喜びよ〉」と言ってピアノに向かった。
鳴り始めたのはなんという浄福の音楽であったことか! 喜びに満ちて空を舞い飛ぶ天使の羽ばたきのように、高音部では三つずつの音が寄り合って音階となり、また離れては分散和音となって、あるときは昇りあるときは降りながら間断なく流れるあいだ、低音部ではほとんど永遠のような悠久の時間が、三拍子の舞曲のステップを踏みながらひとところに留まっているかのようであった。悠太郎も留夏子も、やがて現れる歌詞のないコラール旋律の意味を知っていた。ふたりは今や平明な心境で、ようやく亡き人の非在を受け容れることができた。束の間を生き、出会い、別れ、そして死んでゆく人間が、ともかくも今をこうして生きている。そのことの限りない懐かしさがふたりの胸に溢れた。若死にしたモーツァルトは、バッハのこの曲を聴いたことがあっただろうかと、カトリックとプロテスタントの区別も知らない悠太郎はふと考えた。いや、モーツァルトは永遠の旅の途上で今日この宿屋に留まり、このささやかな音楽の祝祭を初めから終わりまで聴き届けて、また雪の降る天空へと馬車を走らせるのではないか――。窓の外には静かに緩やかに雪が降っていた。あたかもこのペンションのある六里ヶ原が、静かに緩やかに天へと昇ってゆくかのようであった。
ところで悠太郎が誕生日に真花名と話した願い事は、結局叶わずじまいであった。なぜなら色糸が代わる代わる現れるよう巧みに斜め編みされたミサンガが、自然に切れることはなかったからである。悠太郎が発表会で奮闘しているあいだ、真壁の家では梅子がパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、「ウッフフ、家宅捜索」と言いつつ学習机の引き出しを開け、発見した例のミサンガを「お勉強の妨げ」になりそうなほかのものともども、裏庭にあるゴミ燃し場の灰にしてしまったからである。後でこのことを知った悠太郎の虚ろな心には、灰色の冷たい風が吹き過ぎた。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
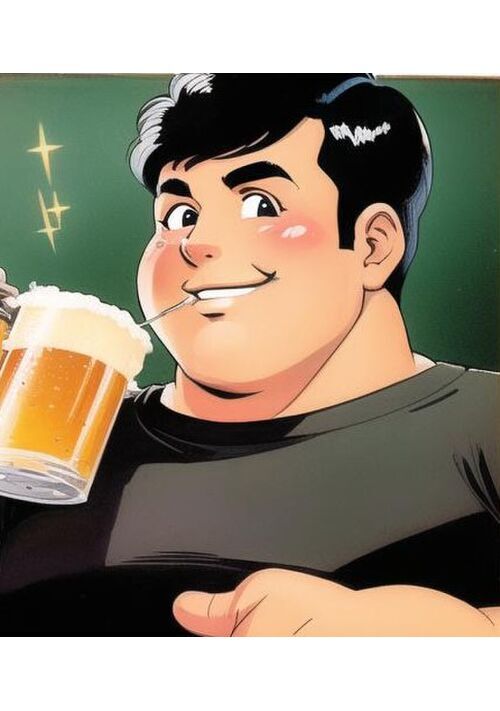
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!



ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















