32 / 73
第十一章 濁り水
二
しおりを挟む
一九九四年の夏は早くからひどく暑く、夏休みも近い七月のその夜の体育館は、異様な熱気に満たされていた。みんなはひとしきり基本や形を稽古して、白い道着に汗を吸わせた。悠太郎もまた隼平や一輝に伍して、大いに気合いと汗を発した。休憩時間になったので、悠太郎は壁際で床に座り込み、膝を抱えて休んでいた。すると何を思ったのか美帆が近づいてきて、「真壁、あなた、あれが弾けるんでしょ?」と囁くような声で言い、ステージ上に置かれたグランドピアノを指さした。突然のことに悠太郎は驚いた。言葉を話す美帆の声を聞いたのはそれが初めてであったし、いったい誰が美帆にそんなことを吹き込んだのかという疑問もあった。悠太郎がふと隼平を振り返ると、ひょろ長い脚を投げ出して座っていた隼平は、斜視気味の目を泳がせた。悠太郎は再び美帆を見たが、その切れ長の目からも赤みの引いた白い顔からも、何らかの感情を読み取ることは難しかった。「弾けるというほどは弾けませんよ」と悠太郎は答えたが、美帆は重ねて「弾きなさいよ」と命じるように言った。悠太郎は内心で困惑しながらも、「美帆さんに聴かせるほどの腕はありません」と言って丁重に断ろうとした。しかし美帆はなおも「弾きなさい」と囁き声を低めて言った。この恐るべきピアニシモが、悠太郎の神経を戦慄させた。副師範の娘にこうして命じられては、悠太郎にはもはや逆らいようがなかったし、美帆はそのことをよく知っていて命じたのである。悠太郎は立ち上がりながら物問いたげな目を見開いて、何の曲を弾いたものかと思案した。もちろん暗譜しているものでなければならないし、短く終わるほうがよい。標題がついた曲のほうが、美帆さんには分かりやすいだろうな――。そう考えた悠太郎は、「では弾きます。ブルグミュラー作曲の〈さようなら〉です」と小さな声で言ってステージへ歩んだ。美帆はもちろん一輝や隼平や篤師範や駿副師範や、その他大勢の門弟たちの視線を背中に感じながらの、気詰まりな歩みであった。悠太郎は鍵盤の蓋を開けて椅子に座った。ペダルは火照った素足に冷たかった。
アレグロ・モルト・アジタート、イ短調、四分の四拍子――と、悠太郎は手許にない『ブルグミュラー25の練習曲』の譜面を思い出しながら弾き始めた。アジタートとは「激情的に」という意味のイタリア語だと陽奈子先生は教えてくれたし、楽譜に赤鉛筆で書き込んでもくれた。ためらいがちに始まる序奏はしかし、第三小節にしてスフォルツァンドへと高まる。激した感情をさらけ出すような七度の上行と、崩れ落ちるような和声的短音階の下降! 時の流れが止まることを願うかのようなラレンタンド! しかしテンポはすぐに戻り、切々と嘆き訴えるように波打つ右手の三連符を、吐息のように、あるいは滴る涙のように下降する左手の四分音符が支える――。なんという悲しみ! なんという愁嘆! だが美帆さん、こんな悲しみやこんな愁嘆は、いったいあなたに何の関わりがあるというのですか? 胸の底から込み上げる悲傷のような左手の三連符のアルペジオ! また右手に移った三連符の嘆きの下に、次から次へと寄せ来るスフォルツァンドの慟哭! こんな悲傷やこんな慟哭は、敏捷な美帆さん、あなたに何の関わりがあるというのですか? ほら、イ短調は平行調のハ長調に変わった。平行調というのは、いいですか美帆さん、同じ調号で表される長調と短調のことですよ。この場合はシャープもフラットもひとつもつかないイ短調とハ長調が平行調なのですね。エスプレッシーヴォは「表情豊かに」という意味のイタリア語です。感情を外に押し出すということです。その白い顔にほとんど表情を持たない美帆さん、たまに薄い唇で薄く笑うだけのあなたに、エスプレッシーヴォということが分かりますか? 別れゆくふたりがいるとして、それが友達なのか恋人なのかぼくは知りません。しかし楽しかった昔を懐かしむようなこのハ長調の部分にも感じられる、心の乱れと惑いはどうでしょう。形でも組手でもいつだって平常心で、乱れを知らないように見える美帆さん、空手機械のように素早くて強いあなたに、この惑乱は何の関わりがあるのでしょう? 美帆さん、あなたはこれっきり、音楽なんかを聴きたがってはいけません。ピアノなんかに近づいてはいけません。それはあなたの健やかさを害します。それはあなたの自然な強さを損ないます。あなたは過剰な感受性を抱えて弱くなってはいけません。ぼくのように病的になってはいけません。あなたは健やかに自然に強くあってください。なんとなればあなたにとっては、それがいちばん美しい在り方なのですから。ぼくはもうけっしてあなたのためにピアノを弾くことはしません。こんなことは本来あってはならなかったのです。なぜあなたはこんなことをぼくに要求したのですか? 敏捷な美帆さん、強い美帆さん、あなたの前でぼくがどんなに惨めだか知っていますか? ああ、楽しかった懐かしい昔の思い出にも影が差す。この下降するメロディーの増二度音程は、ちょっとすごいでしょう? でもそんなことはあなたには感じられなくていいんです。そしてほら、また平行短調が、イ短調が回帰します。切々と嘆き訴えるように波打つ右手の三連符を、吐息のように、あるいは滴る涙のように下降する左手の四分音符が支えます。なんという悲しみ! なんという愁嘆! だが美帆さん、こんな悲しみやこんな愁嘆は、いったいあなたに何の関わりがあるというのですか? 今度という今度はお別れです。さようなら、さようなら、さようなら……。これきりです。お別れです――。
悠太郎は弾き終えると椅子から立ち上がり、鍵盤の蓋を閉めてステージを降りた。いつになく神妙になってしまったみんなもとへの、気詰まりな歩みであった。隼平や一輝や篤師範や、その他大勢の門弟たちの視線が、悠太郎と美帆に代わる代わる注がれた。美帆は悠太郎に何かを言おうとして短く息を吸い込んだ。するとその瞬間に駿副師範が悠太郎を睨みつけ、「何だ真壁、おめえはピアノなんざ弾くのか? そんなのは女のやるようなことじゃねえか! まあずおめえは、女の腐ったような奴だな!」と野太い声で呆れてみせたので、美帆はそのまま言葉を飲み込んでしまった。門弟たちのあいだには、嘲笑の細波が広がった。悠太郎は睫毛の長い目を悄然と伏せながら嘲りに耐えていた。こうしたものなのだ。野卑と鈍感と無知と愚昧! ここにあるのもやっぱりそうしたものばかりだと、これではっきりした。野卑と鈍感と無知と愚昧が支配するこんなところで、美帆さん、あなたはどうしてぼくにあんなことを要求したのですか?――
「お言葉ですが副師範」と清々しい声で言いながら立ち上がったのは紀之であった。「バッハやモーツァルトやベートーヴェンを考えてみてください。有名な音楽家には、男が多くいます」と駿副師範の見解を訂正した紀之は、円かな目を見開いて悠太郎を見た。その表情には、かつて道場で見せたことがない明るさがあった。「達者に弾けるようになったな。別れの感情を表現しながらも、それに流されない骨格がしっかりしている。真壁の先生は、基本を大切にする人だな。ブルグミュラーの〈さようなら〉か。取るに足らない練習曲だと思っていたが、こうして聴くと実にいい。おかげで忘れていた昔を思い出した」と言った紀之は、リスを思わせるやや大きな白い前歯を見せて笑った。悠太郎は大きな目を涙に潤ませた。こんなときでも紀之は、相も変わらず湖の騎士なのであった。
稽古を終えて体育館を出た悠太郎と紀之は、渡り廊下に腰を下ろして靴を履きながら、しばらく話した。暗い戸外の渡り廊下を越えた先には、中学生たちが給食を取る食堂があるということであった。「ノリくんは……入江先輩は、もうヴァイオリンを弾かないんですか?」と悠太郎は、気に懸かっていたことを紀之に尋ねてみた。「ああ、あれはもういいんだ」と紀之は暗がりのなかで肩をすくめた。「楽器を壊されてしまった。それでもう弾けなくなった。まあ詳しくは言わないが、そんなこんながあってな。この中学校へ入ってすぐのことだ。それで空手を始めた。力を求めた。強くなりたいと思った。黒帯にまでなった。だがやはり何かが違うと思っていた。それでいて何が違うのか分からなかった。その迷いをねじ伏せるように稽古を続けてきた。ユウのおかげで今夜ようやく分かった気がする。俺は弱く優しくあれとユウに言ったことを思い出した。白樺の枝がふるえ始める前から、風の思いを知るような子でいろと俺は言ったんだったな。ところが俺は力を求めてしまった。強くなりたいと願ってしまった。だが俺には、たとえ潜在的にであれ、人を傷つけることができなかった。思ってみるだけでも、そんなことは嫌だった。傷つけられっぱなしでいるほうがましだと思った。実生活では身を護るためであれ、拳を振るうことができなかった。ユウはいつか俺に訊いたことがあったな、なぜ一緒に遊んでくれるのかと。今ならその理由がはっきり分かる。俺はおまえのようになりたかったんだ。俺はおまえのようでありたかったんだ。それにしても……」と紀之は語った。悠太郎は信じられないような思いでその話を聞いていた。この中学校で、そしてその先の高校で、いったい何があったというのか? 「それにしても、大きくなるとは嫌なものだな。俺はなんだか自分が濁った水にでもなってしまったような気がする。照月湖の澄んだ水に、ユウとボートを浮かべたあの頃が懐かしい」と、うつむいたまま独り言のように思いを述べた紀之は、「じゃあなユウ、気をつけて帰れよ」と顔を上げてやや明るく言い残すと、迎えの車を待つ悠太郎に別れて、蒸し暑い夜のなかを、校舎の裏の自転車置き場へ消えていった。
「どうして美帆さんはぼくにあんなことを要求したのだろう。そしてノリくんに……入江先輩にいったい何があったのだろう」と悠太郎は考えながら、樹々が緑濃い枝を差し交わす林間の道をゆっくりと歩み、近々と迫る鷹繋山を正面に望みながら、急な坂道を降りてレストラン照月湖ガーデンの前に来た。ガーデンはもはや紀之とは何の関係もなくなっていた。料理の腕は確かだが時々パチンコを打つという、やさぐれた風貌の入江信次郎シェフは株式会社浅間観光を退職し、悠太郎の通学路沿いにある小さなホテルの管理人に転じていた。あるとき千代次は信次郎シェフを評して、眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、「泥舟から真っ先に逃げ出したちゅうわけか? 浅間観光が沈みゆく泥舟ちゅうわけか?」と不興げに言ったが、自分が言ったことの不吉さのあまりいっそう不快になったらしく、宇宙全体を腐らせそうに顔を歪めたものであった。だが千代次の言ったことにも、あながち根拠がないではなかった。浅間観光の永久名誉顧問としての千代次に支払われる報酬は、ひと月十万円から八万円に、そして五万円に減らされていたのである。
レストラン照月湖ガーデンは、観光ホテル明鏡閣に新年度から入った板前の奥さんに任されていた。新海岳史さんというのがその板前であったが、にかっと歯を見せて泣き笑いのような顔をする新海さんを、千代次はあまりよく言わなかった。「ユウ、今度の板さんはのう、包丁よりも鋏を使うほうが得意だちゅうぞ。出来合いの袋物を鋏で開けて、一丁上がりちゅうわけよ。あんな者を入れるんならおめえ、サカエくんが料理をしたほうが、よっぽどいいのう。だがサカエくんは支配人だから、忙しくてそういうわけにもいくめえのう」というのが千代次の評価であった。レストラン照月湖ガーデンを任されたその奥さんは松子さんという名で、マッちゃんと呼ばれていた。たらこ唇のマッちゃんも、これまた評判がよろしくなかった。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、あの人にやらせて、ガーデンが繫盛するもんかね」と言ったことがあった。マッちゃんに任されてからガーデンは、うどんやそばを茹でて食べさせるだけの店になっていた。それも手打ちなんかではなく、袋うどんや乾燥そばを茹でて出しているだけであった。ガーデンのそばについては、この頃ひとつの事件が起こった。そばを食べ終えたひとりの客が「そば湯をください」と要求したのである。乾燥そばのそば湯を求められることを想定していなかったマッちゃんは、大いに狼狽して明鏡閣の事務所に電話を入れ、「サカエさん、どうしよう。そば湯をくれってお客が言うんだよ」と泣きついた。「どうしようもこうしようもあるもんか。乾燥そばを茹でたお湯を出すしかあるめえ。何、捨てちまった? 捨てちまったならおめえ、ねえ袖が振れるかよ。そば湯はありません、捨てちまいました、ごめんなさいと謝るしかあるめえ」というのが、受話器の向こうのサカエさんの答えであった。マッちゃんがその通りにすると、客は大いに立腹して帰った。そして噂は瞬く間に広まり、ガーデンはますます寂れてほとんど開店休業の状態になった。そういう話を悠太郎は秀子から聞いていた。そんな陰気なガーデンを横目に悠太郎は、大きな石段を降りて湖に近づいた。
様変わりしたのはガーデンだけではないなと悠太郎は考えた。これまた新年度から、狐目の男こと春藤秋男さんが、照月湖モビレージの責任者として入社していたのである。黒縁の眼鏡の奥で狐目を吊り上げた春藤さんは、いつも何かに驚いたように不服そうに口を尖らせている人で、その言動もいちいちが奇妙であった。何しろ入社早々にしたことというのが、おロク婆さんとおタキ婆さんを沖縄旅行に連れてゆくことであった。蒼白な顔で苦しげだったおタキ婆さんは南国の旅行から帰ると、見違えるように肌艶がよくなり元気づいていた。普段から血色のよかったおロク婆さんは、ますます活力に溢れていた。「まあず驚いたねえ沖縄というところは! 那覇空港を出るとねえ、もう街路樹に椰子の樹なんか生えてるの! ああ、南国へ来たなあと思ったっけ」とおロク婆さんが言いながら、旅行で撮影された写真のアルバムを開いてみせた。明鏡閣の社員食堂のみんなは、一行がお土産に買ってきたちんすこうを食べてお茶を飲みながら写真に見入った。そこに映っているのは碧緑の海であったり、琉球王国の栄華を偲ばせる豪壮華麗な首里城であったり、民族衣装の花笠を被って笑うおロク婆さんとおタキ婆さんであったりした。白い三角巾のおタキ婆さんは旅行をうっとりと思い出しながら、「あたしゃこれまで生きてきて、こんな楽しい思いをしたことはなかったよ」としみじみ言った。紫色の三角巾のおロク婆さんは、「まあず楽しかったねえ。春藤さんに感謝だよ。この思い出を励みに、またうんと働こうねえ」と活力ある声で言うと、「秀子ちゃん、うんじゅ・いっぺー・ちゅらかーぎー」と話しかけた。おタキ婆さんは「あなたはとても美人ですという意味だよ」と説明した。するとちんすこうを食べていた林浩一さんが、平たい顔をにこやかに笑わせながら、「そういえばユウくんは空手を習っているんでしたよね。 空手も沖縄発祥ですよね」と思い出したように言った。「何だって! ユウちゃんが空手を?」と驚いたおロク婆さんは、「悪いことは言わないからやめておきな。優しいユウちゃんにそんなことをやらせれば、ろくなことにはならないよ。ユウちゃんは絵を描いたり字を書いたり、ピアノを弾いたりしていたほうがよっぽどいいよ」と秀子に忠告した。春藤秋男さんはしかしロビーで黒い革張りのソファに座って、照月湖モビレージの看板の文字に蛍光塗料を塗っていたが、その仕事を切り上げて社員食堂にやって来ると言った。「ほっほい、それじゃ橋爪さん、熊川のほうへ与作をやりに行こうじゃねえか」
草木が生い茂るままに眠らせてある旧ホテルの跡地を開発して、熊川リバーサイドモビレージと称する新たなキャンプ場を作ろうというのが、春藤さんの打ち出した気宇壮大な計画であった。「ヘイヘイホーの定理!」と野良着姿の橋爪進吉さんは、ゲジゲジ眉毛の顔をひしゃげたように笑わせて張り切った。「気をつけとくれ橋爪さん。ヘイヘイホーは大怪我のもとちゅう諺もあるからな」と黒岩栄作支配人が、煙草の煙を輪っかの形にして連続で吐き出すと忠告した。「それを言うなら生兵法でしょう」と突っ込みを入れた板前の新海岳史さんは、にかっと歯を見せて泣き笑いのような顔をした。剽軽者の橋爪さんはしかし「ぼくは死にましぇーん!」と言っておどけたので、社員食堂のみんなは大笑いした。幌つきのジープには、斧やチェーンソーやロープや楔や脚立やヘルメットといった使えそうな道具が、倉庫から出されて満載されていた。春藤さんが運転するそのジープに乗って、寸胴の橋爪さんは河畔へと運ばれてゆくのである。そんな話を悠太郎は母の秀子から聞いていた。この春藤秋男さんのこともまた、悠太郎の祖父母は快く思っていなかった。千代次は眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、「春藤秋男か。名前からしていかがわしいのう。春なんだか秋なんだか分からねえ。浅間観光にも春秋戦国時代が到来したちゅうわけか」と評していた。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、わったしはあの男が好かないよ。あんな者は法螺吹きのいかさま師だよ。あの男は今に浅間観光をかんまして、禍いの種になるよ」と不信感を露わにしていた。ちなみに梅子は搔き回すことを「かんます」と言ったのである。そうだ、浅間観光もずいぶん様変わりしてしまった――。そんなことを考えながら悠太郎は水際に立った。
白樺林の枝葉を揺らす微風によって、暑熱のなかを運ばれてきた異様な臭気が悠太郎の鼻を突いた。この青臭いような生臭さはどこから来るのか? 不審に思って見れば、湖水は絵の具でも混ぜたように緑色に濁っていた。悠太郎は目を疑った。「それにしても、大きくなるとは嫌なものだな。俺はなんだか自分が濁った水にでもなってしまったような気がする」という紀之の言葉に影響されて、悪夢でも見ているのだと信じたかった。それで悠太郎は桟橋の突端から身を乗り出すと、緑色の湖水に手を差し入れた。そして濁った湖水を掬ってみた。緑色に濁った生臭い湖水は、くぼめた手のひらに掬っても緑色に濁っていて生臭かった。悠太郎の手のひらを零れた水は、湖に落ちて波紋を描いた。水面を滑っていたアメンボが驚いて逃げ出した。悠太郎が何度水に手を突っ込んでも、半袖のポロシャツが濡れるほど深々と腕を突っ込んでも、悪夢は醒めなかった。それは悪夢ではなかった。それは紛れもない現実であった。そのことに思い至って、悠太郎は恐怖のあまり胸の奥が冷たくなるのを感じた。次の瞬間には駆け出していた。そして橋の上を右往左往した。そしてボート番小屋に駆け込むと叫んだ。「桜井さん! 照月湖の水が、水が、水が……!」
ライサク老人こと桜井謙助さんは動揺した悠太郎を認めると、驚きのあまりギョロ目を見開いて額に三筋の皺を寄せた。「ああ、知ってるよ。水が緑色になって臭えんだろう? 今朝来て俺たちはみんな驚いたよ。アオコというものらしい。植物プランクトンの大量発生だとよ。こんなことは今までになかった。これも時勢かのう」とライサク老人は、落胆を滲ませながらも落ち着いて言った。だがその落ち着きは悠太郎を怒らせた。「時勢? 時勢ですって? 時勢だなんて言って済ませられることですか? こんなことがあっていいんですか? 照月湖のきれいな水がこんなになってしまうなんて、そんなことが許されていいんですか? ぼくは嫌だ。ぼくは認めない。絶対に認めない。バブルが弾けた。暖冬になった。冷夏になった。不景気になった。明鏡閣のクリスマスパーティーが中止になった。そして今度は照月湖の水がアオコで濁った。これを時勢だなんて言っている場合ですか? こんなのは設計ミスの時勢だ! ぼくは嫌だ。ぼくは認めない。ぼくはこれらのすべてを、絶対に認めない。崩れてゆくものがあるなら、その崩壊を食い止めなければならない。失われていったものは、何もかもひとつ残らず取り戻さなければならない。明鏡閣のみんなが諦めたって、今にぼくが大きくなってうんと勉強して、何もかもをひとつ残らず、あの美しかった時代に戻してみせる。必ず、必ず、必ず元に戻してみせる……!」
そんなことを叫びながら悠太郎は、大きな石段と急な坂道を駆け上がった。走るにつれて樹々の葉叢を洩れる光は、聞こえない音楽の川のようにきらきらと輝いた。お祖父様に知らせなければならない。だが知らせてどうするのか? 知らせるだけでいいのか? ぼくなりに何か考えられることはないのか? 暖冬とか冷夏とか猛暑とか水質汚染とか大気汚染とか、そういう問題を何というのだったか? 環境問題というのではないか? 崩れてゆくものの崩壊を、どうやって食い止める? 失われていったものを、どうやって取り戻す? お祖父様やお祖母様やお母様やぼくの大切なものを、どうやって守る? 環境……守る……環境……守る……。そうだ!――悠太郎は思い出した。学芸村の環境を守る会の代表という人が小学校でお話してくれたのは、つい昨日のことではないか。赤と灰色の市松模様の絨毯を敷いた多目的スペースで、児童たちはその老人の話を聞いたのではなかったか。頭に柔らかな銀髪を波打たせた藤原容三博士は、右半分が染みだらけの顔を全校児童に向けながら、会の活動について話していたではないか。「六里ヶ原は自然豊かなところです。その六里ヶ原に開かれた学芸村は、伝統ある別荘村です。学芸村では桃源郷のような環境が、緩やかな決まりのもとで六十年以上も保たれてきました。桃源郷というのは皆さん分かりますか? 俗世間を離れた、平和で豊かな別世界という意味です。ところが近年では、このあたりにもリゾートマンションの高層建築が造られ始めました。開発によって森林破壊が進んでいます。水道水の質も悪くなっています。これからは積極的に環境を守るための活動をしなければならない。そう考えて私たちは、町や県に陳情したり、新聞広告を出すための募金を集めたりしています。そうです、学芸村の環境を壊すものは何であれ、私たちはこれを許さないのです……」そんなことを話す藤原さんと、悠太郎は一瞬だけ目が合ったような気がしたものである。そうだ、学芸村の環境を守る会だ!
アオコで濁った照月湖は、その日のうちに千代次の細い目の見るところとなった。夕食の席では重苦しい空気のうちに、この重大な異変のことが話し合われた。「ひでえもんだ。あれじゃあ景観も台無しだ。まあすひでえもんだ」と千代次が眼鏡の奥で目をしばたたけば、「あんな臭い湖で、ボートに乗りたがる人がいるのかしら。へら鮒釣りのお客さんだって減っちゃう」と秀子が下膨れの顔に沈鬱な表情を浮かべた。「ウッフフ、まあず嫌だねえ。この暑さのせいもあるのかねえ。今年の夏はウッフフ、まあず暑いからねえ」と梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら言った。しかし千代次は気を取り直して、「だがユウはいいことを教えてくれた。学芸村の環境を守る会か。そんなものがあるらしいちゅう話は聞いていたが、小学校にも来ていたとはな。藤原さんなら俺は知っている。俺は浅間観光の人間だが、学芸村の理事でもある。守る会の代表と話ができるのは、浅間観光で俺しかいねえ。小学校に来たちゅうことは、もう別荘にいるはずだ。明日にでも早速訪ねてみることにしよう」と言うと、たったひとりの孫を極度に細い目でまじまじと見た。「ユウ、何だかんだ言っても、やはりおめえは成長したな」と千代次は柄にもない台詞を吐いた。
アレグロ・モルト・アジタート、イ短調、四分の四拍子――と、悠太郎は手許にない『ブルグミュラー25の練習曲』の譜面を思い出しながら弾き始めた。アジタートとは「激情的に」という意味のイタリア語だと陽奈子先生は教えてくれたし、楽譜に赤鉛筆で書き込んでもくれた。ためらいがちに始まる序奏はしかし、第三小節にしてスフォルツァンドへと高まる。激した感情をさらけ出すような七度の上行と、崩れ落ちるような和声的短音階の下降! 時の流れが止まることを願うかのようなラレンタンド! しかしテンポはすぐに戻り、切々と嘆き訴えるように波打つ右手の三連符を、吐息のように、あるいは滴る涙のように下降する左手の四分音符が支える――。なんという悲しみ! なんという愁嘆! だが美帆さん、こんな悲しみやこんな愁嘆は、いったいあなたに何の関わりがあるというのですか? 胸の底から込み上げる悲傷のような左手の三連符のアルペジオ! また右手に移った三連符の嘆きの下に、次から次へと寄せ来るスフォルツァンドの慟哭! こんな悲傷やこんな慟哭は、敏捷な美帆さん、あなたに何の関わりがあるというのですか? ほら、イ短調は平行調のハ長調に変わった。平行調というのは、いいですか美帆さん、同じ調号で表される長調と短調のことですよ。この場合はシャープもフラットもひとつもつかないイ短調とハ長調が平行調なのですね。エスプレッシーヴォは「表情豊かに」という意味のイタリア語です。感情を外に押し出すということです。その白い顔にほとんど表情を持たない美帆さん、たまに薄い唇で薄く笑うだけのあなたに、エスプレッシーヴォということが分かりますか? 別れゆくふたりがいるとして、それが友達なのか恋人なのかぼくは知りません。しかし楽しかった昔を懐かしむようなこのハ長調の部分にも感じられる、心の乱れと惑いはどうでしょう。形でも組手でもいつだって平常心で、乱れを知らないように見える美帆さん、空手機械のように素早くて強いあなたに、この惑乱は何の関わりがあるのでしょう? 美帆さん、あなたはこれっきり、音楽なんかを聴きたがってはいけません。ピアノなんかに近づいてはいけません。それはあなたの健やかさを害します。それはあなたの自然な強さを損ないます。あなたは過剰な感受性を抱えて弱くなってはいけません。ぼくのように病的になってはいけません。あなたは健やかに自然に強くあってください。なんとなればあなたにとっては、それがいちばん美しい在り方なのですから。ぼくはもうけっしてあなたのためにピアノを弾くことはしません。こんなことは本来あってはならなかったのです。なぜあなたはこんなことをぼくに要求したのですか? 敏捷な美帆さん、強い美帆さん、あなたの前でぼくがどんなに惨めだか知っていますか? ああ、楽しかった懐かしい昔の思い出にも影が差す。この下降するメロディーの増二度音程は、ちょっとすごいでしょう? でもそんなことはあなたには感じられなくていいんです。そしてほら、また平行短調が、イ短調が回帰します。切々と嘆き訴えるように波打つ右手の三連符を、吐息のように、あるいは滴る涙のように下降する左手の四分音符が支えます。なんという悲しみ! なんという愁嘆! だが美帆さん、こんな悲しみやこんな愁嘆は、いったいあなたに何の関わりがあるというのですか? 今度という今度はお別れです。さようなら、さようなら、さようなら……。これきりです。お別れです――。
悠太郎は弾き終えると椅子から立ち上がり、鍵盤の蓋を閉めてステージを降りた。いつになく神妙になってしまったみんなもとへの、気詰まりな歩みであった。隼平や一輝や篤師範や、その他大勢の門弟たちの視線が、悠太郎と美帆に代わる代わる注がれた。美帆は悠太郎に何かを言おうとして短く息を吸い込んだ。するとその瞬間に駿副師範が悠太郎を睨みつけ、「何だ真壁、おめえはピアノなんざ弾くのか? そんなのは女のやるようなことじゃねえか! まあずおめえは、女の腐ったような奴だな!」と野太い声で呆れてみせたので、美帆はそのまま言葉を飲み込んでしまった。門弟たちのあいだには、嘲笑の細波が広がった。悠太郎は睫毛の長い目を悄然と伏せながら嘲りに耐えていた。こうしたものなのだ。野卑と鈍感と無知と愚昧! ここにあるのもやっぱりそうしたものばかりだと、これではっきりした。野卑と鈍感と無知と愚昧が支配するこんなところで、美帆さん、あなたはどうしてぼくにあんなことを要求したのですか?――
「お言葉ですが副師範」と清々しい声で言いながら立ち上がったのは紀之であった。「バッハやモーツァルトやベートーヴェンを考えてみてください。有名な音楽家には、男が多くいます」と駿副師範の見解を訂正した紀之は、円かな目を見開いて悠太郎を見た。その表情には、かつて道場で見せたことがない明るさがあった。「達者に弾けるようになったな。別れの感情を表現しながらも、それに流されない骨格がしっかりしている。真壁の先生は、基本を大切にする人だな。ブルグミュラーの〈さようなら〉か。取るに足らない練習曲だと思っていたが、こうして聴くと実にいい。おかげで忘れていた昔を思い出した」と言った紀之は、リスを思わせるやや大きな白い前歯を見せて笑った。悠太郎は大きな目を涙に潤ませた。こんなときでも紀之は、相も変わらず湖の騎士なのであった。
稽古を終えて体育館を出た悠太郎と紀之は、渡り廊下に腰を下ろして靴を履きながら、しばらく話した。暗い戸外の渡り廊下を越えた先には、中学生たちが給食を取る食堂があるということであった。「ノリくんは……入江先輩は、もうヴァイオリンを弾かないんですか?」と悠太郎は、気に懸かっていたことを紀之に尋ねてみた。「ああ、あれはもういいんだ」と紀之は暗がりのなかで肩をすくめた。「楽器を壊されてしまった。それでもう弾けなくなった。まあ詳しくは言わないが、そんなこんながあってな。この中学校へ入ってすぐのことだ。それで空手を始めた。力を求めた。強くなりたいと思った。黒帯にまでなった。だがやはり何かが違うと思っていた。それでいて何が違うのか分からなかった。その迷いをねじ伏せるように稽古を続けてきた。ユウのおかげで今夜ようやく分かった気がする。俺は弱く優しくあれとユウに言ったことを思い出した。白樺の枝がふるえ始める前から、風の思いを知るような子でいろと俺は言ったんだったな。ところが俺は力を求めてしまった。強くなりたいと願ってしまった。だが俺には、たとえ潜在的にであれ、人を傷つけることができなかった。思ってみるだけでも、そんなことは嫌だった。傷つけられっぱなしでいるほうがましだと思った。実生活では身を護るためであれ、拳を振るうことができなかった。ユウはいつか俺に訊いたことがあったな、なぜ一緒に遊んでくれるのかと。今ならその理由がはっきり分かる。俺はおまえのようになりたかったんだ。俺はおまえのようでありたかったんだ。それにしても……」と紀之は語った。悠太郎は信じられないような思いでその話を聞いていた。この中学校で、そしてその先の高校で、いったい何があったというのか? 「それにしても、大きくなるとは嫌なものだな。俺はなんだか自分が濁った水にでもなってしまったような気がする。照月湖の澄んだ水に、ユウとボートを浮かべたあの頃が懐かしい」と、うつむいたまま独り言のように思いを述べた紀之は、「じゃあなユウ、気をつけて帰れよ」と顔を上げてやや明るく言い残すと、迎えの車を待つ悠太郎に別れて、蒸し暑い夜のなかを、校舎の裏の自転車置き場へ消えていった。
「どうして美帆さんはぼくにあんなことを要求したのだろう。そしてノリくんに……入江先輩にいったい何があったのだろう」と悠太郎は考えながら、樹々が緑濃い枝を差し交わす林間の道をゆっくりと歩み、近々と迫る鷹繋山を正面に望みながら、急な坂道を降りてレストラン照月湖ガーデンの前に来た。ガーデンはもはや紀之とは何の関係もなくなっていた。料理の腕は確かだが時々パチンコを打つという、やさぐれた風貌の入江信次郎シェフは株式会社浅間観光を退職し、悠太郎の通学路沿いにある小さなホテルの管理人に転じていた。あるとき千代次は信次郎シェフを評して、眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、「泥舟から真っ先に逃げ出したちゅうわけか? 浅間観光が沈みゆく泥舟ちゅうわけか?」と不興げに言ったが、自分が言ったことの不吉さのあまりいっそう不快になったらしく、宇宙全体を腐らせそうに顔を歪めたものであった。だが千代次の言ったことにも、あながち根拠がないではなかった。浅間観光の永久名誉顧問としての千代次に支払われる報酬は、ひと月十万円から八万円に、そして五万円に減らされていたのである。
レストラン照月湖ガーデンは、観光ホテル明鏡閣に新年度から入った板前の奥さんに任されていた。新海岳史さんというのがその板前であったが、にかっと歯を見せて泣き笑いのような顔をする新海さんを、千代次はあまりよく言わなかった。「ユウ、今度の板さんはのう、包丁よりも鋏を使うほうが得意だちゅうぞ。出来合いの袋物を鋏で開けて、一丁上がりちゅうわけよ。あんな者を入れるんならおめえ、サカエくんが料理をしたほうが、よっぽどいいのう。だがサカエくんは支配人だから、忙しくてそういうわけにもいくめえのう」というのが千代次の評価であった。レストラン照月湖ガーデンを任されたその奥さんは松子さんという名で、マッちゃんと呼ばれていた。たらこ唇のマッちゃんも、これまた評判がよろしくなかった。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、あの人にやらせて、ガーデンが繫盛するもんかね」と言ったことがあった。マッちゃんに任されてからガーデンは、うどんやそばを茹でて食べさせるだけの店になっていた。それも手打ちなんかではなく、袋うどんや乾燥そばを茹でて出しているだけであった。ガーデンのそばについては、この頃ひとつの事件が起こった。そばを食べ終えたひとりの客が「そば湯をください」と要求したのである。乾燥そばのそば湯を求められることを想定していなかったマッちゃんは、大いに狼狽して明鏡閣の事務所に電話を入れ、「サカエさん、どうしよう。そば湯をくれってお客が言うんだよ」と泣きついた。「どうしようもこうしようもあるもんか。乾燥そばを茹でたお湯を出すしかあるめえ。何、捨てちまった? 捨てちまったならおめえ、ねえ袖が振れるかよ。そば湯はありません、捨てちまいました、ごめんなさいと謝るしかあるめえ」というのが、受話器の向こうのサカエさんの答えであった。マッちゃんがその通りにすると、客は大いに立腹して帰った。そして噂は瞬く間に広まり、ガーデンはますます寂れてほとんど開店休業の状態になった。そういう話を悠太郎は秀子から聞いていた。そんな陰気なガーデンを横目に悠太郎は、大きな石段を降りて湖に近づいた。
様変わりしたのはガーデンだけではないなと悠太郎は考えた。これまた新年度から、狐目の男こと春藤秋男さんが、照月湖モビレージの責任者として入社していたのである。黒縁の眼鏡の奥で狐目を吊り上げた春藤さんは、いつも何かに驚いたように不服そうに口を尖らせている人で、その言動もいちいちが奇妙であった。何しろ入社早々にしたことというのが、おロク婆さんとおタキ婆さんを沖縄旅行に連れてゆくことであった。蒼白な顔で苦しげだったおタキ婆さんは南国の旅行から帰ると、見違えるように肌艶がよくなり元気づいていた。普段から血色のよかったおロク婆さんは、ますます活力に溢れていた。「まあず驚いたねえ沖縄というところは! 那覇空港を出るとねえ、もう街路樹に椰子の樹なんか生えてるの! ああ、南国へ来たなあと思ったっけ」とおロク婆さんが言いながら、旅行で撮影された写真のアルバムを開いてみせた。明鏡閣の社員食堂のみんなは、一行がお土産に買ってきたちんすこうを食べてお茶を飲みながら写真に見入った。そこに映っているのは碧緑の海であったり、琉球王国の栄華を偲ばせる豪壮華麗な首里城であったり、民族衣装の花笠を被って笑うおロク婆さんとおタキ婆さんであったりした。白い三角巾のおタキ婆さんは旅行をうっとりと思い出しながら、「あたしゃこれまで生きてきて、こんな楽しい思いをしたことはなかったよ」としみじみ言った。紫色の三角巾のおロク婆さんは、「まあず楽しかったねえ。春藤さんに感謝だよ。この思い出を励みに、またうんと働こうねえ」と活力ある声で言うと、「秀子ちゃん、うんじゅ・いっぺー・ちゅらかーぎー」と話しかけた。おタキ婆さんは「あなたはとても美人ですという意味だよ」と説明した。するとちんすこうを食べていた林浩一さんが、平たい顔をにこやかに笑わせながら、「そういえばユウくんは空手を習っているんでしたよね。 空手も沖縄発祥ですよね」と思い出したように言った。「何だって! ユウちゃんが空手を?」と驚いたおロク婆さんは、「悪いことは言わないからやめておきな。優しいユウちゃんにそんなことをやらせれば、ろくなことにはならないよ。ユウちゃんは絵を描いたり字を書いたり、ピアノを弾いたりしていたほうがよっぽどいいよ」と秀子に忠告した。春藤秋男さんはしかしロビーで黒い革張りのソファに座って、照月湖モビレージの看板の文字に蛍光塗料を塗っていたが、その仕事を切り上げて社員食堂にやって来ると言った。「ほっほい、それじゃ橋爪さん、熊川のほうへ与作をやりに行こうじゃねえか」
草木が生い茂るままに眠らせてある旧ホテルの跡地を開発して、熊川リバーサイドモビレージと称する新たなキャンプ場を作ろうというのが、春藤さんの打ち出した気宇壮大な計画であった。「ヘイヘイホーの定理!」と野良着姿の橋爪進吉さんは、ゲジゲジ眉毛の顔をひしゃげたように笑わせて張り切った。「気をつけとくれ橋爪さん。ヘイヘイホーは大怪我のもとちゅう諺もあるからな」と黒岩栄作支配人が、煙草の煙を輪っかの形にして連続で吐き出すと忠告した。「それを言うなら生兵法でしょう」と突っ込みを入れた板前の新海岳史さんは、にかっと歯を見せて泣き笑いのような顔をした。剽軽者の橋爪さんはしかし「ぼくは死にましぇーん!」と言っておどけたので、社員食堂のみんなは大笑いした。幌つきのジープには、斧やチェーンソーやロープや楔や脚立やヘルメットといった使えそうな道具が、倉庫から出されて満載されていた。春藤さんが運転するそのジープに乗って、寸胴の橋爪さんは河畔へと運ばれてゆくのである。そんな話を悠太郎は母の秀子から聞いていた。この春藤秋男さんのこともまた、悠太郎の祖父母は快く思っていなかった。千代次は眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、「春藤秋男か。名前からしていかがわしいのう。春なんだか秋なんだか分からねえ。浅間観光にも春秋戦国時代が到来したちゅうわけか」と評していた。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、わったしはあの男が好かないよ。あんな者は法螺吹きのいかさま師だよ。あの男は今に浅間観光をかんまして、禍いの種になるよ」と不信感を露わにしていた。ちなみに梅子は搔き回すことを「かんます」と言ったのである。そうだ、浅間観光もずいぶん様変わりしてしまった――。そんなことを考えながら悠太郎は水際に立った。
白樺林の枝葉を揺らす微風によって、暑熱のなかを運ばれてきた異様な臭気が悠太郎の鼻を突いた。この青臭いような生臭さはどこから来るのか? 不審に思って見れば、湖水は絵の具でも混ぜたように緑色に濁っていた。悠太郎は目を疑った。「それにしても、大きくなるとは嫌なものだな。俺はなんだか自分が濁った水にでもなってしまったような気がする」という紀之の言葉に影響されて、悪夢でも見ているのだと信じたかった。それで悠太郎は桟橋の突端から身を乗り出すと、緑色の湖水に手を差し入れた。そして濁った湖水を掬ってみた。緑色に濁った生臭い湖水は、くぼめた手のひらに掬っても緑色に濁っていて生臭かった。悠太郎の手のひらを零れた水は、湖に落ちて波紋を描いた。水面を滑っていたアメンボが驚いて逃げ出した。悠太郎が何度水に手を突っ込んでも、半袖のポロシャツが濡れるほど深々と腕を突っ込んでも、悪夢は醒めなかった。それは悪夢ではなかった。それは紛れもない現実であった。そのことに思い至って、悠太郎は恐怖のあまり胸の奥が冷たくなるのを感じた。次の瞬間には駆け出していた。そして橋の上を右往左往した。そしてボート番小屋に駆け込むと叫んだ。「桜井さん! 照月湖の水が、水が、水が……!」
ライサク老人こと桜井謙助さんは動揺した悠太郎を認めると、驚きのあまりギョロ目を見開いて額に三筋の皺を寄せた。「ああ、知ってるよ。水が緑色になって臭えんだろう? 今朝来て俺たちはみんな驚いたよ。アオコというものらしい。植物プランクトンの大量発生だとよ。こんなことは今までになかった。これも時勢かのう」とライサク老人は、落胆を滲ませながらも落ち着いて言った。だがその落ち着きは悠太郎を怒らせた。「時勢? 時勢ですって? 時勢だなんて言って済ませられることですか? こんなことがあっていいんですか? 照月湖のきれいな水がこんなになってしまうなんて、そんなことが許されていいんですか? ぼくは嫌だ。ぼくは認めない。絶対に認めない。バブルが弾けた。暖冬になった。冷夏になった。不景気になった。明鏡閣のクリスマスパーティーが中止になった。そして今度は照月湖の水がアオコで濁った。これを時勢だなんて言っている場合ですか? こんなのは設計ミスの時勢だ! ぼくは嫌だ。ぼくは認めない。ぼくはこれらのすべてを、絶対に認めない。崩れてゆくものがあるなら、その崩壊を食い止めなければならない。失われていったものは、何もかもひとつ残らず取り戻さなければならない。明鏡閣のみんなが諦めたって、今にぼくが大きくなってうんと勉強して、何もかもをひとつ残らず、あの美しかった時代に戻してみせる。必ず、必ず、必ず元に戻してみせる……!」
そんなことを叫びながら悠太郎は、大きな石段と急な坂道を駆け上がった。走るにつれて樹々の葉叢を洩れる光は、聞こえない音楽の川のようにきらきらと輝いた。お祖父様に知らせなければならない。だが知らせてどうするのか? 知らせるだけでいいのか? ぼくなりに何か考えられることはないのか? 暖冬とか冷夏とか猛暑とか水質汚染とか大気汚染とか、そういう問題を何というのだったか? 環境問題というのではないか? 崩れてゆくものの崩壊を、どうやって食い止める? 失われていったものを、どうやって取り戻す? お祖父様やお祖母様やお母様やぼくの大切なものを、どうやって守る? 環境……守る……環境……守る……。そうだ!――悠太郎は思い出した。学芸村の環境を守る会の代表という人が小学校でお話してくれたのは、つい昨日のことではないか。赤と灰色の市松模様の絨毯を敷いた多目的スペースで、児童たちはその老人の話を聞いたのではなかったか。頭に柔らかな銀髪を波打たせた藤原容三博士は、右半分が染みだらけの顔を全校児童に向けながら、会の活動について話していたではないか。「六里ヶ原は自然豊かなところです。その六里ヶ原に開かれた学芸村は、伝統ある別荘村です。学芸村では桃源郷のような環境が、緩やかな決まりのもとで六十年以上も保たれてきました。桃源郷というのは皆さん分かりますか? 俗世間を離れた、平和で豊かな別世界という意味です。ところが近年では、このあたりにもリゾートマンションの高層建築が造られ始めました。開発によって森林破壊が進んでいます。水道水の質も悪くなっています。これからは積極的に環境を守るための活動をしなければならない。そう考えて私たちは、町や県に陳情したり、新聞広告を出すための募金を集めたりしています。そうです、学芸村の環境を壊すものは何であれ、私たちはこれを許さないのです……」そんなことを話す藤原さんと、悠太郎は一瞬だけ目が合ったような気がしたものである。そうだ、学芸村の環境を守る会だ!
アオコで濁った照月湖は、その日のうちに千代次の細い目の見るところとなった。夕食の席では重苦しい空気のうちに、この重大な異変のことが話し合われた。「ひでえもんだ。あれじゃあ景観も台無しだ。まあすひでえもんだ」と千代次が眼鏡の奥で目をしばたたけば、「あんな臭い湖で、ボートに乗りたがる人がいるのかしら。へら鮒釣りのお客さんだって減っちゃう」と秀子が下膨れの顔に沈鬱な表情を浮かべた。「ウッフフ、まあず嫌だねえ。この暑さのせいもあるのかねえ。今年の夏はウッフフ、まあず暑いからねえ」と梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら言った。しかし千代次は気を取り直して、「だがユウはいいことを教えてくれた。学芸村の環境を守る会か。そんなものがあるらしいちゅう話は聞いていたが、小学校にも来ていたとはな。藤原さんなら俺は知っている。俺は浅間観光の人間だが、学芸村の理事でもある。守る会の代表と話ができるのは、浅間観光で俺しかいねえ。小学校に来たちゅうことは、もう別荘にいるはずだ。明日にでも早速訪ねてみることにしよう」と言うと、たったひとりの孫を極度に細い目でまじまじと見た。「ユウ、何だかんだ言っても、やはりおめえは成長したな」と千代次は柄にもない台詞を吐いた。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
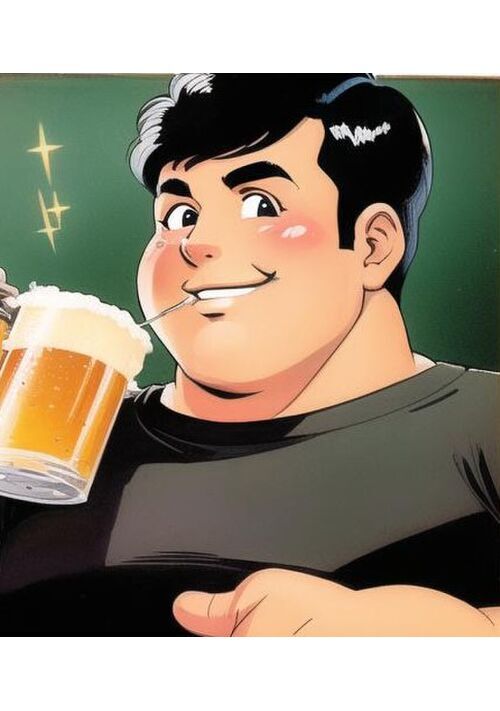
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















