25 / 73
第九章 左手の小指
一
しおりを挟む
また雨漏りがするようになった観光ホテル明鏡閣の大食堂には、調律の狂ったアップライトピアノが壁際に置かれてあった。その古ぼけたピアノの調律が狂っていることは、毛深いながら美しい指で鍵盤を叩いている悠太郎の聴覚には明らかであった。何しろ甘楽集落にある佐藤陽奈子先生の家で弾かせてもらうグランドピアノとは、全然調子が違うのだから。いくつもの音を一緒に鳴らして協和音を弾いても、変に歪んだような、濁ったような響きが混じるのだから。それでも悠太郎はその古ぼけたアップライトピアノを、そういうものとして愛していた。何しろ美しく揺らめく照月湖を右手の窓に望む、懐かしい観光ホテル明鏡閣の大食堂にそのピアノはあったから。奇妙に軽い鍵盤のアクションも、どこか口ごもるようなぼやぼやしたハンマーのアタックも、悠太郎にとってはかえって気楽であった。手入れが行き届いた陽奈子先生のグランドピアノが謹厳な師匠だとすると、明鏡閣のおんぼろなアップライトピアノは、心安い友達といった感じがした。お客さんがいない日のその大食堂には、クロスのかかったテーブルやビニールレザー張りの緑の椅子が、いかにも過去の記憶と未来の予感を帯びたように静かに並んでいたし、冷蔵庫に詰め込まれたビールやコーラやオレンジジュースの瓶はどっしりと充実していたし、調理場の側の天井に近い壁には、かつて一度だけ開催された照月湖の樹氷まつりの写真が、何枚も引き伸ばされて飾られていた。ライトアップされた湖畔の樹氷が華々しかったというその夜のことは、当時まだ三歳ほどだったという悠太郎の記憶からはとうに消えていた。もはやそれは遠い昔のことであった。
そういえば、悠太郎が今ひとりオレンジ色の表紙の『夢みるピアニスト』という楽譜集を開き、物問いたげな目を黒々と見開いて音符を追いながら弾いているのは、〈ロング・ロング・アゴー〉という曲であった。その題名の意味が「遠い遠い昔」であることを、悠太郎は幼稚園に入る前からすでに知っていた。ドソミソ・ドソミソ・ドソミソ・ドソミソ――左手に出てくるこういう音型を何といったかと悠太郎は考え、すぐにアルベルティ・バスという言葉を思い出した。イタリアの作曲家ドメニコ・アルベルティが好んで用いたからその名があるのだと、レッスンのとき悠太郎の左隣の椅子に座った陽奈子先生は、凛とした声で教えてくれた。陽奈子先生の家のグランドピアノがある部屋で、そうして悠太郎が教えを受けるあいだ、いつの頃からか留夏子はソファに座って眩しいものでも見るように、母親である陽奈子先生と、その新しい生徒である悠太郎のやり取りを見守るようになっていた。さすがはルカちゃんのお母様だけあって、本当に陽奈子先生は素敵な人だ。あの先生のもとでピアノの弾き方や音楽の仕組みを学べることが、ぼくにはどんなに幸せか知れない。レッスンのたびに陽奈子先生はたくさんのことを教えてくれるし、ルカちゃんは面白そうに見ていてくれる。考えてみればもう一年以上だ、ぼくがお母様に言われて陽奈子先生の生徒になるために、佐藤さんの農園の広いトウモロコシ畑を抜けて母屋を目指したのは。青空から燦々と光が降っていたあの夏の日に畑道を通るとき、両側に生い茂る背の高いトウモロコシを驚いて見上げたものだった。トウモロコシの雌蕊のひげをなびかせる爽やかな風に、あたり一面の緑濃い葉が海のようにざわめいていたものだった――。
「おおユウくん、お稽古は順調かい?」と声をかけられ、悠太郎は鍵盤を弾く手を止めて振り返った。その声の主は、薄黒いサングラスをかけたサカエさんこと黒岩栄作さんであった。サカエさんは楽譜をのぞき込みながら、「ロング・ロング・アゴーかい。遠い遠い昔か。あの写真の頃に比べりゃあおめえ、ユウくんはずいぶん大きくなったもんだ」と言って、壁に飾られた樹氷まつりの写真を指し示した。そこには結氷した照月湖の上でサカエさんに抱き上げられた小さな悠太郎が映っていた。「人は年を重ねれば重ねるほど、生きてきた過去は長く分厚くなる。小学校三年生のユウくんにだって、はあ立派なロング・ロング・アゴーがあるんべえ」と言ったサカエさんは、七三に分けたふさふさの黒髪を片手で搔き上げた。いつのまにやらピアノのまわりにはサカエさんばかりでなく、観光ホテル明鏡閣の従業員たちが集まってきていた。剽軽者の橋爪進吉さんは、寸胴の体を弾ませるようにピアノに歩み寄ると、ゲジゲジ眉毛の顔をひしゃげたように笑わせながら、「長い長い顎ー!」と言って自分の顎を際限なく伸ばすような仕草をしてみせたので、悠太郎は涙が出るほど笑わずにはいられなかった。頭を四角く刈り込んだ紳士的な南塚亮平支配人は「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いすると、「いやあ感慨無量ですなあ。悠太郎くんがこの明鏡閣でピアノのお稽古ですか。思えばわれらが浅間観光の創業者たる増田ケンポウ社長は邦楽を愛好しましたし、そのご夫人で後を引き継いだ二代目のおイネ社長は、熱海の芸者さんだった人ですからな。洋の東西の違いこそあれ、音楽は音楽です。きっと今頃はご夫妻して、悠太郎くんの上達を泉下で見守ってくださっていることでしょう」と慇懃に言った。バイク好きの林浩一さんは、平たい顔をにこやかに笑わせながら「秀子さん、ユウくんはこの分でいけば、今に女の子にもてますね」と悠太郎の悩み多き母親に冗談めかして言った。そのとき悠太郎はなぜかふと、いつもレッスンを見守ってくれるようになった留夏子のことを思ったが、すぐさまその想念を打ち消そうとした。ルカちゃんは先生の娘さんだから、そんなふうに邪心を持って見るのはよくない。幼稚園の頃から仲良くしてくれているのは、ぼくがあんまり弱いから可哀想に思って構ってくれているだけだ。いつもレッスンを見ていてくれるのだって、自分のお母様とぼくのやり取りを面白がっているだけだ。ルカちゃんはぼくなんかよりよっぽど優れた子だ。ぼくなんかをまともに相手にするはずがない――。そう思った悠太郎は今しがたの林さんの言葉から、留夏子の眩しいものでも見るような切れ長の目や、緑の髪ゴムで留めたポニーテールや、唐松林を吹き渡る朝風のような声を、無理にでももぎ離そうと努めた。そうしてまた左手にあるアルベルティ・バスの音のバランスに注意して、〈ロング・ロング・アゴー〉をさらい始めた。左手の小指が弾くいちばん低い音が、音楽の全体を支えなければならないのである。
おロク婆さんとおタキ婆さんも、えっちらおっちらやって来た。紫色の三角巾を被ったおロク婆さんは、血色のよい赤ら顔に笑みを浮かべて、「ユウちゃんは今に作曲をするよ。あたしがあげる紙にオタマジャクシを書くよ。ダ・ダ・ダ・ダーンてなもんだ」と活力ある声で言った。蒼白な顔のおタキ婆さんは苦しげに目を細めながら、「結局のところ作曲をする」とおちょぼ口でぼそぼそ駄洒落を言ったが、誰も聞いていなかった。会社のロゴが縫い取られた防水仕様の作業服を着て、ギョロ目の桜井謙助さんが現れた。ライサク老人は額に三筋の皺を寄せながら「時勢だのう。この田舎でも男の子がこういうことを習うとは。いやはや時勢だのう」と感慨を漏らした。常務の妹で彫刻家と結婚した、ひょろりと背の高い撫で肩の三池光子さんがいれば、悠太郎のピアノをことのほか喜んで聴いてくれたであろうが、光子さんはすでに定年退職していた。
豊かな黒髪を頭の後ろでお団子にまとめ、下膨れの顔にうっすらと愛想笑いを浮かべた秀子は、隙間の空いた大きな前歯を見せて笑いながら、林さんの冗談口を適当にあしらいつつ、悠太郎がこうなるまでの苦悩を思い出して、青いエプロンを掴んだ手にぶるぶると力を込めた。「そうなのだ、ひとまずはこれでいいのだ。愚図なこの子がおとなしく陽奈子さんのところへ通ってレッスンを受けていてくれれば、ひとまずはこれでいい。この六里ヶ原界隈に、あの陽奈子さんほど精神性の高い人は見当たらない。カトリックの信仰に裏打ちされた豊かな教養と、自己への厳しさは稀に見るものだ。悔しいけれど私なんか、あの人には到底敵わない。愚図なこの子がピアノを通じて、あの優れた女性から多くを学び取り、盗み取り、奪い取ってくれたらいい。そうすればこの子だって負けるはずがない。この子の母親である私だってそこらの馬の骨ではないし、それに離婚したこの子の父親だって、いかに肝っ玉が小さかったとはいえ、一度は外務省に勤めたほどの男だったのだから。幼稚園にして六里ヶ原の明鏡と謳われたこの子だ。優れた教育さえ受けさせれば、そこらの子供たちに負けるはずがない。開拓の連中に劣るはずがない。陽奈子さんの娘の、六里ヶ原始まって以来の奇跡と声望高い、あの留夏子ちゃんにさえ……。そうすれば私もこの子と一緒に老父の不興を買うこともない。そうすれば開拓嫌いでクラシック音楽好きの老母も、私を高く評価してくれるようになるだろう。しかしなぜもっと早く思いつかなかったのだろう。これこそ奇策妙案というものだ。ここまで本当に悩み苦しんだし気が揉めた。この子は今日もまた〈ロング・ロング・アゴー〉を弾いている。たどたどしくはあるが、着実にうまくなっている。この子の耳がいいことも歌がうまいことも、それこそずっとずっと前から私は知っていた。どうかこのまま順調に長続きがしてほしい。それでこそ家族のなかでの私の立場も危うくなくなる。それでこそ私はこの浅間山の麓で、英雄の母になれるのだ……」と秀子は念じながらピアノを弾くわが子を見つめ、青いエプロンを掴んだ手にぶるぶると力を込めつつ、それまでの苦悩の日々を思い起こした。
一九九一年に小学校二年生だった悠太郎が、千代次の強い意向に逆らって野球部への入部を拒否した頃から、千代次はそれまでにも増して苦渋に歪んだ顔をすることが多くなっていた。前年に起こった日経平均株価の大暴落は、バブル経済と呼ばれていた未曽有の好景気に暗い影を落としていたし、同じ年の夏にイラク軍が戦車を連ねてクウェートに侵攻したり、秋には東西ドイツがベートーヴェンの第九交響曲に酔い痴れながら統一されたりした。そうした不安定な世情を、千代次は眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、テレビのブラウン管越しに見つめ続けていた。年が明ければ多国籍軍がイラクの空爆を開始して湾岸戦争が始まり、スカッドミサイルがイラクからイスラエルやサウジアラビアに次々と打ち込まれた。自衛隊はPKOつまり国連平和維持活動の一環として、ペルシャ湾に派遣されている。正子をくれてやった英久の属する空軍だって、いつどうなるか分からねえ。世界は新世紀へと向かって激動している。それなのに何だおめえ、たったひとりの俺の孫の体たらくは。俺の言うことを聞かずに、野球部に入らねえとは何事だ。勉強も運動も一等になるぐれえの気概がなくて、これからの世界を生き延びられるか! こんなことじゃ駄目だろう! 駄目だろう! 駄目だろう!――ともかくも千代次は不機嫌のあまり、日がな一日苦渋に顔を歪めていた。そんな様子を見ていた梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、うちの人がこんな有様じゃあねえ、わったしまで気が滅入るよ。ほれ秀子、あのけったくそ悪い悠太郎をどうにかしろ。お祖父様の言うことが聞けねえなんて、いよいよ悪魔の性質が出てきたよ。おまえが結婚したあの男は、あの悠太郎の父親は悪魔だったんだよ。忌々しいねえ、あのけったくそ悪い孫は、やっぱり悪魔の種だよ。このままじゃあの子は開拓の奴等に遅れを取るよ。おまえはそれでいいのかい? わったしは嫌だね、嫌なこった! わったしの孫が屯匪の孫に遅れを取るなんて御免だよ。そんなことにでもなってみろ。うちの人はねえ、きっとおまえたち親子を家から追い出すよ。馬鹿な親と馬鹿なその子をうちに置いてやるほどウッフフ、わったしたちは寛大じゃないんだからね」と言って秀子を責め苛むのであった。
そんな苦悩の日々にあっても、老朽化が目立ってきた観光ホテル明鏡閣での秀子の仕事は続いていた。悠太郎が野球部への入部を頑なに拒んだのは、長崎県の雲仙普賢岳が大火砕流を発生させて多くの死者を出し、またフィリピンのピナツボ火山が二十世紀最大規模の大噴火を起こした頃であったから、活火山である浅間山の麓に暮らしている多感な悠太郎の不安を、秀子も慮らないではなかった。しかし老父母の不興を買いながら忙しく働き続けることは、秀子にとってやはり応えた。バブル崩壊の兆しが遠くから迫り来るなかにあって、秀子は不吉な予感を振り払おうとでもするかのように、古い柱時計が時を刻むロビーでワインレッドの絨毯に掃除機をかけたり、調理場で金ザルいっぱいの米を研いだり、大量の汚れた食器を洗ったり、小暗い廊下を客室から客室へと渡り歩いて、お茶菓子や小型の冷蔵庫の飲み物を補充したり、トイレやバスルームを清掃したり、洗濯され乾燥したリネンや浴衣やその帯を畳んだりした。私がここで負けるわけにはゆかないのだ。すべてはあの子のためなのだ。あの子を百点満点の子にするために、私はここで働くことに決めたのだ。あれからもう三年以上だが、もっともっと長かったような気がする。これからもまだまだ負けるわけにはゆかないのだ、あの子をこの六里ヶ原の英雄にするまでは。何とかしなければならない、何とかしなければならない――。秀子がぶるぶると身をふるわせながら大食堂の片づけをしていたあるとき、一緒に仕事をしていた黒岩サカエさんが、ふと壁際のアップライトピアノにサングラス越しの目を留めて、「このピアノはおめえ、すっかり古ぼけちまって、調子だって狂っているんべえ。弾いてくれる人もいねえで、宝の持ち腐れだ。どうにか使い道はねえもんかなあ」と言った。そんなサカエさんの言葉を、しかし家庭の悩みで頭がいっぱいの秀子は、上の空で聞いていた。
そしてまた別のあるときには、来たるべき大勢の宿泊客に備えて、秀子は客室のある一階と二階の廊下に掃除機を掛けねばならなかった。二階の西の翼部から大広間の前を通り、ロビーの近くへ降りる階段を一段一段、タンクの大きな業務用の掃除機で苦労しながら清掃していたとき、突然秀子は悠太郎の卒園式の日に開かれた謝恩会のことを思い出した。謝恩会が果てた後で、大広間を出てこの階段を降りるとき、簡素な草色のドレスを着た陽奈子さんはこの踊り場で立ち止まると、静かな決意を込めた凛とした声で、「遠からず甘楽の家でピアノ教室を開くことにしました。自然豊かなこの高原で、農業と芸術をひとつに結びつけることが、長いあいだの私の夢だったの。人の心には多くの計画があっても、すべてが実現するわけじゃないわ。でもやっぱり私は理想を諦めたくないもの」と言ったのである。
そのとき秀子のなかではすべてがひとつに繋がったので、タンクの重たい掃除機を放り出して躍り上がりたいような気持ちであった。「なぜこんなことをもっと早くに思いつかなかったのだろう。そうだ、悠太郎を陽奈子さんの生徒にするのだ。陽奈子さんのピアノ教室に通わせるのだ。悠太郎にピアノを習わせるのだ。練習用の楽器だったらこの明鏡閣にあるではないか。多少狂っていようがピアノはピアノだ。お客さんがいないときの大食堂でお稽古させればいい。これで野球部のことで老父から買った不興を、差し当たり和らげることができる。運動は運動で野球以外のものを、いずれまた何か見つけてやらせればいい。老父は教養のためなら惜しみなくお金を使う人だ。明鏡閣のピアノで練習しているうちに、いずれわが家にも楽器を用意してくれないとも限らない。何しろ老母はクラシック音楽が大好きだ。昔わが家にあったステレオレコードプレーヤーは、小さかった悠太郎が歩きまわるのに危ないので処分してしまったが、そうなる前には老母はずいぶんレコード盤を集めては聴き込んでいたものだった。悠太郎がピアノを弾けるようになれば、そんな老母の機嫌もよくなるに違いない。何より陽奈子さんの娘の留夏子ちゃんやその弟の隼平くんと、悠太郎は幼稚園の頃から仲が良かった。佐藤さんの家にピアノを習いにゆくことを、悠太郎はよもや拒みはすまい。もちろんわが子には群を抜いていてほしい。まわりの子供たちからは抜きん出ていてほしい。しかし生きる気力を失うほどまわりの子供たちから孤立するのも、やはり問題だ。時々はピアノを習いにゆくと見せかけて、ジュンくんやルカちゃんと外で遊んだり、スーパーファミコンに興じたりしたって構わないではないか。そうすれば子供たちを通しても、あの優れた母親の高い精神性を、悠太郎はものにできるのだ。開拓嫌いの老母といえども、ピアノが関われば悪くは言うまい。だがもし子供たちと仲良くなりすぎたら……? いや、心配には及ばない。所詮は子供たちのことだ。いざとなれば引き裂く手段はいくらでもあるというものだ。陽奈子さんのもとで悠太郎にピアノとは! これこそ奇策妙案というものだ。この策はきっとうまくゆく、きっとうまくゆく……」
明鏡閣での仕事を終えた秀子は、宵闇のなか猛然と自動車を飛ばして揺らめく照月湖を右手に走り、レストラン照月湖ガーデンの前で左折して急な坂道を登った。その坂道のコンクリートに刻まれた無数の溝のために、自動車は行き来するたびいつもガタガタと弾むのだが、その夕方の秀子にとってはそんな振動さえ、喜びに弾む心の躍動に等しかった。いくつかの別荘や女学園の山の家の前を通り過ぎ、自動車を真壁の家の門に乗り入れると、秀子は薄紫のミヤコワスレが群れ咲く玄関の前で飛び降りて、激しく叩きつけるように運転席のドアを閉めた。それから玄関のドアをがばと開けバタンと閉め、廊下をドスン・ドスン・ドスン・ドスン・ドスンと五歩踏み鳴らして、居間への引き戸をガラガラと開けた。母の帰宅を告げるその一連の音響とリズムを、悠太郎は居間からガラス戸一枚隔てた縁側の学習机で宿題をこなしながら、今日のお母様は珍しく機嫌がいいなと思って聞いていた。すると秀子は鞄も置かず、水仕事で濡れた青いエプロンも脱がずに悠太郎のもとへ来た。計算ドリルから顔を上げ、物問いたげな目を見開いて不思議そうな表情をするわが子に「悠太郎、おまえはピアノを習うのよ。佐藤陽奈子さんのピアノ教室に入るのよ。ルカちゃんとジュンくんのお母様に、おまえは音楽を教わるのよ」と秀子は告げた。わが子が何の抵抗も示さず、表情ひとつ変えずにこっくりと頷くことまで、秀子の予想していた通りであった。悠太郎は家族の要求を拒むことに疲れていた。あたかも野球部の一件で、一生分の抵抗力を使い果たしてしまったような気がしていた。千代次の求めに応じて野球部に入らなかったことを、悠太郎は重大な罪悪と感じていたから、次に家族から何かを求められたら、どんなに嫌なことでも黙って従うしかないと考えていた。その何かが野球部のように過酷なものでないことを祈るばかりであったが、こうして秀子から告げられたピアノ教室とはまた意外なことであり、慕わしいルカちゃんのお母様の生徒になれると聞けば、罪ある身ながら寛典に処せられたような安堵感が悠太郎の胸に広がった。しかし家族をも容易に信じなくなっていた悠太郎は、珍しく上機嫌の母に胸中を気取られることを恐れて、表情ひとつ変えずにこっくりと頷いたのであった。
若くて背の高い丸橋清一先生は、東南アジア的な濃い目鼻立ちの童顔に喜色を湛えながら、体育館で終業式を終えた後の教室で、一学期を終えた二年生たちを誕生日順に呼び出しては、彼らに通知表を次々と手渡した。大屋原第三集落の神川直矢は、白目の冴えた面白がるような小さな目で、体育以外の自分の成績の芳しくないことを見て取ると、機関銃のように高笑いした。夏休みの宿題など直矢は恐れていなかった。勉強のできる悠太郎に手伝ってもらうことを、はなから当てにしていたのである。大屋原第一集落の佐原康雄は、学年一の俊足で鳴らす体育のみならず、ほかの科目でも平均を上回っていたから、荒れた唇を笑わせて浅黒い顔を輝かせた。栗平の芹沢カイは、未熟児として生まれただけあって身長は誰より低かったが、昇り棒を身軽にするすると昇り降りする能力に恵まれていた。その敏捷さが評価されて、体育の成績もなかなか悪くなかったし、国語では朗読の表現力が抜きん出ていたために好成績を得たので、目許に静かな知性を光らせながら、雀斑の散った小さな顔をニヤリと笑わせた。さてカイより二日遅れて同じ病院で生まれた悠太郎の番が来た。悠太郎の成績はオールAであった――もちろん体育を除いてのことである。虚弱で脚の遅い悠太郎の体育の成績は、惨めなことに最低のCであった。このことがまた家族を怒らせるであろうことは容易に想像できたので、悠太郎は涙ぐみながら睫毛の長い目を悄然と伏せた。甘楽集落の戸井田一輝は、授業中の手悪さを諫める手厳しい評価にはあまり頓着せず、学校から解放されて夏休みを迎えられる喜びに、むっちりと発育のよい体を弾ませた。留夏子の弟の佐藤隼平は、ひょろ長い手足を持て余したような歩き方で、渋々進み出て通知表を受け取った。そのいくらか斜視気味の切れ長の目は、国語の最低評価を表すCの字を見たが、姉と違って教科書の文字を読むことが苦手な隼平であってみれば、やむを得ぬ評価であった。林檎のように赤い頬をした金谷涼子は、幼い頃からお化けをも恐れぬ豪胆さを備えていたから、通知表など恐れるに足りなかった。だが涼子が心配したのは、北軽井沢市街地から登校している諸星真花名のことであった。軽薄な丸橋先生は通知表を真花名に手渡しがてら、あろうことかその中身を児童たちの前で喋ったのみならず、幼稚園時代の心の傷に触れる軽口を、それとは知らずに叩いたのである。「いよっ、真花名ちゃんはオールAだね! 勉強も運動もオールAだ! 悠太郎くんのいいライバルだね! 結婚すれば真壁真花名でマカマカだ! ヒューヒュー! 熱いね!」という丸橋先生の冷やかしに教室中が沸くなかで、髪を短くした真花名は幸薄そうな顔をうつむけ、わずかにしゃくれた顎を胸にくっつけるようにして身をこわばらせていた。そんな真花名を涼子は黒曜石のように光る目で見守っていたが、しかし悠太郎はやがて入門する佐藤陽奈子先生のピアノ教室のことや、そこでも出くわすことになるであろう留夏子のことを考えていた。
そういえば、悠太郎が今ひとりオレンジ色の表紙の『夢みるピアニスト』という楽譜集を開き、物問いたげな目を黒々と見開いて音符を追いながら弾いているのは、〈ロング・ロング・アゴー〉という曲であった。その題名の意味が「遠い遠い昔」であることを、悠太郎は幼稚園に入る前からすでに知っていた。ドソミソ・ドソミソ・ドソミソ・ドソミソ――左手に出てくるこういう音型を何といったかと悠太郎は考え、すぐにアルベルティ・バスという言葉を思い出した。イタリアの作曲家ドメニコ・アルベルティが好んで用いたからその名があるのだと、レッスンのとき悠太郎の左隣の椅子に座った陽奈子先生は、凛とした声で教えてくれた。陽奈子先生の家のグランドピアノがある部屋で、そうして悠太郎が教えを受けるあいだ、いつの頃からか留夏子はソファに座って眩しいものでも見るように、母親である陽奈子先生と、その新しい生徒である悠太郎のやり取りを見守るようになっていた。さすがはルカちゃんのお母様だけあって、本当に陽奈子先生は素敵な人だ。あの先生のもとでピアノの弾き方や音楽の仕組みを学べることが、ぼくにはどんなに幸せか知れない。レッスンのたびに陽奈子先生はたくさんのことを教えてくれるし、ルカちゃんは面白そうに見ていてくれる。考えてみればもう一年以上だ、ぼくがお母様に言われて陽奈子先生の生徒になるために、佐藤さんの農園の広いトウモロコシ畑を抜けて母屋を目指したのは。青空から燦々と光が降っていたあの夏の日に畑道を通るとき、両側に生い茂る背の高いトウモロコシを驚いて見上げたものだった。トウモロコシの雌蕊のひげをなびかせる爽やかな風に、あたり一面の緑濃い葉が海のようにざわめいていたものだった――。
「おおユウくん、お稽古は順調かい?」と声をかけられ、悠太郎は鍵盤を弾く手を止めて振り返った。その声の主は、薄黒いサングラスをかけたサカエさんこと黒岩栄作さんであった。サカエさんは楽譜をのぞき込みながら、「ロング・ロング・アゴーかい。遠い遠い昔か。あの写真の頃に比べりゃあおめえ、ユウくんはずいぶん大きくなったもんだ」と言って、壁に飾られた樹氷まつりの写真を指し示した。そこには結氷した照月湖の上でサカエさんに抱き上げられた小さな悠太郎が映っていた。「人は年を重ねれば重ねるほど、生きてきた過去は長く分厚くなる。小学校三年生のユウくんにだって、はあ立派なロング・ロング・アゴーがあるんべえ」と言ったサカエさんは、七三に分けたふさふさの黒髪を片手で搔き上げた。いつのまにやらピアノのまわりにはサカエさんばかりでなく、観光ホテル明鏡閣の従業員たちが集まってきていた。剽軽者の橋爪進吉さんは、寸胴の体を弾ませるようにピアノに歩み寄ると、ゲジゲジ眉毛の顔をひしゃげたように笑わせながら、「長い長い顎ー!」と言って自分の顎を際限なく伸ばすような仕草をしてみせたので、悠太郎は涙が出るほど笑わずにはいられなかった。頭を四角く刈り込んだ紳士的な南塚亮平支配人は「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いすると、「いやあ感慨無量ですなあ。悠太郎くんがこの明鏡閣でピアノのお稽古ですか。思えばわれらが浅間観光の創業者たる増田ケンポウ社長は邦楽を愛好しましたし、そのご夫人で後を引き継いだ二代目のおイネ社長は、熱海の芸者さんだった人ですからな。洋の東西の違いこそあれ、音楽は音楽です。きっと今頃はご夫妻して、悠太郎くんの上達を泉下で見守ってくださっていることでしょう」と慇懃に言った。バイク好きの林浩一さんは、平たい顔をにこやかに笑わせながら「秀子さん、ユウくんはこの分でいけば、今に女の子にもてますね」と悠太郎の悩み多き母親に冗談めかして言った。そのとき悠太郎はなぜかふと、いつもレッスンを見守ってくれるようになった留夏子のことを思ったが、すぐさまその想念を打ち消そうとした。ルカちゃんは先生の娘さんだから、そんなふうに邪心を持って見るのはよくない。幼稚園の頃から仲良くしてくれているのは、ぼくがあんまり弱いから可哀想に思って構ってくれているだけだ。いつもレッスンを見ていてくれるのだって、自分のお母様とぼくのやり取りを面白がっているだけだ。ルカちゃんはぼくなんかよりよっぽど優れた子だ。ぼくなんかをまともに相手にするはずがない――。そう思った悠太郎は今しがたの林さんの言葉から、留夏子の眩しいものでも見るような切れ長の目や、緑の髪ゴムで留めたポニーテールや、唐松林を吹き渡る朝風のような声を、無理にでももぎ離そうと努めた。そうしてまた左手にあるアルベルティ・バスの音のバランスに注意して、〈ロング・ロング・アゴー〉をさらい始めた。左手の小指が弾くいちばん低い音が、音楽の全体を支えなければならないのである。
おロク婆さんとおタキ婆さんも、えっちらおっちらやって来た。紫色の三角巾を被ったおロク婆さんは、血色のよい赤ら顔に笑みを浮かべて、「ユウちゃんは今に作曲をするよ。あたしがあげる紙にオタマジャクシを書くよ。ダ・ダ・ダ・ダーンてなもんだ」と活力ある声で言った。蒼白な顔のおタキ婆さんは苦しげに目を細めながら、「結局のところ作曲をする」とおちょぼ口でぼそぼそ駄洒落を言ったが、誰も聞いていなかった。会社のロゴが縫い取られた防水仕様の作業服を着て、ギョロ目の桜井謙助さんが現れた。ライサク老人は額に三筋の皺を寄せながら「時勢だのう。この田舎でも男の子がこういうことを習うとは。いやはや時勢だのう」と感慨を漏らした。常務の妹で彫刻家と結婚した、ひょろりと背の高い撫で肩の三池光子さんがいれば、悠太郎のピアノをことのほか喜んで聴いてくれたであろうが、光子さんはすでに定年退職していた。
豊かな黒髪を頭の後ろでお団子にまとめ、下膨れの顔にうっすらと愛想笑いを浮かべた秀子は、隙間の空いた大きな前歯を見せて笑いながら、林さんの冗談口を適当にあしらいつつ、悠太郎がこうなるまでの苦悩を思い出して、青いエプロンを掴んだ手にぶるぶると力を込めた。「そうなのだ、ひとまずはこれでいいのだ。愚図なこの子がおとなしく陽奈子さんのところへ通ってレッスンを受けていてくれれば、ひとまずはこれでいい。この六里ヶ原界隈に、あの陽奈子さんほど精神性の高い人は見当たらない。カトリックの信仰に裏打ちされた豊かな教養と、自己への厳しさは稀に見るものだ。悔しいけれど私なんか、あの人には到底敵わない。愚図なこの子がピアノを通じて、あの優れた女性から多くを学び取り、盗み取り、奪い取ってくれたらいい。そうすればこの子だって負けるはずがない。この子の母親である私だってそこらの馬の骨ではないし、それに離婚したこの子の父親だって、いかに肝っ玉が小さかったとはいえ、一度は外務省に勤めたほどの男だったのだから。幼稚園にして六里ヶ原の明鏡と謳われたこの子だ。優れた教育さえ受けさせれば、そこらの子供たちに負けるはずがない。開拓の連中に劣るはずがない。陽奈子さんの娘の、六里ヶ原始まって以来の奇跡と声望高い、あの留夏子ちゃんにさえ……。そうすれば私もこの子と一緒に老父の不興を買うこともない。そうすれば開拓嫌いでクラシック音楽好きの老母も、私を高く評価してくれるようになるだろう。しかしなぜもっと早く思いつかなかったのだろう。これこそ奇策妙案というものだ。ここまで本当に悩み苦しんだし気が揉めた。この子は今日もまた〈ロング・ロング・アゴー〉を弾いている。たどたどしくはあるが、着実にうまくなっている。この子の耳がいいことも歌がうまいことも、それこそずっとずっと前から私は知っていた。どうかこのまま順調に長続きがしてほしい。それでこそ家族のなかでの私の立場も危うくなくなる。それでこそ私はこの浅間山の麓で、英雄の母になれるのだ……」と秀子は念じながらピアノを弾くわが子を見つめ、青いエプロンを掴んだ手にぶるぶると力を込めつつ、それまでの苦悩の日々を思い起こした。
一九九一年に小学校二年生だった悠太郎が、千代次の強い意向に逆らって野球部への入部を拒否した頃から、千代次はそれまでにも増して苦渋に歪んだ顔をすることが多くなっていた。前年に起こった日経平均株価の大暴落は、バブル経済と呼ばれていた未曽有の好景気に暗い影を落としていたし、同じ年の夏にイラク軍が戦車を連ねてクウェートに侵攻したり、秋には東西ドイツがベートーヴェンの第九交響曲に酔い痴れながら統一されたりした。そうした不安定な世情を、千代次は眼鏡の奥で極度に細い近視の目をしばたたきながら、テレビのブラウン管越しに見つめ続けていた。年が明ければ多国籍軍がイラクの空爆を開始して湾岸戦争が始まり、スカッドミサイルがイラクからイスラエルやサウジアラビアに次々と打ち込まれた。自衛隊はPKOつまり国連平和維持活動の一環として、ペルシャ湾に派遣されている。正子をくれてやった英久の属する空軍だって、いつどうなるか分からねえ。世界は新世紀へと向かって激動している。それなのに何だおめえ、たったひとりの俺の孫の体たらくは。俺の言うことを聞かずに、野球部に入らねえとは何事だ。勉強も運動も一等になるぐれえの気概がなくて、これからの世界を生き延びられるか! こんなことじゃ駄目だろう! 駄目だろう! 駄目だろう!――ともかくも千代次は不機嫌のあまり、日がな一日苦渋に顔を歪めていた。そんな様子を見ていた梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、うちの人がこんな有様じゃあねえ、わったしまで気が滅入るよ。ほれ秀子、あのけったくそ悪い悠太郎をどうにかしろ。お祖父様の言うことが聞けねえなんて、いよいよ悪魔の性質が出てきたよ。おまえが結婚したあの男は、あの悠太郎の父親は悪魔だったんだよ。忌々しいねえ、あのけったくそ悪い孫は、やっぱり悪魔の種だよ。このままじゃあの子は開拓の奴等に遅れを取るよ。おまえはそれでいいのかい? わったしは嫌だね、嫌なこった! わったしの孫が屯匪の孫に遅れを取るなんて御免だよ。そんなことにでもなってみろ。うちの人はねえ、きっとおまえたち親子を家から追い出すよ。馬鹿な親と馬鹿なその子をうちに置いてやるほどウッフフ、わったしたちは寛大じゃないんだからね」と言って秀子を責め苛むのであった。
そんな苦悩の日々にあっても、老朽化が目立ってきた観光ホテル明鏡閣での秀子の仕事は続いていた。悠太郎が野球部への入部を頑なに拒んだのは、長崎県の雲仙普賢岳が大火砕流を発生させて多くの死者を出し、またフィリピンのピナツボ火山が二十世紀最大規模の大噴火を起こした頃であったから、活火山である浅間山の麓に暮らしている多感な悠太郎の不安を、秀子も慮らないではなかった。しかし老父母の不興を買いながら忙しく働き続けることは、秀子にとってやはり応えた。バブル崩壊の兆しが遠くから迫り来るなかにあって、秀子は不吉な予感を振り払おうとでもするかのように、古い柱時計が時を刻むロビーでワインレッドの絨毯に掃除機をかけたり、調理場で金ザルいっぱいの米を研いだり、大量の汚れた食器を洗ったり、小暗い廊下を客室から客室へと渡り歩いて、お茶菓子や小型の冷蔵庫の飲み物を補充したり、トイレやバスルームを清掃したり、洗濯され乾燥したリネンや浴衣やその帯を畳んだりした。私がここで負けるわけにはゆかないのだ。すべてはあの子のためなのだ。あの子を百点満点の子にするために、私はここで働くことに決めたのだ。あれからもう三年以上だが、もっともっと長かったような気がする。これからもまだまだ負けるわけにはゆかないのだ、あの子をこの六里ヶ原の英雄にするまでは。何とかしなければならない、何とかしなければならない――。秀子がぶるぶると身をふるわせながら大食堂の片づけをしていたあるとき、一緒に仕事をしていた黒岩サカエさんが、ふと壁際のアップライトピアノにサングラス越しの目を留めて、「このピアノはおめえ、すっかり古ぼけちまって、調子だって狂っているんべえ。弾いてくれる人もいねえで、宝の持ち腐れだ。どうにか使い道はねえもんかなあ」と言った。そんなサカエさんの言葉を、しかし家庭の悩みで頭がいっぱいの秀子は、上の空で聞いていた。
そしてまた別のあるときには、来たるべき大勢の宿泊客に備えて、秀子は客室のある一階と二階の廊下に掃除機を掛けねばならなかった。二階の西の翼部から大広間の前を通り、ロビーの近くへ降りる階段を一段一段、タンクの大きな業務用の掃除機で苦労しながら清掃していたとき、突然秀子は悠太郎の卒園式の日に開かれた謝恩会のことを思い出した。謝恩会が果てた後で、大広間を出てこの階段を降りるとき、簡素な草色のドレスを着た陽奈子さんはこの踊り場で立ち止まると、静かな決意を込めた凛とした声で、「遠からず甘楽の家でピアノ教室を開くことにしました。自然豊かなこの高原で、農業と芸術をひとつに結びつけることが、長いあいだの私の夢だったの。人の心には多くの計画があっても、すべてが実現するわけじゃないわ。でもやっぱり私は理想を諦めたくないもの」と言ったのである。
そのとき秀子のなかではすべてがひとつに繋がったので、タンクの重たい掃除機を放り出して躍り上がりたいような気持ちであった。「なぜこんなことをもっと早くに思いつかなかったのだろう。そうだ、悠太郎を陽奈子さんの生徒にするのだ。陽奈子さんのピアノ教室に通わせるのだ。悠太郎にピアノを習わせるのだ。練習用の楽器だったらこの明鏡閣にあるではないか。多少狂っていようがピアノはピアノだ。お客さんがいないときの大食堂でお稽古させればいい。これで野球部のことで老父から買った不興を、差し当たり和らげることができる。運動は運動で野球以外のものを、いずれまた何か見つけてやらせればいい。老父は教養のためなら惜しみなくお金を使う人だ。明鏡閣のピアノで練習しているうちに、いずれわが家にも楽器を用意してくれないとも限らない。何しろ老母はクラシック音楽が大好きだ。昔わが家にあったステレオレコードプレーヤーは、小さかった悠太郎が歩きまわるのに危ないので処分してしまったが、そうなる前には老母はずいぶんレコード盤を集めては聴き込んでいたものだった。悠太郎がピアノを弾けるようになれば、そんな老母の機嫌もよくなるに違いない。何より陽奈子さんの娘の留夏子ちゃんやその弟の隼平くんと、悠太郎は幼稚園の頃から仲が良かった。佐藤さんの家にピアノを習いにゆくことを、悠太郎はよもや拒みはすまい。もちろんわが子には群を抜いていてほしい。まわりの子供たちからは抜きん出ていてほしい。しかし生きる気力を失うほどまわりの子供たちから孤立するのも、やはり問題だ。時々はピアノを習いにゆくと見せかけて、ジュンくんやルカちゃんと外で遊んだり、スーパーファミコンに興じたりしたって構わないではないか。そうすれば子供たちを通しても、あの優れた母親の高い精神性を、悠太郎はものにできるのだ。開拓嫌いの老母といえども、ピアノが関われば悪くは言うまい。だがもし子供たちと仲良くなりすぎたら……? いや、心配には及ばない。所詮は子供たちのことだ。いざとなれば引き裂く手段はいくらでもあるというものだ。陽奈子さんのもとで悠太郎にピアノとは! これこそ奇策妙案というものだ。この策はきっとうまくゆく、きっとうまくゆく……」
明鏡閣での仕事を終えた秀子は、宵闇のなか猛然と自動車を飛ばして揺らめく照月湖を右手に走り、レストラン照月湖ガーデンの前で左折して急な坂道を登った。その坂道のコンクリートに刻まれた無数の溝のために、自動車は行き来するたびいつもガタガタと弾むのだが、その夕方の秀子にとってはそんな振動さえ、喜びに弾む心の躍動に等しかった。いくつかの別荘や女学園の山の家の前を通り過ぎ、自動車を真壁の家の門に乗り入れると、秀子は薄紫のミヤコワスレが群れ咲く玄関の前で飛び降りて、激しく叩きつけるように運転席のドアを閉めた。それから玄関のドアをがばと開けバタンと閉め、廊下をドスン・ドスン・ドスン・ドスン・ドスンと五歩踏み鳴らして、居間への引き戸をガラガラと開けた。母の帰宅を告げるその一連の音響とリズムを、悠太郎は居間からガラス戸一枚隔てた縁側の学習机で宿題をこなしながら、今日のお母様は珍しく機嫌がいいなと思って聞いていた。すると秀子は鞄も置かず、水仕事で濡れた青いエプロンも脱がずに悠太郎のもとへ来た。計算ドリルから顔を上げ、物問いたげな目を見開いて不思議そうな表情をするわが子に「悠太郎、おまえはピアノを習うのよ。佐藤陽奈子さんのピアノ教室に入るのよ。ルカちゃんとジュンくんのお母様に、おまえは音楽を教わるのよ」と秀子は告げた。わが子が何の抵抗も示さず、表情ひとつ変えずにこっくりと頷くことまで、秀子の予想していた通りであった。悠太郎は家族の要求を拒むことに疲れていた。あたかも野球部の一件で、一生分の抵抗力を使い果たしてしまったような気がしていた。千代次の求めに応じて野球部に入らなかったことを、悠太郎は重大な罪悪と感じていたから、次に家族から何かを求められたら、どんなに嫌なことでも黙って従うしかないと考えていた。その何かが野球部のように過酷なものでないことを祈るばかりであったが、こうして秀子から告げられたピアノ教室とはまた意外なことであり、慕わしいルカちゃんのお母様の生徒になれると聞けば、罪ある身ながら寛典に処せられたような安堵感が悠太郎の胸に広がった。しかし家族をも容易に信じなくなっていた悠太郎は、珍しく上機嫌の母に胸中を気取られることを恐れて、表情ひとつ変えずにこっくりと頷いたのであった。
若くて背の高い丸橋清一先生は、東南アジア的な濃い目鼻立ちの童顔に喜色を湛えながら、体育館で終業式を終えた後の教室で、一学期を終えた二年生たちを誕生日順に呼び出しては、彼らに通知表を次々と手渡した。大屋原第三集落の神川直矢は、白目の冴えた面白がるような小さな目で、体育以外の自分の成績の芳しくないことを見て取ると、機関銃のように高笑いした。夏休みの宿題など直矢は恐れていなかった。勉強のできる悠太郎に手伝ってもらうことを、はなから当てにしていたのである。大屋原第一集落の佐原康雄は、学年一の俊足で鳴らす体育のみならず、ほかの科目でも平均を上回っていたから、荒れた唇を笑わせて浅黒い顔を輝かせた。栗平の芹沢カイは、未熟児として生まれただけあって身長は誰より低かったが、昇り棒を身軽にするすると昇り降りする能力に恵まれていた。その敏捷さが評価されて、体育の成績もなかなか悪くなかったし、国語では朗読の表現力が抜きん出ていたために好成績を得たので、目許に静かな知性を光らせながら、雀斑の散った小さな顔をニヤリと笑わせた。さてカイより二日遅れて同じ病院で生まれた悠太郎の番が来た。悠太郎の成績はオールAであった――もちろん体育を除いてのことである。虚弱で脚の遅い悠太郎の体育の成績は、惨めなことに最低のCであった。このことがまた家族を怒らせるであろうことは容易に想像できたので、悠太郎は涙ぐみながら睫毛の長い目を悄然と伏せた。甘楽集落の戸井田一輝は、授業中の手悪さを諫める手厳しい評価にはあまり頓着せず、学校から解放されて夏休みを迎えられる喜びに、むっちりと発育のよい体を弾ませた。留夏子の弟の佐藤隼平は、ひょろ長い手足を持て余したような歩き方で、渋々進み出て通知表を受け取った。そのいくらか斜視気味の切れ長の目は、国語の最低評価を表すCの字を見たが、姉と違って教科書の文字を読むことが苦手な隼平であってみれば、やむを得ぬ評価であった。林檎のように赤い頬をした金谷涼子は、幼い頃からお化けをも恐れぬ豪胆さを備えていたから、通知表など恐れるに足りなかった。だが涼子が心配したのは、北軽井沢市街地から登校している諸星真花名のことであった。軽薄な丸橋先生は通知表を真花名に手渡しがてら、あろうことかその中身を児童たちの前で喋ったのみならず、幼稚園時代の心の傷に触れる軽口を、それとは知らずに叩いたのである。「いよっ、真花名ちゃんはオールAだね! 勉強も運動もオールAだ! 悠太郎くんのいいライバルだね! 結婚すれば真壁真花名でマカマカだ! ヒューヒュー! 熱いね!」という丸橋先生の冷やかしに教室中が沸くなかで、髪を短くした真花名は幸薄そうな顔をうつむけ、わずかにしゃくれた顎を胸にくっつけるようにして身をこわばらせていた。そんな真花名を涼子は黒曜石のように光る目で見守っていたが、しかし悠太郎はやがて入門する佐藤陽奈子先生のピアノ教室のことや、そこでも出くわすことになるであろう留夏子のことを考えていた。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
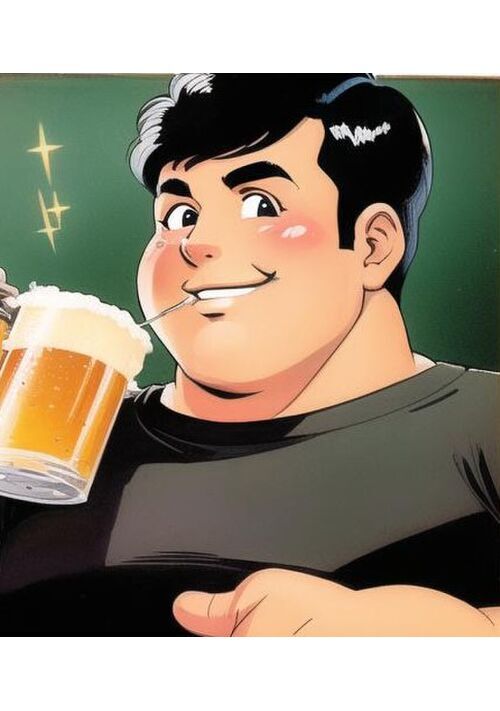
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















