18 / 73
第六章 細波
三
しおりを挟む
そうだった、ぼくは生きてゆけないとはっきり確信したのは、あの悪夢のような面接室のなかでのことだったと、細波立つ湖のきらめきのような大広間での歓談のさなかに、悠太郎は思い出していた。卒園を間近に控えた暗い曇天のその日、年長組の園児たちはひとりずつ面接室に呼ばれて、担任の先生の質問に答えなければならなかった。大きくなったら何になりたいかということがその日の問題であることを、冷たく澄ました温子先生から黄色組のみんなと一緒に予め聞かされたとき、悠太郎の耳からは先生の言葉も園児たちの声もすべて遠のいて、その聴覚は聴覚自身を聴いているようにしいんと鳴り始めた。気が遠くなった悠太郎は、椅子に座っていても立ち眩みのような目眩を覚え、目の奥では夏の夜に庭で遊んだ花火のような緑色や紫色の光が、後から後から湧き出して不気味な形を作っては、消えるそばからまた湧き出した。大きくなったら何になりたい?――牛飼い! お菓子屋さん! 幼稚園の先生! お医者さん! 野球選手! お嫁さん! お母さん! 仮面ライダー! スーパーマリオ!――みんなはそんなふうに答えているらしいことが、悠太郎には不思議でならなかった。砂漠の国で井戸を掘ろうとする人のように、悠太郎は大きくなったらなりたいものを求めて、心の深みを掘り返したが無益であった。それもそのはずで、悠太郎は自分が大きくなることを想定してもいなかったし、また望んでもいなかったからである。
まだ年少組の頃に悠太郎は、幼稚園が終わったらその次はどうなるのかと、しんと静まり返った夏の終わりの学芸村の家で、祖母の梅子に訊いてみたことがあった。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、幼稚園が終わったらねえ、次は小学校へ行くだよ」と答えた。鬱蒼とした樹々の葉叢が、宵闇のなかで夕風にざわざわと鳴っていた。「ではその次は? 小学校の次はどうなるのですか?」と悠太郎は、二重瞼の物問いたげな大きな目を黒々と見開いて尋ねた。「ウッフフ、小学校が終わったらねえ、次は中学校へ行くだよ」と梅子が答えると、また鬱蒼とした樹々の葉叢が、宵闇のなかで夕風にざわざわと鳴った。「ではその次は? 中学校の次はどうなるのですか?」――「ウッフフ、中学校でうんとお勉強したらねえ、その次はうんといい高校へ進むだよ」――「ではその次は? 高校の次はどうなるのですか?」――「ウッフフ、高校でうんとお勉強したらねえ、その次はうんといい大学へ進むだよ」――「ではその次は? 大学の次はどうなるのですか?」――「ウッフフ、大学でうんとお勉強したらねえ、その次はうんといい会社に勤めるだよ」――あたかも悪夢が描かれた絵本のページを先へ先へとめくるように、悠太郎が思い詰めた調子で尋ねるたび、梅子がパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら答えるあいだにも、窓の外では宵闇が深まって、鬱蒼とした樹々の葉叢は夕風にざわざわと鳴り続けていた。「ではその次は? 会社に勤めたらその次はどうなるのですか?」と悠太郎が泣き出さんばかりに尋ねると、梅子はこの悲痛な問いを「ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ!」というアーチ状の高笑いで一笑に付したが、その笑い声は三番目の「ハ」が最も高く、最後の「ハ」は最初の「ハ」よりも低いのである。高笑いのアーチを虚空に描いた後で梅子は、「会社に勤めりゃあおめえ、それっきりだよ。そこでうんと働いてうんとお金を稼いで、年寄りになって終わり。あとは死ぬっきり。ウッフフ、おっしまーい!」と、さも愉快そうなふざけた調子で言ってのけた。それを聞いた悠太郎は、人生という悪夢の絵本を最後のページまで読み終えてしまったような気がして、絶望のあまり言葉を失った。そんなものが人生なら、大きくなってそんな人生が待っているなら、ぼくは絶対に大きくなんかなりたくないと、ざわざわと鳴る宵闇のなかで悠太郎は思うほかなかった。
そんなことを思い出したついでに思い出されたのは、三池光子さんと湖畔に咲く水仙を見た同じ五月のあの日のことであった。煙草の煙が充満する社員食堂を出て悠太郎が明鏡閣を辞するとき、黒岩サカエさんが重い扉の取っ手を押して見送ってくれた。崩れかけていたコンクリートの段の上に出た悠太郎はふとそのとき、扉と売店の窓のあいだの壁に取りつけられた郵便ポストに、ついでその下に取りつけられた木箱に目を留めた。その木箱に「警ら箱」と書かれているのを見た悠太郎は、二重瞼の物問いたげな大きな目を黒々と見開きながら、「たからばこ?」とサカエさんに確かめた。サカエさんはサングラスの奥の目を微笑ませて含んだような笑い声を立てると、「惜しい。あれはケイラバコと読むんだ。ここらに怪しい人がいないかどうか、お巡りさんがパトロールするだろう? 何月何日何時何分に見回りましたという記録を、あの箱のなかに残すだよ」と教えた。崩れかけていたコンクリートの段の上で、地面まで届く赤い三角屋根の陰からサカエさんは、新緑を照らす午後の日の光を眺めながら煙草を吸っていたが、不意に「箱なんていう字がよく読めたな」と今さらのように驚いて言った。自分でもびっくりした悠太郎が、「だって箱に書いてあるんだもの、箱という字だと思ったんです」と答えると、サカエさんはその答えが子供らしいのに安心したのか、吸い込んだ煙を深々と吐き尽くすとしみじみ言った。「宝箱か……悪くねえな。あの箱が宝箱だったら、お巡りさんだって仕事をするのがさぞ楽しかろうさ。いや、お巡りさんだけじゃねえ。この明鏡閣を訪れるすべての人が、ここから宝物を持って帰れる。宝箱か……そうだ、その通りだ。観光ホテル明鏡閣は、六里ヶ原の宝箱でなけりゃあならねえ。ユウくんは俺に大切なことを教えてくれたよ。まだそんなに小さいが、ユウくんはなかなかの詩人だな。いや、難しいことは俺にはよく分からねえが、こうだったらいいなとみんなが思っていることを、そのものずばりの言葉でいうのが詩人ってもんじゃねえか? そうやって世界を少しずつ本当に変えちまうのが本当の詩人だろうよ。ユウくん、俺は決めたぞ。俺はこの観光ホテル明鏡閣を、六里ヶ原の宝箱にするよ。ユウくんのお母さんと一緒にな。この建物もだいぶ年季は入ってきたが、世のなかは景気がいいし、まだまだやりようはあるってもんだ。将来ユウくんが何になっても帰ってこられる懐かしい場所を、俺たちはしっかりと残してゆくぞ。だからユウくんも負けるなよ。淋しくたって負けるなよ……」
気がつけば悠太郎は幼稚園の面接室で、温子先生に問い詰められて泣いていた。「ぼくは何にもなりたくないし、何にもなれないんです。そもそもの前提として、ぼくは大きくなりたくないし、大きくなれないような気がします。仮に大きくなれたとしてもこの虚弱なぼくが、厳しい社会のなかで何らかの責任を果たせる人間になれると思いますか? そんなことはおよそ考えられないことです。ぼくは将軍にも枢密顧問官にも増田ケンポウにもなれません。むしろぼくが大きくなったら、容疑者になり被告になり死刑囚になってしまいます。だからぼくは大きくなんかなりたくないんです。だから大きくなったら何になりたいかという質問はぼくには無意味です。温子先生、お願いです。どうか無意味な質問で園児を苦しめることはおやめになってください。お願いです、ぼくの苦しみをどうか分かってください。お願いです、お願いです、お願いです……」と悠太郎は、大きな目からぽろぽろと涙を落としながら哀訴した。温子先生は尖った顎を傲然と上げて「何かあるでしょう。何でもいいの。本当になれるかどうかなんて心配しなくていいから、素直にユウちゃんのなりたいものを言ってごらんなさい」と追及した。悠太郎は華奢な手の指で涙を拭き拭き、「ではせめてお祖父様と相談させてください。ぼくの人生はぼくの勝手にはなりません。ぼくの人生などというものはないのです。わが家ではお祖父様がいちばん偉いのです。お祖父様の許しもなしに将来のことを勝手に決めたら、どれほどの怒りを被るか知れません。どうか一日の猶予をください。お願いです」となおも哀願した。しかし温子先生はこの哀願をも冷たく撥ねつけて、「先生はユウちゃんの気持ちが知りたいの。お祖父さんのことは今は関係ないの。ユウちゃん自身が何になりたいか知りたいの。自分の考えだって言えなければ、ご家族から愛されないわよ」と無慈悲に告げた。「何もありません。なりたいものも、ぼくの人生も、ぼく自身の考えもありません」と悠太郎がいっそう激しく泣くと、苛立ちを募らせた温子先生は、話し合いを早々に切り上げるべく妥協案を示した。四月生まれの園児から始めて三月生まれの園児まで、黄色組の全員から順番に話を聞かなければならない温子先生としては、九月生まれの悠太郎ひとりに時間を費やすわけにはゆかなかったので、「これから先生が言うもののなかから、ユウちゃんのなりたいものを選びなさい」と命じた。
そのとき温子先生がどんな「なりたいもの」を挙げたのか、悠太郎はもうほとんど憶えてはいなかった。ただ温子先生が冷酷な声で「なりたいもの」の候補をひとつ告げるたびに、自分が泣きじゃくりながら首を横に振ってそれを否定したことを、悠太郎は記憶していた。だが降りしきる雨に乱れる湖のような悠太郎の心は、温子先生が「羊飼い」と言うのを聞いたとき、不思議と清らかな明るみのうちに静まった。年少組の二学期も終わろうとする頃に、年長組の留夏子ちゃんがクリスマスのお話を聞かせてくれたことを、悠太郎は思い出したのである。「夜中に羊の群れを見守っていた羊飼いたちにね、天使が現れたの。天使の光が眩しかったから、羊飼いたちはびっくりしたの。〈怖がらないで、いいこと教えてあげる、救い主が生まれたよ〉って、天使は羊飼いたちに言ったの……」と留夏子は切れ長の目を細めながら、聖書とかいう本に書いてあるお話を教えてくれた。それを思い出した悠太郎の心は、たちどころに故知らぬ平和に満たされていたのである。突然泣きやんだ悠太郎を見て温子先生は不審に思ったが、面倒な話を打ち切る好機とばかり、「それじゃ羊飼いなのね? ユウちゃんのなりたいものは羊飼いでいいのね?」と鋭い声で念を押すと、悠太郎は二重瞼の物問いたげな大きな目を黒々と見開いてこっくりと頷いた。そうした経緯で記念のスクラップブックに記された将来の志望は、当然ながら祖父の千代次の激怒を招くことになり、母の秀子は困惑しながらも老父に同調して悠太郎を叱責した。祖母の梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、「そらっことを! 死にったわけのそらったあことだよ! やっぱりわったしの恐れた通りだよ! 屯匪の孫どもに悪い影響を受けたんだよ!」と喚き散らしたが、「そらっこと」とは空言の、「そらったあこと」とは空戯言の六里ヶ原方言で、くだらない無意味な言葉という意味である。悠太郎は家族に向かって「羊飼い」の意味するところを何ひとつ説明することなく、当たらずといえども遠からずである非難の嵐に耐えながら、あのとき心を満たした故知らぬ平和が、この世のものではないことをはっきりと悟っていた。
観光ホテル明鏡閣の大広間で盛り上がった謝恩会の終わり近くになって、悠太郎に好意的な芹沢美智子さんが富山訛りの独特なイントネーションで、「まったくユウくんは明鏡だね! 六里ヶ原の明鏡だよ!」と言ったとき、悠太郎は物思いに沈みながら睫毛の長い目を伏せて悄然とうつむいていたから、どれほどの母親たちや先生方がその言葉に賛同を示したかはよく分からなかった。ただ「六里ヶ原の明鏡」というその呼び名が、中学校を卒業するまでは自分について回るであろうことを、漠然と予感したにすぎなかった。それよりもいっそうはっきりと記憶に残ったのは、謝恩会が果てた後で大広間を出て階段を降りるとき、ジュンくんを連れた佐藤陽奈子さんが秀子に語ったことであった。簡素な草色のドレスを着た陽奈子さんは踊り場で立ち止まると、静かな決意を込めた凛とした声で、「遠からず甘楽の家でピアノ教室を開くことにしました。自然豊かなこの高原で、農業と芸術をひとつに結びつけることが、長いあいだの私の夢だったの。人の心には多くの計画があっても、すべてが実現するわけじゃないわ。でもやっぱり私は理想を諦めたくないもの」と言ったのである。悠太郎はその話を自分と直接結びつけはしなかったが、この先生にピアノを教わる生徒は幸せだとか、この先生の教室から梨里子ちゃんのようにピアノの上手な子が出るだろうかとか、ジュンくんやルカちゃんはピアノを習うのだろうかとか考えた。
秀子と家に帰った悠太郎は、いつか正子伯母様がプレゼントしてくれたバッタのオートバイのフィギュアに、卒園を報告しようと思った。仮面ライダーBLACKの愛車であったそのオートバイに、つらかった幼稚園での二年間をどうにか乗り切ったことを伝えたかったのである。だが赤い目をした緑のバッタのオートバイは、いつもの飾り棚に見えなかった。棚や引き出しのどこを探しても、それは見当たらなかった。嫌な予感を覚えた悠太郎は、祖母の梅子にふるえる声で、「緑のオートバイをどこかへやりましたか?」と訊いてみた。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、「ああ、あのけったくそ悪いバッタのおもちゃかい? あれならねえ、わったしがぶちゃったよ。あんなものはねえ、お勉強の妨げ! 整理整頓! まあずおめえがいるとウッフフ、うちのなかがいっつまででも片づかねえ! これっからは小学校でうんとお勉強するんだからね。あんなものは、はあ卒業、卒業!」と言って、喜色満面で悠太郎の卒園を祝った。ちなみに「ぶちゃる」とは、六里ヶ原の方言で捨てるという意味である。悠太郎は結氷した心の湖に、アイスドリルで穴を空けられたように感じた。裏庭にコンクリートブロックを積み上げて作られたゴミ燃し場で、オートバイのフィギュアは灰になっていたのである。思えば明鏡閣の食堂で集めた円形のボール紙も、梅子がとうに捨ててしまった。この祖母は孫の大事なものを、片端から処分せずには気が済まなかった。その徹底した潔癖症に、悠太郎は恐怖を覚えた。「これからもこんなことが続くのだ。これからもずっとこうなのだ」と考えると、悠太郎の胸のなかを灰色の虚しい風が吹き過ぎた。
そんな悠太郎の様子を見た秀子は、ここぞとばかり母親らしい優しさを示して、わが子への支配を強めようと考えた。秀子は以前に働いていた山のデパートから白い厚紙を買ってくると、そこにマリオとルイージの絵を描くように言った。「おまえの描いたマリオとルイージがスケートを滑るのよ。そんな格好に描いてごらん」という秀子の指示に従って、悠太郎は赤い帽子のマリオを走っている姿勢で、緑の帽子のルイージをジャンプしている姿勢で、それぞれ色鉛筆で描いた。兄弟とはいえよく見てみれば、マリオとルイージはずいぶん違うことに悠太郎は描きながら気がついた。帽子のマークがマリオはMでルイージはLであるのは当然として、ひげの形も微妙に違うし、弟のルイージのほうが細面だし、背だって兄のマリオよりも高いかもしれないと、悠太郎はファミコンソフトの説明書に描かれたイラストを参照しながら考えた。そうして描いた兄弟の輪郭に沿って、悠太郎は厚紙に鋏を入れた。切り抜かれたマリオ兄弟は、千代次と梅子がそれぞれ床に就いた後に、冷凍庫のなかへ入れられた。「お祖父様とお祖母様に見つからないといいんだけど」といくらか憂わしげに言った秀子は、翌朝も素知らぬ顔で梅子とともに明鏡閣へ出勤していった。その夜も千代次と梅子がそれぞれ床に就くと、秀子は例のものを冷凍庫から取り出した。それは製氷皿の氷に、それぞれの片足を突っ込んだマリオ兄弟であった。「さあ、この上で滑らせてごらん」と秀子は高い食器棚の上から、悠太郎が密かに「お墓の下」と呼んでいるあの円い茶盆を取ってよこした。悠太郎がその茶盆を傾ければ、マリオとルイージが滑った。反対方向に傾ければ、マリオとルイージが反対方向に滑った。どちらかが危うく縁から滑り落ちそうになって悠太郎が慌てると、秀子は隙間の空いた大きな前歯を見せて笑った。ぼくの描いたマリオとルイージが、照月湖でスケートをしている! それを見てお母様が笑っている! 夢みたいだ。夢みたいだ――。その夢は祖父母に知れるといけないので一夜限りに終わったが、悠太郎の心に長いこと残り続けた。悠太郎がそのときあまりに喜んだので、秀子は現実の照月湖でも、わが子にスケートの滑り納めをさせようと考えたのである。一九九〇年の三月のその日に、悠太郎が営業の終わったスケートリンクを、梅子が「フギア」と発音するフィギュアスケート用の靴で、ひとり緩慢に滑っているのはそうしたわけであった。
遥か彼方からの微笑みのような暖かさに午後の気温は上がり、銀盤の表面をうっすらと浸していた水は急に深くなった。このままでは小さな悠太郎の体重をも、氷は支え切れないかもしれなかった。うつむいて滑る悠太郎は、氷をも和らげる柔らかな日射しが、スケート靴の厚い刃に光っているのを見た。このまま氷が融けて春になってぼくが沈んでしまっても、照月湖はやっぱりそよ風に細波立つのだろうと悠太郎は思った。嬉しいことも悲しいことも、ぼくたちひとりひとりの命も、どこか見えない湖にきらめく細波のひとつひとつにすぎないのかもしれない――。そのとき桟橋の突端からサカエさんこと黒岩栄作さんが「おおい、はあ危ねえぞ! ユウくん、早く戻って来お!」と呼ぶ声が、湖の上空を横切るカラスの鳴き声とともに悠太郎の耳に届いた。気泡を閉じ込めた氷が、太陽に照らされて融けながら、ウッドブロックでも叩くような音を発した。
まだ年少組の頃に悠太郎は、幼稚園が終わったらその次はどうなるのかと、しんと静まり返った夏の終わりの学芸村の家で、祖母の梅子に訊いてみたことがあった。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、幼稚園が終わったらねえ、次は小学校へ行くだよ」と答えた。鬱蒼とした樹々の葉叢が、宵闇のなかで夕風にざわざわと鳴っていた。「ではその次は? 小学校の次はどうなるのですか?」と悠太郎は、二重瞼の物問いたげな大きな目を黒々と見開いて尋ねた。「ウッフフ、小学校が終わったらねえ、次は中学校へ行くだよ」と梅子が答えると、また鬱蒼とした樹々の葉叢が、宵闇のなかで夕風にざわざわと鳴った。「ではその次は? 中学校の次はどうなるのですか?」――「ウッフフ、中学校でうんとお勉強したらねえ、その次はうんといい高校へ進むだよ」――「ではその次は? 高校の次はどうなるのですか?」――「ウッフフ、高校でうんとお勉強したらねえ、その次はうんといい大学へ進むだよ」――「ではその次は? 大学の次はどうなるのですか?」――「ウッフフ、大学でうんとお勉強したらねえ、その次はうんといい会社に勤めるだよ」――あたかも悪夢が描かれた絵本のページを先へ先へとめくるように、悠太郎が思い詰めた調子で尋ねるたび、梅子がパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら答えるあいだにも、窓の外では宵闇が深まって、鬱蒼とした樹々の葉叢は夕風にざわざわと鳴り続けていた。「ではその次は? 会社に勤めたらその次はどうなるのですか?」と悠太郎が泣き出さんばかりに尋ねると、梅子はこの悲痛な問いを「ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ・ハ!」というアーチ状の高笑いで一笑に付したが、その笑い声は三番目の「ハ」が最も高く、最後の「ハ」は最初の「ハ」よりも低いのである。高笑いのアーチを虚空に描いた後で梅子は、「会社に勤めりゃあおめえ、それっきりだよ。そこでうんと働いてうんとお金を稼いで、年寄りになって終わり。あとは死ぬっきり。ウッフフ、おっしまーい!」と、さも愉快そうなふざけた調子で言ってのけた。それを聞いた悠太郎は、人生という悪夢の絵本を最後のページまで読み終えてしまったような気がして、絶望のあまり言葉を失った。そんなものが人生なら、大きくなってそんな人生が待っているなら、ぼくは絶対に大きくなんかなりたくないと、ざわざわと鳴る宵闇のなかで悠太郎は思うほかなかった。
そんなことを思い出したついでに思い出されたのは、三池光子さんと湖畔に咲く水仙を見た同じ五月のあの日のことであった。煙草の煙が充満する社員食堂を出て悠太郎が明鏡閣を辞するとき、黒岩サカエさんが重い扉の取っ手を押して見送ってくれた。崩れかけていたコンクリートの段の上に出た悠太郎はふとそのとき、扉と売店の窓のあいだの壁に取りつけられた郵便ポストに、ついでその下に取りつけられた木箱に目を留めた。その木箱に「警ら箱」と書かれているのを見た悠太郎は、二重瞼の物問いたげな大きな目を黒々と見開きながら、「たからばこ?」とサカエさんに確かめた。サカエさんはサングラスの奥の目を微笑ませて含んだような笑い声を立てると、「惜しい。あれはケイラバコと読むんだ。ここらに怪しい人がいないかどうか、お巡りさんがパトロールするだろう? 何月何日何時何分に見回りましたという記録を、あの箱のなかに残すだよ」と教えた。崩れかけていたコンクリートの段の上で、地面まで届く赤い三角屋根の陰からサカエさんは、新緑を照らす午後の日の光を眺めながら煙草を吸っていたが、不意に「箱なんていう字がよく読めたな」と今さらのように驚いて言った。自分でもびっくりした悠太郎が、「だって箱に書いてあるんだもの、箱という字だと思ったんです」と答えると、サカエさんはその答えが子供らしいのに安心したのか、吸い込んだ煙を深々と吐き尽くすとしみじみ言った。「宝箱か……悪くねえな。あの箱が宝箱だったら、お巡りさんだって仕事をするのがさぞ楽しかろうさ。いや、お巡りさんだけじゃねえ。この明鏡閣を訪れるすべての人が、ここから宝物を持って帰れる。宝箱か……そうだ、その通りだ。観光ホテル明鏡閣は、六里ヶ原の宝箱でなけりゃあならねえ。ユウくんは俺に大切なことを教えてくれたよ。まだそんなに小さいが、ユウくんはなかなかの詩人だな。いや、難しいことは俺にはよく分からねえが、こうだったらいいなとみんなが思っていることを、そのものずばりの言葉でいうのが詩人ってもんじゃねえか? そうやって世界を少しずつ本当に変えちまうのが本当の詩人だろうよ。ユウくん、俺は決めたぞ。俺はこの観光ホテル明鏡閣を、六里ヶ原の宝箱にするよ。ユウくんのお母さんと一緒にな。この建物もだいぶ年季は入ってきたが、世のなかは景気がいいし、まだまだやりようはあるってもんだ。将来ユウくんが何になっても帰ってこられる懐かしい場所を、俺たちはしっかりと残してゆくぞ。だからユウくんも負けるなよ。淋しくたって負けるなよ……」
気がつけば悠太郎は幼稚園の面接室で、温子先生に問い詰められて泣いていた。「ぼくは何にもなりたくないし、何にもなれないんです。そもそもの前提として、ぼくは大きくなりたくないし、大きくなれないような気がします。仮に大きくなれたとしてもこの虚弱なぼくが、厳しい社会のなかで何らかの責任を果たせる人間になれると思いますか? そんなことはおよそ考えられないことです。ぼくは将軍にも枢密顧問官にも増田ケンポウにもなれません。むしろぼくが大きくなったら、容疑者になり被告になり死刑囚になってしまいます。だからぼくは大きくなんかなりたくないんです。だから大きくなったら何になりたいかという質問はぼくには無意味です。温子先生、お願いです。どうか無意味な質問で園児を苦しめることはおやめになってください。お願いです、ぼくの苦しみをどうか分かってください。お願いです、お願いです、お願いです……」と悠太郎は、大きな目からぽろぽろと涙を落としながら哀訴した。温子先生は尖った顎を傲然と上げて「何かあるでしょう。何でもいいの。本当になれるかどうかなんて心配しなくていいから、素直にユウちゃんのなりたいものを言ってごらんなさい」と追及した。悠太郎は華奢な手の指で涙を拭き拭き、「ではせめてお祖父様と相談させてください。ぼくの人生はぼくの勝手にはなりません。ぼくの人生などというものはないのです。わが家ではお祖父様がいちばん偉いのです。お祖父様の許しもなしに将来のことを勝手に決めたら、どれほどの怒りを被るか知れません。どうか一日の猶予をください。お願いです」となおも哀願した。しかし温子先生はこの哀願をも冷たく撥ねつけて、「先生はユウちゃんの気持ちが知りたいの。お祖父さんのことは今は関係ないの。ユウちゃん自身が何になりたいか知りたいの。自分の考えだって言えなければ、ご家族から愛されないわよ」と無慈悲に告げた。「何もありません。なりたいものも、ぼくの人生も、ぼく自身の考えもありません」と悠太郎がいっそう激しく泣くと、苛立ちを募らせた温子先生は、話し合いを早々に切り上げるべく妥協案を示した。四月生まれの園児から始めて三月生まれの園児まで、黄色組の全員から順番に話を聞かなければならない温子先生としては、九月生まれの悠太郎ひとりに時間を費やすわけにはゆかなかったので、「これから先生が言うもののなかから、ユウちゃんのなりたいものを選びなさい」と命じた。
そのとき温子先生がどんな「なりたいもの」を挙げたのか、悠太郎はもうほとんど憶えてはいなかった。ただ温子先生が冷酷な声で「なりたいもの」の候補をひとつ告げるたびに、自分が泣きじゃくりながら首を横に振ってそれを否定したことを、悠太郎は記憶していた。だが降りしきる雨に乱れる湖のような悠太郎の心は、温子先生が「羊飼い」と言うのを聞いたとき、不思議と清らかな明るみのうちに静まった。年少組の二学期も終わろうとする頃に、年長組の留夏子ちゃんがクリスマスのお話を聞かせてくれたことを、悠太郎は思い出したのである。「夜中に羊の群れを見守っていた羊飼いたちにね、天使が現れたの。天使の光が眩しかったから、羊飼いたちはびっくりしたの。〈怖がらないで、いいこと教えてあげる、救い主が生まれたよ〉って、天使は羊飼いたちに言ったの……」と留夏子は切れ長の目を細めながら、聖書とかいう本に書いてあるお話を教えてくれた。それを思い出した悠太郎の心は、たちどころに故知らぬ平和に満たされていたのである。突然泣きやんだ悠太郎を見て温子先生は不審に思ったが、面倒な話を打ち切る好機とばかり、「それじゃ羊飼いなのね? ユウちゃんのなりたいものは羊飼いでいいのね?」と鋭い声で念を押すと、悠太郎は二重瞼の物問いたげな大きな目を黒々と見開いてこっくりと頷いた。そうした経緯で記念のスクラップブックに記された将来の志望は、当然ながら祖父の千代次の激怒を招くことになり、母の秀子は困惑しながらも老父に同調して悠太郎を叱責した。祖母の梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、「そらっことを! 死にったわけのそらったあことだよ! やっぱりわったしの恐れた通りだよ! 屯匪の孫どもに悪い影響を受けたんだよ!」と喚き散らしたが、「そらっこと」とは空言の、「そらったあこと」とは空戯言の六里ヶ原方言で、くだらない無意味な言葉という意味である。悠太郎は家族に向かって「羊飼い」の意味するところを何ひとつ説明することなく、当たらずといえども遠からずである非難の嵐に耐えながら、あのとき心を満たした故知らぬ平和が、この世のものではないことをはっきりと悟っていた。
観光ホテル明鏡閣の大広間で盛り上がった謝恩会の終わり近くになって、悠太郎に好意的な芹沢美智子さんが富山訛りの独特なイントネーションで、「まったくユウくんは明鏡だね! 六里ヶ原の明鏡だよ!」と言ったとき、悠太郎は物思いに沈みながら睫毛の長い目を伏せて悄然とうつむいていたから、どれほどの母親たちや先生方がその言葉に賛同を示したかはよく分からなかった。ただ「六里ヶ原の明鏡」というその呼び名が、中学校を卒業するまでは自分について回るであろうことを、漠然と予感したにすぎなかった。それよりもいっそうはっきりと記憶に残ったのは、謝恩会が果てた後で大広間を出て階段を降りるとき、ジュンくんを連れた佐藤陽奈子さんが秀子に語ったことであった。簡素な草色のドレスを着た陽奈子さんは踊り場で立ち止まると、静かな決意を込めた凛とした声で、「遠からず甘楽の家でピアノ教室を開くことにしました。自然豊かなこの高原で、農業と芸術をひとつに結びつけることが、長いあいだの私の夢だったの。人の心には多くの計画があっても、すべてが実現するわけじゃないわ。でもやっぱり私は理想を諦めたくないもの」と言ったのである。悠太郎はその話を自分と直接結びつけはしなかったが、この先生にピアノを教わる生徒は幸せだとか、この先生の教室から梨里子ちゃんのようにピアノの上手な子が出るだろうかとか、ジュンくんやルカちゃんはピアノを習うのだろうかとか考えた。
秀子と家に帰った悠太郎は、いつか正子伯母様がプレゼントしてくれたバッタのオートバイのフィギュアに、卒園を報告しようと思った。仮面ライダーBLACKの愛車であったそのオートバイに、つらかった幼稚園での二年間をどうにか乗り切ったことを伝えたかったのである。だが赤い目をした緑のバッタのオートバイは、いつもの飾り棚に見えなかった。棚や引き出しのどこを探しても、それは見当たらなかった。嫌な予感を覚えた悠太郎は、祖母の梅子にふるえる声で、「緑のオートバイをどこかへやりましたか?」と訊いてみた。梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、「ああ、あのけったくそ悪いバッタのおもちゃかい? あれならねえ、わったしがぶちゃったよ。あんなものはねえ、お勉強の妨げ! 整理整頓! まあずおめえがいるとウッフフ、うちのなかがいっつまででも片づかねえ! これっからは小学校でうんとお勉強するんだからね。あんなものは、はあ卒業、卒業!」と言って、喜色満面で悠太郎の卒園を祝った。ちなみに「ぶちゃる」とは、六里ヶ原の方言で捨てるという意味である。悠太郎は結氷した心の湖に、アイスドリルで穴を空けられたように感じた。裏庭にコンクリートブロックを積み上げて作られたゴミ燃し場で、オートバイのフィギュアは灰になっていたのである。思えば明鏡閣の食堂で集めた円形のボール紙も、梅子がとうに捨ててしまった。この祖母は孫の大事なものを、片端から処分せずには気が済まなかった。その徹底した潔癖症に、悠太郎は恐怖を覚えた。「これからもこんなことが続くのだ。これからもずっとこうなのだ」と考えると、悠太郎の胸のなかを灰色の虚しい風が吹き過ぎた。
そんな悠太郎の様子を見た秀子は、ここぞとばかり母親らしい優しさを示して、わが子への支配を強めようと考えた。秀子は以前に働いていた山のデパートから白い厚紙を買ってくると、そこにマリオとルイージの絵を描くように言った。「おまえの描いたマリオとルイージがスケートを滑るのよ。そんな格好に描いてごらん」という秀子の指示に従って、悠太郎は赤い帽子のマリオを走っている姿勢で、緑の帽子のルイージをジャンプしている姿勢で、それぞれ色鉛筆で描いた。兄弟とはいえよく見てみれば、マリオとルイージはずいぶん違うことに悠太郎は描きながら気がついた。帽子のマークがマリオはMでルイージはLであるのは当然として、ひげの形も微妙に違うし、弟のルイージのほうが細面だし、背だって兄のマリオよりも高いかもしれないと、悠太郎はファミコンソフトの説明書に描かれたイラストを参照しながら考えた。そうして描いた兄弟の輪郭に沿って、悠太郎は厚紙に鋏を入れた。切り抜かれたマリオ兄弟は、千代次と梅子がそれぞれ床に就いた後に、冷凍庫のなかへ入れられた。「お祖父様とお祖母様に見つからないといいんだけど」といくらか憂わしげに言った秀子は、翌朝も素知らぬ顔で梅子とともに明鏡閣へ出勤していった。その夜も千代次と梅子がそれぞれ床に就くと、秀子は例のものを冷凍庫から取り出した。それは製氷皿の氷に、それぞれの片足を突っ込んだマリオ兄弟であった。「さあ、この上で滑らせてごらん」と秀子は高い食器棚の上から、悠太郎が密かに「お墓の下」と呼んでいるあの円い茶盆を取ってよこした。悠太郎がその茶盆を傾ければ、マリオとルイージが滑った。反対方向に傾ければ、マリオとルイージが反対方向に滑った。どちらかが危うく縁から滑り落ちそうになって悠太郎が慌てると、秀子は隙間の空いた大きな前歯を見せて笑った。ぼくの描いたマリオとルイージが、照月湖でスケートをしている! それを見てお母様が笑っている! 夢みたいだ。夢みたいだ――。その夢は祖父母に知れるといけないので一夜限りに終わったが、悠太郎の心に長いこと残り続けた。悠太郎がそのときあまりに喜んだので、秀子は現実の照月湖でも、わが子にスケートの滑り納めをさせようと考えたのである。一九九〇年の三月のその日に、悠太郎が営業の終わったスケートリンクを、梅子が「フギア」と発音するフィギュアスケート用の靴で、ひとり緩慢に滑っているのはそうしたわけであった。
遥か彼方からの微笑みのような暖かさに午後の気温は上がり、銀盤の表面をうっすらと浸していた水は急に深くなった。このままでは小さな悠太郎の体重をも、氷は支え切れないかもしれなかった。うつむいて滑る悠太郎は、氷をも和らげる柔らかな日射しが、スケート靴の厚い刃に光っているのを見た。このまま氷が融けて春になってぼくが沈んでしまっても、照月湖はやっぱりそよ風に細波立つのだろうと悠太郎は思った。嬉しいことも悲しいことも、ぼくたちひとりひとりの命も、どこか見えない湖にきらめく細波のひとつひとつにすぎないのかもしれない――。そのとき桟橋の突端からサカエさんこと黒岩栄作さんが「おおい、はあ危ねえぞ! ユウくん、早く戻って来お!」と呼ぶ声が、湖の上空を横切るカラスの鳴き声とともに悠太郎の耳に届いた。気泡を閉じ込めた氷が、太陽に照らされて融けながら、ウッドブロックでも叩くような音を発した。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
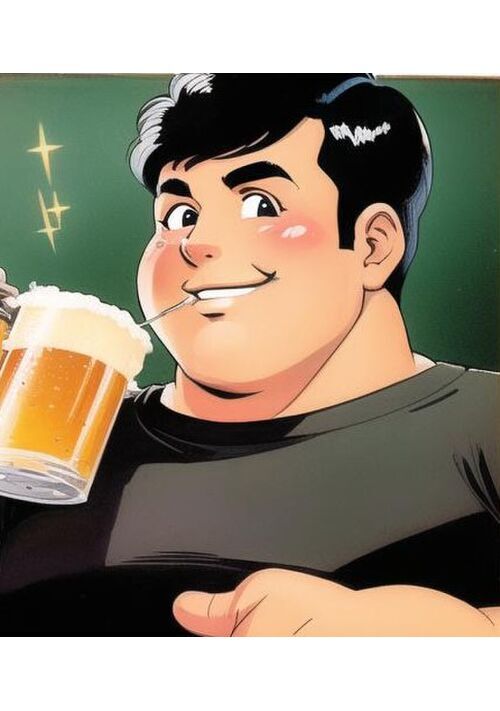
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!



ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。


ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















