5 / 73
第二章 四季折々の花
二
しおりを挟む
六里ヶ原に新緑が芽吹きつつあった五月のその日、悠太郎はひとり桃組の部屋の窓辺に立って、濃いピンクのゼラニウムの花びらをティッシュペーパーに挟んで色を染め出しながら、ある歌の歌詞のことを考えていた。それは大好きなテレビ番組となっていた《仮面ライダーBLACK》の主題歌であった。あの番組には血沸き肉躍る勇壮なオープニングテーマと、切々たる哀愁が身に沁みる静かなエンディングテーマがあった。悲哀の子である悠太郎が、いずれを好んだかは言うまでもない。そのとき彼が考えていたのは、哀愁漂うエンディングテーマの歌詞であった。あの歌とは無関係に、お母様もいつか言っていた。「六里ヶ原には、四季折々の花が咲くのよ」と。あの歌詞のために不思議な体験をしたのは、いつのことだったろう――? 悠太郎はゼラニウムの花びらを挟んだティッシュを、とんとんと叩きながら記憶をたどっていた。
悠太郎ほど真剣に《仮面ライダーBLACK》を視聴していた幼児も珍しいのだが、それには理由がないではなかった。もちろん彼は番組そのものが好きであった。ライダーに変身して活躍する主人公の名前を、悠太郎は自分の名前と比べてみた。苗字と名前の音節数は同じであった。では韻を踏んでいるだろうか? 残念ながら踏んでいないと結論せざるを得なかった。ともあれ暗黒結社によって改造人間にされながら、その悲しみを乗り越えてパンチやキックで悪と戦うヒーローに悠太郎は憧れたが、それだけならどこの幼児も同じであろう。問題は日曜日の十時から十時三十分という放送時間であった。日曜日の午前は、祖父の千代次が報道や政治討論の番組を、立て続けに視聴したい時間帯だったのである。いかに母の秀子が千代次の同意を取りつけてくれたとはいえ、祖父の楽しみを三十分間も奪うことを、悠太郎は心苦しく思った。《仮面ライダーBLACK》が始まる時刻になると、千代次は目に見えて苦い顔をして、極度に細い近視の目をしばたたきながら居間から出て自室に籠もると、おそらく三十分のあいだ書道の稽古でもするか漢詩でも読むか、あるいは『諸君!』や『文藝春秋』のページをめくるかしているのであった。実際のところ四月十日に、四国と本州を結ぶ瀬戸大橋の開通を取り上げた特番によって《仮面ライダーBLACK》が休止になったとき、千代次は「そうかそうか、今日はライダーは休みか。よかったよかった。ほれ見ろ、あんなでけえ橋なんざ架けて、まあず豪儀だのう。これに比べりゃあ照月湖の橋なんざおめえ、マッチ棒みてえなもんさな」と言いながら、上機嫌でブラウン管に見入っていた。悠太郎はライダーの活躍を見られないことが悲しかったが、機嫌のよい祖父を見るのは嬉しかった。幼稚園に入ったばかりの子供にとって、それはやはり複雑な感情であった。もしその千代次が《仮面ライダーBLACK》に難癖をつけてきたらどうしようというのが、もっと前々からの悠太郎の懸念であった。こんなものを観るのは「しゃいなし」だ、つまり六里ヶ原の方言でくだらないことだと千代次が言ったら、そのとき悠太郎は祖父に通じるような論理的な老成した言葉で、この番組を視聴する意義を説明しなければならないと思い詰めていた。この番組は逆境に立ち向かう勇気を育て、正義を愛する人格を涵養し、生きることの喜びのみならず、悲しみをも教えてくれます――。悠太郎はそんなことを言ってみるつもりであった。その説得に失敗すれば、もはや視聴は不可能になるだろう。そんなふうに思い詰めていたから、悠太郎は一回ごとのストーリー展開や怪人の名前のみならず、登場人物たちの台詞回しまでよく記憶していたのである。それにしてもエンディングテーマでのあの不思議な体験は、いつのことだったろう?
そうだった。あれは一九八八年一月十日のことで、寒さの厳しい六里ヶ原は氷雪に閉ざされていたから、ブラウン管のなかで怪人が放つ冷凍の息や鋭い氷柱は、その冷たさをありありと感じさせながら悠太郎に迫ったものである。やがてエンディングが始まったとき、悠太郎はテレビの前で立ち上がると、音声に合わせて歌い始めた。するとそのとき驚くべきことが起こった。悠太郎は白く光る香しい奔流に、突然包まれ飲み込まれ押し流されて、どこかこの世ならぬ次元に拉し去られたのである。悠太郎が恍惚として我を忘れていたのは、現実の時間にすればエンディングテーマが終わるまでのことであったが、その体験があまりにも不思議だったので、いつもなら注意深く耳を傾けるはずの次回予告も、上の空で聞くほかなかった。何かがすっかり変わってしまったのは、あのときだったのだ。ぼくを取り巻くしんとした淋しさが、痛切に感じられるようになったのもあの直後だったし、頼朝が六里ヶ原で催した巻狩や、学芸村を開発した枢密顧問官のお爺さんの政治的な戦いや、浅間観光を設立して豪快に笑っていた増田ケンポウ社長をめぐる難しい話の意味が、急に分かり始めたのもあの直後からだった――。
その哀切な歌の意味を知りたくなった悠太郎は、その夜に〈Long Long ago, 20th Century〉とはどういう意味かと秀子に尋ねてみた。夜空では巨大なオリオン座の赤いベテルギウスが、大犬座の蒼白いシリウスや小犬座の白いプロキオンと、冬の大三角を輝かせていた。風呂上がりの秀子は、シャンプーとリンスの匂いがする濡れた豊かな髪の頭にタオルを巻きつけていたが、幼いわが子の口から突然英語が発せられるのを聞くと、化粧を落としたその下膨れの顔に驚きの色を浮かべながら、「遠い遠い昔、二十世紀という意味よ」と答えた。悠太郎は物問いたげな大きな目を黒々と見開いて首を傾げ、「今は何世紀?」と尋ねた。「一九八八年だから、二十世紀よ」という秀子の答えを聞いた悠太郎は、なぜ今現在が遠い遠い昔なのか、わけが分からなくなった。そんなわが子の様子を見た秀子は、「いったいそれは何なの? どこでそんな英語を憶えたの?」と不思議がって問い質し、それが《仮面ライダーBLACK》のエンディングテーマの題名だと知ると、その歌詞を教えてくれるように促した。求めに応じて悠太郎は姿勢を正し深く息を吸い込むと、前年の秋から繰り返し聴いて記憶していたその主題歌を、か細くはあるがよく澄んだボーイソプラノで歌った。
悠太郎の歌のうまさや記憶力もさることながら、その歌詞に表現された哀惜を汲み取ってしまう感受性にも驚いた秀子は、さてどう言ったらあまり不安がらせずにその意味を説明できるかと思案した。普通の四歳児が聴いて喜ぶような内容ではなかった。そんな主題歌を好むわが子が誇らしくはあったが、その語学力と感受性の過多ゆえに破滅されては元も子もなかった。没落士族の末裔であったこの子の父親は、外務省に入って精神に異常を来たし、そのまた父親は売れない文筆家として不遇を託っていたものである。そんな血の流れを憂えながら秀子は、「世紀末って分かるかしら? 一世紀は百年で終わるの。二十世紀は二〇〇〇年までだから、あと十年ちょっとでしょう? 今がまさに世紀末なの」と説明を始めた。「世紀末って、みんなが不安になるのよ。それまで信じられていたものが信じられなくなって、もうおしまいだっていう気分になるの。でもそんな気分になるだけなのよ。現に世界は続いてきたんだもの。今も自然破壊の問題とか、東と西の冷たい戦争とか、不安なことはいろいろあるでしょう? でも二十一世紀や二十二世紀から振り返ってみれば、この二十世紀はまだいい時代だった。その歌はそういう意味なのよ。ちょっと悲観的な歌だけど、別に心配することはないのよ」としどろもどろなことを言う秀子であったが、実はちょっとどころではなく、あまりに悲観的すぎると思っていた。
世紀末という言葉を聞いた悠太郎は、その主題歌のみならず《仮面ライダーBLACK》そのものに満ち満ちている気分をぴたりと言い当てられたように感じて、深く得心した。人類の文明と文化が危機的状況にあるという世界観は、まさしく世紀末的なのだ。テレビのなかではライダーが悪と戦ってくれている。しかし現実の世界ではどうなのだろう? 「まだ」の反対語が「もう」であることくらいよく知っていた悠太郎は、「それじゃ二十一世紀には、もう人の胸に温もりはなくなってしまうの? もう美しい海も湖もなくなってしまうの? 大地の緑も四季折々の花も、もうなくなってしまうの?」と問わずにはいられなかった。
やはりこの子はただの子ではないなと思いながら、「それはおまえたち次第なのよ」と秀子は答えた。「二十一世紀はおまえたちの時代よ。未来がひどい有様にならないように、おまえたちが世界を守ってゆかなくてはね。仮面ライダーみたいな正義の味方が、何人だって出てこなくちゃならないわね。おまえはその先頭に立てるかな? そのためには悠太郎、いっぱいお勉強するのよ」と秀子は息子に言い含めた。たしかに外務官僚の妻になる望み潰えたが、しかし外務官僚の母か、あるいはそれ以上の者の母になる望みまでは失われていないのだ――。だが母としての栄達のために、悠太郎にわずかでも希望を残してやろうとした秀子の配慮は、千代次によって木っ端微塵に打ち砕かれることになった。山の向こうに日が沈むある夕方に千代次は、極度に細い近視の目をしばたたいてブラウン管を見つめながら、「ユウ、おめえはノストラダムスの大予言ちゅうものを知っているか? 一九九九年の七月に、人類は滅亡するらしいぞ。はあ俺はさんざ生きたからいつ死んでも構わねえが、おめえはまだ高校生だから、気の毒だのう」と衝撃的なことを告げてしまったのである。一九九九年の七月に悠太郎はもうこの世に亡く、真壁の家はもう滅亡しているのだが、そんなことは神ならぬ身の千代次が知る由もなかった。
そうだった――。それから寒さが厳しくなり、それから少し緩んで、庭の雪だるまは薄汚れて小さくなり、明鏡閣の南塚支配人が影のように秀子を迎えにきて、雪は融け泥はぬかるみ、悠太郎はこの幼稚園に入ったのであった。差し当たり今のところはまだ、大地の緑も四季折々の花も失われてはいないらしかった。憲法記念日とこどもの日のあいだの五月四日が、初めて国民の休日となった三連休が始まる前に、梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら軍手や手っ甲を着け、学芸村のどこかにあるという沢へ出かけていって、緑鮮やかなセリやクレソンを喜色満面で籠にいっぱい採ってくると、それらをおひたしや天ぷらにしては食卓に供し、「ほれユウ、食ってみろ。うっまーい!」と言いながら、皿をぐいと押し出して勧めた。悠太郎が自分で食べてみてうまいと感じる前に、先回りして「うっまーい!」などと呪文をかけられては、それ以外の反応のしようがなくなってしまう。こうしたことは以前も以後も繰り返され、悠太郎の自発性の発達を著しく阻害したのであるが、それらが実際うまかったことは不幸中の幸いであったし、何より今年も大地が緑なしていることを、そのセリやクレソンが証明してくれていた。唐松の林だって連休明けの暖かい雨上がりの日に、今年もまた魔法のように一斉に緑の芽を吹いたではないか。それでは四季折々の花はどうか? この春もやはり花は咲いた。五月ともなれば六里ヶ原にも遅い春が訪れ、桜やコブシやタンポポやムスカリの花が、だんだん咲けばいいものを一斉に咲くのである。真壁の家の庭では、冬を追憶するかのようにユキヤナギの白い花の穂が咲きこぼれ、またレンギョウは黄色い星雲のように群れ咲いた。梅子が軍手や手っ甲を着け、電気スタンドの笠のような帽子を被った頭を揺らしながら丹精した花壇には、色様々なクロッカスやチューリップが咲いていた。そしてこの春、悠太郎にとって新たに忘れ難い花となったのは水仙であった。水仙の花の思い出は、照月湖のほとりに建つ観光ホテル明鏡閣に勤めている、ひょろりと背の高い三池光子さんの印象と強く結びつくことになった。
三連休の後の日曜日に《仮面ライダーBLACK》を観終わった悠太郎は、千代次から声をかけられた。「ゴールデンウィークとやらの騒ぎも、今日でひと段落だのう。明鏡閣もぼつぼつ後始末ちゅうところだんべえ。ユウ、おめえ行って、お母様に助けてこお」と千代次は言ったのだが、六里ヶ原の方言では「来る」の命令形は「来お」となるのである。千代次にしてみれば幼稚園が休みのたびに、自分にはけっして心から懐くことのない孫の子守をしたくはなかった。ただでさえ嫌なところへ、休みが三日も続いて余計に嫌気が差していた。可愛げのない孫を追い払い、気兼ねなく心ゆくまでテレビを観たり、書道の稽古をしたり、漢詩を読んだりしたかったのである。祖父の命令を畏み、悠太郎は浅緑に若葉し始めた林間のダート道を歩んで、湖の向こうの正面に迫る鷹繋山を眺めつつ急な坂道を降り、岸辺に葦のそよぐ照月湖を左手に見ながら、観光ホテル明鏡閣へ向かった。地面まで届く赤い三角屋根を戴いた明鏡閣の中央部は、側面から見れば浅間山を思わせる形をしていた。キャノピーをくぐってフロントに通じる正面玄関を入ることはせず、その西側にある崩れかけたコンクリートの段に登って、白いペンキの剥げかけた小さな扉の四角い取っ手を、力いっぱい手前に引いた。取っ手の高さと扉の重さに、小さい非力な悠太郎は苦労したが、そこから入れば社員食堂という名の従業員詰所は、すぐ左にあると教わっていたのである。
その狭苦しい従業員詰所には、煙が充満していた。「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いして慇懃に悠太郎を迎えてくれた南塚支配人も、ふさふさの髪を七三に分けて薄黒いサングラスをかけた黒岩栄作さんも、盛んに煙草を吸っていた。この黒岩さんは、大工作業も電気工事も板前仕事も何でもござれの実力派で、いろいろと変わった企画も立案できる愛すべきアイデアおじさんでもあったが、そのうえ煙草の煙を輪っかの形にして連続で吐き出すという特技さえ持っていた。「みんなは俺のことをサカエさんて呼ぶだよ。ここらあたりはおめえ、黒岩さんだらけだものを」と言いながらサカエさんは、自ら調理した昼食のカレーライスを悠太郎にも振る舞ってくれたが、そこへ生卵をひとつ落とし、なおかつウスターソースをかけて食べるのがサカエさん流なのであった。外仕事から戻ったばかりの剽軽者の橋爪進吉さんも、野良着を脱いで痒い背中をぎざぎざの柱に熊のようにこすりつけながら、ゲジゲジ眉毛の顔をひしゃげたように笑わせて煙草を吸っていたが、思いついたように食器棚から茶托を一枚取り出すと自分の頭に乗せ、「照月湖から河童が出てきて、カッパッパー!」と言って悠太郎を大笑いさせた。窓の反対側には同じくらいの高さに、やや前傾した長方形の鏡が取りつけられていたが、橋爪さんによればそれは、黒岩サカエさんが考案した仕掛けであるということであった。「あれのおかげで窓際に座っていても、駐車場に来た車を見るのに、振り返らなくて済むっちゅうわけだ。まあずサカエさんは横着者だのう」と橋爪さんが言えば、サカエさんは含んだような笑い声を立てて、「俺は海千山千だものを」とやり返すのであった。駐車場でロータリーのように機能する円形の花壇は、やはり色様々なクロッカスやチューリップを咲かせて鏡に映っていた。
そんなやり取りと煙の絶え間に悠太郎は、ふと詰所の壁に飾られている一枚の写真に気がついた。片えくぼを浮かべた恵比寿顔で豪快に笑うその男の写真は、家の仏壇に飾られているものと同じであった。「あっ、増田ケンポウさん」と悠太郎が言うと、居合わせた従業員一同は低い驚きの声にどよめいた。南塚支配人は煙草の煙を吐き出すと、感に堪えないような笑顔で「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いした。「そのお若さで増田ケンポウの顔を知っていますか。さすがは千代次さんのお孫さんですなあ。いや、かく言う私も増田ケンポウに恩義を感じることにかけては、お祖父様に引けを取らないのですよ」と、髪を四角く刈り込んだ支配人は語り始めた。「私の倅があなたくらいの頃でしたか、いやもっと小さな頃だったかもしれません、囲炉裏に転がり落ちましてね、全身に大火傷を負ったのですよ。私は慌てふためきましてね、とっさにケンポウ社長に電話したのです。当時ケンポウ社長はもう脳卒中で倒れた後でしたが、不自由な言葉ながら即座にこう言ってくれました。〈そんな田舎では話にならん! すぐに東京へ連れてこい! 存じ寄りの名医に話をつけておく!〉それで万事言われた通りにしました。倅が死なずに済んだのは、まったく増田ケンポウのおかげなのです。倅には片足を引きずる障害が残りまして、本人はそれで不自由もすればつらくもあったでしょうが、親である私からすれば、生きていてくれただけで万々歳です。本当に増田ケンポウは、倅の命の恩人なのです。お祖父様や私ばかりではありません。ケンポウ社長は日本のために働く者たち皆の幸せを常に考え、命懸けでそれを実現しようとされた。事業の神様などと呼ぶ人もあるそうですが、あながち誇張とも思えません。当節ああいう経営者はもう出ませんな。おっと、これは失言でしたかな? 何も現社長のことをどうこう言うつもりはないのです。ただあんな巨大な人はもう出ないということです。浅間山のマグマのように煮えたぎっていたあのエネルギーが懐かしい。明治は遠くなりにけりですよ。うおっほ、うおっほ、うおっほ……」
そんな話を聞かされた悠太郎は、改めて増田ケンポウを見直していた。なあんだ、やっぱりただの戦争屋さんなんかじゃなかった。立派な偉い人だったじゃないか――。ところが悠太郎がそう思ったとき、うっすらと愛想笑いを浮かべて座っていた秀子にとって面白くない話を、また煙草の煙を吐き出した南塚支配人が、誰にともなく続けたのである。「何もわが子に多くを期待することはないのですよ。それは私だって親ですから、そういう親の気持ちが分からないではありません。実際に倅が死ぬほどの目に遭わなかったら、わが子がただ生きていてくれるだけで嬉しいとは思えなかったかもしれませんな。そうです、生きているということ、命があるということが大事なのです。そのうえ人並みの幸せにでも恵まれたなら、もう万々歳です。何も言うことはないではありませんか。わが子の前途の平々凡々たることを願う心こそ、真の親心ではないですかな。私にはあの一件以来、そう思われてならないのですよ。うおっほ、うおっほ、うおっほ……」支配人がそんなことを言ったとき、サングラスをかけた黒岩サカエさんも、剽軽者の橋爪さんも、皆が皆それとなく秀子の反応を窺うのが悠太郎には感じ取れた。
「狐め。浅間に鳴ける昼狐め」と秀子は、うっすらと愛想笑いを浮かべた下膨れの顔を少しうつむけて思いながら、女性従業員の制服代わりの青いエプロンを着けた体を硬くした。もしかするとテーブルの下に隠れた両手には、ぶるぶると力が込められているのかもしれなかった。ちなみに狐というのは、南塚支配人の家が養孤業をかつて営んでいたことから、そう思ったのである。「何が人並みだ。何が平々凡々だ。不幸な結婚をした私の親心が、あなたなんかに分かるものか。今や私にはこの子だけが希望なのだ。この子にすべてが懸かっているのだ。この子は私のものだ。私のものに何を期待しようが私の勝手だ。そうだ、この子だけが私のものなのだ。家も土地もお金も何もかもが、浅間観光の永久名誉顧問である父のものだ。私がここで働いていることだって、父の意向によるのだ。父に屈服した不幸な出戻り娘の私にとって、私のものと呼べるのはこの子だけだ。人並みでなんか終わらせるものか。平々凡々たる人生なんか歩ませるものか。この子は今に飛び抜けて、抜きん出て、誰よりも偉くなるのだ。そして私は六里ヶ原で英雄の母になるのだ。そのためなら、どんな苦しみにだって耐えてみせる。浅間山が爆発的な噴火で下したお告げは、必ず実現するのだ。必ず、必ず、必ず……」そんな秀子の思いが手に取るように分かってしまったので、悠太郎は睫毛の長い二重瞼の目を伏せて、すっかりしょげてしまった。もし梅子がその場に居合わせたら、事態はもっとこじれたに違いなかったが、幸い梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、照月湖モビレージの掃除に降りていた。
そんなとき優雅な手つきで煙草を吸っていた初老の婦人が、アイシャドウの濃い目をぱちくりさせながら、月光に照らされた黒天鵞絨のような艶のある低音の声で「そうだ、ユウちゃん、お花は好き? 湖のほとりに水仙が咲いたわよ。私と一緒に水仙を見にゆきましょう」と言うが早いか、明鏡閣のロゴが入った陶器の灰皿で煙草を揉み消すと、やおら立ち上がった。灰色がかったボブショートの髪をした、ひょろりと背の高い撫で肩のその婦人こそ光子さんで、彫刻家と結婚したため三池の姓に変わったが、もともとはケンポウさんの甥である常務の妹で、やはり増田姓であったという。それゆえ玄界灘のあたりの訛りが残ったものであろうか、「水仙」と言うとき「ス」の音をいちばん高くして、そこから流れ落ちるようなイントネーションで発音した。助かったとばかり悠太郎は、光子さんの後に従って社員食堂という名の従業員詰所を出た。詰所の正面の売店やその先のゲームコーナーを右手に、客のための大食堂を左手に見ながら、オレンジ色の床タイルが敷き詰められた廊下を歩むあいだ、悠太郎は家で千代次や梅子が光子さんについて語ったことを思い出していた。お祖父様が極度に細い近視の目をしばたたきながら、「まあず豪儀なもんだ。三池さんは優雅でありながら豪快なところがある。増田ケンポウの血筋かのう。ああいう気っ風のいいご婦人は、はあ出ねえような気がすらあな」と言っていたのはこのことだったのか。お祖母様だってパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、三池さんはねえ、麻雀もうんと強いだよ。優雅に煙草を燻らしながら、何食わぬ顔で国士無双なんか決めてねえ、わったしたちをたまがすだよ。音楽に喩えるなら、バッハさんの管弦楽組曲の第二番だね。典雅にして骨太、華麗にして剛毅だよ」と言っていたではないか――。梅子は西洋のいわゆるクラシック音楽を愛好し、その作曲家たちの姓に敬称をつけて呼ぶことを常としていたが、音楽の喩えは強く悠太郎の興味を引いた。玄関の靴箱の上に飾ってある、光子さんのご主人が作ったというブロンズの少女像を見ながら、悠太郎はまだ聴いたことのないバッハさんの曲の響きを夢想するようになっていたが、その日実際に光子さんの振る舞いを目の当たりにしたことで、未知なる曲を少しだけはっきりと思い描けた気がした。ただ梅子が「ウッフフ、血は繋がってないけどねえ、三池さんには先代の女社長を思い出させるところがあるよ」と言ったとき、千代次が苦い顔をして悲しみに沈んだことは、悠太郎の心に奇妙な引っ掛かりを残していた。
悠太郎が入ってきた南側と同じ作りの、白いペンキの剥げかけた北側の二重扉から、ふたりは屋外に出た。黒く四角い取っ手は、光子さんが優雅な手つきで苦もなく押してくれた。ふたりが黒ずんだ石段を下りて照月湖の岸辺へゆくと、そこには白や黄色の水仙がひょろりと咲いていた。もはやボート遊びの客も少なくなった湖は、細波立ちながら昼の光に眩しく光っていた。そのきらめきを見ながら三池光子さんは、「ユウちゃんはナルキッソスのお話を知ってる?」と突然問うた。知らないと首を横に振る悠太郎に、光子さんはアイシャドウの濃い目をぱちくりさせながら教えた。「ギリシャの古いお話よ。昔ナルキッソスっていう美少年がいてね、女の子を相手にしなかったものだから呪いをかけられて、水に映った自分の姿に恋するようにされたの。ナルキッソスはそのまま水仙の花になってしまったんですって」と話す光子さんであったが、よく知られたこの神話についての光子さんの解釈はしかし、いくらか独特なものであった。「自分ばっかり見つめてたら、人間は死んじゃうのよ。そうかといって自分以外の人間ばっかり見つめてるのも、それはそれで大変でしょう? 他人であれ家族であれね。だからナルキッソスは、きっとお花になったのよ。だからお花を見るのは、きっといいことなのよ。お花がよく見えるようになれば、人間だってよく見えるようになるわ」と光子さんは、芸術家の妻らしいと言えなくもない飛躍した論理で語った。
その飛躍した論理が、悠太郎にはひどくしっくり来たのである。自分のことや家族とのことで抱えている困難を、光子さんはいとも優雅に昔話のなかへと置き移してみせてくれた。その見事な手並みに、悠太郎は泣きたいほど感謝せずにはいられなかった。「そうですね、光子さん。本当にその通りですね。できることならぼくだって鏡の外へ出てゆきたいんです。でも怖くて、なかなかうまくゆきません。そうですね、人間が怖かったら、まずはお花を見ればいいんですね。そうすればいつかきっと、お花も人間も大切にできるようになれますよね……」と悠太郎は心の底から思ったが、泣きたいのを堪えていたので言葉には出せなかった。五月の微風に水面は細波立ってきらめき、白や黄色の水仙の花たちは揺れていた。
悠太郎を連れて明鏡閣に戻った光子さんは、ワインレッドの絨毯を敷いたロビーにあるガラスのテーブルに、切り取ってきた幾本かの水仙を生けた花瓶を飾ると、宿泊客が退室した後の部屋を片づけてまわり始めた。スリッパの足音をとっちん、とっちんと響かせて小暗い廊下を歩く光子さんについて歩くうちに、悠太郎には「とっちん、とっちん」という足音が「ちっとん、ちっとん」とも聞こえるようになった。客室のゴミ集めや洗面所掃除で光子さんを手伝った悠太郎は、また廊下に出てスリッパの足音を聞くのを楽しみにした。「とっちん、とっちん」なのか、それとも「ちっとん、ちっとん」なのかと考えていると、悠太郎は催眠術にでもかかったような心地になり、不意にあのエンディングテーマのときに襲ってきた、白く光る香しい奔流を思い出すのであった。それから二階の大広間で、ふたりは洗濯され乾燥した浴衣の帯を畳んだ。光子さんにやり方を教わった悠太郎は、すぐさま美しい五角形に帯を畳めるようになった。「まあ綺麗だこと。ユウちゃんは手先が器用なのね」と光子さんは、月光に照らされた黒天鵞絨のような艶のある声で言いながら、アイシャドウの濃い目をぱちくりさせて感嘆した。
光子さんのギリシャ神話の解釈は、すぐさま悠太郎に著しい影響を与えた。鏡のなかの世界と鏡の外の世界は別なのだという事実を、悠太郎は卒然として悟ったのである。自分にとっての右側は、向かい合った相手にとっては左側だということは、もはや謎でも何でもなかった。翌日の幼稚園で悠太郎は鳩ぽっぽ体操を、前に出て手本を見せている先生方と鏡合わせのようにではなく、まわりの園児たちと同じような左右正しい動きで、ともかくもやり遂げることができたのである。弦巻先生は少しきつい目でその変化を見て取ると、こんな子にも適応力が皆無ではないらしいことに驚いた。
悠太郎ほど真剣に《仮面ライダーBLACK》を視聴していた幼児も珍しいのだが、それには理由がないではなかった。もちろん彼は番組そのものが好きであった。ライダーに変身して活躍する主人公の名前を、悠太郎は自分の名前と比べてみた。苗字と名前の音節数は同じであった。では韻を踏んでいるだろうか? 残念ながら踏んでいないと結論せざるを得なかった。ともあれ暗黒結社によって改造人間にされながら、その悲しみを乗り越えてパンチやキックで悪と戦うヒーローに悠太郎は憧れたが、それだけならどこの幼児も同じであろう。問題は日曜日の十時から十時三十分という放送時間であった。日曜日の午前は、祖父の千代次が報道や政治討論の番組を、立て続けに視聴したい時間帯だったのである。いかに母の秀子が千代次の同意を取りつけてくれたとはいえ、祖父の楽しみを三十分間も奪うことを、悠太郎は心苦しく思った。《仮面ライダーBLACK》が始まる時刻になると、千代次は目に見えて苦い顔をして、極度に細い近視の目をしばたたきながら居間から出て自室に籠もると、おそらく三十分のあいだ書道の稽古でもするか漢詩でも読むか、あるいは『諸君!』や『文藝春秋』のページをめくるかしているのであった。実際のところ四月十日に、四国と本州を結ぶ瀬戸大橋の開通を取り上げた特番によって《仮面ライダーBLACK》が休止になったとき、千代次は「そうかそうか、今日はライダーは休みか。よかったよかった。ほれ見ろ、あんなでけえ橋なんざ架けて、まあず豪儀だのう。これに比べりゃあ照月湖の橋なんざおめえ、マッチ棒みてえなもんさな」と言いながら、上機嫌でブラウン管に見入っていた。悠太郎はライダーの活躍を見られないことが悲しかったが、機嫌のよい祖父を見るのは嬉しかった。幼稚園に入ったばかりの子供にとって、それはやはり複雑な感情であった。もしその千代次が《仮面ライダーBLACK》に難癖をつけてきたらどうしようというのが、もっと前々からの悠太郎の懸念であった。こんなものを観るのは「しゃいなし」だ、つまり六里ヶ原の方言でくだらないことだと千代次が言ったら、そのとき悠太郎は祖父に通じるような論理的な老成した言葉で、この番組を視聴する意義を説明しなければならないと思い詰めていた。この番組は逆境に立ち向かう勇気を育て、正義を愛する人格を涵養し、生きることの喜びのみならず、悲しみをも教えてくれます――。悠太郎はそんなことを言ってみるつもりであった。その説得に失敗すれば、もはや視聴は不可能になるだろう。そんなふうに思い詰めていたから、悠太郎は一回ごとのストーリー展開や怪人の名前のみならず、登場人物たちの台詞回しまでよく記憶していたのである。それにしてもエンディングテーマでのあの不思議な体験は、いつのことだったろう?
そうだった。あれは一九八八年一月十日のことで、寒さの厳しい六里ヶ原は氷雪に閉ざされていたから、ブラウン管のなかで怪人が放つ冷凍の息や鋭い氷柱は、その冷たさをありありと感じさせながら悠太郎に迫ったものである。やがてエンディングが始まったとき、悠太郎はテレビの前で立ち上がると、音声に合わせて歌い始めた。するとそのとき驚くべきことが起こった。悠太郎は白く光る香しい奔流に、突然包まれ飲み込まれ押し流されて、どこかこの世ならぬ次元に拉し去られたのである。悠太郎が恍惚として我を忘れていたのは、現実の時間にすればエンディングテーマが終わるまでのことであったが、その体験があまりにも不思議だったので、いつもなら注意深く耳を傾けるはずの次回予告も、上の空で聞くほかなかった。何かがすっかり変わってしまったのは、あのときだったのだ。ぼくを取り巻くしんとした淋しさが、痛切に感じられるようになったのもあの直後だったし、頼朝が六里ヶ原で催した巻狩や、学芸村を開発した枢密顧問官のお爺さんの政治的な戦いや、浅間観光を設立して豪快に笑っていた増田ケンポウ社長をめぐる難しい話の意味が、急に分かり始めたのもあの直後からだった――。
その哀切な歌の意味を知りたくなった悠太郎は、その夜に〈Long Long ago, 20th Century〉とはどういう意味かと秀子に尋ねてみた。夜空では巨大なオリオン座の赤いベテルギウスが、大犬座の蒼白いシリウスや小犬座の白いプロキオンと、冬の大三角を輝かせていた。風呂上がりの秀子は、シャンプーとリンスの匂いがする濡れた豊かな髪の頭にタオルを巻きつけていたが、幼いわが子の口から突然英語が発せられるのを聞くと、化粧を落としたその下膨れの顔に驚きの色を浮かべながら、「遠い遠い昔、二十世紀という意味よ」と答えた。悠太郎は物問いたげな大きな目を黒々と見開いて首を傾げ、「今は何世紀?」と尋ねた。「一九八八年だから、二十世紀よ」という秀子の答えを聞いた悠太郎は、なぜ今現在が遠い遠い昔なのか、わけが分からなくなった。そんなわが子の様子を見た秀子は、「いったいそれは何なの? どこでそんな英語を憶えたの?」と不思議がって問い質し、それが《仮面ライダーBLACK》のエンディングテーマの題名だと知ると、その歌詞を教えてくれるように促した。求めに応じて悠太郎は姿勢を正し深く息を吸い込むと、前年の秋から繰り返し聴いて記憶していたその主題歌を、か細くはあるがよく澄んだボーイソプラノで歌った。
悠太郎の歌のうまさや記憶力もさることながら、その歌詞に表現された哀惜を汲み取ってしまう感受性にも驚いた秀子は、さてどう言ったらあまり不安がらせずにその意味を説明できるかと思案した。普通の四歳児が聴いて喜ぶような内容ではなかった。そんな主題歌を好むわが子が誇らしくはあったが、その語学力と感受性の過多ゆえに破滅されては元も子もなかった。没落士族の末裔であったこの子の父親は、外務省に入って精神に異常を来たし、そのまた父親は売れない文筆家として不遇を託っていたものである。そんな血の流れを憂えながら秀子は、「世紀末って分かるかしら? 一世紀は百年で終わるの。二十世紀は二〇〇〇年までだから、あと十年ちょっとでしょう? 今がまさに世紀末なの」と説明を始めた。「世紀末って、みんなが不安になるのよ。それまで信じられていたものが信じられなくなって、もうおしまいだっていう気分になるの。でもそんな気分になるだけなのよ。現に世界は続いてきたんだもの。今も自然破壊の問題とか、東と西の冷たい戦争とか、不安なことはいろいろあるでしょう? でも二十一世紀や二十二世紀から振り返ってみれば、この二十世紀はまだいい時代だった。その歌はそういう意味なのよ。ちょっと悲観的な歌だけど、別に心配することはないのよ」としどろもどろなことを言う秀子であったが、実はちょっとどころではなく、あまりに悲観的すぎると思っていた。
世紀末という言葉を聞いた悠太郎は、その主題歌のみならず《仮面ライダーBLACK》そのものに満ち満ちている気分をぴたりと言い当てられたように感じて、深く得心した。人類の文明と文化が危機的状況にあるという世界観は、まさしく世紀末的なのだ。テレビのなかではライダーが悪と戦ってくれている。しかし現実の世界ではどうなのだろう? 「まだ」の反対語が「もう」であることくらいよく知っていた悠太郎は、「それじゃ二十一世紀には、もう人の胸に温もりはなくなってしまうの? もう美しい海も湖もなくなってしまうの? 大地の緑も四季折々の花も、もうなくなってしまうの?」と問わずにはいられなかった。
やはりこの子はただの子ではないなと思いながら、「それはおまえたち次第なのよ」と秀子は答えた。「二十一世紀はおまえたちの時代よ。未来がひどい有様にならないように、おまえたちが世界を守ってゆかなくてはね。仮面ライダーみたいな正義の味方が、何人だって出てこなくちゃならないわね。おまえはその先頭に立てるかな? そのためには悠太郎、いっぱいお勉強するのよ」と秀子は息子に言い含めた。たしかに外務官僚の妻になる望み潰えたが、しかし外務官僚の母か、あるいはそれ以上の者の母になる望みまでは失われていないのだ――。だが母としての栄達のために、悠太郎にわずかでも希望を残してやろうとした秀子の配慮は、千代次によって木っ端微塵に打ち砕かれることになった。山の向こうに日が沈むある夕方に千代次は、極度に細い近視の目をしばたたいてブラウン管を見つめながら、「ユウ、おめえはノストラダムスの大予言ちゅうものを知っているか? 一九九九年の七月に、人類は滅亡するらしいぞ。はあ俺はさんざ生きたからいつ死んでも構わねえが、おめえはまだ高校生だから、気の毒だのう」と衝撃的なことを告げてしまったのである。一九九九年の七月に悠太郎はもうこの世に亡く、真壁の家はもう滅亡しているのだが、そんなことは神ならぬ身の千代次が知る由もなかった。
そうだった――。それから寒さが厳しくなり、それから少し緩んで、庭の雪だるまは薄汚れて小さくなり、明鏡閣の南塚支配人が影のように秀子を迎えにきて、雪は融け泥はぬかるみ、悠太郎はこの幼稚園に入ったのであった。差し当たり今のところはまだ、大地の緑も四季折々の花も失われてはいないらしかった。憲法記念日とこどもの日のあいだの五月四日が、初めて国民の休日となった三連休が始まる前に、梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら軍手や手っ甲を着け、学芸村のどこかにあるという沢へ出かけていって、緑鮮やかなセリやクレソンを喜色満面で籠にいっぱい採ってくると、それらをおひたしや天ぷらにしては食卓に供し、「ほれユウ、食ってみろ。うっまーい!」と言いながら、皿をぐいと押し出して勧めた。悠太郎が自分で食べてみてうまいと感じる前に、先回りして「うっまーい!」などと呪文をかけられては、それ以外の反応のしようがなくなってしまう。こうしたことは以前も以後も繰り返され、悠太郎の自発性の発達を著しく阻害したのであるが、それらが実際うまかったことは不幸中の幸いであったし、何より今年も大地が緑なしていることを、そのセリやクレソンが証明してくれていた。唐松の林だって連休明けの暖かい雨上がりの日に、今年もまた魔法のように一斉に緑の芽を吹いたではないか。それでは四季折々の花はどうか? この春もやはり花は咲いた。五月ともなれば六里ヶ原にも遅い春が訪れ、桜やコブシやタンポポやムスカリの花が、だんだん咲けばいいものを一斉に咲くのである。真壁の家の庭では、冬を追憶するかのようにユキヤナギの白い花の穂が咲きこぼれ、またレンギョウは黄色い星雲のように群れ咲いた。梅子が軍手や手っ甲を着け、電気スタンドの笠のような帽子を被った頭を揺らしながら丹精した花壇には、色様々なクロッカスやチューリップが咲いていた。そしてこの春、悠太郎にとって新たに忘れ難い花となったのは水仙であった。水仙の花の思い出は、照月湖のほとりに建つ観光ホテル明鏡閣に勤めている、ひょろりと背の高い三池光子さんの印象と強く結びつくことになった。
三連休の後の日曜日に《仮面ライダーBLACK》を観終わった悠太郎は、千代次から声をかけられた。「ゴールデンウィークとやらの騒ぎも、今日でひと段落だのう。明鏡閣もぼつぼつ後始末ちゅうところだんべえ。ユウ、おめえ行って、お母様に助けてこお」と千代次は言ったのだが、六里ヶ原の方言では「来る」の命令形は「来お」となるのである。千代次にしてみれば幼稚園が休みのたびに、自分にはけっして心から懐くことのない孫の子守をしたくはなかった。ただでさえ嫌なところへ、休みが三日も続いて余計に嫌気が差していた。可愛げのない孫を追い払い、気兼ねなく心ゆくまでテレビを観たり、書道の稽古をしたり、漢詩を読んだりしたかったのである。祖父の命令を畏み、悠太郎は浅緑に若葉し始めた林間のダート道を歩んで、湖の向こうの正面に迫る鷹繋山を眺めつつ急な坂道を降り、岸辺に葦のそよぐ照月湖を左手に見ながら、観光ホテル明鏡閣へ向かった。地面まで届く赤い三角屋根を戴いた明鏡閣の中央部は、側面から見れば浅間山を思わせる形をしていた。キャノピーをくぐってフロントに通じる正面玄関を入ることはせず、その西側にある崩れかけたコンクリートの段に登って、白いペンキの剥げかけた小さな扉の四角い取っ手を、力いっぱい手前に引いた。取っ手の高さと扉の重さに、小さい非力な悠太郎は苦労したが、そこから入れば社員食堂という名の従業員詰所は、すぐ左にあると教わっていたのである。
その狭苦しい従業員詰所には、煙が充満していた。「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いして慇懃に悠太郎を迎えてくれた南塚支配人も、ふさふさの髪を七三に分けて薄黒いサングラスをかけた黒岩栄作さんも、盛んに煙草を吸っていた。この黒岩さんは、大工作業も電気工事も板前仕事も何でもござれの実力派で、いろいろと変わった企画も立案できる愛すべきアイデアおじさんでもあったが、そのうえ煙草の煙を輪っかの形にして連続で吐き出すという特技さえ持っていた。「みんなは俺のことをサカエさんて呼ぶだよ。ここらあたりはおめえ、黒岩さんだらけだものを」と言いながらサカエさんは、自ら調理した昼食のカレーライスを悠太郎にも振る舞ってくれたが、そこへ生卵をひとつ落とし、なおかつウスターソースをかけて食べるのがサカエさん流なのであった。外仕事から戻ったばかりの剽軽者の橋爪進吉さんも、野良着を脱いで痒い背中をぎざぎざの柱に熊のようにこすりつけながら、ゲジゲジ眉毛の顔をひしゃげたように笑わせて煙草を吸っていたが、思いついたように食器棚から茶托を一枚取り出すと自分の頭に乗せ、「照月湖から河童が出てきて、カッパッパー!」と言って悠太郎を大笑いさせた。窓の反対側には同じくらいの高さに、やや前傾した長方形の鏡が取りつけられていたが、橋爪さんによればそれは、黒岩サカエさんが考案した仕掛けであるということであった。「あれのおかげで窓際に座っていても、駐車場に来た車を見るのに、振り返らなくて済むっちゅうわけだ。まあずサカエさんは横着者だのう」と橋爪さんが言えば、サカエさんは含んだような笑い声を立てて、「俺は海千山千だものを」とやり返すのであった。駐車場でロータリーのように機能する円形の花壇は、やはり色様々なクロッカスやチューリップを咲かせて鏡に映っていた。
そんなやり取りと煙の絶え間に悠太郎は、ふと詰所の壁に飾られている一枚の写真に気がついた。片えくぼを浮かべた恵比寿顔で豪快に笑うその男の写真は、家の仏壇に飾られているものと同じであった。「あっ、増田ケンポウさん」と悠太郎が言うと、居合わせた従業員一同は低い驚きの声にどよめいた。南塚支配人は煙草の煙を吐き出すと、感に堪えないような笑顔で「うおっほ、うおっほ、うおっほ」と咳払いした。「そのお若さで増田ケンポウの顔を知っていますか。さすがは千代次さんのお孫さんですなあ。いや、かく言う私も増田ケンポウに恩義を感じることにかけては、お祖父様に引けを取らないのですよ」と、髪を四角く刈り込んだ支配人は語り始めた。「私の倅があなたくらいの頃でしたか、いやもっと小さな頃だったかもしれません、囲炉裏に転がり落ちましてね、全身に大火傷を負ったのですよ。私は慌てふためきましてね、とっさにケンポウ社長に電話したのです。当時ケンポウ社長はもう脳卒中で倒れた後でしたが、不自由な言葉ながら即座にこう言ってくれました。〈そんな田舎では話にならん! すぐに東京へ連れてこい! 存じ寄りの名医に話をつけておく!〉それで万事言われた通りにしました。倅が死なずに済んだのは、まったく増田ケンポウのおかげなのです。倅には片足を引きずる障害が残りまして、本人はそれで不自由もすればつらくもあったでしょうが、親である私からすれば、生きていてくれただけで万々歳です。本当に増田ケンポウは、倅の命の恩人なのです。お祖父様や私ばかりではありません。ケンポウ社長は日本のために働く者たち皆の幸せを常に考え、命懸けでそれを実現しようとされた。事業の神様などと呼ぶ人もあるそうですが、あながち誇張とも思えません。当節ああいう経営者はもう出ませんな。おっと、これは失言でしたかな? 何も現社長のことをどうこう言うつもりはないのです。ただあんな巨大な人はもう出ないということです。浅間山のマグマのように煮えたぎっていたあのエネルギーが懐かしい。明治は遠くなりにけりですよ。うおっほ、うおっほ、うおっほ……」
そんな話を聞かされた悠太郎は、改めて増田ケンポウを見直していた。なあんだ、やっぱりただの戦争屋さんなんかじゃなかった。立派な偉い人だったじゃないか――。ところが悠太郎がそう思ったとき、うっすらと愛想笑いを浮かべて座っていた秀子にとって面白くない話を、また煙草の煙を吐き出した南塚支配人が、誰にともなく続けたのである。「何もわが子に多くを期待することはないのですよ。それは私だって親ですから、そういう親の気持ちが分からないではありません。実際に倅が死ぬほどの目に遭わなかったら、わが子がただ生きていてくれるだけで嬉しいとは思えなかったかもしれませんな。そうです、生きているということ、命があるということが大事なのです。そのうえ人並みの幸せにでも恵まれたなら、もう万々歳です。何も言うことはないではありませんか。わが子の前途の平々凡々たることを願う心こそ、真の親心ではないですかな。私にはあの一件以来、そう思われてならないのですよ。うおっほ、うおっほ、うおっほ……」支配人がそんなことを言ったとき、サングラスをかけた黒岩サカエさんも、剽軽者の橋爪さんも、皆が皆それとなく秀子の反応を窺うのが悠太郎には感じ取れた。
「狐め。浅間に鳴ける昼狐め」と秀子は、うっすらと愛想笑いを浮かべた下膨れの顔を少しうつむけて思いながら、女性従業員の制服代わりの青いエプロンを着けた体を硬くした。もしかするとテーブルの下に隠れた両手には、ぶるぶると力が込められているのかもしれなかった。ちなみに狐というのは、南塚支配人の家が養孤業をかつて営んでいたことから、そう思ったのである。「何が人並みだ。何が平々凡々だ。不幸な結婚をした私の親心が、あなたなんかに分かるものか。今や私にはこの子だけが希望なのだ。この子にすべてが懸かっているのだ。この子は私のものだ。私のものに何を期待しようが私の勝手だ。そうだ、この子だけが私のものなのだ。家も土地もお金も何もかもが、浅間観光の永久名誉顧問である父のものだ。私がここで働いていることだって、父の意向によるのだ。父に屈服した不幸な出戻り娘の私にとって、私のものと呼べるのはこの子だけだ。人並みでなんか終わらせるものか。平々凡々たる人生なんか歩ませるものか。この子は今に飛び抜けて、抜きん出て、誰よりも偉くなるのだ。そして私は六里ヶ原で英雄の母になるのだ。そのためなら、どんな苦しみにだって耐えてみせる。浅間山が爆発的な噴火で下したお告げは、必ず実現するのだ。必ず、必ず、必ず……」そんな秀子の思いが手に取るように分かってしまったので、悠太郎は睫毛の長い二重瞼の目を伏せて、すっかりしょげてしまった。もし梅子がその場に居合わせたら、事態はもっとこじれたに違いなかったが、幸い梅子はパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら、照月湖モビレージの掃除に降りていた。
そんなとき優雅な手つきで煙草を吸っていた初老の婦人が、アイシャドウの濃い目をぱちくりさせながら、月光に照らされた黒天鵞絨のような艶のある低音の声で「そうだ、ユウちゃん、お花は好き? 湖のほとりに水仙が咲いたわよ。私と一緒に水仙を見にゆきましょう」と言うが早いか、明鏡閣のロゴが入った陶器の灰皿で煙草を揉み消すと、やおら立ち上がった。灰色がかったボブショートの髪をした、ひょろりと背の高い撫で肩のその婦人こそ光子さんで、彫刻家と結婚したため三池の姓に変わったが、もともとはケンポウさんの甥である常務の妹で、やはり増田姓であったという。それゆえ玄界灘のあたりの訛りが残ったものであろうか、「水仙」と言うとき「ス」の音をいちばん高くして、そこから流れ落ちるようなイントネーションで発音した。助かったとばかり悠太郎は、光子さんの後に従って社員食堂という名の従業員詰所を出た。詰所の正面の売店やその先のゲームコーナーを右手に、客のための大食堂を左手に見ながら、オレンジ色の床タイルが敷き詰められた廊下を歩むあいだ、悠太郎は家で千代次や梅子が光子さんについて語ったことを思い出していた。お祖父様が極度に細い近視の目をしばたたきながら、「まあず豪儀なもんだ。三池さんは優雅でありながら豪快なところがある。増田ケンポウの血筋かのう。ああいう気っ風のいいご婦人は、はあ出ねえような気がすらあな」と言っていたのはこのことだったのか。お祖母様だってパンチパーマの頭をゆらゆらと揺らしながら「ウッフフ、三池さんはねえ、麻雀もうんと強いだよ。優雅に煙草を燻らしながら、何食わぬ顔で国士無双なんか決めてねえ、わったしたちをたまがすだよ。音楽に喩えるなら、バッハさんの管弦楽組曲の第二番だね。典雅にして骨太、華麗にして剛毅だよ」と言っていたではないか――。梅子は西洋のいわゆるクラシック音楽を愛好し、その作曲家たちの姓に敬称をつけて呼ぶことを常としていたが、音楽の喩えは強く悠太郎の興味を引いた。玄関の靴箱の上に飾ってある、光子さんのご主人が作ったというブロンズの少女像を見ながら、悠太郎はまだ聴いたことのないバッハさんの曲の響きを夢想するようになっていたが、その日実際に光子さんの振る舞いを目の当たりにしたことで、未知なる曲を少しだけはっきりと思い描けた気がした。ただ梅子が「ウッフフ、血は繋がってないけどねえ、三池さんには先代の女社長を思い出させるところがあるよ」と言ったとき、千代次が苦い顔をして悲しみに沈んだことは、悠太郎の心に奇妙な引っ掛かりを残していた。
悠太郎が入ってきた南側と同じ作りの、白いペンキの剥げかけた北側の二重扉から、ふたりは屋外に出た。黒く四角い取っ手は、光子さんが優雅な手つきで苦もなく押してくれた。ふたりが黒ずんだ石段を下りて照月湖の岸辺へゆくと、そこには白や黄色の水仙がひょろりと咲いていた。もはやボート遊びの客も少なくなった湖は、細波立ちながら昼の光に眩しく光っていた。そのきらめきを見ながら三池光子さんは、「ユウちゃんはナルキッソスのお話を知ってる?」と突然問うた。知らないと首を横に振る悠太郎に、光子さんはアイシャドウの濃い目をぱちくりさせながら教えた。「ギリシャの古いお話よ。昔ナルキッソスっていう美少年がいてね、女の子を相手にしなかったものだから呪いをかけられて、水に映った自分の姿に恋するようにされたの。ナルキッソスはそのまま水仙の花になってしまったんですって」と話す光子さんであったが、よく知られたこの神話についての光子さんの解釈はしかし、いくらか独特なものであった。「自分ばっかり見つめてたら、人間は死んじゃうのよ。そうかといって自分以外の人間ばっかり見つめてるのも、それはそれで大変でしょう? 他人であれ家族であれね。だからナルキッソスは、きっとお花になったのよ。だからお花を見るのは、きっといいことなのよ。お花がよく見えるようになれば、人間だってよく見えるようになるわ」と光子さんは、芸術家の妻らしいと言えなくもない飛躍した論理で語った。
その飛躍した論理が、悠太郎にはひどくしっくり来たのである。自分のことや家族とのことで抱えている困難を、光子さんはいとも優雅に昔話のなかへと置き移してみせてくれた。その見事な手並みに、悠太郎は泣きたいほど感謝せずにはいられなかった。「そうですね、光子さん。本当にその通りですね。できることならぼくだって鏡の外へ出てゆきたいんです。でも怖くて、なかなかうまくゆきません。そうですね、人間が怖かったら、まずはお花を見ればいいんですね。そうすればいつかきっと、お花も人間も大切にできるようになれますよね……」と悠太郎は心の底から思ったが、泣きたいのを堪えていたので言葉には出せなかった。五月の微風に水面は細波立ってきらめき、白や黄色の水仙の花たちは揺れていた。
悠太郎を連れて明鏡閣に戻った光子さんは、ワインレッドの絨毯を敷いたロビーにあるガラスのテーブルに、切り取ってきた幾本かの水仙を生けた花瓶を飾ると、宿泊客が退室した後の部屋を片づけてまわり始めた。スリッパの足音をとっちん、とっちんと響かせて小暗い廊下を歩く光子さんについて歩くうちに、悠太郎には「とっちん、とっちん」という足音が「ちっとん、ちっとん」とも聞こえるようになった。客室のゴミ集めや洗面所掃除で光子さんを手伝った悠太郎は、また廊下に出てスリッパの足音を聞くのを楽しみにした。「とっちん、とっちん」なのか、それとも「ちっとん、ちっとん」なのかと考えていると、悠太郎は催眠術にでもかかったような心地になり、不意にあのエンディングテーマのときに襲ってきた、白く光る香しい奔流を思い出すのであった。それから二階の大広間で、ふたりは洗濯され乾燥した浴衣の帯を畳んだ。光子さんにやり方を教わった悠太郎は、すぐさま美しい五角形に帯を畳めるようになった。「まあ綺麗だこと。ユウちゃんは手先が器用なのね」と光子さんは、月光に照らされた黒天鵞絨のような艶のある声で言いながら、アイシャドウの濃い目をぱちくりさせて感嘆した。
光子さんのギリシャ神話の解釈は、すぐさま悠太郎に著しい影響を与えた。鏡のなかの世界と鏡の外の世界は別なのだという事実を、悠太郎は卒然として悟ったのである。自分にとっての右側は、向かい合った相手にとっては左側だということは、もはや謎でも何でもなかった。翌日の幼稚園で悠太郎は鳩ぽっぽ体操を、前に出て手本を見せている先生方と鏡合わせのようにではなく、まわりの園児たちと同じような左右正しい動きで、ともかくもやり遂げることができたのである。弦巻先生は少しきつい目でその変化を見て取ると、こんな子にも適応力が皆無ではないらしいことに驚いた。
1
お気に入りに追加
6
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。
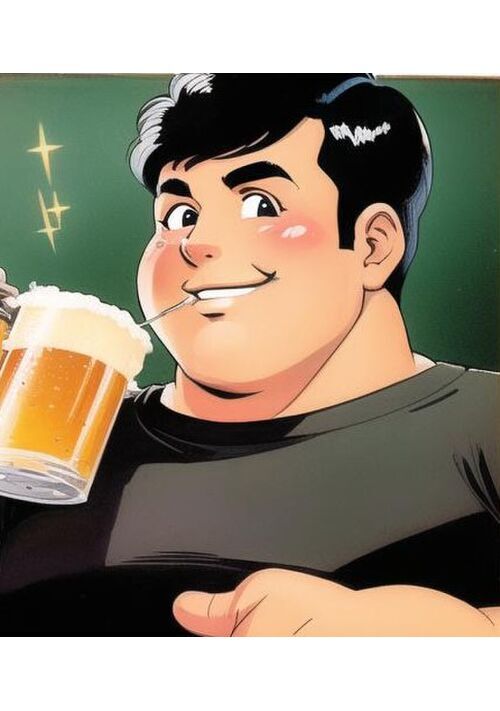
私の神様は〇〇〇〇さん~不思議な太ったおじさんと難病宣告を受けた女の子の1週間の物語~
あらお☆ひろ
現代文学
白血病の診断を受けた20歳の大学生「本田望《ほんだ・のぞみ》」と偶然出会ったちょっと変わった太ったおじさん「備里健《そなえざと・けん」》の1週間の物語です。
「劇脚本」用に大人の絵本(※「H」なものではありません)的に準備したものです。
マニアな読者(笑)を抱えてる「赤井翼」氏の原案をもとに加筆しました。
「病気」を取り扱っていますが、重くならないようにしています。
希と健が「B級グルメ」を楽しみながら、「病気平癒」の神様(※諸説あり)をめぐる話です。
わかりやすいように、極力写真を入れるようにしていますが、撮り忘れやピンボケでアップできないところもあるのはご愛敬としてください。
基本的には、「ハッピーエンド」なので「ゆるーく」お読みください。
全31チャプターなのでひと月くらいお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いしまーす!(⋈◍>◡<◍)。✧♡

隠れドS上司をうっかり襲ったら、独占愛で縛られました
加地アヤメ
恋愛
商品企画部で働く三十歳の春陽は、周囲の怒涛の結婚ラッシュに財布と心を痛める日々。結婚相手どころか何年も恋人すらいない自分は、このまま一生独り身かも――と盛大に凹んでいたある日、酔った勢いでクールな上司・千木良を押し倒してしまった!? 幸か不幸か何も覚えていない春陽に、全てなかったことにしてくれた千木良。だけど、不意打ちのように甘やかしてくる彼の思わせぶりな言動に、どうしようもなく心と体が疼いてしまい……。「どうやら私は、かなり独占欲が強い、嫉妬深い男のようだよ」クールな隠れドS上司をうっかりその気にさせてしまったアラサー女子の、甘すぎる受難!


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。



イケメン彼氏は警察官!甘い夜に私の体は溶けていく。
すずなり。
恋愛
人数合わせで参加した合コン。
そこで私は一人の男の人と出会う。
「俺には分かる。キミはきっと俺を好きになる。」
そんな言葉をかけてきた彼。
でも私には秘密があった。
「キミ・・・目が・・?」
「気持ち悪いでしょ?ごめんなさい・・・。」
ちゃんと私のことを伝えたのに、彼は食い下がる。
「お願いだから俺を好きになって・・・。」
その言葉を聞いてお付き合いが始まる。
「やぁぁっ・・!」
「どこが『や』なんだよ・・・こんなに蜜を溢れさせて・・・。」
激しくなっていく夜の生活。
私の身はもつの!?
※お話の内容は全て想像のものです。現実世界とはなんら関係ありません。
※表現不足は重々承知しております。まだまだ勉強してまいりますので温かい目で見ていただけたら幸いです。
※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・・すみません。
では、お楽しみください。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















