お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説

惑星保護区
ラムダムランプ
SF
この物語について
旧人類と別宇宙から来た種族との出来事にまつわる話です。
概要
かつて地球に住んでいた旧人類と別宇宙から来た種族がトラブルを引き起こし、その事が発端となり、地球が宇宙の中で【保護区】(地球で言う自然保護区)に制定され
制定後は、他の星の種族は勿論、あらゆる別宇宙の種族は地球や現人類に対し、安易に接触、交流、知能や技術供与する事を固く禁じられた。
現人類に対して、未だ地球以外の種族が接触して来ないのは、この為である。
初めて書きますので読みにくいと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

願いを叶えるだけの僕と人形
十四年生
SF
人がいいだけのお人よしの僕が、どういうわけか神様に言われて、人形を背中に背負いながら、滅びたという世界で、自分以外の願いを叶えて歩くことになったそんなお話。

呆然自失のアンドロイドドール
ショー・ケン
SF
そのアンドロイドは、いかにも人間らしくなく、~人形みたいね~といわれることもあった、それは記憶を取り戻せなかったから。 ある人間の記憶を持つアンドロイドが人間らしさを取り戻そうともがくものがたり。

バッドモーニングトキオシェルター
みらいつりびと
SF
SF短編です。全4話。
2000個の冬眠カプセルが並んでいるトキオシェルターで目覚めたのは僕とヤンデレの元カノだけだった……。
バッドエンドがだめな人は読まない方がいいです。

地球人類永久不滅計画 ~機械仕掛けの『NE-1097』~
クライン・トレイン
SF
地球人類の永久不滅計画が実施されていた
それは長きにわたる資本主義の終焉に伴う技術進化の到来であった
そのオカルトティックと言われていた現象を現実のものとしたのは
博士号を持った博士たちであった
そしてそんな中の一人の博士は
技術的特異点など未来観測について肯定的であり楽観主義者であった
そんな中
人々の中で技術的特異点についての討論が成されていた
ドローン監視社会となった世界で人間の為の変革を成される
正にそのタイミングで
皮肉な研究成果を生み出す事実を博士も人類も今だ知らなかった
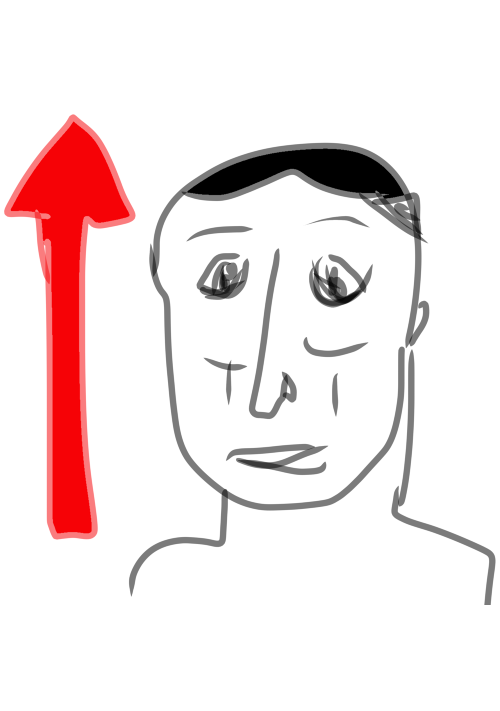
もうダメだ。俺の人生詰んでいる。
静馬⭐︎GTR
SF
『私小説』と、『機動兵士』的小説がゴッチャになっている小説です。百話完結だけは、約束できます。
(アメブロ「なつかしゲームブック館」にて投稿されております)

トライアルズアンドエラーズ
中谷干
SF
「シンギュラリティ」という言葉が陳腐になるほどにはAIが進化した、遠からぬ未来。
特別な頭脳を持つ少女ナオは、アンドロイド破壊事件の調査をきっかけに、様々な人の願いや試行に巻き込まれていく。
未来社会で起こる多様な事件に、彼女はどう対峙し、何に挑み、どこへ向かうのか――
※少々残酷なシーンがありますので苦手な方はご注意ください。
※この小説は、小説家になろう、カクヨム、アルファポリス、エブリスタ、novelup、novel days、nola novelで同時公開されています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















