13 / 49
合コン
しおりを挟む
薄暗い店内。間接照明ばかりで、メニューが良く見えない。要領よく安藤が注文するのに感心しつつ、私はとりあえずビールを頼んだ。
「それじゃあ、とりあえずカンパーイ!」
言葉に反してさほど楽しくなさそうな声で、宴は始まった。
「小野さん、何か趣味とかあるの?」
「小野さん、……」
「あ、あの、きむ……」
「夏美ちゃん、……」
集まっているのは、男四人に女四人。私と加賀見氏、小野さん以外は、安藤がどこからか集めてくれたらしい。
よくもまあ、一週間ちょっとで諸々の手配をしてくれたものだ。私などこの一週間、ロクなことをしていない。
話しかけようとする加賀見氏を遮っているのは、スーツを着込んだ若い男と、ラフな格好のこれまた若い男。世で言うイケメン、と言うにはいささか判断に迷うが、少なくとも私と加賀見氏に比べれば見目はいいだろう。安藤が引き立て役に呼ばれた、と怒っていたのが今ならわかる気もする。
同じく安藤の呼んだ女性二人は、ブス姫に比べればまあいいが、小野さんとは比較対象にもならない。先から男どもが小野嬢にしか食いついていないことはこの場の誰もが知っており、安藤に呼ばれた女二人は時折、すべての男を掌中に収めた小野さんを睨んでは酒をあおっている。
楽しくはないな。ビールのグラスを二つ空けた私の感想はそれくらいだった。こんなものの為に貴重な時間を割くだなんて、どうかしている。これなら、まだゲームでもやっていた方がマシだ。
「だから言ったのに」
思わずEoBのアイコンをタップしたところで安藤に声を掛けられた。
「ちょっと先輩、いくらなんでもこんなとこでまでゲームやりはじめないでくださいよ」
「ああ、悪い」
そう言って画面を消したが、ちっとも悪いとは思っていない。その態度が明らかだったのだろう、安藤はさらにたたみかけてきた。
「あの女の人がエラなんとかってゲームにいるかもって、期待してるんでしょ。エーオースとか言う変な女の人」
くだを巻く安藤の声が思わず大きくて、一瞬周りの人々の視線がこちらに向いた。小野さんに熱中だった男ども――むろん先生もだ――が何事かと目を向けてきたが、すぐにその興味は目の前の美女に戻っていく。
だが悲しいかな、先生の熱視線は、小野嬢の顔面にまるで見えないバリアがあるかのようにはじかれてしまう。 つまり、見向きもされていないのだ。
「ほら、あんなんじゃ余計虚しいだけじゃないですか、加賀見さん。それどころか他の人まで巻き込んで」
隣でひたすら飯と酒をかき込んでいる女二人を眺めながら、安藤がため息まじりに言った。
「無理言って呼んだんです、私の友達。男どもは小野さんの名前を出したらすぐ釣れたんですけど」
「けどよく小野さんを呼び出せたな」
「あれでも、エリートなんですよ」
ちら、と安藤がデレデレ顔の男どもを見た。「本庁から出向してるんです」
「出向?左遷の間違いじゃないのか?」
「それでもエリートには違いないですから。県警の人間に比べりゃ、そりゃあ稼いでるだろうし」
「それでまんまと来てくれたってわけか」
「そ。うまいエサでおびき寄せないと」
ぐびぐびとカシオレを飲み干すと、安藤が店員にお代わりを注文する。
「先輩も何か飲みますか?」
「じゃあ、ビールを」
運ばれてきた酒と、気を利かせて追加で頼んでくれたのだろう枝豆をつまみ、私は反芻する。
「エサ、ねぇ」
私や先生は、エサにすらならないというわけか。
「でもこんな出来レースに呼ばれて誰が楽しいと思います?ほんと、このツケは重いですからね」
安藤が頬を膨らませてなにやら文句を言っているが、河豚がパクパク空気を吐いているようにしか見えない。
「わかってるよ、ちゃんとツケは支払うから」
そのツケの原因である先生は、取りつく島もなくただただ小野さんだけを見つめている。
「しかし、恋は盲目とはよく言ったもんだな」
三杯目のビールを胃に流し込みながら、私は悪態をつく。「本当に周りが見えなくなるんだな」
「先輩はないんですか、そういう経験」
果敢に挑戦しては取り巻きどもに弾かれる、哀れな先生の勇姿をつまみに飲んでいた私は、あれといっしょにしてくれるなとばかりに返した。
「あるわけないだろ」
「嘘ばっかり!小野さんと言い、こないだの相談の人と言い、先輩はすぐ見ために騙されて鼻の下伸ばしてるじゃないですかぁ」
酔っぱらい始めているのか、安藤の声が大きくなる。けれどその騒がしさにもかまわず、私を除いた男どもは未だに小野さんに群がっている。
「所詮男なんてそんなもんなんだよ、ミキ」
「そうそう、身分不相応なくせに、自分は美女を手に入れられるって勘違いして生きてる幸せもんなんだから」
安藤の隣に並ぶ友人二人が、憐れむような目で一斉に私の方を見る。最初にそれぞれ自己紹介してもらったものの、名前はもう忘れてしまった。
こちらも飲み食いするしかすることがないからか、すでにだいぶ出来上がってしまっている。
「アンタだって見た目はまあまあだけど、自分より小さい男なんて願い下げだもん」
「ねぇ。こんな小さいのが隣にいて、釣合取れると思ってんの」
いくら友人とは言え、友人の先輩にずいぶんとな暴言だな。ムッとしながらビールをあおる。数合わせに来てもらった礼を述べるのも忘れて、私は憤慨した表情で安藤の隣の女どもを睨んだ。
そういうあんたたちは、性格ブスだから男に相手にしてもらえないんじゃないのか。
「ちょっと言われただけであれだもん、器の小さな男よねぇ」
「ほんと、つまんないの」
「ナツコにユウナ、これでも私の先輩なんだからやめてよ」
安藤が今更に援護に入るが、遅すぎる。それになんだ、これでもって。
「まあでも、確かにミキとはお似合いかもね」
口の端をゆがめて、ナツコだかユウナだかが言う。
「職場でも仲良しなんでしょ?一緒に合コン来るくらいだもん。いっそのこと付き合っちゃえば」
「はぁ?」
思わず大きな声が出た。ドン、とグラスを置いた衝撃に、さすがの取り巻きとその中心人物もこちらを振り向いた。
「どうしたんだ、リンドウ君」
急に目が覚めたかのような表情で、先生が私を見ている。
「少し、飲みすぎなんじゃないのか」
「別に、俺は大丈夫……」
小野さんまで怪訝そうな顔でこちらを見てくるものだから、気まずさを覚えて言葉を続けた。「いや、少し飲みすぎたみたいで。ちょっと」
立ち上がると、いつもより足もとがふらついた気がした。確かに私は飲みすぎたらしい。フラフラと歩く私を心配して、なぜだか先生が付いてきた。
「ああ、先生。俺は大丈夫ですから、ほらせっかく小野さんを呼んだんです、一緒に」
「いや、もういいんだ。それより、歩けるか?」
背の高い先生に、なかば引きずられる形で私たちは外へと出た。薄暗い店内と打って変わって、逆に外のネオンの方が眩しいくらいだ。店の前の道端に思わずしゃがみ込む。夜風が涼しい。
いくらか、気分がすっきりしてきた。
「すみません、せっかく小野さんに会えたのに、こんな」
「構わないんだ、こうなることは初めからわかっていた」
同じく私の横にしゃがみ込んで、先生が呟いた。
「初めから?俺が酔いつぶれるってことですか」
「違う」
チッチッチ、と変わらずの気障なしぐさで先生が指を振った。
「初めから、私なぞあの美女の相手にされないことは、わかりきっていた」
加賀見さんって、バカなんですか?
私の頭の中に、安藤の声がぐわんぐわんと響く。ああ、確かに馬鹿だったみたいだぞ。
「ならなんで、こんなこと」
「分不相応なことを望んでいるとは重々承知だ」
いつもは湿り気を帯びている声が、やけに乾いている。
「私だって、鏡ぐらいは見るさ」
確かに先生は、四六時中鏡を見ていそうな名前を持っていた。
「そして、自分がどんなだかも知っている」
だがそう言う声は、鏡好きのナルシストの発言には聞こえなかった。
男なんて、勘違いして生きてる幸せ者なんだから。
女どもの声がうるさくて、頭が痛い。
「それでも、もう一目会いたかったんだ。だから、これで満足だ」
相手にもされなかったのに?その言葉が喉までせりあがって、私は軽い吐き気と共にそれを飲み込んだ。
「小野さんは、たぶん悪い人じゃないんだとは思います」
先生の顔を見て言える自信がなくて、私はうつむいて口を開いた。
「ちょっと、数合わせに呼んだ男どもが、思ったよりうるさくて」
こんなことなら、合コン形式ではなくて、一対一で会せてやればよかったのではなかったろうか。そんな後悔が頭をよぎった。
「構わないんだ。面と向かって、彼女と向き合う自信なぞ、最初からなかった。だから、これでいいんだ」
そんなものなのだろうか。あまりに諦めのいい先生に対し、先生に声すら掛けなかった小野さんを、嫌な女だと思い始めている私がいた。安藤の被害妄想ではなくて、小野嬢の本性はあんなものなのだろうか。
「私の要望に応えてくれて、感謝する」
ならばいっそ、この純真な男に、意地の悪い女が取り入らなかったことを感謝すべきなのだろうか。そんなことを思えるほどには、頭がすっきりしてきた。今は何時なのだろう。ジャケットの内ポケットからスマホを取り出したところで、先生に声を掛けられた。
「君もやっているのか?」
そう言われて、はじめ何を指しているのかわからなかった。
「何を?」
「その、ゲームだ」
安藤が騒いでいたのを聞いていたのか。
「エーオースがゲームの中に手がかりがあるかもしれないって、私を誘ったんです。先生もやってるんですか?」
「いや。職場の人間がやっていたので気になって。それよりエーオースと言うのは?」
「ゲームの中で蜂蜜男を殺してしまったかも、とか言ってきた女です。でも彼女より、蜂蜜男と知り合いらしいメリッサの方が怪しい」
「メリッサ?」
「ピンクの髪の、見た目は小さい女の子です。けどあれの中身は年増だな」
「いいじゃないか、仮想世界でならなんにでも姿を変えられる。しかし、そろそろ冷えてきたな」
先生が両手で身体を抱きしめるしぐさをした。
「近いうちに骨を返そう」
腰を上げると、先生が私に手を差し伸べて言った。
「次の日曜。前回は新宿まで来てくれただろう、だから今度は私がそちらにお邪魔しようと思うのだが」
「こちらに?」
今回だって、都内から甲府まで来てもらった手前、何度も来させるのは申し訳ない気がした。「いいですよ、もともと私が無理を言ったんですから。私がそちらに」
「お、ようやくシャンとしてきたな、リンドウ刑事」
「だから、刑事はやめてください」
本当に、あの席で刑事呼ばわりされずに済んでよかった。胸をなでおろす私を見下ろして、先生が続けた。
「行きたい場所があるんだ」
「観光ですか?大したものはないけどなぁ。どこがいいですか?」
「樹海」
「ああ、何とか氷穴とか」
「違う。私が行きたいのは、遺体の発見現場だ」
この意外な発言に、私の目がいよいよ覚めた。
「でも、樹海ですよ」
「なに、緯度と経度がわかれば怖くはない。樹海でコンパスが効かないだなんていうのはただの都市伝説だからな」
では日曜は空けておいてくれたまえ、まあ君のことだから、初めから予定などないだろうが。そう嫌味なセリフを言い残し、先生は店内に戻って行ってしまった。そして、今度は入れ替わりに安藤がやってきた。手には私の鞄を持っている。
「なんだ、もうお開きか?」
荷物を受け取りながら、私は財布から金を出す。
「いくらだ?」
「先輩の分も立て替えてあります。一万円で」
「一万?そんなに飲んだか?」
「何言ってるんですか先輩。合コンなんですから、費用は男性が持ってくれないと」
一万出してこのザマか。しかも、小野嬢だけではなく、あの性格ブス二人の金も含まれていると思うと腹立たしかった。
「結局、あの若い男の子たちも小野さんに相手にされなかったみたいで」
ふふ、と安藤は鼻で笑っている。「ああやって、いろんな男にちやほやさせておいて、突き放すのがあの人の趣味なんですよ」
「嫌な趣味だな」
「そ。言った通りでしょう?」
「ああ。それに、加賀見先生は馬鹿を通り越して天才だった」
「天才?」
「とりあえず、彼は満足してくれたらしい。安藤もすまなかった、ありがとう」
「どういたしまして」
澄ました顔で店を出ていく小野さんを見送って――それでも男二人はまだしつこく食いついているようだが、それさえ振り切って彼女は駅に消えて行ってしまった。
残された男二人と、数合わせの女どもも散り散りに行ってしまい、先生だけが「楽しかった、ありがとう」と紳士的な態度で去っていくのを見届けると、私たちだけが残された。
「で、俺は何を君に返せばいいんだ?」
駅へと足を進めながら、隣の安藤に声を掛ける。なんて割に合わない合コンだろう。さて、いくらせびられるだろうか。下手をしたら、次の給料日まで待ってもらわなければならないかもしれない。
だが、隣りで私を見つめる彼女の唇からは、思わぬ言葉が飛び出してきた。
「これから、先輩の家に行ってもいいですか?」
「それじゃあ、とりあえずカンパーイ!」
言葉に反してさほど楽しくなさそうな声で、宴は始まった。
「小野さん、何か趣味とかあるの?」
「小野さん、……」
「あ、あの、きむ……」
「夏美ちゃん、……」
集まっているのは、男四人に女四人。私と加賀見氏、小野さん以外は、安藤がどこからか集めてくれたらしい。
よくもまあ、一週間ちょっとで諸々の手配をしてくれたものだ。私などこの一週間、ロクなことをしていない。
話しかけようとする加賀見氏を遮っているのは、スーツを着込んだ若い男と、ラフな格好のこれまた若い男。世で言うイケメン、と言うにはいささか判断に迷うが、少なくとも私と加賀見氏に比べれば見目はいいだろう。安藤が引き立て役に呼ばれた、と怒っていたのが今ならわかる気もする。
同じく安藤の呼んだ女性二人は、ブス姫に比べればまあいいが、小野さんとは比較対象にもならない。先から男どもが小野嬢にしか食いついていないことはこの場の誰もが知っており、安藤に呼ばれた女二人は時折、すべての男を掌中に収めた小野さんを睨んでは酒をあおっている。
楽しくはないな。ビールのグラスを二つ空けた私の感想はそれくらいだった。こんなものの為に貴重な時間を割くだなんて、どうかしている。これなら、まだゲームでもやっていた方がマシだ。
「だから言ったのに」
思わずEoBのアイコンをタップしたところで安藤に声を掛けられた。
「ちょっと先輩、いくらなんでもこんなとこでまでゲームやりはじめないでくださいよ」
「ああ、悪い」
そう言って画面を消したが、ちっとも悪いとは思っていない。その態度が明らかだったのだろう、安藤はさらにたたみかけてきた。
「あの女の人がエラなんとかってゲームにいるかもって、期待してるんでしょ。エーオースとか言う変な女の人」
くだを巻く安藤の声が思わず大きくて、一瞬周りの人々の視線がこちらに向いた。小野さんに熱中だった男ども――むろん先生もだ――が何事かと目を向けてきたが、すぐにその興味は目の前の美女に戻っていく。
だが悲しいかな、先生の熱視線は、小野嬢の顔面にまるで見えないバリアがあるかのようにはじかれてしまう。 つまり、見向きもされていないのだ。
「ほら、あんなんじゃ余計虚しいだけじゃないですか、加賀見さん。それどころか他の人まで巻き込んで」
隣でひたすら飯と酒をかき込んでいる女二人を眺めながら、安藤がため息まじりに言った。
「無理言って呼んだんです、私の友達。男どもは小野さんの名前を出したらすぐ釣れたんですけど」
「けどよく小野さんを呼び出せたな」
「あれでも、エリートなんですよ」
ちら、と安藤がデレデレ顔の男どもを見た。「本庁から出向してるんです」
「出向?左遷の間違いじゃないのか?」
「それでもエリートには違いないですから。県警の人間に比べりゃ、そりゃあ稼いでるだろうし」
「それでまんまと来てくれたってわけか」
「そ。うまいエサでおびき寄せないと」
ぐびぐびとカシオレを飲み干すと、安藤が店員にお代わりを注文する。
「先輩も何か飲みますか?」
「じゃあ、ビールを」
運ばれてきた酒と、気を利かせて追加で頼んでくれたのだろう枝豆をつまみ、私は反芻する。
「エサ、ねぇ」
私や先生は、エサにすらならないというわけか。
「でもこんな出来レースに呼ばれて誰が楽しいと思います?ほんと、このツケは重いですからね」
安藤が頬を膨らませてなにやら文句を言っているが、河豚がパクパク空気を吐いているようにしか見えない。
「わかってるよ、ちゃんとツケは支払うから」
そのツケの原因である先生は、取りつく島もなくただただ小野さんだけを見つめている。
「しかし、恋は盲目とはよく言ったもんだな」
三杯目のビールを胃に流し込みながら、私は悪態をつく。「本当に周りが見えなくなるんだな」
「先輩はないんですか、そういう経験」
果敢に挑戦しては取り巻きどもに弾かれる、哀れな先生の勇姿をつまみに飲んでいた私は、あれといっしょにしてくれるなとばかりに返した。
「あるわけないだろ」
「嘘ばっかり!小野さんと言い、こないだの相談の人と言い、先輩はすぐ見ために騙されて鼻の下伸ばしてるじゃないですかぁ」
酔っぱらい始めているのか、安藤の声が大きくなる。けれどその騒がしさにもかまわず、私を除いた男どもは未だに小野さんに群がっている。
「所詮男なんてそんなもんなんだよ、ミキ」
「そうそう、身分不相応なくせに、自分は美女を手に入れられるって勘違いして生きてる幸せもんなんだから」
安藤の隣に並ぶ友人二人が、憐れむような目で一斉に私の方を見る。最初にそれぞれ自己紹介してもらったものの、名前はもう忘れてしまった。
こちらも飲み食いするしかすることがないからか、すでにだいぶ出来上がってしまっている。
「アンタだって見た目はまあまあだけど、自分より小さい男なんて願い下げだもん」
「ねぇ。こんな小さいのが隣にいて、釣合取れると思ってんの」
いくら友人とは言え、友人の先輩にずいぶんとな暴言だな。ムッとしながらビールをあおる。数合わせに来てもらった礼を述べるのも忘れて、私は憤慨した表情で安藤の隣の女どもを睨んだ。
そういうあんたたちは、性格ブスだから男に相手にしてもらえないんじゃないのか。
「ちょっと言われただけであれだもん、器の小さな男よねぇ」
「ほんと、つまんないの」
「ナツコにユウナ、これでも私の先輩なんだからやめてよ」
安藤が今更に援護に入るが、遅すぎる。それになんだ、これでもって。
「まあでも、確かにミキとはお似合いかもね」
口の端をゆがめて、ナツコだかユウナだかが言う。
「職場でも仲良しなんでしょ?一緒に合コン来るくらいだもん。いっそのこと付き合っちゃえば」
「はぁ?」
思わず大きな声が出た。ドン、とグラスを置いた衝撃に、さすがの取り巻きとその中心人物もこちらを振り向いた。
「どうしたんだ、リンドウ君」
急に目が覚めたかのような表情で、先生が私を見ている。
「少し、飲みすぎなんじゃないのか」
「別に、俺は大丈夫……」
小野さんまで怪訝そうな顔でこちらを見てくるものだから、気まずさを覚えて言葉を続けた。「いや、少し飲みすぎたみたいで。ちょっと」
立ち上がると、いつもより足もとがふらついた気がした。確かに私は飲みすぎたらしい。フラフラと歩く私を心配して、なぜだか先生が付いてきた。
「ああ、先生。俺は大丈夫ですから、ほらせっかく小野さんを呼んだんです、一緒に」
「いや、もういいんだ。それより、歩けるか?」
背の高い先生に、なかば引きずられる形で私たちは外へと出た。薄暗い店内と打って変わって、逆に外のネオンの方が眩しいくらいだ。店の前の道端に思わずしゃがみ込む。夜風が涼しい。
いくらか、気分がすっきりしてきた。
「すみません、せっかく小野さんに会えたのに、こんな」
「構わないんだ、こうなることは初めからわかっていた」
同じく私の横にしゃがみ込んで、先生が呟いた。
「初めから?俺が酔いつぶれるってことですか」
「違う」
チッチッチ、と変わらずの気障なしぐさで先生が指を振った。
「初めから、私なぞあの美女の相手にされないことは、わかりきっていた」
加賀見さんって、バカなんですか?
私の頭の中に、安藤の声がぐわんぐわんと響く。ああ、確かに馬鹿だったみたいだぞ。
「ならなんで、こんなこと」
「分不相応なことを望んでいるとは重々承知だ」
いつもは湿り気を帯びている声が、やけに乾いている。
「私だって、鏡ぐらいは見るさ」
確かに先生は、四六時中鏡を見ていそうな名前を持っていた。
「そして、自分がどんなだかも知っている」
だがそう言う声は、鏡好きのナルシストの発言には聞こえなかった。
男なんて、勘違いして生きてる幸せ者なんだから。
女どもの声がうるさくて、頭が痛い。
「それでも、もう一目会いたかったんだ。だから、これで満足だ」
相手にもされなかったのに?その言葉が喉までせりあがって、私は軽い吐き気と共にそれを飲み込んだ。
「小野さんは、たぶん悪い人じゃないんだとは思います」
先生の顔を見て言える自信がなくて、私はうつむいて口を開いた。
「ちょっと、数合わせに呼んだ男どもが、思ったよりうるさくて」
こんなことなら、合コン形式ではなくて、一対一で会せてやればよかったのではなかったろうか。そんな後悔が頭をよぎった。
「構わないんだ。面と向かって、彼女と向き合う自信なぞ、最初からなかった。だから、これでいいんだ」
そんなものなのだろうか。あまりに諦めのいい先生に対し、先生に声すら掛けなかった小野さんを、嫌な女だと思い始めている私がいた。安藤の被害妄想ではなくて、小野嬢の本性はあんなものなのだろうか。
「私の要望に応えてくれて、感謝する」
ならばいっそ、この純真な男に、意地の悪い女が取り入らなかったことを感謝すべきなのだろうか。そんなことを思えるほどには、頭がすっきりしてきた。今は何時なのだろう。ジャケットの内ポケットからスマホを取り出したところで、先生に声を掛けられた。
「君もやっているのか?」
そう言われて、はじめ何を指しているのかわからなかった。
「何を?」
「その、ゲームだ」
安藤が騒いでいたのを聞いていたのか。
「エーオースがゲームの中に手がかりがあるかもしれないって、私を誘ったんです。先生もやってるんですか?」
「いや。職場の人間がやっていたので気になって。それよりエーオースと言うのは?」
「ゲームの中で蜂蜜男を殺してしまったかも、とか言ってきた女です。でも彼女より、蜂蜜男と知り合いらしいメリッサの方が怪しい」
「メリッサ?」
「ピンクの髪の、見た目は小さい女の子です。けどあれの中身は年増だな」
「いいじゃないか、仮想世界でならなんにでも姿を変えられる。しかし、そろそろ冷えてきたな」
先生が両手で身体を抱きしめるしぐさをした。
「近いうちに骨を返そう」
腰を上げると、先生が私に手を差し伸べて言った。
「次の日曜。前回は新宿まで来てくれただろう、だから今度は私がそちらにお邪魔しようと思うのだが」
「こちらに?」
今回だって、都内から甲府まで来てもらった手前、何度も来させるのは申し訳ない気がした。「いいですよ、もともと私が無理を言ったんですから。私がそちらに」
「お、ようやくシャンとしてきたな、リンドウ刑事」
「だから、刑事はやめてください」
本当に、あの席で刑事呼ばわりされずに済んでよかった。胸をなでおろす私を見下ろして、先生が続けた。
「行きたい場所があるんだ」
「観光ですか?大したものはないけどなぁ。どこがいいですか?」
「樹海」
「ああ、何とか氷穴とか」
「違う。私が行きたいのは、遺体の発見現場だ」
この意外な発言に、私の目がいよいよ覚めた。
「でも、樹海ですよ」
「なに、緯度と経度がわかれば怖くはない。樹海でコンパスが効かないだなんていうのはただの都市伝説だからな」
では日曜は空けておいてくれたまえ、まあ君のことだから、初めから予定などないだろうが。そう嫌味なセリフを言い残し、先生は店内に戻って行ってしまった。そして、今度は入れ替わりに安藤がやってきた。手には私の鞄を持っている。
「なんだ、もうお開きか?」
荷物を受け取りながら、私は財布から金を出す。
「いくらだ?」
「先輩の分も立て替えてあります。一万円で」
「一万?そんなに飲んだか?」
「何言ってるんですか先輩。合コンなんですから、費用は男性が持ってくれないと」
一万出してこのザマか。しかも、小野嬢だけではなく、あの性格ブス二人の金も含まれていると思うと腹立たしかった。
「結局、あの若い男の子たちも小野さんに相手にされなかったみたいで」
ふふ、と安藤は鼻で笑っている。「ああやって、いろんな男にちやほやさせておいて、突き放すのがあの人の趣味なんですよ」
「嫌な趣味だな」
「そ。言った通りでしょう?」
「ああ。それに、加賀見先生は馬鹿を通り越して天才だった」
「天才?」
「とりあえず、彼は満足してくれたらしい。安藤もすまなかった、ありがとう」
「どういたしまして」
澄ました顔で店を出ていく小野さんを見送って――それでも男二人はまだしつこく食いついているようだが、それさえ振り切って彼女は駅に消えて行ってしまった。
残された男二人と、数合わせの女どもも散り散りに行ってしまい、先生だけが「楽しかった、ありがとう」と紳士的な態度で去っていくのを見届けると、私たちだけが残された。
「で、俺は何を君に返せばいいんだ?」
駅へと足を進めながら、隣の安藤に声を掛ける。なんて割に合わない合コンだろう。さて、いくらせびられるだろうか。下手をしたら、次の給料日まで待ってもらわなければならないかもしれない。
だが、隣りで私を見つめる彼女の唇からは、思わぬ言葉が飛び出してきた。
「これから、先輩の家に行ってもいいですか?」
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

紫陽花旅館の殺人
mihuyu
ミステリー
主人公が仕事の息抜きに「紫陽花旅館」と言う旅館に泊まることになった。だが、その旅館で殺人事件が発生。しかも、旅館に泊まっていた客5人、従業員10人全員にアリバイがあった。
誰が殺したのか、嘘をついているのは誰か
最後は誰もが驚くミステリー!
※この話はフィクションです
実在する「紫陽花温泉旅館」さんとは全く関係ございません。

パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。


アナグラム
七海美桜
ミステリー
26歳で警視になった一条櫻子は、大阪の曽根崎警察署に新たに設立された「特別心理犯罪課」の課長として警視庁から転属してくる。彼女の目的は、関西に秘かに収監されている犯罪者「桐生蒼馬」に会う為だった。櫻子と蒼馬に隠された秘密、彼の助言により難解な事件を解決する。櫻子を助ける蒼馬の狙いとは?
※この作品はフィクションであり、登場する地名や団体や組織、全て事実とは異なる事をご理解よろしくお願いします。また、犯罪の内容がショッキングな場合があります。セルフレイティングに気を付けて下さい。
イラスト:カリカリ様
背景:由羅様(pixiv)
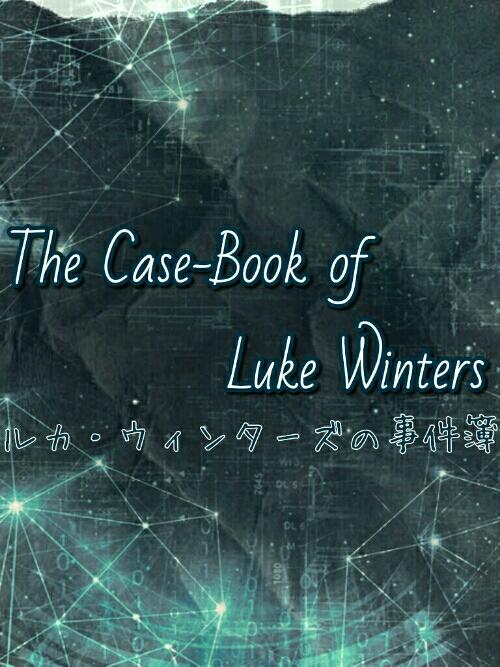
ルカ・ウィンターズの事件簿
一之瀬 純
ミステリー
名門校セティ・クロイツ学園に通う少年ルカ・ウィンターズ。
彼は学園内で起こる様々な事件を解決する探偵だった。
天才少年ルカとその仲間達が巻き起こすストーリーをどうぞご覧下さい。
パロディ作品だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

Star's in the sky with Blood Diamond
汀
ミステリー
The snow of the under world の第二弾。
F県警が震撼した警察官拉致事件から、およそ一年。
捜査第二課に異動した遠野警部は、ある日、古巣であるサイバー犯罪対策課の市川警部に呼び出された。
「特命である人物の警護をしてほしい」と、言われた遠野は……。


鐘楼湖の殺人
大沢敦彦
ミステリー
《あらすじ》
ミステリー作家の阿門正はKADOYAMAの編集者上十石めぐみと鐘楼湖の近くにある旅館「てる」に宿泊。穏やかな環境で執筆に集中することが目的だったが、”死神コンビ”の到来は殺人事件をもたらすのだった。
《登場人物》
・阿門正…ミステリー作家
・上十石めぐみ…KADOYAMA編集者
・大塚國夫…刑事
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















