35 / 38
第19章 森蘭丸
しおりを挟む
(小説名なのに一度も本編で使わないのもどうかと思い、章のタイトルで使ってみました。そうだったかもね?と未来予想図的にこの章をお楽しみ下さい。)
城の屋根や壁に打ち付ける雨音が時折強さを増す。
風を伴う篠突く雨である。
安土城天守閣の三階で久しぶりに信長は政務を執っていた。
家康が都に発った後から、安土は穏やかな日常の姿を取り戻していた。
乱法師は外の様子を見る為に窓を少し空けた。
風向きは逆で雨が吹き込む心配はないが、叩き付ける雨で琵琶湖に水紋がひっきりなしに浮かんでいた。
その琵琶湖の先、安土城から南西の方角に建つ坂本城が霞んで見える。
数日前、襖の細い隙間から目撃した衝撃的な場面が甦る。
今頃光秀は坂本城で戦支度に追われている事だろう。
どのような心境でいるのかと気にはなったが、彼があくまでも寄り添うのは光秀ではなく信長の心である。
足蹴にされた方ではなく、足蹴にした側の精神状態を先ず案じるのは彼ならではであろう。
人は根を詰めれば心身共に疲弊してくる。
信長の家臣でいる事は大変だが、信長である事はもっと大変なのだ。
横並びの家臣達には鬱憤を吐き出せる同じ立場の仲間がいるが、信長には同じ立場の者はいない。
重臣を足蹴にした二日後に、招いた要人達の前で激昂するのは、心身が疲れている証拠なのか。
怒りを示す行動が一時期に集中して発生する傾向は以前からあり、一度怒ると次の日も些細な事で激し易くなる。
「上様、御指示を頂ければ後は私が致しまする。」
今、織田の武将達は四国中国への出陣の準備に追われているが、これは畿内の武将達や三男の信孝に任せておけば良い事で、信長自身が急ぐ必要はない。
出陣とは申せ、数日間本能寺で茶会を催した後、四国中国に赴く予定であるのだから随分優雅な出陣もあったものだった。
確かに二人は急いでいた。
急いでいたのは出陣ではなく上洛の方である。
一月に予定していたが、木曽義政の寝返りにより武田討伐を優先した為、昨年の二月の馬揃え以来、上洛していないという事情にあった。
延期となった分、こちからから持ち掛けて、やや朝廷内に騒動を巻き起こした暦問題も片を付けなければならない。
この国の最高権威である朝廷は形骸化し、信長の力無しでは実政は立ち行かないのだ。
救援としての出馬は急がずとも、上洛後その儘遠征するのだから長い留守の前にどうしても済ませておかなければならない雑事が山積みだった。
殆んどの書状は祐筆に任せているが、信長は必ず目を通して自筆の署名を欠かさない。
今でいう偽造文書が出回ったら大変な事態になってしまう。
偽造を見分ける方法は、黒印、朱印の印章や、花押と呼ばれる署名を図案化したもの等の有無である。
信長は『麟』の文字を図案化した花押を用いており、通常の署名を真似るよりも当然難易度が高くなる。
それと乱法師達奉行の副状も、信頼性を高める役割を担う。
乱法師は常に森乱成利と署名し、その下に花押を記していた。
最も急いでいるのは博多商人島井宗室との会合である。
これまた正月の上洛時に予定されていた茶会が延期されてしまい、今度こそという思いがあった。
上洛というと如何にも帝や公家衆に会う事が第一の目的のように見えるが、島井宗室との茶会こそが信長の心の大半を占めていた。
天下統一まで後少しとなった今、朝廷との細かい決め事や政よりも、毛利討伐後の九州平定に既に目が向いている。
趣味と実益を兼ねた茶会は、天下三肩衝を手中に収め力を誇示し、茶器狂いと言われる収集家としての欲望を満たすだけでなく、九州平定に向け、博多の豪商島井宗室と完全に手を結ぶ契約の場でもあった。
それに家康と穴山梅雪に関連した事情もある。
一向は大坂も観光する手筈となっているが、領主たる身の二人を長く引き留めておく訳にはいかない。
されど遠方から訪ねて来てくれたのだから、名物茶器で最後の持て成しをして別れたいと考えていた。
「うむ、これは後回しで良かろう。先日そなたに伝えた上洛に従う者達の人数はもっと減らそう。人数が多い程、時間が掛かってしまうからな。」
近距離でも、信長の護衛や世話をする者達の頭数を決めるのに必ず一騒動起きる。
護衛と言えば馬廻り衆、世話をする者というと小姓衆だが、その者達にも家臣がいて荷物持ちも含めると結構な人数になってしまうからだ。
「小姓衆だけ二、三十人も連れて行けば良いだろう。此度は侍女も連れて行くからな。」
「小姓衆と侍女でございますか?」
ここで乱法師は信長と己の意識に擦れがある事に気付いた。
自分は護衛としての人員を考えているのに対し、信長は茶会を催すのに必要な人員について考えている事に。
「うむ、それだけいれば白粉共《おしろいども》が押し掛けて来ても手が回るか?」
逆に問われて本能寺での己の立場を考えてみた。
菅屋長頼と猪子兵介は信忠に付いて既に上洛し、長谷川秀一は堺、堀秀政は備中に出陣、矢部家定は四国に出陣する為摂津で待機。
奉行衆は彼等以外にも無論いるが、余り人数を引き連れて行動したくないという信長の意向を尊重すれば、同じ役割を担う者を増やす訳にはいかず、そうすると政務にも携わるのは彼だけになってしまう。
久しぶりの上洛である為、公家衆が献上品を携え押し寄せるのを一人で捌くなど考えただけで頭が痛い。
そんな事よりも茶会の事で頭が一杯なのか、護衛の為の面子を加える事をあまり重視していない事に溜め息を吐いた。
『全く困った御方じゃ。』
「乱、何か申したか?」
心の中で呟いたつもりが、口から洩れてしまっていたらしい。
「いえ、小姓衆だけでは警護の面で手薄ではございませぬか?馬廻り衆は連れていかれないのでございますか?あくまでも人数を増やしたくないと仰せでしたら、少数でも武勇に優れた者を今少しお連れ頂きたいのですが。」
彼の頭に浮かんだのは家康の引き連れて来た面々である。
安土礼賛に当たり、非礼にならぬようにと人数をぎりぎりまで絞り、随行者を余程選び抜いたに違いない。
確か小姓は十数名だったが、それ以外は他国にも名を知られる程の武将が何名も随行していた。
本多忠勝以外にも榊原康政、本多重次や服部半蔵、何れも一騎当千の強者ばかりだ。
無論彼等とて大軍勢に囲まれれば為す術はないが、道中の警護だけならば贅沢な面子であろう。
年若い小姓衆とて武家の子弟である以上、常日頃から武術の鍛練は欠かさない為、信長に危険が及べば十分戦えるとは思う。
だが自分も含め、戦経験のない十代の少年達ばかりの身辺警護では些か手薄な感じは否めない。
いざという時の盾となるだけでなく、確実に敵を倒し活路を開けるような強い手練れを少数精鋭で加えたいと思った。
信長が思案して真っ先に口から出たのは、あまり念頭に無い名前だった。
「弥助を連れて行こう!」
弥助とは、昨年宣教師の奴隷として安土に連れられて来たのを信長が気に入り家臣に取り立てている黒人である。
かなりのお気に入りで武田討伐にも伴っている。
始めは黒い肌と六尺を越える見事な体格に惹かれ、物珍しさが先に立っていたのだが、武術を仕込んだら膂力の強さは並大抵ではなく戦場ではさぞかし活躍してくれそうだと期待していた。
が、彼も実戦経験は無く、乱法師は他の手練れの者達の名前も上げてみた。
高橋虎松、大塚又一郎、伴太郎左衛門、伴正林。
高橋虎松と大塚又一郎は馬廻り衆で武術に長けている上に政務もこなす。
伴太郎左衛門は言わずと知れた甲賀忍者伴家の当主だ。
伴正林も甲賀出身だが忍びではなく、信長の催した相撲会で活躍し、馬廻り衆に取り立てられた剛の者である。
これに下働きの中間衆を加え、五十名程で本能寺に入る事になった。
勿論五十名で出陣しようとしている訳ではない。
軍勢の準備が全て整うまで待っていたら上洛が遅れてしまうからだ。
他の馬廻り衆は後から都に集結させ、武田討伐と同じく、筒井順慶の軍勢を本隊として備中に向かうつもりでいた。
────
「まだ雨が止まぬのか。」
日中でも薄暗く雨は昨日からずっと降り続いている。
厚い雨雲に覆われた曇天続きで、光秀の心は鉛を呑んだように重苦しい。
坂本城の窓から外を見ると、嫌でも目に入るのは巨大な極彩色の安土城だ。
金、銀、朱、青、黒、白。
曇り空であるからこそ忌々しくも余計に目立つ。
築城されたばかりの頃は他の家臣達同様、これ程立派で豪華絢爛、華麗な城は見た事がないと感嘆したものだ。
しかし今はどうだ。
悪趣味でごてごてと、吐き気を催す程威圧的でけばけばしいと感じ、都にある苔むした古寺であれば、雨降りでも風情のある眺めとなろうと考える始末だった。
気の持ちようで同じ物を見てもこれ程感じ方が変わるものか。
安土で受けた屈辱は癒える事なく、腹臣斎藤利三に下された理不尽極まりない命令には頭を抱えるばかりだ。
坂本城に戻った直後、斎藤利三を部屋に呼ぶや思わず抱き締め、光秀は恥も外聞も無く咽び泣いた。
訳を話すと利三も共に怒り泣いてくれた。
互いが互いを思い、己の為ではなく、主の為に利三は稲葉家に戻ると告げた。
戻らねば自刃と脅されたのだから、それしか方法がないのだ、と。
戻っても戻らなくとも大事な腹臣を失う事に変わりなく、それはならぬと光秀が押し留め、他に良い方法はないかと考えあぐね、結局堂々巡りとなり結論が出ない。
そうこうするうちに信長に対する憤りを二人で吐き出し、利三は感極まりとうとうこんな事を口にした。
「自刃する覚悟を持って上様を弑し奉る──」
これを聞いた光秀の顔は青を通り越しさっと白くなった。
「──なっ──何と、とんでもない事を──そのようなそのような恐ろしい事を──」
震えながら部屋中を見回し、誰かに聞かれていないかと慌て取り乱す。
戯れ言であっても、重臣の口から洩れた恐ろしい言葉は口が裂けても光秀には言えない。
身震いしながら利三の顔を見ると、光秀と同じく僅かに青ざめ身を固くしていたが、遥かに落ち着いているのに違和感を覚えた。
『何故、儂よりもこんなに落ち着いて斯様な言葉を吐けるのか。』
その疑問の答えには直ぐに思い至った。
それは利三が陪臣だからだ。
陪臣とは家臣の家臣の事で、光秀自身は信長の直臣となる。
陪臣だからこそ信長に対して畏れ敬う気持ちが光秀よりも薄いのだろう。
陪臣は信長に間接的な恩義はあっても、直接の主である光秀に、より強い忠誠心を抱く。
主と家臣でありながら、同じ家臣という立場を共有するせいか、信長と光秀よりも、光秀と利三の方がより親密な間柄と言えた。
利三が陪臣故に信長を恐れないのだと分かったところで、危険な発言には変わりなかった。
「内蔵助、儂が悪かった。そちを苦しめるような事を申すから、そんな事を……頼む……頼むから、そのような事は二度と申すな。」
「戯れ言ではございませぬ。某も我慢の限界なのです。他に何か良い策があるとでも?」
今、この国の者が恐れて到底言えない事を口にしたせいで利三の瞳は危険な光を帯びていた。
「良い案……良い案……」
己の弱さを責めるような強い視線に射抜かれ、所在なげにぐるぐると部屋中を歩き回る。
「近習の誰かに取り成しを……」
直接信長の怒りに触れる機会が多過ぎる光秀に思い付くのは、精々それくらいしかなかった。
「奉行衆は全て筑前の息が掛かり信用出来ぬと仰せではなかったか!長宗我部討伐も稲葉家の事も、筑前が裏で奉行衆を操り、己に有利になるように手を回したのだと。それに、お乱のような腰巾着が上様の御裁決に異を唱えるとは到底思えぬ。これでも殿は頭を垂れて畳に額を擦り付ければ何とかなるとお思いか?」
利三の意見がどうのと言う前に、陪臣の身でありながら、秀吉や乱法師を呼び捨てにした事に度肝を抜かれた。
辛うじて信長の事は『上様』と呼んでいるのだなと、気迫に押されながらも細かい事に気付いた。
「なれどまさか──真に上様を害し奉る事が出来ると思うておるのか!御目通りの際には刀は預けるのじゃぞ。仮に小刀を持ち込めたとしても、陪臣のそちが上様と二人だけで会うなど許されると思うのか。外出される時には尚の事、護衛の者達が十重二十重に周りを囲み、直ぐに取り押さえられてしまうぞ!頼むから愚かな考えは止せ!」
「…………」
その時、利三は反論しなかった。
しかし、言い返せないからでは無かったのだと光秀は後に思い知る事になる。
─────
備中の秀吉の救援の為の出陣準備は光秀の鬱々とした気持ちとは裏腹に着々と進んでいた。
実は、長宗我部元親は家康が上洛した二十一日の日付で信長に恭順の意を示す書状を出していた。
土佐から送られた書状が仲介役の斎藤利三の手に渡り、更に信長の手に渡るのにはどれくらい日数を要するのか。
江戸時代の飛脚が江戸から京都まで最短三、四日程度掛かったようなので、土佐から安土までなら一週間は掛かりそうである。
五月の末か六月の始めにぎりぎり信長の手に渡ったところで、四国討伐を取り止めにする事はなかっただろう。
光秀は本心と向き合うのも、将来の不安に向き合うのも恐ろしく、出陣の準備に追われている振りをした。
『内蔵助は何と正直なのだろうか。』
ふと羨ましくなった。
戯れ言でも寝言でも、心の内で思い浮かべる事さえ恐ろしい言葉を簡単に口に出すとは。
口に出来る人間の方が鬱憤を溜め込まず、不満を軽減出来るのかもしれないと思った。
光秀は若い頃から群を抜いて頭脳明晰で、何に於いても人に遅れを取った事がない。
学問、兵法、武術、和歌、茶道、あらゆる知識をあっという間に修得し、趣味は嗜み程度で終わらず、自身が師となれる程の腕前だ。
要は表向き温厚に見えても内に秘めた闘志は凄まじく、死ぬ程の負けず嫌い。
人に弱味を見せたり、人前で失態を犯すなど持っての他。
彼は失態を犯し信長の前で震え平伏する者達に常に冷めた視線を注いできた。
何故、熟慮しないのか。
あらゆる場面を想定し、考えた上で行動すれば失敗などないのだ、と。
ところが今や失態を犯した訳ではないのに責められ足蹴にされ、己の立場に始終不安を抱えている有り様だ。
何がどこで狂ってしまったのか──
鼠じゃ──備中にいる小狡い鼠が仕組んだからこのような事態になった。
それを訴えたら足蹴にされた上に讒言を吹き込む悪者にされ、斎藤利三にまで厳しい沙汰が下ってしまったのだ。
あまりにも理不尽。
四国討伐よりも、こうなった全ての元凶たる秀吉の救援を命じられた事に強い憤りを覚え、怒りで胸が詰まり呼吸が苦しくなった。
『儂は何をやっておるのじゃ……何の為に……誰の為に……』
城内の者達は兵糧、武器、弾薬、衣類、陣を設営する為の道具、その他諸々の武具を纏め、出陣の準備で忙しい。
備中に行くのは誰の為じゃ──
断じて小賢しい鼠の為ではない。
では、上様の為か──
己を足蹴にした時の憎々しげな目を思い出し首を振る。
ならば己の為か──
不満を押し殺して命令に従う事により今の地位を守り抜き、或いは更なる出世を──
否、否、否、どれを思い浮かべても切なく虚しい。
備中に出陣し、秀吉を助けたとて今の地位と領地が保証されるとは思えない。
恐らく毛利を平らげたら、安芸に国替えとなり、九州平定に力を注がせるつもりか。
九州は果てしなく遠い。
信州でさえ足軽共は行くのを嫌がったのだ。
無理もない。
自分でさえ嫌だ。
皆が行きたがらない九州を平定したとて、その土地が自分の物になる保証もない。
寧ろ、そこにしか使い途がない己を追い込み働かせ、使い捨てるつもりではないのか。
苦汁を飲み耐えたところで腹臣の斎藤利三まで失ったら、この手の内に何が残るのだろうか。
あの時ああしておけば良かったのにという後悔の念だけか。
頭脳明晰であるが故に先の事を楽観視出来ない上に誇り高く、誰よりも有能な寵臣として扱われてきたからこそ、足蹴にされ相当に心が傷付いていた。
『……それにしても……上様を弑し奉るなど……』
利三の言葉を思い返した。
『あわよくば成し遂げても、取り押さえられ処刑、一族郎党皆殺し──』
恐ろしい想像に身体をぶるっと震わせる。
『結局何も変わらぬ。家督は岐阜の中将様が継いでおられるのじゃから上様御一人を弑し奉っても、儂等の立場が良くなるどころか家族にまで災禍が及ぶ事になる。今の状況を変えたければ、織田家を潰すくらいの覚悟が無ければ無理であろう。 今の織田家と真っ向から戦をして勝てる大名などあろうか。ふう……それ故に皆従うのじゃ。甲斐の武田まで滅び、毛利、上杉、長宗我部、島津、天下平定まで後一歩か……天下が治まれば今以上に上様の御力は強まり、誰も逆らえなくなる。 我慢しているのは儂だけではない……皆、強い者には従うしかない運命なのじゃ。何をされても……何を失っても……』
信長を倒すなど荒唐無稽過ぎると、想像を巡らす事さえ諦めようとしたその時、ふと思った。
『待てよ。皆我慢している。儂だけではない。例えば北条はどうじゃ?佐久間信盛の伜は?教如は?武田や荒木の残党は?上様に万が一の事あらば、四国の長宗我部は間違いなく喜ぶ。毛利や上杉も無論。ひょっとして徳川も……織田家中でも喜ぶ者は数多いるのではないか?皆、必死に献上品を贈り、従順な振りをしているだけで、心は不平不満だらけに違いない。』
そう考えると気持ちが少しだけ軽くなり、信長が死んだら諸国の武将達はどのような動きをするのだろうかと想像してみた。
信忠が生きていたら意味が無い為、信長父子が何者かに暗殺されたという風に状況を深刻に変えて妄想に耽った。
辛い現実を忘れ有り得ない事を夢想するのは楽しいものだ。
現在の武将達の居場所からすると、安土と都に近い坂本城にいる己が圧倒的に有利で小気味良かった。
ただ信忠が死んでも、信雄、信孝は生きており、信忠の幼い息子三法師もいるのだから、結局織田家の天下は変わらない。
家中の中で一歩抜きん出る為には、下手人を捕らえるのが自分でなくてはならない筈だ。
妄想を暫し楽しんだが、考え出した状況では偶然に頼り過ぎていて展開に限界があり、詰まらないと感じた。
知らない誰かが、信長と信忠両名を都合良く葬るなどとは、端から現実離れした状況に過ぎる。
『先ず、誰が、何時、どのような方法で二人を殺めるかを考えなければなるまい。』
光秀は現実を忘れる為に、思う存分怜悧な頭脳を働かせ、最初に時と方法を考えてみた。
『安土におられる時には警護が厳重過ぎて無理じゃな。鷹狩りなど少数で油断している時が望ましいが、中将様が岐阜におられては意味がない。すると上洛時の方が狙い易いのか。何日も都に滞在される事が多いから鷹狩りよりは日にちが選べる。必ず本能寺を宿所とされる筈じゃが、手薄であっても堀に石垣まであるのだから、少数で打ち破るのは無理であろう。しかも悟られれば逃げられてしまうし、京都所司代村井貞勝の邸はすぐ正面じゃ。中将様も共に都にあっても宿所は妙覚寺。別々の場所となると余計に手勢が必要となる。』
梅雨時の憂さ晴らしと言い訳して始め、倒し難い相手をどうやって倒すかを考えてみるだけの、ほんの遊びのつもりだった。
一流の武将として戦略を考えるのを、ただ楽しんでいるだけ──
それが今や、しきりに爪を噛んでいる事さえ気付かぬ程に没頭していた。
徐々に現実味を帯び形を成して行く思考。
何時、どのような方法で、それ等が明確になってくると、次は誰ならば成し得るかという段階に進んで行く。
信長が限られた人数で都に入った時を襲撃するとしても、襲う側の人数が少数では討ち果たせない。
ならば、ある程度の人数、いや、軍勢が都に入る方法はあるのか。
軍勢が都に近付けば、入る前に察知される。
が、それは敵の軍勢の場合だ。
今、都の周辺では皆が出陣の準備をしているから、味方の軍勢が動いたとて怪しむ者はいないだろう。
無論、都周辺にいる武将でなければ無理だ。
西国に行くと見せ掛けて、都に乱入する。
と、すると夜半に動き未明に襲うのが良かろう。
都の近くにいる武将となると、大和の筒井順慶と丹後の細川藤孝が直ぐに思い浮かんだ。
二人とも己の与力で縁戚関係にあり、教養人としても親しい交流がある。
細川藤孝の伜の忠興は娘玉の夫で、筒井順慶の室の一人は、光秀の正室ひろの妹だ。
細川藤孝とは足利義昭の幕臣だった頃からの付き合いで、筒井順慶は信長に臣従を誓う際に間に立ったのが光秀だった。
二人の軍事力と都から近い居城ならば、見咎められた場合の言い訳さえ考えておけば軍を進め、謀反を起こす事は可能であろう。
『謀反』の言葉が頭に浮かんだ途端、さすがに現実に立ち返る。
『……いや、考えてみているだけの気晴らしじゃ……』
気を取り直し思考を続けた。
『二人の動機は何じゃ。うむ、何でも良いか。あくまでも仮定であるからな。それよりも、どちらかが──順慶にしておこう。順慶の方が大軍を動かせる。敵に回したら恐ろしい程の──大和の国衆が従えば間違いなく。順慶が謀反を成功させたら次は朝廷に働きかけ、御綸旨を賜れば簒奪者とは言われなくなる。機内の武将で真っ先に味方しそうなのは──待てよ、儂はどうする?順慶が謀反に成功したら儂は──順慶を討伐するのか?兵部(細川藤孝)は?もし順慶が逸早く兵部を味方に付けたら討伐側に回って勝ち目はあるのか。』
毛利、上杉、長宗我部、織田家に敵対する諸大名に信長を討ち果たしたと書状を送れば、援軍の当てがなくなった秀吉は毛利の大軍の前に為す術はなくなる。
上杉と対峙する柴田勝家は動けず、森長可は信濃の国衆に八つ裂きにされるのが落ちだ。
上野の滝川一益は、謀反を知った北条氏に攻められ直ぐに都には上って来れない。
甲斐の河尻と徳川はどうなるか──
これから、家康は都から堺に向かう予定だ。
信忠は一旦都を離れても、本能寺の茶会に必ず出席するだろう。
信忠と共にいる家康は?
信長父子を共に葬った後、或いは同時に家康も討つ事が出来るかもしれない。
その考えは光秀を興奮させた。
信長父子だけでなく東海の雄家康まで同時に倒せる千載一遇の機会に気付いてしまったからだ。
光秀は、信長が家康を堺遊覧の後、本能寺に信忠と共に呼び寄せるつもりとは知らなかった。
なれど、家康に対する持て成し振りを見れば、十中八九茶会に招くつもりだと確信していた。
家康は脅威だ。
朝廷を取り込めば、機内の武将は順慶に従うだろうが、家康を生かしておいたら上手く関東を制圧し、軍勢を纏め上げ立ち向かってくるだろう。
ここまで考え、ある事に思い至った。
『儂は機内にいる。出陣の準備が調えば丹波亀山城に入る──順慶に敵対するより、従った方が明らかに得策ではないのか。無論、情勢次第じゃが、安土城を占拠し機内さえ制圧すれば──戦わずして従う武将は大勢いる筈じゃ。第一織田家に恨みを持つ者は多い。表向き力に従っているだけじゃからな。何故こんな事を考え始めたのか──そもそも上様が討たれて儂は?』
─────
「上様が参られます。」
安土城内に賜った部屋で、乱法師は献上品に対する中々終わらない礼状書きををしているところだった。
襖の外で小姓に告げられ、どきりとする。
『今宵は参られるとは、特に仰せではなかったのに──』
この時間に来るのだから、朝まで共に過ごすつもりでいるのだろう。
彼は寝衣にすら着替えておらず、初夏に相応しい単の小袖に袴も着けず寛いだ姿であった為、前持って言ってくれれば、あれこれと仕度をしておいたのに、突然ばたばたとそうした準備をするのは、はしたない事なのにと少し不満に思った。
女性のように白粉に紅を指す訳でなくとも、愛でられる側には色々と準備があるのだ。
不満と言っても部屋に来て欲しくないという意味ではなく、信長が私的な目的で部屋を訪れるような場合、乙女にも似た心持ちで少しでも美しく取り繕いたいと思うのは男心も変わらない。
愛しい者の突然の訪れは、どうでも良い相手とは異なる緊張感を生み、そこから蜜のような甘い香りが漂い始める。
無意識のうちに所作や表情が女性のように優しげに和らぎ、乱法師は手を付いて信長を迎えた。
楝色《おうちいろ》(薄い青紫)と白藍《しらあい》の少し波打つ二色の横段模様に、淡い色彩で紫陽花が辻が花で染め抜かれ、夏の虫達が金糸銀糸で刺繍された小袖に、襟元から覗く下に身に付けた真っ白な下着が彼の清楚な風情を引き立てていた。
袴を身に着けていないからとて乱れた感じはしないが、寛いでいた様子を慌てて取り繕う様子が却って好ましく可憐に思えてしまう。
日頃から公の場でも信長は彼に対しては格段に打ち解け笑顔を見せ、声音も明らかに優しげだが、純粋に二人きりの時間を求める場合は更にそこに甘さが加わる。
五年も側に置いても飽く事ない美しい姿に、やはりまだ元服させたくないという気持ちが強く湧き上がってくる。
金山城で突然元服を願い出られた時には、つい強く制してしまったが、彼の庇護者と己を位置付け成長を見守るつもりでいる以上、その時期を考えない訳にはいかない。
だが主という立場以上に只の男として彼を愛する気持ちが勝っている為、金山での一件は聞かなかった事として、すっかり頭の片隅に追いやってしまっていた。
二人きりの私的な空間で、乱法師がつい嫋やかになってしまうのと同じく、信長も彼の肩を抱き滑らかな頬に唇を寄せ、すっかり甘い声音に変わる。
「遅くまで礼状を書いていたのか。細々とした事でそなたも疲れているであろう。」
「あまり時間が経っては非礼になってしまいまする故。」
「そういえば、上洛したら白粉共が進物を持って来るだろうが、全部突き返して良いぞ!」
「全て、でございますか?」
信長が行く所行く所、ともかく献上品の山が積み上げられ取り次ぐ方は休む暇とてない。
献上品を受け取らなくて良ければ大幅に仕事が削減されて楽になる。
つまり受け取った品の目録も付けなくて良いし、礼状も書かなくて済む事になる訳だ。
追従の品々は、大抵権力者信長にとっては目にした物ばかりだ。
贈られる品々が、己の為でない事が歴然としている以上、媚びへつらう公卿達に付き合う時間が勿体無いと考えていた。
以前から下らない前置きや追従を無駄な事と嫌っていたが、殿上人と呼ばれる特に位の高い公卿達の献上品を全て突き返すとは。
久しぶりの上洛間近と、必死に品を見繕っている側はさぞかし面食らうに違いない。
そこが信長らしくはあるが、伝統を重んじ何事もしきたりと言い張り、話しも回りくどく無駄な事に時間を掛けたがる公家と根本的に相容れないところなのだろう。
「ふふふ──進物を返してやったら奴等の顔が白くなるかのう。おお、もう既に白いか。ははは──大分そなたの仕事も楽になるであろう。欲しい物は楢柴肩衝じゃ。もうすぐ手に入る!」
「上様が望まれて御手に入らぬ物は最早この日の本にはないのでございましょう。天下三肩衝が御手元に揃うのを私も早う見たいと存じまする。」
それは天下統一を必ず成し遂げる事を約束するような神器に思え、乱法師も心待ちにしていた。
歴代の天皇が継承してきた三種の神器は有名だが、日本では奇数が縁起良いとされてきた為、膳に載せる料理の数も七五三の形式である。
故に天下三肩衝を三種の神器に見立て、手にした者が天下を取るというように噂する者達もいる。
それは迷信というよりは、力のある者の所に名物が集まるという、必然的な世の流れに過ぎないのかもしれないのだが。
「近衛前久様が太政大臣の官職を辞されたと内府様(近衛信基)より伺いましたが、その──」
確かな答えを得たいと思っている訳ではないのだが、勧修寺晴豊と勅使に対する返答は乱法師にもはっきりしない儘だ。
上洛を迎えれば公卿達は信長の任官について再び言及してくるのではないか。
近衛前久の息子の内府信基は、朝廷側の人間として乱法師に探りを入れてきた。
信長の上洛の目的は、ただ単に中国出陣の寄り道ではないだろう、と。
島井宗室を招いた茶会とて、侘び寂びどころか政治の匂いが憚る事なく漂ってくる。
信長の心中を推し量ってばかりで朝廷は混乱し、近衛前久の辞任は信長に譲る為との見方が大半であった。
はっきりしない態度に右往左往するのは、主導権が完全に信長の手にあるという事を物語っている。
「ふむ、暦が先ず先じゃ。近衛は気を回し過ぎじゃな。太政大臣になる気は全くない。伜の信基にでもくれてやれば良いものを。」
少なくとも、『三職』のうち最も位の高い太政大臣になる気はないらしい事だけは分かった。
官職に就く事をこの先も望んでいないのだろうか。
望めば、帝の地位以外なら太政大臣にさえなれるというのに。
「乱、信基に聞かれたのか?」
「はっきりと聞かれた訳ではないのですが、朝廷の関心事の一つではあるようです。」
「そのうち答えは出す。──それより──」
いきなり信長から伝わる体温を熱く感じ、その先に続く言葉は嫌でも分かった。
「枕が一つしかありませぬ。持って来させるよう……」
「枕など後で良かろう。睦み合うのに必要ない。いっそ儂の手枕で朝まで寝てみるか?」
戯れ言めいているが意外と目は本気だ。
「御手が疲れてしまいましょう。寝衣に着替えて参りますので、御待ち下さいませ。」
すっかり熱くなった信長の身体から逃れ、屏風の後ろに隠れるように入った。
若い乱法師の身体も明らかな変化を伴い熱く火照り始め、少しだけ鎮める時を稼ごうと、ゆっくり帯に手を掛けた。
「あっ──」
後ろから不意に抱き締められ驚きで声を上げる。
乱法師の手に代わり、信長の手が背後から帯に掛かり解き始めた。
「わざわざ着替える必要はなかろうと思うてのう──」
少し焦る乱法師に構わず、帯をほどく音が静かな夜を淫靡に傾けていく。
襟元から差し入れられた手が肌を撫で、優しく愛で始めた。
救いを求めて長い睫毛に縁取られた艶やかな瞳が後ろにさ迷う。
視線を合わせた後、信長は白い首筋を強く吸うと、帯を解き終わった手で小袖の裾を割り囁いた。
「仕方が無い奴じゃ。こんなに、もう……」
耳朶をほんのり赤くする乱法師の反応を楽しみつつ、抱いた儘移動し褥に縺《もつ》れ込んだ。
乱法師の泳ぐ爪先が、褥に広がる美しい柄の小袖に襞を寄せるが、信長の着衣は殆んど乱れていない。
腕に縋り付き、乱法師は何度も啼いた。
互いに精を放った後も余韻を楽しみ戯れ合い、口付けを交わす。
行為が終わると身体を浄めて直ぐに寝てしまう事もあるが、今度こそ寝衣に着替えて褥に臥そうとすると、腕の所に乱法師の頭を載せ、言った通り手枕をしてくれた。
「枕を……」
「面倒じゃから、この儘──で良い──」
結局、手枕をした儘、近頃の多忙で蓄積した疲労には勝てず信長は寝入ってしまった。
主の腕からそっと頭を外し、信長の寝息を聞きながら、彼も眠りに落ちた。
────
「後少し……少しで出陣しなければならなくなる。」
足軽隊、騎馬隊、鉄砲隊、それぞれの隊長から出陣準備の進行状況の報せがある度に光秀の心は重く沈んで行く。
今の光秀の一番の願いは、時を止める事だったのかもしれない。
自身の出陣と信孝軍の四国への渡海を止める事が出来たなら──
斎藤利三の件は考えれば考える程行き詰まってしまう。
那波の件も裁決がまだなのだから、後回しになっているのだろうか。
出陣が近付くにつれ心が暗くなるのは、利三と那波の件は必ず出陣前に裁決が下されると思っているからでもある。
利三が戻ると許しを乞えば一件落着と楽観視は出来ない。
戻ったら戻ったで一悶着ありそうだし、裁決が下る前に戻ると言えば、本当に稲葉家に返さなくてはならなくなる。
光秀は返したくないし、利三も帰りたくない。
故に切腹という選択肢しか許されないのであれば、ぎりぎりの答えとして戻る事を選ぶというのが二人の考えなのだ。
つまり、切腹から緩い処罰に変わるのを待っているというのが正しい。
都での信忠や家康の動きが、手の者や親友の吉田兼和から耳に入ってくる。
次の予定は確か都の清水での能見物らしい。
「呑気なものだ。そろそろ堺に向かうのだろうか。」
本能寺での茶会を催すのに一役買っている光秀が、堺にいる三茶頭達の動きを前もって知るのは訳も無い。
『いつ上様が上洛され本能寺で茶会が催されるのか──そのうち、お乱から報せが届くのか。ひょっとして儂にも同席せよと御命令があるやもしれぬな。島井宗室を招いて楢柴肩衝を手に入れるのは、九州を制圧する為の布石でもあるのだからな。すると──』
「──殿──殿!」
暗い思いの淵に堕ち掛けていた光秀は、鋭く己を呼ぶ声で現に戻った。
そこには心配そうな表情でこちらを見つめる利三の姿があった。
「今、そなたの事や様々な事を考えていた。」
必死に現から逃れようとしても、今一番の悩みの種である利三を前にしては、先日のように架空の戦略を立てて夢想に耽る事も出来ない。
───全ての期限が迫っていた。
「明日には出陣の準備は整ってしまいまする。真に備中に出陣されるおつもりですか?」
光秀の気持ちを痛い程、斟酌《しんしゃく》しているのが伝わってくる。
同時に責められているようにも聞こえ、主でありながら身が縮まる思いがした。
「そうか。それは……皆に、呉々も気を緩めず士気を高め、敵を討ち滅ぼせば備中は遠いが必ずや生きて帰って来れると……」
「くっ!真に殿はそれで良いと思っておられるのか!!!」
利三の怒声に光秀の身体がびくっと跳ねた。
「今の儘で良くなければ、どうすれば良いと?前に申していた上様を害し奉るという愚挙を……命じよというのか?」
光秀の頭の中には、先日筒井順慶を仮の謀反人として立てた戦略が浮かんでいた。
「我等をこのような立場に追い込んだ、にっくき筑前守!四国討伐の為の軍勢は着々と準備が進み、来月初めには渡海するでしょう。殿はそれを指をくわえて見ているばかりか、備中に後詰めとして行かねばならぬ屈辱!どう御思いか?備中で毛利と対峙しながら、長宗我部が滅ぼされる戦況を黙って聞いていろと?毛利を討ち滅ぼした後、筑前の得意気な顔を側で見るなど──某には、いや、側で見る事さえ叶わぬやも知れませぬ。某は備中に行く前に自刃を命じられ──殿!全てを止める事は出来ないやもしれませぬが、内蔵助は乱心したと仰せ下されば殿に害は及びませぬ。無駄に自刃するくらいならば殿の御為に死にとうござる。」
斎藤利三の目は赤く血走っていた。
彼は現状をしっかりと見据えている。
悩みに悩み抜き、事を起こすなら今だと──
今、事を起こさねば、僅かな間嵐をやり過ごす事が出来たとしても、やがて呑み込まれ全てを失うかもしれない。
「そんな事は断じてさせぬ!──そちにだけ汚名を着せるような真似は絶対にさせぬ!」
利三の己を思う言葉に身体の内側で焔がめらめらと燃え盛った。
「家臣にここまで言わせるとは。情けない。儂の……儂の力が足りぬばかりに。済まぬ……済まぬ……」
光秀の瞳は涙で濡れていた。
理不尽な事と分かっていながら立ち向かえない情けなさと、大事な家臣を失おうとしているのにどうする事も出来ない悔しさ。
頭の中に筒井順慶の姿が浮かび上がった。
先日夢想した戦略──
あれは順慶ではなく己ではないのか。
「内蔵助、そちにだけ死ねと命じる事は出来ぬ。儂は今の状況を止める、ただ一つの策を考えついたやもしれぬ。だが、それは余りにも恐ろしい……聞いて付いていけぬと判断したら、そちは逃げよ!どこまでも逃げよ!!」
言葉に出すのは恐ろしかった。
一度口にしたら後戻り出来ぬ恐ろしい企て。
分かっていた。
言葉に出すという事は実現可能を意味し、誰にも止められぬ程に加速して行くという事を。
「して、その策とは?」
─────
「御上洛に当たり、随行する者達の名前を書き出しましたので御目通し下さりませ。」
本日は凝った造りの庭園が見える天守閣の御殿で信長は政務を執り行っていた。
安土城はともかく広く部屋はあり余っている。
華やかな襖絵、柱の金銀細工、欄間の複雑な鳥草花の彫刻。
使わないのは勿体無いと、たまに気分転換で部屋を変えていた。
「うむ、これだけいれば取り合えず大丈夫であろう。何も無ければ二十九日に上洛致す。城之助(信忠)にそのように伝えておけ。」
乱法師の手渡した紙に目を通し、指示を出した。
随行する者の中には弟の坊丸、力丸だけではなく、己の家臣として姉の夫で義兄に当たる青木次郎左衛門も加えている。
信長御気に入りの気が利く者達ばかりを選んだが、どちらかというと自分の気に入りの小倉松寿を加える事も忘れてはいなかった。
「明後日には、中将様と浜松様は堺に向かわれるそうでございますが、明日は清水の舞台での能見物とか。 都をすっかり堪能されていらっしゃるようですから、本能寺に参られた時に沢山楽しい御話しが聞けそうでございますね。」
「三河も随分羽を伸ばして楽しんでおるようじゃな。堺でも茶会に酒宴に旨い料理と接待三昧にして引き留めよう。すっかり緩みきった顔を拝むのが楽しみじゃ。何しろ生来の無骨者で、儂と同じ戦ばかりの男であったからのう。」
信長は髭を撫で楽しそうに笑った。
「三七様(信孝)からも書状が届いておりまする。伊賀甲賀雑賀の衆だけではなく、丹波丹後山城からも兵を集められ、凡そ一万四千の兵にて伊勢を発たれ、明後日に安土に御立ち寄りになり軍勢を御覧に入れたいと。」
三男信孝からの報告にまたもや信長は嬉しそうに笑みを浮かべた。
何だかんだ言っても、息子や娘に対しては普通の父親としての愛情を持つ信長である。
嫡男信忠は人品、武勇、知性、父に対する従順さに加え家督を既に譲られている時点で別格だが、稀代の馬鹿息子次男信雄よりは遥かに器が上だと、信孝には期待している様子が窺えた。
「名物の茶器はいつ運び込ませましょうか?大変な御値打ちの茶器ばかり三十八種も。万が一割れてしまうような事があっては大変でございます。慎重に運ばせねばなりませぬが如何なる方法を取るべきかと──」
信長は少し思案してから答えた。
「上洛と同時で良かろう。大事な物であればこそ、儂の側が一番守られておるから安全じゃ。」
という訳で、一つ一つが値が付けられない程の高価な茶器は、小規模な上洛行列と共に荷台で普通に運ばれる事となった。
三十八種の茶器目録を、祐筆楠木長譜に書かせ島井宗室に渡す手筈になっている。
持ち込まれる茶器は特に秘蔵の一品ばかりだ。
信長の自作の小唄『不動行光、つくも髪、人には五郎左、御座候う。』に唄い込まれた御気に入りの珠光茄子。
現在世界に三点しか存在しない曜変天目茶碗は、漆黒の釉に星のような斑文が散り、その回りに青紫の輪が出来、茶碗を掌で傾けると見る角度によって虹色とも玉虫色とも言えるような不思議な色と光の変化が楽しめる、宇宙を閉じ込めたような奇跡の茶器なのだ。
他には、万歳大海の茶入れや、茶室に掛けられる掛け軸として、宗の水墨画家、牧谿《もっけい》のくはいの絵やぬれ烏の絵も持ち込むつもりだ。
「弘法大師の直筆千字文の屏風も部屋に置いたら見応えがあろう。」
弘法大師真蹟千字文とは、かの有名な弘法大師直筆の『千字文』を二曲一双の屏風に仕立てたものだ。
千字文とは、 言うなれば単に子供が漢字を覚える為に重複する事の無い千字を用い書かれた長い漢詩の事である。
ただ、『弘法も筆の誤り』の諺を生み出す程の能書家の貴重な筆跡である為、侘び寂びを良しとする茶席には、牧谿の水墨画と並び非常に相応しい調度品と言えるだろう。
小姓や侍女等が細心の注意を払い名物茶器を金襴緞子の袋に入れ、何重にも布でくるみ、綿を入れた桐箱の中に収めていく。
その様子を眺めながら、ふと思い出したように信長が口を開いた。
「仙は元気に過ごしておるか?」
はっと乱法師は顔を上げた。
仙千代は、同僚小姓に対する子供じみた暴力沙汰を咎められ、小姓の任を解かれた愚弟である。
唐突に信長の口から仙千代の名前が出たので困惑した。
無論仙千代は元気に過ごしている。
だが、小姓を解任されたのは今月の初旬なのに、その儘答えれば反省していないと思われるのではと躊躇う。
乱法師の心配を他所に信長の口調は穏やかで、改めて罪を責めるような素振りは全く感じられなかった。
「仙は私の邸で勉学に励み、写経をしたり、武術の鍛練もしてはおりますが、行く行くは僧侶になると気持ちを固めているようでございます。ただ未だ安土に置いておりますのは──」
「元気ならば良かった。やんちゃ坊主が僧侶になってまた喧嘩致さねば良いが。木魚ではなく、坊主の頭を叩かぬようにと申しておいた方が良いぞ!」
乱法師は大きく包み込むような信長の言葉に涙が零れそうになった。
結果としては厳しい処分ではあるが、仙千代の至らぬ点を父親のように受け止めた上で罰したからこそ、将来を気に掛けてくれているのだと感じたからだ。
いずれは金山に建立中の妙願寺の住職とする事になろうが、安土に置いているのには理由があった。
上杉と睨み合いながら信州統治に力を注ぐ長可に加え、自身と弟の坊丸、力丸は此度中国に出陣する。
毛利は手強い上に、更に九州にまで遠征となったら一体いつ戻って来られるのか、信長の側で十重二十重に守られているとはいえ、戦場に赴く以上油断は出来ない。
ここが末っ子の辛いところだが、折角僧侶になる気でいても、兄達に何かあったら再び強制的に還俗させられる事になる。
『いきなり全員に何か起こるとは思えないが、仙千代とて武家の男子。母上御一人でおられるよりは、いた方が心強い事もあろう。』
という訳で遠征から戻って来るまでは安土に置いておく事にしたのだ。
─────
斎藤利三は光秀の策を聞き力強く頷いた。
「殿はやはりこの内蔵助が惚れ込んだ御方じゃ!これ程見事な策は諸葛孔明とて考え付きますまい。儂の主は殿御一人!全てを変えるならば今じゃ!今しかない!」
光秀は利三の闘志漲る瞳を見て愕然とし、褒められているのにがっかりした。
『と……止めてくれぬのか……』
心の俊巡を吐き出してしまうと、光秀の理知的な頭脳は冷静さを取り戻し、本気で企てを決行する勇気は却って萎んでしまった。
「物見遊山ではないのじゃぞ。知られただけでも処刑されてしまう程の企てなのじゃぞ。そちは分かっておるのか……」
この儘では本当に謀反決行となってしまうと、自分で考え言い出しておきながら焦った。
「無論!儂の愚策と比べて何と見事な!その戦略ならば天下をひっくり返し、殿が信長に代わり天下を治める事も出来ましょうぞ!」
利三の瞳はぎらぎらと輝き、血の気は収まるどころか更に滾《たぎ》り、『信長』と呼び捨てにした事にぞくりと光秀の肌が粟立った。
「……くぅ……真に真にそんな大それた事が成功すると思っておるのか。最早、織田家は天下を取ったも同然。東西南北見渡したとて、う……上様を弑し奉る事が出来る者などおらぬ。いや、上様だけではないのじゃ…中将様も討ち果たし、天下を我が物にしようという企てぞ!朝廷を味方に付けたとて……諸大名が従うであろうか?よしんば成功したとて、その後は簒奪者、謀反人として囲まれ捕らえられ……一族郎党悉く処刑されて終わりではないのか?」
光秀の煮え切らぬ態度に利三は鋭い眼光で言い放った。
「上様とは、誰の事でございますか?」
一瞬、利三が錯乱してしまったのかと光秀はぽかんと口を開けた。
「無論、安土の──」
「ふっふっ笑止!上様は安土になどおられませぬ。真の上様は鞆《とも》においでじゃ。御忘れか?殿や某こそ、真の将軍にお仕えした幕臣であったという事を!簒奪者は信長にござる。畏れ多くも上様を鞆に追いやり、朝廷から将軍職を賜っている訳でもないのに上様などと僭称《せんしょう》し、天下を略奪せんとする不届き者。鞆におられる真の将軍、足利義昭公を奉じ、信長父子を討ち果たし、我等の手で都に御連れ致せば簒奪者どころか殿は英雄にございまする。」
光秀は、その言葉に心が揺れた。
この企てを成功させる為には信長父子の首級を上げるのが先ず第一だが、事実上の支配者が討たれた後、諸大名が誰に従うべきか混乱するのは必至である。
光秀の与力は味方になってくれたとしても、他の大名達は戦況を見て有利な方に付くに決まっている。
討伐後に朝廷に働き掛け、己が新たな支配者である事を世に知らしめるのは勿論だが、何故討ったのかが、『天下を我が物にしたかった』では信長と変わらなくなってしまう。
正直、己も利三も足利義昭に忠誠心など皆無な上、都に戻したからとて今更足利幕府に天下を統べる力があるとは思っていない。
あくまでも大義名分に過ぎないが、ここにきて信長が何の官職にも就いていない事が幸いし、忘れかけていた足利将軍を担ぎ上げ、諸国に将軍の名で書状を発すれば味方する者も増えるに違いない。
将軍義昭にとっても悪い話しではないだろう。
現在の庇護者である毛利が信長に敗北してしまったらと、己の処遇に不安を抱えている筈だからだ。
光秀の推測では、信長が「上様」と呼ばれている以上、将軍職に一旦は任官し、信忠に譲るつもりでいるのではと考えていた。
つまり、信長が正式に朝廷から将軍職を賜れば、足利義昭の官職は剥奪され無効となる。
今の状況を利用するのであれば、信長が任官する前に討たなければならない。
全ての状況が、光秀に強く訴えかけているような気がした。
『時は今──』と。
「畿内の儂の与力、せめて細川父子、筒井順慶には策を話し、味方に引き入れておかねばなるまい。あの二人の力が得られなければ、さすがに儂一人の力では……」
「いいえ!いいえ!それは違いまするぞ!断じて誰にも話してはなりませぬ。数を増やせば足並みが揃わなくなり、必ず尻込みする者が出て参りまする。あの御二人が、策を話したからとて、いきなり安土に駆け込み注進するとは思えませぬが、時は今しかござらぬ。確実に説得し、味方に引き入れるだけの時間がないのでござる。故に、決行は我等だけで──」
光秀ですら、ややもすると迷い尻込みする程の大それた企てなのだ。
いきなり、こんな策を打ち明けて一緒にやりましょうなどと快諾する者など長宗我部、毛利、上杉くらいしかいないであろう。
いや、毛利上杉ですら罠かと疑うに違いない。
当然、明らかな反信長勢力には危険のない範囲で書状を発するべきなのは確かなのだが。
行動を起こすべき最善の時は数日後に迫っている。
今から毛利、上杉、長宗我部、鞆の足利義昭に書状を送ったとて、着く頃には信長父子との戦いは決している。
それに下手に書状を出し、誰かの手に誤って渡り事が露見したら──
「儂一人で……か。家中の者には?どうするのじゃ。何と説明する?主だった者達を説得しなければ。説得出来なかったら?」
「殿、家中の者にもぎりぎりまで話してはなりませぬ。話せば動揺が走り、心弱き者から洩れる危険がありまする。」
利三の言葉は説得力があったが、私的にも親しく縁戚関係でもある与力の力も得ず、敵に書状が届く前に行動を起こさねばならず、己の信頼する重臣達にすら直前まで打ち明けずに決断するのかと思うと身体が嫌でも震えてくる。
しかし神仏の啓示ではないかとすら思える千載一遇の好機。
それに気付いたのは己だけであり、成し遂げ得るのも己だけなのだという高揚感。
「やるのか──やらぬのか──いつやるべきか。出陣の準備は整っている。いつまでも坂本にいれば怪しまれる。吉田兼和から都の状況と信忠の動きも聞けるな。軍勢が都に入る理由を念の為考えておかねばなるまい。まだ亀山には向かわぬ。今少し動きがあってからじゃ。こちらにとって良い動きがあるのを待つ──」
────
「上様、都におられる中将様から書状を頂きました。」
「何と書いてある?」
今日は僅かに晴れ間が覗き、天守閣の最上階から見える琵琶湖は久しぶりの陽の光を反射して鏡面のように輝いていた。
最上階で政務を行っていては報告に来る家臣達が上がってくるのがさすがに大変なので、本日は二階にいて今は休憩中といったところだ。
甘い物好きの信長は金平糖を一摘まみ口に放り込むと、信忠の書状に目を通す。
その文章は年下の側近に宛てた物としては非常に丁寧な文面であった。
家督を継いだ嫡男信忠ですら実父に直接送らず乱法師に文を宛て取り次いで貰わねばならぬのだから、他の家臣達は尚更気を遣っていた事だろう。
年若くとも、常に信長の側にいて意向や指示を伝える、主と一心同体の彼の特殊な立場を良く物語っている。
『浜松殿と能を見た後、一緒に堺に向かう予定でおりましたが、父上が近々御上洛と御乱から聞いたので、堺には行かず都で御上洛を御待ち致します。』といった内容だった。
乱法師に対する気の遣いようもだが、家康に同行しているのは、そもそも父の命令であるのに、上洛を知ってしまった以上、家康を後回しにしてでも出迎えをしなければという、最高権力者を父に持つ息子の気苦労が伝わってくるようだ。
この選択こそが彼の命を奪う事になろうとは、無論予期出来よう筈もなかった──
────
「堺の千宗易と都の吉田兼和から、同じ内容の報せが届いた。」
「殿、御二人には此度の事は──」
「無論、知らせてなどおらぬ。」
不安に顔を曇らせる利三にきっばりと光秀は言いきった。
恐ろしくないと言えば嘘になる。
真にやる気かと何度も問われれば迷いはきっと生じるだろう。
だが、今の光秀は神仏の加護を信じ、精神状態は落ち着いていた。
知らせは信忠が堺行きを取り止めて都に留まるという内容であった。
千宗易は堺で家康と共に信忠も持て成すつもりでいた為、非常に残念だと書いて寄越した。
わざわざ知らせて来たのは、来る本能寺での茶会に光秀も同席すると思っているからだろう。
吉田兼和は以前から都での大きな出来事は親友の光秀に知らせ、代わりに光秀は安土での動きを兼和に知らせてやっていた。
坂本城と都は近い為、気軽に訪ねて来るのは相変わらずだが、さすがに光秀がこんな大それた企てを内に秘めているとは気付いてはいない。
いくら細川父子や吉田兼和と親しい間柄とはいえ、今打ち明ければ止められるのは分かりきっている。
だが信長父子を討ち果たした暁には、必ずや味方になってくれると信じてはいた。
「──森お乱が信長が二十九日に上洛すると通達してきたようじゃ。」
「……では、いよいよ。」
「うむ。」
光秀と利三の真っ直ぐに見据えた瞳の中には互いの姿が映っていた。
何があっても裏切らない。
地獄に堕ちるのも共にと。
五月二十六日、明智の軍勢は近江の坂本城を出発し、丹波の亀山城を目指した。
────
「上様、立派な軍勢でございますね。あんなに遠くまで続いておりまする。一万以上、いえ、二万はおりますでしょうか?」
天守閣最上階から見下ろしているのは、信長の三男三七信孝が伊勢から率いてきた一万四千余りの軍勢である。
これから摂津に向かう途上、信長に挨拶がてら、軍備えを見て貰おうと安土に参上したのだ。
「ふむ、中々立派な軍勢じゃがまだまだじゃ!三七も総大将として出陣するのじゃから、もっと立派にしてやろうではないか。」
副将に丹羽長秀、他に蜂谷頼隆などの熟練の武将に加え、信長の評価が高い甥の津田信澄も付けてやった。
信孝を支える人材も豪華だが、更に兵馬、兵糧、黄金もたっぷり与え、万全の態勢で伜を送り出す。
「日向守殿は昨日坂本を発たれ、亀山城に既に入られていらっしゃいますが、やはり本能寺には呼ばれるおつもりでございますか?」
ほんの少しだけ信長の顔色を窺うように乱法師が言った。
襖の細い隙間からとはいえ、光秀が足蹴にされた光景はかなり衝撃的だった。
その出来事を実は気にしている事を別の気遣いをしているように、亀山城からだと備中に出陣する光秀にとっては都に戻る形になりますが、と上手く覚られぬように言ったつもりだったが、勘の鋭い信長には伝わってしまったかもしれない。
「無論じゃ!」
答えは異常な程あっさりしていた。
乱法師は仕えて僅か五年にしかならないが、信長を若い頃から知る武将達に言わせると、昔に比べれば随分と丸くなっているそうなのだ。
余程嘗ては鬼のようだったのかと思うが、確かに『圧切り長谷部』で茶坊主の胴を真っ二つに圧し切った現場や、三十代の頃、二条城の建設中、女子の被り物を取ろうとした雑兵の首を一太刀で刎ねる場面に遭遇した者達からすれば、足蹴にしたくらいは可愛いものなのかもしれない。
そのように考えながら、もう一つの確認すべき心配事を思い出した。
「稲葉家から明智家に引き抜かれた、那波と斎藤の件でございますが……」
「それは既に裁決し、菊(堀秀政)から日向守に沙汰済みじゃ!」
「どのような御裁決を下されたのでございますか?」
足蹴にした事よりも実はそちらの方を気に掛けていた。
「那波は稲葉に戻せと命じた!斎藤内蔵助は本来であれば稲葉家に戻るのが筋であるが、今更戻したところで却って争いの火種の素となるやもしれず。戻らねば自刃せよと申し渡した件については、処罰が厳し過ぎると猪子兵介から取り成しがあった為、内蔵助に関しては明智家に留まるのを許す事とした。だが、以後このような事を再び主家、或いは儂の断りなくするような事があれば間違いなく自刃は免れ得ぬとな。そう申し渡した。」
それを聞き、これで憂いなく光秀が備中に出陣出来るだろうと安堵した。
「では、二十九日に御上洛され、翌日には本能寺に御公家衆が大勢参られるかと存じますが、その日には茶会は開かず、六月二日に催されるという事で宜しいでしょうか?日向守殿には、追って私から書状で報せておきまする。」
城の屋根や壁に打ち付ける雨音が時折強さを増す。
風を伴う篠突く雨である。
安土城天守閣の三階で久しぶりに信長は政務を執っていた。
家康が都に発った後から、安土は穏やかな日常の姿を取り戻していた。
乱法師は外の様子を見る為に窓を少し空けた。
風向きは逆で雨が吹き込む心配はないが、叩き付ける雨で琵琶湖に水紋がひっきりなしに浮かんでいた。
その琵琶湖の先、安土城から南西の方角に建つ坂本城が霞んで見える。
数日前、襖の細い隙間から目撃した衝撃的な場面が甦る。
今頃光秀は坂本城で戦支度に追われている事だろう。
どのような心境でいるのかと気にはなったが、彼があくまでも寄り添うのは光秀ではなく信長の心である。
足蹴にされた方ではなく、足蹴にした側の精神状態を先ず案じるのは彼ならではであろう。
人は根を詰めれば心身共に疲弊してくる。
信長の家臣でいる事は大変だが、信長である事はもっと大変なのだ。
横並びの家臣達には鬱憤を吐き出せる同じ立場の仲間がいるが、信長には同じ立場の者はいない。
重臣を足蹴にした二日後に、招いた要人達の前で激昂するのは、心身が疲れている証拠なのか。
怒りを示す行動が一時期に集中して発生する傾向は以前からあり、一度怒ると次の日も些細な事で激し易くなる。
「上様、御指示を頂ければ後は私が致しまする。」
今、織田の武将達は四国中国への出陣の準備に追われているが、これは畿内の武将達や三男の信孝に任せておけば良い事で、信長自身が急ぐ必要はない。
出陣とは申せ、数日間本能寺で茶会を催した後、四国中国に赴く予定であるのだから随分優雅な出陣もあったものだった。
確かに二人は急いでいた。
急いでいたのは出陣ではなく上洛の方である。
一月に予定していたが、木曽義政の寝返りにより武田討伐を優先した為、昨年の二月の馬揃え以来、上洛していないという事情にあった。
延期となった分、こちからから持ち掛けて、やや朝廷内に騒動を巻き起こした暦問題も片を付けなければならない。
この国の最高権威である朝廷は形骸化し、信長の力無しでは実政は立ち行かないのだ。
救援としての出馬は急がずとも、上洛後その儘遠征するのだから長い留守の前にどうしても済ませておかなければならない雑事が山積みだった。
殆んどの書状は祐筆に任せているが、信長は必ず目を通して自筆の署名を欠かさない。
今でいう偽造文書が出回ったら大変な事態になってしまう。
偽造を見分ける方法は、黒印、朱印の印章や、花押と呼ばれる署名を図案化したもの等の有無である。
信長は『麟』の文字を図案化した花押を用いており、通常の署名を真似るよりも当然難易度が高くなる。
それと乱法師達奉行の副状も、信頼性を高める役割を担う。
乱法師は常に森乱成利と署名し、その下に花押を記していた。
最も急いでいるのは博多商人島井宗室との会合である。
これまた正月の上洛時に予定されていた茶会が延期されてしまい、今度こそという思いがあった。
上洛というと如何にも帝や公家衆に会う事が第一の目的のように見えるが、島井宗室との茶会こそが信長の心の大半を占めていた。
天下統一まで後少しとなった今、朝廷との細かい決め事や政よりも、毛利討伐後の九州平定に既に目が向いている。
趣味と実益を兼ねた茶会は、天下三肩衝を手中に収め力を誇示し、茶器狂いと言われる収集家としての欲望を満たすだけでなく、九州平定に向け、博多の豪商島井宗室と完全に手を結ぶ契約の場でもあった。
それに家康と穴山梅雪に関連した事情もある。
一向は大坂も観光する手筈となっているが、領主たる身の二人を長く引き留めておく訳にはいかない。
されど遠方から訪ねて来てくれたのだから、名物茶器で最後の持て成しをして別れたいと考えていた。
「うむ、これは後回しで良かろう。先日そなたに伝えた上洛に従う者達の人数はもっと減らそう。人数が多い程、時間が掛かってしまうからな。」
近距離でも、信長の護衛や世話をする者達の頭数を決めるのに必ず一騒動起きる。
護衛と言えば馬廻り衆、世話をする者というと小姓衆だが、その者達にも家臣がいて荷物持ちも含めると結構な人数になってしまうからだ。
「小姓衆だけ二、三十人も連れて行けば良いだろう。此度は侍女も連れて行くからな。」
「小姓衆と侍女でございますか?」
ここで乱法師は信長と己の意識に擦れがある事に気付いた。
自分は護衛としての人員を考えているのに対し、信長は茶会を催すのに必要な人員について考えている事に。
「うむ、それだけいれば白粉共《おしろいども》が押し掛けて来ても手が回るか?」
逆に問われて本能寺での己の立場を考えてみた。
菅屋長頼と猪子兵介は信忠に付いて既に上洛し、長谷川秀一は堺、堀秀政は備中に出陣、矢部家定は四国に出陣する為摂津で待機。
奉行衆は彼等以外にも無論いるが、余り人数を引き連れて行動したくないという信長の意向を尊重すれば、同じ役割を担う者を増やす訳にはいかず、そうすると政務にも携わるのは彼だけになってしまう。
久しぶりの上洛である為、公家衆が献上品を携え押し寄せるのを一人で捌くなど考えただけで頭が痛い。
そんな事よりも茶会の事で頭が一杯なのか、護衛の為の面子を加える事をあまり重視していない事に溜め息を吐いた。
『全く困った御方じゃ。』
「乱、何か申したか?」
心の中で呟いたつもりが、口から洩れてしまっていたらしい。
「いえ、小姓衆だけでは警護の面で手薄ではございませぬか?馬廻り衆は連れていかれないのでございますか?あくまでも人数を増やしたくないと仰せでしたら、少数でも武勇に優れた者を今少しお連れ頂きたいのですが。」
彼の頭に浮かんだのは家康の引き連れて来た面々である。
安土礼賛に当たり、非礼にならぬようにと人数をぎりぎりまで絞り、随行者を余程選び抜いたに違いない。
確か小姓は十数名だったが、それ以外は他国にも名を知られる程の武将が何名も随行していた。
本多忠勝以外にも榊原康政、本多重次や服部半蔵、何れも一騎当千の強者ばかりだ。
無論彼等とて大軍勢に囲まれれば為す術はないが、道中の警護だけならば贅沢な面子であろう。
年若い小姓衆とて武家の子弟である以上、常日頃から武術の鍛練は欠かさない為、信長に危険が及べば十分戦えるとは思う。
だが自分も含め、戦経験のない十代の少年達ばかりの身辺警護では些か手薄な感じは否めない。
いざという時の盾となるだけでなく、確実に敵を倒し活路を開けるような強い手練れを少数精鋭で加えたいと思った。
信長が思案して真っ先に口から出たのは、あまり念頭に無い名前だった。
「弥助を連れて行こう!」
弥助とは、昨年宣教師の奴隷として安土に連れられて来たのを信長が気に入り家臣に取り立てている黒人である。
かなりのお気に入りで武田討伐にも伴っている。
始めは黒い肌と六尺を越える見事な体格に惹かれ、物珍しさが先に立っていたのだが、武術を仕込んだら膂力の強さは並大抵ではなく戦場ではさぞかし活躍してくれそうだと期待していた。
が、彼も実戦経験は無く、乱法師は他の手練れの者達の名前も上げてみた。
高橋虎松、大塚又一郎、伴太郎左衛門、伴正林。
高橋虎松と大塚又一郎は馬廻り衆で武術に長けている上に政務もこなす。
伴太郎左衛門は言わずと知れた甲賀忍者伴家の当主だ。
伴正林も甲賀出身だが忍びではなく、信長の催した相撲会で活躍し、馬廻り衆に取り立てられた剛の者である。
これに下働きの中間衆を加え、五十名程で本能寺に入る事になった。
勿論五十名で出陣しようとしている訳ではない。
軍勢の準備が全て整うまで待っていたら上洛が遅れてしまうからだ。
他の馬廻り衆は後から都に集結させ、武田討伐と同じく、筒井順慶の軍勢を本隊として備中に向かうつもりでいた。
────
「まだ雨が止まぬのか。」
日中でも薄暗く雨は昨日からずっと降り続いている。
厚い雨雲に覆われた曇天続きで、光秀の心は鉛を呑んだように重苦しい。
坂本城の窓から外を見ると、嫌でも目に入るのは巨大な極彩色の安土城だ。
金、銀、朱、青、黒、白。
曇り空であるからこそ忌々しくも余計に目立つ。
築城されたばかりの頃は他の家臣達同様、これ程立派で豪華絢爛、華麗な城は見た事がないと感嘆したものだ。
しかし今はどうだ。
悪趣味でごてごてと、吐き気を催す程威圧的でけばけばしいと感じ、都にある苔むした古寺であれば、雨降りでも風情のある眺めとなろうと考える始末だった。
気の持ちようで同じ物を見てもこれ程感じ方が変わるものか。
安土で受けた屈辱は癒える事なく、腹臣斎藤利三に下された理不尽極まりない命令には頭を抱えるばかりだ。
坂本城に戻った直後、斎藤利三を部屋に呼ぶや思わず抱き締め、光秀は恥も外聞も無く咽び泣いた。
訳を話すと利三も共に怒り泣いてくれた。
互いが互いを思い、己の為ではなく、主の為に利三は稲葉家に戻ると告げた。
戻らねば自刃と脅されたのだから、それしか方法がないのだ、と。
戻っても戻らなくとも大事な腹臣を失う事に変わりなく、それはならぬと光秀が押し留め、他に良い方法はないかと考えあぐね、結局堂々巡りとなり結論が出ない。
そうこうするうちに信長に対する憤りを二人で吐き出し、利三は感極まりとうとうこんな事を口にした。
「自刃する覚悟を持って上様を弑し奉る──」
これを聞いた光秀の顔は青を通り越しさっと白くなった。
「──なっ──何と、とんでもない事を──そのようなそのような恐ろしい事を──」
震えながら部屋中を見回し、誰かに聞かれていないかと慌て取り乱す。
戯れ言であっても、重臣の口から洩れた恐ろしい言葉は口が裂けても光秀には言えない。
身震いしながら利三の顔を見ると、光秀と同じく僅かに青ざめ身を固くしていたが、遥かに落ち着いているのに違和感を覚えた。
『何故、儂よりもこんなに落ち着いて斯様な言葉を吐けるのか。』
その疑問の答えには直ぐに思い至った。
それは利三が陪臣だからだ。
陪臣とは家臣の家臣の事で、光秀自身は信長の直臣となる。
陪臣だからこそ信長に対して畏れ敬う気持ちが光秀よりも薄いのだろう。
陪臣は信長に間接的な恩義はあっても、直接の主である光秀に、より強い忠誠心を抱く。
主と家臣でありながら、同じ家臣という立場を共有するせいか、信長と光秀よりも、光秀と利三の方がより親密な間柄と言えた。
利三が陪臣故に信長を恐れないのだと分かったところで、危険な発言には変わりなかった。
「内蔵助、儂が悪かった。そちを苦しめるような事を申すから、そんな事を……頼む……頼むから、そのような事は二度と申すな。」
「戯れ言ではございませぬ。某も我慢の限界なのです。他に何か良い策があるとでも?」
今、この国の者が恐れて到底言えない事を口にしたせいで利三の瞳は危険な光を帯びていた。
「良い案……良い案……」
己の弱さを責めるような強い視線に射抜かれ、所在なげにぐるぐると部屋中を歩き回る。
「近習の誰かに取り成しを……」
直接信長の怒りに触れる機会が多過ぎる光秀に思い付くのは、精々それくらいしかなかった。
「奉行衆は全て筑前の息が掛かり信用出来ぬと仰せではなかったか!長宗我部討伐も稲葉家の事も、筑前が裏で奉行衆を操り、己に有利になるように手を回したのだと。それに、お乱のような腰巾着が上様の御裁決に異を唱えるとは到底思えぬ。これでも殿は頭を垂れて畳に額を擦り付ければ何とかなるとお思いか?」
利三の意見がどうのと言う前に、陪臣の身でありながら、秀吉や乱法師を呼び捨てにした事に度肝を抜かれた。
辛うじて信長の事は『上様』と呼んでいるのだなと、気迫に押されながらも細かい事に気付いた。
「なれどまさか──真に上様を害し奉る事が出来ると思うておるのか!御目通りの際には刀は預けるのじゃぞ。仮に小刀を持ち込めたとしても、陪臣のそちが上様と二人だけで会うなど許されると思うのか。外出される時には尚の事、護衛の者達が十重二十重に周りを囲み、直ぐに取り押さえられてしまうぞ!頼むから愚かな考えは止せ!」
「…………」
その時、利三は反論しなかった。
しかし、言い返せないからでは無かったのだと光秀は後に思い知る事になる。
─────
備中の秀吉の救援の為の出陣準備は光秀の鬱々とした気持ちとは裏腹に着々と進んでいた。
実は、長宗我部元親は家康が上洛した二十一日の日付で信長に恭順の意を示す書状を出していた。
土佐から送られた書状が仲介役の斎藤利三の手に渡り、更に信長の手に渡るのにはどれくらい日数を要するのか。
江戸時代の飛脚が江戸から京都まで最短三、四日程度掛かったようなので、土佐から安土までなら一週間は掛かりそうである。
五月の末か六月の始めにぎりぎり信長の手に渡ったところで、四国討伐を取り止めにする事はなかっただろう。
光秀は本心と向き合うのも、将来の不安に向き合うのも恐ろしく、出陣の準備に追われている振りをした。
『内蔵助は何と正直なのだろうか。』
ふと羨ましくなった。
戯れ言でも寝言でも、心の内で思い浮かべる事さえ恐ろしい言葉を簡単に口に出すとは。
口に出来る人間の方が鬱憤を溜め込まず、不満を軽減出来るのかもしれないと思った。
光秀は若い頃から群を抜いて頭脳明晰で、何に於いても人に遅れを取った事がない。
学問、兵法、武術、和歌、茶道、あらゆる知識をあっという間に修得し、趣味は嗜み程度で終わらず、自身が師となれる程の腕前だ。
要は表向き温厚に見えても内に秘めた闘志は凄まじく、死ぬ程の負けず嫌い。
人に弱味を見せたり、人前で失態を犯すなど持っての他。
彼は失態を犯し信長の前で震え平伏する者達に常に冷めた視線を注いできた。
何故、熟慮しないのか。
あらゆる場面を想定し、考えた上で行動すれば失敗などないのだ、と。
ところが今や失態を犯した訳ではないのに責められ足蹴にされ、己の立場に始終不安を抱えている有り様だ。
何がどこで狂ってしまったのか──
鼠じゃ──備中にいる小狡い鼠が仕組んだからこのような事態になった。
それを訴えたら足蹴にされた上に讒言を吹き込む悪者にされ、斎藤利三にまで厳しい沙汰が下ってしまったのだ。
あまりにも理不尽。
四国討伐よりも、こうなった全ての元凶たる秀吉の救援を命じられた事に強い憤りを覚え、怒りで胸が詰まり呼吸が苦しくなった。
『儂は何をやっておるのじゃ……何の為に……誰の為に……』
城内の者達は兵糧、武器、弾薬、衣類、陣を設営する為の道具、その他諸々の武具を纏め、出陣の準備で忙しい。
備中に行くのは誰の為じゃ──
断じて小賢しい鼠の為ではない。
では、上様の為か──
己を足蹴にした時の憎々しげな目を思い出し首を振る。
ならば己の為か──
不満を押し殺して命令に従う事により今の地位を守り抜き、或いは更なる出世を──
否、否、否、どれを思い浮かべても切なく虚しい。
備中に出陣し、秀吉を助けたとて今の地位と領地が保証されるとは思えない。
恐らく毛利を平らげたら、安芸に国替えとなり、九州平定に力を注がせるつもりか。
九州は果てしなく遠い。
信州でさえ足軽共は行くのを嫌がったのだ。
無理もない。
自分でさえ嫌だ。
皆が行きたがらない九州を平定したとて、その土地が自分の物になる保証もない。
寧ろ、そこにしか使い途がない己を追い込み働かせ、使い捨てるつもりではないのか。
苦汁を飲み耐えたところで腹臣の斎藤利三まで失ったら、この手の内に何が残るのだろうか。
あの時ああしておけば良かったのにという後悔の念だけか。
頭脳明晰であるが故に先の事を楽観視出来ない上に誇り高く、誰よりも有能な寵臣として扱われてきたからこそ、足蹴にされ相当に心が傷付いていた。
『……それにしても……上様を弑し奉るなど……』
利三の言葉を思い返した。
『あわよくば成し遂げても、取り押さえられ処刑、一族郎党皆殺し──』
恐ろしい想像に身体をぶるっと震わせる。
『結局何も変わらぬ。家督は岐阜の中将様が継いでおられるのじゃから上様御一人を弑し奉っても、儂等の立場が良くなるどころか家族にまで災禍が及ぶ事になる。今の状況を変えたければ、織田家を潰すくらいの覚悟が無ければ無理であろう。 今の織田家と真っ向から戦をして勝てる大名などあろうか。ふう……それ故に皆従うのじゃ。甲斐の武田まで滅び、毛利、上杉、長宗我部、島津、天下平定まで後一歩か……天下が治まれば今以上に上様の御力は強まり、誰も逆らえなくなる。 我慢しているのは儂だけではない……皆、強い者には従うしかない運命なのじゃ。何をされても……何を失っても……』
信長を倒すなど荒唐無稽過ぎると、想像を巡らす事さえ諦めようとしたその時、ふと思った。
『待てよ。皆我慢している。儂だけではない。例えば北条はどうじゃ?佐久間信盛の伜は?教如は?武田や荒木の残党は?上様に万が一の事あらば、四国の長宗我部は間違いなく喜ぶ。毛利や上杉も無論。ひょっとして徳川も……織田家中でも喜ぶ者は数多いるのではないか?皆、必死に献上品を贈り、従順な振りをしているだけで、心は不平不満だらけに違いない。』
そう考えると気持ちが少しだけ軽くなり、信長が死んだら諸国の武将達はどのような動きをするのだろうかと想像してみた。
信忠が生きていたら意味が無い為、信長父子が何者かに暗殺されたという風に状況を深刻に変えて妄想に耽った。
辛い現実を忘れ有り得ない事を夢想するのは楽しいものだ。
現在の武将達の居場所からすると、安土と都に近い坂本城にいる己が圧倒的に有利で小気味良かった。
ただ信忠が死んでも、信雄、信孝は生きており、信忠の幼い息子三法師もいるのだから、結局織田家の天下は変わらない。
家中の中で一歩抜きん出る為には、下手人を捕らえるのが自分でなくてはならない筈だ。
妄想を暫し楽しんだが、考え出した状況では偶然に頼り過ぎていて展開に限界があり、詰まらないと感じた。
知らない誰かが、信長と信忠両名を都合良く葬るなどとは、端から現実離れした状況に過ぎる。
『先ず、誰が、何時、どのような方法で二人を殺めるかを考えなければなるまい。』
光秀は現実を忘れる為に、思う存分怜悧な頭脳を働かせ、最初に時と方法を考えてみた。
『安土におられる時には警護が厳重過ぎて無理じゃな。鷹狩りなど少数で油断している時が望ましいが、中将様が岐阜におられては意味がない。すると上洛時の方が狙い易いのか。何日も都に滞在される事が多いから鷹狩りよりは日にちが選べる。必ず本能寺を宿所とされる筈じゃが、手薄であっても堀に石垣まであるのだから、少数で打ち破るのは無理であろう。しかも悟られれば逃げられてしまうし、京都所司代村井貞勝の邸はすぐ正面じゃ。中将様も共に都にあっても宿所は妙覚寺。別々の場所となると余計に手勢が必要となる。』
梅雨時の憂さ晴らしと言い訳して始め、倒し難い相手をどうやって倒すかを考えてみるだけの、ほんの遊びのつもりだった。
一流の武将として戦略を考えるのを、ただ楽しんでいるだけ──
それが今や、しきりに爪を噛んでいる事さえ気付かぬ程に没頭していた。
徐々に現実味を帯び形を成して行く思考。
何時、どのような方法で、それ等が明確になってくると、次は誰ならば成し得るかという段階に進んで行く。
信長が限られた人数で都に入った時を襲撃するとしても、襲う側の人数が少数では討ち果たせない。
ならば、ある程度の人数、いや、軍勢が都に入る方法はあるのか。
軍勢が都に近付けば、入る前に察知される。
が、それは敵の軍勢の場合だ。
今、都の周辺では皆が出陣の準備をしているから、味方の軍勢が動いたとて怪しむ者はいないだろう。
無論、都周辺にいる武将でなければ無理だ。
西国に行くと見せ掛けて、都に乱入する。
と、すると夜半に動き未明に襲うのが良かろう。
都の近くにいる武将となると、大和の筒井順慶と丹後の細川藤孝が直ぐに思い浮かんだ。
二人とも己の与力で縁戚関係にあり、教養人としても親しい交流がある。
細川藤孝の伜の忠興は娘玉の夫で、筒井順慶の室の一人は、光秀の正室ひろの妹だ。
細川藤孝とは足利義昭の幕臣だった頃からの付き合いで、筒井順慶は信長に臣従を誓う際に間に立ったのが光秀だった。
二人の軍事力と都から近い居城ならば、見咎められた場合の言い訳さえ考えておけば軍を進め、謀反を起こす事は可能であろう。
『謀反』の言葉が頭に浮かんだ途端、さすがに現実に立ち返る。
『……いや、考えてみているだけの気晴らしじゃ……』
気を取り直し思考を続けた。
『二人の動機は何じゃ。うむ、何でも良いか。あくまでも仮定であるからな。それよりも、どちらかが──順慶にしておこう。順慶の方が大軍を動かせる。敵に回したら恐ろしい程の──大和の国衆が従えば間違いなく。順慶が謀反を成功させたら次は朝廷に働きかけ、御綸旨を賜れば簒奪者とは言われなくなる。機内の武将で真っ先に味方しそうなのは──待てよ、儂はどうする?順慶が謀反に成功したら儂は──順慶を討伐するのか?兵部(細川藤孝)は?もし順慶が逸早く兵部を味方に付けたら討伐側に回って勝ち目はあるのか。』
毛利、上杉、長宗我部、織田家に敵対する諸大名に信長を討ち果たしたと書状を送れば、援軍の当てがなくなった秀吉は毛利の大軍の前に為す術はなくなる。
上杉と対峙する柴田勝家は動けず、森長可は信濃の国衆に八つ裂きにされるのが落ちだ。
上野の滝川一益は、謀反を知った北条氏に攻められ直ぐに都には上って来れない。
甲斐の河尻と徳川はどうなるか──
これから、家康は都から堺に向かう予定だ。
信忠は一旦都を離れても、本能寺の茶会に必ず出席するだろう。
信忠と共にいる家康は?
信長父子を共に葬った後、或いは同時に家康も討つ事が出来るかもしれない。
その考えは光秀を興奮させた。
信長父子だけでなく東海の雄家康まで同時に倒せる千載一遇の機会に気付いてしまったからだ。
光秀は、信長が家康を堺遊覧の後、本能寺に信忠と共に呼び寄せるつもりとは知らなかった。
なれど、家康に対する持て成し振りを見れば、十中八九茶会に招くつもりだと確信していた。
家康は脅威だ。
朝廷を取り込めば、機内の武将は順慶に従うだろうが、家康を生かしておいたら上手く関東を制圧し、軍勢を纏め上げ立ち向かってくるだろう。
ここまで考え、ある事に思い至った。
『儂は機内にいる。出陣の準備が調えば丹波亀山城に入る──順慶に敵対するより、従った方が明らかに得策ではないのか。無論、情勢次第じゃが、安土城を占拠し機内さえ制圧すれば──戦わずして従う武将は大勢いる筈じゃ。第一織田家に恨みを持つ者は多い。表向き力に従っているだけじゃからな。何故こんな事を考え始めたのか──そもそも上様が討たれて儂は?』
─────
「上様が参られます。」
安土城内に賜った部屋で、乱法師は献上品に対する中々終わらない礼状書きををしているところだった。
襖の外で小姓に告げられ、どきりとする。
『今宵は参られるとは、特に仰せではなかったのに──』
この時間に来るのだから、朝まで共に過ごすつもりでいるのだろう。
彼は寝衣にすら着替えておらず、初夏に相応しい単の小袖に袴も着けず寛いだ姿であった為、前持って言ってくれれば、あれこれと仕度をしておいたのに、突然ばたばたとそうした準備をするのは、はしたない事なのにと少し不満に思った。
女性のように白粉に紅を指す訳でなくとも、愛でられる側には色々と準備があるのだ。
不満と言っても部屋に来て欲しくないという意味ではなく、信長が私的な目的で部屋を訪れるような場合、乙女にも似た心持ちで少しでも美しく取り繕いたいと思うのは男心も変わらない。
愛しい者の突然の訪れは、どうでも良い相手とは異なる緊張感を生み、そこから蜜のような甘い香りが漂い始める。
無意識のうちに所作や表情が女性のように優しげに和らぎ、乱法師は手を付いて信長を迎えた。
楝色《おうちいろ》(薄い青紫)と白藍《しらあい》の少し波打つ二色の横段模様に、淡い色彩で紫陽花が辻が花で染め抜かれ、夏の虫達が金糸銀糸で刺繍された小袖に、襟元から覗く下に身に付けた真っ白な下着が彼の清楚な風情を引き立てていた。
袴を身に着けていないからとて乱れた感じはしないが、寛いでいた様子を慌てて取り繕う様子が却って好ましく可憐に思えてしまう。
日頃から公の場でも信長は彼に対しては格段に打ち解け笑顔を見せ、声音も明らかに優しげだが、純粋に二人きりの時間を求める場合は更にそこに甘さが加わる。
五年も側に置いても飽く事ない美しい姿に、やはりまだ元服させたくないという気持ちが強く湧き上がってくる。
金山城で突然元服を願い出られた時には、つい強く制してしまったが、彼の庇護者と己を位置付け成長を見守るつもりでいる以上、その時期を考えない訳にはいかない。
だが主という立場以上に只の男として彼を愛する気持ちが勝っている為、金山での一件は聞かなかった事として、すっかり頭の片隅に追いやってしまっていた。
二人きりの私的な空間で、乱法師がつい嫋やかになってしまうのと同じく、信長も彼の肩を抱き滑らかな頬に唇を寄せ、すっかり甘い声音に変わる。
「遅くまで礼状を書いていたのか。細々とした事でそなたも疲れているであろう。」
「あまり時間が経っては非礼になってしまいまする故。」
「そういえば、上洛したら白粉共が進物を持って来るだろうが、全部突き返して良いぞ!」
「全て、でございますか?」
信長が行く所行く所、ともかく献上品の山が積み上げられ取り次ぐ方は休む暇とてない。
献上品を受け取らなくて良ければ大幅に仕事が削減されて楽になる。
つまり受け取った品の目録も付けなくて良いし、礼状も書かなくて済む事になる訳だ。
追従の品々は、大抵権力者信長にとっては目にした物ばかりだ。
贈られる品々が、己の為でない事が歴然としている以上、媚びへつらう公卿達に付き合う時間が勿体無いと考えていた。
以前から下らない前置きや追従を無駄な事と嫌っていたが、殿上人と呼ばれる特に位の高い公卿達の献上品を全て突き返すとは。
久しぶりの上洛間近と、必死に品を見繕っている側はさぞかし面食らうに違いない。
そこが信長らしくはあるが、伝統を重んじ何事もしきたりと言い張り、話しも回りくどく無駄な事に時間を掛けたがる公家と根本的に相容れないところなのだろう。
「ふふふ──進物を返してやったら奴等の顔が白くなるかのう。おお、もう既に白いか。ははは──大分そなたの仕事も楽になるであろう。欲しい物は楢柴肩衝じゃ。もうすぐ手に入る!」
「上様が望まれて御手に入らぬ物は最早この日の本にはないのでございましょう。天下三肩衝が御手元に揃うのを私も早う見たいと存じまする。」
それは天下統一を必ず成し遂げる事を約束するような神器に思え、乱法師も心待ちにしていた。
歴代の天皇が継承してきた三種の神器は有名だが、日本では奇数が縁起良いとされてきた為、膳に載せる料理の数も七五三の形式である。
故に天下三肩衝を三種の神器に見立て、手にした者が天下を取るというように噂する者達もいる。
それは迷信というよりは、力のある者の所に名物が集まるという、必然的な世の流れに過ぎないのかもしれないのだが。
「近衛前久様が太政大臣の官職を辞されたと内府様(近衛信基)より伺いましたが、その──」
確かな答えを得たいと思っている訳ではないのだが、勧修寺晴豊と勅使に対する返答は乱法師にもはっきりしない儘だ。
上洛を迎えれば公卿達は信長の任官について再び言及してくるのではないか。
近衛前久の息子の内府信基は、朝廷側の人間として乱法師に探りを入れてきた。
信長の上洛の目的は、ただ単に中国出陣の寄り道ではないだろう、と。
島井宗室を招いた茶会とて、侘び寂びどころか政治の匂いが憚る事なく漂ってくる。
信長の心中を推し量ってばかりで朝廷は混乱し、近衛前久の辞任は信長に譲る為との見方が大半であった。
はっきりしない態度に右往左往するのは、主導権が完全に信長の手にあるという事を物語っている。
「ふむ、暦が先ず先じゃ。近衛は気を回し過ぎじゃな。太政大臣になる気は全くない。伜の信基にでもくれてやれば良いものを。」
少なくとも、『三職』のうち最も位の高い太政大臣になる気はないらしい事だけは分かった。
官職に就く事をこの先も望んでいないのだろうか。
望めば、帝の地位以外なら太政大臣にさえなれるというのに。
「乱、信基に聞かれたのか?」
「はっきりと聞かれた訳ではないのですが、朝廷の関心事の一つではあるようです。」
「そのうち答えは出す。──それより──」
いきなり信長から伝わる体温を熱く感じ、その先に続く言葉は嫌でも分かった。
「枕が一つしかありませぬ。持って来させるよう……」
「枕など後で良かろう。睦み合うのに必要ない。いっそ儂の手枕で朝まで寝てみるか?」
戯れ言めいているが意外と目は本気だ。
「御手が疲れてしまいましょう。寝衣に着替えて参りますので、御待ち下さいませ。」
すっかり熱くなった信長の身体から逃れ、屏風の後ろに隠れるように入った。
若い乱法師の身体も明らかな変化を伴い熱く火照り始め、少しだけ鎮める時を稼ごうと、ゆっくり帯に手を掛けた。
「あっ──」
後ろから不意に抱き締められ驚きで声を上げる。
乱法師の手に代わり、信長の手が背後から帯に掛かり解き始めた。
「わざわざ着替える必要はなかろうと思うてのう──」
少し焦る乱法師に構わず、帯をほどく音が静かな夜を淫靡に傾けていく。
襟元から差し入れられた手が肌を撫で、優しく愛で始めた。
救いを求めて長い睫毛に縁取られた艶やかな瞳が後ろにさ迷う。
視線を合わせた後、信長は白い首筋を強く吸うと、帯を解き終わった手で小袖の裾を割り囁いた。
「仕方が無い奴じゃ。こんなに、もう……」
耳朶をほんのり赤くする乱法師の反応を楽しみつつ、抱いた儘移動し褥に縺《もつ》れ込んだ。
乱法師の泳ぐ爪先が、褥に広がる美しい柄の小袖に襞を寄せるが、信長の着衣は殆んど乱れていない。
腕に縋り付き、乱法師は何度も啼いた。
互いに精を放った後も余韻を楽しみ戯れ合い、口付けを交わす。
行為が終わると身体を浄めて直ぐに寝てしまう事もあるが、今度こそ寝衣に着替えて褥に臥そうとすると、腕の所に乱法師の頭を載せ、言った通り手枕をしてくれた。
「枕を……」
「面倒じゃから、この儘──で良い──」
結局、手枕をした儘、近頃の多忙で蓄積した疲労には勝てず信長は寝入ってしまった。
主の腕からそっと頭を外し、信長の寝息を聞きながら、彼も眠りに落ちた。
────
「後少し……少しで出陣しなければならなくなる。」
足軽隊、騎馬隊、鉄砲隊、それぞれの隊長から出陣準備の進行状況の報せがある度に光秀の心は重く沈んで行く。
今の光秀の一番の願いは、時を止める事だったのかもしれない。
自身の出陣と信孝軍の四国への渡海を止める事が出来たなら──
斎藤利三の件は考えれば考える程行き詰まってしまう。
那波の件も裁決がまだなのだから、後回しになっているのだろうか。
出陣が近付くにつれ心が暗くなるのは、利三と那波の件は必ず出陣前に裁決が下されると思っているからでもある。
利三が戻ると許しを乞えば一件落着と楽観視は出来ない。
戻ったら戻ったで一悶着ありそうだし、裁決が下る前に戻ると言えば、本当に稲葉家に返さなくてはならなくなる。
光秀は返したくないし、利三も帰りたくない。
故に切腹という選択肢しか許されないのであれば、ぎりぎりの答えとして戻る事を選ぶというのが二人の考えなのだ。
つまり、切腹から緩い処罰に変わるのを待っているというのが正しい。
都での信忠や家康の動きが、手の者や親友の吉田兼和から耳に入ってくる。
次の予定は確か都の清水での能見物らしい。
「呑気なものだ。そろそろ堺に向かうのだろうか。」
本能寺での茶会を催すのに一役買っている光秀が、堺にいる三茶頭達の動きを前もって知るのは訳も無い。
『いつ上様が上洛され本能寺で茶会が催されるのか──そのうち、お乱から報せが届くのか。ひょっとして儂にも同席せよと御命令があるやもしれぬな。島井宗室を招いて楢柴肩衝を手に入れるのは、九州を制圧する為の布石でもあるのだからな。すると──』
「──殿──殿!」
暗い思いの淵に堕ち掛けていた光秀は、鋭く己を呼ぶ声で現に戻った。
そこには心配そうな表情でこちらを見つめる利三の姿があった。
「今、そなたの事や様々な事を考えていた。」
必死に現から逃れようとしても、今一番の悩みの種である利三を前にしては、先日のように架空の戦略を立てて夢想に耽る事も出来ない。
───全ての期限が迫っていた。
「明日には出陣の準備は整ってしまいまする。真に備中に出陣されるおつもりですか?」
光秀の気持ちを痛い程、斟酌《しんしゃく》しているのが伝わってくる。
同時に責められているようにも聞こえ、主でありながら身が縮まる思いがした。
「そうか。それは……皆に、呉々も気を緩めず士気を高め、敵を討ち滅ぼせば備中は遠いが必ずや生きて帰って来れると……」
「くっ!真に殿はそれで良いと思っておられるのか!!!」
利三の怒声に光秀の身体がびくっと跳ねた。
「今の儘で良くなければ、どうすれば良いと?前に申していた上様を害し奉るという愚挙を……命じよというのか?」
光秀の頭の中には、先日筒井順慶を仮の謀反人として立てた戦略が浮かんでいた。
「我等をこのような立場に追い込んだ、にっくき筑前守!四国討伐の為の軍勢は着々と準備が進み、来月初めには渡海するでしょう。殿はそれを指をくわえて見ているばかりか、備中に後詰めとして行かねばならぬ屈辱!どう御思いか?備中で毛利と対峙しながら、長宗我部が滅ぼされる戦況を黙って聞いていろと?毛利を討ち滅ぼした後、筑前の得意気な顔を側で見るなど──某には、いや、側で見る事さえ叶わぬやも知れませぬ。某は備中に行く前に自刃を命じられ──殿!全てを止める事は出来ないやもしれませぬが、内蔵助は乱心したと仰せ下されば殿に害は及びませぬ。無駄に自刃するくらいならば殿の御為に死にとうござる。」
斎藤利三の目は赤く血走っていた。
彼は現状をしっかりと見据えている。
悩みに悩み抜き、事を起こすなら今だと──
今、事を起こさねば、僅かな間嵐をやり過ごす事が出来たとしても、やがて呑み込まれ全てを失うかもしれない。
「そんな事は断じてさせぬ!──そちにだけ汚名を着せるような真似は絶対にさせぬ!」
利三の己を思う言葉に身体の内側で焔がめらめらと燃え盛った。
「家臣にここまで言わせるとは。情けない。儂の……儂の力が足りぬばかりに。済まぬ……済まぬ……」
光秀の瞳は涙で濡れていた。
理不尽な事と分かっていながら立ち向かえない情けなさと、大事な家臣を失おうとしているのにどうする事も出来ない悔しさ。
頭の中に筒井順慶の姿が浮かび上がった。
先日夢想した戦略──
あれは順慶ではなく己ではないのか。
「内蔵助、そちにだけ死ねと命じる事は出来ぬ。儂は今の状況を止める、ただ一つの策を考えついたやもしれぬ。だが、それは余りにも恐ろしい……聞いて付いていけぬと判断したら、そちは逃げよ!どこまでも逃げよ!!」
言葉に出すのは恐ろしかった。
一度口にしたら後戻り出来ぬ恐ろしい企て。
分かっていた。
言葉に出すという事は実現可能を意味し、誰にも止められぬ程に加速して行くという事を。
「して、その策とは?」
─────
「御上洛に当たり、随行する者達の名前を書き出しましたので御目通し下さりませ。」
本日は凝った造りの庭園が見える天守閣の御殿で信長は政務を執り行っていた。
安土城はともかく広く部屋はあり余っている。
華やかな襖絵、柱の金銀細工、欄間の複雑な鳥草花の彫刻。
使わないのは勿体無いと、たまに気分転換で部屋を変えていた。
「うむ、これだけいれば取り合えず大丈夫であろう。何も無ければ二十九日に上洛致す。城之助(信忠)にそのように伝えておけ。」
乱法師の手渡した紙に目を通し、指示を出した。
随行する者の中には弟の坊丸、力丸だけではなく、己の家臣として姉の夫で義兄に当たる青木次郎左衛門も加えている。
信長御気に入りの気が利く者達ばかりを選んだが、どちらかというと自分の気に入りの小倉松寿を加える事も忘れてはいなかった。
「明後日には、中将様と浜松様は堺に向かわれるそうでございますが、明日は清水の舞台での能見物とか。 都をすっかり堪能されていらっしゃるようですから、本能寺に参られた時に沢山楽しい御話しが聞けそうでございますね。」
「三河も随分羽を伸ばして楽しんでおるようじゃな。堺でも茶会に酒宴に旨い料理と接待三昧にして引き留めよう。すっかり緩みきった顔を拝むのが楽しみじゃ。何しろ生来の無骨者で、儂と同じ戦ばかりの男であったからのう。」
信長は髭を撫で楽しそうに笑った。
「三七様(信孝)からも書状が届いておりまする。伊賀甲賀雑賀の衆だけではなく、丹波丹後山城からも兵を集められ、凡そ一万四千の兵にて伊勢を発たれ、明後日に安土に御立ち寄りになり軍勢を御覧に入れたいと。」
三男信孝からの報告にまたもや信長は嬉しそうに笑みを浮かべた。
何だかんだ言っても、息子や娘に対しては普通の父親としての愛情を持つ信長である。
嫡男信忠は人品、武勇、知性、父に対する従順さに加え家督を既に譲られている時点で別格だが、稀代の馬鹿息子次男信雄よりは遥かに器が上だと、信孝には期待している様子が窺えた。
「名物の茶器はいつ運び込ませましょうか?大変な御値打ちの茶器ばかり三十八種も。万が一割れてしまうような事があっては大変でございます。慎重に運ばせねばなりませぬが如何なる方法を取るべきかと──」
信長は少し思案してから答えた。
「上洛と同時で良かろう。大事な物であればこそ、儂の側が一番守られておるから安全じゃ。」
という訳で、一つ一つが値が付けられない程の高価な茶器は、小規模な上洛行列と共に荷台で普通に運ばれる事となった。
三十八種の茶器目録を、祐筆楠木長譜に書かせ島井宗室に渡す手筈になっている。
持ち込まれる茶器は特に秘蔵の一品ばかりだ。
信長の自作の小唄『不動行光、つくも髪、人には五郎左、御座候う。』に唄い込まれた御気に入りの珠光茄子。
現在世界に三点しか存在しない曜変天目茶碗は、漆黒の釉に星のような斑文が散り、その回りに青紫の輪が出来、茶碗を掌で傾けると見る角度によって虹色とも玉虫色とも言えるような不思議な色と光の変化が楽しめる、宇宙を閉じ込めたような奇跡の茶器なのだ。
他には、万歳大海の茶入れや、茶室に掛けられる掛け軸として、宗の水墨画家、牧谿《もっけい》のくはいの絵やぬれ烏の絵も持ち込むつもりだ。
「弘法大師の直筆千字文の屏風も部屋に置いたら見応えがあろう。」
弘法大師真蹟千字文とは、かの有名な弘法大師直筆の『千字文』を二曲一双の屏風に仕立てたものだ。
千字文とは、 言うなれば単に子供が漢字を覚える為に重複する事の無い千字を用い書かれた長い漢詩の事である。
ただ、『弘法も筆の誤り』の諺を生み出す程の能書家の貴重な筆跡である為、侘び寂びを良しとする茶席には、牧谿の水墨画と並び非常に相応しい調度品と言えるだろう。
小姓や侍女等が細心の注意を払い名物茶器を金襴緞子の袋に入れ、何重にも布でくるみ、綿を入れた桐箱の中に収めていく。
その様子を眺めながら、ふと思い出したように信長が口を開いた。
「仙は元気に過ごしておるか?」
はっと乱法師は顔を上げた。
仙千代は、同僚小姓に対する子供じみた暴力沙汰を咎められ、小姓の任を解かれた愚弟である。
唐突に信長の口から仙千代の名前が出たので困惑した。
無論仙千代は元気に過ごしている。
だが、小姓を解任されたのは今月の初旬なのに、その儘答えれば反省していないと思われるのではと躊躇う。
乱法師の心配を他所に信長の口調は穏やかで、改めて罪を責めるような素振りは全く感じられなかった。
「仙は私の邸で勉学に励み、写経をしたり、武術の鍛練もしてはおりますが、行く行くは僧侶になると気持ちを固めているようでございます。ただ未だ安土に置いておりますのは──」
「元気ならば良かった。やんちゃ坊主が僧侶になってまた喧嘩致さねば良いが。木魚ではなく、坊主の頭を叩かぬようにと申しておいた方が良いぞ!」
乱法師は大きく包み込むような信長の言葉に涙が零れそうになった。
結果としては厳しい処分ではあるが、仙千代の至らぬ点を父親のように受け止めた上で罰したからこそ、将来を気に掛けてくれているのだと感じたからだ。
いずれは金山に建立中の妙願寺の住職とする事になろうが、安土に置いているのには理由があった。
上杉と睨み合いながら信州統治に力を注ぐ長可に加え、自身と弟の坊丸、力丸は此度中国に出陣する。
毛利は手強い上に、更に九州にまで遠征となったら一体いつ戻って来られるのか、信長の側で十重二十重に守られているとはいえ、戦場に赴く以上油断は出来ない。
ここが末っ子の辛いところだが、折角僧侶になる気でいても、兄達に何かあったら再び強制的に還俗させられる事になる。
『いきなり全員に何か起こるとは思えないが、仙千代とて武家の男子。母上御一人でおられるよりは、いた方が心強い事もあろう。』
という訳で遠征から戻って来るまでは安土に置いておく事にしたのだ。
─────
斎藤利三は光秀の策を聞き力強く頷いた。
「殿はやはりこの内蔵助が惚れ込んだ御方じゃ!これ程見事な策は諸葛孔明とて考え付きますまい。儂の主は殿御一人!全てを変えるならば今じゃ!今しかない!」
光秀は利三の闘志漲る瞳を見て愕然とし、褒められているのにがっかりした。
『と……止めてくれぬのか……』
心の俊巡を吐き出してしまうと、光秀の理知的な頭脳は冷静さを取り戻し、本気で企てを決行する勇気は却って萎んでしまった。
「物見遊山ではないのじゃぞ。知られただけでも処刑されてしまう程の企てなのじゃぞ。そちは分かっておるのか……」
この儘では本当に謀反決行となってしまうと、自分で考え言い出しておきながら焦った。
「無論!儂の愚策と比べて何と見事な!その戦略ならば天下をひっくり返し、殿が信長に代わり天下を治める事も出来ましょうぞ!」
利三の瞳はぎらぎらと輝き、血の気は収まるどころか更に滾《たぎ》り、『信長』と呼び捨てにした事にぞくりと光秀の肌が粟立った。
「……くぅ……真に真にそんな大それた事が成功すると思っておるのか。最早、織田家は天下を取ったも同然。東西南北見渡したとて、う……上様を弑し奉る事が出来る者などおらぬ。いや、上様だけではないのじゃ…中将様も討ち果たし、天下を我が物にしようという企てぞ!朝廷を味方に付けたとて……諸大名が従うであろうか?よしんば成功したとて、その後は簒奪者、謀反人として囲まれ捕らえられ……一族郎党悉く処刑されて終わりではないのか?」
光秀の煮え切らぬ態度に利三は鋭い眼光で言い放った。
「上様とは、誰の事でございますか?」
一瞬、利三が錯乱してしまったのかと光秀はぽかんと口を開けた。
「無論、安土の──」
「ふっふっ笑止!上様は安土になどおられませぬ。真の上様は鞆《とも》においでじゃ。御忘れか?殿や某こそ、真の将軍にお仕えした幕臣であったという事を!簒奪者は信長にござる。畏れ多くも上様を鞆に追いやり、朝廷から将軍職を賜っている訳でもないのに上様などと僭称《せんしょう》し、天下を略奪せんとする不届き者。鞆におられる真の将軍、足利義昭公を奉じ、信長父子を討ち果たし、我等の手で都に御連れ致せば簒奪者どころか殿は英雄にございまする。」
光秀は、その言葉に心が揺れた。
この企てを成功させる為には信長父子の首級を上げるのが先ず第一だが、事実上の支配者が討たれた後、諸大名が誰に従うべきか混乱するのは必至である。
光秀の与力は味方になってくれたとしても、他の大名達は戦況を見て有利な方に付くに決まっている。
討伐後に朝廷に働き掛け、己が新たな支配者である事を世に知らしめるのは勿論だが、何故討ったのかが、『天下を我が物にしたかった』では信長と変わらなくなってしまう。
正直、己も利三も足利義昭に忠誠心など皆無な上、都に戻したからとて今更足利幕府に天下を統べる力があるとは思っていない。
あくまでも大義名分に過ぎないが、ここにきて信長が何の官職にも就いていない事が幸いし、忘れかけていた足利将軍を担ぎ上げ、諸国に将軍の名で書状を発すれば味方する者も増えるに違いない。
将軍義昭にとっても悪い話しではないだろう。
現在の庇護者である毛利が信長に敗北してしまったらと、己の処遇に不安を抱えている筈だからだ。
光秀の推測では、信長が「上様」と呼ばれている以上、将軍職に一旦は任官し、信忠に譲るつもりでいるのではと考えていた。
つまり、信長が正式に朝廷から将軍職を賜れば、足利義昭の官職は剥奪され無効となる。
今の状況を利用するのであれば、信長が任官する前に討たなければならない。
全ての状況が、光秀に強く訴えかけているような気がした。
『時は今──』と。
「畿内の儂の与力、せめて細川父子、筒井順慶には策を話し、味方に引き入れておかねばなるまい。あの二人の力が得られなければ、さすがに儂一人の力では……」
「いいえ!いいえ!それは違いまするぞ!断じて誰にも話してはなりませぬ。数を増やせば足並みが揃わなくなり、必ず尻込みする者が出て参りまする。あの御二人が、策を話したからとて、いきなり安土に駆け込み注進するとは思えませぬが、時は今しかござらぬ。確実に説得し、味方に引き入れるだけの時間がないのでござる。故に、決行は我等だけで──」
光秀ですら、ややもすると迷い尻込みする程の大それた企てなのだ。
いきなり、こんな策を打ち明けて一緒にやりましょうなどと快諾する者など長宗我部、毛利、上杉くらいしかいないであろう。
いや、毛利上杉ですら罠かと疑うに違いない。
当然、明らかな反信長勢力には危険のない範囲で書状を発するべきなのは確かなのだが。
行動を起こすべき最善の時は数日後に迫っている。
今から毛利、上杉、長宗我部、鞆の足利義昭に書状を送ったとて、着く頃には信長父子との戦いは決している。
それに下手に書状を出し、誰かの手に誤って渡り事が露見したら──
「儂一人で……か。家中の者には?どうするのじゃ。何と説明する?主だった者達を説得しなければ。説得出来なかったら?」
「殿、家中の者にもぎりぎりまで話してはなりませぬ。話せば動揺が走り、心弱き者から洩れる危険がありまする。」
利三の言葉は説得力があったが、私的にも親しく縁戚関係でもある与力の力も得ず、敵に書状が届く前に行動を起こさねばならず、己の信頼する重臣達にすら直前まで打ち明けずに決断するのかと思うと身体が嫌でも震えてくる。
しかし神仏の啓示ではないかとすら思える千載一遇の好機。
それに気付いたのは己だけであり、成し遂げ得るのも己だけなのだという高揚感。
「やるのか──やらぬのか──いつやるべきか。出陣の準備は整っている。いつまでも坂本にいれば怪しまれる。吉田兼和から都の状況と信忠の動きも聞けるな。軍勢が都に入る理由を念の為考えておかねばなるまい。まだ亀山には向かわぬ。今少し動きがあってからじゃ。こちらにとって良い動きがあるのを待つ──」
────
「上様、都におられる中将様から書状を頂きました。」
「何と書いてある?」
今日は僅かに晴れ間が覗き、天守閣の最上階から見える琵琶湖は久しぶりの陽の光を反射して鏡面のように輝いていた。
最上階で政務を行っていては報告に来る家臣達が上がってくるのがさすがに大変なので、本日は二階にいて今は休憩中といったところだ。
甘い物好きの信長は金平糖を一摘まみ口に放り込むと、信忠の書状に目を通す。
その文章は年下の側近に宛てた物としては非常に丁寧な文面であった。
家督を継いだ嫡男信忠ですら実父に直接送らず乱法師に文を宛て取り次いで貰わねばならぬのだから、他の家臣達は尚更気を遣っていた事だろう。
年若くとも、常に信長の側にいて意向や指示を伝える、主と一心同体の彼の特殊な立場を良く物語っている。
『浜松殿と能を見た後、一緒に堺に向かう予定でおりましたが、父上が近々御上洛と御乱から聞いたので、堺には行かず都で御上洛を御待ち致します。』といった内容だった。
乱法師に対する気の遣いようもだが、家康に同行しているのは、そもそも父の命令であるのに、上洛を知ってしまった以上、家康を後回しにしてでも出迎えをしなければという、最高権力者を父に持つ息子の気苦労が伝わってくるようだ。
この選択こそが彼の命を奪う事になろうとは、無論予期出来よう筈もなかった──
────
「堺の千宗易と都の吉田兼和から、同じ内容の報せが届いた。」
「殿、御二人には此度の事は──」
「無論、知らせてなどおらぬ。」
不安に顔を曇らせる利三にきっばりと光秀は言いきった。
恐ろしくないと言えば嘘になる。
真にやる気かと何度も問われれば迷いはきっと生じるだろう。
だが、今の光秀は神仏の加護を信じ、精神状態は落ち着いていた。
知らせは信忠が堺行きを取り止めて都に留まるという内容であった。
千宗易は堺で家康と共に信忠も持て成すつもりでいた為、非常に残念だと書いて寄越した。
わざわざ知らせて来たのは、来る本能寺での茶会に光秀も同席すると思っているからだろう。
吉田兼和は以前から都での大きな出来事は親友の光秀に知らせ、代わりに光秀は安土での動きを兼和に知らせてやっていた。
坂本城と都は近い為、気軽に訪ねて来るのは相変わらずだが、さすがに光秀がこんな大それた企てを内に秘めているとは気付いてはいない。
いくら細川父子や吉田兼和と親しい間柄とはいえ、今打ち明ければ止められるのは分かりきっている。
だが信長父子を討ち果たした暁には、必ずや味方になってくれると信じてはいた。
「──森お乱が信長が二十九日に上洛すると通達してきたようじゃ。」
「……では、いよいよ。」
「うむ。」
光秀と利三の真っ直ぐに見据えた瞳の中には互いの姿が映っていた。
何があっても裏切らない。
地獄に堕ちるのも共にと。
五月二十六日、明智の軍勢は近江の坂本城を出発し、丹波の亀山城を目指した。
────
「上様、立派な軍勢でございますね。あんなに遠くまで続いておりまする。一万以上、いえ、二万はおりますでしょうか?」
天守閣最上階から見下ろしているのは、信長の三男三七信孝が伊勢から率いてきた一万四千余りの軍勢である。
これから摂津に向かう途上、信長に挨拶がてら、軍備えを見て貰おうと安土に参上したのだ。
「ふむ、中々立派な軍勢じゃがまだまだじゃ!三七も総大将として出陣するのじゃから、もっと立派にしてやろうではないか。」
副将に丹羽長秀、他に蜂谷頼隆などの熟練の武将に加え、信長の評価が高い甥の津田信澄も付けてやった。
信孝を支える人材も豪華だが、更に兵馬、兵糧、黄金もたっぷり与え、万全の態勢で伜を送り出す。
「日向守殿は昨日坂本を発たれ、亀山城に既に入られていらっしゃいますが、やはり本能寺には呼ばれるおつもりでございますか?」
ほんの少しだけ信長の顔色を窺うように乱法師が言った。
襖の細い隙間からとはいえ、光秀が足蹴にされた光景はかなり衝撃的だった。
その出来事を実は気にしている事を別の気遣いをしているように、亀山城からだと備中に出陣する光秀にとっては都に戻る形になりますが、と上手く覚られぬように言ったつもりだったが、勘の鋭い信長には伝わってしまったかもしれない。
「無論じゃ!」
答えは異常な程あっさりしていた。
乱法師は仕えて僅か五年にしかならないが、信長を若い頃から知る武将達に言わせると、昔に比べれば随分と丸くなっているそうなのだ。
余程嘗ては鬼のようだったのかと思うが、確かに『圧切り長谷部』で茶坊主の胴を真っ二つに圧し切った現場や、三十代の頃、二条城の建設中、女子の被り物を取ろうとした雑兵の首を一太刀で刎ねる場面に遭遇した者達からすれば、足蹴にしたくらいは可愛いものなのかもしれない。
そのように考えながら、もう一つの確認すべき心配事を思い出した。
「稲葉家から明智家に引き抜かれた、那波と斎藤の件でございますが……」
「それは既に裁決し、菊(堀秀政)から日向守に沙汰済みじゃ!」
「どのような御裁決を下されたのでございますか?」
足蹴にした事よりも実はそちらの方を気に掛けていた。
「那波は稲葉に戻せと命じた!斎藤内蔵助は本来であれば稲葉家に戻るのが筋であるが、今更戻したところで却って争いの火種の素となるやもしれず。戻らねば自刃せよと申し渡した件については、処罰が厳し過ぎると猪子兵介から取り成しがあった為、内蔵助に関しては明智家に留まるのを許す事とした。だが、以後このような事を再び主家、或いは儂の断りなくするような事があれば間違いなく自刃は免れ得ぬとな。そう申し渡した。」
それを聞き、これで憂いなく光秀が備中に出陣出来るだろうと安堵した。
「では、二十九日に御上洛され、翌日には本能寺に御公家衆が大勢参られるかと存じますが、その日には茶会は開かず、六月二日に催されるという事で宜しいでしょうか?日向守殿には、追って私から書状で報せておきまする。」
0
お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説

妖刀 益荒男
地辻夜行
歴史・時代
東西南北老若男女
お集まりいただきました皆様に
本日お聞きいただきますのは
一人の男の人生を狂わせた妖刀の話か
はたまた一本の妖刀の剣生を狂わせた男の話か
蓋をあけて見なけりゃわからない
妖気に魅入られた少女にのっぺらぼう
からかい上手の女に皮肉な忍び
個性豊かな面子に振り回され
妖刀は己の求める鞘に会えるのか
男は己の尊厳を取り戻せるのか
一人と一刀の冒険活劇
いまここに開幕、か~い~ま~く~

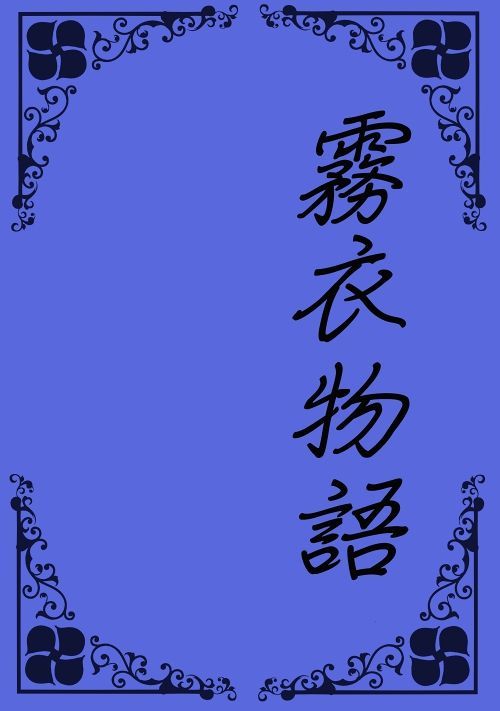
霧衣物語
水戸けい
歴史・時代
竹井田晴信は、霧衣の国主であり父親の孝信の悪政を、民から訴えられた。家臣らからも勧められ、父を姉婿のいる茅野へと追放する。
父親が国内の里の郷士から人質を取っていたと知り、そこまでしなければ離反をされかねないほど、酷い事をしていたのかと胸を痛める。
人質は全て帰すと決めた晴信に、共に育った牟鍋克頼が、村杉の里の人質、栄は残せと進言する。村杉の里は、隣国の紀和と通じ、謀反を起こそうとしている気配があるからと。
国政に苦しむ民を助けるために逃がしているなら良いではないかと、晴信は思う、克頼が頑なに「帰してはならない」と言うので、晴信は栄と会う事にする。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

三国志 群像譚 ~瞳の奥の天地~ 家族愛の三国志大河
墨笑
歴史・時代
『家族愛と人の心』『個性と社会性』をテーマにした三国志の大河小説です。
三国志を知らない方も楽しんでいただけるよう意識して書きました。
全体の文量はかなり多いのですが、半分以上は様々な人物を中心にした短編・中編の集まりです。
本編がちょっと長いので、お試しで読まれる方は後ろの方の短編・中編から読んでいただいても良いと思います。
おすすめは『小覇王の暗殺者(ep.216)』『呂布の娘の嫁入り噺(ep.239)』『段煨(ep.285)』あたりです。
本編では蜀において諸葛亮孔明に次ぐ官職を務めた許靖という人物を取り上げています。
戦乱に翻弄され、中国各地を放浪する波乱万丈の人生を送りました。
歴史ものとはいえ軽めに書いていますので、歴史が苦手、三国志を知らないという方でもぜひお気軽にお読みください。
※人名が分かりづらくなるのを避けるため、アザナは一切使わないことにしました。ご了承ください。
※切りのいい時には完結設定になっていますが、三国志小説の執筆は私のライフワークです。生きている限り話を追加し続けていくつもりですので、ブックマークしておいていただけると幸いです。

織田信長 -尾州払暁-
藪から犬
歴史・時代
織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。
守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。
織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。
そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。
毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。
スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。
(2022.04.04)
※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。
※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

天竜川で逢いましょう 起きたら関ヶ原の戦い直前の石田三成になっていた 。そもそも現代人が生首とか無理なので平和な世の中を作ろうと思います。
岩 大志
歴史・時代
ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。
けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。
髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。
戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!?
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















