お気に入りに追加
29
あなたにおすすめの小説

戦国を駆ける軍師・山本勘助の嫡男、山本雪之丞
沙羅双樹
歴史・時代
川中島の合戦で亡くなった軍師、山本勘助に嫡男がいた。その男は、山本雪之丞と言い、頭が良く、姿かたちも美しい若者であった。その日、信玄の館を訪れた雪之丞は、上洛の手段を考えている信玄に、「第二啄木鳥の戦法」を提案したのだった……。
この小説はカクヨムに連載中の「武田信玄上洛記」を大幅に加筆訂正したものです。より読みやすく面白く書き直しました。

滝川家の人びと
卯花月影
歴史・時代
故郷、甲賀で騒動を起こし、国を追われるようにして出奔した
若き日の滝川一益と滝川義太夫、
尾張に流れ着いた二人は織田信長に会い、織田家の一員として
天下布武の一役を担う。二人をとりまく織田家の人々のそれぞれの思惑が
からみ、紆余曲折しながらも一益がたどり着く先はどこなのか。

帰る旅
七瀬京
歴史・時代
宣教師に「見世物」として飼われていた私は、この国の人たちにとって珍奇な姿をして居る。
それを織田信長という男が気に入り、私は、信長の側で飼われることになった・・・。
荘厳な安土城から世界を見下ろす信長は、その傲岸な態度とは裏腹に、深い孤独を抱えた人物だった・・。
『本能寺』へ至るまでの信長の孤独を、側に仕えた『私』の視点で浮き彫りにする。

天竜川で逢いましょう 起きたら関ヶ原の戦い直前の石田三成になっていた 。そもそも現代人が生首とか無理なので平和な世の中を作ろうと思います。
岩 大志
歴史・時代
ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。
けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。
髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。
戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!?

四代目 豊臣秀勝
克全
歴史・時代
アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。
読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。
史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。
秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。
小牧長久手で秀吉は勝てるのか?
朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?
朝鮮征伐は行われるのか?
秀頼は生まれるのか。
秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

鬼を討つ〜徳川十六将・渡辺守綱記〜
八ケ代大輔
歴史・時代
徳川家康を天下に導いた十六人の家臣「徳川十六将」。そのうちの1人「槍の半蔵」と称され、服部半蔵と共に「両半蔵」と呼ばれた渡辺半蔵守綱の一代記。彼の祖先は酒天童子を倒した源頼光四天王の筆頭で鬼を斬ったとされる渡辺綱。徳川家康と同い歳の彼の人生は徳川家康と共に歩んだものでした。渡辺半蔵守綱の生涯を通して徳川家康が天下を取るまでの道のりを描く。表紙画像・すずき孔先生。
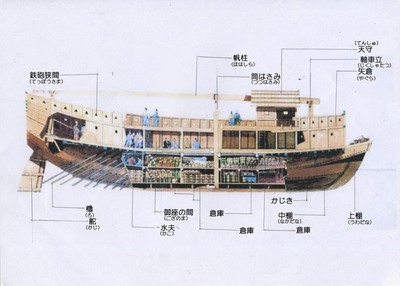

猿の内政官 ~天下統一のお助けのお助け~
橋本洋一
歴史・時代
この世が乱れ、国同士が戦う、戦国乱世。
記憶を失くした優しいだけの少年、雲之介(くものすけ)と元今川家の陪々臣(ばいばいしん)で浪人の木下藤吉郎が出会い、二人は尾張の大うつけ、織田信長の元へと足を運ぶ。織田家に仕官した雲之介はやがて内政の才を発揮し、二人の主君にとって無くてはならぬ存在へとなる。
これは、優しさを武器に二人の主君を天下人へと導いた少年の物語
※架空戦記です。史実で死ぬはずの人物が生存したり、歴史が早く進む可能性があります
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















